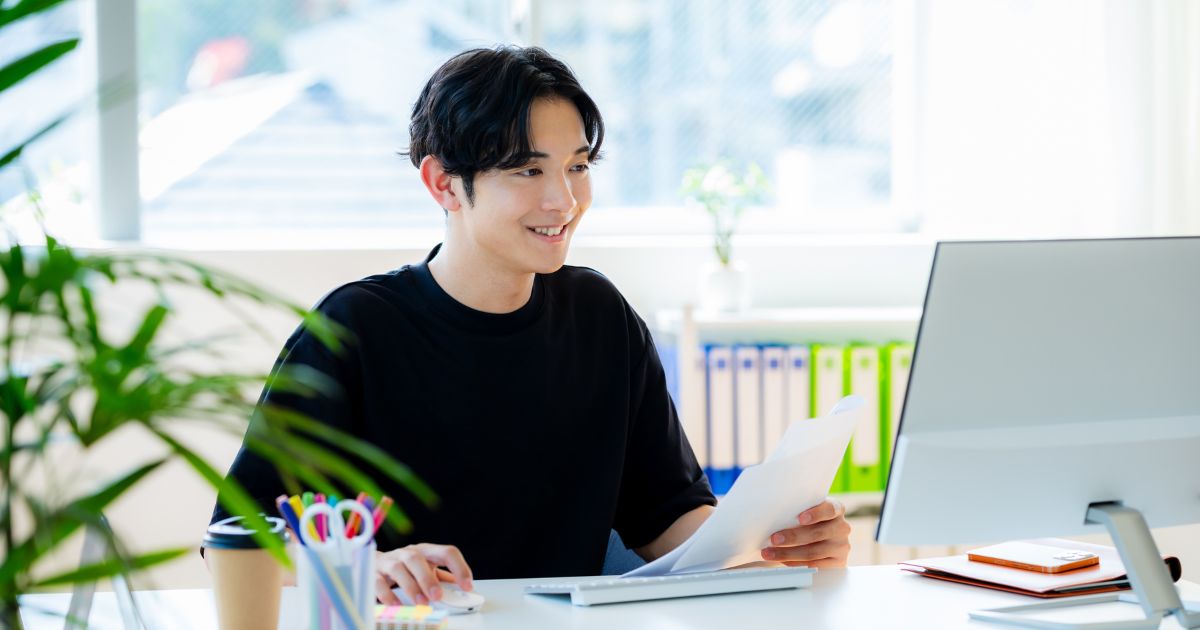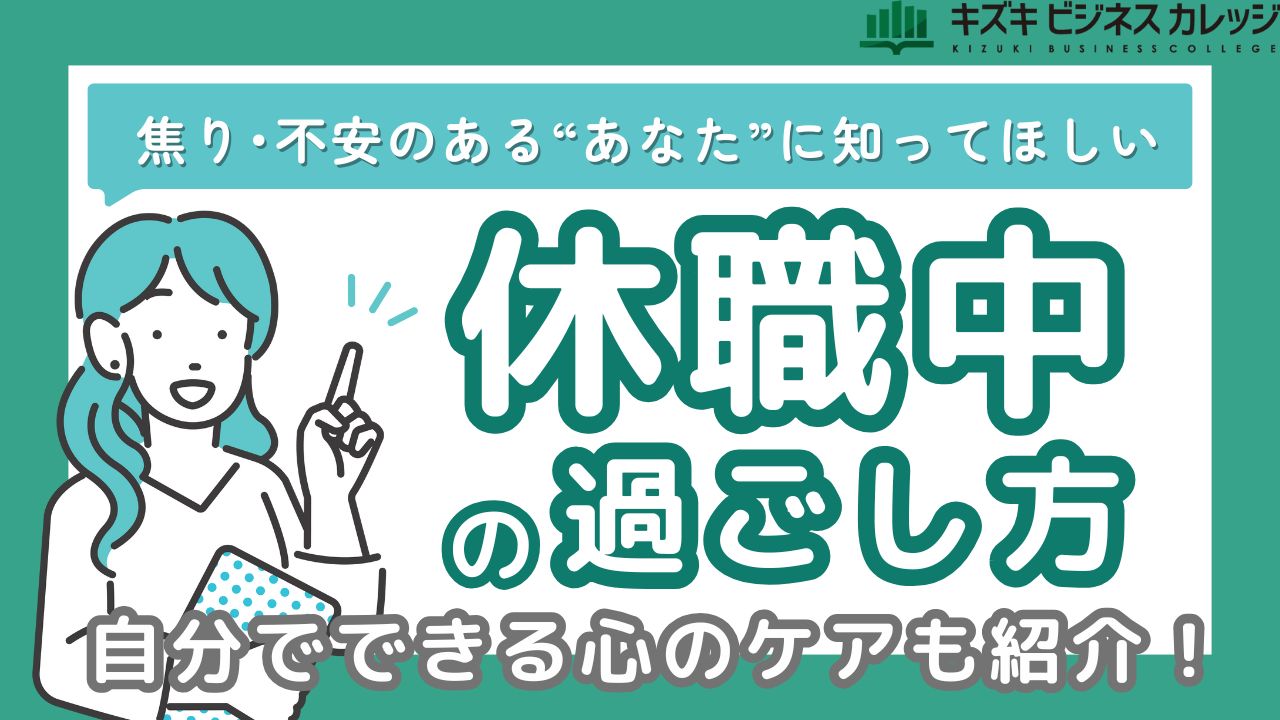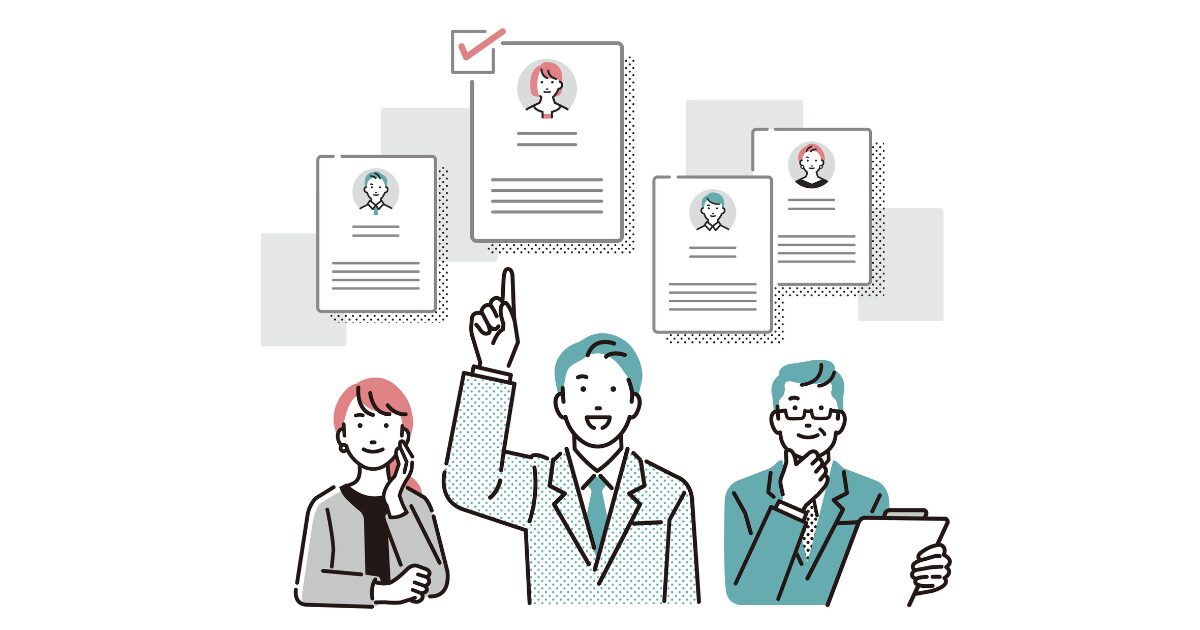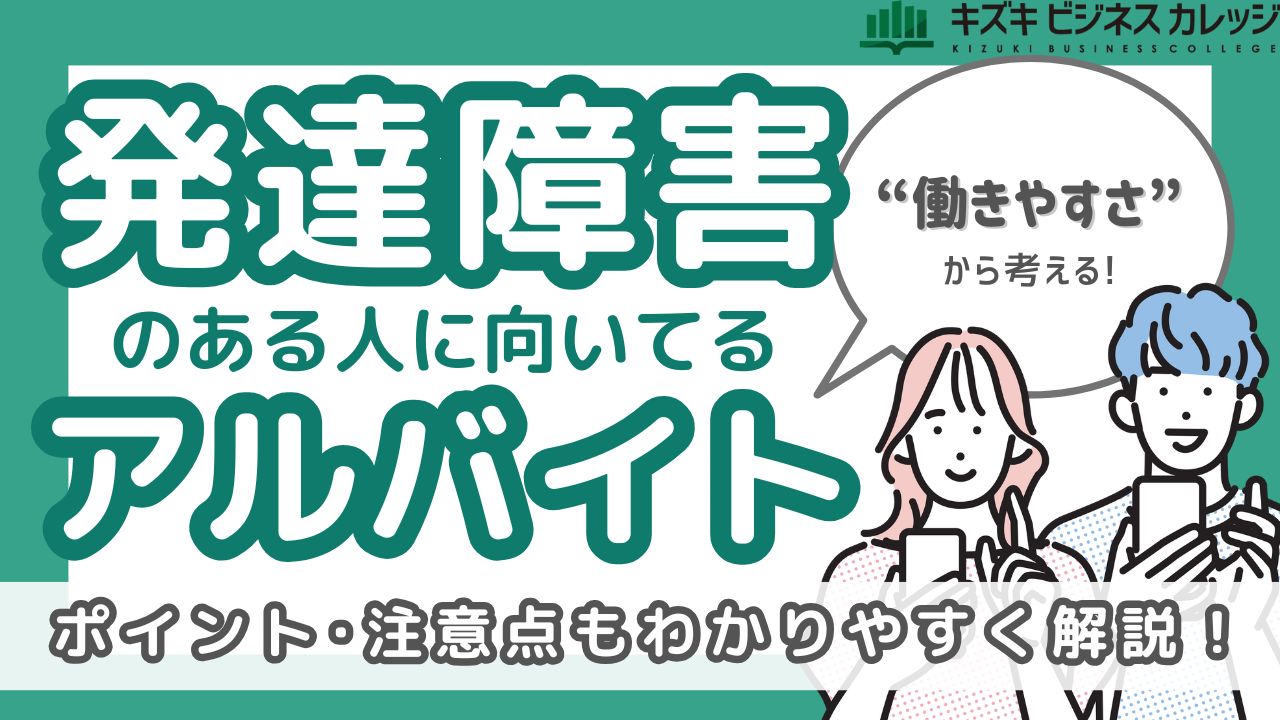発達障害のある人のストレスへの対処法 ストレスを感じやすい理由を解説【ストレス対策ブック配布中】

こんにちは、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
発達障害(ADHD・ASDなど)のある人は、感覚過敏や過集中、マルチタスクの困難さなど、特性に起因するストレスを日々抱えやすい傾向があります。
こうした声を受け、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、発達障害の特性に合わせた『"発達障害"特化型ストレス対策ハンドブック』を無料公開しました。
ストレスの原因を特性との関係から丁寧に解説し、気づきを得られる自己診断チェックリストを掲載。すぐに使える対処法を一冊にまとめています。
PDF形式で、どなたでも無料でダウンロードいただけます。ぜひ以下リンクからダウンロードください。
なお、このコラムでは、発達障害のある人がストレスを感じやすい理由、ストレスを予防する方法、ストレスを溜めすぎたときの対応について解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
ストレスを抱える発達障害のあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
発達障害のある人がストレスをため過ぎることで二次障害が発生する可能性がある
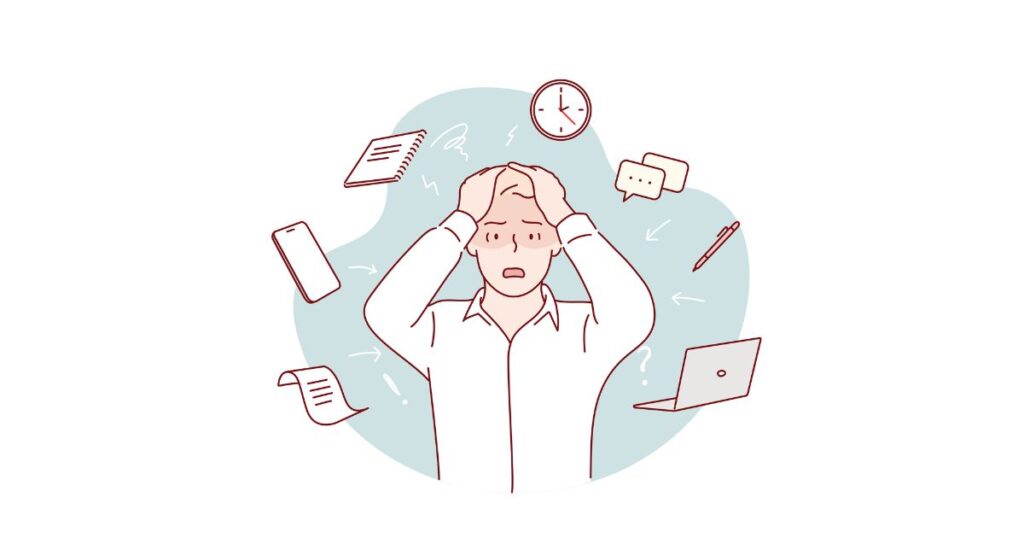
発達障害のある人がストレスをため過ぎると、発達障害の二次障害を発症する可能性があります。
発達障害の二次障害とは、発達障害や発達障害グレーゾーンの傾向・特性に伴って発生する精神障害やひきこもりなどの二次的な困難や問題のことです。(参考:齊藤万比古『発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート』、小栗正幸『発達障害児の思春期と二次障害予防のシナリオ』)
発達障害の二次障害は、うつ病などの病気・障害の発症に限りません。あくまで、発達障害に関連して起こる二次的な問題の総称です。
なお、発達障害があると、必ず二次障害が発生するわけではありません。
発達障害の二次障害については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害のある人がストレスを感じやすい理由3選
発達障害のある人の場合、その特性から仕事や日常生活の小さなことでストレスを抱えることもあるでしょう。
この章では、発達障害のある人がストレスを感じやすい理由について解説します。
発達障害の特性は人によって異なるため、困りごとも一人ひとり異なります。ここで解説する理由以外でストレスを抱える人もいるかと思います。今回解説する内容はあくまで一部です。実際のあなたとは異なる部分もあるため、参考としてご覧ください。
理由①過剰適応

発達障害のある人は、職場になじむためにより多くの努力を必要とする人が多いと思います。それを過剰適応と呼びます。(参考:障害者職業総合センター「就業経験のある発達障害者の職業上のストレスに関する研究-職場不適応の発生過程と背景要因の検討-」)
過剰適応とは、周囲の期待や要求へ応えようとして、必要以上に努力をしている状態を指します。(参考:風間惇希「大学生における過剰適応と抑うつの関連」)
社会生活を送るうえで、円滑なコミュニケーションを取る努力は必要です。しかし、それが行き過ぎて無理をしている状態が続くと、過剰適応になります。
過剰適応時の具体的な反応としては、以下のようなケースが確認されています。
- 興味が持てないことにも興味を持ったように振る舞い、ストレスを抱える
- 本当はやりたくない仕事も、周囲の期待に応えようとして取り組む
- 上司・同僚などからの要求だからと、理不尽な内容でも応える
- 本音と建前を使うコミュニケーションは苦手だけれど、職務上必要とされるから意識してコミュニケーションを取る
- 同僚と協力してひとつの仕事をこなさないといけないが、自分がケアレスミスをして足を引っ張らないように常に意識を張り巡らせている
以上のように、特性を補うために努力した行動が、過度な負担・ストレスとなる可能性があります。
理由②感覚過敏
発達障害のある人の中には、感覚過敏のある人がいます。
感覚過敏とは、聴覚・視覚・触覚・嗅覚・味覚の五感の一部、または複数からの刺激を過度に感じることで、苦痛や不快感が生じている状態のことです。(参考:イルセ・サン・著、枇谷玲子・訳『鈍感な世界に生きる敏感な人たち』、岡田尊司『過敏で傷つきやすい人たち HSPの真実と克服への道』、安田祐輔『ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に勉強するための本』)
例えば、以下のような日々の生活の中で起こるさまざまな刺激に反応してストレスを感じることもあるでしょう。
- パソコンの画面が明るすぎて目が疲れる
- 空調の音や同僚の話し声がとてもうるさく感じる
- 衣服が肌に当たるところがちくちくして気になってしまう
感覚過敏については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
理由③過集中や衝動性

過集中や衝動性からさまざまな活動をしたのに適度な休憩を取れないとどうしても疲れがたまり、その疲れはストレスといった形で心身に表れます。
過集中とは一つのことに対して過剰に没頭する状態のことです。よいことに聞こえるかもしれませんが、作業を終えたあとは、疲れるというデメリットがあります。
衝動性とは、感情や行動を自分で制御できない状態、思いついたことをよく考えずに行動する状態のことです。(参考:YouTubeこころ診療所チャンネル「ADHDだと疲れやすい原因5つ【感覚過敏や過集中など、精神科医が7分で説明】大人の発達障害|発達障害』」)
例えば、以下のような場面でストレスを感じるでしょう。
- 自分が得意な作業に集中していたら昼休憩を取り忘れていた
- 休むことが苦手で大掃除をする
- 買い物に行ったりして一日中動き回った
発達障害のある人がストレスを予防する方法6選
発達障害のある人はその特性から、社会生活においてストレスを感じやすい人が多くいます。
この章では、筆者の知見に基づき、発達障害のある人のストレスを予防する方法について解説します。皆さんのお役に立てる対処法があれば嬉しいです。
方法①休憩時間にリフレッシュする

ストレスを感じたら、休憩時間に一人になって心のリフレッシュをすることをオススメします。
例えば、コミュニケーションに苦手意識がある人は、業務中にどうしても発生するコミュニケーションが原因でストレスを抱えやすいでしょう。そんなときはコミュニケーションをとらなければならない人から離れたところでしっかり休憩するようにしてみてください。
筆者の場合は、昼食の時間は一人になり、好きな音楽を聞きながら食事をしています。音楽を聞くことで一人の世界に入り込むことができ、安心することができます。
方法②会社に配慮を求める
2016年度から、事業主には、過重な負担とならない範囲で障害のある人に対して合理的配慮の提供が義務付けられています。(参考:厚生労働省『発達障害のある方への職場における配慮事例のご紹介』)
合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と同じように生活し、活動できる均等な機会を確保するために必要な配慮のことです。障害のある人が業務上で支障があったときに改善するための措置を取ることも合理的配慮に含まれます。
口頭指示だけでは忘れてしまうので、メモやメールにて指示をして欲しい、質問するタイミングが掴めず困ってしまうことが多いので、質問できる決まったタイミングを作って欲しいというように、自分が業務を遂行するうえで苦手とすることを職場の人に相談することで配慮をしてもらえるかもしれません。
合理的配慮については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
方法③それぞれの刺激を緩和する

こちらで解説したように、感覚過敏が原因でストレスを感じる発達障害のある人は、刺激を緩和するツールを使用してみてください。
例えば、単純に思われるかもしれませんが、耳栓や、PCの明るさを軽減するフィルムなどのツールを使ってみましょう。
同時に耳栓などのツールを使用していることは、あらかじめ職場に伝えておきましょう。何かある場合は肩を叩いてもらう、チャットで知らせてもらうなどをお願いしておくことも有効です。
筆者の場合は、明るいパソコンの画面を見ているととても疲れてしまうため、画面の明度を下げて作業しています。
方法④過集中を防ぐ
ひとつの仕事に集中できることはとても良いことだと思われるかも知れませんが、過集中は疲労を過度にためてしまいます。
休憩を忘れて作業してしまうことを防ぐため、アラームなどを用いて、疲れていなくても決まったタイミングで休憩をとるようにしましょう。
筆者は目の前にパソコンがあるとどうしても作業してしたくなるため、昼休憩など、決まったタイミングで休憩を取るのと同時に、パソコンなどがある作業スペースから離れるようにしています。
方法⑤衝動性を抑える

衝動的にあれもこれもとやることによって、本来やるべきことを忘れたり、遅れたりして叱責を受けたり、あるいは単純に疲れることがあるでしょう。
衝動的に行動する原因のひとつとして、外部からの刺激や情報によって今やるべきことから意識が逸れやすいことが挙げられます。そのため、周囲からの刺激を減らしたり、行動しづらい仕組みを作ることで、衝動的な行動を減らすようにしましょう。
例えば、筆者は、作業中にスマートフォンが気になると、ついつい触り続けるということがあります。
そういう時は、スマートフォンをすぐに触れないように鞄に入れたり、自分から離れた場所に置くようにしています。
スマートフォンが視界に入らないように、鞄から取り出すのにチャックをあける必要をつくるなど、めんどうな手間をわざと設けるという工夫をしています。業務中はもちろん資格勉強など、なにかに集中したいときには有効な方法でしょう。
方法⑥生活リズムを整える
基本的なストレス対策として睡眠、運動、食事が大事になることはよく知られています。この中で比較的改善しやすいことと言えば、眠る時間の調整でしょう。
睡眠をとることでストレスや体調は以下のように改善します。(参考:健康づくりのための睡眠指針の改定に関する検討会「健康づくりのための睡眠ガイド2023」)
- 日中のストレスや疲れをいやすことができる
- 嫌な記憶や不要な記憶を消し、大切な情報が記憶として定着、強化される
- 脳や血管、免疫などの増進、維持に重要とされる
筆者の場合、休日も含めて起きる時間を午前8時頃に固定するようにしています。同じ時間に起きることで、自然と自分に合った入眠時間に眠くなるようになりました。はじめは日中眠くなるなどの問題もありましたが、その時は20分程度の仮眠をして、夜の睡眠を邪魔しないように工夫しました。
発達障害のある人がストレスを溜めすぎたときの2つの対応
こちらで解説したストレスを予防する方法を実践したにも関わらず、ストレスの改善がみられないこともあるかと思います。
そのときは、ストレス源から離れることも効果的な対応です。
仕事がストレスになっている場合は思い切って休職、転職を視野に入れてみてもよいかもしれません。
この章では、発達障害のある人がストレスを溜めすぎたときの対応について解説します。
ストレスが長期間続くと、うつ病など、ほかの精神疾患などを発症する可能性があります。ストレスを溜めすぎることで起こる問題については、こちらで解説します。
対応①休職

1つ目の対応は、休職です。
休職とは、雇用契約を維持したまま労働を免除、または停止させる措置のことです。(参考:大阪府「34 休職と休業」、友常祐介『正しく知る 会社「うつ」の治し方・接し方』)
まずは、家族や友人などの周囲の人、主治医などの信頼できる専門家、支援機関に今の辛い気持ちや仕事での悩みを相談をしてみましょう。
精神的に疲労しているとき、人は判断が鈍りがちです。そんなときは一人で考え込まず、周囲に相談してみてください。第三者の視点かつ、あなたのことを考えたアドバイスをしてくれるはずです。そのアドバイスを加味したうえで、休職についての判断をしてみてください。
休職を検討している人は、休職期間も重要になるため職場の就業規則を必ず確認してください。確認することが難しい場合は、人事を担当する部署に問い合わせてみてください。
休職の手続きをすることは、精神が疲弊しているときは難しいかもしれません。ですが、人によっては、無断欠勤自体がストレスになることもあります。無断欠勤の罪悪感によるストレスや不安をなくし、しっかりと休むためにも、手続きをしてみましょう。
しかし、どうしてもしんどいときは、そういった手続きを行うことも難しいでしょう。そんなときは、主治医やお住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口、精神保健福祉センターなどに相談してみてください。休職に関する相談に乗ってもらえるでしょう。
- 厚生労働省働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトこころの耳「相談窓口案内」
- 厚生労働省総合労働相談コーナーのご案内
- 厚生労働省全国の精神保健福祉センター
休職については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
対応②転職
2つ目の対応は、転職です。
どうしても仕事が合わない、その職場で働くことがストレスでしかない場合、転職という手段もあります。転職活動をする上で、自分の特性にあっている職場を探すことが大切です。そのためには転職準備の段階で自分を知ることが重要です。
自身の得意・不得意、職場にお願いしたい配慮などをはっきりとさせておくことをオススメします。自分を知る方法として、ハローワークの精神・発達障害者雇用サポーターや就労移行支援事業所に相談してみるなどがあります。
厚生労働省「発達障害者の就労支援」
発達障害のある人の転職については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)
発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。
- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)
- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)
- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)
同じ診断名でも、人によって多様な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人は、他の発達障害が併存している可能性もあります。
発達障害の概要や種類、原因、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
【無料配布中】発達障害特化型ストレス対策ハンドブック

発達障害(ADHD・ASDなど)のある方は、感覚過敏や過集中、マルチタスクの困難さなど、特性に起因するストレスを日々抱えやすい傾向があります。
中でも、新年度や環境の変化が重なるこの季節は、「知らないうちに疲弊してしまう」「些細な刺激でつらくなる」といった悩みを抱える方が急増します。
こうした声を受け、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)は、発達障害の特性に合わせた『"発達障害"特化型ストレス対策ハンドブック』を無料公開しました。
ストレスの原因を特性との関係から丁寧に解説し、気づきを得られる自己診断チェックリストを掲載。すぐに使える対処法を一冊にまとめています。
PDF形式で、どなたでも無料でダウンロードいただけます。
- 発達障害の特性とストレスの関係をわかりやすく解説
- 「なぜ自分はこんなに疲れるのか?」を理解するヒント
- ストレスの対処法を確認できるチェックリスト
- 感覚・思考・行動・環境別のストレス対処法
- 明日から使えるセルフケアの実践アイデア
- 発達障害の診断がある、もしくは発達障害グレーゾーンの方
- 自分は発達障害かもしれないとお悩みの方
- 仕事や日常生活での疲れがなかなか抜けない方
- 自分に合ったストレス対処法が見つからず悩んでいる方
- 「頑張りすぎて燃え尽きる」を繰り返してしまう方
以下リンクからダウンロードをお願いします。
- コラム内のリンクから簡単なフォームに入力
- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り
- URLからハンドブックを取得
- ※ご提供には簡単なフォーム入力が必要です。
- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。
- ※本ハンドブックのダウンロード後、無断での配布・転載はお控えください。
まとめ:無理はしないでください

今の社会は、普通として求められるレベルが大変高いと個人的に感じています。
学校や職場などで周囲の人がスムーズなコミュニケーションやマルチタスクをできるのに、自分はできないと落ち込むことが筆者自身よくあります。
もちろん、発達障害でない人でも、多少なりとも得意・不得意はあるかと思います。しかし、発達障害のある人は、得意・不得意が日常生活を送るのに困るレベルで表れることがあります。そのため、不得意なことに対するストレスが多大にかかることがあるでしょう。
ストレスにより心身の体調に違和感がある場合、無理をせず、心療内科や精神科の受診をしてください。
また、仕事で辛い思いをしている人は、休職や転職を視野に入れた上で支援機関の利用を視野に入れてください。
このコラムを読んで、あなたのストレスが、少しでも減れば幸いです。
発達障害のある人はストレスを感じやすいのは、なぜですか?
発達障害のある人がストレスを予防する方法を教えてください。
監修志村哲祥
しむら・あきよし。
医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。
臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。
【著書など(一部)】
『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』
他、学術論文多数
日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧
時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
監修角南百合子
すなみ・ゆりこ。
臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→