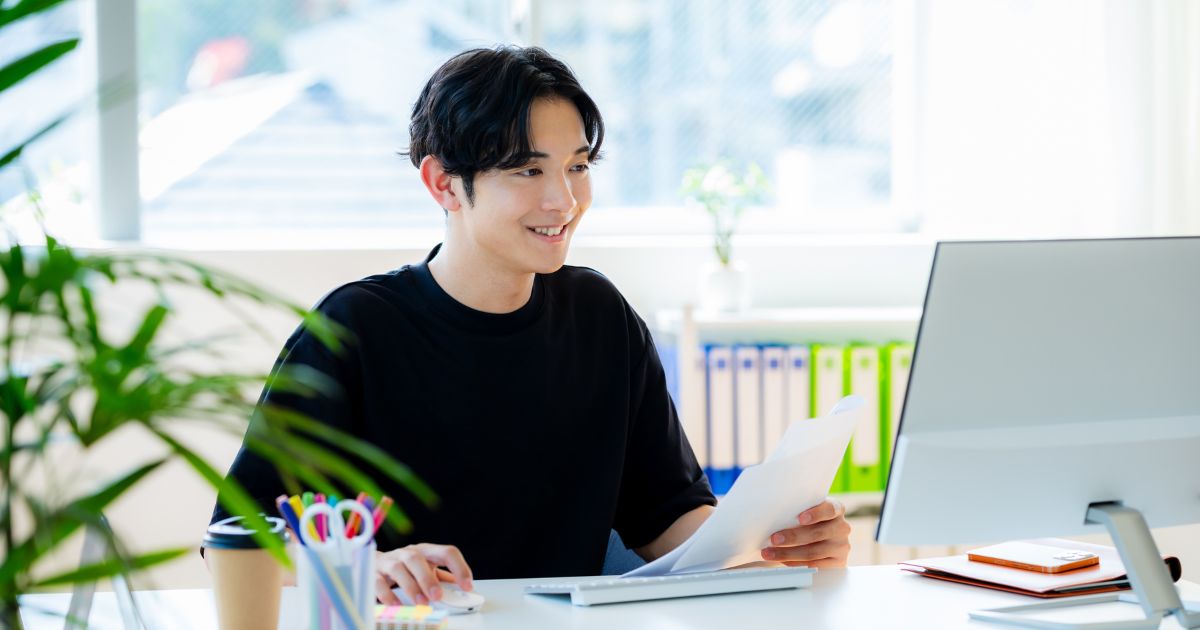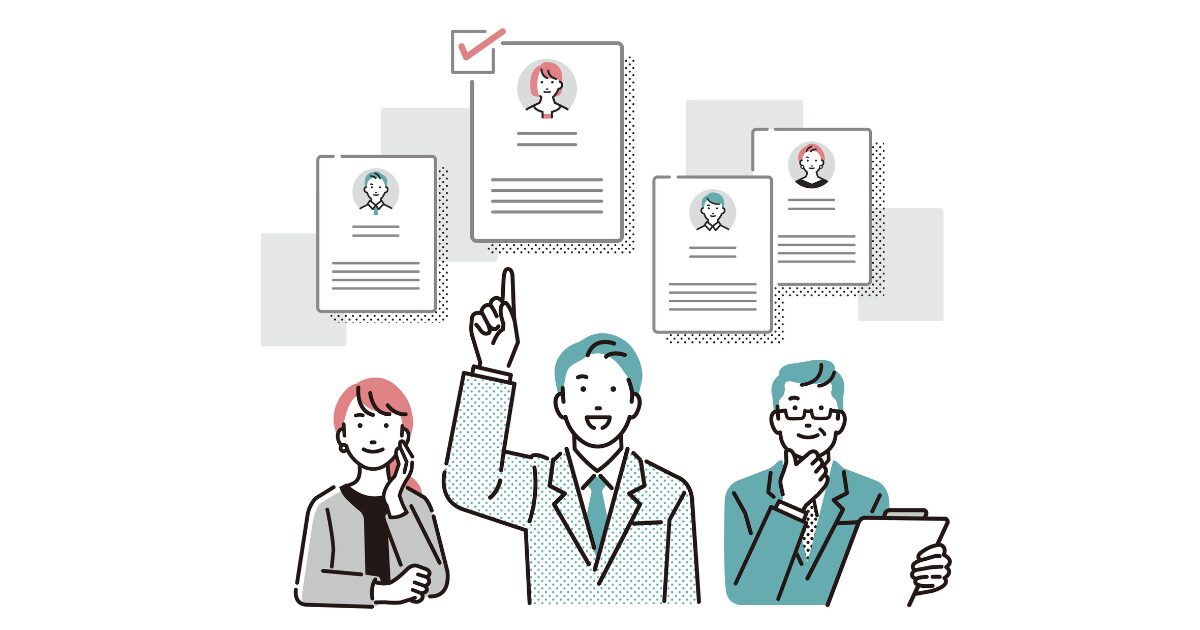発達障害とは?生まれつき? ADHD、ASD、LD/SLDを解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
このコラムでは、発達障害の概要や種類、原因、治療方法などについて解説します。
発達障害について知りたいあなたの参考になれば幸いです。
発達障害でお悩みのあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 平均4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)
発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。
- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)
- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)
- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)
同じ診断名でも、人によって多様な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人は、他の発達障害が併存している可能性もあります。
発達障害の診断名・分類の変更
2013年に行われたアメリカ精神医学会が定めた精神障害の診察基準『DSM』の改訂の際、発達障害という診断名・分類は、神経発達症群/神経発達障害群という診断名・分類に変更されています。
WHO(世界保健機関)が定めるICD(国際疾病分類)における診断名・分類も、2018年に『DSM-5』に合わせて発達障害から神経発達症群/神経発達障害群に変更されています。
それに伴い、自閉症やアスペルガー症候群など、いくつかの診断名・分類は変更されています。しかし、変更前の診断名・分類が、法令や病院などで現在も使用されることがあります。
『DSM-5』によると、神経発達症群/神経発達障害群は、以下のように定義されています。
神経発達症群とは、発達期に発症する一群の疾患である。この障害は典型的には発達期早期、しばしば小中学校入学前に明らかとなり、個人的、社会的、学業、または職業における機能障害を引き起こす発達の欠陥により特徴づけられる
(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』)
ただし、日本の法令では、医学的に最新の診断名・分類が反映されていないものもあります。例えば、発達障害者支援法における発達障害の定義は、以下のとおりです。
この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
(参考:文部科学省「特別支援教育について」)
なお、国内の発達障害の研究は、まだまだ発展途上です。定義や名称、分類などは、今後も少しずつ変わっていくのかもしれません。
発達障害の性別ごとの割合
厚生労働省によると、発達障害と診断された人約87万2000人のうち、男性は約58万9000人で約67.5%、女性は約27万6000人で約46.9%、不明は約7000人で約2.5%という結果が出ています。(参考:厚生労働省「令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」)
特に、ASDに限ると、男性は女性の約4倍であるという説もあります。(参考:厚生労働省「e-ヘルスネット ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について」)
ただしこれは必ずしも、発達障害のある男性の方が女性より多いということを意味しているわけではありません。
発達障害があっても、その特性による困難さが目立たないことも多くあります。そのため、発達障害の診断を受けていない、受ける必要がない人が一定数いるということも示唆しています。
発達障害の診断は医師だけが可能

発達障害の診断は、医師による問診や心理士が実施する心理検査を中心に行われます。
発達障害の診断は医師だけが可能です。
自分は発達障害であると思っている場合でも、必ずしも、発達障害であるとは限りません。
どういった状態が診断基準に当てはまるか、他の病気や障害の可能性がないかどうかを含めて、医師だけが判断できます。
診断基準にあるいずれかの症状に該当していると思う場合でも、自身で「発達障害である」と判断しないようにしましょう。
発達障害であるかどうかを知りたい場合、病院を受診することをオススメします。
診断を受けるのが不安な場合、事前に支援機関やお住まいの自治体の発達障害支援センター、あるいは、障害福祉を担当する部署・窓口などに相談してみてください。
発達障害の原因
発達障害の原因は、現在の医学では明確に特定されていません。現在のところ、生まれつきの脳機能の障害が原因であると考えられています。
少なくとも、本人の努力不足や親の育て方、ストレス、環境などが原因ではないことは明らかになっています。発達障害は、原因不明かつ生まれつきのものであり、誰かに責任があるわけではありません。
発達障害を精査するための検査2選

発達障害の正確な診断にあたっては、数値やデータ、生育歴などで可能な限り客観的な証拠に基づくことが重要です。
この章では、発達障害を精査するための検査について解説します。
もちろん、こうした検査結果だけで診断することはありませんが、検査結果を参考にして発達障害の可能性を診断することもあります。
方法①WAIS
WAIS(ウェクスラー式成人知能検査)とは、全般的なIQを測ったうえで、包括的に知的能力を測ることができる成人向けの知能検査のことです。精神科病院やクリニックにて行われ、主に臨床心理士が検査を担当することが多いです。(参考:日本文化科学社「WAIS™-IV知能検査」)
検査の対象は、16歳0カ月〜90歳11カ月の青年および成人です。
WAIS-IVでは具体的には、特定の認知領域の知的機能である以下の4つの項目と全般的な知能を表す全検査IQ(FSIQ)について検査します。
- 言語理解(VCI):言語的な情報や、自分自身が持つ言語的な知識を状況に合わせて応用する能力
- 知覚推理(PRI):非言語的な情報をもとに推論する能力。また、新規な情報に基づく課題処理能力
- ワーキングメモリー(WMI):情報を記憶に一時的にとどめ、その情報を操作する能力
- 処理速度(PSI):単純な視覚情報を素早く正確に、順序良く処理する、あるいは識別する能力
以上の4つの能力を、具体的な数値だけでなく、自分の能力が他人と比べてどのくらいの位置にあるのかという結果まで割り出します。
必要な費用は1万〜2万円ほどと少し高額です。予約も大体1か月以上前から取らなければいけないなどの手間がかかります。
しかし、病院によって対応は多少異なりますが、検査結果を単純に示すだけでなく、検査中の様子も見た上で、普段の生活・学業・仕事への取り組み方や改善点、参考になる資料の紹介など、専門の臨床心理士から指導を受けることができます。
WAIS-IVの受診を希望する場合は、お近くの精神科病院に確認してみましょう。
方法②WISC
WISC(ウェクスラー式児童知能検査)とは、全般的なIQを測ったうえで、包括的に知的能力を測ることができる児童向けの知能検査のことです。こちらも精神科病院やクリニック、児童思春期科などにて、医師や臨床心理士によって行われます。(参考:日本文化科学社「WISC™-V知能検査」)
検査の対象は、5歳0か月〜16歳11か月の児童です。
具体的には、特定の認知領域の知的機能である以下の5つの項目と全般的な知能を表す全検査IQ(FSIQ)について検査します。
- 言語理解(VCI):言語的な情報や、自分自身が持つ言語的な知識を状況に合わせて応用する能力
- 視空間認知(VSI):空間における視覚情報を処理して解釈する能力
- 流動性推理(FRI):抽象的な思考や新しい問題の解決など、さまざまな文脈での論理的に推論する能力
- ワーキングメモリー(WMI):情報を記憶に一時的にとどめ、その情報を操作する能力
- 処理速度(PSI):単純な視覚情報を素早く正確に、順序良く処理する、あるいは識別する能力
WISCの受診を希望する場合は、お近くの精神科病院に確認してみましょう。
発達障害の治療方法
少なくとも現在の医学では、発達障害を根本的に治癒させる方法はありません。(参考:社会福祉法人 恩賜財団済生会「大人の発達障害との向き合い方~仕事のお悩み編~」、NHK「発達障害を生き抜くために 診断と治療」)
発達障害の特性は、その人が生まれもったものの感じ方や考え方、行動の仕方と深く結びついており、それらを根本的に変化させることはできないため、治癒できるものではありません。
ただし、発達障害の特性やそれに伴う苦労や困難は、薬物療法や社会心理的な療法などによって、緩和させることは可能です。
例えば、ADHD症状の治療薬には、ADHDの特性である不注意や多動性などを改善する効果が認められています。(参考:厚生労働省「メチルフェニデート」、中川の郷療育センター「発達障害の当事者とまわりの人のための薬はじめてガイド」)
発達障害の特性に関連する治療薬は市販されておらず、入手には医師の処方箋が必要です。薬物療法などについては、専門の医師に相談しましょう。
また、発達障害に関する情報を得たり、その特性と向き合い理解したり、必要に応じて適切なサポートを利用したりすることで、その苦労や困難を減らし生きやすくすることはできるでしょう。発達障害のある人が利用できる支援制度や支援機関はたくさんあります。
発達障害の特性を緩和・改善する治療薬や対応などは確立されてきています。必要以上に不安に感じる必要はありません。
発達障害と併発しやすい病気・状態、間違えられやすい病気・状態

発達障害と併発しやすい病気・状態として、以下が挙げられます。ここでは、ひきこもりなどの病気ではない状態も含めます。(参考:黒澤礼子『新版 大人の発達障害に気づいて・向き合う完全ガイド』)
- 双極性障害
- 睡眠リズム障害(概日リズム睡眠・覚醒障害)
- てんかん
- むずむず脚症候群
- ひきこもり
- ニート
- 家庭内暴力
- 非行・挑発的行動
- うつ病
- 統合失調症
- 摂食障害
- 強迫症
- 社交不安症
- パーソナリティ障害
- 睡眠時無呼吸症候群
それぞれの病気・状態によって、必要な治療・対応は異なります。
病気の診断は、医師による問診や心理士が実施する心理検査を中心に行われます。
医師以外には病気の診断・判断はできません。ほかの病気に該当していると思う場合でも、自身で「その病気がある」と判断しないようにしましょう。
その病気・状態に該当するかどうかを知りたい場合、病院を受診することをオススメします。
診断を受けるのが不安な場合、事前に支援機関やお住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に相談してみてください。
また、専門の医師でも区別が難しい場合もあります。すでに診断を受けており、現在の治療方法などが思わしくないようであれば、別の病気・状態である可能性もあります。
疑われる場合は、セカンドオピニオンを求めて別の病院や支援機関に相談することも検討してみてください。
発達障害グレーゾーンとは?

発達障害グレーゾーンとは、発達障害と同様の特性や傾向がいくつか認められるものの、診断基準を満たすほどではないため、発達障害と診断されるには至らない状態のことです。(参考:姫野桂『発達障害グレーゾーン』)
発達障害グレーゾーンという言葉は、医学的に正式な診断名称ではありません。
複数ある発達障害の診断基準の一部を満たしていないために、発達障害の確定診断をつけることができない状態のことを、発達障害グレーゾーンと表現しているだけです。
発達障害グレーゾーンについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害の二次障害とは?
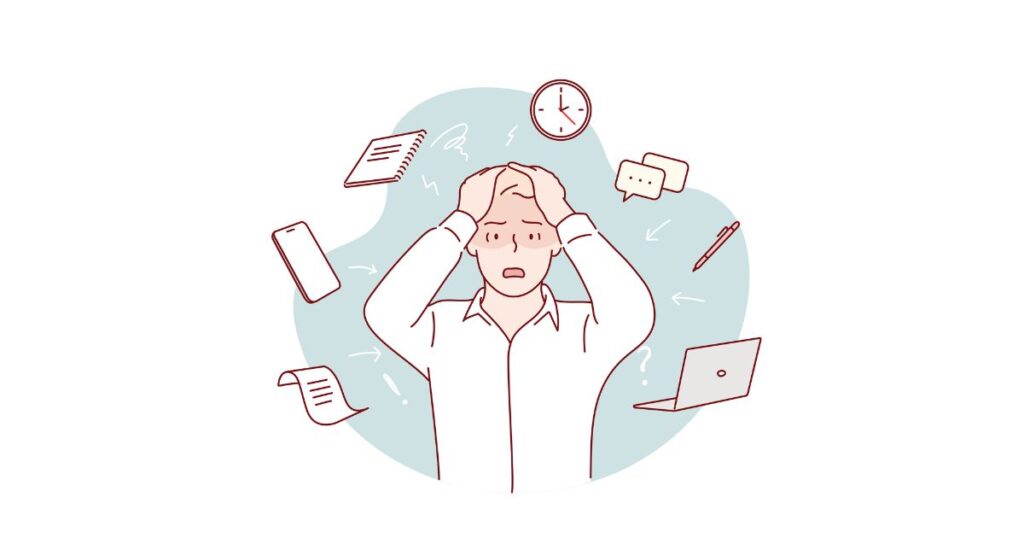
二次障害とは、主障害に起因して起こる副次的な障害のことです。ここで取り上げている発達障害の二次障害とは、発達障害や発達障害グレーゾーンの傾向・特性に伴って発生する精神障害やひきこもりなどの二次的な困難や問題のことを指します。(参考:齊藤万比古『発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート』、小栗正幸『発達障害児の思春期と二次障害予防のシナリオ』)
発達障害の二次障害は、うつ病といった精神面に現れることもあれば、暴力などの行動面で現れることもあります。発達障害に関連して起こる二次的な問題の総称です。
なお、発達障害があると、必ず二次障害が発生するわけではありません。
発達障害の二次障害については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
大人の発達障害とは?
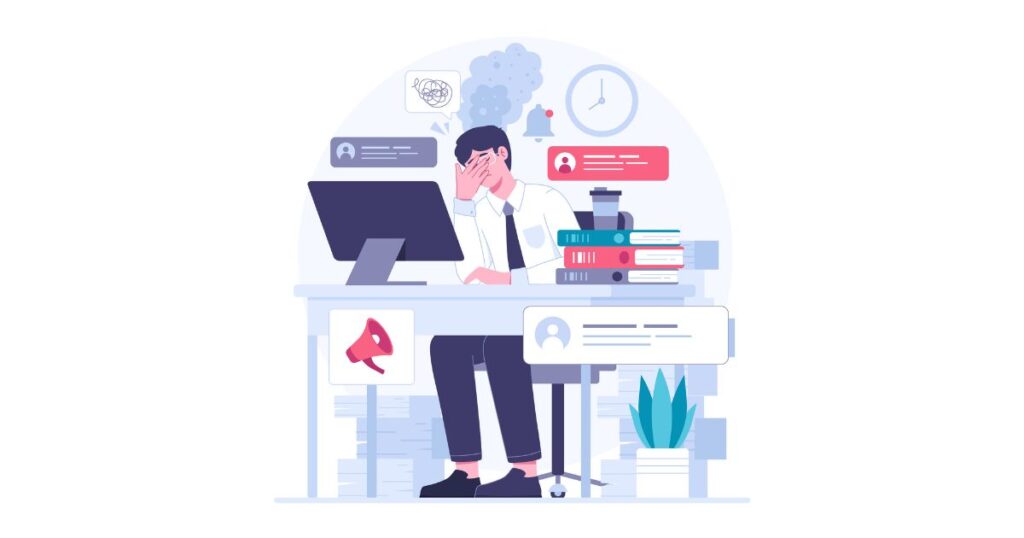
大人の発達障害は、医学的に正式な診断名称ではない俗語です。(参考:林寧哲『これでわかる 大人の発達障害』、黒澤礼子『新版 大人の発達障害に気づいて・向き合う完全ガイド』)
明確に定められた定義はありませんが、一般的には、幼少期の時点で診断を受けておらず、大人になってから発達障害の確定診断を受けた状態のことを指すようです。また、幼少期の時点で発達障害の確定診断を受けていた人が、大人になった状態のことを、大人の発達障害と表現することもあるようです。
なお、発達障害は、脳の構造的な特性によって生じる、生まれつきのものです。本来、発達障害の特徴は一般的に乳幼児から幼児期に現れます。大人と子どもで本質的には異なる部分はなく、現在の医学では、大人になっても継続するものとされています。
そのため、「大人になってから発達障害になる」「成長するにつれて発達障害になる」ということはありえません。また、「思春期から」「育ち方や親のしつけの影響で」など、成長してから、または成長につれて後天的に発達障害になるということもありえません。
大人の発達障害については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
ADHDとは?

ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害、Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)とは、不注意性や多動性・衝動性の特性から日常生活などに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、田中康雄・監修『大人のAD/HD』、岩波明『大人のADHD─もっとも身近な発達障害』、司馬理英子『ササッとわかる 「大人のADHD」 基礎知識と対処法』、星野仁彦『それって、大人のADHDかもしれません』、e-ヘルスネット「ADHD(注意欠如・多動症)の診断と治療」)
ADHDの特性は大きく、以下の2つの特性に分けられます。
- 不注意性:忘れ物やケアレスミスが多い、注意散漫、整理整頓・管理が不得意
- 多動性・衝動性:落ち着きがない、気が散りやすい、後先考えず行動する
ADHDのある人だからといってすべての特性が生じるというわけではありません。いずれかの特性、または複数の特性から困難が生じている人もいます。
ADHDのある人は、必ず不注意性や多動性・衝動性が現れるというわけではなく、人によって特性の現れ方、得意なこと・不得意なことが違う点が大きな特徴です。
ADHDの概要や特性、診断基準などについては、以下のコラムで解説しています。
ASDとは?

ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害、Autism Spectrum Disorder)とは、人とのコミュニケーションなどに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、e-ヘルスネット「ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について」、CDC「Autism Spectrum Disorder (ASD) 」、厚生労働省「No.1 職域で問題となる大人の自閉症スペクトラム障害」、福西勇夫、福西朱音『マンガでわかるアスペルガー症候群の人とのコミュニケーションガイド』)
かつて使用されていた以下の診断名・分類は、ASDという診断名・分類に統合されています。
- アスペルガー症候群
- 自閉症
- 高機能自閉症
- 広汎性発達障害(PDD)
それぞれ別の発達障害として、診断基準も異なっていましたが、2013年に行われた『DSM-5』の改訂の際に、厳密に区分するのではなく、地続きの=スペクトラムな障害として捉える現在のASDに変更されました。
ただし、変更前の診断名・分類が、法令や病院、日常会話などで現在も使用されることがあります。また、かつてアスペルガー症候群などと診断された人が、現在のASDという名称を認知していないこともあります。
ASDの概要や特性、診断基準などについては、以下のコラムで解説しています。
LD/SLDとは?

LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害、Learning Disorder/Specific Learning Disorder)とは、読む・書く・計算する・推論するなど、特定の学習行為のみに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』、厚生労働省「学習障害(限局性学習症)」、小池敏英・監修『LDの子の読み書き支援がわかる本』、バーバラ・エシャム・文、マイク&カール・ゴードン・絵、品川裕香・訳『算数の天才なのに計算ができない男の子のはなし 算数障害を知ってますか?』)
LD/SLDは症状別に、以下の3つの種類に分類されます。
- 読字障害(ディスレクシア)
- 書字表出障害(ディスグラフィア)
- 算数障害(ディスカリキュリア)
LD/SLDのある人は、全ての学習行為に困難が生じるというわけではありません。
いずれかの学習行為、または複数の学習行為に困難が生じている人もいます。計算することのみが不得意、読むことと書くことが不得意などのように、人によって様々です。
また、いずれの学習行為においても、人によって得意なこと、不得意なことは異なってきます。
例えば、読字障害のある人のなかでも、スムーズな音読が不得意な人もいれば、音読はできてもその内容を理解することが難しいという人もいます。
このように、LD/SLDのある人は、学習する事柄が総合的に不得意というわけではなく、ごく一部の事柄に困難が生じるという点が大きな特徴です。
LD/SLDの概要や特性、診断基準などについては、以下のコラムで解説しています。
まとめ:適切に支援を利用しましょう
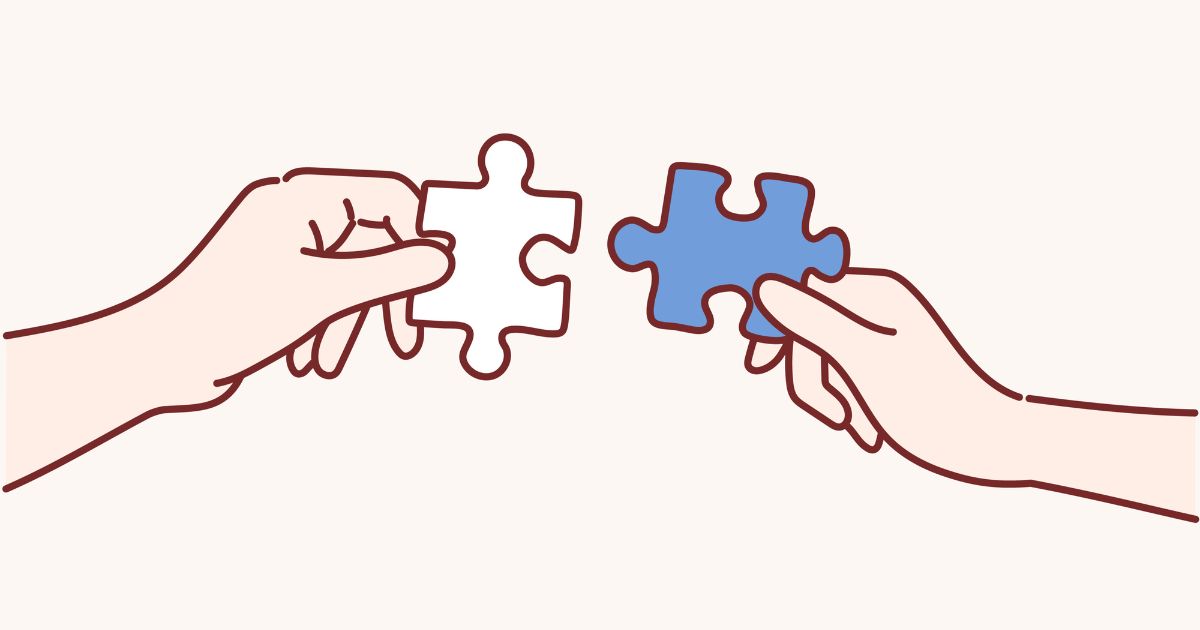
発達障害にはさまざまな種類があり、特性も大きく異なります。
また、同じ診断名であっても特性には個人差があるため、自分に合ったサポートを受けるためには、発達障害について詳しい専門家や支援機関に相談することが大切です。
発達障害に関する悩みを一人で考え込まず、ぜひさまざまな専門家や支援機関に相談することを検討してみてください。
発達障害とは何ですか?
発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。
詳細については、こちらで解説しています。
発達障害の種類を教えてください。
以下が考えられます。
- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)
- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)
- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)
詳細については、こちらで解説しています。
監修志村哲祥
しむら・あきよし。
医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。
臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。
【著書など(一部)】
『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』
他、学術論文多数
日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧
時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年6月現在8校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
監修角南百合子
すなみ・ゆりこ。
臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年6月現在、首都圏・関西に8校舎を展開しています。トップページはこちら→