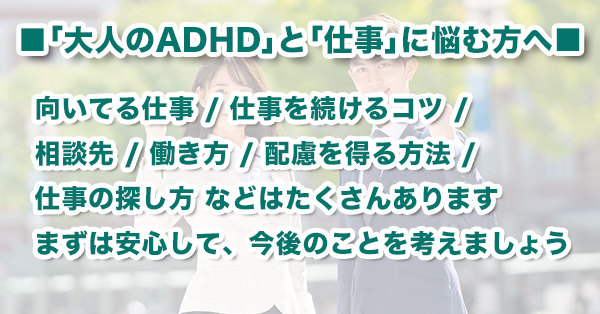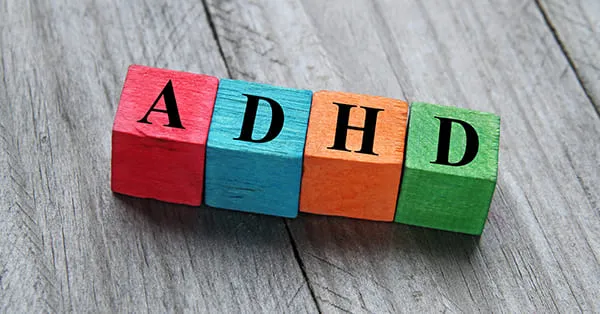ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)とは? 特性や診断基準を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
ADHDをご存知でしょうか?発達障害の1つで、次のような特性があります。
- 物忘れやぼーっとしている不注意
- じっとしていられない多動
- 急に何かをやりたくなる衝動性
- 何かに没頭しすぎる過集中
現在では、子どもの発達障害については理解が進み、幼少期からのサポート体制が整備されつつあります。
一方で、現在すでに成人している大人は、子どもの頃には自身のADHDに気づかず、大人になって仕事・家事・結婚・育児などのやることや責任が増える中で、「なぜ自分はこれが苦手なんだろう」「できないんだろう)…」となってから気づかれるケースも多いようです。
このコラムでは、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)の知見に基づき、ADHDの概要などについて解説します。(参考:司馬理英『ササッとわかる「大人のADHD」基礎知識と対処法 基礎知識と対処法』、岩波明『大人のADHD─もっとも身近な発達障害』、星野仁彦『それって、大人のADHDかもしれません』)
ADHDでお悩みのあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 平均4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
ADHDとは?

ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害、Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)とは、不注意性や多動性・衝動性の特性から日常生活などに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、田中康雄・監修『大人のAD/HD』、岩波明『大人のADHD─もっとも身近な発達障害』、司馬理英子『ササッとわかる 「大人のADHD」 基礎知識と対処法』、星野仁彦『それって、大人のADHDかもしれません』、e-ヘルスネット「ADHD(注意欠如・多動症)の診断と治療」)
ADHDの特性は大きく、以下の2つの特性に分けられます。
- 不注意性:忘れ物やケアレスミスが多い、注意散漫、整理整頓・管理が不得意
- 多動性・衝動性:落ち着きがない、気が散りやすい、後先考えず行動する
ADHDのある人だからといってすべての特性が生じるというわけではありません。いずれかの特性、または複数の特性から困難が生じている人もいます。
ADHDのある人は、必ず不注意性や多動性・衝動性が現れるというわけではなく、人によって特性の現れ方、得意なこと・不得意なことが違う点が大きな特徴です。
ADHDの特性
ADHDの主な特性は、以下のとおりです。
なお、ADHDのある人全てに、以下の特性が必ずあるとは限りません。また、以下の特性に当てはまる場合でも、必ずADHDであるというわけではありません。
- 忘れ物や失くし物が多い
- 整理整頓が苦手
- 注意散漫でのケアレスミスが多い
- 確認作業が苦手
- 片づけができない
- じっとしていられず落ち着きがない
- 気が散りやすい
- 人の話を聞いていない
- 直接話しかけられても、話を聞いているように見えない
- 思いついたままに発言し、行動する
- 特定のものごとに極端に熱中する
- 他人の会話をさえぎったり、割り込んだりする
- 指示を最後までやり遂げず、仕事を終えられない
- 課題や仕事を計画的に進めることが困難である
- おしゃべりが止まらず、人が口を挟む隙を与えない
- マルチタスクやスケジュール管理が苦手
- 順番を待つのが苦手
- 我慢をすることが苦手
- 時間の経過を正確に把握できない
- 時間の見積もりが甘い
- 未来の予定を具体的にイメージできない
- 時間に対する焦燥感を感じにくい
- 約束を守れない
- 衝動買いをすることがある
- 金銭管理が苦手
- 発想力や独創性に優れている
- アイデアがたくさん浮かぶ
- 好奇心が強く、行動力や決断力がある
- 興味のあることには抜群の集中力を発揮する
ADHDの診断基準

アメリカ精神医学会が定めた精神障害の診察基準『DSM-5』によると、ADHDの診断基準は以下のとおりです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』)
- (a)学業、仕事、または他の活動中に、しばしば綿密に注意することができない、または不注意な間違いをする (例:細部を見過ごしたり、見逃してしまう、作業が不正確である)
- (b)課題または遊びの活動中に、しばしば注意を持続することが困難である (例:講義、会話、または長時間の読書に集中し続けることが難しい)
- (c)直接話しかけられたときに、しばしば聞いていないように見える (例:明らかな注意を逸らすものがない状況でさえ、心がどこか他所にあるように見える)
- (d)しばしば指示に従えず、学業、用事、職場での義務をやり遂げることができない (例:課題を始めるがすぐに集中できなくなる、また容易に脱線する)
- (e)課題や活動を順序立てることがしばしば困難である (例:一連の課題を遂行することが難しい、資料や持ち物を整理しておくことが難しい、作業が乱雑でまとまりない、時間の管理が苦手、締め切りを守れない)
- (f)精神的努力の持続を要する課題(例:学業や宿題、成人では報告書の作成、書類に漏れなく記入すること、長い文書を見直すこと)に従事することをしばしば避ける、嫌う、またはいやいや行う
- (g)課題や活動に使うようなもの(例:学校教材、鉛筆、本、道具、財布、鍵、書類、眼鏡、携帯電話)をしばしばなくしてしまう
- (h)しばしば外的な刺激(成年後期および成人では無関係な考えも含まれる)によってすぐ気が散ってしまう
- (i)しばしば日々の活動(例:用事を足すこと、お使いをすること、青年後期および成人では、電話を折り返しかけること、お金の支払い、会合の約束を守ること)で忘れっぽい
- 上記の項目のうち、6つ以上の項目が少なくとも6か月以上続いている
- 症状のいくつかが2つ以上の環境(職場・家庭・学校など)で見られる
- 12歳以前から複数の症状が見られる
- (a)しばしば手足をそわそわ動かしたりトントン叩いたりする、またはいすの上でもじもじする
- (b)席についていることが求められる場面でしばしば席を離れる (例:教室、職場、その他の作業場所で、またはそこにとどまることを要求される他の場面で、自分の場所を離れる)
- (c)不適切な状況でしばしば走り回ったり高い所へ登ったりする (注:成人では、落ち着かない感じのみに限られるかもしれない)
- (d)静かに遊んだり余暇活動につくことがしばしばできない
- (e)しばしば”じっとしていない”、またはまるで”エンジンで動かされているように”行動する (例:レストランや会議に長時間留まることができないかまたは不快に感じる;他の人には、落ち着かないとか、一緒にいることが困難と感じられるかもしれない)
- (f)しばしばしゃべりすぎる
- (g)しばしば質問が終わる前に出し抜いて答え始めてしまう (例:他の人達の言葉の続きを言ってしまう;会話で自分の番を待つことが困難である)
- (h)しばしば自分の順番を待つことが困難である (例:列に並んでいるとき)
- (i)しばしば他人を妨害し、邪魔する (例:会話、ゲーム、または活動に干渉する;相手に聞かずにまたは許可を得ずに他人の物を使い始めるかもしれない;青年または成人では、他人のしていることに口出ししたり、横取りすることがあるかもしれない)
- 上記の項目のうち、6つ以上の項目が少なくとも6か月以上続いている
- 症状のいくつかが2つ以上の環境(職場・家庭・学校など)で見られる
- 12歳以前から複数の症状が見られる
発達障害グレーゾーンとは?

発達障害グレーゾーンとは、発達障害と同様の特性や傾向がいくつか認められるものの、診断基準を満たすほどではないため、発達障害と診断されるには至らない状態のことです。(参考:姫野桂『発達障害グレーゾーン』)
発達障害グレーゾーンという言葉は、医学的に正式な診断名称ではありません。
ただし、発達障害の確定診断をつけることができない状態のことを発達障害グレーゾーンと表現しているだけであって、発達障害グレーゾーンとは症状が軽いことを意味するわけではありません。
発達障害グレーゾーンについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害の二次障害とは?
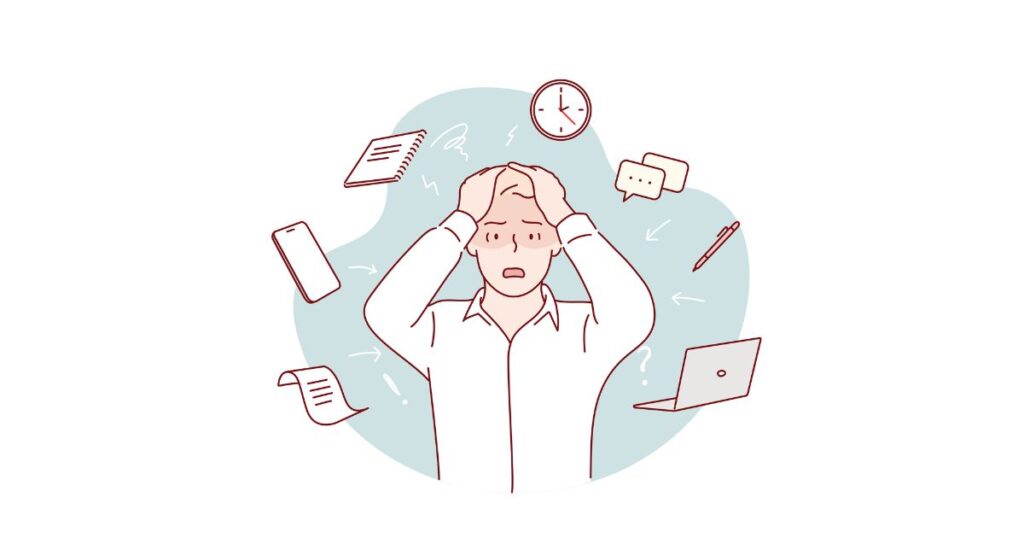
二次障害とは、主障害に起因して起こる副次的な障害のことです。ここで取り上げている発達障害の二次障害とは、発達障害や発達障害グレーゾーンの傾向・特性に伴って発生する精神障害やひきこもりなどの二次的な困難や問題のことを指します。(参考:齊藤万比古『発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート』、小栗正幸『発達障害児の思春期と二次障害予防のシナリオ』)
発達障害の二次障害は、うつ病といった精神面に現れることもあれば、暴力などの行動面で現れることもあります。発達障害に関連して起こる二次的な問題の総称です。
なお、発達障害があると、必ず二次障害が発生するわけではありません。
発達障害や発達障害グレーゾーンの傾向・特性が原因で発生する以下のような困難や問題は、発達障害の二次障害に該当します。
- 周囲とのコミュニケーションが上手く取れずに適応障害になる
- うつ病や不安障害などの精神障害を発症する
- ひきこもり状態になる
発達障害の二次障害については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
大人の発達障害とは?

大人の発達障害とは、医学的に正式な診断名称ではなく、明確な定義がない俗語のことです。(参考:林寧哲『これでわかる 大人の発達障害』、黒澤礼子『新版 大人の発達障害に気づいて・向き合う完全ガイド』)
医学的に正式な診断名称ではないため、明確に定められた定義はありませんが、一般的には、幼少期の時点で診断を受けておらず、大人になってから発達障害の確定診断を受けた状態のことを指すようです。また、幼少期の時点で発達障害の確定診断を受けていた人が、大人になった状態のことを、大人の発達障害と表現することもあるようです。
発達障害は、生まれつきのものです。本来、発達障害の特徴は一般的に乳幼児から幼児期に現れます。大人と子どもで本質的には異なる部分はなく、現在の医学では、大人になっても継続するものとされています。
そのため、「大人になってから発達障害になる」「成長するにつれて発達障害になる」ということはありえません。また、「思春期から」「満〇歳から」「育ち方や親のしつけの影響から」など、成長してから、または環境によって後天的に発達障害になるということも基本的にはありません。
大人の発達障害については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
ADHDの特性に対して、日常でできる工夫・対策
ADHDの方は、その特性に伴って、日常生活で苦手なことや苦労することがあります。代表的な4つの苦労・苦手とその対策を紹介しますので、参考になさってください。
ただしこちらも一般論であるため、もしかしたら「あなた」とは合わないかもしれません。ご紹介する対策は、まずは、「苦手には、対策がある」という安心材料にしてください。
その上で、「実際のあなたの困りごと」への対策は、後述する相談先を利用することで、具体的にわかっていくと思います。お悩みは、一人で抱え込まないことが大切です。
①時間・スケジュールの管理が苦手

ADHDの方は、時間の管理が苦手だったり、不注意によって約束をすっかり忘れたりすることもあります。また、過集中によって「何か」に没頭して予定時間を過ぎていた!などということもあります。
スケジュールや約束は、発生や変更の都度、紙のスケジュール帳に書き込んだり、スマートフォンのカレンダーに入力したりしましょう。スマートフォンの場合は、リマインド機能やアラーム機能も活用できます。予定を「自分の頭の中」だけで覚えようとせず、外部に記録することで、パッと見て「予定がわかる体制」を整えることができます。
特にマルチタスクについては、下記コラムをご覧ください。
②せっかちでイライラする
衝動的で気持ちの抑制が苦手な性質・特性は、日常的なイライラにつながります。イライラはさらに、周囲との衝突や、自分の心身のさらなる不調につながります。
自分がせっかちであると自覚し、心に上手にブレーキをかけましょう。具体的な例としては、「その場所から離れる」「ゆっくり深呼吸を繰り返す」「音楽を聴いてクールダウンする」などがあります。自分の形に合うブレーキを見つけましょう。
③うっかりミスが多い

特性によって、ワーキングメモリー(何かを実行するときに、一時的に記憶を保持・使用するメカニズムのこと)が小さいために、やるべきことをすっぽり抜けて忘れがちで、うっかりミスが多い傾向があります。
毎日の業務や家事の中で、ルーティン化できるものをルーティン化しましょう。次項のチェックリストと合わせて、決まった時間に決まった方法で作業を行うようにすれば、ミスを減らしていけます。
チェックリストを作成し、作業に漏れがないかを確認しましょう。リストは、メモ・手帳・ふせん、スマートフォンのメモ帳などで作成できます。リストの作成・確認に時間・手間がかかる…と思うかもしれませんが、正確に作業を行うことでやり直しなどが減ります。そのため、総合的には、ミスとともに必要な時間・手間も減るはずです。
特にケアレスミスへの対策は、下記コラムをご覧ください。
④すぐにクヨクヨして思い悩む
特性によってミスが多いと、そのことを思い出してついクヨクヨと思い悩んだり、「自分はダメだ…」と思い込んだり、パニックを起こしたりすることもあります。
終わったことは、悩んでいても変わりません。これまでのミスを悔やむのではなく、ミスの原因を見つけ、同じミスを繰り返さない方法を考えることに頭を使いましょう。また、ADHDそのものを公表するかは別として、「ミスが多いことを自覚している。対策を一緒に考えてもらえませんか」と周りに相談する方法もあります。その上で、ミスをしたときには、まず謝るべき人に謝るようにすると、人間関係も変に悪化しないですみます。
ADHDの特性や悩み事を相談できる団体:専門家に相談することが大切
ADHDを含め発達障害の難しいところは、「ADHDである」と本人も周囲も気づいていないケースが多いことです。
周囲も自分自身も「性格のせい」で「努力が足りないせい」と言われ、「発達障害がある」という考えに至らない、ということです。
これまでに紹介したような「特性(に関するお悩み)」に思い当たる節があるようでしたら、ぜひ、支援団体や医療機関と話をする(つながりを保つ)ことをオススメします。
ADHDであってもなくても、お悩みや困り事は、自分だけ、家族だけで抱えず、専門的な知識を有する人たちに相談することで、具体的な解決策や対策が見つかっていきます(また、話をするだけでも気が軽くなります)。
きっと、これからの人生を前向きに歩き始めることができると思います。
ここからは、ADHDのことを相談できる団体の例をご紹介します(地域や他の特性に応じて、他にも相談先はあると思いますので、ぜひ積極的に探してみてください)。
①医療機関

「ある人が発達障害(ADHD)かどうか」は、医師だけが診断できます。
次のような方は、発達障害の診断を行っている病院に行ってみましょう。一般的には、精神科、神経科、心療内科などになると思います。
- まだ診断を受けていなくて、自分が発達障害(ADHD)かどうかを確定させたい方
- 既に診断を受けていて、医学的な相談(服薬、睡眠、体調管理など)をしたい方
「自分が発達障害(ADHD)であることが(=これまでの悩み事・困り事の原因が)わかって安心した」とおっしゃる方は少なくありません。
一方で、いきなり医療機関に行くことに心理的なハードルが高い方(自分が発達障害・ADHDだと確定することが不安な方)もいるでしょう。 また、発達障害を診断できる医師・専門家は、増えてきたとは言え少数なので、予約が難しい場合もあります。
そのような場合は、次項以下の支援機関とまずは話をしてみましょう。「医師の診断を受けるべきかどうか」から相談できますし、診断を受けない場合でもサポートを受けられることもあります。
②発達障害者支援センター
発達障害者支援センターは、発達障害の早期発見と早期支援を目的として、当事者や家族の生活をサポートする支援機関です。運営は、公的な認可を受けた法人が行っています。
発達障害の大人も支援の対象です。また、確定診断が下りていなくても、発達障害の可能性がある方であれば、窓口での相談が可能です。あなたが「ADHDかどうかまだわからない」という状態でも相談できます。
具体的な支援内容は事業者や自治体ごとに異なりますが、生活上の相談の他にも、就労支援事業として、ハローワークなどの関連機関と連携した求人に関する情報提供や、就業先への障害特性に関するアドバイスなどを行っています。
特に精神保健福祉士や社会福祉士などが在籍しているセンターでは、より「ASDなどの発達障害に特化したサポート」を受けられます。
窓口は、各都道府県や指定の事業所に設置されていますので、ご興味のある方はお近くの相談窓口を探してみてください。
③障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは、障害のある方の就業面と生活面の支援を一体的に行うサポート機関です。(参考:京都府「障害者就業・生活支援センターについて」)
専門の支援員が、「長く働くためにはどうすればいいか」「次こそは自分に合った環境で働きたい」「自分の特性を理解しつつ次の就職先を探したい」といった方の相談を受けています。
以下のような方を対象に、様々なサポートを提供しています。
- 求職中の人
- 仕事を辞めたがまた働きたいと考えている人
- 求職相談
- 職場定着相談
- 生活相談
- 職場の環境改善などの相談
- 求職活動を支援するために、ハローワークや事業主等との調整
- 職業準備訓練のあっせん
- 実習先との連絡調整
- ※その他にも様々な支援活動が行われています
障害者就業・生活支援センターの全国一覧はこちらをご覧ください。
④精神保健福祉センター
精神保健福祉センターとは、発達障害を含む精神障害の方のサポートを目的に、精神保健福祉法によって各都道府県に設置された支援機関です。ご本人だけでなく、ご家族や関係者の方からも、精神衛生に関する相談を受け付けています。
前にも述べたとおり、発達障害をお持ちの方は、二次障害として別の精神疾患を抱えることもありますので、相談先として精神保健福祉センターを知っておくことは有益かと思います。
精神保健福祉センターは、他の支援機関と比較して、精神疾患に特化している点が特徴と言えるでしょう。
匿名でも相談を受け付けています。(参考:東京都福祉保健局「精神保健福祉センターとは」)
全国の精神保健福祉センターの一覧は、厚生労働省のウェブサイト「全国の精神保健福祉センター一覧」をご覧ください。
⑤発達支援室・こども発達支援センター

あなたが「お子さんの発達を気にしている親御さん」や「未成年」である場合は、発達支援室やこども発達支援センターなども、有力なサポート団体です。
それらでは、発達が気になるお子さんとその親御さんのために、次のようなサポートを行っています。(参考:東京都新宿区「子ども総合センター 発達支援コーナー 愛称『あいあい』」、大阪市発達障がい者支援センター エルムおおさか「サービス内容」
- 発達相談・サービス利用相談(発達検査の実施、支援利用計画の作成、通所支援の案内などを含む)
- 児童発達支援・放課後等デイサービス
- 在宅児等訪問支援
- 障害幼児一時保育
- 保育所等訪問支援
- 保護者相談会
- 就労支援
- 関係機関との連携支援
- 発達障がいの正しい理解や支援の方法を広めるための研修
- パンフレットやウェブサイトを通じた情報提供
実施内容は市区町村ごとに異なりますので、気になる方はお住まいの市区町村のウェブサイトなどで確認してみましょう。
⑥身近な頼り先(家族や友人など)
家族や友人も、相談先になりえます。あなたのことを思ってくれている家族や友人に相談すると、きっと気が軽くなるはずですし、具体的な解決策が見つかる可能性もあります。
ただし、身近な人たちには「発達障害の専門知識」がない可能性が高いことは心に留めておきましょう。専門的な相談は、前項までに相談した団体などに相談することをお勧めします。
ADHDのお悩み解決のためのお役立ち情報
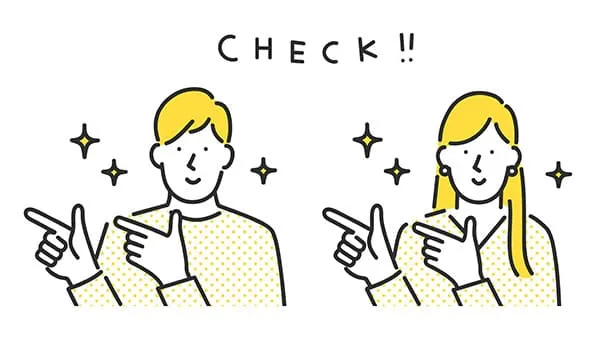
ADHDに関係するお悩みなどを解決するためのコラムを紹介します。気になるものがあれば、ご覧ください。
①仕事・職業関係
ADHDによる職業上の困難を抱えている人は大勢います。本記事では、ADHDの方に向いている職業から、仕事探しをするときのポイントまで、徹底解説します。
仕事の悩みを感じやすい「大人のADHD」。男性に多いと言われることもありますが、もちろん女性もいます。この記事では、ADHDの人が仕事を続けるコツ、配慮を得る方法、仕事探しのポイント、適職、受けられる支援など、「仕事の悩み」を解決する方法を徹底解説します。
ADHDのせいで就職活動がうまくいかないのではないかと不安になっていませんか?ADHDの特性を強みとして活かす方法がわかれば、あなたに合った就職先は見つかります。ADHDの方向けに、ADHDの特徴、アピールポイント、あなたに合った就職先の見つけ方を徹底解説します。
ADHDの人に向けて、転職のコツ、ADHDの人にオススメの仕事、転職成功のためのステップ、転職エージェントの例、転職の体験談などをご紹介します。
ADHDの概要、プログラマーとシステムエンジニアの概要、ADHDの方がプログラマーに向いている理由、ADHDの方がプログラマーに向いていないケース、ADHDの方の仕事術、ADHDの方の仕事探しに役立つサポート団体をまとめて紹介します。
ADHDの方は、仕事で悩むことが多いと言われています。特にADHDの特性である「不注意傾向」が強い場合、遅刻やミスが重なり、「どう対処したらよいか分からない」とお悩みの方も多いです。この記事では、ADHDの方によくある仕事の悩みと具体的な対策を徹底解説します。
②特性対策関係
ADHDの方の緊張感やストレスをやわらげるための対策を、仕事・生活・二次障害に分けて解説します。「雇用枠や働き方の見直し」「起床時間を決める」「定期的なカウンセリング」などを実施することで、ADHDの方の生活・仕事がやりやすくなります。
ADHDの方が仕事を上手に進める上で、「タスク管理」は有効だとよく言われています。しかし、タスク管理がどういうものかよく分からず、「タスク管理を始めたけれど、うまくいかない」と疑問を持つ方が多いかと思います。そこで今回は、仕事でお悩みのADHDの方へ向けて、仕事におけるタスク管理術を徹底解説いたします。
この記事では、ADHDの概要、ADHDとマルチタスクの関係(よくある困り事)、ADHDの方のマルチタスクへの対策例、ADHDの方に向いていると思われる仕事/向いていないと思われる仕事などをまとめて紹介します。
この記事では、ADHDのケアレスミスへの対策、ADHDの概要、ADHDの診断と「治療」、ADHDの相談先、周りの人の対応法などをまとめて紹介します。
③総合的な悩み・私生活関係
ものをなくす、ミスが多い、睡眠障害、やるべき作業を忘れるなどなど、筆者も含めてADHDの当事者は様々な「生きづらい」経験をしています。特性に応じた「生きづらい」を減らすツールを使うことで、生きづらい経験も減り、周囲の理解も得られ、特性を補うことが可能になります。
この記事では、大人のADHDの特徴、大人のADHDかもと思ったときにできること、ADHDの特性への対応方法、ADHDの方の仕事術・仕事の探し方、大人のADHDの方をサポートする団体などをご紹介します。
ADHDの特性に関連して、「人間関係が続かないこと」にお悩みの方は少なくありません。この記事では、ADHDの方が人間関係が続かない理由や解決方法(対策)を紹介します。一つ一つの困りごとの改善方法が見つかり、自分にも自信が持て、さらによりよい人間関係の形成につながっていくはずです。
発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)
発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。
- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)
- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)
- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)
同じ診断名でも、人によって多様な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人は、他の発達障害が併存している可能性もあります。
発達障害の概要や種類、原因、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ:あなたの「生きやすさ」に繋がっていくはず

以上、ADHDの概要をご紹介いたしました。
ADHDの、不注意、多動・衝動、過集中といった特性やそれに伴う困りごとは周囲に理解を得られにくいかもしれません。ともすれば、ご本人であるあなたも、努力不足や、やる気がない事の問題だと思ってらっしゃるかもしれません。
ですが、相談先はたくさんありますし、特性や困り事への対策もたくさんあります。ぜひ、支援機関・サポート団体・医療機関などとお話をしてください。
そうすることで、きっとあなたの「生きやすさ」に繋がっていくはずです。
ADHDの特性を知りたいです。
主な特性は、次の3点です。(1)不注意、(2)多動性、(3)衝動性。詳細はこちらをご覧ください。
ADHDの相談先を知りたいです。
よくある例として、次の6つが挙げられます。(1)医療機関、(2)発達障害者支援センター、(3)障害者就業・生活支援センター、(4)精神保健福祉センター、(5)発達支援室・こども発達支援センター、(6)友人・家族など。詳細はこちらをご覧ください。
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年6月現在8校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年6月現在、首都圏・関西に8校舎を展開しています。トップページはこちら→