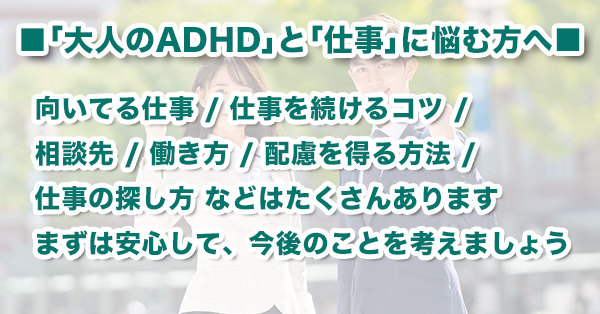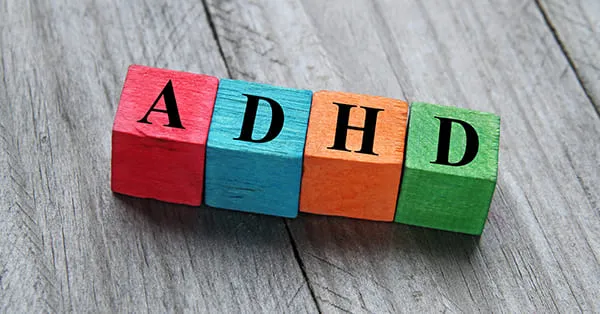マルチタスクが苦手なADHDのある人ができる対策 苦手とする理由を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
ADHD(注意欠如・多動性障害)のあるあなたは、マルチタスクが苦手なことで、以下のようにお悩みではありませんか?
- マルチタスクが苦手だけれど業務上やらなくてはならない
- どういう対策をすればADHDの特性をカバーできるの?
- マルチタスクが苦手でもできる仕事は?
- ADHDに関する具体的な仕事の悩みを相談できるところは?
このコラムでは、マルチタスクが苦手なADHDのある人ができる対策やマルチタスクを苦手とする理由、意識すべきポイント、抱えやすい困難について解説します。
マルチタスクが苦手なADHDのあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 平均4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
マルチタスクが苦手なADHDのある人ができる対策8選
この章では、マルチタスクが苦手なADHDのある人ができる対策について解説します。
あくまで例の一つです。この他にもたくさんありますので、試行錯誤したり、サポート団体に相談したりしてご自身にあった方法を見つけていくことをオススメします。
解説する各対策自体がマルチタスクの一つになるかもしれないというお悩みも、そうした中で解決していくはずです。
対策①ToDoリストを作る

対策の1点目は「ToDoリストを作る」という方法です。
ToDoリストとは、業務の中で実際に取るべき行動、これからすべきことに焦点を絞って項目化したものです。
理想的なToDoリストは、記載事項を順次実行するだけで、目標達成や課題解決に至るリストです。
実際に処理が終わったら、その項目を線で塗りつぶしたり、末尾に「済み」と記載したりと進捗などの状況確認をすることも大切です。
そうすることで、現在の状態が把握できるだけでなく、達成感も得られるため、モチベーションも上がるというメリットも期待できます。
このようなタスクのリスト化は、マルチタスクをしなくてはならないときに、自分のするべき仕事を見失わないための道しるべになります。
自作のメモ帳などが向いてる場合もあれば、アプリやエクセルなどが向いてる場合もあります。
いくつか試して、ご自分に合いそうなToDoリストを見つけてみましょう。
ToDoリスト以外のアプリなどについては、対策⑧でご紹介します。
対策②優先順位を付けて順番に片付ける
何から手をつけて良いのか分からない時には優先順位を付けて順番に片付けることも大事です。
今自分が抱えている作業(タスク)を書き出し、締め切りや難易度などで分類分けをしてみるとやるべきことが明確になるでしょう。
仕事の状況は日々変わるので、「今日の優先順位は、毎朝9時に確認する」など、優先順位を都度、見直すルーティンをつくるようにしましょう。
「優先しなければいけないのは分かっているけど、苦手だ、やりたくない…」と後回しにしたり、なかなか着手する気になれないこともあるかもしれません。
そのようなときは、「とにかく今日はこの案件だけは片付けよう」など、タスクの絞り込みをすることでうまくいく場合もあります。
と、言うのはカンタンですが、「優先順位づけにも苦労がある」というのもよく聞くお話です。慣れないうちは一人で抱え込まず、職場の先輩や上司の助けを借りることも一つの方法です。
対策③周囲の人にリマインドをお願いする

3点目は「周囲の人にリマインドをお願いする」です。
ADHDのある人は、何かの案件に取り組んでいるときに別の案件が舞い込むと、新しい方に気を取られて、元々行っていた案件を後で思い出せなくなったり、次の予定を忘れたりするということも多いと言われています。
周囲の人と予定(「もともと行っていた案件の締切」や「この後の会議の時間」など)を共有して、リマインドをお願いしておくことで「うっかり忘れてしまう」ことの予防をすることができます。
思い出すための時間を削減できますし、失念することも減るはずです。
マルチタスクに伴う困難を一人で解決しようとせず、周りの同僚やご家族に協力してもらえることがないかを考えてみましょう。
「人に頼むのは迷惑かも…」と思う人は、「頼まなかった結果として仕事が滞る方が迷惑」と考えるようにするといいかもしれません。
対策④手帳・メモ帳・スマホを携帯してすぐにメモを取る
「手帳・メモ帳・スマホなどを常に携帯して、タスクが発生したら、すぐにメモを取る習慣をつける」というのも効果的な対策です。
そうすることで、注意散漫による物忘れなどを防止することができます。
ADHD向けのクリニックを開院している福西勇夫先生は、「アイデアが思い浮かんだときにはひとまずメモしておいて、『書き留めたらToDoリストをまず確認する』といったルール設定をすると、効果が上がりやすい」と述べています。 (参考:『マンガでわかる 大人のADHDコントロールガイド』)
アイデアをメモすることは、「もしかしたらこのアイデアを忘れてしまうかもしれない」という焦りを軽減できて、安心にもつながるそうです。
次々に浮かんだアイデアに翻弄されて時間が過ぎることが多いというADHDのある人は、手帳やメモ帳をポケットに入れるなど、携帯するための工夫を取り入れてみるのも一つの手です。
なお、詳しくは対策⑥でお伝えしますが、メモ帳を使うならメモ帳に一本化することもポイントです。
対策⑤リストをすぐに引き出せるようにする

4点目とも関連して、5点目は、「リストをすぐに引き出せるようにする」です。
これにはタスクをすぐに記録できるようにする、タスクを確認しやすくするという2つの目的があります。
整理整頓が苦手の場合、リスト(メモ帳など)が机の上や引き出しの中に埋もれていたり、必要なファイルをどこに保存したのか分からなくなってしまうといったことが起こりやすいと言われています。
メモ帳・手帳・スマホなどは机・カバン・ポケットの決まった場所に配置したり、パッと確認できるところに掲示したりするのがオススメです。アプリやExcelなどを利用するなら、スマホを開いてすぐにアクセスできる場所や、PCのデスクトップ上など、目につきやすいところに配置するようにしましょう。
対策⑥タスク管理の媒体をできるだけ一つにまとめる
6つ目は、「タスク管理の媒体をできるだけ一つにまとめる」です。
ADHDのある人の中には、メモを付ける習慣は身についているけれど、手帳、ノート、電子ファイルなど、複数の媒体に記録が散らばっているということがあります。
タスクを記入する媒体は、できるだけ一つのファイルや手帳にまとめましょう。
急いで書き留めたメモがあったなら、すぐにメインの媒体に集約することが大切です。そうすることで、抜けや漏れといったタスク管理の難しさを緩和できるはずです。
対策⑦整理整頓だけする時間を作る

7つ目は、「整理整頓だけする時間を作る」という方法です。
ADHDのある人は、マルチタスクをして作業に追われているうちに収拾がつかなくなると感じていることが珍しくありません。
一日のうちに整理整頓だけする時間を作ることで、自分の行動や抱えているタスクを一度落ちついて見直すことができるようになります。
整理整頓だけをする時間に、付箋やメモなどを一つの媒体に転記してまとめたり、優先順位を再検討したりすれば、タスクの見通しがずっとよくなるはずです。
対策⑧アプリやツールを利用する
最後にオススメしたいのは、「アプリやツールを利用する」ことです。
すでにご紹介したToDoリスト以外でも、スマートフォンの内蔵アプリや、Googleの提供しているアプリのように、効果的なタスク管理を可能にする無料のツールがたくさんあります。設定した時間になると画面上にアラートを表示するリマインダー機能が付いているものもあります。
また、近年はADHDの特性をカバーすることを目的に開発されたタスク管理ツールが注目を集めています。
例えば、社会福祉法人SHIPの提供している「タスクペディア」は、ADHDの当事者が編みだしてきたタスク管理の手法を採用して開発されています。
また、医療分野において幅広いソリューションを提示している株式会社Welbyが開発した「AOZORA」も、ADHDのある人向けのタスク管理ツールとして知られています。
いずれも、当事者や専門医の監修を経ているので、安心してご利用いただけるでしょう。
ADHDのある人がマルチタスクを苦手とする理由

マルチタスクとは、一般に、業務を並行的に進めたり、同時に処理したりすることを指します。
ADHDのある人が、マルチタスクを苦手とする理由として、以下の2つを挙げることができます。
- タスクに限らず、物事の整理整頓が苦手
- 新しいタスクやアイデアに気を取られやすい
ADHDのある人の中には、物事の整理整頓が苦手という特性にある人が多いです。
そうした場合、未処理の業務が増えるとタスクそのものを失念したり、スケジュールを確認せずに先延ばしにして、仕事が滞りやすくなります。
また、ADHDのある人は発想力に富むため、次々に新しいアイデアが浮かぶという特徴があります。
新しいアイデアが浮かぶこと自体はよいことかもしれませんが、やろうとしていたことから意識が逸れて抜けたり、新規の案件に気を取られて優先順位を見失ったりするケースが少なくないのです。
こうしたADHDの特性が、マルチタスクを困難にしている要因と考えられます。
マルチタスクが苦手なADHDのある人が抱えやすい困難3選
マルチタスクが苦手なADHDのある人は、さまざまな場面で困難を感じやすいといわれています。
この章では、マルチタスクが苦手なADHDのある人が抱えやすい困難について解説します。こうした悩み事もご紹介したサポート団体などと話をすることで、実際のあなたのための具体的な対策が見つかっていくと思います。
困難①ミスや物忘れが頻発する

1つ目は、ミスや物忘れが頻発するという困難です。
急な依頼や新しい案件の方に気を取られやすいため、1つのことに集中して正確に処理をするのが難しくミスや物忘れが頻発し、業務処理に支障をきたしやすいとされています。
困難②業務の向き・不向きの差が大きい
2つ目は、業務の向き・不向きの差が大きいという困難です。
ADHDのある人は、行動力や発想力は高いものの、精密さや細やかさに欠けるため、厳密なスケジューリングや正確な処理を求められると、力を発揮しづらいと言われています。
例えば、窓口業務と事務処理を同時に進めるようなマルチタスクを求められる仕事だと、事務処理の方の正確性が著しく落ち、ケアレスミスをしやすくなる傾向にあります。
それゆえ、以下のように、業務の向き・不向きがはっきりしやすいとされています。
- 営業はできるけれど事務が苦手
- 口頭での説明は得意だけれど資料作成が苦手
困難③どんな職種を選べばいいかわからない

3つ目は、どんな職種を選べばいいかわからないという困難です。
程度の差はあれ、マルチタスクはほとんどの職種につきものです。
仕事では、電話応対、会議資料の作成、事務書類の処理、打ち合わせ、業務の進行や進捗管理などさまざまなタスクを、突発的な案件に対応できる余裕も考慮に入れながら、並行的に進めることが求められます。
しかし、ADHDのある人の場合、特定の業務に取り組んでいると他の業務のことを失念しやすく、パフォーマンスを発揮できる職種がないと感じるケースもあるようです。
結果として「どんな職種を選べばいいかわからない」という悩みも、ADHDのある人によくある困難です。
マルチタスクが苦手なADHDのある人が意識すべきポイント3点
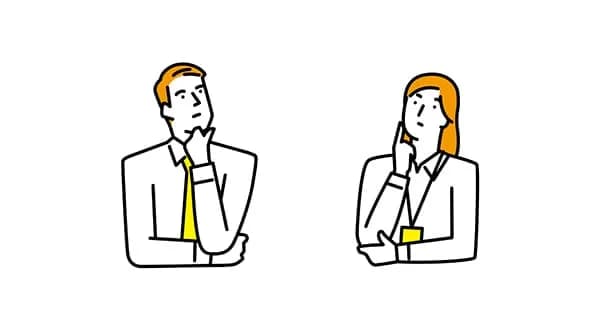
マルチタスクが苦手なADHDのある人が意識すべきポイントは、以下のとおりです。
- 試行錯誤して自分に合った方法を見つける
- 自分一人で抱え込まず、発達障害の支援機関に相談する
- 同時並行が苦手なのか、割り込みが苦手なのかを意識した上で、具体的な困難を記録する
まずは、試行錯誤して自分に合った方法を見つけることです。
書籍やインターネットで解説されている対策は、人によっては合う・合わないがあります。ADHDの特性は人それぞれです
そのため、あくまでも方法論は参考にとどめ、あなたに合った対策を試していくことが大切なのです。
そして、実際に試行錯誤を重ねる際には、自分一人で抱え込まず、発達障害の支援機関に相談することが大切です。
就労移行支援事業所など、専門家のアドバイスを受けながら自分に合う働き方を見つけられるとよいでしょう。
マルチタスクが苦手といっても、大きく分けて同時並行が苦手な場合と割り込みが苦手な場合の2つのパターンがあります
- 電話中にメモを取るのが苦手
- 会議で発言しながら議事録を取ることが苦手
- 作業中に電話を取るのが苦手
- 特定の業務中に話しかけられるのが苦手
これらを意識・記録することで、マルチタスクの苦手さについて、職場や支援者などに相談しやすくなり、対策も考えて行きやすくなります。
ぜひ一人で抱え込まずに、周囲の人やサポート団体を頼るようにしてください。
マルチタスクが苦手なADHDのある人に向いてる仕事・向いてない仕事
この章では、マルチタスクが苦手なADHDのある人に向いてる仕事・向いてない仕事について解説します。
ADHDと一言で言っても、人によって特性、得意な部分・苦手な部分は異なります。また、職場環境や業務内容によっても特性との相性が変わります。
ここで紹介する仕事はあくまで一例であり、この仕事なら必ず向いてる・向いてないという意味ではありません。
マルチタスクが苦手であっても向いてる仕事はあるという安心材料の一つとしてお役立てください。
実際のあなたに向いてそうか、環境の合う求人がありそうかなどについては、前章の相談先などにも相談しながら検討することをオススメします。
マルチタスクが苦手なADHDのある人に向いてる仕事

マルチタスクの苦手なADHDのある人には、以下のようなクリエイティブ系の仕事が向いてるかもしれません。
- デザイナー
- アニメーター
- イラストレーター
- カメラマン
以上の仕事は、一概には言えませんが「シングルタスクの積み重ねで成り立つ仕事」と考えられます。
スケジュール管理や事務仕事が必要とはなりますが、自分の業務に専念できる環境であるため、計算や書類作成の合間に打ち合わせや電話応対が舞い込んくるなどのマルチタスクが生じる可能性は、比較的少ないといえるでしょう。
また、起業家や実業家のような、庶務よりもアイデア出しや企画立案に重点が置かれている仕事や、細かなスケジュール管理は補佐役や秘書がしてくれたりする仕事も向いてる可能性があります。
マルチタスクが苦手なADHDのある人に向いてない仕事
反対に、マルチタスクが苦手な場合は、以下のような庶務や雑務が発生しやすい仕事だと活躍しづらいかもしれません。
- 経理職
- 総務職
- 秘書担当
以上の仕事は、細かい単位のマルチタスクや処理の正確さ、スケジューリングの厳密さが求められます。
苦手なマルチタスクの機会が多い→ケアレスミスが頻発する→修正処理に追われてパニックになる。という流れが比較的発生しやすく、活躍がしにくい可能性があります。
マルチタスクが苦手なADHDのある人が利用できる支援機関
この章では、マルチタスクが苦手なADHDのある人が利用できる支援機関を紹介します。
ここで挙げている支援機関の中には、マルチタスクの対策を含めて、ADHDのある人が実際の仕事で活躍するための訓練を実施しているところもあります。
基本的には無料で相談を受け付けている機関のみを紹介していますが、その他にも支援機関は多数ありますので、興味を持ったなら、ぜひ調べてみてください。
支援機関①就労移行支援事業所

就労移行支援事業所では、病気や障害と向き合いながら一般企業への就職を目指す人向けに、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを提供しています。 (参考:厚生労働省※PDF「就労移行支援事業」)
就労移行支援事業の対象となるのは、以下の条件を満たす人です。
- 原則18歳から65歳未満であること
- 一般企業への就職または仕事での独立を希望していること
- 精神障害、発達障害、身体障害、知的障害や難病を抱えていること
※障害者手帳は必須ではなく、専門医による診断書があればサービスを受けることができます。
具体的な支援内容は事業所によって異なりますが、あなたの障害特性に合わせた個別支援計画に基づいて、職業相談からメンタル面の相談、基本的なタスク処理の訓練や専門スキルの習得、インターン先から就職先の紹介までと、幅広いサポートを行っています。
相談は無料ですので、支援内容に興味を抱いた事業所に一度、詳細をお問い合わせください。
就労移行支援事業所の詳細は、コラム「就労移行支援とは?サービス内容から就労継続支援との違いまで解説」をご覧ください。
支援機関②発達障害者支援センター
発達障害者支援センターは、発達障害の早期発見と早期支援を目的として、症状に悩む当事者や家族の生活をサポートする支援機関です。
確定診断が下りていなくても、ADHDなどの発達障害の可能性がある人であれば、相談が可能です。
子どもだけでなく、大人も支援の対象です。
センターによっては、精神保健福祉士や社会福祉士などが在籍していますので、より発達障害に特化したサポートを受けられます。
具体的な支援内容は自治体ごとに異なりますが、生活上の相談の他にも、就労支援事業として、ハローワークなどの関連機関と連携した求人に関する情報提供や、就業先への障害特性に関するアドバイスなどを行っています。
窓口は、各都道府県や指定の事業所に設置されていますので、支援をご希望の場合は以下の参考リンクからお近くの相談窓口を探してみてください。
- 国立障害者リハビリテーションセンター「発達障害者支援センター・一覧|相談窓口の情報」
支援機関③障害者就業・生活センター
障害者就業・生活支援センターでは、就業及びそれに伴う日常生活上の支援が必要な障害のある人に対し、センター窓口での相談や職場・家庭訪問などを実施しています。
そのため、仕事に関する相談だけでなく、生活面でのサポートもあわせて受けたい人にオススメです。
厚生労働省の資料によると、2023年4月時点で337センターが設置されており、当事者の身近な地域において、就業面と生活面を一体に捉えた相談と支援を行っています。
興味のある人は、以下のサイトを参考に、お近くの事業所にご相談ください。
- 厚生労働省「障害者就業・生活支援センター」
支援機関④地域障害者職業センター

地域障害者職業センターでは、発達障害に限らず、障害者一人ひとりのニーズに応じて、職業評価、職業指導、職業訓練などの専門的な職業リハビリテーションサービスを提供しています。
とりわけ、自分に合った職業や職種が見つからないことで悩んでいる人にオススメです。
運営は、「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」が行っており、全国47都道府県に設置されています。
また、当事者だけでなく、事業主に対しても障害者の雇用管理に関する相談・援助を実施しています。ご興味のある人は以下の参考リンクからお近くの相談窓口を探してみてください。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」
ADHDとは?

ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害、Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)とは、不注意性や多動性・衝動性の特性から日常生活などに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、田中康雄・監修『大人のAD/HD』、岩波明『大人のADHD─もっとも身近な発達障害』、司馬理英子『ササッとわかる 「大人のADHD」 基礎知識と対処法』、星野仁彦『それって、大人のADHDかもしれません』、e-ヘルスネット「ADHD(注意欠如・多動症)の診断と治療」)
ADHDの特性は大きく、以下の2つの特性に分けられます。
- 不注意性:忘れ物やケアレスミスが多い、注意散漫、整理整頓・管理が不得意
- 多動性・衝動性:落ち着きがない、気が散りやすい、後先考えず行動する
ADHDのある人だからといってすべての特性が生じるというわけではありません。いずれかの特性、または複数の特性から困難が生じている人もいます。
ADHDのある人は、必ず不注意性や多動性・衝動性が現れるというわけではなく、人によって特性の現れ方、得意なこと・不得意なことが違う点が大きな特徴です。
ADHDの概要や特性、診断基準などについては、以下のコラムで解説しています。
まとめ:ADHDの特性でマルチタスクが苦手でも、対策はあります

特性に伴う苦手をカバーするため以下の3つを意識してみてくださいね。
- 試行錯誤して自分に合った方法を見つけていくこと
- 自分一人で抱え込まず、発達障害のサポート機関と相談をすること
- 同時並行が苦手なのか、割り込みが苦手なのかを意識した上で、具体的に困った話を記録する
ADHDのある人が仕事をうまく進めるためには、自分の特性を理解して、それに合った方法を身につけることが大切です。
その際には、上司や同僚などの職場の人にサポートを求めたり、かかりつけの医師や専門家、支援機関の意見を取り入れてみてください。
マルチタスクが苦手でも、対策次第で仕事を上手に進めることはできますから、安心してください。
このコラムが、マルチタスクにお悩みのあなたのお役に立ったなら幸いです。
ADHDでマルチタスクに悩む自分が相談できるところを知りたいです。
監修志村哲祥
しむら・あきよし。
医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。
臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。
【著書など(一部)】
『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』
他、学術論文多数
日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧
時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年6月現在8校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
監修角南百合子
すなみ・ゆりこ。
臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年6月現在、首都圏・関西に8校舎を展開しています。トップページはこちら→