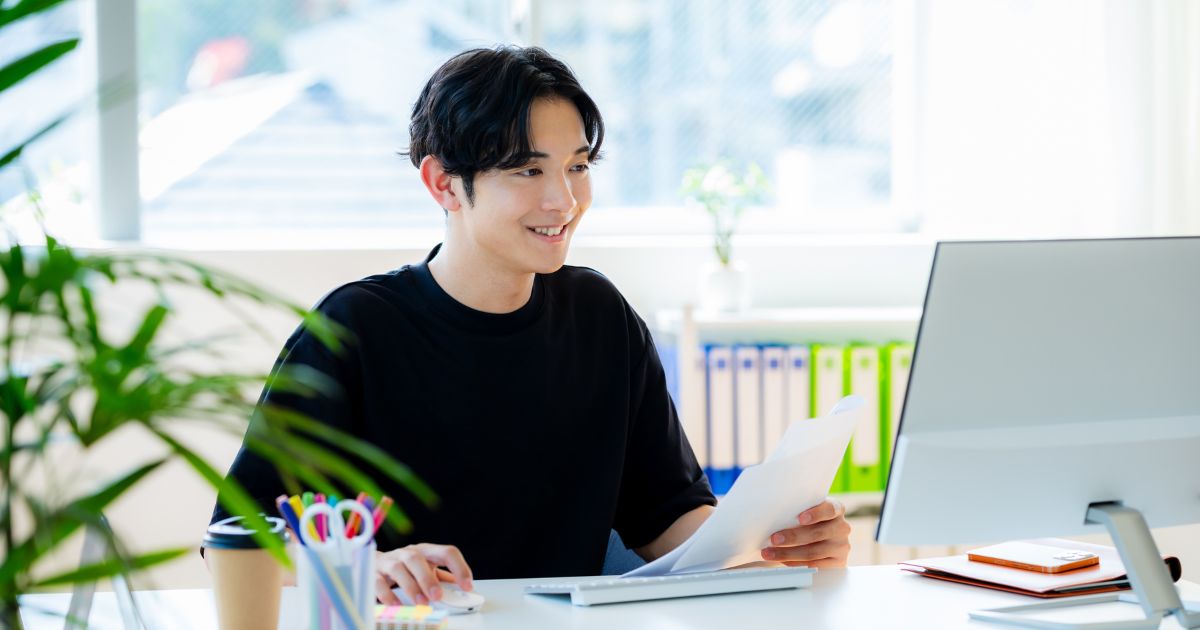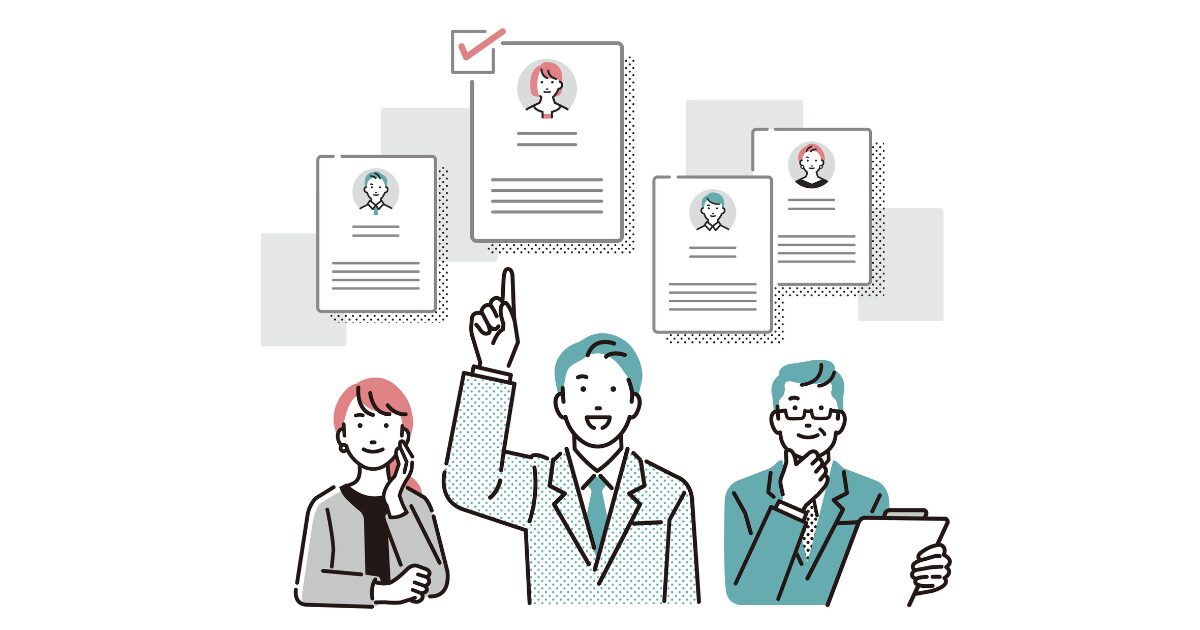発達障害のある人のグループホーム利用まとめ 利用の流れや注意点を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)利用者で発達障害の当事者である伊東里奈(仮名)です。
病気・障害のある人がサポートを受けながら共同生活を行うグループホーム。グループホームは、発達障害のある人も利用可能です。
このコラムでは、グループホームの概要や支援内容、利用する条件、グループホームのタイプ、スタッフ、利用する流れ、利用するメリット、利用する際の注意点について解説します。
発達障害があり、グループホームの利用を考えている人、実家を出てグループホームに入居したい人、一人暮らしをやめてグループホームに入居する人などには、参考になるはずです。ぜひご覧ください。
また、ご本人以外に、親御さんなどご家族が読んでも参考になると思います。
グループホームの利用を検討しているあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 平均4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
グループホームとは?
この章では、グループホームの概要や支援内容、利用条件について解説します。
グループホームの概要

グループホームとは、病気・障害のある人が、専門スタッフやヘルパーの支援を受けながら複数人と集団生活を行う家のことです。(参考:厚生労働省「グループホーム」)
厚生労働省は、以下のように説明しています。
知的障害者や精神障害者、認知症高齢者などが専門スタッフの支援のもと集団で暮らす家のこと
(参考:厚生労働省「グループホーム」)
自分一人ではなかなか親元からの自立が難しい場合、または、一人暮らしに不安があると感じる場合、スタッフの補助を受けながら自分の力で暮らせるグループホームは、選択肢の一つに挙げてもよいでしょう。
発達障害のある人の場合、以下のように考えている人は、グループホームが向いているかもしれません。
- いつまでも親に甘えたくない
- 自分で生活したいが、完全な一人暮らしには自信がない
グループホームは、一般的な「施設」というよりも、家庭的な雰囲気を感じられる場所です。共同住宅タイプや戸建てタイプなどさまざまなタイプがあります。
厚生労働省も、「障害のある方が地域の中で家庭的な雰囲気の下、共同生活を行う住まいの場」と説明しています。(参考:厚生労働省「障害者の住まいの場の確保に関する施策について」)
1つのグループホームに入居する人数は多くの場合、2〜10人程度です。個室はもちろん、共有の居間や浴室等、共同生活に必要なものがそろっています。
グループホームの支援内容
グループホームでは、以下のようなサービスが提供されることがあります。具体的な内容はホームによって異なります。
- 食事の提供
- 健康管理
- 金銭管理
- 緊急時などの安全管理
- 料理、掃除、洗濯などの基本的な生活のサポート・アドバイス
グループホームでは、入居者個々人の得意・不得意を考慮して、「どうすればあなたらしく生きていけるか」をスタッフと一緒に考えながら生活を組み立てることができます。
生活を組み立てるために、利用者ごとの個別支援計画が作られます。
個別支援計画とは、以下のような困りごとの改善についての、目標と改善策のことです。
- 働いてお金を稼ぐことはできているが、金銭管理が苦手なので、サポートしてほしい
- 忘れっぽくて、書類の管理・提出・記入のミスが多いので、一緒にチェックしてほしい
- コミュニケーションが苦手だが、少しずつ練習していきたい
- 生活のこと、仕事のことで困ったり、不安だったりすることを相談したい
- 洗濯機の使い方、洗濯物の干し方、掃除機の掛け方など、困ったりわからなくなったりしたときに、相談できる人がほしい
計画と目標のモニタリングを、半年に1回程度見直していくことができます。また、必要に応じて支援内容を調整することも可能です。
あなたの得手不得手に合わせた生活を、一緒に作っていけるはずです。
グループホームを利用する条件
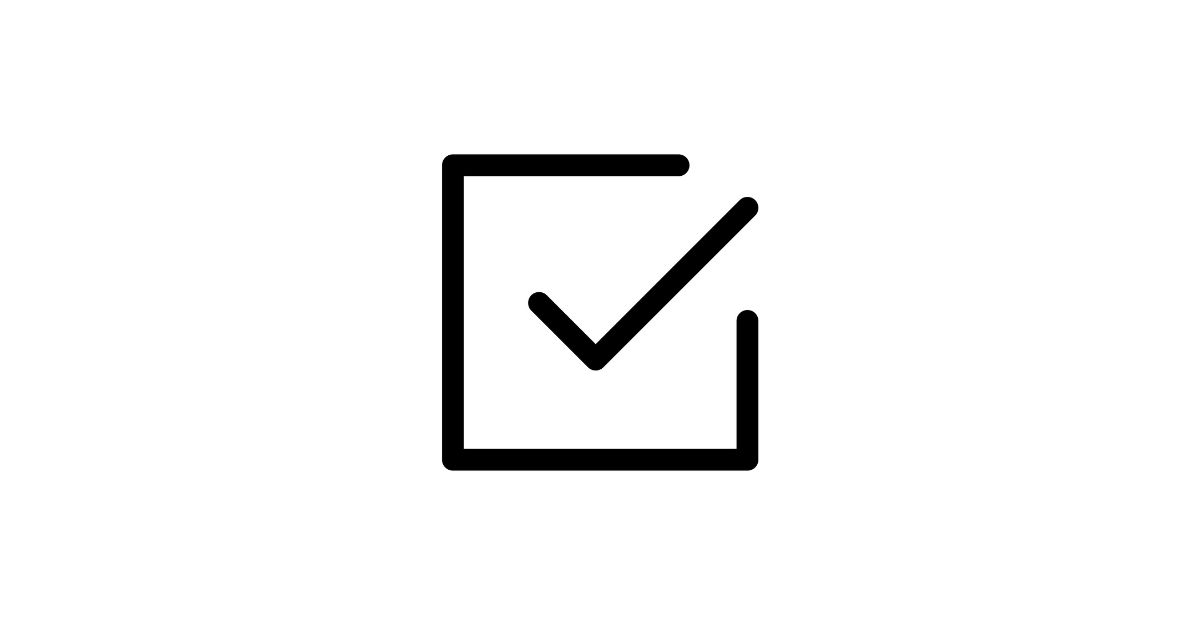
グループホームを利用できる人は、基本的に、支援があれば共同生活に支障をきたすことなく、自立した生活が送れる人です。
具体的には以下のとおりです。
- 身体障害のある人
- 知的障害のある人
- 精神障害のある人
- 発達障害のある人
- 難病のある人
18歳以上65歳未満
※身体障害のある人の場合は、65歳以上の人、65歳の誕生日前日までに障害福祉サービスを利用したことがある人も利用可能。
補足①:グループホームの利用には、障害者手帳の提示を求められることがある
グループホームを利用するためには、障害者手帳の提示を求められることがあります。障害者手帳があるとスムーズに進むので、持っていない場合は事前に準備をしておくと良いでしょう。
障害者手帳とは、障害がある人に交付される手帳のことです。
障害者手帳をお持ちの人は、障害者総合支援法の対象となり、グループホーム利用以外にもさまざまな支援が受けられます。(参考:厚生労働省「障害者手帳について」)
障害者手帳については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
補足②:グループホームは、生活保護などを受給しながら利用できる
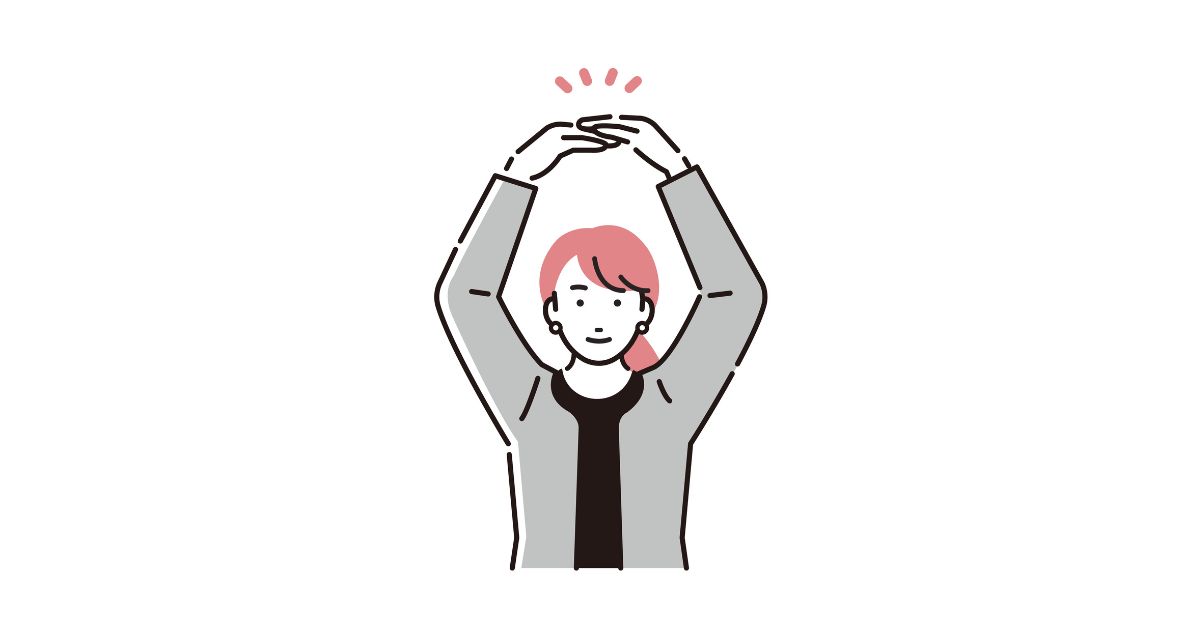
グループホームは有料ですが、経済的に難しい場合やまだ働けない場合は生活保護などの経済的支援制度を受給しながら入居できます。
生活保護の場合は、家賃に使える金額である家賃扶助基準額が設けられているので、その範囲内の金額を利用することになります。
ただし、一般論として、発達障害があるというだけで生活保護を受給することは難しいとされています。なぜなら、受給の可否は、経済状況も含めた「困難の程度」から判定されるからです。
経済的支援は他にもあります。「実際のあなたが何を利用できるか」については、専門家や支援機関に相談してみてください。
特に、役所・グループホーム・発達障害のある人たちをサポートする団体などに確認することをオススメします。
生活保護については、以下のコラムで解説しています。うつ病のある人に向けたコラムですが、生活保護そのものの解説は発達障害のある人が読んでも参考になるはずです。ぜひご覧ください。
グループホームの4つのタイプ
発達障害のある人の場合、生活援助事業としてのグループホームを利用することになります。
生活援助事業としてのグループホームとは、主に知的障害や精神障害のある人向けのグループホームのことです。
こうしたグループホームでは、自力で社会生活を営むために、補助が必要なポイントをスタッフがサポートし、円滑に生活できるようになっています。
この章では、グループホームのタイプについて解説します。
どのタイプのグループホームがあなたに合うか、参考になれば嬉しいです。
タイプ①外部サービス利用型グループホーム

外部サービス利用型グループホームとは、自立した日常生活を営む上で、援助が必要な人を対象としたグループホームのことです。
主に夜間において、相談や日常生活の中で必要な援助を提供します。
一概には言えませんが、キズキビジネスカレッジ(KBC)の見聞きする範囲では、発達障害のある人は、この外部サービス利用型グループホームを利用することが多いようです。
うつ病や身体障害など、別の病気・障害もある場合は、他のタイプも様々に検討してみましょう。
入浴・排泄・食事のような介護系の援助を外部の介護事業所に委託している点は、こちらで紹介する介護サービス包括型グループホームとの違いです。
タイプ②サテライト型住居グループホーム
サテライト型住居グループホームとは、2014年に創設された新しいタイプのグループホームのことです。(参考:厚生労働省「障害者の住まいの場の確保に関する施策について」」)
グループホームの近くにあるアパートやマンションなどで生活し、本体のグループホームで食事をしたり、他の利用者との交流を持ったりできます。
何か生活をしていく上で困ったことがあれば、必要に応じてグループホームの支援員のサポートを受けられます。集団生活が苦手な人や、グループホームを出たら一人暮らしをしたいと考えている人に適しており、一人暮らしに近いかたちで利用できます。
利用できる期間が2年間と期限つきという点は、注意が必要です。
タイプ③介護サービス包括型グループホーム

介護サービス包括型グループホームとは、日常生活で援助が必要な人が対象のグループホームのことです。
主に夜間や休日に、相談・入浴・排泄・食事等の介護サポートをします。
利用する人の職場や日中活動サービスとの連絡調整や余暇活動などの、社会生活上の援助もしています。
タイプ④日中活動サービス支援型グループホーム
日中活動サービス支援型グループホームとは、重度の障害や高齢であるために他の日中サービスを受けられない人を対象としているグループホームのことです。
家事や相談などの日常生活上のサポート、入浴・排泄・食事の介護サービスなどに対応しています。
他のグループホームが夜間や休日にサービスを実施するのに対し、日中の時間帯もグループホームで過ごすことができます。
そのため、世話人や生活支援員の人数が他のグループホームより多めに配置されています。
定員1〜5人の短期入所を併設し、在宅で生活する人の緊急一時的な宿泊の場となることもあるそうです。
補足:日常生活に近い生活をする介護サービスのあるグループホーム

日常生活に近い生活をする介護サービスのあるグループホームとは、認知症のある高齢な人向けが多いグループホームのことです。
病院では生活に変化がなく認知症が進行しやすくなるため、リアルに近い生活やケアをすることで進行を遅らせることを目的としたグループホームです。発達障害のある人には、直接的には関係ないかもしれません。
グループホームのスタッフ
グループホームを利用するにあたって、どのような人が働いていて自分を手助けしてくれるのか気になりますよね。
この章では、グループホームのスタッフについて解説します。
スタッフ①世話人

主な仕事は、日常生活上の健康・金銭管理や家事などのサポートや相談業務です。服薬管理や生活相談も担当しています。
スタッフ②生活支援員
生活の相談や入浴などをサポートします。
世話人と似ていますが、主な仕事は、障害のある人のお風呂や排泄、食事介助などの介護業務です。
スタッフ③管理者

グループホーム全体のマネジメントや業務全体の管理を担当しています。
働くスタッフ、利用する人、施設の運営や収支など、グループホームが滞りなく運営できるよう日々チェックしています。
スタッフ④サービス管理責任者
個別支援計画の作成などをします。
利用する人の特性や今後の展望など、様々な情報に基づいて目標設定をしていきます。
それに伴い、医療機関や支援機関などと連携し、利用する人に合ったサービスを提供するため調整をしたりすることもあります。
発達障害のある人がグループホームを利用する流れ
この章では、発達障害のある人がグループホームを利用するまでの一般的な手続きの流れについて解説します。
流れそのものとともに、自分でできること、他の人に手伝ってもらうと助かることも確認しましょう。
流れ①入居するグループホームを探す

まずは、入居したいグループホームを探します。
各グループホームは、インターネット検索などで探すことができます。
また、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に問い合わせて、グループホームを利用したい旨を伝えると、その自治体にあるグループホームやその特徴などの詳細を教えてもらえると思います。
流れ②障害福祉サービスの受給申請を行う
利用したいグループホームが見つかったら、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に行きます。
グループホームを利用するためには、自治体による障害支援区分の判定と、利用の許可が必要だからです。入居契約そのものは、グループホームと直接行います。
契約成立までは、1〜2か月くらいかかることもあります。
流れ③グループホームの見学をする

気になるグループホームが見つかったら、連絡を入れて、見学に行きましょう。
Webサイトの写真でも雰囲気は掴めるかもしれませんが、実際に現地に行った方が、自分が利用したときのイメージが沸きやすいはずです。
また、スタッフや、時間が合えば他の利用する人とも話して、より具体的な雰囲気やルールなど確認できます。
ただし、申請してすぐに入居できるわけではありません。一般的には、複数のグループホームを見学することが望ましいです。
流れ④希望のグループホームでの面談をする
見学後は、グループホームのスタッフと面談を行い、あなたが利用できそうかどうかの検討や、入居に際しての詳細な条件などを話し合います。
この段階では、あなたの特性や日々の困りごと、どのようなサポートや支援が適切かなど、様々なことを聞かれると思います。
聞かれた内容を元に、サービス等利用計画の作成や、利用契約などを進めていきます。
特性などについては事前にメモに書いておくなど準備しておくとよいでしょう。また、その場で答えられなければ、後日に伝えましょう。
グループホームによっては、契約までに複数回の面談をすることもあります。
流れ⑤契約をしてグループホームに入居する

自治体の許可が出たら、入居契約を成立させて入居できます。
荷物や書類など、入居に向けて必要なものを準備しましょう。
グループホームごとに入居までかかる時間や必要書類が異なる場合があります。漏れがないようにこまめにチェックしましょう。
発達障害のある人がグループホームを利用する4つのメリット
発達障害のある人がグループホームを利用するメリットについて解説します。
グループホームに住むご自分の姿をイメージする手助けになればと思います。
メリット①サポートを受けながら、自分の生活を築いていける
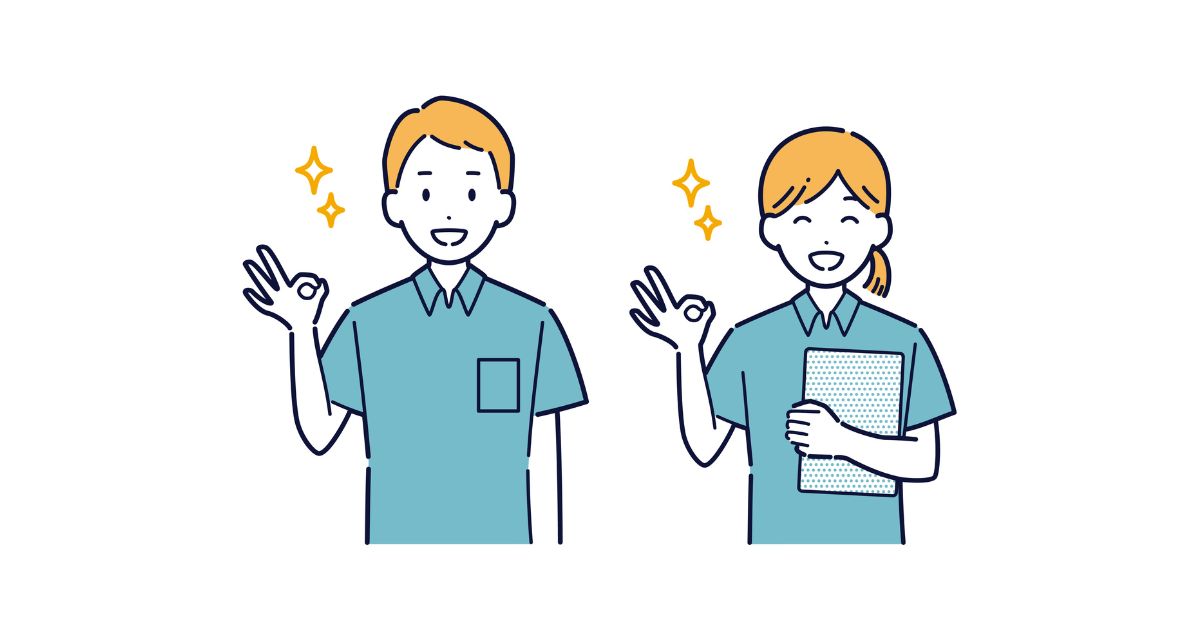
グループホームでは、スタッフのサポートを得ながら、自分でできる範囲で生活リズムや生活パターンを作り上げていくことができます。
実家などで誰かと同居していると、同居人との生活リズムの兼ね合いを考えなければなりません。逆に、一人暮らしでは自分で生活リズムを一から作らなければならないため大変です。
グループホームであればそれらの悩みを、解消できるでしょう。
メリット②専門スタッフの具体的なサポートを得られる
グループホームでは、サービス等利用計画に基づいた日々の具体的なサポートを受けることができます。
書類手続きや炊事、整理整頓、掃除など、自分だけでは苦手なことやできないことに関しては、スタッフのサポートを受けられます。
一方で、これなら自力で何とかできるということは、積極的に自分の力でやっていくこともできます。
例えば、少しずつ料理ができるようになりたいと思う人が、スタッフのサポートを得ながら練習して、苦手を克服していくなどです。
支援を通じて、自分の力でどのように生活を築き上げていくのかを決められます。
メリット③生活の安定によって、心身も安定する

グループホームでは、衣食住のサポートを受けたり、手続きなどのわからないことや苦手なことの手助けも受けたりできるので、生活が安定します。
「自分で何とかしなくては」と背負い込む必要が自然となくなるため、ストレスが軽減し、心身ともに安定するはずです。
一人暮らしでは、日々の仕事、家事、その他手続きなどを自分一人で運営しなければならないため、自動的にワンオペ状態になることもあるでしょう。
それらの調整が苦手な発達障害のある人にとっては、精神的にも肉体的にも負担が大きいことは想像に難くありません。だからこそ、一人暮らしに尻込みする発達障害のある人はよくいらっしゃるはずです。
メリット④自立を通して自分に自信を持てる
グループホームでは、スタッフのサポートを受けつつ、自分の生活をコーディネートし、自分の生活を運営していきます。そうした中で、「自分も自立できる!」と、自分を認めることができるようになるはずです。
発達障害のある人は、個人差はあれど、その特性から他者と衝突したり、同年代に比べて失敗が多かったりします。そのために親や教師などの大人から怒られることも多く、自分に自信を持てなくなることがあったはずです。
グループホームを通じてできることが増えていくことで、傷ついて失った自信を取り戻していけるでしょう。
発達障害のある人がグループホームを利用する際の注意点
この章では、発達障害のある人がグループホームを利用する際の注意点について解説します。
実際にグループホームの利用を検討している途中で、「しまった!?」という事態になることを防ぐために、ここで確認しておきましょう。
注意点①入居期限がある場所とない場所がある

グループホームには、入居期限がない滞在型と、入居期限3年という原則がある通過型の2種類があります。
入居を検討する際には、いつまで入居できるのか、どのくらい入居していたいのかなどを慎重に考えましょう。
注意点②利用費がかかる
グループホームの利用には、以下のように、家賃などの費用がかかります。
- 家賃
- 福祉サービス料
- 食費
- 光熱費
- その他の生活費
こちらで解説したとおり、グループホームは、生活保護を受給しながらの利用も可能です。生活保護以外にも、各自治体で設けられている支援制度もあります。
金銭面に不安があるなら、どのような支援制度があるのか、あなたが利用できるのかなど、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口や専門家、支援機関に相談してみてください。
注意点③すぐには入居できない

グループホームは、申請してすぐに入居することはできません。
事務的に必要な、障害福祉サービスの受給には最大で約2か月、合計で長ければ約3か月以上が必要です。
また、時間をかけて面談・手続きをするグループホームもあります。
そもそも、最初のグループホーム探しや、見学日の調整、引越しの準備などにも時間が必要です。入居までの道のりは、月単位で考えておくのがよいでしょう。
似た話として、「希望するグループホームに、入居できる空きがない」可能性も考慮しておきましょう。
注意点④スタッフの人数や生活環境が希望と合わないことがある
グループホームでは、スタッフの人数・配置や生活環境がそれぞれで異なります。「そのグループホームでは、どのようなサポートをいつ受けられるのか」をきっちり把握しておきましょう。
24時間対応しているグループホームもありますが、「困ったときに、いつでもリアルタイムで相談できる」というイメージを持って入居しても、自分が利用しているグループホームは対応していない、という可能性があるのです。
キズキビジネスカレッジ(KBC)の見聞きする範囲でも、実際にグループホームに入居している人から、「自分の都合のつく時間にはスタッフがいないから、支援を受けづらい」という話が寄せられることもあります。
また、日中の活動場所が決まっていないと入居できないグループホームもあります。注意しておきましょう。
発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)
発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。
- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)
- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)
- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)
同じ診断名でも、人によって多様な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人は、他の発達障害が併存している可能性もあります。
発達障害の概要や種類、原因、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ:サポートを受けつつ自分なりの自立した生活を築いていきましょう

「自立して自分らしく生きたい」という気持ちは、発達障害の有無を問わず、誰しも持っている当たり前のものです。
サポートを受けつつ、自分なりの生活を築き上げていけたらいいですよね。
お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口や発達障害のある人を支える支援機関に相談すれば、グループホームの利用だけでなく、その他の支援制度や支援機関に繋がることができるかもしれません。
誰かに頼った時点で、それは自立とは言えないなんてことはありません。
発達障害の有無に関係なく、人間は、日常の些細なことまで誰かの手助けを得て生きています。いろんな人たちに苦手なことのサポートを受けて、自分の得意なことを活かして生きていくことが「自立」なのだと、私は思います。
いろんな方法を模索して、あなたらしい暮らしを築いていきましょう!
グループホームとは、どんな場所ですか?
グループホームとは、病気・障害のある人が、専門スタッフやヘルパーの支援を受けながら複数人と集団生活を行う家のことです。
詳細については、こちらで解説しています。
グループホームには、どんなタイプがありますか?
以下が考えられます。
- 外部サービス利用型グループホーム
- サテライト型住居グループホーム
- 介護サービス包括型グループホーム
- 日中活動サービス支援型グループホーム
- 日常生活に近い生活をする介護サービスのあるグループホーム
詳細については、こちらで解説しています。
監修志村哲祥
しむら・あきよし。
医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。
臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。
【著書など(一部)】
『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』
他、学術論文多数
日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧
時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年6月現在8校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
監修角南百合子
すなみ・ゆりこ。
臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年6月現在、首都圏・関西に8校舎を展開しています。トップページはこちら→