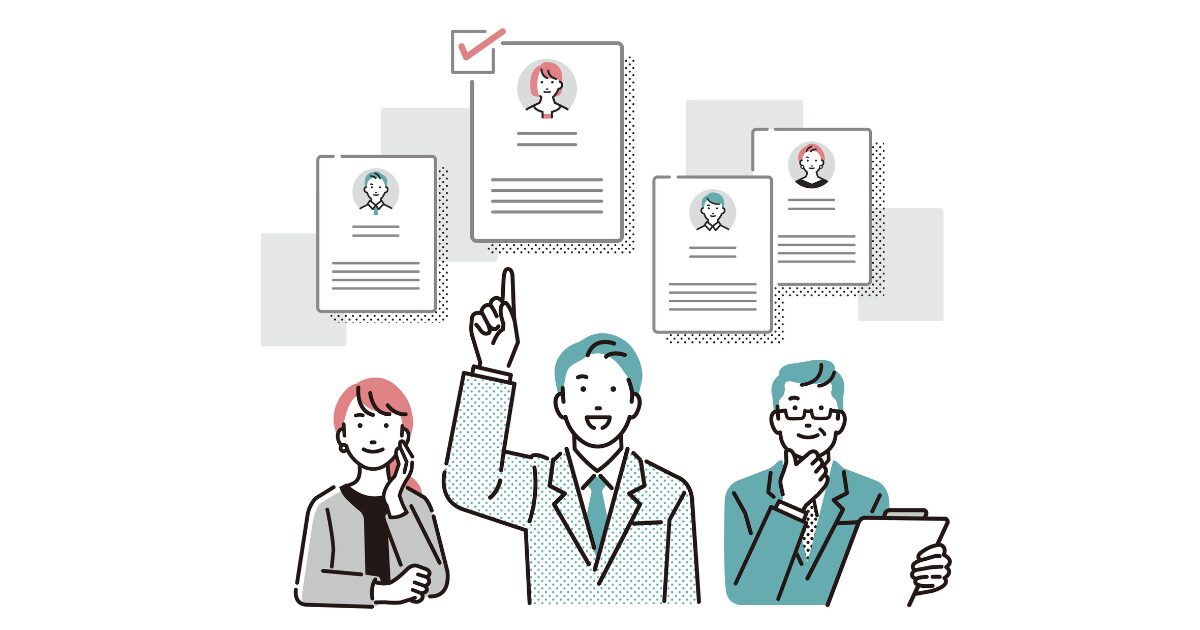仕事ができないのは発達障害のせい? お悩み別の対策と対処法を解説
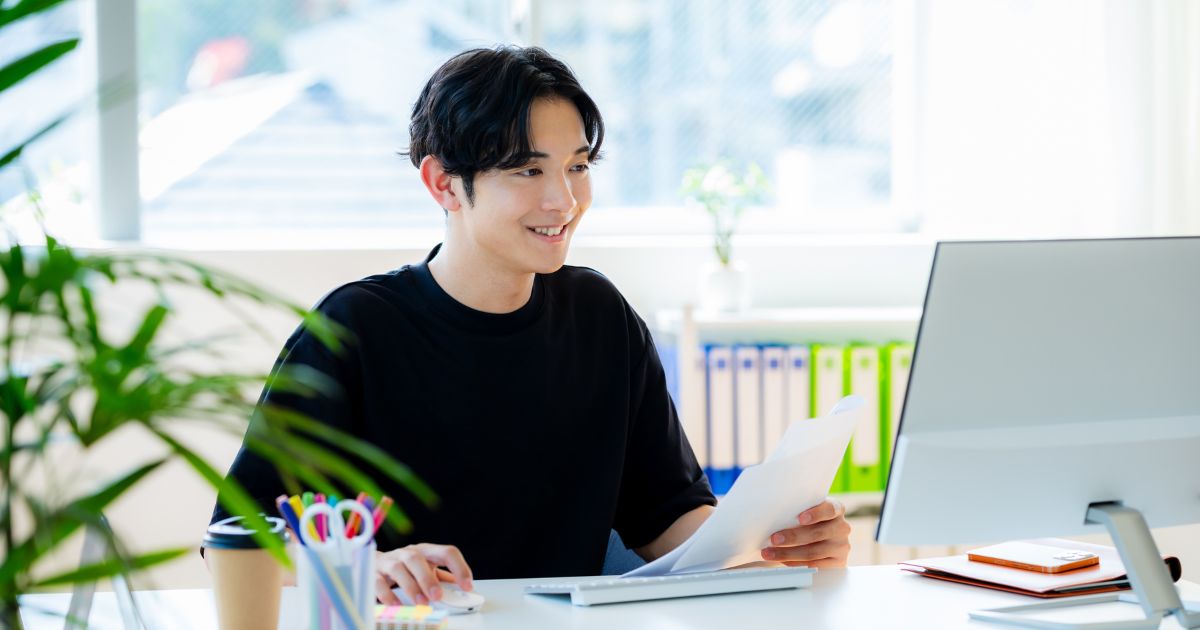
こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
このコラムをお読みのあなたは、発達障害が原因で仕事ができないと悩んではいませんか?
「大人の発達障害」という言葉が知られるようになって以来、仕事ができないことで悩む発達障害のある人の存在が広く認知されるようになりました。
それに伴い、発達障害のある人ができる仕事術や、職場の人ができる配慮についても、様々な方法や意見が交わされるようになってきています。
このコラムでは、仕事をする上で発達障害のある人が抱えやすい困難や対策、対処法、仕事探しのコツについて解説します。あわせて、一緒に働いている人ができる対応を紹介します。
仕事ができないと悩んでいる発達障害のある人は、ぜひ一度、読んでみてください。
さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、発達障害の特性によるストレスに悩む人に向けて、発達障害の特性に合わせた『"発達障害"特化型ストレス対策ハンドブック』を無料配布を開始いたしました。
ストレスの原因を特性との関係から丁寧に解説し、気づきを得られる自己診断チェックリストを掲載。すぐに使える対処法を一冊にまとめています。
ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。
また、発達障害の特性によるストレスへの対処法については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。
仕事ができないとお悩みの発達障害のあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 平均4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
「発達障害だから仕事できない」とあきらめる必要はありません
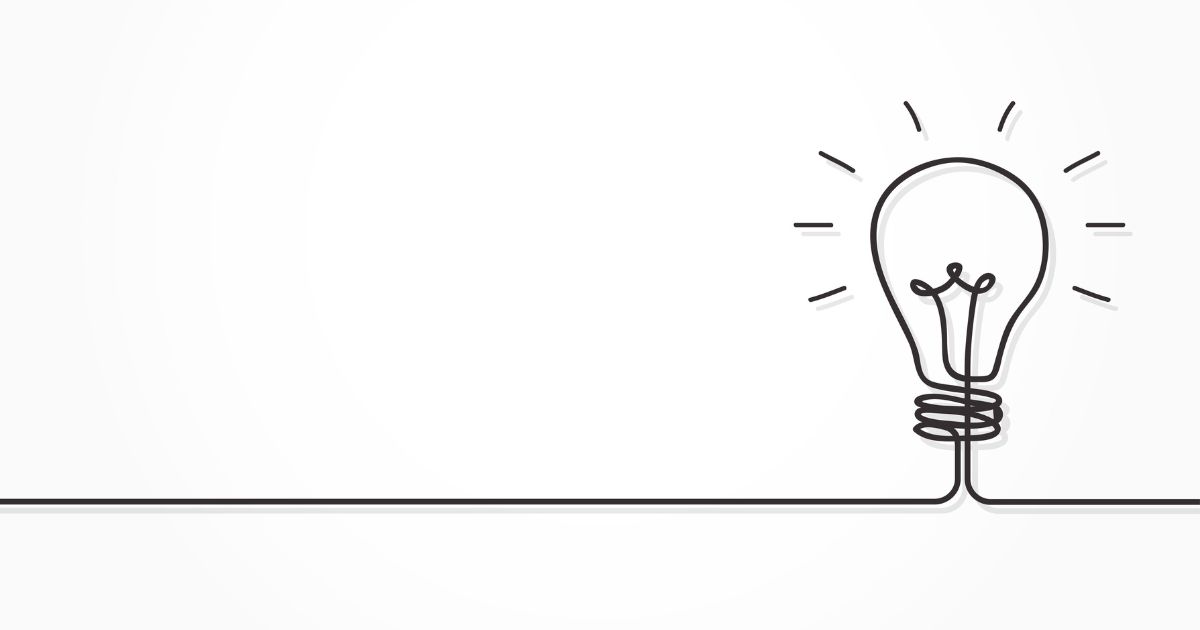
発達障害のある人が抱えやすい困難の一つに、発達障害の特性が原因で仕事がうまくできないという問題があります。
例えば、 ASDのある人だと、特定の場面におけるコミュニケーションに困難があることで、周囲の同僚とうまくいかないことがあります。
また、ADHDのある人は、一定の条件下でミスをしやすいため、修正や訂正の作業に追われて、結果として多くの仕事を抱え込むことも少なくありません。
中には、仕事上の困難を自分の努力不足や甘えのせいだと思い詰めて、うつ病などの二次障害を発症する人もいます。
しかし、発達障害の特性は、努力だけではどうにもならない面があります。「職場の人と同じように仕事ができない自分はダメだ」などと思い詰める必要はありません。
発達障害の特性が原因で仕事ができないとあきらめるのではなく、自分の特性ではできないこともあるのだと受け入れることから始めてみてもよいかもしれません。
その上で、できないことではなく、できることに着目することが大切です。
人によっては、「みんなと同じようにできないこと」を受け入れることが難しいかもしれません。
しかし、自分の特性を受け入れることで、「自分は何ができるか」という方向に思考が切り替わり、新しい対策が見えてくる場合が多いのです。
ぜひ、「仕事ができない」とあきらめる前に、ご自身の特性を理解して、その特性を受け入れてみてください。
仕事ができないと悩む発達障害のある人が抱えやすい仕事上の困難4選
発達障害の特性によって異なりますが、人によって仕事上で困難になるケースがあります。
仕事をする際は自分が何を苦手としているかを理解しましょう。
この章では、発達障害のある人が抱える仕事上の困難について解説します。
ただし、ここで紹介する事例はあくまで一例です。実際のあなたの状況と異なることもあるでしょう。あくまで参考としてご覧ください。
なお、前提として、いずれの場合も、まずは医師やカウンセラー、発達障害のある人をサポートする支援機関などに相談し、自分に必要なサポートを確認することから始めましょう。(参考:中山和彦、小野和哉『図解 よくわかる大人の発達障害』、宮尾益知『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』)
困難①業務の遂行が難しい

1つ目の困難は、業務の遂行が難しいことです。
発達障害には、業務に支障をきたすさまざまな特性があります。
ADHDのある人であれば、ミスや確認作業の不手際が多いことで悩むこともあるでしょう。また、ASDのある人であれば、意思疎通がうまく図れないなどがあるでしょう。
もちろん、ある程度は工夫することでカバーすることも可能です。しかし、努力だけで全てを補うことは難しいことも当然あります。
それゆえ、「がんばってはみたものの業務遂行が難しい」と感じて、「仕事ができない」と思うようになる人が多いようです。
困難②自分の特性に関する理解を職場で得づらい
2つ目の困難は、自分の特性に関する理解を職場で得づらいことです。
発達障害に関する認知は拡大していますが、全員が理解をしているわけではありません。
特性に関する配慮を求めづらい可能性もあるため、発達障害のある人、特に発達障害グレーゾーンのある人の場合は、発達障害の確定診断がないため、医学的かつ客観的に自分の特性を説明しづらいです。仕事や日常生活に影響する特性があるにも関わらず、障害者手帳を取得できなかったり、障害者雇用での就労ができなかったりするため、発達障害のある人とはまた別の困難を抱えることがあるでしょう。
困難③誰に相談していいかわからない

3つ目の困難は、誰に相談していいかわからないことです。
職場で発達障害があることを公表せずに働いている人は多くいます。
そうした人は、発達障害の特性に伴うミスや問題から「能力がない」と判断されて、同僚や上司などの職場の人から適切な評価を得られないという状況に陥ることがあります。
「仕事ができない」と思うようになったとしても、周囲の人に打ち明けることができず、悩むケースが少なくありません。
その結果、そのつらさを原因に仕事ができないと思うようになったり、退職を検討するようになったりするのです。
また、発達障害グレーゾーンの場合は、確定診断が下りていないことから、医師に相談していいものかどうか、迷うことが多いでしょう。
こうした困難を抱えている場合、支援機関に相談することをオススメ゙します。
困難④二次障害がある
発達障害の二次障害があることで働けないということも、よく聞く困難の1つです。
発達障害の二次障害とは、発達障害や発達障害グレーゾーンの傾向・特性に伴って発生する精神障害やひきこもりなどの二次的な困難や問題のことです。(参考:齊藤万比古『発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート』、小栗正幸『発達障害児の思春期と二次障害予防のシナリオ』)
発達障害のある人は、その特性の影響から生活や仕事での困難が多く、ストレスを抱えやすい傾向にあります。
職場では、正確な処理やコミュニケーションを求められます。うまく対応できなければ、上司などの職場の人からの注意や叱責を受けることもあるでしょう。
こうした発達障害の特性に伴って生じる疲労やストレスが積み重なった結果、何らかの二次障害が発生する可能性があります。
その二次障害の症状や状況によるさまざまな困難・問題に悩まされ、働けなくなったり、退職に至ったりすることもあるのです。
中には、うつ病などの治療のために通院したタイミングで、はじめて自分が発達障害であることを知ったという人もいるそうです。
二次障害がある場合は、二次障害の治療を行うとともに発達障害の特性への対応をしていくことをオススメします。
発達障害の二次障害については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
仕事ができないと悩む発達障害のある人ができる対策:種類別に解説
この章では、発達障害のある人ができる対策について種類別に解説します。
対策①ASDのある人ができる対策

ASDのある人は具体的には、以下のような困難を抱えやすいと言われています。(参考:本田秀夫『自閉症スペクトラムがよくわかる本』、厚生労働省「No.1 職域で問題となる大人の自閉症スペクトラム障害」、太田晴久『職場の発達障害 自閉スペクトラム症編』)
- 人間関係がうまくいかない
- 職場の人とコミュニケーションをうまく取れない
- 雑談についていけない
- 関係性を理解しづらい
- 職場の状況や上下関係を理解しにくい
- TPOに合った行動ができない
- 職場で求められるマナーや適切な服装がわからない
- 名前を呼ばれても反応しない
- 質問の意図や発言の狙いを察することができない
- 身振りや表情の意味を読み取れない
- さじ加減がわからない
- 自分だけのルールにこだわる
- 周囲から、「話を聞いていない」と誤解されやすい
- 報告、連絡、相談をうまくできない
- 決まった順序に強いこだわりがある
- 予定が変わるとパニックになりやすい
- 暗黙のルールなど明示されてない決まりに疎い
- 感覚過敏がある
仕事の現場では、取引先や上司や同僚などの職場の人など、さまざまな人間関係が存在しますが、ASDのある人はそれらの関係を意識することが苦手です。
また、他人の話をさえぎったり、相手の本音に気づかず傷つけたりするなど、相手に不快感を与えることもあるでしょう。
ほかにも、漠然とした指示を理解するのが不得意なASDのある人もいます。
業務処理能力に問題はなくても、コミュニケーションが上手く取れないため、「仕事ができない」という印象につながる傾向があります。
こうした困難に直面せず、落ちついた環境で働けるかどうかが、仕事をする上で重要になります。
ASDのある人が仕事上の困難に対してできる対策は、以下のとおりです。
- 曖昧な指示ではなく、具体的な指示を求める
- 話を聞くとき、相手の顔を見てあいづちを打ちながら聞く
- 視線を合わせるのが難しければ鼻のあたりを見る
- あらかじめ「すみませんが、目を見て話すと緊張してしまうんです」と伝える
- 上司に「報告、連絡、相談」をしてよいタイミングをあらかじめ確認しておく
- 予定の変更にパニックになりやすいことを伝え、予定の変更が予想されるときには理由とともに早めに教えてもらえるようにしておく
- 暗黙のルールを明文化して理解する(例:「今度遊びにおいで」「またご飯でも行こう」と言われても、社交辞令の可能性を考慮し、電話やメールで確認を取ってからにする/相手の体型や外見のことは口にしない/話す内容や口調を相手や場面によって切り替えるなど)
- 過敏な感覚をツールでカバーする
- 聴覚過敏の場合、ノイズキャンセリングイヤホンを使う
- 感謝や謝罪の言葉を、スムーズに伝えられるように練習してておく
発達障害のある人のコミュニケーションに関する悩みについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
ASDのある人の職場での対処法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
感覚過敏については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
対策②ADHDのある人ができる対策
ADHDのある人は具体的に、以下のような困難を抱えやすいと言われています。(参考:榊原洋一『図解 よくわかる大人のADHD』、日本精神神経学会「今村明先生に「ADHD」を訊く」)
- 確認作業がうまくいかない
- スケジュールやタスクの管理が苦手
- 整理整頓ができない
- 締切を守りづらい
- 忘れ物や記入漏れなどのミスが多い
- 物を失くすことが多い
- 興味のあることは集中し過ぎて過集中になる
- 気が散りやすい
- 貧乏ゆすりなど常に身体を動かしていないと落ちつかない
- 他人の意見に耳を傾ける前に発言したり行動したりする
- 優先順位をつけることが苦手で、場当たり的に行動する
- 場に合わせた発言をするのが難しい
- 段取りを考えながら並行作業をすることが苦手
ADHDのある人は、確認作業やスケジュール管理が苦手な傾向にあります。
やるべきことを先延ばしにしてしまったり、計画的に物事に取り組んだりすることが苦手なため努力不足、能力不足と誤解されることがあります。
また、整理整頓ができないという仕事上の困難もあります。書類の整理が苦手なため、机の上が散らかりやすく、場合によっては書類を紛失することもあります。
ほかにもこつこつと取り組むことが苦手で、期限ぎりぎりになり、最後に焦ってミスをすることもあります。そして、失敗をすることで余計にパニックになり、悪循環に陥ることもあります。
それらの行動から、職場の人からだらしない、怠惰だと受け取られることも、ADHDのある人が抱える困難と言えるでしょう。
ADHDのある人が仕事上の困難に対してできる対策は、以下のとおりです。
- 「忘れっぽい」「ミスを防ぎたい」とあらかじめ上司や同僚に伝えた上で、メモを取るようにしておく
- スマホのアラーム機能などを利用して、予定していた作業にリマインドを行う
- 仕事と違うことを考えそうになったときに、顔を洗ったり、背伸びをしたりして自分でストップをかける習慣をつくる予定・指示・作業工程・時間割などを紙に書き出して視覚化し、見てわかるようにする
ADHDのある人のマルチタスクとケアレスミスの対策については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
対策③LD/SLDのある人ができる対策

LD/SLDのある人が抱える仕事上の困難は、特定の情報理解が難しいことや情報伝達の手段が合わないことです。
どの情報が苦手なのかは、LD/SLDのある人それぞれの特性によって異なります。
自分の苦手な情報処理が必要な仕事では困難を抱えやすいでしょう。
一方で苦手な情報を使わない仕事であれば、困難を減らせます。
例えば、書く・計算することに困難があるLD/SLDのある人は、PCのキーボードや電卓といったツールが日常的に用いられている職場では、あまり問題になることはないでしょう。
他に読むことや聞くこと、推論することなどに困難があるLD/SLDのある人についても、苦手な情報をツールで補助する、または形式を変えるなどの工夫をすれば、仕事上の困難を減らすことができます。
LD/SLDのある人が仕事上の困難に対してできる対策は、以下のとおりです。
- 会議などで使用する書類は、先に目を通すためにあらかじめ渡してもらう
- 使用したい道具について、あらかじめ周囲に伝えておく
- 電子ファイルのテキストを、自分の得意なフォントや文字幅のテキストに変換する(紙の書類はスキャン→テキスト化→変換する)
- 署名をハンコなどで代用する
- 筆記のメモが苦手なことを伝え、メモはスマホ・タブレット・PCで取る
学習障害のある人ができる仕事術については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
仕事ができないと悩む発達障害のある人と一緒に働く人ができる対応5選
発達障害のある人に対して、どのように接するべきかを悩まれる人も多くいらっしゃいます。
この章では、発達障害のある人と一緒に働く人に向けて、職場でできる対応について解説します。
対応①特性を理解する

前提として大切なのは、特性によって生じている出来事は本人の努力不足のせいではないと理解することです。
発達障害は脳の処理機能に偏りが生じる、脳の構造上の特性です。そのため、本人の努力次第ではどうにもならない面があります。
まずは、何ができて、何ができないか、その人自身の特性を理解することから始めましょう。
発達障害のある人と一緒に働く人の中には、その人の特性を理解しないまま、単に「仕事ができない」と決めつける人も見受けられます。
しかし、発達障害のある人は、オールラウンドに仕事がこなせるタイプよりも、ひとつのことに集中できる業務、環境の中で力を発揮できるタイプの方が多いと言われています。
その特性について理解した上で、できないことではなく、できることに着目して、仕事をお願いしたり、協働したりすることを心がけて行くことが大切です。その上で、無理なく、その人の苦手をフォローする仕組みを作れないかを考えていけると互いに仕事がしやすくなるでしょう。
特性を理解することが、発達障害のある人との接し方を考える上で、出発点になります。
対応②その人が理解しやすいように説明をする
発達障害の特性への理解が進んだら、それを具体的に業務で実践できるように落とし込んでみましょう。
その際、重要となるのが、その人が理解しやすいように説明をすることです。
マニュアルの利用や指示の出し方など、それまで職場で問題なく行われてきたことであっても、発達障害のある人にとっては理解しづらいところが多々あるかもしれません。
単にマニュアルを渡したり指示を出したりして済ませるのではなく、その人に理解しやすいように補足していくことが必要です。
最初は労力が必要になるかもしれませんが、特にASDのある人など、その人の型にはまれば、想定以上の成果を上げることもあります。
ただ単に「仕事ができない」と見放すのではなく、その人にあったマニュアルを新たに作ることや、指示の出し方を変えられないかなどを、ぜひ考えてみてください。
対応③具体的に伝える
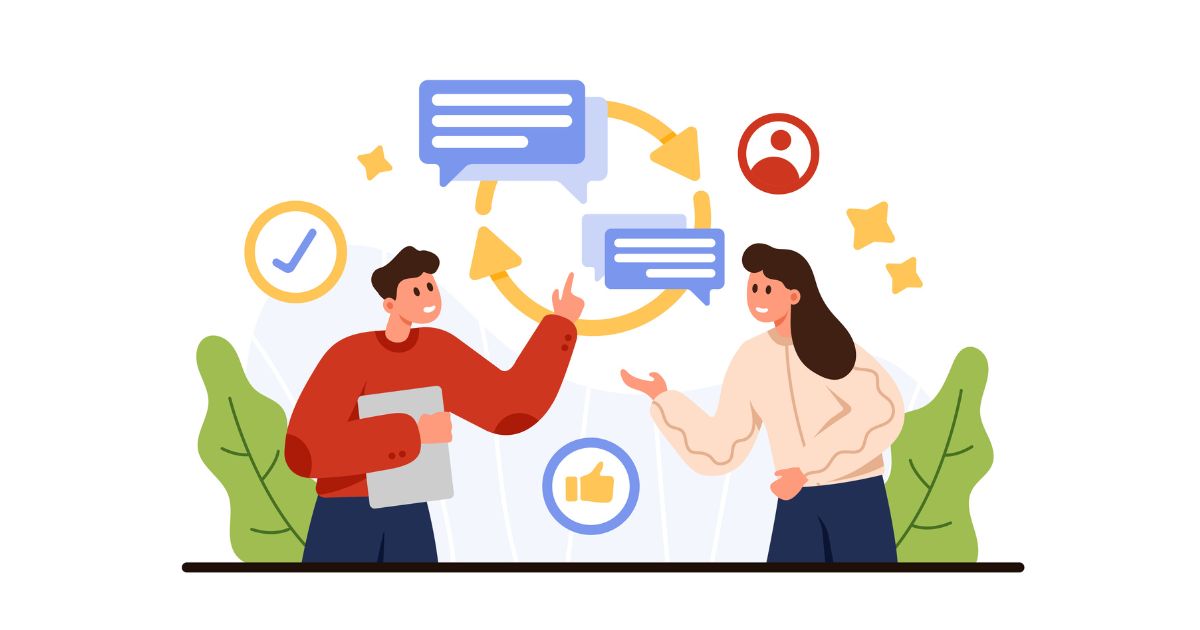
気心知れた職員に対しては、どうしても「じゃああとは適当にやっておいて」など、抽象的な表現で指示を出してしまうときもあるでしょう。
しかし、発達障害のある人にとっては、どこまでが「適当」なのか、具体的な範囲に対して悩んでしまうことがあります。
気心知れた職員であっても、また、信頼できる職員であっても、発達障害のある人に対しては、できるだけ具体的な指示を出すよう心がけましょう。
また、業務内容を教えるときもざっくりとしたニュアンスではなく、どのフォルダを開き、どのファイルを使ってどのような業務をどれくらいの時間をかけて行うのかなど、細部まできちんと伝えることが大切です。
対応④特性障害に合わせた業務に就いてもらう
発達障害にはさまざまな特性があり、また人によってその現れ方が異なります。発達障害のある人には、ある面が苦手な一方で、別の側面が得意であったり、無理なく作業し続けられたりすることも少なくありません。
そのため、発達障害のある人に業務を任せるときは、本人から得意・不得意をヒアリングし、特性に合わせた業務に就いてもらいましょう。
例えば、不注意の特性が見られるADHDのある人に最後の確認作業を任せたり、細かな計算を伴う資料作成などをお願いしたりしても、その特性によって、確認漏れや多少の計算ミスが出る可能性もあります。
一方で、特定の業務には高い集中力を発揮して、素早く作業を進行できる可能性があります。中には、細かな数字に強く、細部まで見落としなくきちんとミスを見つけられるといった特性のある人もいるでしょう。
特性に合わせて仕事の割り振りや順序、配置を工夫することがよいパフォーマンスにつながります。発達障害のある人の多くは、適切な配置をすることができれば、問題なく一緒に働けるはずです。
このような仕事環境を周囲が作ることで、発達障害のある人も自分の特性を一つの特徴と捉えることができ、業務に自信を持って取り組むことができるかもしれません。
その人の特性をある種の個性として受けとめる周囲の姿勢が大切です。単に苦手な面を知るだけでなく、どの業務をお願いすれば成果を上げやすいかをぜひ考えてみてください。
対応⑤産業医や専門家の指示を仰ぐ

発達障害のある人を職員として迎え入れたときは、産業医や専門家、支援機関と連携して行くことが大切です。
専門家や支援機関との連携によって、発達障害に対して理解を深めながら働くことができます。
なお、自社に産業医がいない場合は、地域産業保健センターを利用することで、無料で適切なアドバイスを受けることができます。
発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)
発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。
- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)
- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)
- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)
同じ診断名でも、人によって多様な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人は、他の発達障害が併存している可能性もあります。
発達障害の概要や種類、原因、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
【無料配布】”発達障害”特化型 ストレス対策ハンドブック

- 仕事がしんどい…
- もう出社したくない…
そんな気持ちを抱えながら、仕事を続けていませんか?
発達障害のある人は、仕事や日常生活で特有のストレスを感じやすいことがあります。マルチタスクが苦手、感覚過敏、過集中による疲れなど、ストレスの要因は多岐にわたります。
こうしたストレスを放置すると、心身の健康を損ね、仕事のパフォーマンスにも影響を及ぼすことがあります。
本ハンドブックでは、発達障害のある人が感じやすいストレスの原因と、その対処法を詳しく解説します。
また、ストレスマネジメントの自己評価ができるチェックリストも掲載しています。日々の生活習慣を振り返る際にご活用ください。
- 発達障害の特性とストレスの関係をわかりやすく解説
- 「なぜ自分はこんなに疲れるのか?」を理解するヒント
- ストレスの対処法を確認できるチェックリスト
- 感覚・思考・行動・環境別のストレス対処法
- 明日から使えるセルフケアの実践アイデア
- 発達障害の診断がある、もしくは発達障害グレーゾーンの人
- 自分は発達障害かもしれないとお悩みの人
- 仕事や日常生活での疲れがなかなか抜けない人
- 自分に合ったストレス対処法が見つからず悩んでいる人
- 「頑張りすぎて燃え尽きる」を繰り返してしまう人
- リンクから申し込みフォームにアクセス
- 簡単なフォームに入力
- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り
- URLから資料を取得!
- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。
- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。
- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。
また、発達障害の特性によるストレスへの対処法については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ:発達障害でも活躍することはできます

発達障害のある人は仕事全般ができないわけでは決してありません。
特性を理解した上で、それに合った仕事を与えられれば、充分活躍の機会は得られます。
そのため、仕事を続ける上では、周囲の人に特性を理解してもらうこと、相談することが大切です。
場合によっては、医師や支援機関から職場に対して、障害特性について説明してもらうなどのサポートを受けるのもよいでしょう。
ぜひ、ひとりで抱え込まずに、周囲の人を頼ってみてください。
このコラムが、少しでも仕事ができないと悩む発達障害のある人の、助けになれば幸いです。
仕事ができないと悩む発達障害のある人が抱えやすい仕事上の困難を教えてください。
仕事ができないと悩む発達障害のある人と一緒に働く人ができる対応はありますか?
監修志村哲祥
しむら・あきよし。
医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。
臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。
【著書など(一部)】
『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』
他、学術論文多数
日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧
時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年6月現在8校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
監修角南百合子
すなみ・ゆりこ。
臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年6月現在、首都圏・関西に8校舎を展開しています。トップページはこちら→