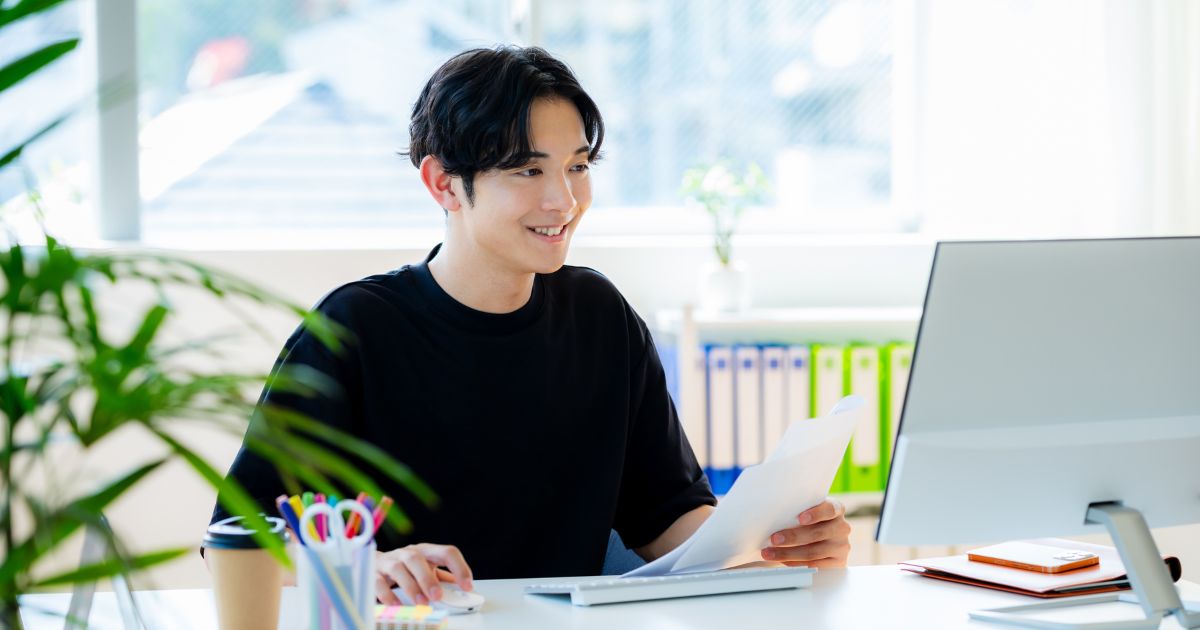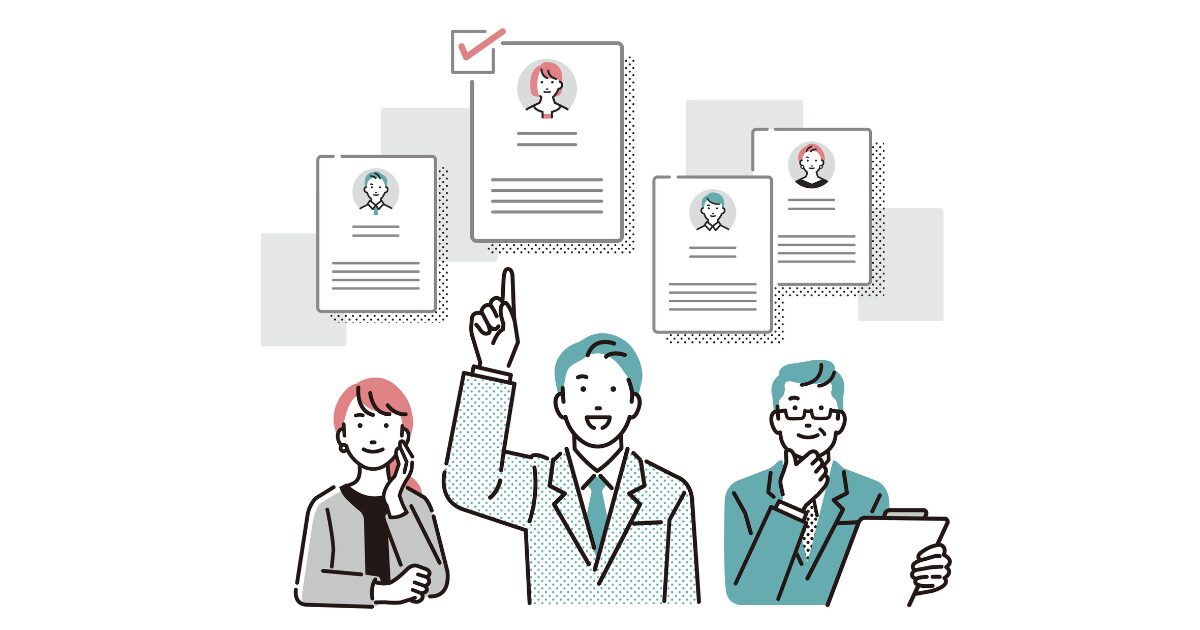発達障害のある人にオススメのSST(ソーシャルスキルトレーニング) メリットや進め方を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
発達障害のあるあなたは、以下のようにお考えではないでしょうか?
- 発達障害が原因で、以前から対人関係が上手くいかず悩んでいる...
- SST(ソーシャルスキルトレーニング)というものがあると聞いたが、どんな効果があるのか知りたい
SST(ソーシャルスキルトレーニング)によってこれまで抱えていた悩みが軽くなったり、人との関わりに自信が持てたらうれしいですよね。
このコラムでは、SSTの概要や具体例、発達障害のある人がSSTを受けるメリットなどについて解説します。
このコラムを読むだけでSSTについて理解が深まり、すぐ実行に移せるようになります。
発達障害があり、SSTに興味がある場合は、ぜひ最後までご覧ください。
SSTを検討している発達障害のあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 平均4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
SSTとは?
この章では、SSTの概要や対象、目的、効果について解説します。
SST(ソーシャルスキルトレーニング)の概要

SSTとは、「Social Skills Training(ソーシャルスキルトレーニング)」の略で、社会生活に必要なスキルを学ぶプログラムのことです。
社会生活の中で他人と関わる際に必要となるスキルを、模倣学習、教示、体験を繰り返しながら学びます。
SSTの対象
SSTの主な対象は、社会生活で必要になる以下のようなスキルが身についていない、または苦手な人です。
- 他者とのコミュニケーション
- 指示の理解や判断
- 感情のコントロール
- 他者の気持ちの理解
SSTは子どもも大人も対象です。
発達障害のある人がコミュニケーション能力をトレーニングするために、SSTを利用することができます。
発達障害のある人のコミュニケーションの特性については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
SSTの目的

SSTの主な目的は、社会生活の中で他人と関わる際に必要となるスキルを身につけ、社会生活を円滑に送れるようにすることです。
発達障害の特性の中にはうまく感情のコントロールができなかったり、コミュニケーションに困り感を抱いたりすることが多々あります。
こうした場合、感情を強く表出しすぎたり、場にふさわしくない発言をしたりして、社会生活を送りづらくなることがあるのです。
SSTはそんな人が社会になじんで生活を送れるように、他者の感情の理解や人間関係の構築の仕方など、ソーシャルスキルをトレーニングする場になっています。
SSTの効果
SSTによって、対人関係の悩みが減り、社会生活を送りやすくなる効果が期待されます。
例えば、SSTで表情が描かれたカードや写真を見て、その人は今どんな感情なのかを想像する練習をしたとしましょう。すると、実生活でも他者の表情から感情を推測できるようになります。
それまでは自分が思ったことをすべて口に出していた人も、相手の感情がわかれば「これは相手の気分を害している発言だから、もう言うのはやめよう」と、抑えられる機会が増えるでしょう。
このように、SSTによって集団生活を円滑に送りやすくなるようなスキルを身につけられるのです。
補足:SSTは就労支援でも活用されている

SSTは、子どもも大人も受けられます。
特に大人向けとしては、就労支援にもSSTは活用されており、一般企業や就労移行支援事業所などでも取り入れられています。
例えば、うつ病などの精神疾患で休職している人に対して復職に向けたロールプレイを行う、発達障害のある人が就職できるようにSSTを用いて就労支援するなどがあります。
そのため、大人でも発達障害のある人にとっては、SSTは重要な取り組みです。自分に必要だと感じたら、取り入れてみることをオススメします。
発達障害のある人が利用できる就労支援については、以下コラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害のある人が就活を成功させるコツについては、以下コラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害のある人もSSTを受けることは可能

発達障害がある人も、SSTを受けることができます。
社会生活で悩みや不安を抱えているならば、SSTが解決の糸口になるかもしれません。
SSTを受けられる支援機関は、こちらで紹介します。
なお、SST以外にも、発達障害のある大人の人が受けられる支援はあります。
SST以外の支援の詳細については、以下コラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害のある人がSSTを受けるメリットとデメリット・注意点
発達障害のある人がSSTを受けるメリットは、以下の2つです。
- どのような場面でどのような言動を取ったらよいかを具体的に学び、習得できる
- それによる成功体験を積み重ねることで、人との関わりに自信が持てるようになる
SSTを受けるデメリットは、基本的にありません。ただし、実際にSSTを受ける際には以下のような注意点があります。
- スキルの習得に時間がかかる
- 利用できる機関が限られている
- 機関によっては有料の場合があるSSTを受けた結果をほかの参加者にフィードバック(振り返り、感想の述べ合い)するときには、叱責や非難に聞こえないようにする
- 自分はそのつもりはなくても、相手は叱責されたように受け止めることもある
この注意点を学ぶことも、SSTの一つかもしれません。重要なのは、参加者同士が成功体験を積み重ねることです。
あなたに発達障害があり、他者とのコミュニケーションに悩んでいるのなら、SSTは有効な解決策の一つと言えます。
苦手な部分に向き合うことは辛いことでもありますが、ぜひ勇気をもって一歩踏み出してみてください。
SSTの進め方
この章では、SSTの進め方について解説します。
進め方①行動分析
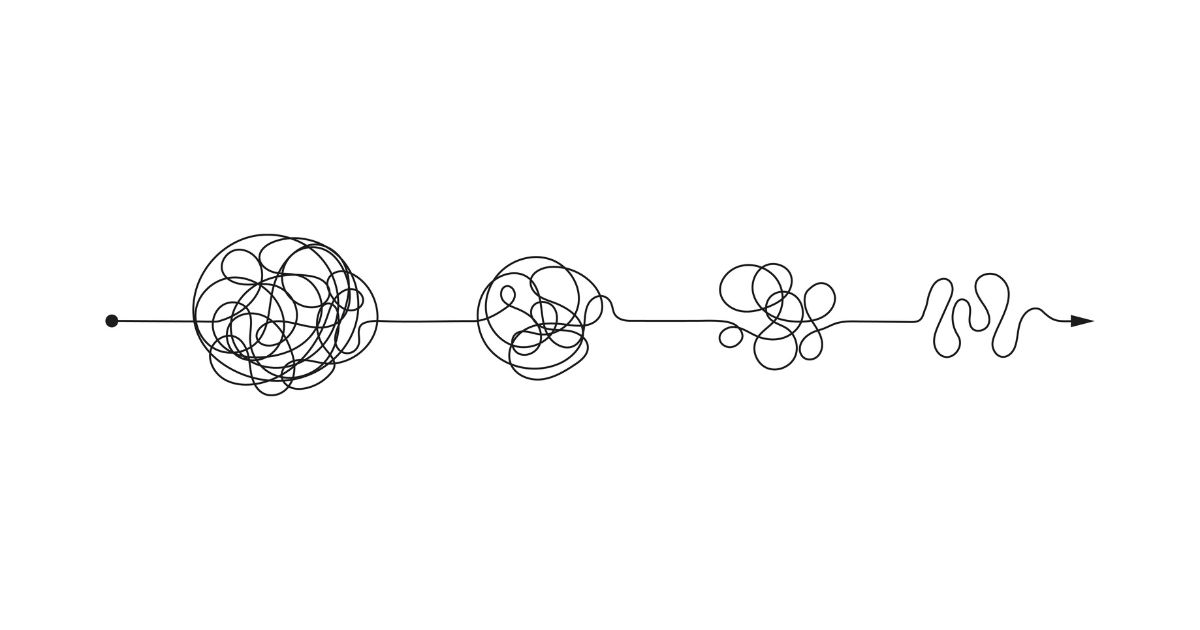
まずは行動分析を通して、あなたに必要なソーシャルスキルが何かを支援員とともに見つけます。
例えば、同僚や友人とうまく会話を続けることができない、理由はわからないが輪から遠ざけられる、などの一連の出来事を、以下の3つに分けて考え、行動パターンを導き出します。
- どのようなときに=条件
- 何をして=行動
- どうなったか=結果
そのパターンから、できること・できないことを把握します。
SSTを受ける人は多種多様な悩みを抱えており、その人にあったトレーニングが必要です。
進め方②教示
教示はインストラクションとも言われます。
支援員があなたに、いつ、誰が、どこで、何を、どのように、なぜトレーニングするのかを明確に伝えることです。
なぜなら、ただやるより、どのような目的があるのか、何を身につければいいのかをわかっていたほうが効果的にトレーニングできるからです。
教示で約束やルールを提示する場合もあり、これを守ることもSSTの一つになります。
言葉での説明で十分に理解できない場合は図や絵で説明することもあるため、どなたでも安心して受けられます。
進め方③モデリング

モデリングは見て学ぶ段階です。実際にある場面を想定し、支援員がお手本として振る舞いを見せます。
あなたはその振る舞いを見て、後ほど自分で実践するときの参考にするのです。
モデリングでは、よい振る舞いだけでなく、よくない振る舞いもあわせて見せる場合があります。
これはどこがよくないのかを考えることにより、違う場面でも応用的に考えられるようになるからです。
実際にあなたが経験した場面を題材にするとイメージが湧きやすいため、事前にアンケートで聞かれるケースもあります。
進め方④リハーサル
リハーサルでは、実際にあなたが行動します。手法はさまざまです。ロールプレイで演じたり、ゲームやカード教材を使ってワークをしたりなどがあります。
脳に定着させてスキルを身につけるうえでは、リハーサルを通して実際に自分で経験することが非常に重要なのです。
また、リハーサルは一度だけでなく何度も実施したほうが効果的です。場合によっては、モデリングとリハーサルを繰り返し行うこともあります。
自分のなかに落とし込めるまで、何度もチャレンジしてみましょう。
進め方⑤フィードバック

リハーサルの内容を受けて、支援員からフィードバックをもらいます。褒められたところはあなたのよい部分ですので、素直に受け止め、次からも自信を持って取り組んでみてください。
場合によっては、改善点を伝えられることもあるでしょう。しかし、落ち込む必要はありません。それはあなたが悪いのではなく、学習したことや経験したことがが少なかったために上手くできなかっただけです。
はじめてのことでも最初からすべて上手くこなせる人はいません。失敗を経験して、そこから学んでいくことで上達していきます。
あなたの社会生活がもっと充実するようにアドバイスしてくれているはずなので、前向きに捉え、実践してみましょう。
もし、アドバイスの内容がわからなかったり納得できなかったりする場合は、正直に聞いて大丈夫です。
進め方⑥般化
般化はいわば復習であり、SSTで習ったことを日常生活で実践してみるパートです。般化によって、実際の生活でスキルを生かせるようになります。
日常生活でどのように練習したらいいかわからない人は、課題や宿題を与えてもらいましょう。
「このような場面でこのような動きをする」というのがわかれば、取り組みやすくなるでしょう。
SST中は上手くできるが、日常生活では上手くできないということもあるかもしれませんが、焦らなくて大丈夫です。何度も繰り返し練習して、身につけていきましょう。
SSTの主な種類
SSTと一言で言っても、さまざまな種類があります。
この章では、SSTの主な種類について解説します。
それぞれの具体例はこちらで解説しています。参考にしてください。
種類①ゲーム・カード教材

ゲームやカード教材を使うと、楽しみながら学べるのが特徴です。子どもから大人まで、幅広い年代へ向けたSSTに用いられます。
ゲームやカード教材には、以下のような要素が含まれています。
- ルールを守る
- 勝ち負けを受け入れる
- 他者と協力する
そのため、楽しみながらも、ソーシャルスキルを身につけられるのです。
種類②ディスカッション・ディベート
ディスカッション・ディベートは、気持ちの理解やコミュニケーションを練習するのにぴったりです。
相手の意見を聞いたうえで、感情的にならず、論理的に自分の意見を伝える必要があります。これは特に、ビジネスの場において求められることです。
ときには誰かと協力する場合もあるでしょう。ディスカッション・ディベートは一度に複数の能力を鍛えられる非常に有効な手段と言えます。
種類③ロールプレイ

ロールプレイは実際にある場面を想定し、どのように振る舞えばいいのかを実演する方法です。
日常生活の場面に見立てて練習できるため、抱えている悩みや課題に直接アプローチできます。
実演後はフィードバックをもらうことによって、よいところや改善点を把握できます。実際に困った経験が思い浮かぶ人におすすめの方法です。
SSTの具体例6選
この章では、SSTの具体例を紹介します。
なお、ゲームに関してはSSTのために作られたものではありません。ですが、楽しく遊べてSSTの効果があるものばかりです。
具体例①ボブジテン(ゲーム・カード教材)

ボブジテンは、カタカナ語を日本語だけで説明するゲームです。具体的にはパソコンやラグビーなどの言葉を、日本語のみを使って説明するのです。
ルール自体はシンプルですが、コミュニケーション能力や感情コントロール能力を鍛えられます。
ゲームの進め方としては、山札からカードを1枚引きカタカナ語のお題を確認します。その後日本語だけでお題を相手に伝えて、答えてもらう流れです。
どのような言葉を使うと相手が想像しやすいか、どのような抑揚で話すと相手が理解しやすいかなど、考えるべきことはたくさんあります。
そして、理解してもらえないからといって感情的になると、さらに伝わりづらくなります。
説明が苦手、すぐイライラする機会が多いという人におすすめです。(参考:ClaGlaウェブショップ「ボブジテン〈TUKAPON〉」)
具体例②はぁって言うゲーム(ゲーム・カード教材)
はぁって言うゲームは、お題の一言を声と表情だけで表現するゲームです。例えば、怒っているときの「はぁ」や、うれしいときの「えー」などです。
一言しか発せないため、表情や言葉の抑揚でお題を伝える必要があります。
また、お題を出す側はもちろん、読み取る側もトレーニングになります。
この表情はどのような気持ちなのか、先ほどとはどのような違いがあるのかを読み取るには、かなり集中しなければなりません。
自分の感情を伝えるのが苦手、相手の感情を読み取るのが苦手という人におすすめです。(参考:幻冬舎edu「はぁって言うゲーム」)
具体例③「遅刻するときの行動」がテーマのディスカッション・ディベート

ディスカッションやディベートのテーマとして、遅刻するときの行動などがあります。
ディスカッションやディベートでは、以下のようなことを話し合います。
- 遅刻をどのように伝え、どのように謝るか
- 予定の実施や変更をどうするか
- 遅刻の言い訳に嘘をつくことは許されるか否か
遅刻に関しては社会的な通念も絡んでくるため、議論が盛り上がりやすいテーマです。
ディベートでは自分の考えと逆の立場で議論する場合もあるため、他者の気持ちの理解や論理的に説明する力も鍛えられます。
具体例④「忙しそうな人への質問」がテーマのディスカッション・ディベート
忙しそうな人への質問も、ディスカッション・ディベートのテーマの一例です。
どのタイミングで聞くべきなのか、どのように聞くべきなのかなど、考慮することはたくさんあるでしょう。
このテーマは、相手と自分を天秤にかけてどちらを優先するべきか、そもそも本当に忙しいのか聞くべきなのかなど、実際に遭遇する可能性が高い場面について考えられます。
ディベートでは自分がどう思っているかとは無関係に、割り当てられた立場を主張する訓練をします。ディベートでいつもの自分とは逆の立場でしばしば議論することによって、状況判断能力やコミュニケーション能力を鍛えられます。
具体例⑤報告・連絡・相談のロールプレイ

ロールプレイで、ビジネスの基本である報告・連絡・相談を練習するケースは珍しくありません。
そもそも何を伝えればいいのか、報告・連絡・相談しないとなぜいけないのかを考えられるでしょう。
上司役の人に忙しい振りやぶっきらぼうな振りなどをしてもらえば、より多くのシチュエーションに応用できます。
報告・連絡・相談で失敗を経験した、「なんで言わなかったの?」と言われる機会が多い人は、ロールプレイで練習しておくといいでしょう。
報連相ができない理由については、以下コラムで解説しています。ぜひご覧ください。
具体例⑥「なにかを断る場面」のロールプレイ
断るという行為は一見シンプルですが、相手の気持ちを考えすぎたりそもそも断り方がわからなかったりするために、断れない人もいます。
そんな人はロールプレイで練習しておきましょう。断らないとどうなるのか、どうすれば相手に不快に思われずに断れるのかなどを学べます。
日ごろから友人の頼みを断れずに何でも引き受けてしまう人には、ぴったりのテーマです。
補足:日常生活で般化

SSTはトレーニングの時間だけではなく、日常生活でも取り入れることによって身に付きます。
例えば、家族や友人に1日の出来事を簡潔に話すだけでも、相手に自分の言葉を伝える練習になります。
日常生活でSSTを取り入れられる場面はたくさんあるので、積極的に実践し、自分のものにしていきましょう。
SSTを受けられる支援機関
SSTはさまざまな施設で受けられます。以下が主な例です。
- 精神科デイケア
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援A型事業所(A型作業所)
- 就労継続支援B型事業所(B型作業所)
- 若者地域サポートステーション
- 地域活動支援センター
- 障害者就業・生活支援センター
就職を目指している場合は、就労移行支援事業所でSSTをしながら就職へ向けて動くのがオススメです。
就労移行支援事業所や就労継続支援A型事業所(A型作業所)、就労継続支援B型事業所(B型作業所)については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
また、未成年の場合は以下の場所でSSTを受けられます。
- 幼稚園や保育所、認定こども園(巡回相談員として専門家が訪問)
- 小学校や中学校(カウンセラーの訪問)
- 大学の研究機関や療育施設
いずれも全国に存在する施設です。
SSTを希望する場合は、ご自宅・お勤め先などの最寄りの施設にお問い合わせください。
キズキビジネスカレッジ(KBC)利用者のSST体験談

Aさんは、ADHDのグレーゾーンでした。
体調不良で会社を退職後、就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ(KBC)」に通い、SSTの講座「ビジネスシーン失敗回避術」を受講しました。
Aさんは以前、「空気が読めない」「あの場であのような発言はだめ」などと言われたことがありました。
ですが、SSTを受講したことで、NG例や模範例をディスカッション、ロールプレイングを通じて学べたので、安全な環境で対人関係能力を向上させられるようになりました。
SSTはあくまでも「練習」なので、失敗を恐れる必要もありません。
Aさんは数回受講することで、講師からも助言を求められるようになり、対人能力の向上を実感しました。
発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)
発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。
- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)
- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)
- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)
同じ診断名でも、人によって多様な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人は、他の発達障害が併存している可能性もあります。
発達障害の概要や種類、原因、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ:SSTは発達障害のある人が社会生活を送りやすくなる助けになります

あらためて、SSTとは、社会生活の中で他人と関わる際に必要となるスキルを、模倣学習、教示、体験を繰り返しながら学ぶことです。
SSTによって、対人関係が苦手な人でも、社会生活を送りやすくすることができます。
発達障害のある人もSSTを実践することで、人との関わり方が上手になり、自分に自信が持てるようになります。
SSTは病院や就労移行支援事業所で受けられるので、ぜひ、お近くでSSTを受けられる場所を積極的に探してみてください。
このコラムが、あなたのソーシャルスキルを変えていく一助となったなら幸いです。
SSTとは何ですか?
SSTとは、「Social Skills Training(ソーシャルスキルトレーニング)」の略で、社会生活に必要なスキルを学ぶプログラムのことです。社会生活の中で他人と関わる際に必要となるスキルを、模倣学習、教示、体験を繰り返しながら学びます。
詳細については、こちらで解説しています。
SSTには、どのような種類がありますか?
監修志村哲祥
しむら・あきよし。
医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。
臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。
【著書など(一部)】
『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』
他、学術論文多数
日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧
時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年6月現在8校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
監修角南百合子
すなみ・ゆりこ。
臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年6月現在、首都圏・関西に8校舎を展開しています。トップページはこちら→