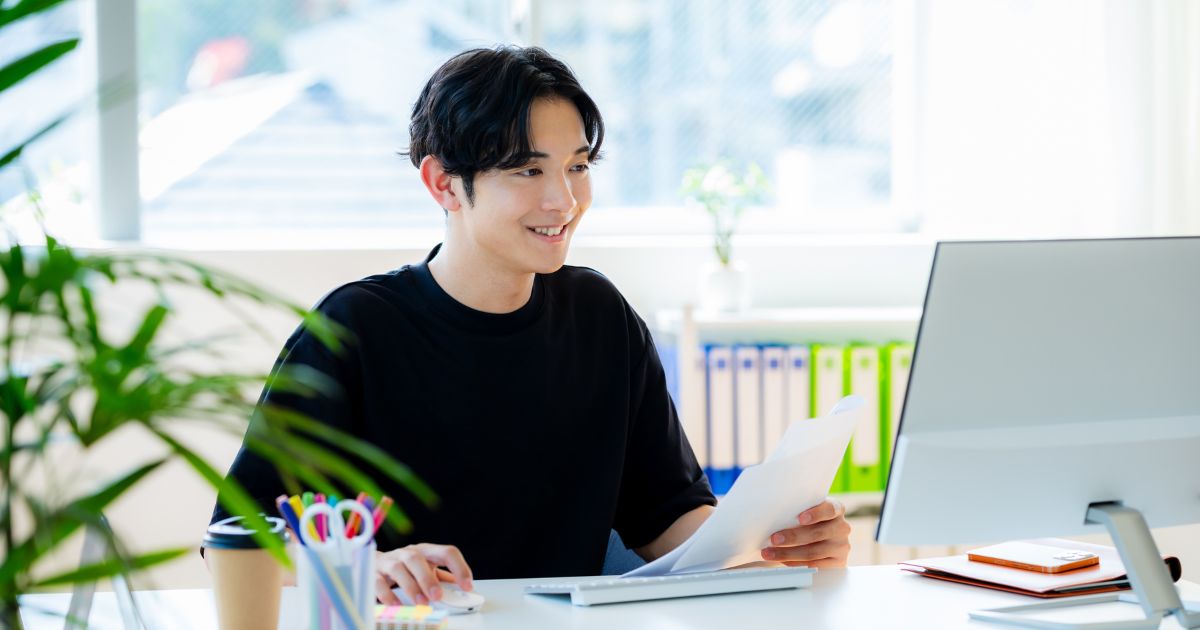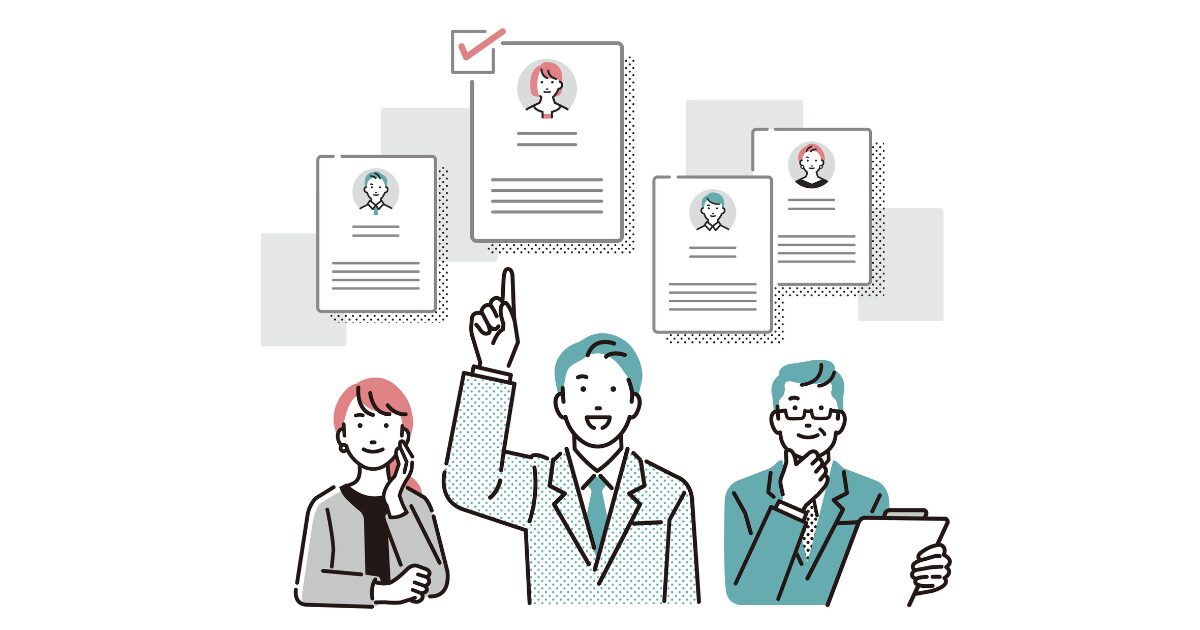コミュニケーションが苦手な発達障害のある人ができる対策 コミュニケーション障害との違いを解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
発達障害のある人が特に悩みを抱えやすいと言われているのが、職場でのコミュニケーションに関する困難です。
あなたも職場でのコミュニケーションに悩んでいませんか?
発達障害によるコミュニケーションの問題を解決するには、特性や原因を理解し、適切な対処法を考えていくことが大切です。
このコラムでは、コミュニケーションが苦手な発達障害のある人ができる対策や悩む原因、コミュニケーション障害との違いについて解説します。あわせて、コミュニケーションが苦手な発達障害のある人の事例を紹介します。
発達障害によるコミュニケーションの問題でお悩みであれば、ぜひ一度、読んでみてください。
コミュニケーションが苦手な発達障害のあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 平均4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
コミュニケーションが苦手な発達障害とは?:困難が生じやすいのはASD

コミュニケーションを苦手とする発達障害は、ASDです。
ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害、Autism Spectrum Disorder)とは、人とのコミュニケーションなどに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、e-ヘルスネット「ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について」、CDC「Autism Spectrum Disorder (ASD) 」、厚生労働省「No.1 職域で問題となる大人の自閉症スペクトラム障害」、福西勇夫、福西朱音『マンガでわかるアスペルガー症候群の人とのコミュニケーションガイド』)
また、LD/SLDのある人も条件によっては、コミュニケーションに悩むことがあります。
LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害、Learning Disorder/Specific Learning Disorder)とは、読む・書く・計算する・推論するなど、特定の学習行為のみに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』、厚生労働省「学習障害(限局性学習症)」、小池敏英・監修『LDの子の読み書き支援がわかる本』、バーバラ・エシャム・文、マイク&カール・ゴードン・絵、品川裕香・訳『算数の天才なのに計算ができない男の子のはなし 算数障害を知ってますか?』)
ADHDのある人は、主にミスや忘れ物が多いという特性から、行動面での困難が生じやすいと言われています。しかし、それらの特性は、直接的にはコミュニケーションに問題が生じないと考えられます。
発達障害とコミュニケーション障害との違い

発達障害に関連するコミュニケーションの困難は、コミュニケーション障害と混同されることもありますが、それぞれ全く異なる障害です。
コミュニケーション障害とは、発声や発音、文法の組み立てが難しかったり、人とやりとりするのが難しかったりする、人とのコミュニケーションに困難が生じる障害のことです。
アメリカ精神医学会が定めた精神障害の診察基準『DSM-5』によると、発達期に発症する神経発達症群/神経発達障害群のグループに含まれます。そして、コミュニケーション症群・コミュニケーション障害群は、人とのコミュニケーションに困難が生じるグループを指します。(参考:日本精神神経学会・監修『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』)
コミュニケーション障害の詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
コミュニケーションに関する困難がある場合、必ずしもコミュニケーション障害であるとは限りません。同様に、発達障害とも限りません。
コミュニケーションが苦手だから発達障害に違いないと思い込んだり、発達障害だからと言ってコミュニケーションに困難があると決めつけたりしないことが大切です。
コミュニケーションに悩んでいる人は、自己判断せずに、専門の医療機関を受診することをオススメします。
コミュニケーション障害のある人に向いてる仕事については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
ASDのある人がコミュニケーションに悩む3つの原因
発達障害のある人がコミュニケーションを考えるときには、単にコミュニケーションが苦手で片づけるのではなく、その原因を細かく分けて考えることが大切です。
この章では、ASDのある人がコミュニケーションに悩む原因について解説します。(参考:本田秀夫『自閉症スペクトラム』、宮尾益知『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』)
前提:コミュニケーションに関する悩みは基本的に、発達障害の特性に由来している

発達障害のある人のコミュニケーションに関する悩みは基本的に、発達障害の特性に由来していると言われています。
発達障害は、生まれつきの脳機能障害です。コミュニケーションを困難にしている原因そのものを解消することはできません。本人の努力だけでは、どうにもならない面があるのも事実です。
しかし、原因を理解するのは大切なことです。理由は以下のとおりです。
- その原因にピンポイントで合う対処法を考えるため
- 周囲の人や職場の人に、具体的にどうしてほしいかを伝えるため
以上のことを認識した上で、対処法を検討していきましょう。
原因①身振りや表情の意味を読み取れない
1つ目の原因は、身振りや表情の意味を読み取れないことです。
コミュニケーションは、以下の2種類に分けられます。(参考:中村真「3.表情とコミュニケーション」)
- バーバル・コミュニケーション:言葉のやり取りからなる言語的コミュニケーション
- ノンバーバル・コミュニケーション:身振りや表情や声のトーンからなる非言語的コミュニケーション
実際の意思疎通のうち、非言語的コミュニケーションが占める割合は90%以上と言われており、特に親密度が増すほど非言語的コミュニケーションの割合は大きくなると考えられています。
非言語コミュニケーションの難しいところは、相手の表情などで意味合いが変わってくるところです。
例えば、相手が笑いながら「変なことを言うなよ」と言った場合、相手は怒っているのではなく、むしろ打ち解けた調子でコミュニケーションを求めていることが多いでしょう。
しかし、ASDのある人は身振りや表情から相手の意図を判断しづらい特性があります。
そのため、発言を文字通りに受け取り、「変なことは言っていません」といった返答をすることが多いです。
こうしたやり取りの積み重ねにより、ASDのある人はコミュニケーションがうまくできないと思われることが多いのです。
原因②さじ加減がわからない

2つ目の原因は、さじ加減がわからないことです。
仕事の場面などで、「適当に」や「ちょっと」などの曖昧な表現が使われることは日常茶飯事でしょう。
しかし、ASDのある人は言葉を文字通りに受け取るため、「適当」と言われても、果たしてどの程度が「適当」なのかがわからずに固まります。
そして、状況を考慮せずに丁寧すぎたり、雑すぎたりする処理をすることがあるのです。
こうしたさじ加減がわからないことが原因で、コミュニケーションをうまくできない場合があります。
原因③関係性を理解しづらい
3つ目の原因は、関係性を理解しづらいことです。
職場では、上司や部下などの上下関係があり、それに合わせて言葉遣いを変えるのが基本です。
しかし、ASDのある人は、上下関係や社会関係などの曖昧なものを理解しづらいため、相手が上司であって同じ環境にいるというだけで、友達のように接することがあります。
また、不快に思って注意する人がいても、ASDのある人はそもそもの関係性を認識するのが苦手な傾向があるため、指摘を理解することが難しいと言われています。
LD/SLDのある人がコミュニケーションに悩む原因

情報伝達の手段が合わない場合、LD/SLDのある人はコミュニケーションに悩むことがあります。
LD/SLDのある人は、自分が苦手とする方法で情報伝達の手段を取られると、発達障害の特性上、その内容をうまく認識することができません。
例えば、目で見た文字や文章を読むことに困難が生じるLD/SLDのある人の場合、テキストで込み入った指示を受けても、内容をきちんと理解することは難しいでしょう。
そして、後でその指示内容を問われて答えられなかったときなどに、「コミュニケーションが取れない」と思われるのです。
コミュニケーションが苦手な発達障害のある人ができる対策4選
この章では、コミュニケーションが苦手な発達障害のある人ができる対策について解説します。(参考:對馬陽一郎『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害のある人が会社の人間関係で困らないための本』、木津谷岳『これからの発達障害者「雇用」』)
対策①具体的な指示を依頼する

まず実践してほしい対策が、具体的な指示をお願いすることです。
ASDのある人はあいまいな表現をされると混乱することがあり、指示された内容を理解できない場合があります。
職場の人があなたの特性を理解していない場合、「適宜」や「適当に」などの抽象的な表現を用いて、あなたに裁量を委ねることが多いでしょう。
指示をきちんと受け止めずに実行すると、誤った処理をして、「この人は仕事ができない」と相手に思われることもあるかもしれません。
そのようなことを防ぐために、「具体的にいつまでにやればいいのか教えてください」などと伝えて、できるだけ具体的な指示をお願いするようにしましょう。
「この書類を何部印刷して、何階のA会議室のホワイトボードの前の机に置いておいてください」などの具体的な指示があれば、ぐっと仕事がしやすくなるはずです。また、職場の人もあなたの特性に対して今まで以上に理解を深めることができるでしょう。
必要に応じて、具体的なお願いを紙やメールなどの文章で作成してもらうこともオススメです。
対策②自分専用のマニュアルを作る
自分専用のマニュアルをつくるのもよいでしょう。
多くの場合、社内のマニュアルは、その業務を行う人全員にわかるように書かれているはずですが、多少は作成者の感覚やさじ加減が反映されています。
場合によっては、「ころ合いを見計らって」や「〇〇さんの手が空いたときに」などの曖昧な指示が入り込んでいることもあるでしょう。
しかし、ASDのある人はこのような曖昧さが苦手な傾向があります。
業務の処理中に混乱したり、極端な対応を取ったりしないためにも、あなたの特性に合ったマニュアルが必要です。
自分らしく働けるように、得意なことを活かせるマニュアルづくりに取り組んでみてください。業務処理中のコミュニケーションのすれ違いを生まないためにも必要なはずです。
まずは自分でマニュアルを作り、それを職場の人に確認してもらうとよいでしょう。
仕事に関するマニュアルづくりが難しいと感じる場合は、まずは普段の暮らしの中で使えるマニュアルを試しにつくってみるのもよいかもしれません。
対策③文字や図を用いた説明を求める

3つ目の対策は、文字や図を用いた説明を求めることです。
LD/SLDのある人は、会議の場などで、苦手とする情報形式で説明されると、話についていけなくなることがあります。また、LD/SLDのある人と同様に、ASDのある人の中にも、文字や音声情報だと理解しづらい傾向のある人がいます。
これは、受け手側のASDのある人やLD/SLDのある人だけで対処できるものではありません。
日頃から、理解しやすい情報形式でのコミュニケーションをお願いしたり、説明の方法を理解しやすいものに変えてもらうよう、周囲に働きかけたりするとよいでしょう。
LD/SLDのある人ができることに、ICレコーダーなどを取り入れるというものがあります。
最近では、文字を読むのが苦手なLD/SLDのある人向けに、文書の自動読み上げをする機械などもあります。こういったものを仕事の場に活かすのもよいでしょう。
対策④支援機関に相談する
最後にオススメしたい対策は、支援機関を利用することです。
専門家や支援機関の客観的な意見は、あなたのコミュニケーションの悩みの解消に役立つはずです。
発達障害のある人の就労をサポートしている支援機関はたくさんあります。さまざまな事例を知る専門家の存在は、必ずやあなたの助けになるでしょう。発達障害グレーゾーンの人でも相談可能な支援機関もあります。ご安心ください。
中には、あなたと職場の間に入ってコミュニケーションのサポートをしたり、働きやすい方法を一緒に探したりする支援機関もあります。
気になる支援機関があれば問い合わせてみましょう。どの支援機関が適切かわからないという場合は、主治医やお住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口、専門家などに相談してみてください。
コミュニケーションが苦手な発達障害のある人の事例3選
この章では、コミュニケーションが苦手な発達障害のある人の事例を紹介します。(参考:太田晴久『職場の発達障害 自閉スペクトラム症編』、星野仁彦『発達障害に気づかない大人たち〈職場編〉』)
事例①極端な処理をしたASDの人の事例

1つ目の事例は、仕事で極端な処理をしたASDのあるAさんの事例です。
ASDのあるAさんは、障害者雇用で事務職で就労しています。
職場の人から、障害特性について配慮を得ていましたが、あるとき、一緒に仕事をしているBさんが、会議があることを忘れていたため、慌ててAさんに資料の印刷を頼みました。
そのときに、会議に参加する人数を伝えた上で、「余裕を持って多めに刷っておいてください」と付け加えました。
Bさんは、印刷に不備があった際のために、参加者に加えて5部ほど刷ってもらうことを意図していました。
しかし、印刷物を回収しにAさんに尋ねると、参加人数の2倍以上の書類が印刷されており、コピー機もまだ稼働中だったそうです。
Aさんは「余裕を持って多めに」という指示のさじ加減がわからず、また、Bさんも慌てて曖昧な指示をしたために起こったコミュニケーションのすれ違いでした。
事例②取引先を怒らせたASDのある人の事例
2つ目の事例は、取引先を怒らせたASDのあるCさんの事例です。
新卒で採用されたCさんは、学生時代からコミュニケーションを取ることが苦手だったため、あまり人と関わらない職種で就労していました。
しかし、それでも取引先の人とやり取りをする機会は、ある程度生じます。
あるとき、仕事を請け負っている取引先の人が、Cさんの会社を訪れたため、先輩のDさんと一緒に応対をしました。
普段からDさんがメールでやり取りしているのを見ていたこともあり、取引先の人も全く知らない人ということではありませんでした。
ただし、知人とはいえ当然、敬語の使用が求められる場面です。にも関わらず、Cさんは取引先の人に対して、全く敬語を使わずに、いきなり友達であるかのように話しかけました。
はじめは相手も面食らっていただけですが、態度があまりにもぶしつけだったため、時間が経つにつれて先輩のDさんの目から見ても明らかに不快そうな表情を浮かべるようになりました。
しかし、Cさんは相手が声を荒げたり直接的な注意をしなかったため、最後まで友達に話すような態度を続けて取引先との関係を悪化させることになりました。
事例③会議の内容を理解できなかったLD/SLDのある人の事例

3つ目の事例は、会議の内容を理解できなかったLD/SLDのあるEさんの事例です。
Eさんには軽度のLD/SLDがあり、ゆっくりとした会話なら聞き取れるものの、早いスピードで言葉がやりとりされると内容を追えなくなる、聴くことへの困難があります。
とはいえ、普段はそれほど困難を感じることはなく、会議などの場でも資料を読み込んだり、前もって議題を聞いたりすることでカバーできていました。
しかし、その日の会議は事前の資料配布もなく、当日配られた書類もデータの羅列のみで、パワーポイントもありませんでした。
さらに、会議が長引いたこともあり、Eさんは途中で内容を追うことができなくなりました。
そして意見を求められたときに、全く的外れな発言をして場をシラけさせました。
発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)
発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。
- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)
- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)
- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)
同じ診断名でも、人によって多様な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人は、ほかの発達障害が併存している可能性もあります。
発達障害の概要や種類、原因、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ:発達障害でコミュニケーションが難しくても工夫次第で対策はできます

発達障害のある人が働く上では、周囲の人のサポートが必要不可欠です。
ひとりでは成り立たないコミュニケーションの困難は、特にサポートが必要です。
ぜひ、このコラムで紹介してきた情報を参考に、周囲の人や職場の人、専門家や支援機関に協力を求めてください。
発達障害によるコミュニケーションの困難に悩む人の助けになれば幸いです。
コミュニケーションが苦手な発達障害はありますか?
コミュニケーションを苦手とする発達障害は、ASDです。また、LD/SLDのある人も条件によっては、コミュニケーションに悩むことがあります。
詳細については、こちらで解説しています。
コミュニケーションが苦手な発達障害のある人ができる対策を教えてください。
監修志村哲祥
しむら・あきよし。
医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。
臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。
【著書など(一部)】
『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』
他、学術論文多数
日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧
時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年6月現在8校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
監修角南百合子
すなみ・ゆりこ。
臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年6月現在、首都圏・関西に8校舎を展開しています。トップページはこちら→