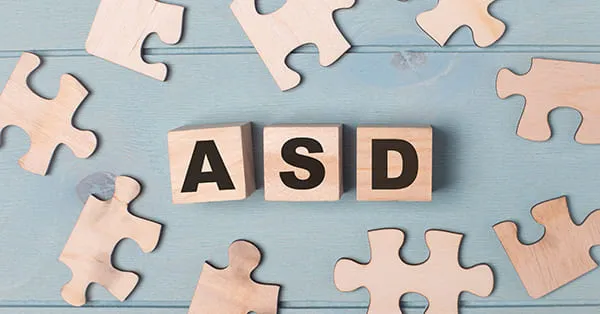ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)とは? 特性や診断基準を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
あなたは、ご自身や、ご家族、身近な人たちがASDではないか?とお悩みなのではないでしょうか?
このコラムでは、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)の知見に基づき、ASDの概要などについて解説します。
ASDの特性に由来にする困難がある可能性は否定しません。ですが、現在は相談先や特性への対策もたくさんあります。この記事を読むことで、不安が解消し、実際のあなたが次にどう行動するべきかなどが見えてくると思います。
さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、仕事や働き方に悩むASDのある人に向けて、「ASD×仕事 実践ガイドブック」の無料配布を開始いたしました。
ASDの基本から仕事に影響するポイント、向いてる仕事、仕事選びの視点までを、わかりやすく丁寧に解説しています。
ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。
また、ASDのある人に向いている仕事ついては、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。
ASDの特性のお悩みのあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 平均4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
ASDとは?

ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害、Autism Spectrum Disorder)とは、人とのコミュニケーションなどに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、e-ヘルスネット「ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について」、CDC「Autism Spectrum Disorder (ASD) 」、厚生労働省「No.1 職域で問題となる大人の自閉症スペクトラム障害」、福西勇夫、福西朱音『マンガでわかるアスペルガー症候群の人とのコミュニケーションガイド』)
かつて使用されていた以下の診断名・分類は、ASDという診断名・分類に統合されています。
- アスペルガー症候群
- 自閉症
- 高機能自閉症
- 広汎性発達障害(PDD)
それぞれ別の発達障害として、診断基準も異なっていましたが、2013年に行われた『DSM-5』の改訂の際に、厳密に区分するのではなく、地続きの=スペクトラムな障害として捉える現在のASDに変更されました。
ただし、変更前の診断名・分類が、法令や病院、日常会話などで現在も使用されることがあります。また、かつてアスペルガー症候群などと診断された人が、現在のASDという名称を認知していないこともあります。
ASDの特性
ASDの主な特性は、以下のとおりです。
なお、ASDのある人全てに、以下の特性が必ずあるとは限りません。また、以下の特性に当てはまる場合でも、必ずASDであるというわけではありません。
- 相手の身振りや表情の意味、意見・気持ち、発言の意図・意図などを察しづらい
- コミュニケーションの齟齬が生じやすい
- 会話による意思疎通をうまくできない、会話がかみ合わない
- 「空気が読めない」と言われる
- 一方的なコミュニケーションになりやすい
- 場の状況や上下関係に無頓着
- 他人の発言をそのまま繰り返す
- 人と目線が合いにくい
- 名前を呼ばれても反応しない
- 人に関心がない
- 自分の考えと別の可能性を想定しづらい
- 相手の立場に立って考えることが苦手
- 比喩や冗談を理解しづらい
- 交友関係を広げるのが苦手
- 自分だけのルールにこだわる
- 臨機応変な対応が苦手
- 特定領域の記憶力が優れている
- こだわりが強い
- 興味関心の範囲が狭い
- 好きなことには精通している
- 一つのことに集中しすぎる
- 興味関心のない領域に関する知識が著しくない
- 予定が急変するとパニックになる
ASDの診断基準
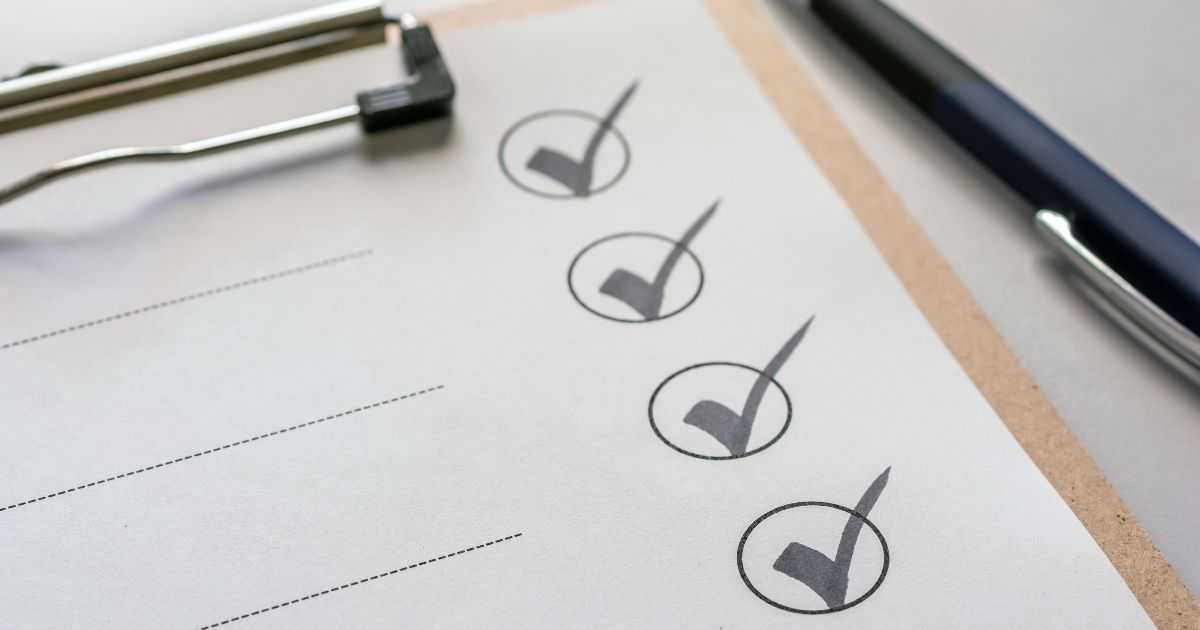
アメリカ精神医学会が定めた精神障害の診察基準『DSM-5』によると、ASDの診断基準は以下のとおりです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』)
- A.複数の状況で社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的欠陥がある
- 相互の対人的-情緒的関係の欠落で、例えば、対人的に異常な近づき方や通常の会話のやり取りのできないことといったものから、興味、情動、または感情を共有することの少なさ、社会的相互反応を開始したり応じたりすることができないことに及ぶ
- 対人的相互反応で非言語的コミュニケーション行動を用いることの欠陥、例えば、まとまりのわるい言語的、非言語的コミュニケーションから、アイコンタクトと身振りの異常、または身振りの理解やその使用の欠陥、顔の表情や非言語的コミュニケーションの完全な欠陥に及ぶ
- 人間関係を発展させ、維持し、それを理解することの欠陥で、例えば、さまざまな社会的状況に合った行動に調整することの困難さから、想像上の遊びを他者と一緒にしたり友人を作ることの困難さ、または仲間に対する興味の欠如に及ぶ
- B.行動、興味、または活動の限定された反復的な様式が2つ以上ある
- 情動的または反復的な身体の運動、ものの使用、または会(例:おもちゃを一列に並べたり物を叩いたりするなどの単調な常同行動、反響言語、独特な言い回し)
- 同一性への固執、習慣への頑ななこだわり、または言語的、非言語的な儀式的行動様式(例:小さな変化に対する極度の苦痛、移行することの困難さ、柔軟性に欠ける思考様式、儀式のようなあいさつの習慣、毎日同じ道順をたどったり、同じ食物を食べたりすることへの要求)
- 強度または対象において異常なほど、きわめて限定され執着する興味(例:一般的ではない対象への強い愛着または没頭、過度に限局したまたは固執した興味)
- 感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さ、または環境の感覚的側面に対する並外れた興味(例:痛みや体温に無関心のように見える、特定の音または触感に逆の反応をする、対象を過度に嗅いだり触れたりする、光または動きを見ることに熱中する)
発達障害グレーゾーンとは?

発達障害グレーゾーンとは、発達障害と同様の特性や傾向がいくつか認められるものの、診断基準を満たすほどではないため、発達障害と診断されるには至らない状態のことです。(参考:姫野桂『発達障害グレーゾーン』)
発達障害グレーゾーンという言葉は、医学的に正式な診断名称ではありません。
ただし、発達障害の確定診断をつけることができない状態のことを発達障害グレーゾーンと表現しているだけであって、発達障害グレーゾーンとは症状が軽いことを意味するわけではありません。
発達障害グレーゾーンについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害の二次障害とは?
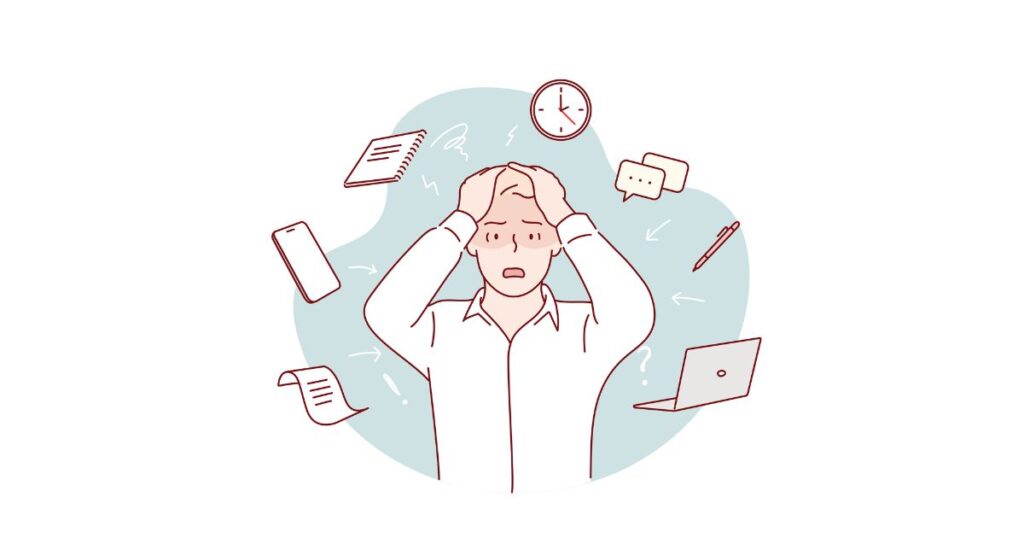
二次障害とは、主障害に起因して起こる副次的な障害のことです。ここで取り上げている発達障害の二次障害とは、発達障害や発達障害グレーゾーンの傾向・特性に伴って発生する精神障害やひきこもりなどの二次的な困難や問題のことを指します。(参考:齊藤万比古『発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート』、小栗正幸『発達障害児の思春期と二次障害予防のシナリオ』)
発達障害の二次障害は、うつ病といった精神面に現れることもあれば、暴力などの行動面で現れることもあります。発達障害に関連して起こる二次的な問題の総称です。
なお、発達障害があると、必ず二次障害が発生するわけではありません。
発達障害や発達障害グレーゾーンの傾向・特性が原因で発生する以下のような困難や問題は、発達障害の二次障害に該当します。
- 周囲とのコミュニケーションが上手く取れずに適応障害になる
- うつ病や不安障害などの精神障害を発症する
- ひきこもり状態になる
発達障害の二次障害については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
大人の発達障害とは?

大人の発達障害とは、医学的に正式な診断名称ではなく、明確な定義がない俗語のことです。(参考:林寧哲『これでわかる 大人の発達障害』、黒澤礼子『新版 大人の発達障害に気づいて・向き合う完全ガイド』)
医学的に正式な診断名称ではないため、明確に定められた定義はありませんが、一般的には、幼少期の時点で診断を受けておらず、大人になってから発達障害の確定診断を受けた状態のことを指すようです。また、幼少期の時点で発達障害の確定診断を受けていた人が、大人になった状態のことを、大人の発達障害と表現することもあるようです。
発達障害は、生まれつきのものです。本来、発達障害の特徴は一般的に乳幼児から幼児期に現れます。大人と子どもで本質的には異なる部分はなく、現在の医学では、大人になっても継続するものとされています。
そのため、「大人になってから発達障害になる」「成長するにつれて発達障害になる」ということはありえません。また、「思春期から」「満〇歳から」「育ち方や親のしつけの影響から」など、成長してから、または環境によって後天的に発達障害になるということも基本的にはありません。
大人の発達障害については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
「自分は(この人は)ASD かもしれない」と思うタイミング

ここでは、ASD の当事者と、関係者(親など育児に関わる人)の観点から、「もしかしたら自分は(この人は)ASD かもしれない」と思うきっかけの例を紹介します。
あくまで例ですので、「こういう人は必ずASDである」というものではありません。
①「社会人の自分」の場合
ASDは、他の発達障害と比べて、大人(新社会人)になってから発覚するケースが多いようです。
なぜなら、ASDの人は、記憶力が高いことがあり、学校での暗記中心の勉強ではあまり苦労せずに、成績優秀な人として評価されることもある(成績優秀なために、学校生活に適応しているように見えることがある)からです。
しかし社会に出ると、ASDの特性によって、次のように苦労するケースが見受けられ、そのタイミングで気づくことがあるのです。
- 「いつも無口で愛想がない」と周りから指摘される
- 自分では相手に言われた通りのことをしただけだと思うのに、なぜか相手が怒り出すことがよくある
- 臨機応変な対応、予定の変更が苦手なので、スケジュール変更の度に慌てる
- マルチタスクが苦手で、同僚よりもミスが多かったり、仕事が遅かったりする
自分の特性に気づくタイミングがないまま、社会に出て周囲からいきなり冷たくされると、生きづらさを感じるでしょう。
この状況が今の自分にも当てはまるとしたら、ASDの可能性があるかもしれません。
最近、「大人の発達障害」という言葉が広まってきました。「大人の発達障害」とは、カンタンに言うと、「大人(社会人)になってから自身の発達障害に気づくこと」を意味します。発達障害は生まれつきのものですので、「子どもの頃は発達障害ではなかった人が、大人になってから発達障害になる」ということはありません。
②「親から見た、子ども」の場合
ASDは、生まれつきのものです。そのため、子どもの頃から特徴的な行動をとることがあります。
例えば、次のような行動があります。
- 幼稚園や保育園、学校で友達ができず、集団生活に馴染めていない
- 偏食であり、食べ物の好き嫌いが激しい
- 複雑な動きを求められるスポーツや運動(ダンスなど)が苦手
ASDの可能性がある子どもは、ASDの特性上、自分から悩みを打ち明けることが難しいかもしれません。そのため、親御さんは、次のようなことを心がけるとよいでしょう。
- 何か違和感があるときに気軽に相談できる相手を作っておく(地域の保健師、かかりつけ医、保育士・幼稚園教諭・学校の先生など)
- 後述するサポート団体を積極的に利用する
③「パートナー、夫婦」の場合
パートナーと付き合ってから、または共同生活を始めてから、相手のことをASDかもしれないと思うケースもあります。
一緒に生活を送る中で、「この人は少しずれているかも?」と感じるシチュエーションが頻繁にある場合は、ASDの可能性があるかもしれません。
具体的には、次のようなシチュエーションです。
- 自分の気持ちを伝えても、相手の表情は変わらない。考えていることが全くわからないときがある
- 妥協してほしいと思っても、譲ってくれない
共同生活を送る上で、パートナー同士での理解は大事なことです。
相手も、心の中では「自分には何か特性があるのかも」などと思っている可能性もあります。第三者機関や専門家に相談をしてはいかがでしょうか。
自分が(ある人が)ASDかどうかは医師だけが診断できる

「ある人がASDかどうか」は、病院(医師)のみが診断できます。
①病院探し
自分、ご家族(お子さん・配偶者など)、恋人などがASDかどうかを知りたい場合は、まずは、発達障害の検査ができる精神科を探すところから始めましょう。
なかなか見つからない場合は、お住まいの地域の保健所、発達障害者支援センター、精神保険福祉センターに電話やwebで問い合わせましょう。
②事前準備
診察の予約が取れたら、検査の前の事前準備として、ご自身の状態や困りごとを伝えやすいように、メモを準備するなど工夫をするとよいでしょう。
メモの具体的な内容としては、次のようなものが考えられます。
- 仕事上で特に指摘されるミスや言動
例)「話を聞いていますか?」と言われる - 対人関係でよく苦労すること
例)「ノリが悪い」と指摘される - 周りの人からよく言われる言葉
例)「マイペースだよね」
メモのフォーマット例として、鳥取大学医学部の井上雅彦教授が監修した「わたしのトリセツ」というものがあります。簡単に使えて便利ですので、ぜひ参考にご覧ください。
③診察時には、パートナーや家族の同伴がオススメ
ASDの診断を受ける際は、パートナーや家族の同伴を病院から勧められるケースも多いです。
ASDの可能性のある人の同伴者からの情報や、一緒に生活を送る中で相手に感じていた「ズレ」は、重要な情報となります。
特に親御さんの同伴は、生育歴の確認のために大切です(母子手帳の持参を求められることもあります)。
その上で、同伴者が隣にいると、受診する人も心を落ち着かせて診断に臨むことができるでしょう。
④特に子どもを診てもらう場合
特に子どもがASDの診断を受けるかどうかは、一般的には親が判断することになるでしょう(また、診察に関連して「親が話すこと」も多いはずです)。
親御さんの中には、「診断は受けさせたいけれど、実際に我が子が発達障害だとしたら、私はすぐには受け入れられないかもしれない」と不安な人も少なくありません。
ASDの確定診断が出た場合、親御さんの方が、我が子の将来を心配する気持ちと現実を受け入れる気持ちなどが混同して、パニックになることもあるようです。
しかし、お子さんや親御さんをサポートする団体などはたくさんあります。
お子さんの発達障害を受け止められるようになる人もおりますので、サポート団体などの利用は、積極的に検討してみてください。
特に「子どもの発達障害(ASD)」について相談できるところとしては、「児童発達支援(児発)」や「放課後等デイサービス(放デイ)」などがあります(お近くの団体は、ネット検索などで見つかります)。
障害のある児童が通所し、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う施設です。(参考:独立行政法人福祉医療機構WAM NET「児童発達支援センター 」)
学校通学中の障害児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。(参考:独立行政法人福祉医療機構WAM NET「放課後等デイサービス」)
⑤病院での検査の前に、カウンセリングやサポート団体への相談もアリ
「医療機関での検査には抵抗がある(ASDであることが確定することが怖い)」と感じる人は、発達障害と確定していなくても利用できる専門機関やカウンセラー(臨床心理士・公認心理師)への相談をオススメします。
相談では、「検査・診断を受けるべきかどうか」を話すことができます。
結果として「検査は受けない」と決めた場合でも、特性・思考・言動など、「生きづらさ」を軽くしていくためのアドバイスを受けることができます。
一般論としては、ASDの特性が実際にある(関係する)かどうかに関わらず、「悩み事」は、専門的な知識を持つ人に相談した方が解決しやすくなります。
ASDの特性上、言語を介したやり取り(相談)が苦手で、ストレスになる人もいらっしゃいます。
しかし、「発達障害に関する相談を行っているところ」は、そうした「苦手」に理解があります。
ぜひ、相談先を探してみてください。
⑥診断が出たらショックを受けそうな人・受けている人へ
ASD などの発達障害がある人は、生きづらさを感じることが多いです。
理由としては、仕事やプライベートで、「失敗」や「できないこと・苦手なこと」そのものや、失敗・苦手への周囲からの指摘や注意が続くからです。
ASDの確定診断をポジティブに捉える人は、珍しくありません。
それは、失敗や苦手の原因がわかることで、次のように思うからです。
- 「ああ、今までの生きづらさは、先天的なモノだったんだ」
- 「やっと原因がわかって、ホッとした」
しかし一方で、「生きづらさ」を感じている中で、「医療機関の検査を検討すること」、「検査の結果、自分に障害があると確定すること」が、さらに大きな負担やショックとなる人も少なくないことも事実です。
他に、次のようなことを思う人もいるでしょう。
- 「もっと早く知っていれば、対策も早く考えられたのに」
- 「今までの苦労はなんだったんだろう」
ASDだとわかったのならば(自己受容までのプロセス)

診断を受けた後に、「自分はASDだったんだ」と落ち込む人は少なくありません。
筆者である私も、自分が発達障害であると知ってから、何日間も落ち込んでいました。
「そんなはずはない!」と自分の発達障害を認めたくない気持ちも湧いてくるかもしれません。
過去の失敗やトラブルとASDの関連を考えて、頭が混乱する人もいます。
しかし、ASDの特性には、対策もたくさん考えられています。
「自分の特性」との適切な付き合い方がわかれば、特性に伴う苦労を減らしたり、逆に特性を活かして私生活や職業生活を営んだりすることもできます。
そうするうちに、「自分とASD」のことを、徐々に受け入れられるようになると思います。
ASDの特性を理解した生活の例

- 自分の苦手とする行動をサポートしてくれる人(家族・パートナー・友人など)を頼る
- 職場や学校以外で、自分が落ち着ける場所(カフェや公園など)を見つける
- サポート団体や医療機関などを積極的に利用する(頼れる場所・相談できる場所はたくさんあります。また、家族や友人以外にも、一緒になって考える人はたくさんいます)
- 特に仕事との付き合い方や適職については、下記コラムで紹介しています。よければご覧ください。
ASDによる二次障害

ASDに限らず、発達障害の特性に関連して、メンタルダウンや行動力の低下が起きる場合があります。
この状態が続くと、精神疾患などの「二次障害(発達障害という一次的な障害に関連して起きる二次的な問題)につながることがあります。
代表的な二次障害には、以下の病気・行動があります。
- うつ病
- 不安障害(強迫性障害、パニック障害)
- 摂食障害
- 依存症(アルコール、薬物、ギャンブルなど)
- 睡眠障害
- 不登校
- ひきこもり
- 反社会的行動
二次障害の前兆として、食事が取れなくなる(取りすぎる)、眠れなくなる(寝すぎる)、 常に不安な気持ちになるなどがあります。
ASDの人が、社会人になってから二次障害を引き起こすケースは多く存在します。
その代表的な原因に、「周りの同期や同僚が当たり前にできることが、自分は全くできない」があります。
誰しも、社会生活に慣れるまでは一定の時間を要します。
しかし、ASDの人は、特性によって、同じミスや失礼に当たるコミュニケーションを何度も繰り返す傾向があります。
これらは、特性由来の失敗ではあるものの、周囲からは「仕事をなめている」「やる気を感じられない」という厳しい目で見られることになりがちです。
「自分にできることはない」と過度に自信を喪失して、自己肯定感が低下すると、二次障害としての精神疾患などにつながるリスクが高まります。
発達障害の二次障害の詳細は、下記コラムに記しています。よければご覧ください。
ADHDやLDなど、他の発達障害の併存

ASDの人は、他の発達障害のADHD(注意欠如・多動症・衝動性)やSLD(限局性学習障害)も併存していることがあります。
ASDの特性以外に、ADHDの特性(多動性など)やSLDの特性(文字の読み書きが困難など)もあるということです。
この場合は、対策・対応も、複数の特性に向けて同時進行で行う必要があります。
理想的な対応は、後述するサポート団体を利用しながら発達障害由来のストレスの回避方法を身につけたりして、健康的な生活を送ることです。
二次障害もある場合は、病院やそれぞれの状態のサポート団体に相談できます。
ASDの人を身近でサポートする人へ

ASDの人と近くで生活されている人や、非専門家の立場で当事者をサポートしている人(ご家族、友人、職場の人など)に向けて、考え方などのアドバイスをお伝えします。
①相互の理解を深めましょう
家庭や職場など、ASDの人と過ごす生活では、当事者に対して「どのように接すればいいのか」と感じることがよくあるでしょう。
何かのサポート・支援をしたときに、相手が無表情で何も感謝の言葉がないときなどは、気分を害するかもしれません。
大事なのは、相互の理解を深めることです。
どのようにしたらストレスが少ない生活を一緒に送れるのか、(専門家も交えつつ、)話し合う時間を設けてみましょう。
「どんなことをされたら嬉しいのか」「苦手なことはなんなのか」と相互の理解を深めていけば、落とし所が見つかるはずです。
また、ASDの人は、特性上、感情表現が苦手なことがあります。表情だけでなく、一つ一つの言葉に寄り添ってみてください。
②サポート団体を積極的に利用しましょう
ASDの人のサポートは、「チームで支える」という意識が重要です。
逆に言うと、「ASDの当事者を、私一人で(家庭だけで、上司である自分だけで)なんとかしないと」と考えるのはオススメできません。
各分野(ASD、日常生活、人間関係、コミュニケーション、仕事など)の専門的な知識を有するメンバーとチームで支援することで、当事者もご家族も、「無用な苦労やすれ違い」などから解放され、心身ともに充実した生活を送りやすくなります。
理想的なチームメンバーの具体例には、医師やカウンセラーのような専門家、自治体、発達障害のサポート団体、親族、同僚などがあります。
ASDの人の適職探しは、就労移行支援事業所の利用がオススメ

ASDの人で、現在離職中だったり、退職を検討していたりするなら、「再就職した職場での人間関係」のために、就労移行支援事業所の利用もオススメです。
就労移行支援事業所とは、「病気や障害のある人の(再)就職・転職を援助する福祉サービス」のことです。
各事業所は、公的な認可を得た民間事業者が運営しています。そのサービス内容は多岐にわたります。多くの事業所で、「職場でのコミュニケーション方法」を学ぶことができます。
- 職場での人間関係を良好に築く・保つ方法の習得
- 転職のための知識・技能の習得
- 履歴書・経歴書・エントリーシートの作成支援
- メンタル面のサポート
- 再就職・転職先候補や、職場体験実習(インターン)の紹介
- 転職後の職場定着支援
利用の可否は、お住まいの自治体が、下記などに基づいて判断します。
- 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などがある
- 18歳以上で満65歳未満の人
- 離職中の人(例外あり)
※上記を満たすなら、障害者手帳を所持していなくても利用可能です。
ご自身が利用できるかどうかは、自治体や、各就労移行支援事業所に相談してみましょう。
就労移行支援についてさらに詳しく知りたい人は、下記コラムをご覧ください。
ASDに関する正しい情報収集の仕方

ASDなどの発達障害は、メディアやSNSでも扱われるワードとなりました。多様性の時代ということもあり、少数派である人々の悩みや心配事が、多くの人の目に届くようになりました。
しかしその反面、信憑性のない情報が大量に流れているのも事実です。
「正しい情報」は、一般論としては、次のような団体に相談すると、参考となる書籍などを紹介してもらえます。
- 公的な団体
- 発達障害のサポート団体(発達障害者支援センターなど)
- 標準医療を行う病院
- 臨床心理士・公認心理師
自分や親しい人が発達障害であるとわかった直後に、冷静に正しい判断をすることは難しい場合もあるでしょう。
まずは時間をゆっくりとかけて、気持ちを落ち着かせましょう。そして、不確かな情報や、心ない言葉に振り回されないようにして、特性を受け止めていきましょう。
ASDのお悩み解決のためのお役立ち情報

このウェブサイト(就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)のウェブサイト)では、ASDや発達障害全般について、お悩みを解決するためのコラムを多数公開しています。
それぞれのコラムには、対策に加えて相談先も掲載しています。以下、悩み別に紹介しますので、気になったものがあればぜひご覧ください。
①「ASDと仕事」について
ASDの人に向いてる仕事はもちろんあります。この記事では、ASDの人が職業を考えるときに知っておきたい長所と短所、向いてる仕事と向きづらい仕事、適職を探す方法などを解説します。
実際に10か月の休職を経験した筆者の視点から、有意義な休職中の過ごし方を徹底解説します。また、休職中の過ごし方と併せて、復職後の人事の対応も紹介。休職中の過ごし方を知りたい人は、ぜひご一読ください。
「発達障害の特性に関連して、退職するかどうか悩んでいる、退職したら再就職できるのかも不安」という人に向けて、退職の前後にできること・しておきたいことを徹底解説します。
発達障害の人が転職を成功させるコツは、特性を理解した上で適切な専門機関を利用することです。この記事では、発達障害の特性理解に役立つ方法を事例つきで解説します。
就職の際に「障害者手帳を持つ人」が利用できる「障害者雇用(障害者枠)」について、概要、現状、条件、相談先などを徹底解説します。
②「ASDと家庭・学校生活」などについて
キズキ共育塾コラム「発達障害」のカテゴリー
主には親御さんに向けて、「発達障害と勉強」「発達障害と受験」「発達障害のお子さんに親ができること」などを紹介しています。(キズキ共育塾は、キズキビジネスカレッジ(KBC)と同じく、株式会社キズキが運営する完全個別指導塾です)
③「ASDとお金」について
「傷病手当金とは何か?」「うつ病の人が傷病手当金を受給できる条件」「傷病手当金と障害年金の併用」「うつ病の人が受けられるその他の経済的支援」「再就職や転職のためのサポート」などを紹介します(うつ病の人に向けた記事ですが、傷病手当そのものの解説は参考になると思います)。
病気や障害があると受給できる可能性がある「障害年金」について、概要、障害年金受給のための条件・金額、障害年金の相談先・支援制度などをQ&A形式でまとめて紹介します。
発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)
発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。
- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)
- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)
- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)
同じ診断名でも、人によって多様な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人は、他の発達障害が併存している可能性もあります。
発達障害の概要や種類、原因、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
【無料配布中!】ASD×仕事 実践ガイドブック
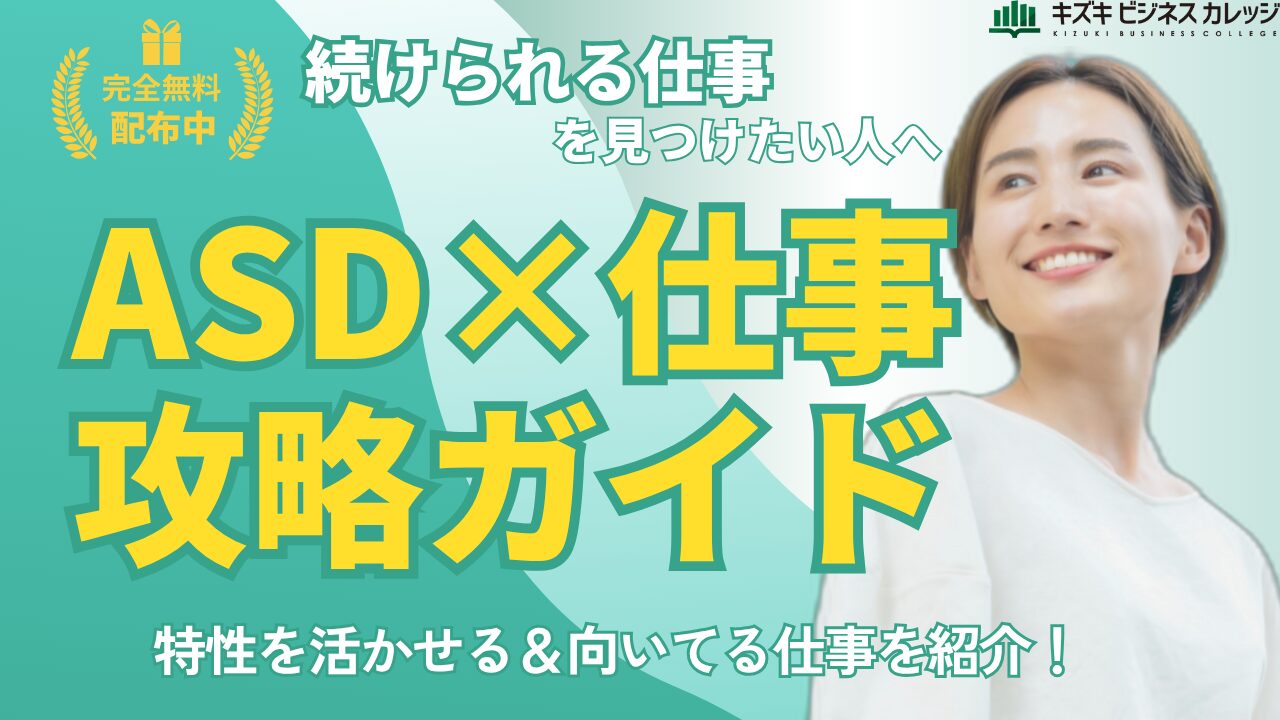
- 「職場の人とうまくやっていけない」
- 「感覚過敏でオフィス環境がつらい」
- 「こだわりが強すぎてつかれる…」
このように、ASDの特性ゆえに仕事に関する悩みを抱える人は少なくありません。
ASDのある人は、対人関係や感覚処理、物事へのこだわりの強さなど、特有の認知や行動パターンを持つため、一般的な働き方や職場のルールに適応しづらいことがあるためです。
また、自分に合った職場や働き方を見つけられず、「長く続けられる仕事が見つからない…」と悩む人も多くいらっしゃいます。
さらに、今の職場や働き方に合わせようと無理をして、特性に合わない働き方を続けた結果、ストレスの蓄積から体調不良やうつ病などの二次障害につながることもあります。
そのため、ぜひ本ガイドブックで「ASDのある人に向いてる仕事」や「仕事選びの視点」を知り、今のあなたに合った仕事を見つけていきましょう。
- ASDとは?
- ASDの特性が仕事に影響するポイント
- 向いてる仕事(具体的な職種例)
- 仕事選びで意識したい3つの視点(環境/業務内容/サポート体制)
- 正社員以外の働き方や支援機関の利用などの選択肢
- 向いてる仕事を見つけるためのチェックリスト
- ASDの診断を受けており、仕事選びに悩んでいる人
- 働き始めたものの、人間関係や業務がつらく長続きしない人
- 自分の特性に合った仕事を見つけたい人
- 就労支援を検討しているが、まずは情報を集めたい人
- 支援者・家族として、当事者の就労をサポートしたい人
- リンクから申し込みフォームにアクセス
- 簡単なフォームに入力
- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り
- URLから資料を取得!
- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。
- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。
- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。
また、ASDのある人に向いている仕事については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ:お悩みをあなただけで抱え込まないでください
以上、ASD(自閉スペクトラム症)の概要・よくある悩み事・相談先・関連情報をまとめて紹介しました。
最初にお伝えしたことの繰り返しですが、ASDについての相談先や特性はたくさんあります。お悩みをあなただけ(ご家族だけ)で抱え込まず、ぜひ、サポート団体を利用してください。この記事が、あなたの「安心」や「次の一歩」に繋がったなら幸いです。
自分が(家族が、周りの人が)ASDかどうかを知りたいです。
「ある人がASDかどうか」は医師だけが診断できます。気になるなら、病院で検査を受けましょう。ただし、「検査を受けるべきかどうか」は各種サポート団体に相談できます。詳細はこちらをご覧ください。
ASDの特性には何がありますか?
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年6月現在8校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年6月現在、首都圏・関西に8校舎を展開しています。トップページはこちら→