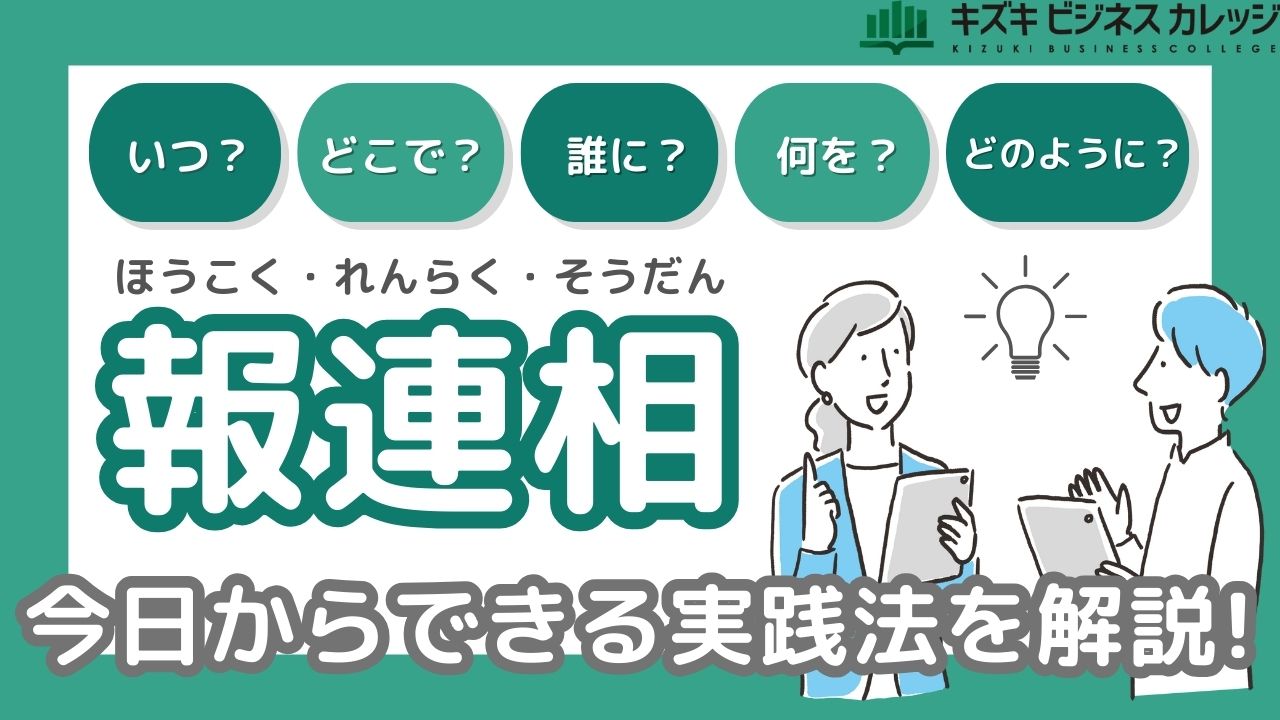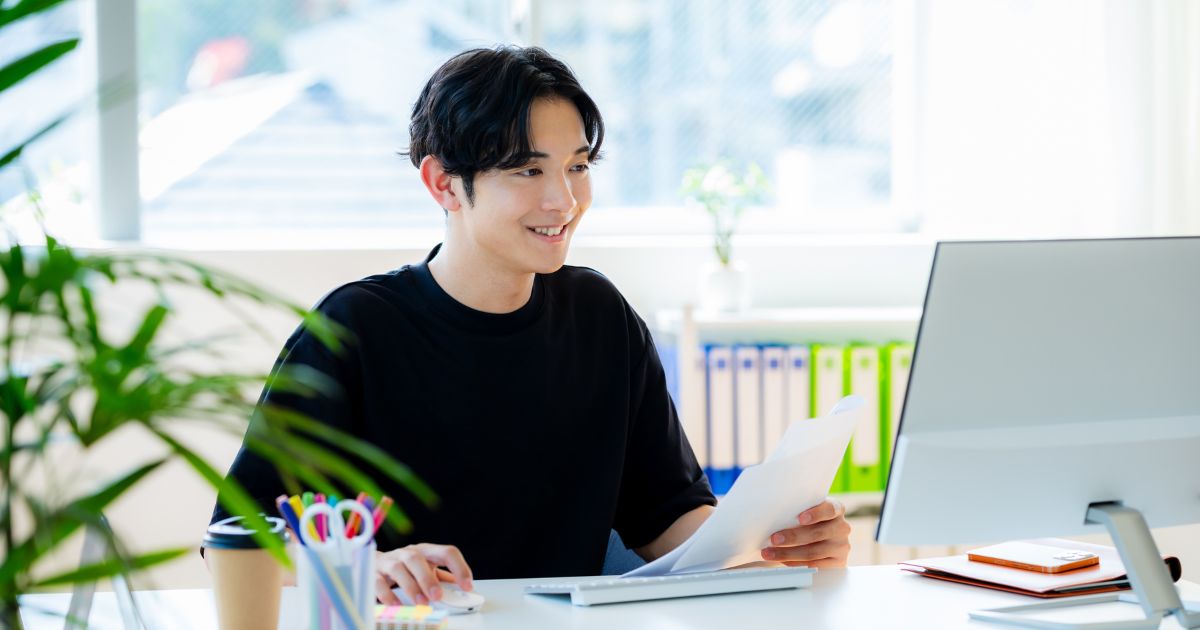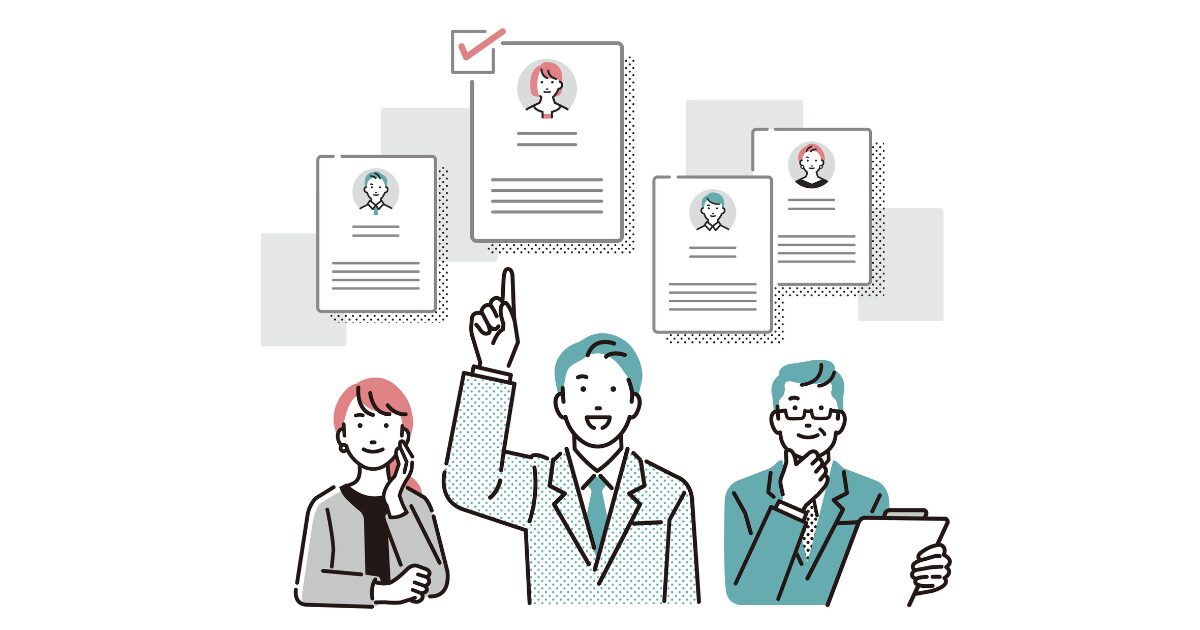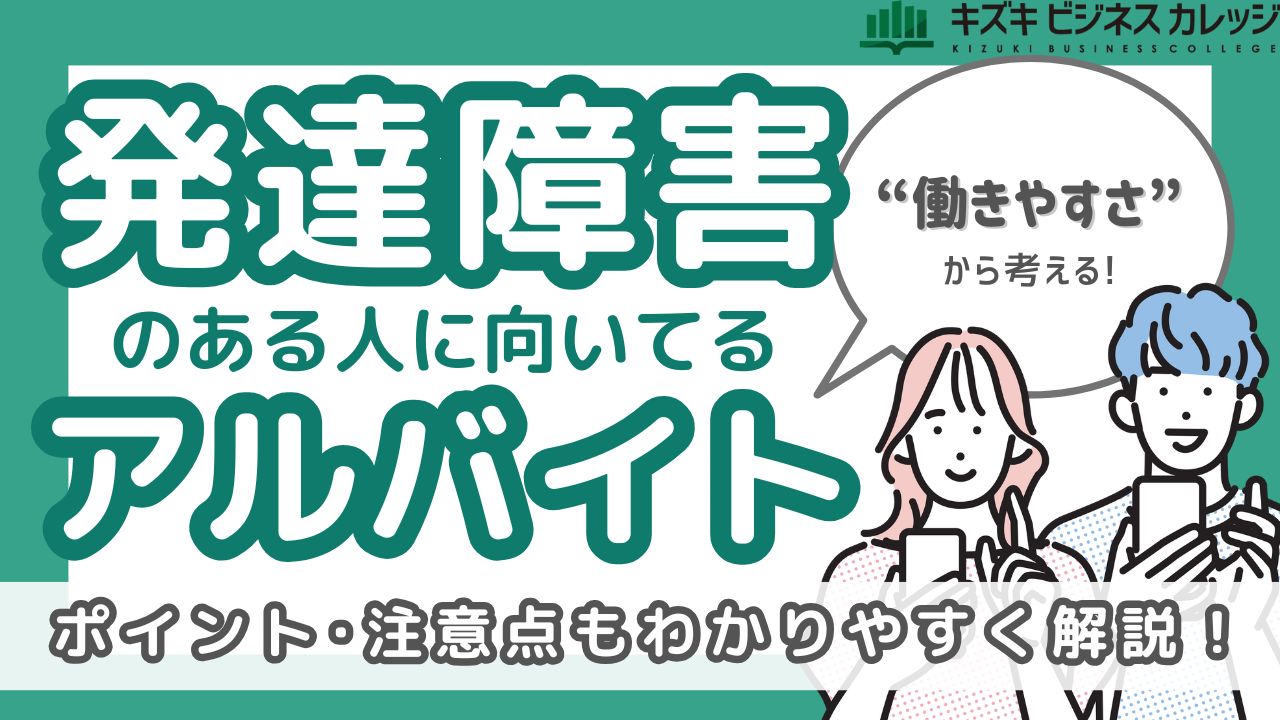発達障害のある人が実践できる仕事術16選 意識すべき前提を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
あなたは、発達障害の特性によって以下のような悩みを抱えていませんか?
- 仕事で失敗が増えて困っている
- 自分に合う仕事の進め方がわからない
- 就労で相談できる機関を知りたい
発達障害は、それぞれ特性が異なり、その現れ方も人によって異なります。仕事を円滑に進め働きやすくするには、自分に合った対策をしなければなりません。
このコラムでは、発達障害のある人が実践できる仕事術、意識すべき前提について解説します。
大人の発達障害で仕事に悩んでいる人は、ぜひ一度読んでみてください。
さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、仕事や働き方に悩むASDのある人に向けて、「ASD×仕事 実践ガイドブック」の無料配布を開始いたしました。
ASDの基本から仕事に影響するポイント、向いてる仕事、仕事選びの視点までを、わかりやすく丁寧に解説しています。
ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。
また、ASDのある人に向いてる仕事ついては、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。
仕事にお悩みの発達障害のあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
発達障害のある人が仕事をする上で意識すべき3つの前提
この章では、発達障害のある人が仕事をする上で意識すべき前提について解説します。
前提①自分の特性を理解する

発達障害のある人が働く上で特に重要なことは、自分の特性を理解することです。
発達障害のある人は、特性による向き・不向きや、得意・不得意が顕著に現れる傾向にあります。できないことについては、努力や工夫だけでは、どうしてもカバーできない面があります。
まずはあなた自身が、何ができて、何ができないか、何が得意で、何が苦手なのかなどの自分の特性に対する自己理解を深めてみてください。
自己分析をすることで、その特性にあった働きやすい仕事や職場、仕事術が見えてくるかもしれません。
前提②周囲の人に理解を求める
発達障害のある人が仕事をする上で大切なのは、上司や同僚などの職場の人や、家族や友人など、周囲の人に理解とサポートを求めることです。
発達障害のある人は、仕事や日常生活で困難を抱えていても、本人には自覚が薄い場合もあります。また、周囲のサポートなしで苦手なことを克服することは、発達障害の有無を問わず誰にとっても困難です。
仕事上の困難を和らげるために、職場の人とのコミュニケーションを通して、周囲にも自分の特性を理解してもらう働きかけをしてみてください。
周囲の人からのサポートがあれば、苦手な部分をカバーしてもらえるだけでなく、苦手なことも頑張る意欲が向上し、克服につなげやすくなるでしょう。あなたが苦手なことを自力で克服することが難しいと感じているのであれば、周囲からのサポートを受けることがオススメです。
特に仕事の多くはひとりで行うものではありません。ひとりで抱え込まずに上司や同僚などの職場の人に協力を仰いでみてください。
取り入れられそうな仕事術を見つけたら、ご自身で試すだけでなく、職場の人とできるだけ共有するとよいでしょう。
発達障害グレーゾーンのある人の場合であれば、医師から「発達障害という明確な診断は下せないが、発達障害グレーゾーンではある」と言われたなどと、伝えられるとよいかもしれません。ただし、こうした特性に関しての情報は個人情報ですし、伝えることで距離を置かれることもありえます。誰にでも自由に話すよりも、協力が得られそうな人や助けてくれる人を中心に話してみる方がよいでしょう。
前提③支援機関を利用する

発達障害のある人が仕事をする上で、支援機関を利用することもオススメです。
専門家や支援機関の客観的な意見は、あなたの仕事に役立つはずです。仕事に関して悩んでいるのであれば、就労面のサポートに特化している支援機関を利用してみてください。
発達障害のある人の就労をサポートしている支援機関はたくさんあります。さまざまな事例を知る専門家の存在は、必ずやあなたの仕事の支えとなるでしょう。発達障害グレーゾーンのある人でも相談可能な支援機関もあります。ご安心ください。
支援機関では、就労に関するさまざまなサポートを受けられます。また、ほかにも、日常生活に関するサポート、メンタル面に関するサポートなどを受けられる可能性があります。
発達障害のある人の就労をサポートしてきた支援機関であれば、過去の事例を交えながら、あなたに合ったアドバイスをしてくれるはずです。あなた自身が気づいていない特性について理解し、あなたの可能性を広げることにつながるかもしれません。
気になる支援機関があれば問い合わせてみましょう。どの支援機関が適切かわからないという場合は、主治医やお住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口、専門家などに相談してみてください。
発達障害のある人が実践できる仕事術16選
この章では、発達障害のある人が実践できる仕事術について解説します。
発達障害のある人は、自身の特性を理解した上で適切な仕事術を取り入れることで、仕事での困難を減らすことができます。
自分にとってできないことではなく、できることにフォーカスし、仕事に取り組んでみましょう。
取り入れられそうなものを見つけたら、積極的に実践してみてください。(参考:宮尾益知『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、太田晴久『職場の発達障害 自閉スペクトラム症編』、星野仁彦『発達障害に気づかない大人たち』、田中康雄『大人のAD/HD』、對馬陽一郎『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害のある人が会社の人間関係で困らないための本』、木津谷岳『これからの発達障害者「雇用」』、姫野桂『「発達障害かも?」という人のための「生きづらさ」解消ライフハック』)
仕事術①具体的な指示を依頼する、指示を確認する

仕事術の1つ目は、具体的な指示を依頼することです。これは特に、ASDのある人向けの仕事術です。
ASDのある人はあいまいな表現をされると混乱することがあり、指示された内容を理解できない場合があります。
職場の人があなたの特性を理解していない場合、「適宜」や「適当に」などの抽象的な表現を用いて、あなたに裁量を委ねることが多いでしょう。
曖昧な指示のまま実行すると、誤った処理をして、「この人は仕事ができない」と相手に思われることもあるかもしれません。
そのようなことを防ぐために、「〇時までにやっておけばよいですか?」「〇〇の場合はこうしても大丈夫ですか?」などと伝えて、できるだけ確認をしたり、具体的な指示をお願いするようにしましょう。
「この書類を何部印刷して、何階のA会議室のホワイトボードの前の机に置いておいてください」などの具体的な指示があれば、ぐっと仕事がしやすくなるはずです。また、職場の人もあなたの特性に対して理解を深め、どういう指示がわかりやすいか知ることができるでしょう。
必要に応じて、具体的なお願いを紙やメールなどの文章で作成してもらうこともオススメです。
ただし、あまりに詳細な内容を毎回要求することには、相手に時間的・心理的コストを払わせることになります。お願いをする際には、可能であれば自分から提案して、イエスかノーで答えてもらえる状態にしてから質問するなど、具体的に指示をしてもらいやすい状態を整えていきましょう。
仕事術②やることをリスト化する
2つ目の仕事術は、やることをリスト化すること、To doリストを作成することです。これは特に、毎日の時間管理に対して苦手意識を持つADHDのある人やASDのある人に有効な仕事術です。
やらなければならないことが増えると、頭の中で効率を考えこなそうとしても、別の業務を進めるうちに忘れることがあります。やらなければならないことを忘れると予定が狂い、誰かに迷惑をかけることにもつながります。
やることを徹底的にリスト化しておけば、ある程度はミスを回避できるはずです。毎日のやるべきことをきちんと達成できるよう管理してみましょう。
やることに関しては、起きてから出かけるまでや帰宅してから寝るまで、出勤してから退勤するまでなど、日常的にやることや仕事でやるべきことの内容とその所要時間などをそれぞれリスト化しておくとよいでしょう。
また、目的の時間までに準備すべきことが明確になるため、寝坊や遅刻を防ぐことにもつながるでしょう。時間の見積もりが甘かったり、未来の予定を具体的にイメージできなかったりする発達障害のある人には特にオススメです。
具体的な方法として、やることを紙に書きだして、完了したら、線を引いて消すなどの方法が考えられます。
また、リスト化をサポートするツールを使うのも有効です。ツールを使うメリットとして、以下が挙げられます。
- 可視化することで確認が容易に確実に出来る
- 一目見てやったかどうか、忘れ物がないかどうかがすぐわかる
- 所要時間なども自由に設定して書けるため、イメージしやすい
カレンダーや日記、ノート、ToDoリストの全てを一元管理できるアプリなど、手軽に導入できるツールを利用するとよいでしょう。
その日のうちにやらなければならないことがあるときは、スマートフォンのタスク管理アプリを使うのがオススメです。
Googleカレンダーと同期できる「Google ToDoリスト」やiOSのメインアプリである「リマインダー」などがオススメです。
なお、業務内容や手順をリスト化することは、ASDのある人にも有効です。ASDのある人は、見通しが立ちにくい状況に混乱しやすいという特性を持つ人が多いと言われています。リスト化することで、思考が整理されて、見通しを立てて仕事ができるようになります。
自分が落ちついて業務に取り組むためにも、手順や順序などをリスト化してみてください。そうすれば、これまで以上に仕事に集中できるようになるはずです。
仕事術③スケジュールを整理する

スケジュールは、時間別、目的別、場所別などに分類して全て書き出すのがオススメです。書き出しておくことで、やるべきことが一目瞭然でわかるようになります。
書いた内容の追加・削除・変更が生じるたびに更新することで、発達障害の特性があっても、自分できちんと管理できるはずです。
仕事術④業務の優先順位をつける
こちらで解説したリスト化やこちらで解説したスケジュールの整理とも関連しますが、業務の優先順位をつけることも重要です。
仕事に取り組む中で、どの業務から手を付けて良いものか迷う人もいるでしょう。発達障害のある人の中には、こだわりの強さが目立つ人も少なくありません。
中には任された順番どおりにこなしていきたいというこだわりが出ることもあります。しかし、そのこだわりを優先して仕事をしていると、結果的に後で慌てる事態になる恐れがあります。
そのようなときは、提出予定日や締切などの期限を洗い出し、一覧表をつくり優先順位をつけていくことをオススメします。それぞれの期限を一覧表に書き出すことで、なにから手をつければいいのかをすぐに確認・把握できます。
付箋にやるべきことと期限を書き、視界に入れて置いておくこともオススメです。
やるべきことを達成したらそれが書かれた付箋を捨てるなど、動作を組み込むことでより業務内容を整理できるでしょう。また、視覚的に残りの業務量を把握できるので、前向きな気持ちを維持しながら次の作業に取り組めるはずです。
仕事術⑤自分専用のマニュアルをつくる

自分専用のマニュアルをつくるのもよいでしょう。
多くの場合、社内のマニュアルは、その業務を行う人全員にわかるように書かれているはずですが、多少は作成者の感覚やさじ加減が反映されています。
場合によっては、「ころ合いを見計らって」や「〇〇さんの手が空いたときに」などの曖昧な指示が入っていることもあるでしょう。
しかし、ASDのある人はこのような曖昧な表現が苦手な傾向があります。
業務の処理中に混乱したり、極端な対応を取ったりしないためにも、あなたの特性に合ったマニュアルが必要です。
自分らしく働けるように、得意なことを活かせるマニュアルづくりに取り組んでみてください。業務処理中のコミュニケーションのすれ違いを生まないためにも必要なはずです。
まずは自分でマニュアルを作り、それを職場の人に確認してもらうとよいでしょう。
仕事に関するマニュアルづくりが難しいと感じる場合は、まずは普段の暮らしの中で使えるマニュアルを試しにつくってみるのもよいかもしれません。
仕事術⑥わからないことを質問する
わからないことを質問することも、立派な仕事術です。
仕事を進めて行く中で、わからないことがあり困るときは必ずあります。そのようなときは、どれだけ些細なことでもわかるまで職場の人に説明を求めましょう。
聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥ということわざがあるように、以前質問したことを聞くのは恥ずかしさがある一方、知らないままでは一生知らないままでいることになります。
また、説明を受けた後は自分の言葉や図など、自分にとってわかりやすい方法でメモに残すのがオススメです。
仕事術⑦整理整頓の時間を設定する
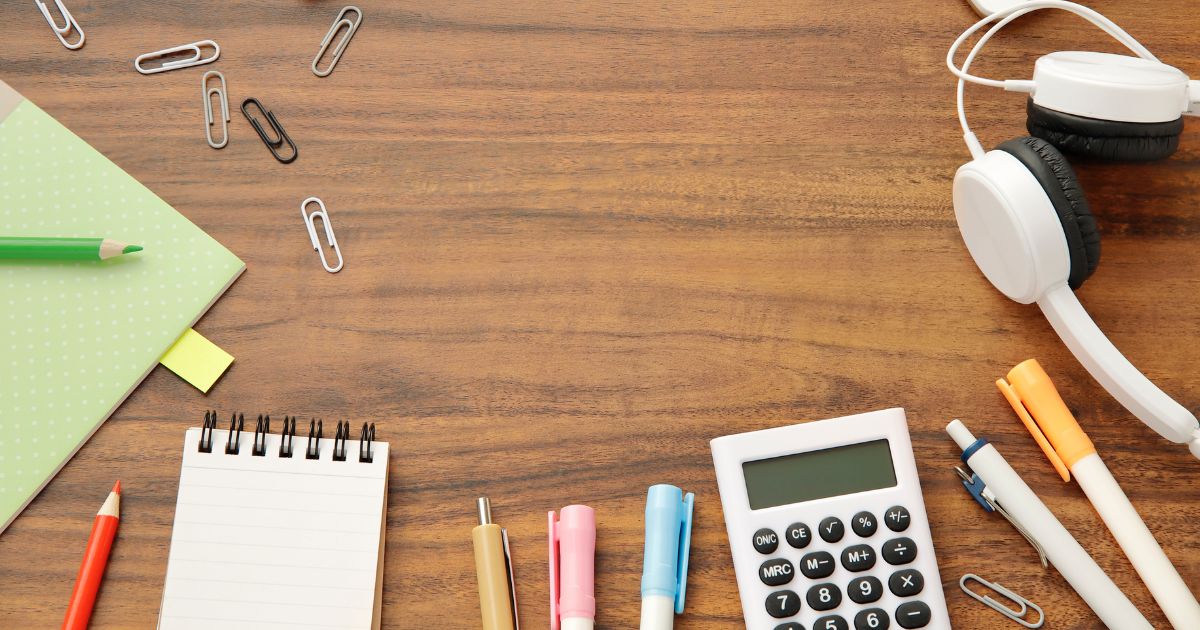
7つ目は、整理整頓の時間を設定することです。これは、ADHDのある人に特に効果がある仕事術です。
ADHDのある人は、整理整頓が苦手で、気がつくとすぐに机の上が散らかる傾向があります。仕事に夢中になって駆け回るうちに、自身の所有物を整理できなくなるのです。
この傾向は、ミスや忘れ物、紛失などに繋がります。対策として、一日スケジュールの中に、あらかじめ整理整頓だけをする時間を作ることで緩和できるでしょう。
仕事術⑧文字や図を用いた説明を求める
8つ目は、文字や図を用いた説明を求めることです。
LD/SLDのある人は、会議の場などで、苦手とする情報形式で説明されると、話についていけなくなることがあります。また、LD/SLDのある人と同様に、ASDのある人の中にも、文字だけ、あるいは音声情報だけだと、理解しづらい傾向のある人がいます。
これは、受け手側のASDのある人やLD/SLDのある人だけで対処できるものではありません。
日頃から、理解しやすい情報形式でのコミュニケーションをお願いしたり、説明の方法を理解しやすいものに変えてもらうよう、周囲に働きかけたりするとよいでしょう。
LD/SLDのある人ができることに、ICレコーダーなどを取り入れるというものがあります。
最近では、文字を読むのが苦手なLD/SLDのある人向けに、文書の自動読み上げをする機械などもあります。こういったものを仕事の場に活かすのもよいでしょう。
仕事術⑨ダブルチェックを依頼する

9つ目は、ダブルチェックを依頼することです。これはADHDのある人に有効でしょう。
努力をしても発生する見落としやミスを何としても防ぎたい場面に、効果を発揮します。
ダブルチェックは、発達障害のある人だけでなく、発達障害のない人も普段から取り入れることが多いため、自然に頼めるのではないでしょうか?
同僚や先輩にチェックをお願いしてから上司に提出するなど、職場の人と連携しやすい方法を検討してみてください。
そうすることで、自分なりにリカバリーしながら適切なスケジュール内にミスのない書類を提出できるようになるはずです。
仕事術⑩ひとつの業務に集中する時間を設定する
ひとつの業務に集中する時間を設定することは特に、マルチタスクが苦手なADHDやASDのある人に有効です。
ADHDやASDのある人は、ほかの作業が気になることで、結果的に全体の業務に影響がでるという場合が多いです。
そのため、業務時間の中で、この時間はこの業務だけをしようなどと、ひとつのことだけに取り組む時間を設けることで、特性をカバーできるかもしれません。
仕事術⑪アラームを設定する

作業ごとや予定ごとにアラームを設定するのも効果的でしょう。
これは、特定の分野に関して強い興味を持つ特性のある人や時間経過を体感的に把握しづらい特性のある人に有効です。
発達障害のある人は、自分の関心分野などに高い集中力を発揮できるため、何時間も続けて作業をする過集中という状態を引き起こしやすい傾向にあります。
このようなケースでは、自分の体調や疲労に気づきにくく、食事を忘れて深夜まで仕事をしたりと無理をして作業することも少なくありません。
高い集中力は仕事のパフォーマンスを向上させる利点もあります。一方で、疲労が蓄積して体調を崩せば仕事だけでなく私生活にも影響します。場合によっては寝坊や遅刻につながるでしょう。
あらかじめアラームを設定して、休憩時間をつくれれば、それらの事態を避けられるはずです。アラーム機能を活用して、休憩時間をつくるようにしてみてください。
もちろん、予定を守るためにも、アラームは有効です。支度を開始する時間までアラームとして設定しておくと、後から慌てて準備をして、遅刻をするといったリスクを下げることができます。
人によっては、アラームの設定をしたいが、アラーム音が不快だから抵抗感があるという人もいるでしょう。そのような人には、「おこしてME」というアプリのように、端末に保存してある音楽が鳴るように設定できるものがオススメです。
また、周りにアラーム音を聞かれたくないという人や、作業に集中するためにイヤホンをしているという人は、「イヤホン目覚まし時計」のようなアプリを利用するとよいでしょう。
ほかにも、予定時刻の前にバイブレーションがなるように設定できる機能のあるアプリもあります。
仕事術⑫電子機器を仕事に取り入れる
特定の情報の入出力が苦手なLD/SLDのある人は、電子機器を仕事に取り入れることで、格段に仕事効率が上がる可能性があります。
例えば、会議の場以外でもICレコーダーを使用したり、日頃から電卓を持ち歩いたりするなどの工夫をしてみましょう。
ただし、ICレコーダーで録音などをする場合、会話の内容によっては機密情報が含まれる可能性もあります。ICレコーダーを使用する際は、周囲に確認した上で録音してください。その上で、データの取り扱いに注意しましょう。
最近では、Googleが提供しているアプリを筆頭に、文書の自動読み上げツールの技術も格段に進歩しています。
ほかにも計算に困難が生じるLD/SLDのある人であれば、小型の電卓を常に携帯するなど、工夫次第で特性をカバーすることは可能です。
あなたの特性に合わせてフォローしてくれる電子機器が見つかるはずです。
こういった電子機器を仕事の場に活かすことで、仕事ができないという悩みを解決できないか、考えてみてください。
仕事術⑬遅刻対策をする

遅刻は人間関係などさまざまな場面で悪影響を及ぼします。そのため、さまざまな遅刻対策が欠かせません。
発達障害のある人ができる遅刻対策は、以下のとおりです。
- 事前に持ち物を準備しておく
- 毎日の起床と就寝の時間を定める
- 日頃から所要時間を計測する
- 前倒しで行動する癖をつける
- 予定時刻を早めに設定してもらう
- 当日にリマインドできる仕組みをつくる
発達障害のある人ができる遅刻対策については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
仕事術⑭報連相対策する
発達障害のある人には、複数の事柄をまとめて全体を把握することが苦手であったり、相手の心情や状況をくみ取ることが苦手といった特性から、報連相が苦手なことあります。
報連相は仕事においてとても重要な業務の一環であるため、意識的に対処していかなければなりません。
発達障害のある人ができる報連相対策は、以下のとおりです。
- 報連相する内容を整理する
- 報連相する相手の優先順位を決めておく
- 報連相のタイミングをあらかじめ相談する
- 把握すべきことを記録する
- スケジュールで管理する
- 説明方法の配慮をしてもらう
- 言葉遣いや話し方を意識する
- 見た目や態度を意識する
- どのような情報もひとまず報告する
- イレギュラーに備え、予定通りに行かなかった場合のバックアップも考える
発達障害のある人ができる報連相対策については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
仕事術⑮うまくいった対策を真似してみる

ほかの人のうまくいった対策を真似してみることも仕事術と言えるかもしれません。
お手本となる人がいればイメージしやすく、これまで紹介した仕事術を取り入れやすくなります。
身近に発達障害があり、うまく対策できている人がいれば、やり方をまねしたり、仕事の進め方を直接聞くことをオススメします。
もし身近に手本となる人がいないなら、発達障害に関連する書籍などで情報収集してみましょう。発達障害のある人向けの書籍には仕事の進め方に関する書籍もあります。
また、インターネットやYouTubeでも情報発信をしている人もいます。自分が実践できそうであれば積極的に取り入れてみてください。
仕事術⑯ライフハックを身につける
発達障害のある人が日常生活を営む上で、身につけるべきものは、発達障害の特性に関わるライフハックかもしれません。
ライフハックとは、丁寧な生活や仕事をするための基礎的な技術のことです。
発達障害のある人ができるライフハックについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
補足:転職を検討する

発達障害の特性から、周囲や業務内容と折り合いがつかないときは、思い切って転職するのも方法の一つです。
転職するきっかけは人によってさまざまです。もちろん、人間関係に馴染めないといった理由で転職を選ぶ人もいますが、苦手とする業務があったと気付いたり、自分には向いてないと気付いたりしたことを、一つのきっかけとして転職する人もたくさんいます。
自分の不得意なことが把握できれば、苦手と感じる業務以外の仕事を選べばやりやすくなるはずです。腰を据えて働ける職場を探しやすくなるでしょう。
発達障害のある人の転職については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
仕事ができないと悩む発達障害のある人と一緒に働く人ができる対応
 仕事ができないと悩む発達障害のある人と一緒に働く人ができる対応は、以下のとおりです。
仕事ができないと悩む発達障害のある人と一緒に働く人ができる対応は、以下のとおりです。
- 特性を理解する
- その人が理解しやすいように説明をする
- 具体的に伝える
- 障害に合わせた業務に就いてもらう
- 産業医や専門家の指示を仰ぐ
発達障害のある人と一緒に働く人ができる対応については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)
発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。
- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)
- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)
- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)
同じ診断名でも、人によって多様な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人は、ほかの発達障害が併存している可能性もあります。
発達障害の概要や種類、原因、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
【無料配布中!】ASD×仕事 実践ガイドブック
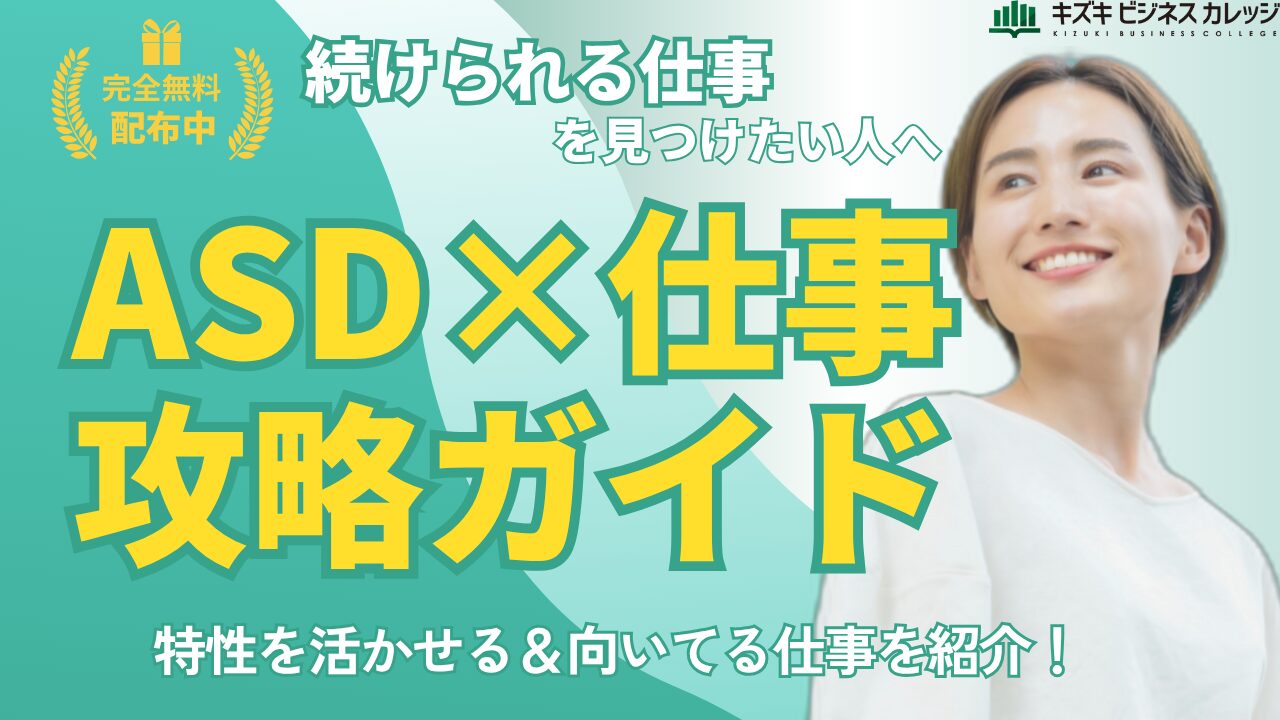
- 「職場の人とうまくやっていけない」
- 「感覚過敏でオフィス環境がつらい」
- 「こだわりが強すぎてつかれる…」
このように、ASDの特性ゆえに仕事に関する悩みを抱える人は少なくありません。
ASDのある人は、対人関係や感覚処理、物事へのこだわりの強さなど、特有の認知や行動パターンを持つため、一般的な働き方や職場のルールに適応しづらいことがあるためです。
また、自分に合った職場や働き方を見つけられず、「長く続けられる仕事が見つからない…」と悩む人も多くいらっしゃいます。
さらに、今の職場や働き方に合わせようと無理をして、特性に合わない働き方を続けた結果、ストレスの蓄積から体調不良やうつ病などの二次障害につながることもあります。
そのため、ぜひ本ガイドブックで「ASDのある人に向いてる仕事」や「仕事選びの視点」を知り、今のあなたに合った仕事を見つけていきましょう。
- ASDとは?
- ASDの特性が仕事に影響するポイント
- 向いてる仕事(具体的な職種例)
- 仕事選びで意識したい3つの視点(環境/業務内容/サポート体制)
- 正社員以外の働き方や支援機関の利用などの選択肢
- 向いてる仕事を見つけるためのチェックリスト
- ASDの診断を受けており、仕事選びに悩んでいる人
- 働き始めたものの、人間関係や業務がつらく長続きしない人
- 自分の特性に合った仕事を見つけたい人
- 就労支援を検討しているが、まずは情報を集めたい人
- 支援者・家族として、当事者の就労をサポートしたい人
- リンクから申し込みフォームにアクセス
- 簡単なフォームに入力
- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り
- URLから資料を取得!
- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。
- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。
- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。
また、ASDのある人に向いてる仕事については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ:発達障害でも工夫次第で仕事は続けられます

仕事術というと、個人でできるものが多くなりますが、発達障害の人にまずオススメしたいことは、自分の特性を理解した上で、周りに協力を求めることです。
繰り返しになりますが、一人で抱え込まずに周囲の人に相談してみてください。
それは、あなたの障害の助けになるだけでなく、ストレスを軽減することにもつながります。
このコラムをお読みになった発達障害のある人の仕事の悩みが、少しでも解消されることを祈っています。
発達障害のある人が仕事をする上で意識すべきことはありますか?
発達障害のある人が実践できる仕事術を教えてください。
以下が考えられます。
- 具体的な指示を依頼する、指示を確認する
- やることをリスト化する
- スケジュールを整理する
- 業務の優先順位をつける
- 自分専用のマニュアルをつくる
- わからないことを質問する
- 整理整頓の時間を設定する
- 文字や図を用いた説明を求める
- ダブルチェックを依頼する
- ひとつの業務に集中する時間を設定する
- アラームを設定する
- 電子機器を仕事に取り入れる
- 遅刻対策をする
- 報連相対策する
- うまくいった対策を真似してみる
- ライフハックを身につける
詳細については、こちらで解説しています。
監修志村哲祥
しむら・あきよし。
医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。
臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。
【著書など(一部)】
『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』
他、学術論文多数
日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧
時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
監修角南百合子
すなみ・ゆりこ。
臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→