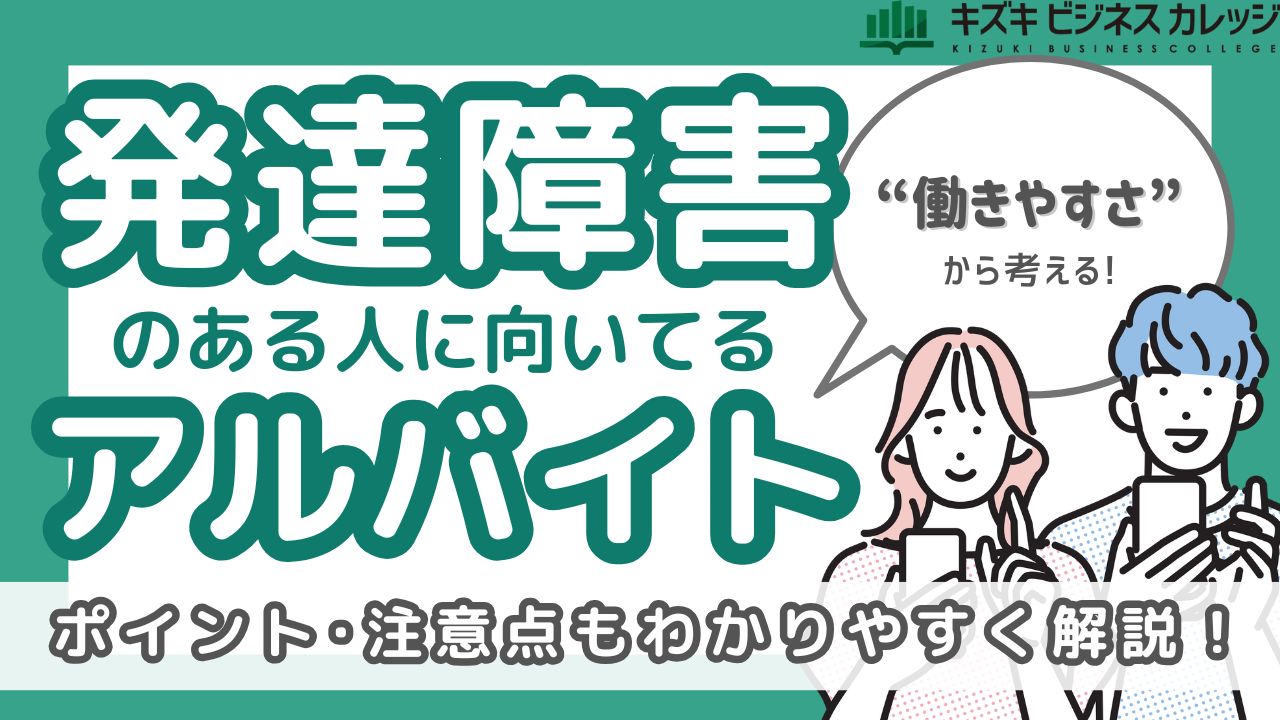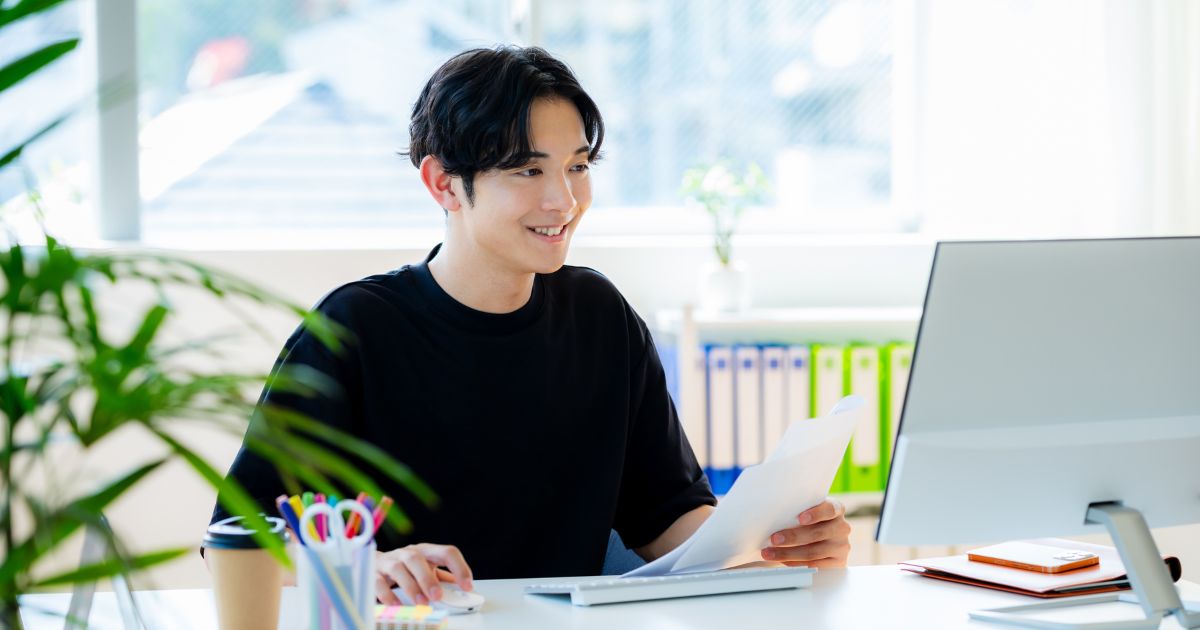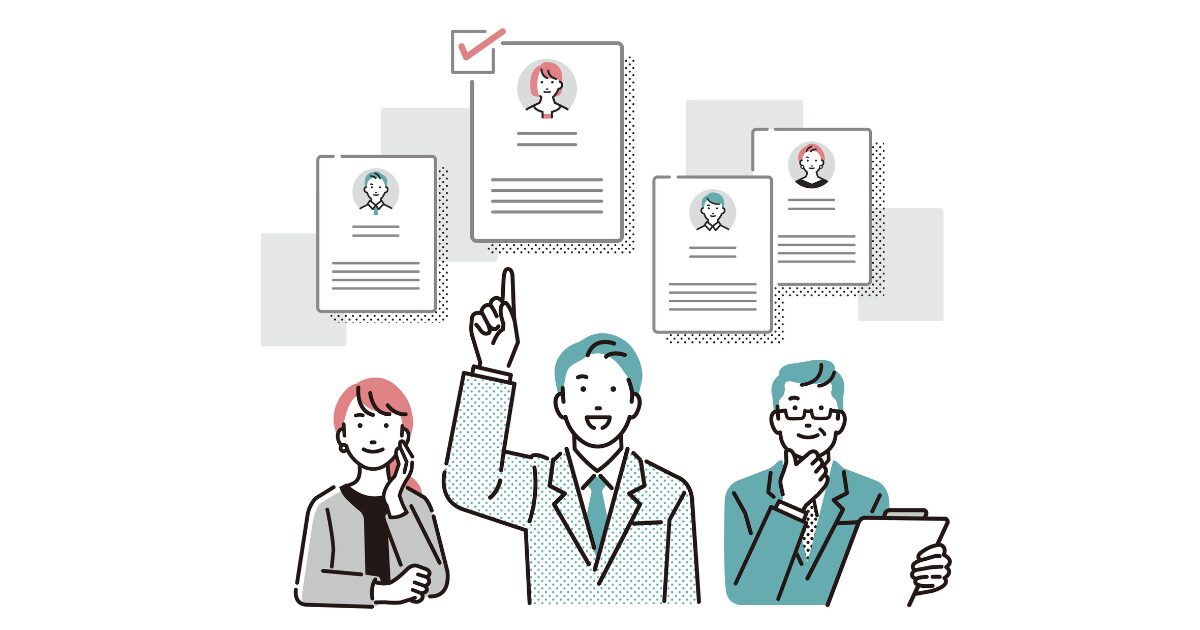発達障害のある人が就活を成功させるステップ 就職を成功させるコツを解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
発達障害のあるあなたは、就活する中でいくつかお悩みを抱えていませんか?
例えば、それまでの学校や家庭などでは問題なく過ごせてきた人が、就活する中で困難や生きづらさが表面化したことで、発達障害であることを知るというケースも珍しくありません。
就活の場面では、発達障害のある人が困難を覚えやすいポイントがいくつかあります。
また、就活に成功した後も、仕事内容とのミスマッチなどから、転職を繰り返すということもあります。
このコラムでは、就活を成功させるステップや就職を成功させるコツについて解説します。あわせて、発達障害のある人が就活を成功させた体験談と失敗させた体験談を紹介します。
発達障害に関連して就活でお悩みのあなたに役立てば幸いです。
さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、仕事や働き方に悩むASDのある人に向けて、「ASD×仕事 実践ガイドブック」の無料配布を開始いたしました。
ASDの基本から仕事に影響するポイント、向いてる仕事、仕事選びの視点までを、わかりやすく丁寧に解説しています。
ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。
また、ASDのある人に向いてる仕事ついては、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。
就活を成功させたい発達障害のあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
発達障害のある人が就活を成功させる4つのステップ
この章では、発達障害のある人が就活を成功させるステップについて解説します。
自己分析・自己の特性の理解や業界研究は、発達障害の有無を問わず重要です。
なお、最近では、大学のキャリアセンターやジョブカフェ、就労移行支援事業所などで発達障害のある人の就活をサポートしています。
それらの支援機関を積極的に利用することで将来を見据えた就活が可能になります。悩みを一人で抱えずに、就活を進めてみてください。
前提:就活を始める前に確認すべきこと

就活を始める前に、以下の点が該当するか確認してみてください。
- 就職する意欲がある
- 体調管理ができる
- 生活リズムが整っている
- 社会的なマナーや身だしなみ、挨拶の方法を理解している
就活を始めるには、モチベーションが必要です。
ひとりで進めることに負担を感じる場合は、主治医に相談したり、支援機関からの支援を受けたりすることを検討してみてください。
ステップ①自分の特性や状況の整理
発達障害があると言っても、全員が全く同じ症状・特徴・傾向があるわけではありません。
まずは、自分の特性や状況を整理し、就職先や働き方の選択肢を考えることが必要です。そうすることで、自分にはどんな選択肢があるのかを考えられるようになるでしょう。
とはいえ、発達障害のある人が、自分の特徴について一人だけで考えるのは大変かもしれません。
そんなときは、支援機関に相談してみてください。
発達障害のある人の就活をサポートする支援機関はたくさんあります。支援機関を利用しながら、自分の特性や状況の整理を進めていきましょう。
ステップ②自己分析・自分の特性の理解
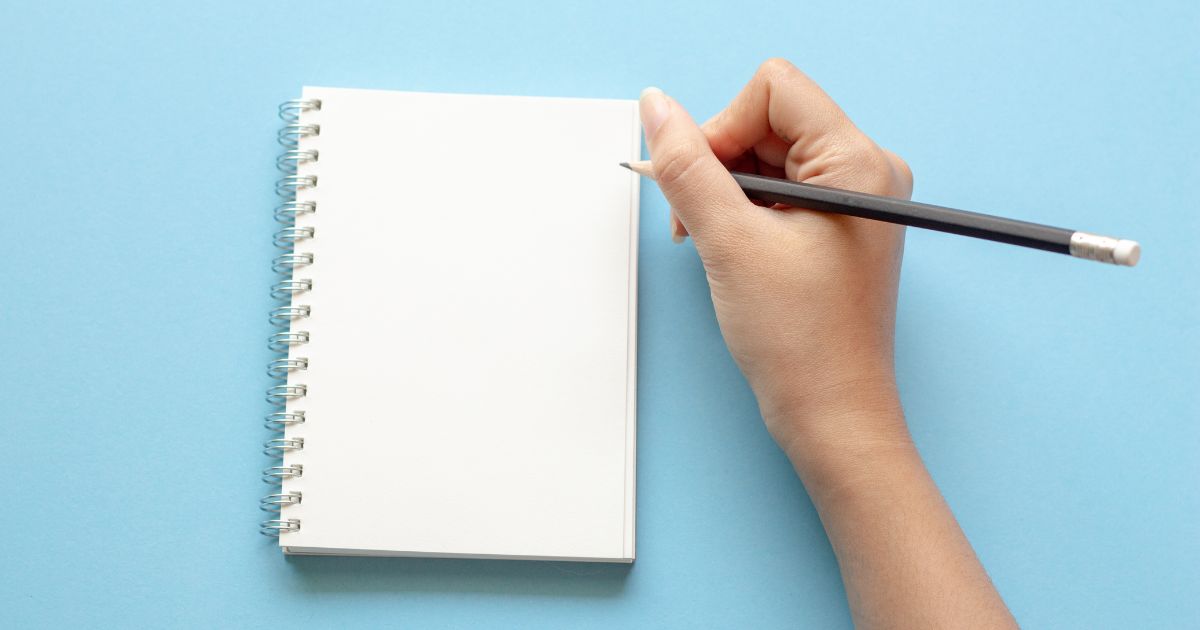
発達障害のある人の場合、自己分析・自己の特性の理解は特に重要です。
こちらで解説しますが、発達障害のある人は、特性による向き・不向きや、得意・不得意が顕著に現れる傾向にあります。
就活に際して、その特性を活かす方法を考えたり、特性をカバーする習慣を身につけたりするためにも、自分の特性の理解は欠かせません。
自己分析の方法として、以下が考えられます。
- 自分史の作成
- 性格の分析
- 自分の興味の整理
- 自分の特性の分析
自己分析ができれば、以下のように、向いてる仕事やなりたい仕事、向いてない仕事やなりたくない仕事などが明確になるはずです。
- 一人でコツコツ細かい作業をすることが得意→エンジニアになる
- 社交的で一つのことに集中すると力が発揮できる→営業職を希望する
- 黙々と数字を扱うのが得意→経理を目指す
- マルチタスクが苦手→マネージャーや総務職は避ける
- 周囲の音などが気になる→騒音が少ない会社や一人で作業できるスペースなどがある会社を選ぶ
- コツコツと作業することが得意だが具体的な職種が思いつかない→落ち着いた職場という条件から、不向きではない職種を探す
ステップ③業界研究
自己分析で向いてる仕事などが明確になった後は、その仕事に関連する職場・業界について、社風や働き方などが自分の性格・特性と一致するかどうかを検討しましょう。
特に発達障害のある人が働くためには、職場の雰囲気は重要です。例えば、雑談が苦手な人であれば、雑談が少ない職場を選んだ方が働きやすいはずです。
ほかにも、空気を読むことが求められない自由な空気感の職場の場合は、コミュニケーションが苦手という困難を避けられるでしょう。
また、職場の雰囲気以外にも、職場のルール・就労規則については、よく調べておきましょう。
発達障害のある人の中には、生活リズムが独特な人や感覚過敏が原因で満員電車に乗ることができない人などがいます。
そうした場合は、時差出勤やフレックスタイムが認められている会社や短時間勤務ができる会社など、自分の特性にあったルール・就労規則がある職場を検討するのもいいかもしれません。
加えて、以下の点についても確認しておくと、実際の職場の様子が想像しやすいと思います。
- 発達障害のある人の採用実績の有無
- 病気・障害のある人への配慮の実績の有無
ステップ④エントリー

発達障害のある人にとって、特にたくさんのエントリーを行う場合、複数のエントリーシートの作成、面接の準備、スケジュール管理などで困難を覚える可能性があります。
もし、発達障害のことを相手に開示した上で就活するオープン就労を検討している場合は、自分の特性のことや求めたい配慮、不調時の自己対策法について、適切に伝えられるように準備しておきましょう。
発達障害のある人が就活に際して、有効な対策やツール、練習法などはもちろんあります。当然、あなたの特性や職種などによっては、向き不向きはあるでしょう。
そんなときは、あなた一人のことをサポートする支援機関を利用して、あなたの就活を生活させるための具体的な方法を検討するようにしましょう。
発達障害のある人が就職を成功させるコツ22選
発達障害のある人が就職をうまく進めるためには、いくつかの工夫が必要です。
この章では、発達障害のある人が就職を成功させるコツについて解説します。
就職を成功させたい発達障害のある人は、この章で紹介するコツを実践してみてください。(参考:木津谷岳『これからの発達障害者「雇用」』、厚生労働省、NPO法人 ジョブコーチ・ネットワーク「発達障害者の就労相談 ハンドブック」、厚生労働省「発達障害の特性(代表例)」)
- コツ①発達障害の悩みをひとりで抱え込まない
- コツ②主治医に相談する
- コツ③カウンセラーに相談する
- コツ④二次障害がある場合は治療を優先する
- コツ⑤支援機関を利用する
- コツ⑥支援制度を利用する
- コツ⑦自分の特性を理解する
- コツ⑧特性をカバーする方法を身につける
- コツ⑨特性を活かす方法を考える
- コツ⑩経歴以外にアピールできる点を整理する
- コツ⑪生活習慣を整える
- コツ⑫リワークを利用する
- コツ⑬スキルを習得する
- コツ⑭雇用枠を検討する
- コツ⑮働き方を検討する
- コツ⑯雇用形態を検討する
- コツ⑰発達障害があることを開示するか検討する
- コツ⑱フリーランスとして働くことを検討する
- コツ⑲アルバイト・パートなどの非正規雇用で働き始めてみる
- コツ⑳就労継続支援A型/B型での就労する
- コツ㉑当事者会や相談会に参加する
- コツ㉒履歴書・職務経歴書・面接の対策をする
コツ①発達障害の悩みをひとりで抱え込まない

前提として、発達障害の悩みをひとりで抱え込まないようにしてください。
自力だけで解決しようとすると、良い案が思いつかず、さらにストレスを溜め込む場合があります。そうなると、就職の成功は遠のきます。
あなたの次の一歩を考える上で大切なことは、以下の2点です。
- 焦って結論を出さない
- 主治医や支援機関、専門家に相談をする
これから解説するとおり、発達障害のある人が就職を成功させるコツはたくさんあります。
まずは焦らず、医師やカウンセラー、専門家、支援機関などと相談してみてください。そうすることで、はじめて見つかる解決策もあるはずです。
そして、あなたの特性や困りごとを整理した上で、どのような仕事・働き方が向いてるのかを考えてみてください。
ぜひ、人の助けを借りながら進めてみてください。
コツ②主治医に相談する
発達障害のある人は、あなたの状況をよく知っている主治医に相談してから就職活動を始めることをオススメします。
継続的に診てくれている主治医であれば、あなたの特性や状態をチェックした上で、調子の波にあわせた適切なアドバイスをくれるはずです。
二次障害がある場合は休養や治療をすることが優先となります。あなただけで状態を判断せずに、就職活動を始める前に、必ず主治医と相談しながら就職活動に取り組むようにしてください。
二次障害がある場合については、こちらで解説します。
コツ③カウンセラーに相談する

医師による診察だけでなく、1時間などの単位でじっくり話を聴いてもらえるカウンセラーに相談するのも一つの手段です。
カウンセリングでは、健康面の悩みだけでなく、仕事に関する悩みにも相談でき、専門家の視点からのアドバイスを得られます。発達障害に伴う働けないという悩みに対しても、丁寧に耳を傾けてくれるでしょう。
相談するなかで、自分ではわかっていなかった悩みや、就職で優先したい条件が見えてくるかもしれません。
適切に医師やカウンセラーに相談しながら、就職活動を進めていくとよいでしょう。
どこに相談に行ったらいいのかわからないときは、日本臨床心理士会が運営している以下のWEBサイトで検索できます。ぜひ利用してみてください。
日本臨床心理士会「臨床心理士に出会うには」
コツ④二次障害がある場合は治療を優先する
発達障害の二次障害とは、発達障害や発達障害グレーゾーンの傾向・特性に伴って発生する精神障害やひきこもりなどの二次的な困難や問題のことです。(参考:齊藤万比古『発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート』、小栗正幸『発達障害児の思春期と二次障害予防のシナリオ』)
就職活動を行う前にまずは、二次障害があるかどうかを確認してください。二次障害がある場合、治療を優先して行ってください。
経済状況や環境によっては、就職に向けて焦る気持ちもあるかもしれません。しかし、焦って治療しないまま就職活動をすると、プレッシャーから、二次障害の症状・状態を悪化させるリスクがあります。
そもそも体調が就活・就職できる状態ではなかったり、選考結果で心身の調子を悪化させたり、大きなストレスを抱えたりする可能性もあります。ほかにも、就職活動への意欲が湧かなかったり、すぐに疲れたりする場合、それ自体が二次障害だったということもありえるでしょう。
二次障害のある状態で就職活動を行っても、本来の特性が見えづらいばかりか、就業前に体力を使い果たすこともあるため、就職を成功させることができません。
もし二次障害が発症しているならば、しっかり二次障害を治療して、安定して働ける状態まで回復することを優先してください。
自分の状態がわからないという人は、二次障害の有無を確認するためにも、医療機関に相談しましょう。
就職活動開始のタイミングは、主治医の意見を踏まえた上で、判断をしていくことが望ましいでしょう。
病院に行くことに抵抗がある場合は、ひとまず専門家や支援機関などに相談するのもよいでしょう。
発達障害の二次障害については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
コツ⑤支援機関を利用する
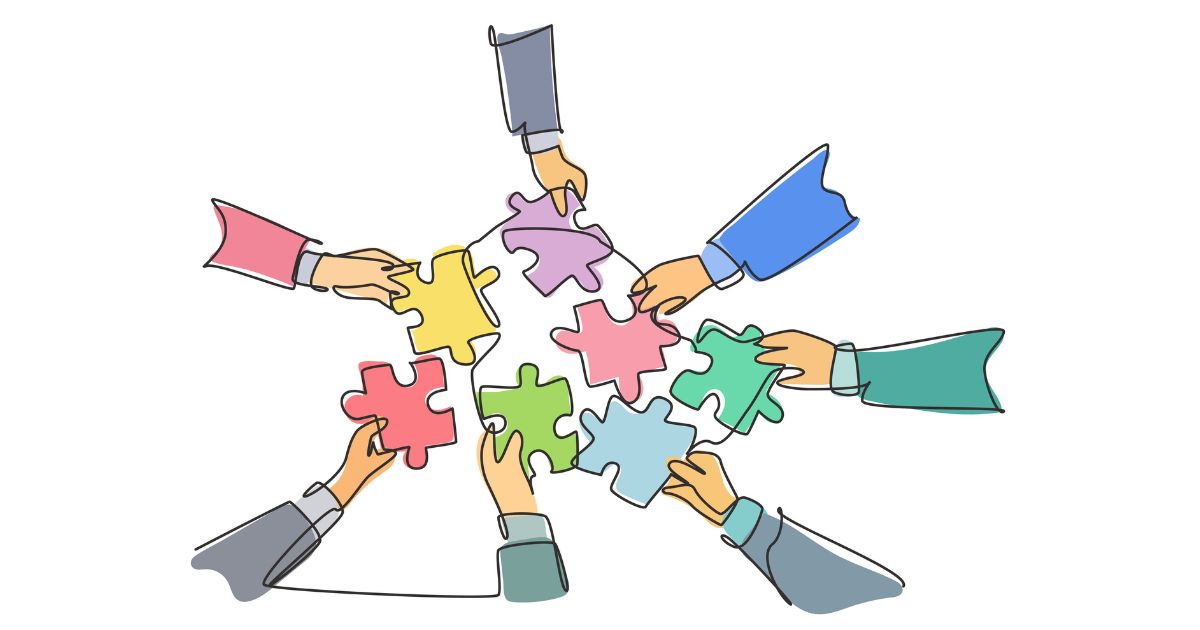
発達障害のある人が就職を成功させるためには、支援機関を利用することをオススメします。
発達障害のある人が就職活動を進めようとしても、なにから手をつけていいかわからないという状態に陥りがちです。
そういった場合、専門家や支援機関の客観的な意見が、あなたの就職活動の成功に役立つはずです。就職活動に関して悩んでいるのであれば、就労面のサポートに特化している支援機関を利用してみてください。
発達障害のある人の就労をサポートしている支援機関はたくさんあります。さまざまな事例を知る専門家の存在は、必ずやあなたの就職活動の支えとなるでしょう。発達障害グレーゾーンのある人でも相談可能な支援機関もあります。ご安心ください。
支援機関では、履歴書の書き方の指導や面接対策などの就職活動に直に結びつくサポートのほかに、向いてる仕事のアドバイス、仕事の紹介、インターンの斡旋など、就労に関するさまざまなサポートを受けられます。また、ほかにも、日常生活に関するサポート、メンタル面に関するサポートなどを受けられる可能性があります。
発達障害のある人の就労をサポートしてきた支援機関であれば、過去の事例を交えながら、あなたに合ったアドバイスをしてくれるはずです。あなた自身が気づいていない特性について理解し、あなたの可能性を広げることにつながるかもしれません。
特に、就職活動をしているのに就職先が決まらず、その原因が自分でもわからないまま、職歴のない状態が続いている人などは、支援機関に相談することで、一人では気付かなかった原因に思い至るケースが少なくありません。
自分のことを話すのは苦手、過去のことを話すのは恥ずかしい、などと思うかもしれませんが、自身のことを正直にお伝えするようにしましょう。どう話したらいいのかわからないというときは、そのことに正直に伝えてください。相手は相談を聞くプロです。あなたに合わせて聞き方なども変えてくれるはずです。
なお、支援機関ごとに理念は異なります。あなたとは相性が合わないことも考えられるため、そんなときも、自分のことを理解されないと落ち込まず、自分に合いそうな次の支援機関を探してください。
気になる支援機関があれば問い合わせましょう。どの支援機関が適切かわからないという場合は、主治医やお住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口、専門家などに相談してみてください。
発達障害のある人が利用できる支援機関については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
コツ⑥支援制度を利用する
就職活動が長期化することで、経済的な不安を抱える人もいるでしょう。
発達障害のある人も利用できる支援制度はたくさんあります。ご安心ください。
支援制度を利用することは、全く恥ずかしいことではありません。
支援制度を利用して経済的に安心することで、仕事復帰・仕事探しも含めて次の一歩にも進みやすくなります。
その点を心に留めながら、支援制度の利用を検討してみてください。
ただし、個々人の状況によって、支援制度の利用対象であるかどうか、どの程度の支援を受けられるかは異なります。
どの支援制度を利用できるかわからない人は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口やこちらで解説する支援機関に相談してみてください。
発達障害のある人が利用できる支援制度については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
コツ⑦自分の特性を理解する

発達障害のある人が働く上で特に重要なことは、自分の特性を理解することです。
発達障害のある人は、特性による向き・不向きや、得意・不得意が顕著に現れる傾向にあります。できないことについては、努力や工夫だけでは、どうしてもカバーできない面があります。
例えば、現在就労している仕事に対して、働きにくい、仕事が辛いと感じる場合、業務内容に自分の不得意な業務が含まれている可能性があります。
まずはあなた自身が、何ができて、何ができないか、何が得意で、何が苦手なのかなどの自分の特性に対する自己理解を深めてみてください。
自己分析をすることで、その特性にあった働きやすい仕事や職場、仕事術が見えてくるかもしれません。
自分の特性への理解が深まれば、面接や履歴書などで、あなたの特性をより詳しく知ってもらうための説明がうまくできるでしょう。また、就職した後も、業務内容や業務量について職場の人に相談する際に役立つはずです。
自分の特性を理解するために、紙に書き出してリスト化する方法が有効です。
以上の方法は、あなた自身の特性を客観的に整理できる上、何度も見返すことができるようになるためオススメです。LD/SLDの特性で紙に書き出すことが難しい場合は、サポートできるツールを利用してみてください。
また、特性を考える際には、あなたが普段感じていることのほかに、あなたのことをよく理解している家族や友人などの周囲の人から意見をもらうのも効果的です。
自分一人だけで考えるのではなく、家族や友人などの周囲の人、専門家、支援機関などに相談してみてください。
コツ⑧特性をカバーする方法を身につける
発達障害のある人が就職活動を成功させるためには、特性をカバーする方法を身につけることが大切です。
なんらかの特性があっても、うまくカバーできれば業務中の悩みや負担を減らせます。
例えば、ASDのある人であれば、仕事の予定をスケジュールに記載したり、やるべき仕事を一覧にしたりするのが効果的です。
ADHDのある人であれば、指示を紙でもらったり、仕事に必要なものをすべて鞄1つにまとめることでミスを減らせます。
あなたの特性に詳しい家族や友人など周囲の人や主治医、支援機関と協力して、特性をカバーできる習慣を見つけてみましょう。
コツ⑨特性を活かす方法を考える

9つ目のコツは、特性を活かす方法を考えることです。
特性を活かす方法を考える上で、前提となるのは、こちらで解説したとおり、自分の特性を理解することです。
そこからさらに、仕事に活かせそうな特性を考えてみてください。そうすることで、あなたにあった就職先が見えてくる可能性が高まります。
福島学院大学大学院教授の星野仁彦氏は、発達障害のある人が職人的なこだわりを仕事に活かせれば、発達障害のない人以上に素晴らしい業績が残せる可能性があると指摘しています。(参考:星野仁彦『発達障害に気づかない大人たち〈職場編〉』)
また、発達障害の人には向いてないとされる仕事でも、あなたの特性に向いてる仕事である可能性はもちろんあります。
自分の特性にあった仕事に就職できれば、仕事での成果を挙げやすいはずです。なにより特性を活かせる仕事が見つかれば、楽しみながら継続して働くことができるでしょう。
自分の強みやこだわりを仕事と結びつけられないか、考えてみてください。
コツ⑩経歴以外にアピールできる点を整理する
経歴以外にアピールできる点を整理することも、コツの1つです。特に職歴がない人の場合に有効です。
人事担当者は面接などの際、職務経験以外の要素からあなたの人柄を掴む手がかりを求めます。例えば、以下のようなものです。
- 学生時代に頑張ったことは何か
- 昔から継続して取り組んでいることはあるか
- 過去の失敗をどのように挽回したか・挽回しようと努力したか
些細なことでも構いません。経歴以外の過去の出来事を一度思いだして、整理してみるとよいでしょう。
具体的には、中学生のとき、高校生のときなど、時間に区切りを付けて、まずはその頃に何に取り組んでいたのかを書きだしてみてください。
もしかすると、あなた一人で思いだせることには限りがあるかもしれません。
その場合は、家族や友人などの周囲の人、主治医や支援機関などの助けを借りるのもよいでしょう。
学生時代から日記やブログを書き続けているなど、あなたの個人的な趣味・習慣であっても、他人の目から見れば、継続性があると解釈できる場合もあります。
ぜひ、過去の出来事や、あなたが続けていることなど、小さなことでも良いので書きだしてみてください。
コツ⑪生活習慣を整える

生活習慣を整えることも意識しましょう。
例えば、特定分野や関心のあることに強い集中力を発揮する過集中の傾向がある発達障害のある人の場合、時間を忘れて作業に没頭するため、気が付くと徹夜になり、生活リズムが乱れる場合があります。
ほかにも、就労や就学をしていない発達障害のある人の場合、昼夜逆転するなど、生活習慣が安定しづらい可能性もあるでしょう。
しかし、就職活動の選考・面接は、基本的には昼間に行われます。また、実際に就職したら日中の活動時間が多くなるでしょう。
そのため、日中のパフォーマンスを上げるためにも、まずは生活習慣を整えるように意識することが大切です。
コツ⑫リワークを利用する
就職・再就職を検討している人には、リワークを利用することをオススメします。
リワークとは、return to workの略で、病気や障害が原因で休職中の人を対象に行う、復職や転職、再就職に向けたリハビリテーションのことです。リワークプログラムと同じ意味で、復職支援プログラムや職場復帰支援プログラムという名称が使われることもあります。
リワークについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
コツ⑬スキルを習得する

仕事に結びつくスキルを習得することも、就職を成功させるコツの1つです。特に、いまの自分の能力に自信が持てないという人にオススメです。
例えば、職歴がない状態や働いていない状態が続いていて、仕事ができるかどうかわからないという人の場合、実践的な職業訓練・実習を行うことで、スキルや知識が基礎から身につくだけでなく、就職後のイメージもしやすくなるかもしれません。
スキルの習得は、就労移行支援事業所などの支援機関を利用するといいでしょう。
就労移行支援事業所などの支援機関では、一般的なビジネスマナーや文章作成などの基本スキル、簿記・会計・マーケティングなどの専門スキルを身につけるための講習などが受けられます。
また、職業能力開発訓練校のように、一日の時間割を組んであったり、学びの成果を発表するイベントを催したりと、一般的な学校と同様の形態を取っている支援機関もあります。
職業能力開発訓練校の場合、一般的な事務スキルやITに関する専門スキル、物流工程の知識や電気設備技術など、習得できるスキル・知識はさまざまです。
職業に結びつくスキルを身につけるための講習は、一回限りではなく、継続的に行う必要があります。定期的に通えば、生活リズムを整えられるというメリットもあるでしょう。
支援機関によっては、入門コースから始められるカリキュラムもあるため、あなたのペースにあわせて、スキルの習得を目指してみてください。
なお、職業訓練を受けるためには、ハローワークの窓口へ申し込む必要があります。
通える範囲に職業訓練校があるか、希望のコースを受けられるか、まずは確認してみてください。
また、お住まいの都道府県に設置されているハローワークでも、公共職業訓練への斡旋や、事業主と3か月の有期雇用契約を締結して働く障害者トライアル雇用を実施しています。気になる人はハローワークに確認してみましょう。(参考:厚生労働省「ハロートレーニング」)
コツ⑭雇用枠を検討する
雇用枠を検討することも重要です。
雇用枠には、大きくわけて、障害者雇用と一般雇用の2種類があります。
障害者雇用とは、障害のある人を対象とした雇用枠のことです。障害の特徴や内容に合わせて安心して働けるようにするため、いわゆる一般雇用とは就労条件が異なります。
一般雇用とは、障害者雇用以外の雇用枠のことです。障害の有無にかかわらず誰でも応募することが可能です。
発達障害のある人は、障害者雇用で就労することも可能です。
障害者雇用の場合、発達障害の特性に応じて、業務内容や業務量を調整してもらえるなど、特別な配慮を受けることが可能です。そのため、一般雇用での就労に比べて働きやすくなるかもしれません。
一般雇用から転職をして障害者雇用で就労したことで、快適に仕事できるようになったという発達障害のある人もいます。
対して、一般雇用の場合、一般的に障害者雇用よりも賃金水準が高く、就職先の選択肢が広いというメリットがあります。
障害者雇用と一般雇用は、絶対的にどちらがよいというものではありません。雇用枠を検討する際には、専門家や支援機関に相談しながら、慎重に判断してください。
障害者雇用については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
コツ⑮働き方を検討する
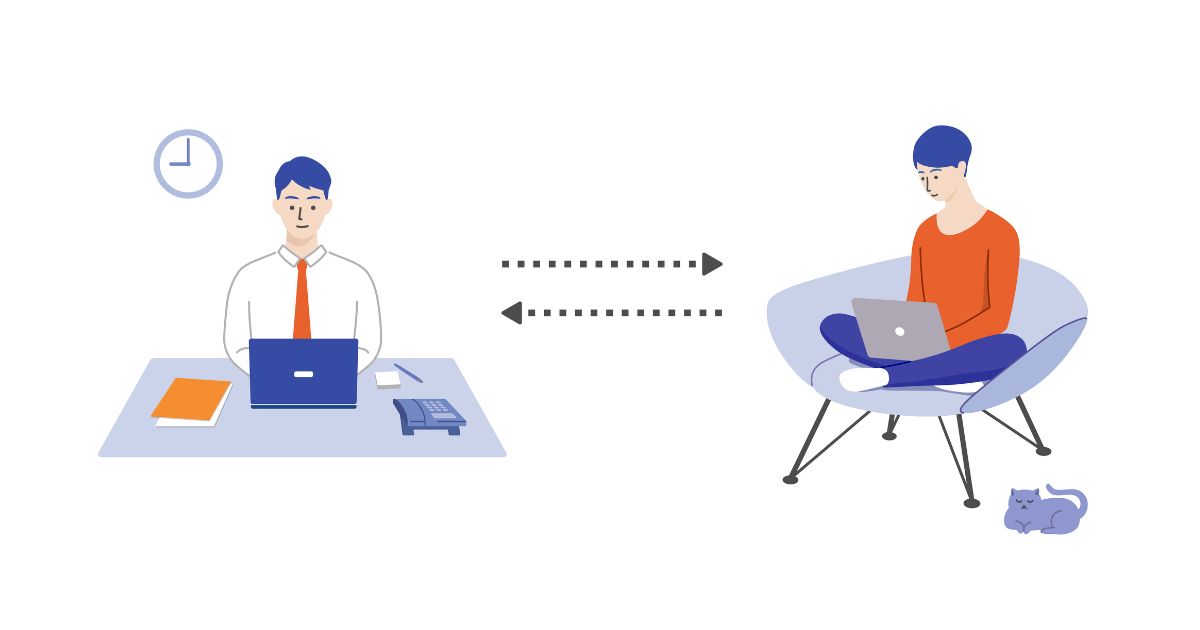
働き方が合っていないと、仕事自体が負担になり働き続けるのが難しくなります。
特性によっては、勤務時間に融通を利かせられるフレックス制や裁量労働制、リモートワーク、フリーランスの方が向いてるという人もいるでしょう。
発達障害の特性や程度、経済状況、生活と仕事の優先順位などを総合的に考えて判断することが大切です。
働き方には、それぞれ一長一短があります。
無理なく働き続けるためには、特定の職業や働き方にこだわりすぎず、特性や経済状況、向き不向きなどを総合的に考えて、主治医や支援機関などに相談しつつ、あなたが働きやすい方法を選択しましょう。
コツ⑯雇用形態を検討する
発達障害のある人に限らず、就職時には正規雇用か非正規雇用かのいずれかを選択する必要があります。
正規雇用とは、一般的に雇用期間や職務地などを定めずにフルタイムで勤務する雇用形態のことです。
非正規雇用とは、契約期間が決まっている雇用形態のことです。
正規雇用の場合、雇用状況や経済面が安定する点がメリットと言えます。その一方、責任が重くなる傾向にあります。
非正規雇用の場合、自身の生活を優先した自由度の高い働き方ができる点がメリットと言えます。一方で、正規雇用と比べると給与が低い傾向にあり、急に仕事がなくなるリスクがあります。
なお、一般的に、発達障害以外を含む障害のある人は非正規雇用が多い傾向があります。(参考:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」、厚生労働省「障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~」)
とはいえ、最初のうちは望まぬ非正規雇用だったとしても、安定的に働けると見なされて、正規雇用に転換するということもあります。
正規雇用と非正規雇用それぞれの特徴を把握し、自分に合った働き方を考えてみましょう。
コツ⑰発達障害があることを開示するか検討する

就職活動をするとき、発達障害があることを伝えるかどうか悩むことがあるかもしれません。また、雇用後に発達障害の診断を受けた場合も、職場に伝えるかどうか悩むでしょう。伝えるかどうかは、あなた自身で決めることができます。
就職活動・就労方法には、オープン就労とクローズ就労の2種類があります。
オープン就労とは、病気や障害などを開示して就職活動・就労をすることです。
クローズ就労とは、病気や障害などを開示せずに就職活動・就労をすることです。
オープン就労するメリットとデメリット・注意点、クローズ就労のメリットとデメリット・注意点はそれぞれ以下のとおりです。
- 業務内容や配属先への配慮を受けられる
- 病気や障害を開示できることによる安心感がある
- 就職先と支援機関の連携したサポートを受けられる
- その日の調子に合わせて勤務形態を変更しやすい
- 障害者雇用の場合、給与水準が比較的低い
- 障害者雇用の場合、求人数が比較的少ない
- 障害者雇用の場合、職種の選択肢が比較的少ない
- 給与水準が比較的高い
- 求人数や職種が豊富
- キャリアアップしやすい
- 発達障害への配慮を受けられない
- 病気や障害などを隠すことで不安が生じる
- 就職先と支援機関の連携したサポートを受けられない
オープン就労をする場合、障害者雇用の対象になります。障害のある人でも、個々の能力や特性に応じて、安定的に働けるようにすることを目的としています。
障害者雇用でオープン就労をする場合は、基本的に障害者手帳が必要です。障害者手帳の申請については、必要な書類として交付申請書と診断書用紙があります。お住まいの市町村の担当窓口に問い合わせてみてください。 なお、職場への発達障害の申告は、義務ではありません。
事業者が従業員の障害について把握できるのは、本人が自ら申告した場合と特別な職業上の必要性等がある場合に限られます。(参考:厚生労働省「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」)
採用後に発達障害があることが判明した場合でも、障害者雇用調整金や報奨金の申請などの手続きがなければ、申告の必要はありません。
オープン就労、クローズ就労については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
コツ⑱フリーランスとして働くことを検討する
発達障害のある人は、定時の勤務や通勤の困難さ、職場での人間関係の困難さなどから、就職にこだわらずフリーランスとして働くのもオススメです。
例えば、以下の仕事などはフリーランスでも働けます。
- Webライティング
- アプリの制作
- 翻訳
- デザイン
以上のスキルがある人、スキル獲得のために勉強できる人の場合は、フリーランスという働き方を選ぶことも一案です。
ただし、発達障害のある人がフリーランスとして働く場合も、メリットとデメリット・注意点があります。それぞれ意識するといいでしょう。
- 自分に合わない会社のルールなどに縛られずに好きなように働ける
- 定時の勤務が困難な人でも働ける
- 自己管理が求められる
- 苦手な作業でも自分で責任を持つ必要がある
コツ⑲アルバイト・パートなどの非正規雇用で働き始めてみる

発達障害の特性から働くことに難しさを感じている場合、いきなり正規雇用で働くことになると、どうしてもプレッシャーがかかります。自分を奮い立たせることはよいことではありますが、無理をして体調を壊す恐れもあります。
絶対に正規雇用で働くと気負わずに、まずはアルバイトから開始することで、働くこと自体に慣れていくというのも、有効な手段でしょう。
アルバイト・パートなどの非正規雇用で働くメリットとして、以下が考えられます。
- 正規雇用に比べて、採用されやすい
- 正規雇用に比べて、辞めやすい
- 興味のある仕事を掛け持ちしやすい
- 労働時間を調整しやすい
試しにアルバイト・パートとして働いてみることで、就労に慣れたり、あなたの得意・不得意、興味・関心が改めてわかったりすることもあるはずです。あなたに向いてる仕事やあなたに合った働き方などを確認する意味でも、アルバイトという選択肢は最適でしょう。
一定期間働けた実績や過去の作業経験があれば、就職活動の際のアピールにもなるはずです。
職場によっては、非正規雇用で就労するうちに実績が評価されて、正規雇用での就労への転換を打診されることがあるかもしれません。
万が一続けられなかったとしても、向いてない仕事や働き方がわかったことで、就職活動に役立つでしょう。向いてない仕事がわかったとポジティブに捉えてみてください。
発達障害のある人に向いてるアルバイトについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
コツ⑳就労継続支援A型/B型での就労する
就労継続支援A型/B型とは、一般企業での就労が難しい人に対して、実業務の機会やスキルアップのための職業訓練を提供する支援のことです。
A型とB型の違いは雇用契約と年齢制限の有無であり、利用者の障害に差はありません。
雇用契約がある、65歳未満を対象としたA型のほうが賃金が高い傾向があります。
一般企業への就職が難しい人や、支援を受けながら働きたい人は、就労継続支援事業所での就労も考えてみてください。
就労継続支援A型/B型については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
コツ㉑当事者会や相談会に参加する

最後のコツは、当事者会や相談会に参加することです。
近年、支援機関やSNSなどで出会った発達障害のある人同士が、自助グループを結成したり、地域の当事者会・相談会を開催したりして、活動することが増えてきています。
2019年7月には、東京都の発達障害者会が東京都発達障害当事者会ネット(TTN)を発足したことでも話題になりました。
このような発達障害の当事者会や相談会では、さまざまな背景のある発達障害のある人が集まるため、自分と似た境遇の人と情報共有できる機会も持てるかもしれません。
ただし、当事者会は、特性や症状などに分け隔てなく、発達障害として一括りにされている場合があります。
そういった場合、当事者会の中に進行役などがいないと、なかなか意見が合わない、コミュニケーションがスムーズに進まないといったこともあるそうです。
もし参加される場合は事前に、何を目的にした会なのか、その会にはどのような特性がある人が多く集まるのかなど、事前にしっかりと確認した上で、参加することをオススメします。
コツ㉒履歴書・職務経歴書・面接の対策をする
履歴書・職務経歴書・面接の対策も就職を成功させるカギになります。(参考:厚生労働省「就職活動に困難な課題を抱える障害のある学生等への就職支援」)
事前に履歴書や職務経歴書を作り込み、面接の練習をしておけば、なぜこの仕事をしたいのか、どんな部分を配慮してほしいのか、などについてうまく伝えられます。
特に障害者雇用での就職を希望する人や、職場に障害があることを伝えて就労したい人の場合、自分の特性や配慮してほしいことを相手に伝わるように説明することが求められます。
1人では対策が難しいと感じる人に対して、サポートしてくれる支援機関は多数あるので安心してください。
発達障害のある人の就活成功体験談3選
この章では、発達障害のある人の就活成功体験談を紹介します。
あわせて、フリーランスとして働き始めた発達障害のある人の体験談も紹介します。
体験談①自己分析や特性理解を徹底的にしたことでメーカーの内定を獲得

小学生のときに発達障害の診断を受けたEさん。
ご両親はEさんの進路に不安があったそうですが、大学は商学部に進学しました。
数字に強いEさんは、ITスキルにも自信があったため、大学では簿記とITの勉強に力を入れていたそうです。
自分の強みを育てつつ、大学のキャリアセンターを利用しながら、自己分析や特性理解を徹底的に行ったことで、Eさんは就活時の面接で、できることとできないことを整理して伝えることができました。
その結果、障害者雇用でメーカーの内定を獲得。経理関係の部署にて、今も充実した社会人生活を送っています。
体験談②自分の強みを活かしてIT企業のプログラマーとして就職
小さいころからプログラミングが大好きだったFさんは、中学生のころに発達障害の診断を受けました。
人とのコミュニケーションが苦手なFさんは、プログラミング能力を活かして働くことを考え、大学時代からスマホアプリを自主的に製作したり、ITベンチャー企業でインターンシップを重ねたりして、大学生活を送りました。
就活では、コミュニケーション能力ではなく制作物を評価する社風のIT企業にエントリーしました。そこで、それまでに開発したアプリが高く評価され、IT企業のプログラマーとして一般雇用で就職することが決まりました。
Fさんは、現在もさまざまなアプリなどの開発に携わっています。
体験談③ストレスを減らすためフリーランスのエンジニアへ

Gさんは、小さいころからプログラミングが得意でした。学生時代から自作でアプリを開発した経験もあります。
ただし、発達障害の特性から睡眠障害や感覚過敏などがあったため、IT部門に就職した会社についても日々の勤務に困難がありました。
そこで、会社を退職し、フリーランスのエンジニアとしてキャリアをスタート。自宅でアプリ開発やウェブ開発に参加するように働き方を変えました。
収入としては大きな変動がないのですが、ストレスが大きく減り、それまでよりもずっと楽に過ごせるようになっています。
一方、経理や税金面の仕事は苦手なので、友人の経理経験者や家族に依頼することで支えてもらっています。
発達障害のある人の就活失敗体験談2選
この章では、発達障害のある人の就活失敗体験談を紹介します。
体験談①自分のことをうまく伝えられず就活に失敗

テレビで放映されているアニメをすべて録画し、アニメ雑誌を読み込むほどにアニメが大好きなAさんは、勉強が非常に得意で、苦労することなく都内の有名大学の法学部に入学しました。
声優の声をすぐに聞き分けられるほど、アニメを愛しているAさん。大学在学中は、オタク活動にのめり込み、歌手としても活躍する声優のコンサートに参加すべく、日本全国を巡る日々を送っていたそうです。
Aさんは聴覚過敏があり、外界からの刺激に敏感でした。そのため、ときには定期的に家に引きこもることがあったそうです。しかし、勉強面での困り感はなく、大学卒業に必要な単位も難なく取得し、問題なく大学生活を謳歌していました。
そんなAさんでも、就活はうまくいきませんでした。
自分の気持ちやしたいことを伝えることが苦手だったAさんは、面接で自分のことをうまく伝えられず、さまざまな企業の面接担当者から「何を考えているかわからない」と言われることが多かったのです。そうして、採用試験に落ちる日々が続きました。
100社以上の就活を経て、やっとの思いでIT企業に入社したAさんでしたが、今度は職場の人とうまくコミュニケーションがとれず、結局退社することになったのです。
体験談②計画的な行動が苦手で就活が難航
とにかく何でも挑戦してみるBさんはスポーツが大好きで、大学在学中には世界中をバックパッカーするようなアクティブさがありました。
思いつきで次から次へと行動をしたり、議論が大好きでどんなこともストレートに伝えたりする面があるBさん。大学時代にも、サークル活動に夢中になりすぎて単位を大量に落とし、留年寸前になったこともあったそうです。
とはいえ、就活を始めるまでは、特性が原因で大きな問題になることはありませんでした。
そんなBさんも、就活になると、ADHDとASDの特性に影響を受けるようになりました。膨大なエントリーシートの作成、説明会や面接のスケジュール管理、SPI試験に向けた勉強、面接での受け答え…。
計画を立てて段取りを組んで行動することが大の苦手であるという特性、ものをはっきり言うという特性が、そうした就活の内容に不向きだったのです。
就活を続けたBさんですが、膨大なエントリーシートの処理が間に合わなかったり、面接の時間に遅刻したり、面接会場に向かう道中で迷子になったり、面接担当者と大喧嘩したり、話がかみ合わなかったり…。そうしたことが続き、結果として就活に失敗しました。
アクティブな行動力と自由な発想を持つBさんは、周囲の人から「ベンチャー企業やクリエイティブな会社があいそう」と言われていました。
それにも関わらず、ADHDのある人には不向きと言われる正確性が重要な金融業界を中心に受けたことも、失敗の一因だったのかもしれません。
発達障害のある人の就職に関するよくある質問4選
この章では、発達障害のある人の就職に関するよくある質問を紹介します。
同じ疑問を持っている場合は、ここで一緒に解消しておきましょう。
Q1.発達障害があると就職はできない?
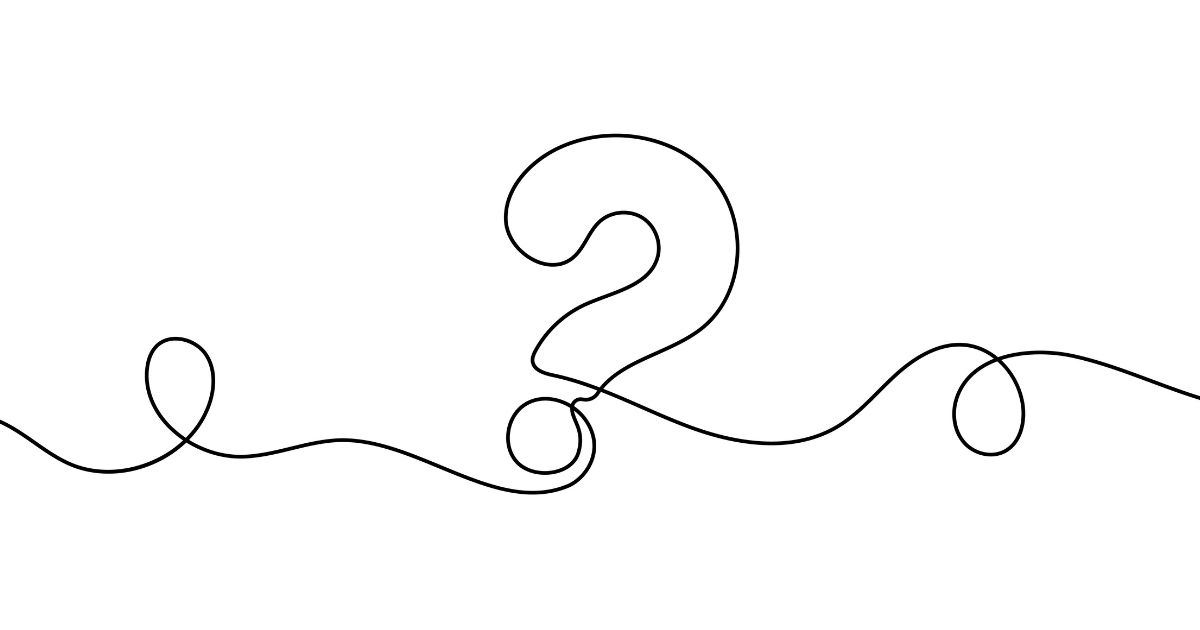
簡単ではありませんが、就職はできます。
厚生労働省の発表によると、民間企業における発達障害のある人の雇用数は、年々増加傾向です。(参考:厚生労働省「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」)
また、障害者職業総合センターの調査によると、発達障害のある人はほかの障害がある人に比べて、職場定着率が高いようです。(参考:障害者職業総合センター「障害者求人により就職した障害者の職場定着状況等」)
発達障害のある人も、十分に就職できる可能性はあります。最初から諦めるのではなく、まずは就労移行支援事業所などに相談してみましょう。
Q2.障害者雇用での就職と一般雇用での就職は何が違う?
障害者雇用の場合、一般雇用より適切な配慮を受けられます。
対して、一般雇用は職業の幅が広く、給料が高い傾向があります。
それぞれメリットとデメリット・注意点があるため、あなたの状況などにあわせて検討しましょう。あなたに適している雇用形態については、就労支援を行っている支援機関に相談してみてください。
障害者雇用については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
Q3.発達障害があることを職場へ伝えた方がいい?

基本的には本人の自由なので、どちらでも大丈夫です。
職場によっては、発達障害があることを伝えておいた方が、業務内容やコミュニケーションの方法などに関する配慮を受けられるため、働きやすくなるでしょう。
オープン就労とクローズ就労では、それぞれメリットとデメリット・注意点があるため、あなたの状況などにあわせて検討しましょう。
職場に発達障害があることを伝えるか悩んでいる場合は、支援機関に相談してみてもよいかもしれません。
オープン就労とクローズ就労については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
Q4.発達障害グレーゾーンと言われましたが、発達障害のある人と同様に支援機関を利用できますか?
発達障害グレーゾーンのある人でも利用できる支援機関はあります。
利用の可否は、発達障害グレーゾーンであるかどうかよりも、現在の状況がどうかという観点で判断されることもあります。
利用したい支援機関がある場合、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口や支援機関に相談してみましょう。
仮に希望する支援機関を利用できない場合でも、利用可能なほかの支援機関を紹介されることもあります。
発達障害グレーゾーンについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)
発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。
- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)
- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)
- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)
同じ診断名でも、人によって多様な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人は、ほかの発達障害が併存している可能性もあります。
発達障害の概要や種類、原因、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
【無料配布中!】ASD×仕事 実践ガイドブック
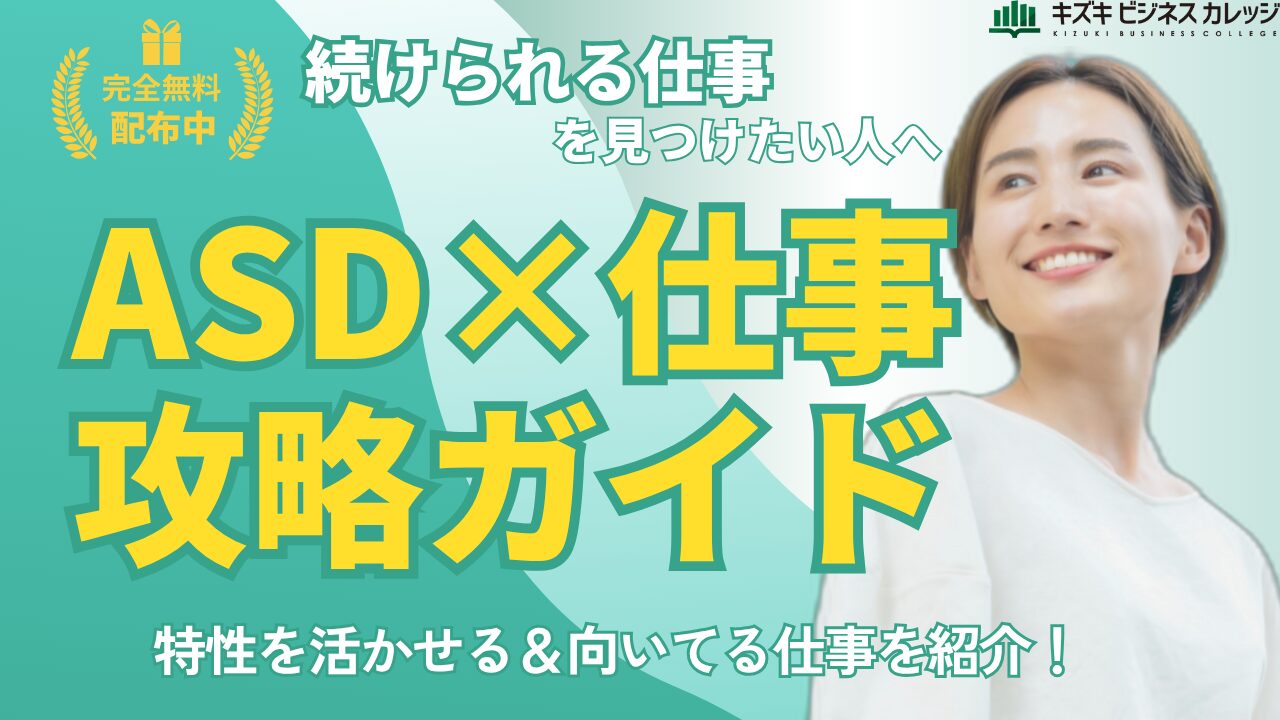
- 職場の人とうまくやっていけない
- 感覚過敏でオフィス環境がつらい
- こだわりが強すぎてつかれる…
このように、ASDの特性ゆえに仕事に関する悩みを抱える人は少なくありません。
ASDのある人は、対人関係や感覚処理、物事へのこだわりの強さなど、特有の認知や行動パターンを持つため、一般的な働き方や職場のルールに適応しづらいことがあるためです。
また、自分に合った職場や働き方を見つけられず、「長く続けられる仕事が見つからない…」と悩む人も多くいらっしゃいます。
さらに、今の職場や働き方に合わせようと無理をして、特性に合わない働き方を続けた結果、ストレスの蓄積から体調不良やうつ病などの二次障害につながることもあります。
そのため、ぜひ本ガイドブックでASDのある人に向いてる仕事や仕事選びの視点を知り、今のあなたに合った仕事を見つけていきましょう。
- ASDとは?
- ASDの特性が仕事に影響するポイント
- 向いてる仕事(具体的な職種例)
- 仕事選びで意識したい3つの視点(環境/業務内容/サポート体制)
- 正社員以外の働き方や支援機関の利用などの選択肢
- 向いてる仕事を見つけるためのチェックリスト
- ASDの診断を受けており、仕事選びに悩んでいる人
- 働き始めたものの、人間関係や業務がつらく長続きしない人
- 自分の特性に合った仕事を見つけたい人
- 就労支援を検討しているが、まずは情報を集めたい人
- 支援者・家族として、当事者の就労をサポートしたい人
- リンクから申し込みフォームにアクセス
- 簡単なフォームに入力
- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り
- URLから資料を取得!
- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。
- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。
- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。
また、ASDのある人に向いてる仕事については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ:自分にあった就活をすることは可能です

就活に成功しても、就職後に働き続けるにしても、発達障害のある人に困難が起こりえることは否定しません。
しかし、その困難をカバーして、自分にあった就活をすることは可能です。
あなた一人だけで就活をがんばるのではなく、専門家や支援機関に相談しながらすすめてみてください。
発達障害のある人が就活を成功させるステップを教えてください。
発達障害のある人が就職を成功させるコツはありますか?
以下が考えられます。
- 発達障害の悩みをひとりで抱え込まない
- 主治医に相談する
- カウンセラーに相談する
- 二次障害がある場合は治療を優先する
- 支援機関を利用する
- 支援制度を利用する
- 自分の特性を理解する
- 特性をカバーする方法を身につける
- 特性を活かす方法を考える
- 経歴以外にアピールできる点を整理する
- 生活習慣を整える
- リワークを利用する
- スキルを習得する
- 雇用枠を検討する
- 働き方を検討する
- 雇用形態を検討する
- 発達障害があることを開示するか検討する
- フリーランスとして働くことを検討する
- アルバイト・パートなどの非正規雇用で働き始めてみる
- 就労継続支援A型/B型での就労する
- 当事者会や相談会に参加する
- 履歴書・職務経歴書・面接の対策をする
詳細については、こちらで解説しています。
監修志村哲祥
しむら・あきよし。
医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。
臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。
【著書など(一部)】
『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』
他、学術論文多数
日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧
時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
監修角南百合子
すなみ・ゆりこ。
臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→