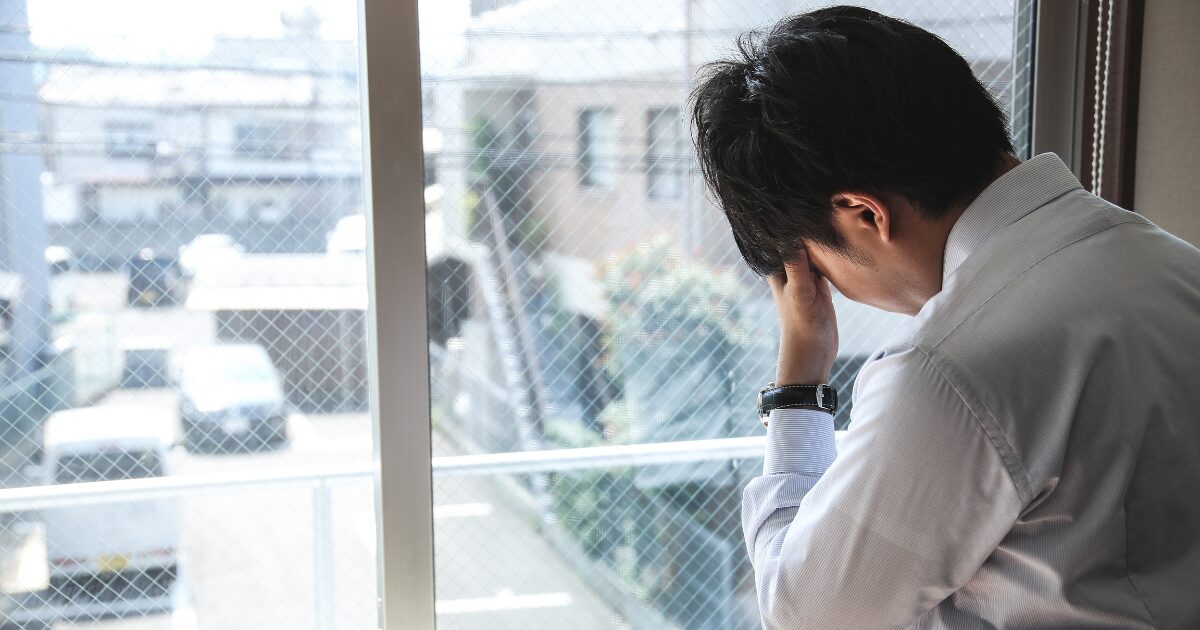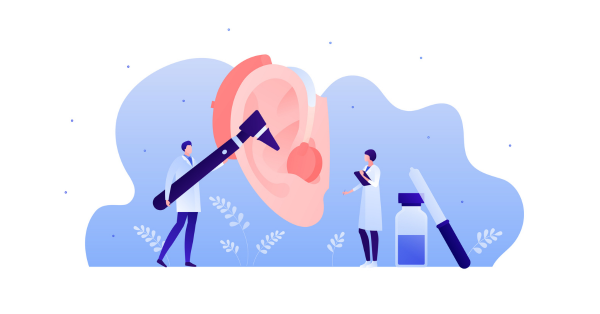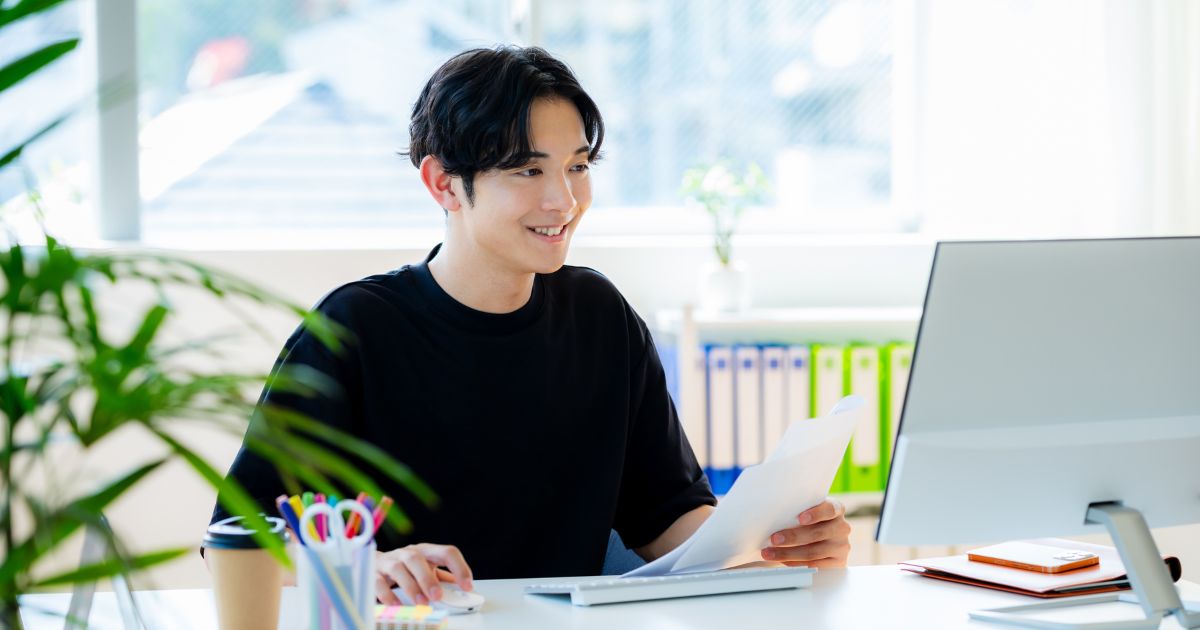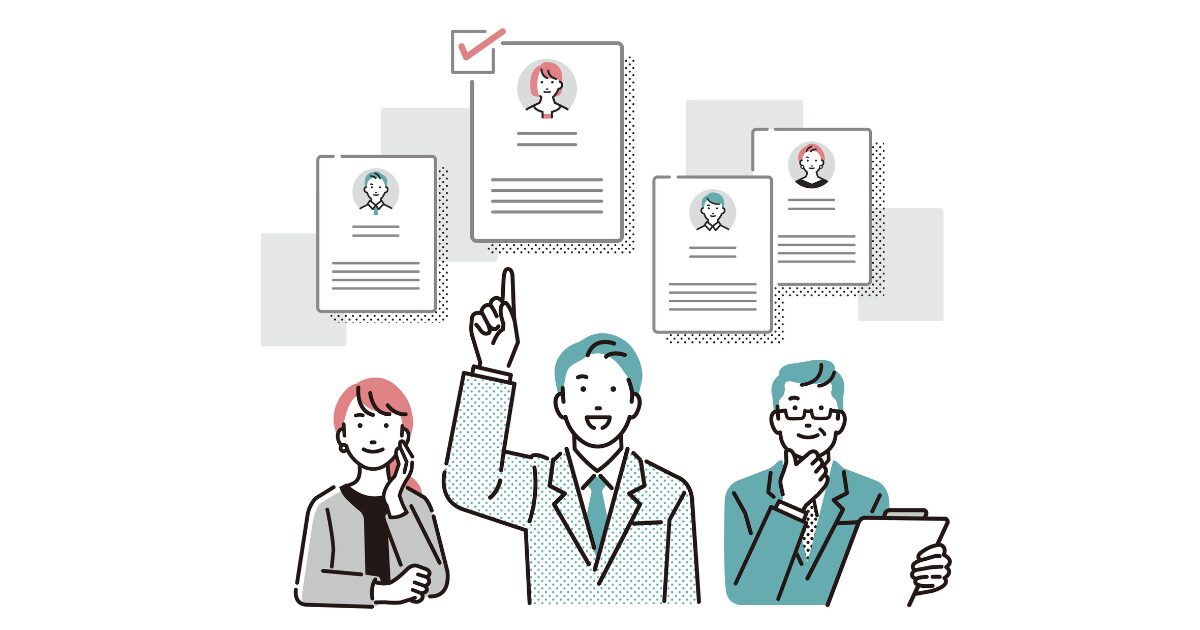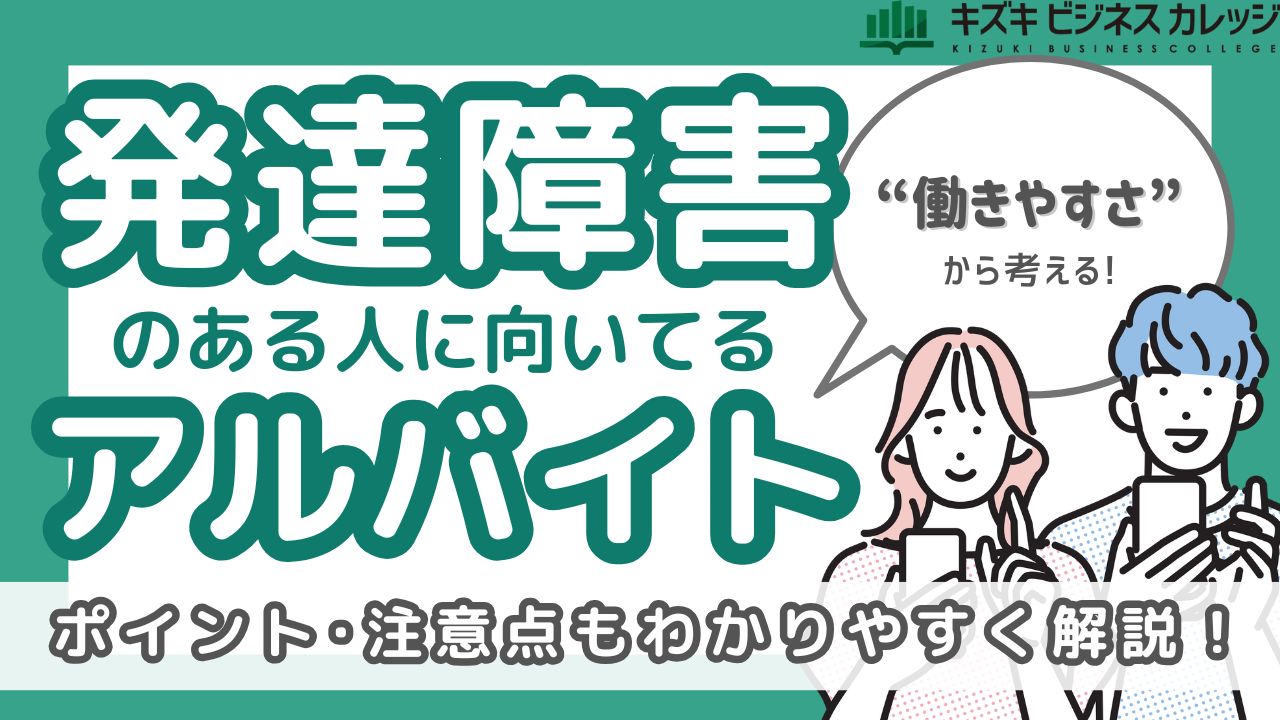発達障害がある人がなりやすい過剰適応とは? 対処法も解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
発達障害のあるあなたは過剰適応という言葉を聞いた経験があるのではないでしょうか?
しかし、過剰適応とは何なのか、どう注意すればよいのかなど、具体的なイメージが掴めずに困惑している人もいるかもしれません。
このコラムでは、過剰適応の概要や過剰適応を理解するポイント、発達障害と過剰適応の関係などについて解説します。
過剰適応について理解を深め、自身の障害とよりよい付き合い方をしていきたい人は、ぜひご覧ください。
さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、発達障害の特性によるストレスに悩む人に向けて、発達障害の特性に合わせた『"発達障害"特化型ストレス対策ハンドブック』を無料配布を開始いたしました。
ストレスの原因を特性との関係から丁寧に解説し、気づきを得られる自己診断チェックリストを掲載。すぐに使える対処法を一冊にまとめています。
ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。
また、発達障害の特性によるストレスへの対処法については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。
過剰適応にお悩みのあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
過剰適応とは?

発達障害のある人は、職場になじむためにより多くの努力を必要とする人が多いと思います。それを過剰適応と呼びます。(参考:障害者職業総合センター「就業経験のある発達障害者の職業上のストレスに関する研究-職場不適応の発生過程と背景要因の検討-」)
過剰適応とは、周囲の期待や要求へ応えようとして、必要以上に努力をしている状態を指します。(参考:風間惇希「大学生における過剰適応と抑うつの関連」)
社会生活を送るうえで、円滑なコミュニケーションを取る努力は必要です。しかし、それが行き過ぎて無理をしている状態が続くと、過剰適応になります。
過剰適応時の具体的な反応としては、以下のようなケースが確認されています。
- 興味が持てないことにも興味を持ったように振る舞い、ストレスを抱える
- 本当はやりたくない仕事も、周囲の期待に応えようとして取り組む
- 上司・同僚などからの要求だからと、理不尽な内容でも応える
- 本音と建前を使うコミュニケーションは苦手だけれど、職務上必要とされるから意識してコミュニケーションを取る
- 同僚と協力してひとつの仕事をこなさないといけないが、自分がケアレスミスをして足を引っ張らないように常に意識を張り巡らせている
以上のように、特性を補うために努力した行動が、過度な負担・ストレスとなる可能性があります。
外的適応と内的適応とは?
過剰適応は、外的適応と内的適応のバランスが崩れることで引き起こされます。(参考:J-STAGE「大学生における過剰適応と抑うつの関連――自他の認識を背景要因とした新たな過剰適応の構造を仮定して――」 )
外的適応とは、社会的な功績の達成、他者からの期待・要求に応える行為など、社会や文化への適応のことです。
内的適応とは、安心感や満足感といった自分の気持ちに応える行為などの自己の内面への適応のことです。
したがって、過剰適応は、周囲との付き合い=外的適応が自分の気持ち=内的適応よりも強く働くことで、他人優先の行動が顕著になっている状態といえます。
過剰適応にならないためには、外的適応・内的適応のバランスを取れるよう、意識して行動することが大切です。
発達障害の過剰適応の5つの原因

2011年に実施された調査では、過剰適応になる場合、以下に挙げる5つの傾向が関係していることがわかっています。(参考:J-STAGE「大学生における過剰適応と抑うつの関係――自他の認識を背景要因とした新たな過剰適応の構造を仮定して――」)
- 自己抑制:自分の考えや感情を、他人に伝えない
- 自己不全感:自分の評判が良くないと感じる。自信を持てない
- 他者配慮:自分が我慢すればいいと思う。自分が多少困ったとしても、他人のために何かする
- 期待に沿う努力:他人からの期待を敏感に感じ取り、応えようとする
- 良く思われようとする行動:他人から嫌われないように、あるいは気に入られるように行動する
このような傾向が強くなったと感じたときには、注意が必要です。負担がかかっていることを把握し、自分の気持ちを見つめなおすとともに、リフレッシュするための時間を設けるようにしましょう。
発達障害(ASD・ADHD)と過剰適応の関係
この章では、発達障害(ASD・ADHD)と過剰適応の関係について解説します。
発達障害と過剰適応の関連性

2020年に実施された知的障害と過剰適応に関する調査にて、発達障害と過剰適応の関連性も取り上げられています。(参考:東京学芸大学リポジトリ「知的障害のある中学・高等部生徒の過剰適応に関する全国調査」)
発達障害の障害種別で見ると、とくに、ASD(自閉症スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)のある人は過剰適応になりやすいことがわかります。
次いで、ADHD(注意欠如・多動性障害)のある人も、過剰適応になりやすい傾向が確認されました。
- ASD:162人、約48.9%
- ADHD:53人、約16.0%
- LD/SLD:9人、約2.7%
また知的障害がある人における、程度別の割合は以下のとおりとなっています。
- なし・境界域:58人、約17.5%
- 軽度:157人、約47.4%
- 中度:59人、約17.8%
- 重度:12人、約3.6%
- そのほか・不明:45人、約13.6%
重度の障害がある人よりも軽度の障害のある人のほうが、過剰適応を起こしやすい傾向にあることがわかります。
発達障害のある人が過剰適応しやすい要因
同調査では、知的障害がある人に顕著な過剰適応反応として、以下の傾向が認められました。(参考:東京学芸大学リポジトリ「知的障害のある中学・高等部生徒の過剰適応に関する全国調査」)
- 自分の能力を超えた課題に取り組む
- ストレス状態にあることを認識しないまま、無理を続ける
- 他者へ向けて過剰に努力し、自分自身に大きな負荷を課す
発達障害のある人は、社会に適応しようとするなかで、特性にともなう問題が生じないように努力をしすぎている可能性が考えられるでしょう。
結果として問題なく社会生活を送れているように見えても、本人からすれば、無理を続けてかろうじて実現できている状態という可能性もあります。
発達障害のある人が過剰適応にならないためには、一人で無理をせず、周囲を頼ることも大切なことを覚えておきましょう。
過剰適応を放置するとどうなる?

過剰適応になっていることに気付かずに無理をし続けると、二次障害を引き起こす可能性があります。
二次障害とは、主障害に起因して起こる副次的な障害のことです。ここで取り上げている発達障害の二次障害とは、発達障害や発達障害グレーゾーンの傾向・特性に伴って発生する精神障害やひきこもりなどの二次的な困難や問題のことを指します。(参考:齊藤万比古『発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート』、小栗正幸『発達障害児の思春期と二次障害予防のシナリオ』)
例えば、過剰適応によってストレス・疲労が蓄積されたり、理想と現実の違いから自己肯定感が下がったりする可能性があります。そうした状態を放置すれば、抑うつ症状、うつ病、適応障害を引き起こす可能性が高まるでしょう。
特に、男性では自己抑制と自己不全感が、女性では自己不全感が、それぞれ抑うつ症状の発症と関係することがわかっています。(参考:J-STAGE「大学生における過剰適応と抑うつの関係――自他の認識を背景要因とした新たな過剰適応の構造を仮定して――」)
さらに、過剰適応を放置することで、以下のようなストレス性疾患が生じる可能性もあります。(参考:こころの耳「2 ストレスからくる病」)
- 過換気症候群
- 筋収縮性頭痛
- メニエール病
- アトピー性皮膚炎
- 過敏性腸症候群
- 顎関節症
こうした病気に関する情報は以下のコラムでまとめています。気になる症状がある人は、あわせて確認しておきましょう。
発達障害による過剰適応への対処法4選
この章では、発達障害による過剰適応への対処法について解説します。
対処法①コンディションを確認する
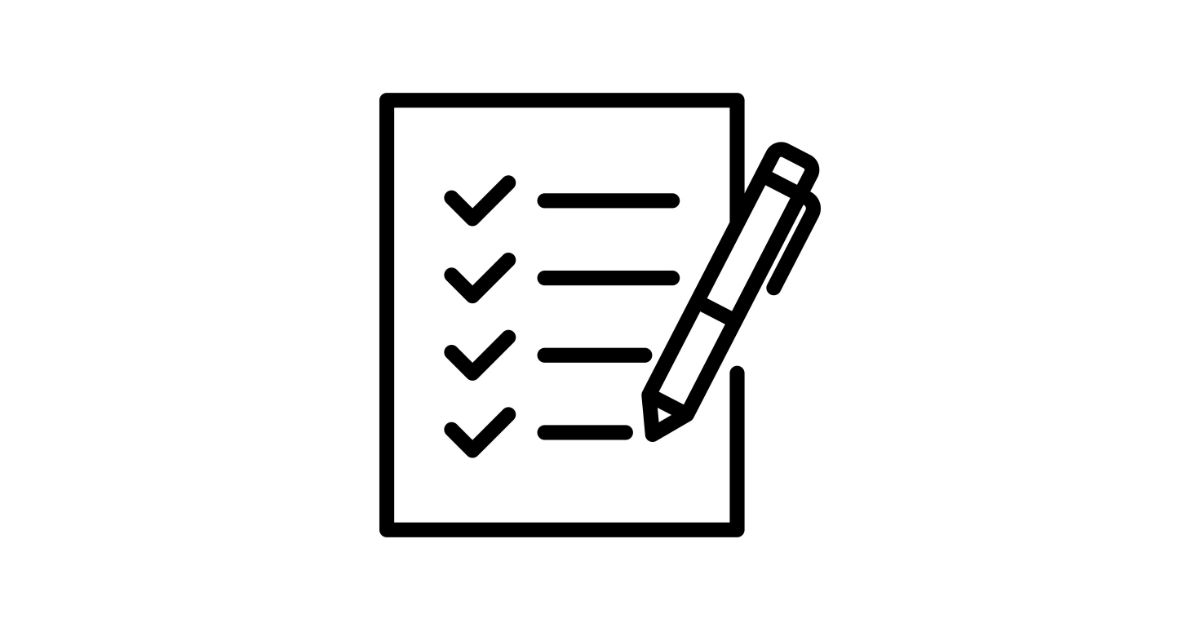
過剰適応は、本人が気付かないうちに深刻化する傾向があります。
そのため、日々または定期的にコンディションを確認し、異常があれば早めに気付けるように心がけることも大切です。
具体的な方法として、以下の項目についてチェックしておくとよいでしょう。
- 日々の睡眠時間や、睡眠の質などを記録する
- 食欲の有無、食事の量などを記録する
- 趣味・リフレッシュの時間を確保できているか、楽しめているかを記録する
ただし発達障害のある人のなかには、記録付けが苦手な人も少なくありません。それぞれを自分自身で評価して記録するのもよいですが、大変だと感じるときには、以下の手段を試してみるのもよいでしょう。
- 睡眠の質を計測するアプリケーションを利用する
- ストレス計測機能が搭載されたデバイスを利用する
- 定期的にストレスのセルフチェックをする
ストレスチェックは、厚生労働省と一般社団法人日本産業カウンセラー協会が運営するポータルサイト「こころの耳」で提供されています。
「疲労蓄積度セルフチェック2023(働く方用)」は約5分でできるため、利用を検討してみましょう。(参考:こころの耳)
対処法②自分のことを周囲へ伝える練習をする
過剰適応になっていても、他者から見れば問題なく生活できているように見えて、問題が発覚しにくい傾向にあります。
そのため、自分自身の状態をきちんと伝えられるように、練習をしておくのがよいでしょう。
例えば、相手に配慮をしながら自分の意見も表現するコミュニケーション方法として、アサーションがあります。
アサーションとは、相手の立場・考え方・価値観などへ配慮しながらも、自身の意見・主張も適切に伝えるコミュニケーションスキルのことです。
そうしたコミュニケーション方法を実行するためにはどうすればよいのか、重要なポイントを知っておくと、過剰適応を防ぐために役立つでしょう。
コミュニケーションスキルの練習・習得は、発達障害がある人を対象にした支援機関でサポートしています。一度、近隣にある支援機関のサポート内容を確認してみましょう。
対処法③適したストレス発散方法を見つける

ストレスを溜め込みすぎないよう、自分自身に合うストレス発散方法を見つけておくことも大切です。発達障害のある人は、以下の理由によってとくにストレスを感じやすい傾向にあります。
- 環境に合わせるために努力をしている
- 感覚過敏がある
- 過集中や衝動性によってエネルギーを消費している
日々ストレスが溜まるため、意識してストレス発散をしておくことが大切です。発達障害のある人がストレスを発散する方法は以下のコラムで解説しています。あわせて確認しておきましょう。
対処法④支援機関を利用する
障害のある人を対象にした支援機関を利用して、ストレスを軽減するトレーニングに取り組むのも、大切な対処法のひとつです。
支援機関には以下のような場所があり、ソーシャルスキルトレーニングやコミュニケーションスキル向上の取り組みができる場合があります。(参考:厚生労働省「令和3年度 厚生労働省 発達障害者支援施策について」、厚生労働省「発達障害の理解」)
- 就労移行支援事業所
- ハローワーク
- 発達障害者支援センター
- 障害者就業・地域生活支援センター
各支援機関に関しては以下のコラムで解説しているため、利用を検討したい人はあわせて確認しておきましょう。
発達障害による過剰適応がある人が仕事を続けるコツ
この章では、発達障害による過剰適応がある人が仕事が仕事を続けるコツについて解説します。
コツ①苦手なことは意識して伝える

発達障害のある人には、以下の傾向があることはすでに取り上げたとおりです。(参考:東京学芸大学リポジトリ「知的障害のある中学・高等部生徒の過剰適応に関する全国調査」言)
- 自分の能力を超えた課題に取り組む
- ストレス状態にあることを認識しないまま無理を続ける
- 他者へ向けて過剰に努力し、自分自身に大きな負荷を課す
そのため、苦手なことはきちんと伝え、努力しすぎないようにすることが大切です。
もしかしたら、あなたが苦手な仕事はほかの人にとって得意・好きな仕事かもしれません。あるいは、みんな苦手なら分担してできるよう協力してくれる可能性もあります。
自分にとってどのようなことに苦手意識を抱くのか、周囲に知ってもらうようにしましょう。
コツ②自分を責めすぎないよう意識する
発達障害のある人が過剰適応になる要因のひとつとして、自信の無さや低さがあります。
また、過剰適応に関する全国調査では、過剰適応における具体的な様子として、完璧主義があることも指摘されました。(参考:東京学芸大学リポジトリ「知的障害のある中学・高等部生徒の過剰適応に関する全国調査」)
完璧主義とは、さまざまな物事に高い目標を設定して、その達成に向けて行動する姿勢を指す言葉です。また、そのような姿勢の人物を完璧主義者といいます。(参考:中野敬子、臼田倫美、中村有里『完璧主義の適応的構成要素と精神的健康の関係』)
注意していても、失敗やミスがあるのはだれしも同じです。常に完璧を追求するのではなく、失敗するときもあることを受け入れ、自分を責めすぎないようにすることが大切です。
【無料配布】”発達障害”特化型 ストレス対策ハンドブック

- 仕事がしんどい…
- もう出社したくない…
そんな気持ちを抱えながら、仕事を続けていませんか?
発達障害のある人は、仕事や日常生活で特有のストレスを感じやすいことがあります。マルチタスクが苦手、感覚過敏、過集中による疲れなど、ストレスの要因は多岐にわたります。
こうしたストレスを放置すると、心身の健康を損ね、仕事のパフォーマンスにも影響を及ぼすことがあります。
本ハンドブックでは、発達障害のある人が感じやすいストレスの原因と、その対処法を詳しく解説します。
また、ストレスマネジメントの自己評価ができるチェックリストも掲載しています。日々の生活習慣を振り返る際にご活用ください。
- 発達障害の特性とストレスの関係をわかりやすく解説
- 「なぜ自分はこんなに疲れるのか?」を理解するヒント
- ストレスの対処法を確認できるチェックリスト
- 感覚・思考・行動・環境別のストレス対処法
- 明日から使えるセルフケアの実践アイデア
- 発達障害の診断がある、もしくは発達障害グレーゾーンの人
- 自分は発達障害かもしれないとお悩みの人
- 仕事や日常生活での疲れがなかなか抜けない人
- 自分に合ったストレス対処法が見つからず悩んでいる人
- 「頑張りすぎて燃え尽きる」を繰り返している人
- リンクから申し込みフォームにアクセス
- 簡単なフォームに入力
- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り
- URLから資料を取得!
- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。
- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。
- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。
また、発達障害の特性によるストレスへの対処法については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ:自分も大切にして過剰適応を防ごう

発達障害のある人が過剰適応にならないためには、自分自身も大切にすることがポイントとなります。他者だけでなく、自分自身にも意識を向け、無理をしすぎないようにしましょう。
また円滑なコミュニケーションを取ることが難しいと感じる人は、支援機関を利用してトレーニングをしておくのもよいでしょう。
より円滑なコミュニケーションができるようになれば、対人関係でのストレスを軽減できる可能性があります。
このコラムが、発達障害・過剰適応に悩むあなたの助けになることを願っています。
過剰適応とは、どのような状態ですか?
過剰適応とは、周囲の期待や要求へ応えようとして、必要以上に努力をしている状態を指します。
詳細については、こちらで解説しています。
発達障害による過剰適応への対処法はありますか?
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→