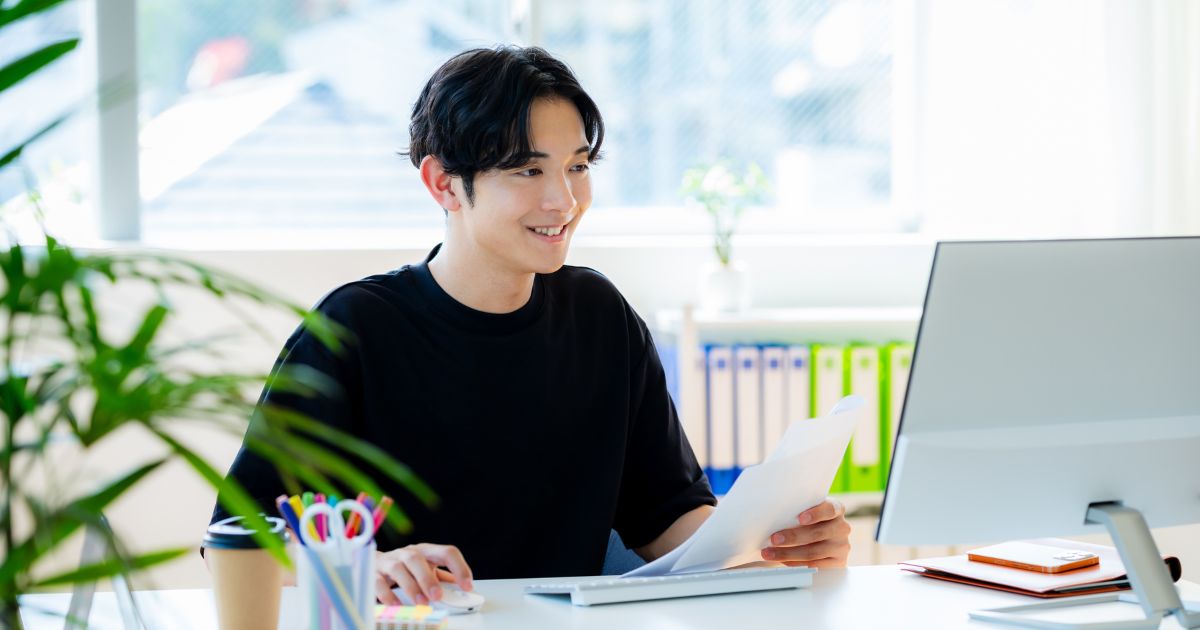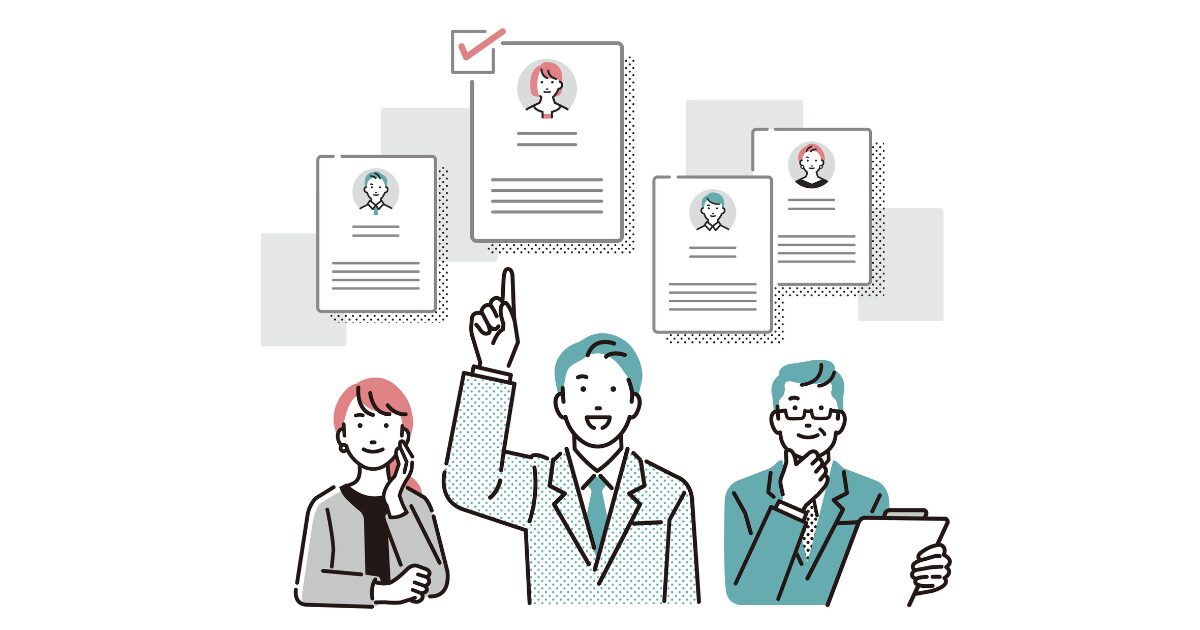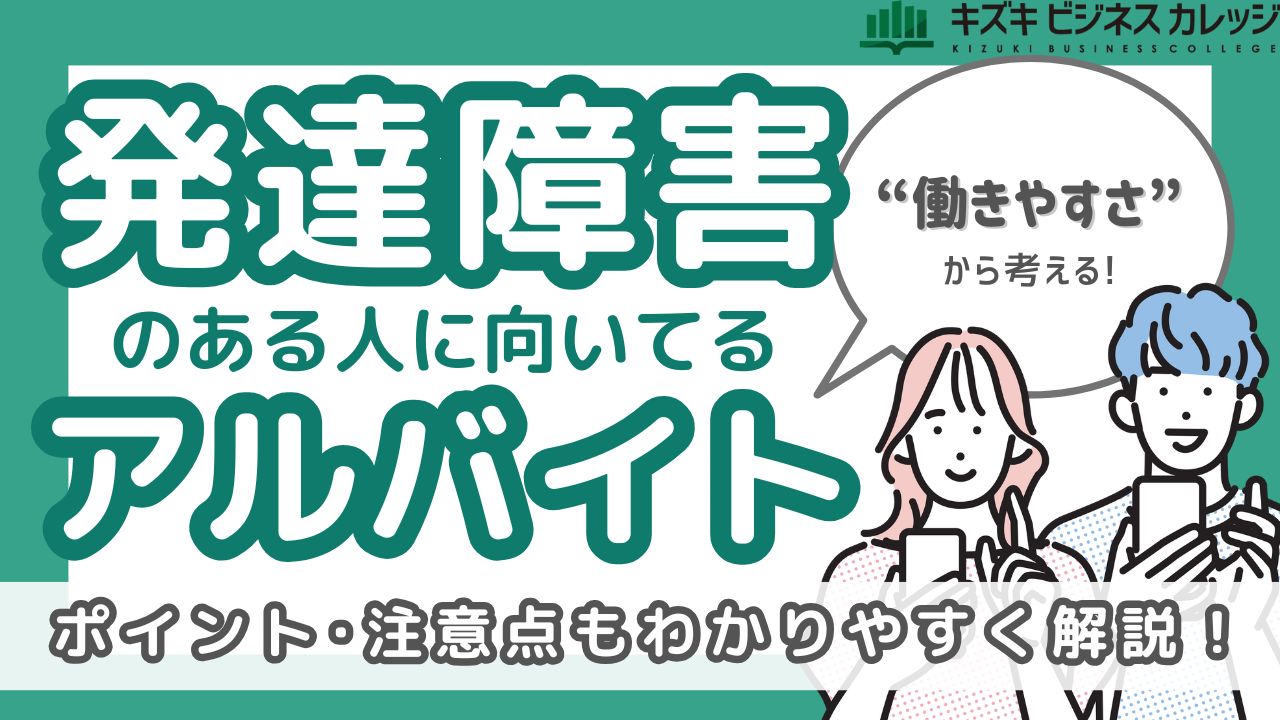大人の発達障害とは? 子どもの発達障害との違いを解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
発達障害と聞くと子どもに特有の障害と思う人も少なくありません。しかし、実は、大人の発達障害も珍しいものではないのです。
近年、メディアでも大人の発達障害が取り上げられることが多くなりました。
このコラムを読んでいるあなたも、仕事や生活の上で困難を感じていて、「もしかして、私は発達障害なのかもしれない」とお悩みではないでしょうか?
このコラムでは、大人の発達障害の概要や、診断に関する注意点、生きづらさを減らす方法について解説します。あわせて、職場で見られる大人の発達障害に関する事例を紹介します。
発達障害のあるあなたはもちろん、発達障害のある人への接し方にお悩みのあなたも、ぜひ参考にしてください。
このコラムが、少しでもあなたの生きやすさと次の一歩につながれば幸いです。
発達障害のあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)
発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。
- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)
- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)
- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)
同じ診断名でも、人によって多様な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人は、他の発達障害が併存している可能性もあります。
発達障害の概要や種類、原因、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
大人の発達障害とは?
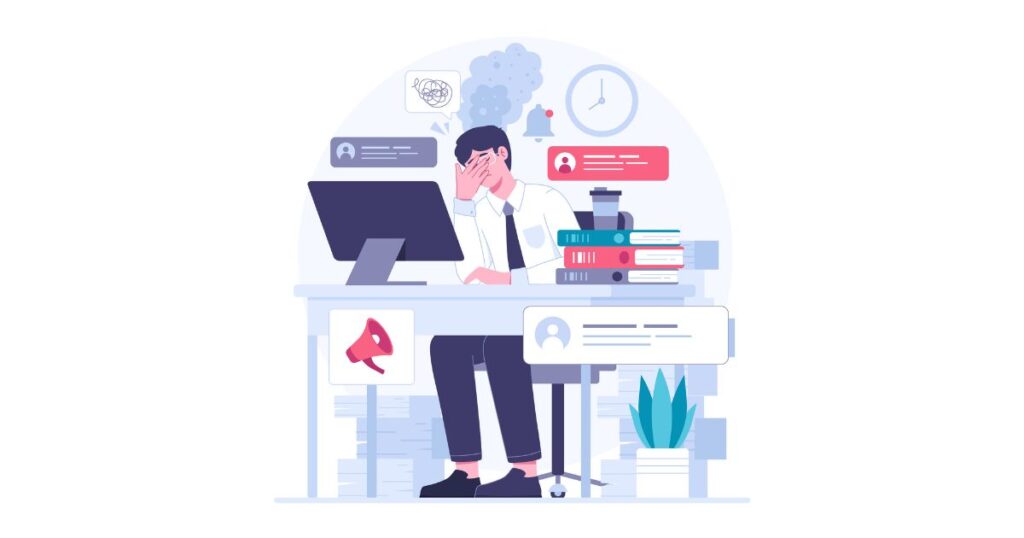
大人の発達障害は、医学的に正式な診断名称ではない俗語です。(参考:林寧哲『これでわかる 大人の発達障害』、黒澤礼子『新版 大人の発達障害に気づいて・向き合う完全ガイド』)
明確に定められた定義はありませんが、一般的には、幼少期の時点で診断を受けておらず、大人になってから発達障害の確定診断を受けた状態のことを指すようです。また、幼少期の時点で発達障害の確定診断を受けていた人が、大人になった状態のことを、大人の発達障害と表現することもあるようです。
なお、発達障害は、脳の構造的な特性によって生じる、生まれつきのものです。本来、発達障害の特徴は一般的に乳幼児から幼児期に現れます。大人と子どもで本質的には異なる部分はなく、現在の医学では、大人になっても継続するものとされています。
そのため、「大人になってから発達障害になる」「成長するにつれて発達障害になる」ということはありえません。また、「思春期から」「育ち方や親のしつけの影響で」など、成長してから、または成長につれて後天的に発達障害になるということもありえません。
大人になってから発達障害に気がつく理由

発達障害は生まれつきのものですが、大人になってから発達障害の特性が顕在化し、成人後に診断がつく人も多く存在します。
大人になってから発達障害に気がつく理由として、以下のようなケースが考えられます。
- 大人になるまで、発達障害だと知らなかった
- 大人になるにつれて、発達障害の特性による困難が増加して意識するようになった
- 幼少期は発達障害の特性が目立たなかったため、受診していなかった
- 幼少期には目立った発達障害の特性や困難が見られなかった
- 幼少期から発達障害の特性や困難が見られたが、周囲の人のサポートが厚いため発達障害の特性や困難などが目立たなかった
現在はある程度の支援体制が整い、発達障害のある人は子どもの頃に発見されることが増えています。その場合、適切な療育・サポートを受けつつ、発達障害に関連する生きづらさを少しずつ解消していきます。その甲斐もあってか、「発達障害は子どもの障害だ」というイメージを持つ人がいるのかもしれません。
しかし現在、大人である人たちが子どもの頃には、発達障害は一般的ではありませんでした。
適切な診断やサポートを受けられないまま、変わった人として見過ごされて来たケースが多かったのです。中には、誤って統合失調症や適応障害などの別の診断が下されたケースもあるそうです。
そのため、大人になってから特性を自覚して、または他人から指摘され、病院に行って診断がつくことも少なくありません。
大人になってから発達障害に気がつく人の特徴・傾向
大人になってから発達障害に気がつく人には、以下のような特徴・傾向があるとされています。
- 優先順位がつけられず、仕事を効率的に進められない
- 身の回りの整理整頓ができず、忘れ物や紛失が多い
- 対人関係において独りよがりな言動があり、トラブルになることがある
- 周囲の環境や支援が整わないと、精神障害などの二次障害に発展することがある
適切なサポートを受けることで、発達障害の特性に伴う大人としての生きづらさにも、具体的な対策がわかっていきます。
大人の発達障害の診断に関する2つの注意点
近年、何らかの生きづらさのために、自身の発達障害を疑って精神科を訪れる人が増えています。
この章では、大人の発達障害の診断に関する注意点について解説します。
注意点①診断を受けていないのに「自分は発達障害だ」と思い込まないようにする

発達障害の特性があると自分で思っている場合でも、「必ず発達障害である」とは限りません。
例えば、コミュニケーションの難しさは多くの人が感じるものです。発達障害の特徴・特性は、ある程度は誰にでも当てはまるものです。
診断基準にあるいずれかの症状に該当していると思う場合でも、自身で「発達障害がある」と判断しないようにしましょう。
生きづらさがあるのは事実だとしても、その原因は他の精神疾患かもしれません。また、シャイな性格や社会経験の少なさなど、病気・障害とは別の要因に由来するものかもしれません。
生きづらさの原因を発達障害にとらわれることなく考えることで、あなたに合う対処法なども、より多くの選択肢の中から探せるようになるでしょう。
注意点②発達障害の診断は医師だけが可能
発達障害の診断は、医師による問診や心理士が実施する心理検査をもとにして、医師が行います。医師以外には発達障害の診断・判断はできません。
どの程度から診断基準に当てはまるかどうかは、他の病気や障害の可能性がないかどうかを含めて、医師だけが判断できます。
発達障害があるかどうかを知りたい場合、病院を受診することをオススメします。
診断を受けるのが不安な場合、事前に支援機関やお住まいの自治体の発達障害者支援センター、障害福祉を担当する部署・窓口に相談してみてください。
診断の際には、「幼い頃から学校生活や対人関係などで困難があったか」などについて、幼い頃の通信簿や連絡帳、ご家族の記憶も参考にされます。
なお、発達障害の診断が出ることで、「これまでの困難がわかって、安心した」と思う人は多いようです。
一方で、「自分に障害があることが確定するのが怖い」と思い、検査を受けることをためらう人もいます。
「自分は検査を受けるべきかどうか」については、専門家や支援機関に相談しましょう。
補足:発達障害のセルフチェック

自分に発達障害の可能性があるのか、なるべく手軽に知りたいという人もいらっしゃるのではないでしょうか?
例えば、以下の書籍では、基礎調査票の15項目の設問に答え、結果をグラフ化した評価シートを参照することにより、発達障害かどうかの傾向を知ることができます。
しかし、これらのテストの結果はあくまで参考です。繰り返すとおり、医師以外には発達障害の診断・判断はできません。
チェックリストにあるいずれかの症状に該当していると思う場合でも、自身で「発達障害がある」と判断しないようにしましょう。
大人の発達障害の生きづらさを減らす方法
この章では、大人の発達障害の生きづらさを減らす方法について解説します。
前提:適切な支援を利用しながら、自分の特性を理解する

大人の発達障害の特性は、職場、家庭、子育てなど、あらゆる場面で発現することがあります。それらの発達障害の特性に伴う困難が、全くないわけではありません。
しかし、必ずしも「発達障害があると、社会生活や子育てが不向きである」というわけではありません。
発達障害がありながらも、職場に適応していたり、子どもを健康に育てている人もいます。むしろ、発達障害のない人よりも活躍している人もたくさんいます。
大切なのは、自分の特性を理解することと必要に応じて適切な支援を利用することです。
そうすることで、仕事でも、家庭でも、その他社会生活でも、あなたの特性とうまくつき合っていけるようになるでしょう。
大人の発達障害の生きづらさを減らすコツ
発達障害のある大人の中には、がんばっているつもりなのに、怠けているとみなされたり、トラブルが多く、孤独を感じやすかったりなど、深刻な悩みに通じる生きづらさを抱えている人がいます。
大人の発達障害の生きづらさを減らすコツは、以下のとおりです。
- 信頼できる情報を集めて知識を身につける
- 就労移行支援事業所などの支援機関に相談する
- 自分の特性や得意なこと、苦手なことを周囲に伝えて理解してもらう
信頼できる情報は、政府広報オンラインや厚生労働省のWEBサイト、医学会のWEBサイトなど、公的機関や信頼できる支援機関が発信している情報を集めるようにしましょう。
現在は発達障害に関するさまざまな支援機関があります。診断を受けていない状態でも、発達障害の確定診断がなくても利用できるところもあります。
そうした支援機関を利用することで、実際のあなたのための具体的な対策がわかっていくでしょう。
また、支援機関を利用することで、自分の特性も見えてくるはずです。
大人の発達障害の生きづらさを減らす環境調整

発達障害のある大人が自分のよさを発揮して生きていくために重要なのが、環境調整です。(参考:厚生労働省「発達障害のある方への職場における配慮事例のご紹介」)
環境調整とは、障害に関連する困りごとが起きないように、環境を調整することです。
これは、取り巻く環境を変えることで、困難さを減らす試みと言えるでしょう。
具体的には、以下のようなことが挙げられます。
- 視覚刺激に敏感な場合、作業や学習の場をすっきりさせ、余計な刺激が入らないようにする
- 聴覚刺激に過敏さがある場合、うるさい場所から離れるか、ヘッドホンを使うなどして大きな音や声が聞こえない環境にする
- マルチタスクが苦手で家事に負担感がある場合、家事を外注してやるべきことを減らす
ちょっとした工夫で発達障害に関連する困りごとを減らすことができ、二次障害の防止にもつながります。
大人の発達障害の生きづらさを減らすライフハック
発達障害のある人が日常生活を営む上では、生活や仕事をするための基礎的な技術、ライフハックも重要です。
自身の特性や困難にあわせたライフハックを知っておくと、仕事や生活の場で役立つでしょう。
発達障害のある人のライフハックについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
職場で見られる大人の発達障害に関する事例3選
この章では、職場で見られる大人の発達障害に関する事例を紹介します。(参考:備瀬哲弘『大人の発達障害アスペルガー症候群、AD/HD、自閉症が楽になる本』)
前提:発達障害があっても働くことはもちろん可能

大人の発達障害の特徴がトラブルにつながる事例は、たくさんあります。
- 会議のアポ取りなどの物忘れが激しい
- 衝動性が激しく、つい必要ないことまで言ってしまう
- 非常に細かいことまで確認したり指示したりしてしまって話をするのを敬遠される
しかし、繰り返しますが、発達障害だからといって自己卑下的になる必要はありません。
あなたの特性により適した環境を作ることができたり、より適切な支援を受けることができれば、今よりも働きやすくなったり、優れた能力を開花できる可能性は十分にあるのです。
事例①普通であることに憧れるAさん
Aさん(55歳)は、翻訳者です。
外見も身だしなみも気をつけており、マナーもきちんとしています。医師からの印象も、変わったところはありません。
Aさんのように、外見や話し方に違和感がない発達障害のある人も多くいます。
そんなAさんは、子どもの頃から周囲とうまくいかず、いわゆる普通であることに憧れていました。
大学を出た後、Aさんの個性を知る母は大学院進学を勧めましたが、Aさんは「普通でいたい」と会社勤めの道に進みました。
しかし、会社に入るとAさんはたくさんのできないことに直面します。
まずは、電話対応ができません。いつ電話が鳴るかわからないという状況で臨機応変な対応ができず、電話に恐怖を感じるようになります。
もう一つはお茶出しでした。仕事の流れを読み、課長さんの機嫌を見て、タイミングよくお茶を出すことが、Aさんには何よりも難しかったのです。
「どうしてこんな忙しいときにお茶を出すんだ!」と怒鳴られたり、今は忙しいだろうと考えてお茶を出さずにいると「お茶が飲みたいんだけど、気が利かないね」とイヤミを言われたり。
電話対応にもお茶出しにも、決まったルールがありません。
人の顔色や空気を読んで行動しなくてはならないこれらの仕事は、発達障害のある人たちが苦手とするところです。
大学受験も入社試験もパスし、翻訳家としても活躍できるAさんですが、多くの人がこなせる仕事ができず、普通の会社員生活を送ることができませんでした。
事例②職場の女性から怖がられるBさん
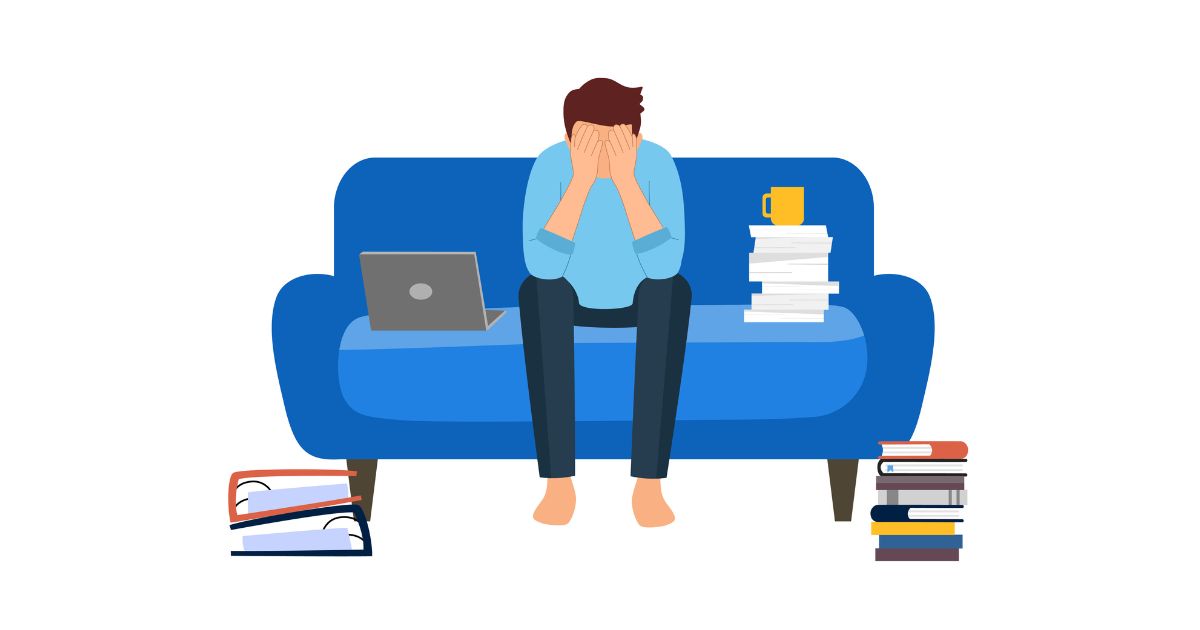
Bさん(男性、41歳)は、会社員です。
上司は、Bさんの次のような行動に困り、精神科に相談を行いました。
あるとき、Bさんの斜め前のデスクの女性が何気なく豆乳を飲み始めました。
その姿を、Bさんは睨みつけるように、じーっと凝視します。女性は、飲食をしたのが気に障ったのかと思い「すみません」と謝りました。
すると、Bさんは「謝ることはないですね」と言って、急にニンマリと笑ったのです。それからも、Bさんがその女性の顔を凝視することが続きました。
女性の顔を睨むようにじーっと凝視した後、突然ニンマリと笑い、「今日は天気がいいですね」「傘が必要なので忘れないでくださいね」などと話しかけるのです。
Bさんのこうした行動に、その女性はすっかり怖くなって上司に相談し、上司も精神科医に相談したのです。
医師がBさんから話を聞いたところ、Bさんは姉から、「女性と話をするときには、目を見て笑いかけるようにしたほうがいい」と言われていたそうなのです。
女性を睨みつけるように見えたのも、ニンマリ笑うのも、姉から教わったマニュアルどおりに振る舞っていただけで、Bさんに悪気は一切ありませんでした。
たしかに、目を見て話すことや、笑いかけることはコミュニケーションにおいて大切なことです。ですが、女性の顔色や空気を読んだものではないため、結果として不気味なものになっていたのでした。
事例③会社にアロハシャツを着て行くCさん
Cさん(23歳)は会社員です。
Cさんが会社にアロハシャツを着て行くことに困った母親が、医師に相談しました。
Cさんは、子どものころから強いこだわりを持っていました。
お母さんの話によれば、同じTシャツを色違いで何枚もそろえたり、同じスニーカーを何足も買ったりしていたとのことです。他にも、「明日は運動会だ」と決まっていたのに雨で延期になったことが納得できず、何時間も泣き続けたといったことがあったそうです。
そんなCさんは、今はアロハシャツにこだわりを持っているいるようでした。
見かねた上司が「そんな派手なシャツを着て、社会人らしくないぞ」と注意すると、今度はおとなしい色のアロハシャツを着て出勤します。
上司としては暗に「スーツやシャツなど仕事に適した格好をしてほしい」と伝えてたつもりでも、Cさんは上司の言葉を文字通り「派手なシャツはいけない」と捉え「地味な色のアロハシャツならいいのだ」と解釈しました。
こうした、人の言葉を言葉どおりに受け取ってしまうことも、発達障害の特徴です。発達障害のある人は、冗談や皮肉がわからないことが多いといわれるのもこのためです。
医師はお母さんに、社会には就業規則に書いていないルールも存在することを具体的に示してCさんに教えていく方法を提案しました。
まとめ:大人の発達障害は決して劣っているわけではなく、社会的不適合者でもありません

公認心理師・臨床心理士・臨床発達心理士である黒澤礼子氏によると、発達障害の特性があっても、人は変わることができると言います。(参考:黒澤礼子『新版 大人の発達障害に気づいて・向き合う完全ガイド』)
発達障害のある人は、決して劣っているわけではなく、社会的不適合者でもありません。
適切なサポートを受ければ、発達障害の特徴を活かして、今よりももっと社会で活躍したり幸福な生活を手に入れることは可能です。
現在の大人の多くが、発達障害の診断や支援が一般的ではない時代に子供時代を過ごしました。
ちょっと変わった人として放置され、生きづらさを噛み締めて生きて来られた人も多いかと思います。
しかし、そのような人でも、適切なサポートで変わることはできるのです。生きづらさを抱えるあなたが適切なサポートに出会い、より生きやすくなることを願っています。
大人の発達障害とは、何ですか?
明確に定められた定義はありませんが、一般的には、幼少期の時点で診断を受けておらず、大人になってから発達障害の確定診断を受けた状態のことを指すようです。また、幼少期の時点で発達障害の確定診断を受けていた人が、大人になった状態のことを、大人の発達障害と表現することもあるようです。
詳細については、こちらで解説しています。
大人の発達障害の生きづらさを減らすコツを教えてください。
以下が考えられます。
- 信頼できる情報を集めて知識を身につける
- 就労移行支援事業所などの支援機関に相談する
- 自分の特性や得意なこと、苦手なことを周囲に伝えて理解してもらう
詳細については、こちらで解説しています。
監修志村哲祥
しむら・あきよし。
医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。
臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。
【著書など(一部)】
『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』
他、学術論文多数
日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧
時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
監修角南百合子
すなみ・ゆりこ。
臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→