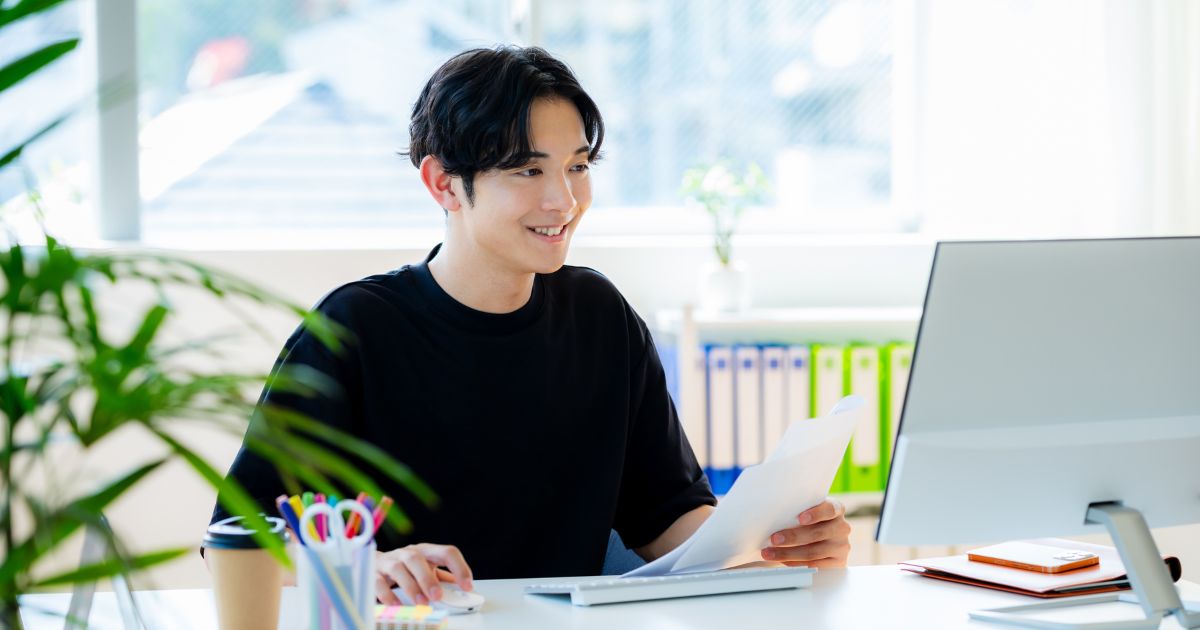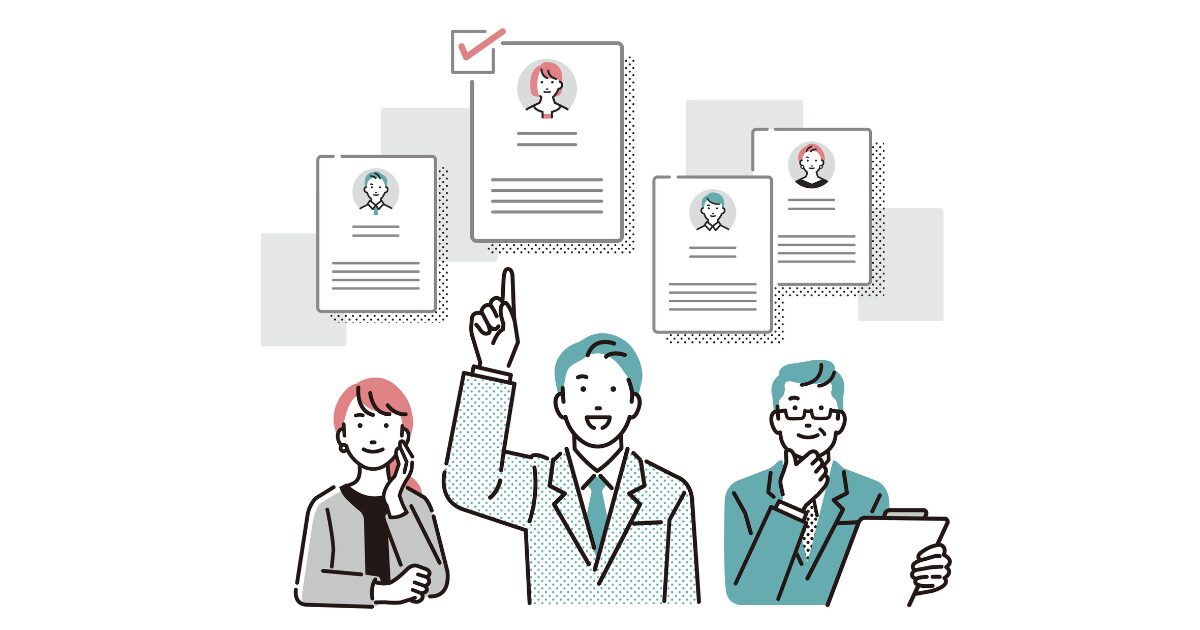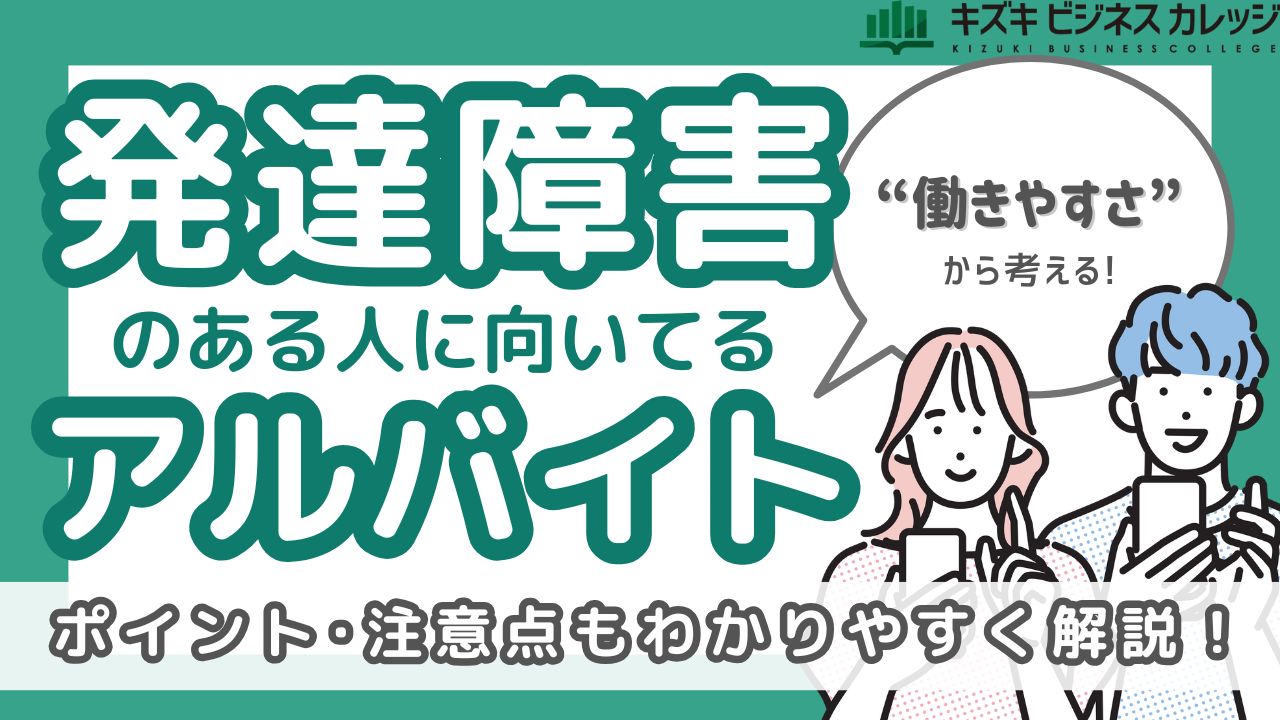発達障害のある人の一人暮らし 対策を課題別に解説

こんにちは、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
発達障害のあるあなたは、「一人暮らしをしたいけど、自分にできるだろうか?」とお悩みではないでしょうか?
発達障害のある人も、充実した一人暮らしをしている方はたくさんいます。自分の特性を理解して対策をしたり、福祉サービスを活用したりしつつ、一人暮らしを通じて自分に自信をつけていっています。
このコラムでは、発達障害のある人の一人暮らしに関する課題や一人暮らしで役に立つ対策について解説しています。
このコラムで解説する対策は、一人暮らしで利用できる対策ではありますが、実家やグループホームでも利用できます。一人暮らしを始める前に、試しにやってみることをオススメします。
このコラムを読むことで、あなたの一人暮らしも実現に近づくはずです。
グループホームの利用を検討している人や一人暮らしとグループホームのどちらがよいか悩んでいる発達障害のある人は、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
一人暮らししたい発達障害のあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
発達障害のある人の一人暮らしに関する4つの課題
一人暮らしをすると、あらゆることを自分で管理する必要があります。
発達障害のある人が一人暮らしをする場合、避けては通れない課題があります。
この章では、発達障害のある人の一人暮らしに関する課題について解説します。
それぞれの課題について、対策を身につけることで、発達障害のある人の一人暮らしはより充実したものになっていくでしょう。
ここで挙げる課題への対策は、あなた一人で考える必要はありません。あなたの特性によっては、ここで解説する以外の対策ももちろん考えられます。
発達障害のある人をサポートする支援機関に相談することで、実際のあなたの一人暮らしに役立つ具体的な方法などが見えてくるはずです。ぜひ積極的に相談してみてください。
課題①金銭管理

発達障害のある人の中には、金銭管理に苦手意識を持つ方が少なくないようです。
これは、ADHDの特性である不注意や衝動性、ASDの特性であるこだわりの強さなどが影響しやすいと言われています。
ADHDの特性のひとつである不注意に関する例を挙げると、計画や見通しを立てることに苦手意識を抱きやすいために、家計簿をつけることや毎月の収支を把握することそのものに苦手意識を持つ人もいるようです。
ほかにも衝動性という特性によって、欲しいものがあると感情や衝動を抑えられず、衝動買いをしてしまい、気付けばお金を使いすぎてしまった、というケースはよく見聞きします。
ADHDの衝動性については、NHKスペシャル取材班が、以下のように紹介しています。(参考:NHKスペシャル取材班『発達障害を生きる』)
ADHDは、細やかな注意ができずケアレスミスをしやすい、注意を持続することが困難、注意散漫で人の話を聞けないように見える、課題や活動に必要なものを忘れがちなどの不注意症状や、座っているときにそわそわして落ち着かない、不適切な状況で走り回る、しゃべり過ぎるなどの多動性の症状が観られる障害です。予測したり、考えたりする前に行動してしまう衝動性もみられます。
(参考:NHKスペシャル取材班『発達障害を生きる』)
これらの特性によってお金を使いすぎる日が続けば、自分を責める日が訪れる、責める日が続くことが懸念されます。
自分を責めず、さらに自分の生活をきちんと安定させるためにも、このコラムを参考にしながら発達障害の特性について知識を深め、どのようなことを対策すればよいのかを見つけてもらえたら幸いです。
金銭管理に関する対策は、こちらで解説しています。
課題②生活環境管理
生活環境管理にも懸念点があります。
例えば、ライフステージの変化です。学校での生活から就職により職業生活に移行した場合、学校生活とは違った能力を求められることに心身に負担を感じやすく、苦手意識を持つ人がいます。
もう少し細かく説明すると、学校生活では生徒や学校の先生との間で求められるコミュニケーション能力や、宿題をしなければならないといった実行機能が必要です。しかし、社会に出て働くとなれば、その能力に合わせて社会性や想像力、注意機能といった能力も必要になります。
さらに、一人暮らしを始めるとすれば、身の回りのことや食事、掃除や片付けなど、生活全般にかかわる維持も必要になってくるでしょう。毎日働きながら生活の維持に取り組み、さらに仕事に必要なスキルを取得することになれば、多くのストレスがかかることは想像に難くありません。
その結果、一つひとつを対処していくことにやがて苦手意識が芽生え、働くことに苦痛を感じる方もいらっしゃいます。
生活の管理と一口に言っても、その言葉の中にはじつに多くのやらなければならないことがあります。それらを毎日こなすことに対し漠然とした気持ちになる方は、なんらかの対策を考え、実行することが大切です。
生活環境管理に関する対策は、こちらで解説しています。
課題③体調管理

体調管理にもいくつかの懸念点があります。
例えば、ASDの場合、特性の1つに感覚過敏が挙げられます。
感覚過敏のある人の中には、思考の中断を余儀なくされるほどの強い刺激を感じ、頭が真っ白になり、我慢できるレベルではないほど心に強い影響を与えることもあります。(参考:NHKスペシャル取材班『発達障害を生きる』)
周囲から発する大小さまざまな音などが気になり、体調不良につながる人もいます。
一人暮らしを始めるときは、近隣住民の生活音や交通機関の音などによって体調不良につながる可能性について考慮する必要があると言えるでしょう。
体調管理に関する対策は、こちらで解説しています。
課題④人間関係
発達障害のある人が特に悩みを抱えやすいと言われている課題は、人間関係です。
その理由には、以下のような原因があると考えられています。
- 身振りや表情を読み取れない
- さじ加減がわからない
- 関係性を理解しづらい
- 情報伝達の手段が合わない
発達障害のある人のコミュニケーションの対策について、以下のコラムで解説しています。
主に職場でのコミュニケーションについて解説していますが、一人暮らしを始める上でも参考になる内容なので、ぜひご覧ください。
発達障害のある人の一人暮らしにかかる費用

一人暮らしをするにあたっては、まず月々にかかる費用を押さえておきましょう。
厚生労働省によるデータを参考にすると、一人暮らしに必要な費用は、平均としては「家賃+14万1881円」が必要になるようです。(参考:総務省統計局「家計調査 2023年 1~3月期」)
- 家賃:地域や条件によって大きく異なる
- 光熱・水道代:1万7548円(うち電気代は9340円、ガス代は4430円、水道代は2163円、その他は1615円)
- 家具・家事用品:4275円
- 被服及び履物:4140円
- 食費:4万6011円(うち外食は8246円)
- 保健医療費:6349円
- 交通・通信費:1万9376円
- 教育費:8円
- 教養娯楽費:1万6804円
- その他:3万1645円
- 家賃を除く合計:14万1881円
実際のあなたにどれくらいのお金が必要なのか、検討してみましょう。
補足として、年間の家賃が年収の20~25%であれば、家賃以外の支出を捻出しても貯蓄に回す資金を残せるギリギリのラインとなる場合が多いとのことです。(参考:三菱UFJ銀行「家賃の適正予算はいくら?あなたの年収から考える適正家賃」)
また、家賃と電気代・ガス代・水道代などの公共料金の支払い方法には、一般的に、以下の2つがあります。
- 都度、送られてくる支払用紙を持って、コンビニなどで支払う
- 口座やクレジットカードからの自動引き落とし設定をする
都度支払うことで費用が把握しやすくなる半面、振込忘れなども起こりやすいため、ご自身にあった支払方法を選んでみてください。
発達障害の人の一人暮らしで役に立つ金銭管理に関する対策
発達障害の人の一人暮らしで役に立つ金銭管理に関する対策は、以下のとおりです。
- よく考えてから買い物をする
- 必要な物はあらかじめメモを残す
- 現金は必要最低限のみ持ち歩く
- プリペイドカードまたはデビッドカードを使用する
- 家計簿をつける
- 家賃や公共料金などの支払いをきちんと管理する
- 日常生活自立支援を利用する
発達障害の一人暮らしで役に立つ金銭管理に関する対策については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害の人の一人暮らしで役に立つ生活環境管理に関する対策

発達障害の人の一人暮らしで役に立つ生活環境管理に関する対策は、以下のとおりです。
- 生活必需品を把握する
- 持ち物をセット化する
- 物の置き場を決める
- 移動中も物の持ち方を決める
- 1週間の服の組み合わせを決めておく
- 自炊でもできるレシピを調べる
- 調理しやすい野菜・冷凍野菜・缶詰を使う
- 外食は控える
- 好きなもの・食べられるものだけで選ばない
- 掃除・片付けはなにかしらのついでにする
- ゴミ出しをなにかしらのついでにする
- ゴミ出し日をアラームで管理する
- 洗濯物は段階を踏んで行う
発達障害の人の一人暮らしで役に立つ生活環境管理に関する対策については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害の人の一人暮らしで役に立つ体調管理に関する対策
発達障害の人の一人暮らしで役に立つ体調管理に関する対策は、以下のとおりです。
- 生活リズムを整える
- 生活環境を変えてみる
- 疲労感があるときは全てをシャットダウンする
- サングラスやイヤフォンを取り入れる
- 思う存分好きな物を楽しむ時間をつくる
発達障害の人の一人暮らしで役に立つ体調管理に関する対策については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害のある人の一人暮らしに関する相談先3選
この章では、発達障害のある人の一人暮らしに関する相談先を紹介します。気になる支援機関があれば、お近くにあるか調べてみましょう。
一人暮らしだからといって、諸々の悩みなどをあなた一人で抱え込む必要はありません。専門的な知識を持つ人たちに相談に乗ってもらうことも可能なんです。
いずれも、実際に相談に行く前に、生活環境管理や金銭管理など、どのようなことで困っているのかをメモなどしておくとスムーズに進められます。
相談先①自治体の障害福祉を担当する部署・窓口

あなたがお住まいの自治体には、障害福祉を担当する部署・窓口があるはずです。
その部署・窓口では、ヘルパー制度などの一人暮らしを成立させる上で必要なサポートについての相談ができます。また、より専門的な別の支援機関を紹介してもらえることもあります。
障害福祉を担当する部署・窓口がわからないときは、お住まいの自治体のWEBサイトや総合窓口で確認しましょう。
相談先②一般相談支援事業所・特定相談支援事業所
一般相談支援事業所と特定相談支援事業所とは、自治体が指定する相談支援事業所のことです。
障害のある人が自立できるように、自治体が中心となって運営しています。サポートが必要な本人や家族が利用できます。
一般相談支援事業所では、さまざまな相談に応じる基本相談支援に加えて、障害者のある人が施設や病院から離れて地域生活を送る際に必要になる地域移行支援、障害者のある人が地域で暮らし続けるための地域定着支援も実施しています。
また、特定相談支援事業所では、面談などを通じて相談者の状況に合わせ福祉サービスが受けられるようサービス等利用計画を作成し、定期的にサービスの利用状況などヒアリングします。
相談先③消費者ホットライン

消費者ホットラインは、消費者庁が運営する支援機関のことです。発達障害の有無を問わず、一人暮らしをするときに覚えておきたい相談先の1つです。
例えば、以下のようなトラブルの相談が可能です。
- オークションサイトやフリマサイトで購入したものが予定日を過ぎても届かない
- 無料商品だったはずなのに商品代金を請求された
一人暮らしを初めてまもなくの間は、さまざまな契約・物事を一人でこなす必要があります。
トラブルに巻き込まれそうになったときに、専門的な知識をもって解決したいときは、消費者ホットラインを頼ってみるとよいでしょう。
発達障害のある人が一人暮らしに関して利用できる福祉サービス2選
この章では、発達障害のある人が一人暮らしに関して利用できる福祉サービスを紹介します。
福祉サービス①日常生活自立支援

日常生活自立支援とは、認知症のある高齢者や知的障害のある人、精神障害のある人などのうち判断能力が不十分な人が対象の福祉サービスのことです。
自立した生活が送れるように、契約に基づき福祉サービスの利用援助などが行われます。利用希望者は自治体に申請・相談する必要があります。
援助内容は、以下のとおりです。
- 定期訪問による生活の観察
- 通帳、権利証の預かり・払い戻し・預金の解約など日常生活費の管理
- 公共料金・家賃などの支払いおよび書類の整理など
なお、利用料は自治体が定める料金を利用者が負担します。ただし、契約締結前の初期相談等にかかわる経費・生活保護受給世帯の利用料については無料です。
福祉サービス②居宅介護
居宅介護とは、ホームヘルパーが自宅を訪問して、利用者の身の回りのことを援助する福祉サービスのことです。
障害者手帳の有無は関係なく、掃除や洗濯、調理といった生活にまつわる家事の援助が受けられます。
なお、利用にあたっては障害者総合支援法における障害支援区分が区分1以上であることが条件です。利用を希望する人は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に相談するとよいでしょう。
発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)
発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。
- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)
- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)
- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)
同じ診断名でも、人によって多様な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人は、他の発達障害が併存している可能性もあります。
発達障害の概要や種類、原因、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ:対策や相談を行えば、発達障害のある人の一人暮らしは充実してきます

人にも相談しながら、自分ができること、苦手なことを掘り起こして分析し、どうすれば一人暮らしができるようになるか探ってみましょう。
自分の生活をいろんなことを工夫して営むことは、自分に自信をつけられるチャンスにもなります。あなたの一人暮らしが充実したものになるよう祈っています。
発達障害のある人の一人暮らしでは、どんな課題がありますか?
発達障害のある人が一人暮らしについて相談できるところはありますか?
監修志村哲祥
しむら・あきよし。
医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。
臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。
【著書など(一部)】
『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』
他、学術論文多数
日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧
時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
監修角南百合子
すなみ・ゆりこ。
臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→