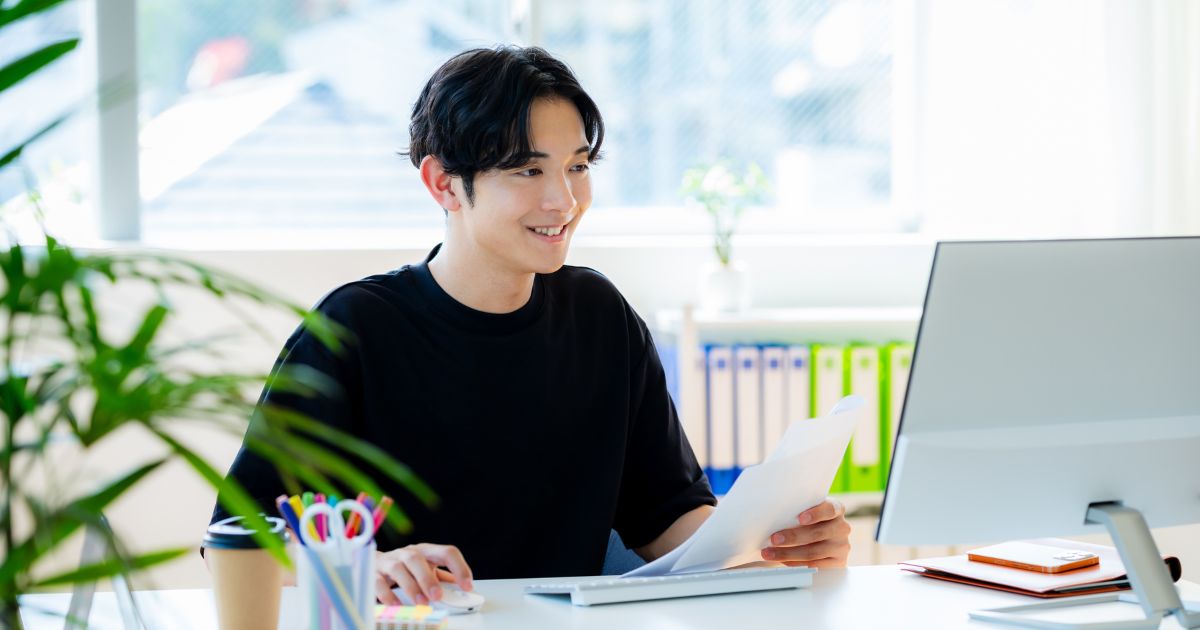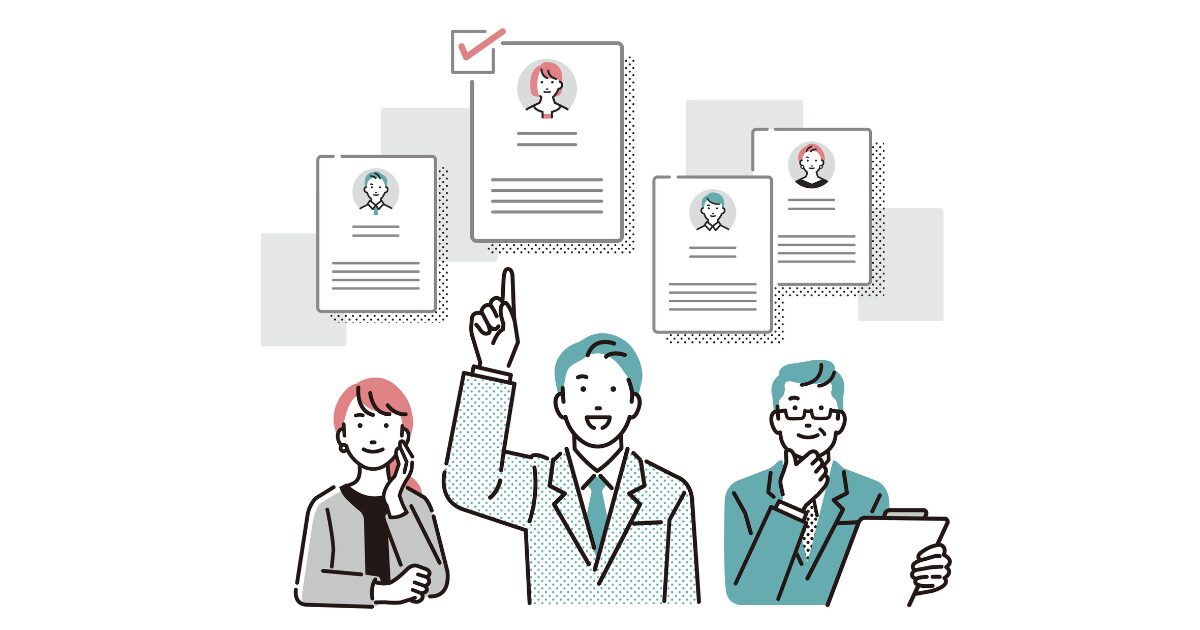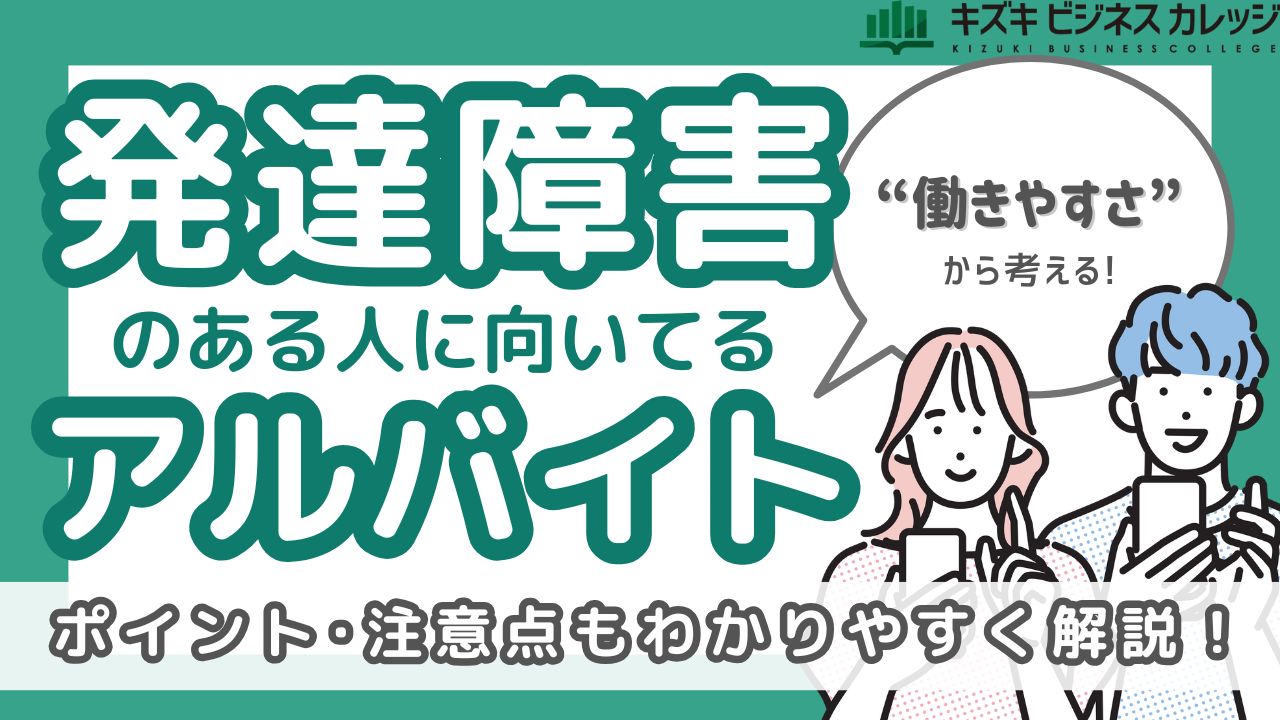聴覚過敏とは? 発達障害との関係や対策を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
発達障害のあるあなたには、以下のような聴覚過敏に関する悩みを抱えていませんか?
- 周りの音や声がうるさく聞こえて、外出がつらい
- 目の前の作業に集中したいのに、周囲の話し声で気が散る
音や声は意識しなくても聞こえてくるため、気になるとつらいですよね。
このコラムでは、発達障害に関連する聴覚過敏にフォーカスして、キズキビジネスカレッジ(KBC)の知見や聴覚過敏の当事者である筆者の経験に基づき、聴覚過敏の概要や発達障害に関連する聴覚過敏への対策について解説します。あわせて、聴覚過敏に悩む発達障害のある人と一緒に働く人が理解しておくべきポイントについても解説します。
解説する対策は、発達障害の有無に関わらず参考になるはずです。
さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、発達障害の特性によるストレスに悩む人に向けて、発達障害の特性に合わせた『"発達障害"特化型ストレス対策ハンドブック』を無料配布を開始いたしました。
ストレスの原因を特性との関係から丁寧に解説し、気づきを得られる自己診断チェックリストを掲載。すぐに使える対処法を一冊にまとめています。
ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。
また、発達障害の特性によるストレスへの対処法については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。
聴覚過敏でお悩みのあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
感覚過敏とは?

感覚過敏とは、聴覚・視覚・触覚・嗅覚・味覚の五感の一部、または複数からの刺激を過度に感じることで、苦痛や不快感が生じている状態のことです。(参考:イルセ・サン・著、枇谷玲子・訳『鈍感な世界に生きる敏感な人たち』、岡田尊司『過敏で傷つきやすい人たち HSPの真実と克服への道』、安田祐輔『ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に勉強するための本』)
症状や程度は人によってさまざまですが、感覚過敏のある人の多くが日常生活や仕事の場面においてストレスを感じていると言われています。その強弱は人によって異なります。
感覚過敏の種類は、以下のとおりです。
- 聴覚過敏:音に対する感覚過敏
- 視覚過敏:目に入る視覚情報に対する感覚過敏
- 触覚過敏:皮膚に触れるものに対する感覚過敏
- 嗅覚過敏:においに対する感覚過敏
- 味覚過敏:味や食感に対する感覚過敏
目や耳や鼻などの感覚器に先天的な異常がある場合など、幼少期から感覚過敏を自覚している人もいます。また、不安やストレスが原因で、大人になってから感覚過敏の症状に悩む人もいます。
感覚過敏とは反対に、ある感覚が極端に鈍くなる感覚鈍麻があります。感覚過敏と感覚鈍麻の両方が見られる人もいます。
感覚過敏については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
聴覚過敏とは?
この章では、聴覚過敏の概要や発達障害との関連などについて解説します。
聴覚過敏の概要
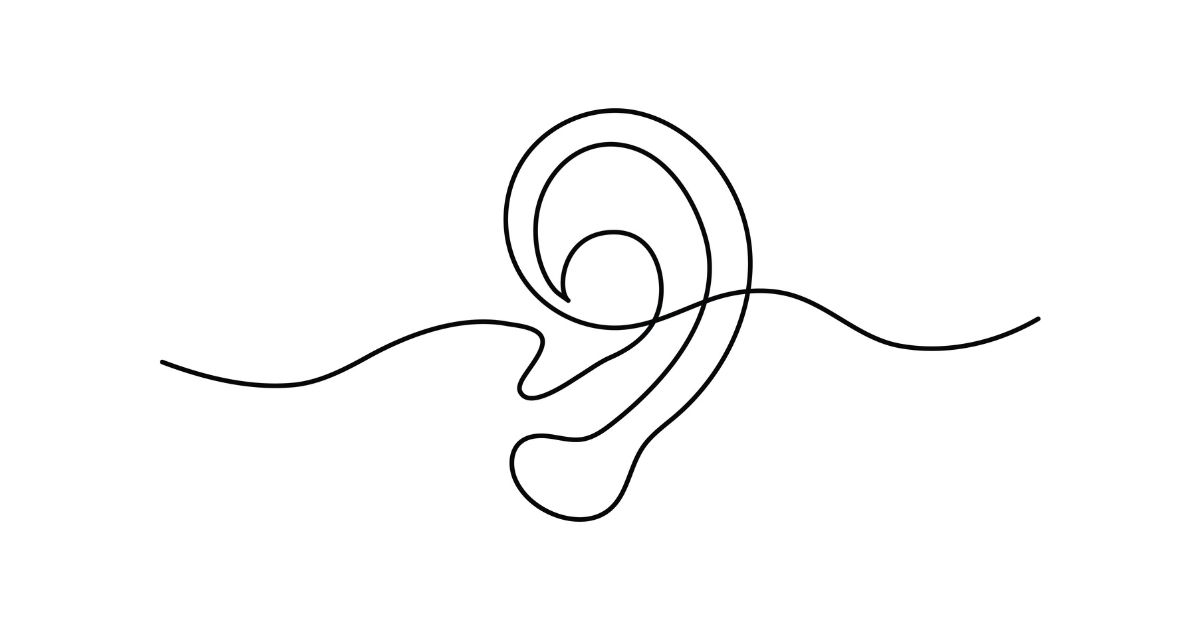
聴覚過敏とは、音に対する感覚過敏のことです。
聴覚過敏のある人は、必要な音を選別することが苦手です。一般的な人が無意識に行っている聞き取るべき音の取捨選択がうまくできず、常に脳が疲労を感じやすい状態にあるのです。
その程度は人それぞれであり、少し気になるくらいの人もいれば、寝込むほどつらく感じる人もいます。
聴覚過敏の症状や診断基準、治療についてはまだまだわからないことが多く、社会的認知が十分に進んでいるとは言えません。
そのために周囲から誤解され、理解されないことによる二次障害を引き起こすこともあります。
聴覚過敏の症状・困りごと
聴覚過敏の症状は、以下のとおりです。
- 時計の針の音のような小さな物音が気になる
- 冷蔵庫などの機械の作動音の音が大きく聞こえる
- ベルや掃除機など特定の種類の物音が耳に突き刺さるように感じて苦痛を覚える
- 音の遠近感をうまく把握できない
- 周りの音すべてが耳の中に入ってきて、必要な情報を選別するのが難しい
- 電車や人の多い飲食店、人混みなどの騒がしい場所だとすぐに疲れる
- 電子音を゙聞くと耳を刺すような感覚を覚える
- 周囲の雑音や話し声が大きく聞こえ、会話に集中できない
- 予期しない音や大きな音でパニックになる
- 特定の音で耳の痛みや頭痛・めまいが伴う
普段の生活や職場で周りの音が気になるのは、一般的にもよくあることです。
しかし、聴覚過敏のある人は、こうした音が気になるという程度では済みません。仕事や勉強に集中できないだけでなく、体調を崩すこともあるのです。
聴覚過敏のある人が生活の中で感じる困りごととして、以下のような例が挙げられます。
- 人混みのある場所など、さまざまな音があふれている環境では、疲れが溜まり体調が悪くなる
- 目の前の人の声と周りの声の音量が同じくらいに聞こえて、会話が聞き取りにくい
- 蛍光灯のノイズ音や時計の秒針の音が気になる
- 掃除機やドライヤーなど、家電の音が耳に刺さるように聞こえてくる
- 工事現場や踏切の警報器など、街中で突然鳴り響く大きな音が苦手
聴覚過敏の原因①耳の機能

耳には、大き過ぎる音を緩衝する働きがあります。なんらかの原因でこうした機能に障害が起きると、聴覚過敏の症状を引き起こすことがあるのです。(参考:あさひ町榊原耳鼻咽喉科医院「周囲の音が響く・うるさく聞こえる・聴覚過敏」)
聴覚過敏の原因②脳の機能
聴覚過敏は、脳の働き方に偏りがあることも原因のひとつとされています。(参考:あさひ町榊原耳鼻咽喉科医院「周囲の音が響く・うるさく聞こえる・聴覚過敏」)
アメリカ精神医学会が定めた精神障害の診察基準『DSM-5』では、発達障害との関連が示されています。詳しくは、こちらで解説します。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』)
そのほか、てんかんや片頭痛、うつ病なども聴覚過敏と関連があると言われています。
聴覚過敏の原因③ストレス・疲労

ストレスや疲労も、聴覚過敏の症状が悪化する原因となります。
普段は生活に支障のない程度でも、疲れているときには周囲の音がひどく苦痛に感じる人もいます。
自分がどんなときに聴覚過敏の症状が出るのか、普段から把握しておきましょう。(参考:NHK「困りごとのトリセツ」)
聴覚過敏の確認方法
聴覚過敏かどうかをセルフチェックできる簡易シートが公開されています。
以下のサイトを参考にしてください。
障害者職業総合センター「感覚特性チェックシート/感覚特性見える化シート」
感覚過敏研究所「医療機関向け感覚過敏相談シート」
また、自分では意識していなくとも聴覚過敏の症状が出ている場合もあります。なぜか職場で集中が持続できなかったり、人混みで疲れやすくなったりするという人は、無意識のうちに聴覚過敏の状態になっているかもしれません。
以上の症状は、特に疲れやストレスが溜またときに強くなることが多いようです。「疲れてきたな」と感じたら、早めに休むと比較的楽になることもあります。
発達障害と聴覚過敏の関係

聴覚障害にはさまざまな原因があるとされていますが、発達障害と関連がある場合も多いと言われます。
発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)
人の脳には、雑多な情報の中から自動的に必要なものだけを拾い出してくる機能があります。これは心理学用語で、選択的注意/聴取と呼ばれるものです。
しかし、聴覚過敏のある人は、不要な音にまで意識が向く傾向があります。そうなると、本当に必要な聞きたい内容に集中できなくなるのです。
反対に聴覚鈍麻の場合は、大きな音でも小さい音のように聞こえることがあります。こうした症状は、人によって違います。
一人ひとりの状況にあった対応を取るためには、自分の症状の特徴を把握し、専門家と相談しながら、対策を考えていく必要があります。
発達障害の概要や種類、原因、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
聴覚過敏に悩む発達障害のある人ができる対策6選
この章では、聴覚過敏に悩む発達障害のある人ができる対策について解説します。
対策①医療機関に相談する

聴覚過敏がある人は、まずは専門家のアドバイスを受けることが必要です。
残念ながら、聴覚過敏の治療法はまだ確立していません。
しかし、医師をはじめとする専門家は、最新の知識や豊富な経験を持っています。聴覚過敏などの症状に悩んだときには無理をせず、病院を受診して医師と対策を相談しましょう。
医師の専門的な目線でアドバイスがもらえれば、生活を見直すきっかけになり、日々の生活を安心して過ごすことができるようになります。
また、聴覚過敏があることによる生活への影響とその配慮に関する助言を、診断書として出してもらうことが可能です。
また、発達障害があると思われる場合は、精神科・心療内科を受診しましょう。聴覚過敏からくるストレスや精神的なものを和らげる治療薬の処方をしてもらえるほか、カウンセリングなどの心理療法も受けられます。
発達障害以外の原因が考えられて、どこを受診するべきか迷う場合は、まずは耳鼻咽喉科で相談してくださいね。
対策②騒がしい場所や時間帯を避ける
できるだけ、騒がしい場所や時間帯を避けて過ごしてみましょう。具体的には、以下のような方法があります。
- テレビを長時間つけない
- 周囲が騒がしいと感じるときは、別室で休む
- 買い物は人のいない時間を狙うか、ネットですませる
耳に入る音の量を減らすことで、脳への負担を減らすことができるでしょう。
対策③外で活動する時間の目安を決める

外出時は、不特定多数の音が耳に入ってきます。家の外で活動する際は、疲れが残らないように◯時までには帰るなどの目安時間を決め、計画的に行動しましょう。
こうすることで不必要なストレスに晒されることが減り、過度に疲労することを防ぐことができます。
どうしても長時間外出しなくてはいけないときは、事前に少しずつ体を慣らしておきましょう。
対策④食事や睡眠などを見直す
疲れやストレスを軽減させるためには、睡眠や食事などの生活習慣の改善も有効です。
特に栄養面では、ビタミンB群の継続的な摂取が効果的であるという結果も伝えられています。(参考:大正製薬「ビタミンB群とは」)
必要に応じて、食べ物やサプリメントで補うとよいでしょう。
対策⑤補助ツールを使用する

日常生活では、大きな音のある場所をなるべく避けるとともに、刺激を軽減できるアイテムを活用することが有効です。
聴覚過敏に役立つアイテムには以下のようなものがあります。
- 全体的に音量を減らしたいとき:アナログ耳栓、イヤーマフ
- 特定の音域にある音(エアコンやざわつきなど)を減らしたいとき:デジタル耳栓、ノイズキャンセリングイヤホン・ヘッドホン
これらのグッズを持ち歩くことで、苦手な音がある環境であっても、聞こえてくる音を減らすことができます。
特に耳栓はかさばらず、生活に取り入れやすいアイテムです。不調の原因が音にあるかもと思ったら、まずは耳栓を試してみるのもよいでしょう。
対策⑥周囲の人に配慮を求める
耳栓などを使って周りの音を遮断する際には、周囲の理解が必要です。
家庭や職場では、事前に自分の状態を話し、アイテムを使用する許可を取っておきましょう。
周囲へ聴覚障害のことを伝えるアイテムには、聴覚過敏保護用シンボルマークがあります。
このマークは、聴覚過敏の保護用具を使っていることと、聴覚過敏の状態の程度について周知することを目的として設計されたものです。
聴覚過敏保護用シンボルマークは、誰でも無償で印刷し、利用することができます。
シールなどにしてイヤーマフなどのグッズに貼ったり、カバンにぶら下げたりすると、あなたの症状を知らない人にも、状況を理解してもらいやすくなります。
ダウンロードは、以下のサイトから可能です。
株式会社石井マーク「聴覚過敏保護用シンボルマーク」
また、特に仕事について聴覚過敏の症状が原因で支障が出る場合は、職場側に症状を説明して理解やサポートを求めてみましょう。
- 職場での耳栓などの聴覚保護アイテムの使用について許可を得る
- 騒音の多い業務機器の担当や、通路側に近い座席となることを避ける
- 集中を要する業務の際は、なるべく声掛けを控えてもらう
ご自身の特性や症状について話すことで、合理的配慮を得られることがあります。(参考:e-Gov法令検索「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)」、厚生労働省「合理的配慮指針」、政府広報オンライン「事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化」、内閣府「合理的配慮の提供が義務化されます!」)
合理的配慮については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
聴覚過敏に悩む発達障害のある人と一緒に働く人が理解しておくべきポイント3点
この章では、聴覚過敏に悩む発達障害のある人と一緒に働く人が理解しておくべきポイントについて解説します。
身近な人と一緒に読んだり、聴覚過敏の話をするきっかけにしたりしていただければ幸いです。
ポイント①聴覚過敏の症状は、人によって異なる

聴覚過敏の症状は、人によって表れ方が異なります。つまり、必要な配慮も個々に異なるということです。
職場や家庭の環境を整える際には、どのような配慮が必要かを本人と話し合い、必要な対策をひとつずつ確認する作業が必要です。
ポイント②発達障害のある人は、集中力に特性があるケースが多い
聴覚過敏の有無に関わらず、多くの場合、発達障害のある人は、集中力にも特性が現れます。
個人差はありますが、発達障害のある人は、うまく環境に適合したときは、非常に高い集中力を発揮して仕事に取り組むため、めざましい成果を残す可能性があります。
一方で、周囲の騒音や頻繁な声掛けなどが原因で、集中力が途切れやすいこともあります。
本人が集中しやすい環境を整え、個性にあった働き方ができるように配慮してください。
ポイント③聴覚過敏・発達障害のある人への対応は、職場全体への相乗効果を生む

聴覚過敏や発達障害のある人への個別の環境調整は、職場側からすると大きな負担に感じるかもしれません。
しかし、多様性に対応した環境整備は、ほかの人にとっても働きやすい環境につながります。一人ひとりが存分に力を発揮できる環境は、職場全体の業績も向上させます。
職場全体の心理的な安全性も、きっと高まっていくことでしょう。
【無料配布】”発達障害”特化型 ストレス対策ハンドブック

- 仕事がしんどい…
- もう出社したくない…
そんな気持ちを抱えながら、仕事を続けていませんか?
発達障害のある人は、仕事や日常生活で特有のストレスを感じやすいことがあります。マルチタスクが苦手、感覚過敏、過集中による疲れなど、ストレスの要因は多岐にわたります。
こうしたストレスを放置すると、心身の健康を損ね、仕事のパフォーマンスにも影響を及ぼすことがあります。
本ハンドブックでは、発達障害のある人が感じやすいストレスの原因と、その対処法を詳しく解説します。
また、ストレスマネジメントの自己評価ができるチェックリストも掲載しています。日々の生活習慣を振り返る際にご活用ください。
- 発達障害の特性とストレスの関係をわかりやすく解説
- 「なぜ自分はこんなに疲れるのか?」を理解するヒント
- ストレスの対処法を確認できるチェックリスト
- 感覚・思考・行動・環境別のストレス対処法
- 明日から使えるセルフケアの実践アイデア
- 発達障害の診断がある、もしくは発達障害グレーゾーンの人
- 自分は発達障害かもしれないとお悩みの人
- 仕事や日常生活での疲れがなかなか抜けない人
- 自分に合ったストレス対処法が見つからず悩んでいる人
- 頑張りすぎて燃え尽きることを繰り返している人
- リンクから申し込みフォームにアクセス
- 簡単なフォームに入力
- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り
- URLから資料を取得!
- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。
- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。
- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。
また、発達障害の特性によるストレスへの対処法については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ:あなたに合った対策を取ってください

生活の中の音を苦痛に感じる聴覚過敏は、仕事の効率や体調に大きな影響を及ぼします。
病院を受診したうえで耳栓などのアイテムの活用を検討するなど、特性にあった対策を取ってください。
それでもうまくいかないときは、周囲の人に相談し、働きやすい環境を整えましょう。サポート機関の支援を受けるのもオススメです。
聴覚過敏そのものを直す手段はありません。環境を整え、自分自身の個性にあった生活環境を作っていきましょう。
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)もお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
聴覚過敏とは何ですか?
聴覚過敏とは、音に対する感覚過敏のことです。聴覚過敏のある人は、必要な音を選別することが苦手です。一般的な人が無意識に行っている聞き取るべき音の取捨選択がうまくできず、常に脳が疲労を感じやすい状態にあるのです。
詳細については、こちらで解説しています。
聴覚過敏に悩む発達障害のある人ができる対策を教えてください。
以下が考えられます。
- 医療機関に相談する
- 騒がしい場所や時間帯を避ける
- 外で活動する時間の目安を決める
- 食事や睡眠などを見直す
- 補助ツールを使用する
- 周囲の人に配慮を求める
詳細については、こちらで解説しています。
監修志村哲祥
しむら・あきよし。
医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。
臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。
【著書など(一部)】
『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』
他、学術論文多数
日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧
時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
監修角南百合子
すなみ・ゆりこ。
臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→