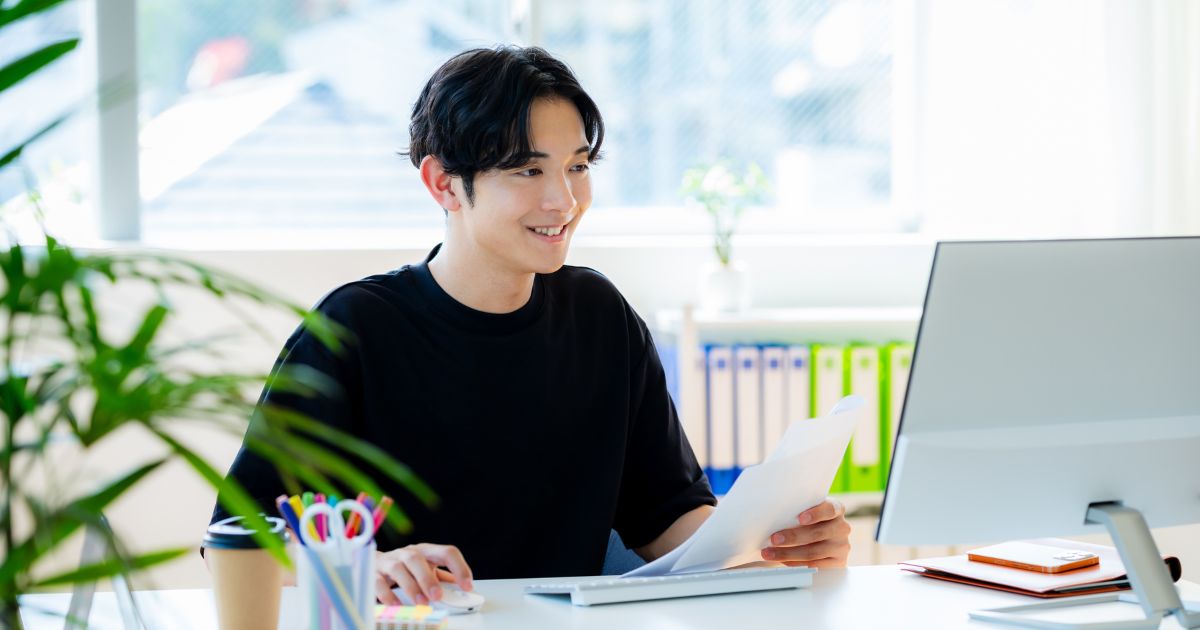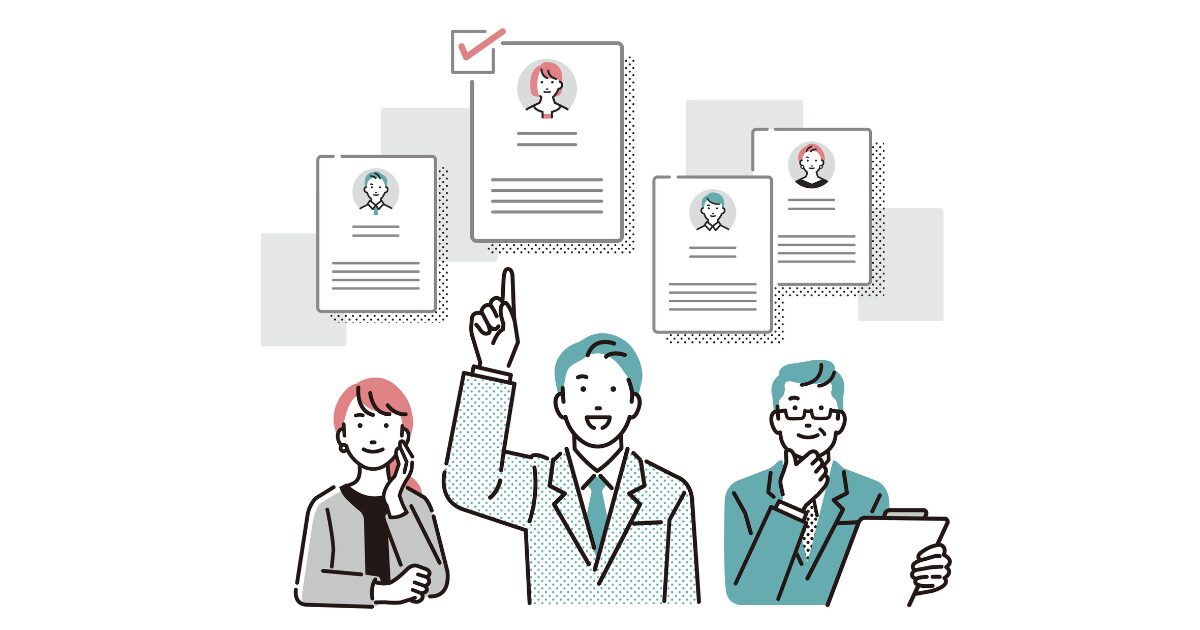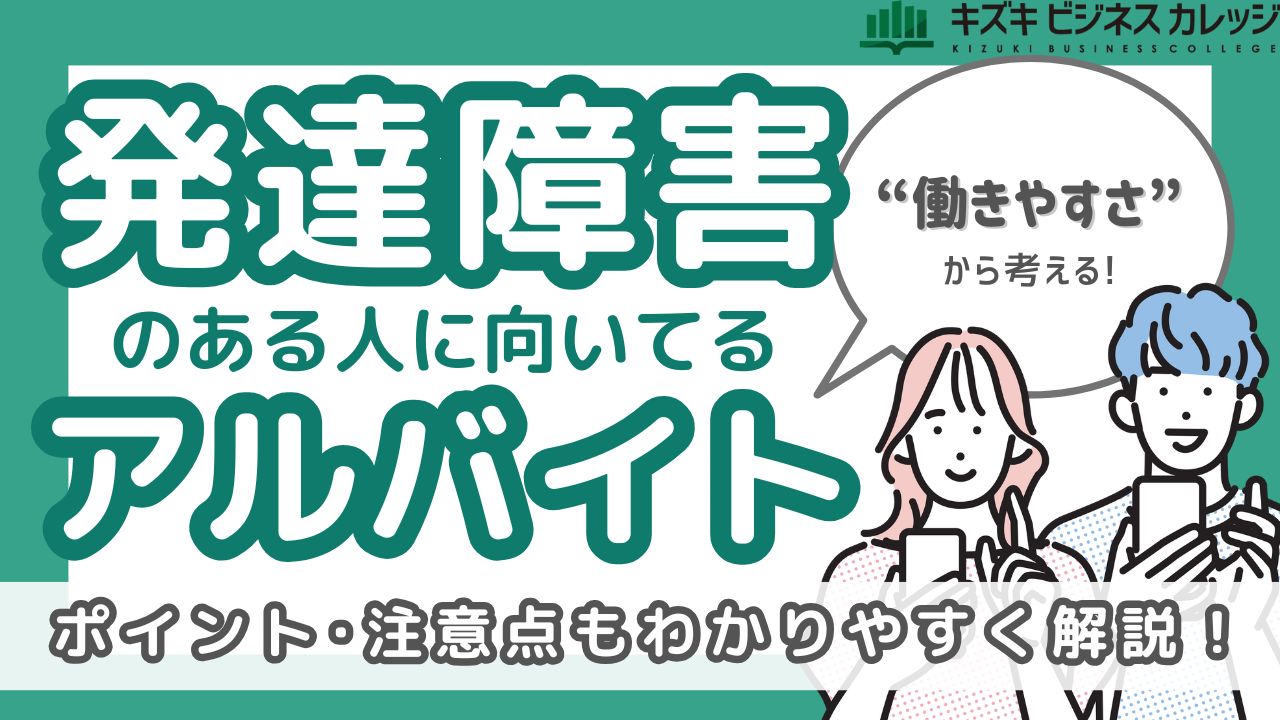発達障害のある私が自立する一歩を踏み出すまでの物語 就労移行支援事業所の利用体験談を紹介

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)利用者の不二麟太郎(仮名)です。。
発達障害のあるあなたは、働き方などに関するお悩みを抱えていませんか?
もしかしたら、大人になってから発達障害に気づき、戸惑いも抱えているのかもしれませんね。そして、自立したいと思っているのでしょう。
筆者自身、大人になってから発達障害の診断を受けました。
診断を受けた当時は、「これから、どのような働き方をすればよいのだろうか...」と、すごく悩みました。
このコラムでは、発達障害のある私が自立する一歩を踏み出すまでの体験談を紹介します。
発達障害のある私が自立に向けて考えたことや、就労移行支援事業所で取り組んでいることなどをお話します。
お悩みを抱えている発達障害のあるあなたの自立に、少しでも参考になれば幸いです。
自立したい発達障害のあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
きっかけは異動〜働くなかで顕在化した発達障害の特性〜

私が発達障害の診断を受けたのは、大学卒業後、日本料理のお店で料理人として働いていた社会人2年目のときです。
社会人1年目に働いていた日本料理のお店は、板前の店長と私の2人で切り盛りする小規模なお店でした。
そんなに忙しいお店ではなく、自分のペースで仕事ができるので、店長からも仕事ぶりを評価してもらえていました。
そんな中、社会人2年目になり、規模が大きく集客数も多い系列の本店に異動することになったんです。
本店は、それまでに働いていたお店に比べて、お店の規模や従業員の数、料理のクオリティや品数など、なにもかもが違いました。
それまでより仕事のスピードや頭の回転の速さ、仕事の優先順位づけについての重要性が高まったのです。
そこで、それまで潜在的にはあっても気がつかなかった発達障害の特性が一気に顕在化しました。そして、社会生活に支障をきたすようになったのです。
仕事がつらくて逃亡〜発達障害の診断を受けるに至った経緯〜

発達障害の特性と多忙という環境要因によって、私は、以下のような状態になりました。
- 注文が重なるとパニックになる
- 仕事の優先付けができない
- マルチタスクができない
こうしたことが原因で私は、料理長から叱責されることが多くなりました。
状況を改善したい一心で、誰よりも早く出勤してその日の予約を書き出して頭に入れたり、休憩時間を取らずに夜営業の準備をしたりと、私なりに努力をしました。それでも、臨機応変な対応は一向にできるようになりませんでした。
料理長から「お前どこかおかしいんじゃないか?」「本当に大学を卒業したのか?」などと厳しい言葉で叱責される度に、「自分でもどこかおかしいのかもしれない...」と感じるようになりました。
当時の私は不眠が続いたり、原因不明の嘔吐や蕁麻疹(じんましん)の症状が現れたりするようになっていました。いま思い返すと、発達障害による二次障害が出ていたんだと思います。
毎日の仕事がつらかった私は、インターネットで「仕事 臨機応変 対応 できない」などと検索しました。
すると、発達障害に関するページを見つけたのです。その内容を読んだことで、「私もこれだ!」と感じました。
さっそく、私は病院で発達障害の検査を受けました。ですが、その結果が出るのを待たずして、仕事へのストレスが限界に。ある朝、私は出勤しないで仕事から逃亡しました。両親が警察に捜索願を出す事態にまで発展したのです。
結局、仕事はそのまま退職することになりました。
そして、退職後に検査結果が出ました。私の特性には、広汎性発達障害(現:ASD)という診断名がついたのです。
いつかは再び自立したい〜就労移行支援事業所を利用しようと思った理由〜

仕事を辞めてから、しばらく休養することにしました。
ベッドの上で横になりながら考えたことは、「これからどうしようか」ということでした。
当時の私は、「仕事を逃げ出して職場の人たちや家族に迷惑を掛けた」とトラウマになっていたため、すぐに就職活動をすることは考えられませんでした。「働きたい...でもすぐには無理だ...」という心境です。
そんなときに、主治医から就労移行支援事業所の利用を提案されました。
調べてみると、就労移行支援事業所とは、精神障害や発達障害などのなんらかの病気・障害のある人を対象に、働くために必要な知識と能力を高めるサポートをしてくれる支援機関であることがわかりました。
「いつかは再び自立したい」と思っていた私は、就職するためのステップとして、就労移行支援事業所を利用してみようと思いました。
さらに調べるうちに、私の家のすぐ近くにも就労移行支援事業所があることもわかり、見学に行ってみることにしたのです。
いくつか体験した上で決めた方がいい〜複数の就労移行支援事業所の見学で感じたこと〜

まずは、就労移行支援事業所がどんなところか一度確認するため、家から自転車で15分程の距離にある就労移行支援事業所に行ってみました。
そこは内装がとてもカラフルで、なんだかすごくワクワクしました。
その就労移行支援事業所は、部屋に入退室するときの挨拶やの徹底など、事細かにルールが決められていたのが印象的でした。また、就職活動を意識して、毎週火曜日はスーツを着用することを義務づけている点も、その就労移行支援事業所の特色だったように思います。
私は、その就労移行支援事業所に体験入所してみました。
1週間の体験を終え、本当に入所しようか悩んでいると、スタッフさんは、「ほかにもたくさんの就労移行支援事業所があるから、いろいろ体験してから決めた方がいいですよ」と、アドバイスをくれました。
その言葉に勇気づけられて、私は、ほかの就労移行支援事業所も体験することにしました。
次に行ったのは、主に都内に展開している人気のある就労移行支援事業所です。その人気ぶりは、枠が開いて通所できるようになるまでに、3か月かかるほどでした。
その就労移行支援事業所は、発達障害に特化したプログラムを行っており、実際に会社で働くことを想定した訓練が多いような印象でした。また、150社を超える企業と連携しており、利用者がその就労移行支援事業所独自の求人を利用できる点が人気の理由だったように思います。
その次に体験した就労移行支援所は、とにかく自己理解のプログラムに力をいれていました。
講師がホワイトボードの前に立ち、まるで本当の学校のように講義を行っていた点が印象的でした。
3つの就労移行支援事業所の体験を通じて感じたことは、それぞれの事業所によって、取り組んでいることも雰囲気も年齢層も多種多様だということです。
また、同じ運営元であっても、個別の就労移行支援事業所によって、雰囲気が大きく異なっていると感じました。
「自分にあった就労移行支援事業所を見つけるためには、さらにいくつかの就労移行支援事業所を体験した上で決めた方がいいかもしれない」。そう考えた私は、もう少し、ほかの就労移行支援事業所を見学してみようと決めました。
おそるおそる参加した当事者会〜自分に合った就労支援事業所との出会い〜

ほかの就労移行支援事業所の見学を検討していたあるとき、都内のカフェで「発達障害を語る会」という発達障害のある人の当事者会が開催されることをSNSで知りました。
当時、参加者を募集していた回のテーマは、「発達障害×就労」。次の働き方を模索していた私は、強烈に興味を惹かれました。そして、おそるおそる会に参加してみることにしたのです。
実際にその会に参加すると、ほかに参加していた発達障害のある女性が、ある就労移行支援事業所の紹介をしていました。
その就労移行支援所こそが、現在私が通うキズキビジネスカレッジ(KBC)だったのです。
キズキビジネスカレッジ(KBC)では、会計、プログラミング、英語、マーケティングなどの専門スキルに特化した講義を受けられるとのことでした。
私は、「うつ病や発達障害による離職期間をポジティブな時間に変える」というキズキビジネスカレッジ(KBC)の理念と、その女性の熱弁に魅了されたことをよく覚えています。
当時は開設まもない就労移行支援所でしたが、「ここに通いたい!」と強く思い、体験入所をした上で通所することに決めました。
ピアサポートを仕事にしたい!~見つけた将来の夢~

キズキビジネスカレッジ(KBC)に通所することを決めてから入所するまでの期間、次の働き方を考えながら、発達障害の当事者でもある株式会社キズキ社長の安田祐輔氏の著書『暗闇でも走る』をなんとなく読みました。(参考:安田祐輔『暗闇でも走る』)
さらに、その本の中で紹介されていた、株式会社マザーハウス代表取締役兼チーフデザイナーの山口絵理子氏の著書『裸でも生きる〜25歳女性起業家の号泣戦記〜』も読みました。(参考:山口絵理子『裸でも生きる ~25歳女性起業家の号泣戦記~』)
どちらの書籍についても、「社会や人のためにこんなにもがんばっている人がいるのか」と感銘を受けました。
そして「自分も社会の役に立ちたい」という漠然とした気持ちがふつふつと湧いて、「発達障害の診断を受けた自分だからこそできることは何か」を考えるようになりした。
考えるうちに、それは、「当事者として、同じように発達障害の特性で悩んでいる人をサポートする仕事だ」と思うようになったんです。
一般的に、同じ生きづらさを抱える人同士がお互いに支え合う活動のことをピアサポートと言います。
私は、「ピアサポートを自分の仕事にしたい!」と、明確な目標を持って、キズキビジネスカレッジ(KBC)に入所しました。
自立する上で自分の特性を知る重要性〜就労移行支援事業所で取り組んでいること〜

発達障害の特性に関連して離職した人がもう一度社会復帰するにあたって、本当に重要なことは何でしょうか?
それは、自分の発達障害の特性を知り、なぜ前の仕事が続かなかったのか、どのような対策をすれば発達障害の特性をカバーすることができるのかを知ることだと思います。
なぜなら、自分の発達障害の特性を知らなければ、その特性にあった対策をできない上、適切なサポートを職場に求めることができないからです。
自分の発達障害の特性を理解せずに社会復帰できたとしても、以前の職場と同じ失敗を繰り返す可能性が高いでしょう。
キズキビジネスカレッジ(KBC)では、「自己理解講座」という、文字通り、自分の特性について理解するための講義が開講されています。
その講義で、私は、「聴覚から入ってくる情報を処理することが苦手だ」という特性があることを理解しました。さらに、情報が複雑になればなるほど、頭の中でパニックになる傾向に気が付いたのです。
この発達障害の特性に関する気づきは、私が料理人として働いていたとき、オーダーが重なるとよくパニックになっていた経験と合致します。
これは私の発達障害の特性の一つであり、自分一人の努力では対処しきれないことがあったのかもしれないと、不甲斐なかった料理人時代の自分を許容することができるようになりました。
ほかにも、苦手だった電話対応に対して電話対応シートを作ることや、相手の言った言葉を復唱し自分のペースに巻き込むというやり方で対策を立てることができることを知りました。
自分の苦手を知り、苦手なことへの対応策を練ることができたことは、社会復帰する上での心の安心につながったように思います。
自分でできることを模索中〜スキル向上に向けて取り組んでいること〜

現在の私は、キズキビジネスカレッジ(KBC)に通所しながら、病気・障害のある人に対して、ピアサポートで寄り添える支援員を目指して、日々スキル向上に努めています。
いまスキル向上に向けて取り組んでいることは、さまざまな業務に活かせるWord、Excel、PowerPointなどのPCスキルの向上です。
実際に就労移行事業所のスタッフさんを見ても、一人一台パソコンを持っていて、利用者の活動を報告書にまとめたり、講座の資料をPowerPointで作ったりと、PCスキルが求められる仕事がたくさんあることがわかります。
どんなに頭がいい人でも、どんなに偏差値が高い大学を出ている人でも、当事者や似た経験をした人でなければ、本当の意味でのつらさや大変さはわからないと、私は思っています。
似た体験をしているという経験は、自分の病気・障害で困っている人に対して、より一層寄り添ったサポートができると考えています。
ピアサポートの支援員という仕事は、発達障害という、今まで自分がマイナスに考えていた特性をプラス変えることができる仕事のはずです。
ただ、具体的に自分にどんな支援ができるのかは、今の時点では模索中です。
一口に障害のある人と言っても、十人十色な困りごとに対して、一人ひとり違った支援が必要だとも実感しています。
いろんな人に寄り添ったサポートができるように、元ひきこもりの人が書いた本や元不登校の人が書いた本など、生きづらさを感じていた人が書いた本を積極的に読むようにしています。
最近は、VRを使っていろいろな障害のある人の世界を実際に体験できるということも知りました。こうしたツールや体験を通じて、さまざまな障害のある人の気持ちが理解できるようになりたいと思っています。
発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)
発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。
- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)
- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)
- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)
同じ診断名でも、人によって多様な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人は、ほかの発達障害が併存している可能性もあります。
発達障害の概要や種類、原因、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ〜一人だけでチャレンジする必要はありません〜

発達障害の診断を受けてすぐの頃、私は、次の働き方について考えるために、自立した生活を送る発達障害のある当事者の体験談をインターネットなどで調べたりしていました。
このコラムは、当時の私と同じように、「発達障害に関連して離職して、これから先どうすればいいのかわからない」と困っている人たちの参考になればと思って書きました。
発達障害のある人が自立するためには、一人だけでチャレンジする必要はありません。
現在は、さまざまなタイプの就労移行支援事業所があります。あなたの特性や、あなたの考える自立に合う居場所もきっとあります。
まずは、気になる就労移行支援事業所を探して、自分に合いそうな就労移行支援事業所を見つけましょう。
あなたの自立を、心から祈っています。
発達障害とはなんですか?
発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。。
詳細については、こちらで解説しています。
どうすれば発達障害のある私は、自立できますか?
発達障害のある人が自立するためには、一人だけでチャレンジする必要はありません。現在は、さまざまなタイプの就労移行支援事業所があります。あなたの特性や、あなたの考える自立に合う居場所もきっとあります。まずは、気になる就労移行支援事業所を探して、自分に合いそうな就労移行支援事業所を見つけましょう。
詳細については、こちらで解説しています。
監修志村哲祥
しむら・あきよし。
医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。
臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。
【著書など(一部)】
『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』
他、学術論文多数
日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧
時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
監修角南百合子
すなみ・ゆりこ。
臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→