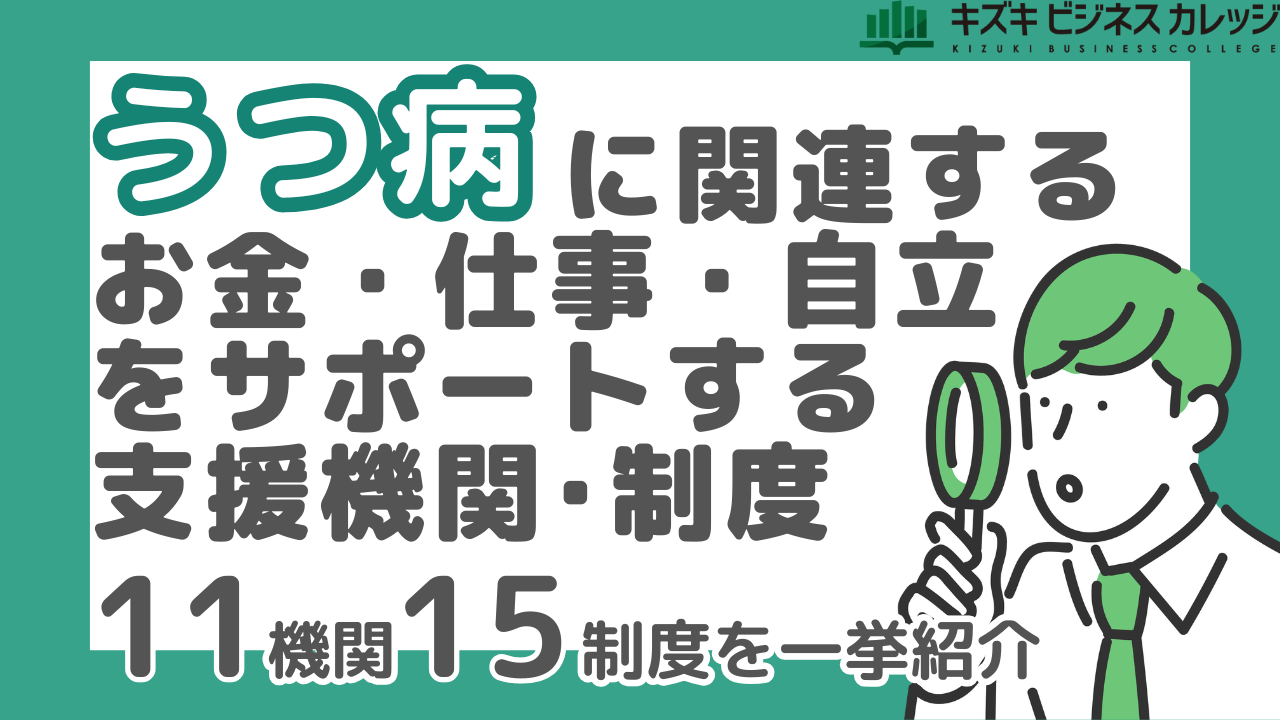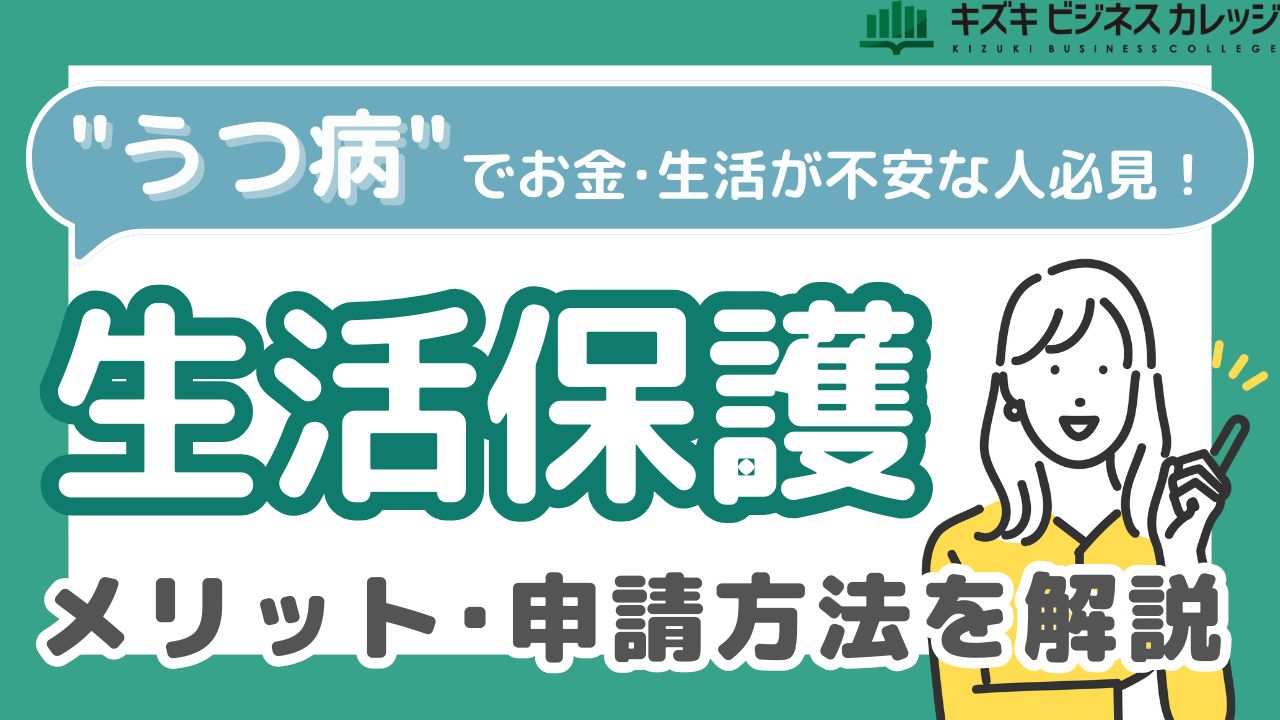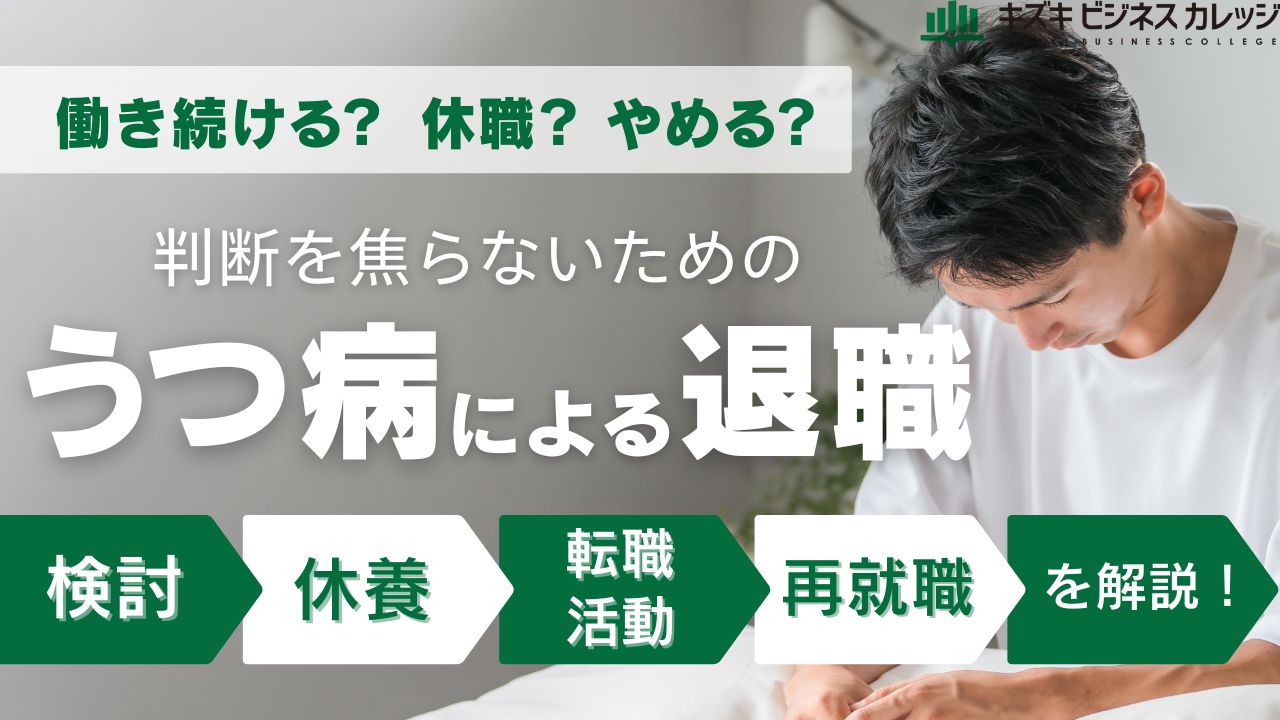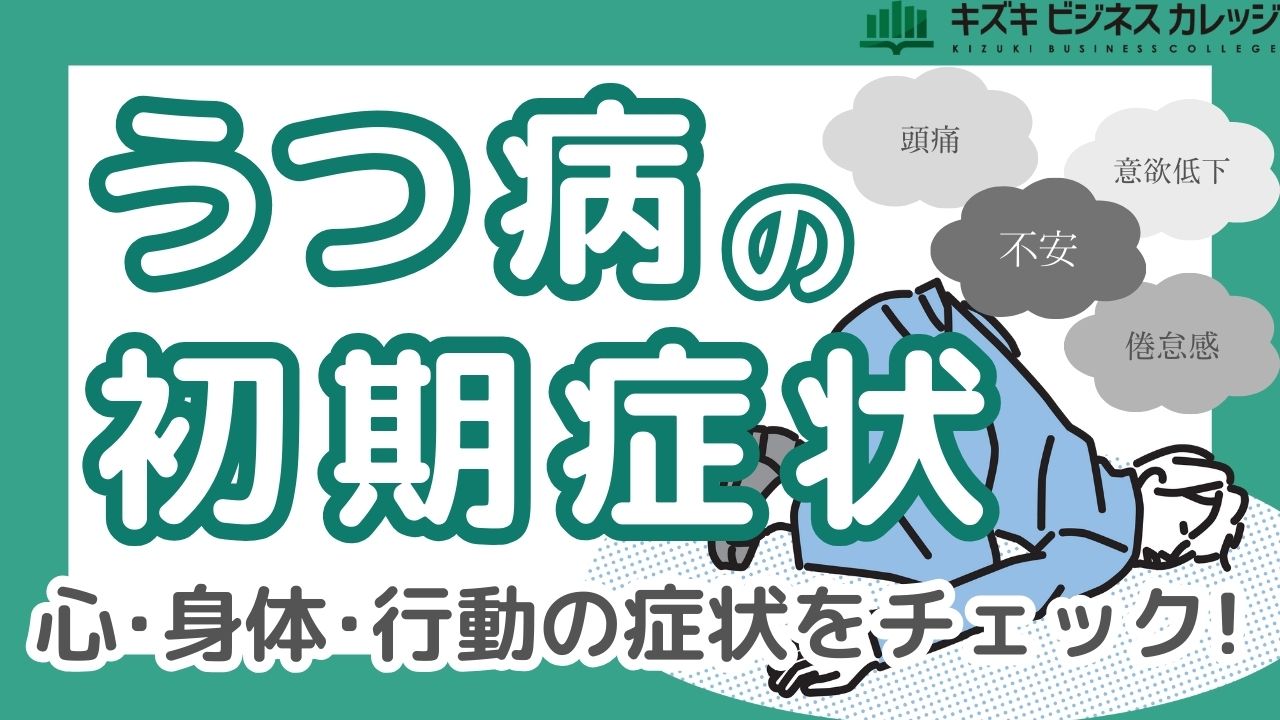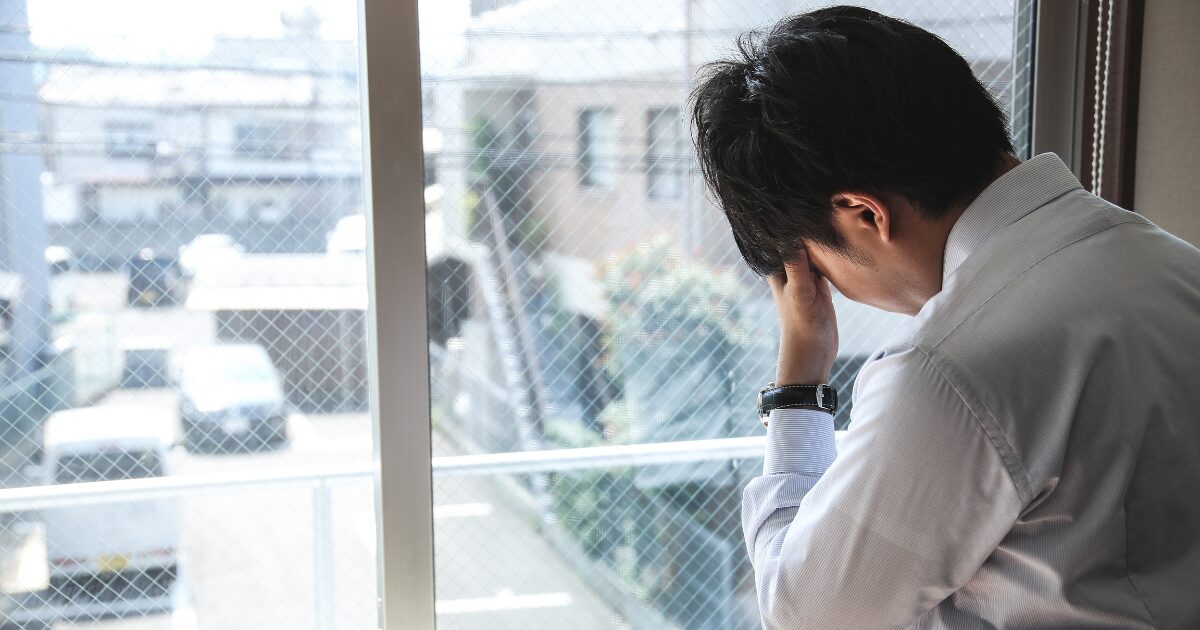うつ病で退職した人が失業保険を受給する方法 受給条件や申請方法を解説【ガイドブック配布中】
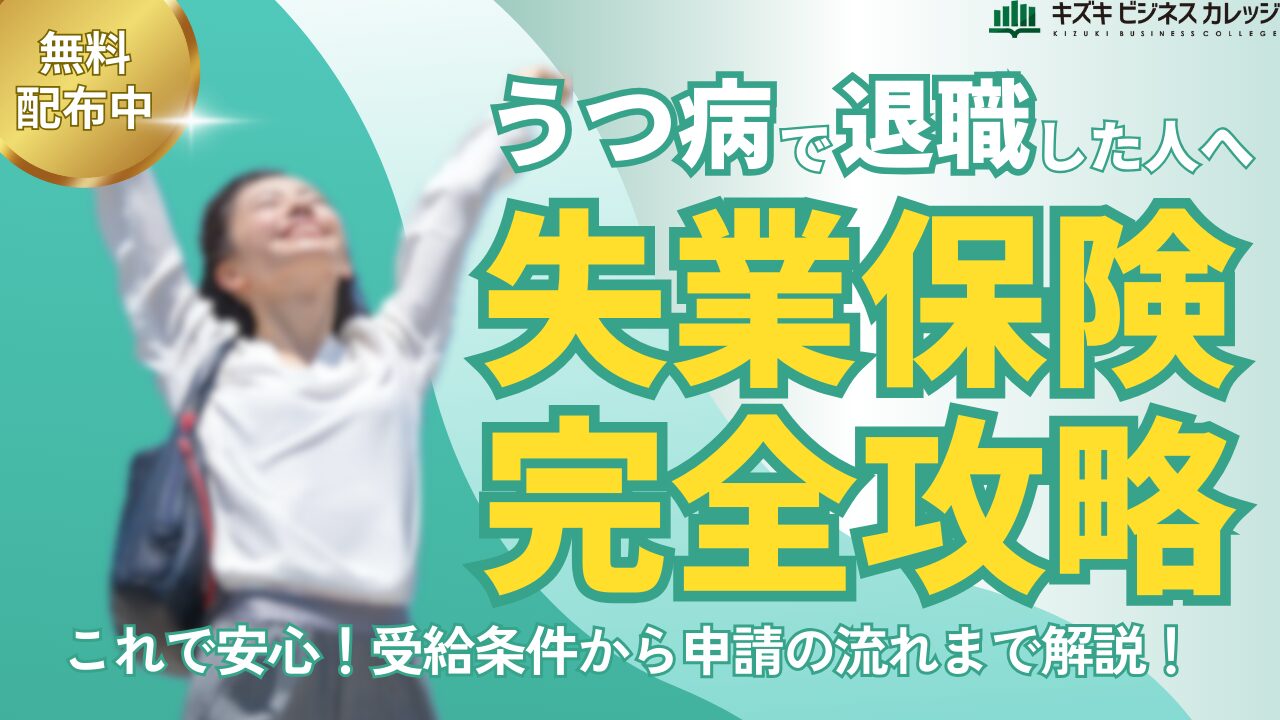
こんにちは、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
うつ病やメンタル不調で退職し、「これからの生活が不安…」「失業保険ってもらえるの?」と悩んでいませんか?
そんな不安を抱える人に向けて、就労支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)は、失業保険の基本から申請手続きまでをやさしく解説した完全攻略ガイドブックを無料で公開しました。こちらからダウンロードください。
2025年4月の法改正の情報を盛り込みアップグレード!受給条件や必要書類、支給額の目安、申請の流れなど、うつ病などで退職した人が知っておくべき情報を1冊にまとめています。
PDF形式で、どなたでも無料でダウンロードいただけます。ぜひ以下ボタンからダウンロードください。
なお、このコラムでは、退職した、または退職を検討しているうつ病のある人に向けて、うつ病で退職する人が失業保険を受給する方法や退職するときの流れ、失業保険の概要などについて解説します。あわせて、うつ病のある人が失業保険以外に利用できる支援制度を紹介します。
失業保険の申請を検討しているうつ病のあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
うつ病で退職した人が失業保険を受給する方法
この章では、うつ病で退職した人が失業保険を受給する方法について解説します。
前提:医師や支援機関などに相談しましょう

失業保険(失業手当、雇用保険給付)の仕組みには、複雑な部分があります。
退職の理由やうつ病の状態などによって、受給期間を延長できる可能性や、受給できない可能性もあります。また、失業保険(失業手当、雇用保険給付)の内容は、随時改定・改正されます。
実際のあなたが失業保険(失業手当、雇用保険給付)を利用できるかどうかは、主治医や専門家、支援機関に相談してみてください。
今すぐ働けるうつ病で退職した人の場合
今すぐ働けるうつ病で退職した人は、ハローワークで申請して、求職活動を行うことで、失業保険(失業手当、雇用保険給付)を受給できます。
また、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は、2か月の給付制限期間なしに受給できます。
失業保険(失業手当、雇用保険給付)を受給できる、今すぐ働けるうつ病のある人でも、失業保険(失業手当、雇用保険給付)以外の支援制度を利用できる可能性があります。併用することでより安心できるようになるでしょう。
今すぐ働けないうつ病で退職した人の場合

うつ病で退職した人が今すぐ働けるかどうかは、状況によって異なり、医師の判断が必要な場合もあります。
うつ病の症状が重く、今すぐ働けないと判断された場合、失業保険(失業手当、雇用保険給付)を受給できない可能性があります。
そのため、「うつ病の症状がありつつ、失業保険(失業手当、雇用保険給付)を受給したい人」は、自分がすぐに仕事ができる状態かどうか、医師に相談して検討する必要があります。
うつ病の症状が重く、今すぐ働けない人は、以下のような方法を考えましょう。
- 失業保険(失業手当、雇用保険給付)以外の支援制度の利用を検討する
- 失業保険(失業手当、雇用保険給付)の受給期間の延長手続きを行う
就職困難者の認定を検討する
失業保険(失業手当、雇用保険給付)は、働ける状態になれば改めて申請できます。また、うつ病のある人が利用できる支援制度は失業保険(失業手当、雇用保険給付)以外にもあります。
失業保険(失業手当、雇用保険給付)を受給できなさそうだからといって、不安になる必要はありません。
補足:長時間労働やパワハラでうつ病になり退職した人の場合

長時間労働やパワハラなどが原因でうつ病になり退職を余儀なくされた人は、特定受給資格者に該当することがあります。
特定受給資格者に該当すると、失業保険(失業手当、雇用保険給付)の受給日数が多くなり、受給開始日が早くなるなどの優遇を受けることができます。
特定受給資格者に該当すると思う場合は、退職前にパワハラなどのうつ病になった原因があることを職場に伝え、会社都合の退職にする必要があります。
ただし、以下のような場合、ハローワークで退職理由を会社都合に変更できる可能性があります。
- 職場に伝えづらい場合
- 職場に伝えても対応してもらえない可能性がある場合
- どうしても早く職場から離れたいため、自己都合の理由で退職した場合
職場が長時間労働やパワハラを認めず、裁判で争わなくてはならないケースもあります。
必要に応じて、事前に弁護士などにも相談しましょう。労災認定を受けた場合は、労災保険や慰謝料を受け取れる可能性もあります。
うつ病の症状がある状態で職場と話し合うことは、大変な場合もあるでしょう。
特定受給資格者にすぐに該当しない場合でも、失業保険(失業手当、雇用保険給付)以外の支援制度を利用したり、体調がよくなってから職場に伝えることは可能です。
実際の対応は、体調を見つつ、専門家や支援機関などと相談して検討しましょう。
失業保険とは?

失業保険(失業手当、雇用保険給付)とは、失業・退職した人が就職するまでの一定期間に給付金を支給する支援制度のことです。正式名称は、基本手当です。(参考:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」、ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」、ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」)
また、失業保険は失業した人の金銭面の不安を軽減し、求職活動に専念できるようにすることを目的としています。(参考:厚生労働省「基本手当について」)
そのため、失業保険は、退職後に就労できる状態の場合に利用できます。具体的な受給金額や受給期間は、その人の退職の状況などによって異なります。
申請は、お住まいの自治体に設置されているハローワークで行なえます。
失業保険については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
失業保険の傷病手当とは?
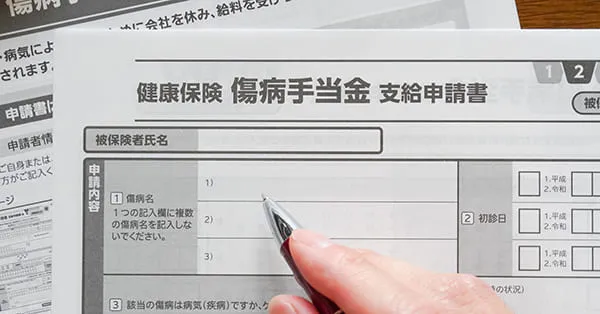
病気やケガ、障害によって15日間以上続けて求職活動ができない場合、つまり失業保険(失業手当、雇用保険給付)を受給できる状態ではない場合、失業保険(失業手当、雇用保険給付)の傷病手当を受給することができます。
なお、失業保険(失業手当、雇用保険給付)の傷病手当は、健康保険(社会保険)の傷病手当金とは異なります。
また、失業保険(失業手当、雇用保険給付)の傷病手当と健康保険(社会保険)の傷病手当金は同時に受給できない点には注意してください。また、公務員は失業保険の対象でとはならないため、注意してください。
失業保険の受給条件
失業保険(失業手当、雇用保険給付)の受給条件は、以下のとおりです。
- 離職状態にある
- 退職までの一定期間、雇用保険に加入していた
- 今すぐ働く意思があり、求職活動を行っている
ここで言う求職活動とは、企業への面接訪問などに限らず、窓口相談や職業訓練も含まれています。それらの活動ができる場合、就労できない状態の人でも、条件を満たすことは可能です。
以下のような人は、受給条件を満たしています。
- 積極的に就職しようとする意思がある人
- いつでも就職できる健康状態や環境などである人
- 積極的に仕事を探しているにも関わらず、現在職業に就いていない人
逆に、以下のような人は、受給条件を満たしていないため、失業保険(失業手当、雇用保険給付)を受給できません。
- 妊娠・出産・育児などのために、すぐに就労できない人
- 病気・ケガ・障害などのために、すぐに就労できない人
- 就職するつもりがない人
- 家事に専念している人
- 学業に専念している人
- 会社などの役員に就任している人
- 雇用保険に加入していなかった自営業の人
失業保険の受給金額

失業保険(失業手当、雇用保険給付)の受給金額は、ハローワークに提出する離職票に基づいて、以下のように算出されます。
- (離職前6か月の給与の総支給額の合計÷180)×給付率(50〜80%)
給与の総支給額とは、税金や社会保険料などが控除される前の、基本給と役職手当や通勤手当などの各種手当を合計した金額のことです。ただし、賞与などは除きます。
給付率は、およそ50〜80%です。相対的に賃金の低かった人ほど高い率になります。ただし、60歳〜64歳の場合、45〜80%になります。
- 月額平均約15万円の給与だった場合、支給額は約11万円
- 月額平均約20万円の給与だった場合、支給額は約13.5万円
失業保険(失業手当、雇用保険給付)の受給金額の上限額は、年齢によって異なります。
2022年8月1日時点の、1日あたりの上限額は、以下のとおりです。
- 30歳未満:6835円
- 30歳以上45歳未満:7595円
- 45歳以上60歳未満:8355円
- 60歳以上65歳未満:7177円
なお、65歳以上の人が失業した場合には、失業保険(失業手当、雇用保険給付)ではなく高年齢求職者給付金が支給されます。高年齢求職者給付金の場合、年金と併用して受給することも可能です。
失業保険を申請する流れ・手続き
失業保険(失業手当、雇用保険給付)の申請方法は以下のとおりです。(参考:ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」)
- 離職票を用意する
- ハローワークで申請手続きをする
- 7日間の待期期間と2か月の給付制限期間の経過を待つ
- ハローワークの給付説明会に行く
- ハローワークで、決められた回数の求職活動をする
- 失業の認定を受ける
- 口座に給付金が振り込まれる
職場によっては、離職票の発行に時間がかかることもあります。早めに準備しましょう。
ハローワークでの申請手続きの後、7日間の待機期間が設けられます。待機期間中は、アルバイトを含む就労が禁止されます。注意しましょう。
失業保険(失業手当、雇用保険給付)は、今すぐ働く意思があることが受給条件であるため、決められた回数、ハローワークで求職活動をする必要があります。
転職エージェントなどのハローワーク以外の支援機関で求職活動している人の場合、実際には「ハローワークでの求職活動が形式的になる」ことも珍しくないようです。
また、現実として失業状態が続いている場合でも、継続して受給するためには、失業の認定を原則として4週間に一度受ける必要があります。
失業保険の受給対象者
この章では、失業保険の受給対象者について解説します。
受給対象者①自己都合退職者
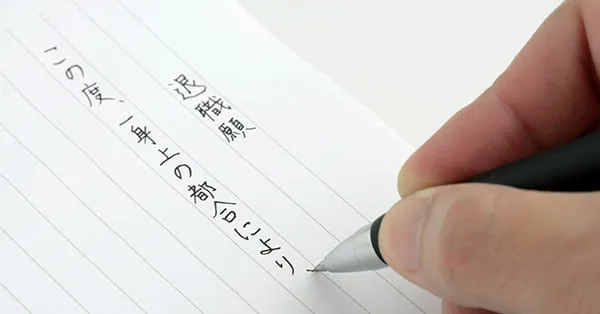
自己都合退職者とは、病気や転職などの自己都合の理由で退職した人のことです。
退職時に「一身上の理由」と書く場合、自己都合退職者に該当します。
うつ病を理由とする退職の場合は基本的に、自己都合退職者に該当します。ただし、個別の状況やハローワークの判断によって、それ以外に該当することもあるそうです。
受給対象者②特定理由離職者
特定理由離職者とは、健康上の理由や妊娠・出産・育児、介護、家庭の都合などの正当な理由により、自分の意思で退職した人のことです。
定年後、休養してから働きたい人も特定理由離職者に該当します。
受給対象者③特定受給資格者

特定受給資格者とは、企業の倒産や解雇などの職場都合で退職した人のことです。
長時間労働やパワハラなどが原因で退職を余儀なくされた人も、特定受給資格者に該当することがあります。
失業保険の受給期間
失業保険(失業手当、雇用保険給付)の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。
受給日数(給付日数)は、勤続年数などによって異なります。
また、退職の状況により、受給期間(給付日数)は以下のように異なります。
- 自己都合退職者の場合:90〜150日
- 特定理由離職者の場合:90〜150日
- 職場に契約更新を拒まれた特定理由離職者の場合:90〜330日
- 特定受給資格者の場合:90〜330日
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の場合、所定受給日数(給付日数)は120日です。
離職した日の翌日から申請するまでに期間があく場合、受給日数(給付日数)を残していたとしても、離職した日の翌日から1年経過した日付をもって受給は終了します。
例えば、「本当ならば120日間受給できたにも関わらず、申請が遅れたため、受給開始から50日目に離職した日の翌日から1年が経過し、50日分しか受給できなかった」などのケースもありえます。
受給を考えている人は、早めにハローワークに申請しましょう。
失業保険の受給開始日

自己都合退職者の失業保険(失業手当、雇用保険給付)の受給開始日は、ハローワークで申請した日から7日間の待期期間が経過した後、2か月の給付制限期間が経過した日以降です。
以前の給付制限期間は、3か月でしたが、2022年10月以降に退職した人から、2か月に変更されています。
自己都合退職者だけでなく、過失が原因で退職などの自分に責任があって退職する場合も、2か月の給付制限期間が設けられます。
特定理由離職者や特定受給資格者の失業保険(失業手当、雇用保険給付)の受給開始日は、ハローワークで申請した日から7日間の待期期間が経過した日以降です。自己都合退職者と異なり、2か月の給付制限期間はありません。
ただし、7日間の待期期間が経過した日以降すぐに受給できるとは限りません。求職活動実績の認定が必要なため、おおむね1か月後から受給可能だと考えておくといいでしょう。
特定理由離職者の場合、受給期間を最長3年間延長することができます。受給期間を延長する場合、ハローワークへの申請が必要です。郵送や代理人による申請も可能です。
失業保険を利用する際の注意点
この章では、失業保険を利用する際の注意点について解説します。
注意点①公務員や自営業は失業保険(失業手当、雇用保険給付)の対象にならない

基本的に、公務員や自営業の人は、失業・退職・廃業しても失業保険(失業手当、雇用保険給付)の対象になりません。
自営業の人の場合、そもそも雇用保険に加入していないため、失業保険(失業手当、雇用保険給付)の対象になりません。
公務員が、失業保険(失業手当、雇用保険給付)の対象にならない理由は、以下のとおりです。
- 雇用保険に加入していない
- 国家公務員法などの法律により、失業・退職時の保障として失業保険(失業手当、雇用保険給付)を超える給付が確保される仕組みが設けられている
- 公務員以外の人と比べて雇用が安定している
ただし、郵便局などの雇用保険法の適用事業所で就労していた公務員の場合、失業保険(失業手当、雇用保険給付)を受給できる可能性があります。
また、ほかの公務員の場合、失業保険(失業手当、雇用保険給付)に相当するサポートとして、「退職手当」があります。
注意点②病気や障害の症状・特性の程度によって、就職困難者に認定されることもある
病気や障害の症状・特性の程度が重く、就労が難しそうな人は、就職困難者に認定されることがあります。
就職困難者の場合、以下のような優遇されることがあります。
- 2か月の受給制限期間がない
- 受給日数(給付日数)が長くなる
就職困難者の認定は、障害者手帳の取得が条件です。
ただし、あくまで就職困難者であるため、全く求職できない人、求職する意志のない人は対象にはなりません。
雇用保険の加入状況の確認方法

雇用保険の加入状況の確認はハローワークで可能です。
ハローワークには、雇用保険の被保険者資格取得の届出が適正になされているかどうかの確認を、労働者自らが照会できる仕組みがあります。
気になる人は、ハローワークにご確認ください。
また、一般的に、ご自分が雇用保険に加入しているかどうかは、「給与明細上で、雇用保険の名目での控除があるかどうか」で確認できます。
雇用保険の名目での控除がある場合、雇用保険に加入していると判断できます。逆に、雇用保険の名目での控除がない場合、雇用保険に加入していないと判断できます。
ただし、例外的に、「雇用保険の名目での控除があるが、実際には雇用保険に加入していない」というケースがあります。これは、いわゆる「ブラック企業」に見られるケースです。
その場合、ハローワークなどの支援機関に相談しましょう。
うつ病のある人が失業保険以外に利用できる支援制度
うつ病のある人が利用できる支援制度は、失業保険(失業手当、雇用保険給付)だけではありません。
支援制度はほかにもたくさんあります。ご安心ください。
この章では、うつ病のある人が失業保険(失業手当、雇用保険給付)以外に利用できる支援制度を紹介します。
実際のあなたが利用できるかについては、専門家や支援機関などに相談してみましょう。
失業保険(失業手当、雇用保険給付)を含めて、支援支援を利用することは、決して恥ずかしいことではありません。
各支援制度を利用しつつ、経済的に安心して、うつ病の治療・休養に専念することで、次の一歩にも進みやすくなります。
うつ病のある人が利用できる支援制度については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
補足①:失業保険(失業手当、雇用保険給付)と傷病手当金は併用できない
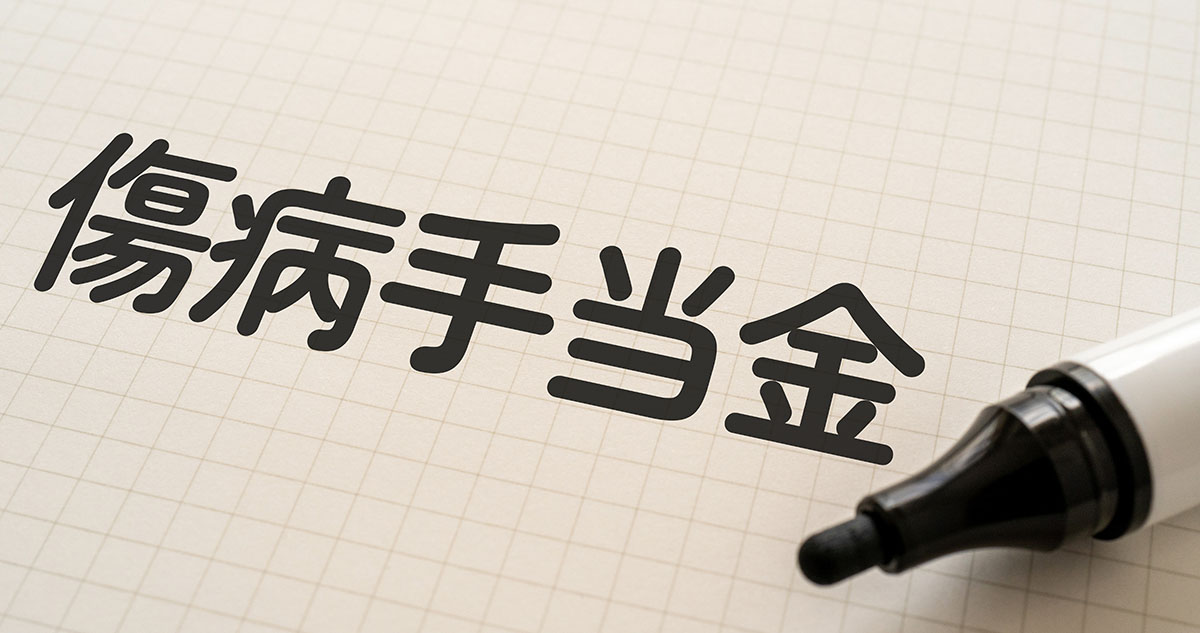
失業保険(失業手当、雇用保険給付)は、退職後に就労できる状態の場合に利用できる支援制度です。対して、傷病手当金は退職前・在職中に就労できない状態の場合に利用できる支援制度です。
そのため、傷病手当金と失業保険(失業手当、雇用保険給付)は、同時期に併用できません。
ただし、時期に応じて切り替えて受給することは可能です。
例えば、退職後も傷病手当金の受給期間があり、以下の条件を満たす場合、退職後も継続して傷病手当金を受給することは可能です。
- ①被保険者の資格喪失をした日の前日=退職日までに継続して1年以上の健康保険任意継続期間を除く被保険者期間があること
- ②退職日時点で傷病手当金を受給している、または、受給条件を満たしていること
なお、退職日に出勤・就労した場合、継続受給の受給条件を満たさなくなるため、被保険者の資格喪失した日=退職日の翌日以降の傷病手当金の受給はできません。
具体的に気になる場合は、以下のような流れができそうか、ハローワークや支援機関などに確認してみましょう。
- 在職中に、傷病手当金を申請・受給して治療
- 退職して働けないうちは、傷病手当金の受給を継続
- 働ける状態になったら、失業保険(失業手当、雇用保険給付)を申請・受給
補足②:失業保険(失業手当、雇用保険給付)と障害年金は併用できる
障害年金は、求職しながらでも働きながらでも受給できます。なお、前年度の給与が高額になると、減額・支給停止になる可能性があるため、注意してください。
年金という名前ではありますが、高齢者だけではなく、20歳以上の人なら受給できます。また、病気やケガが治るまでは、生涯にわたって受給可能です。
働く意思があり、働ける状態にある場合は、障害年金と失業保険(失業手当、雇用保険給付)を同時に利用できます。
うつ病とは?

うつ病とは、気分の落ち込みや憂うつ感、さまざまな意欲の低下などの精神的症状と、不眠、食欲の低下、疲労感などの身体的症状が一定期間持続することで、日常生活に大きな支障が生じる精神障害・気分障害のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、厚生労働省「1 うつ病とは:」、厚生労働省「うつ病に関してまとめたページ」、厚生労働省「うつ病」、国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「うつ病」、株式会社メディカルノート「うつ病について」、MSDマニュアルプロフェッショナル版「抑うつ症候群」)
また、脳の機能が低下している状態、脳のエネルギーが欠乏した状態を指し、脳の中で神経細胞間のさまざまな情報の伝達を担うセロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンなどの神経伝達物質のバランスの乱れや、感情や意欲を司る脳の働きに何らかの不調が生じているものと考えられています。
うつ病の概要や症状、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
【無料配布中】『うつ病で退職した人必見!失業保険 完全攻略ガイドブック』
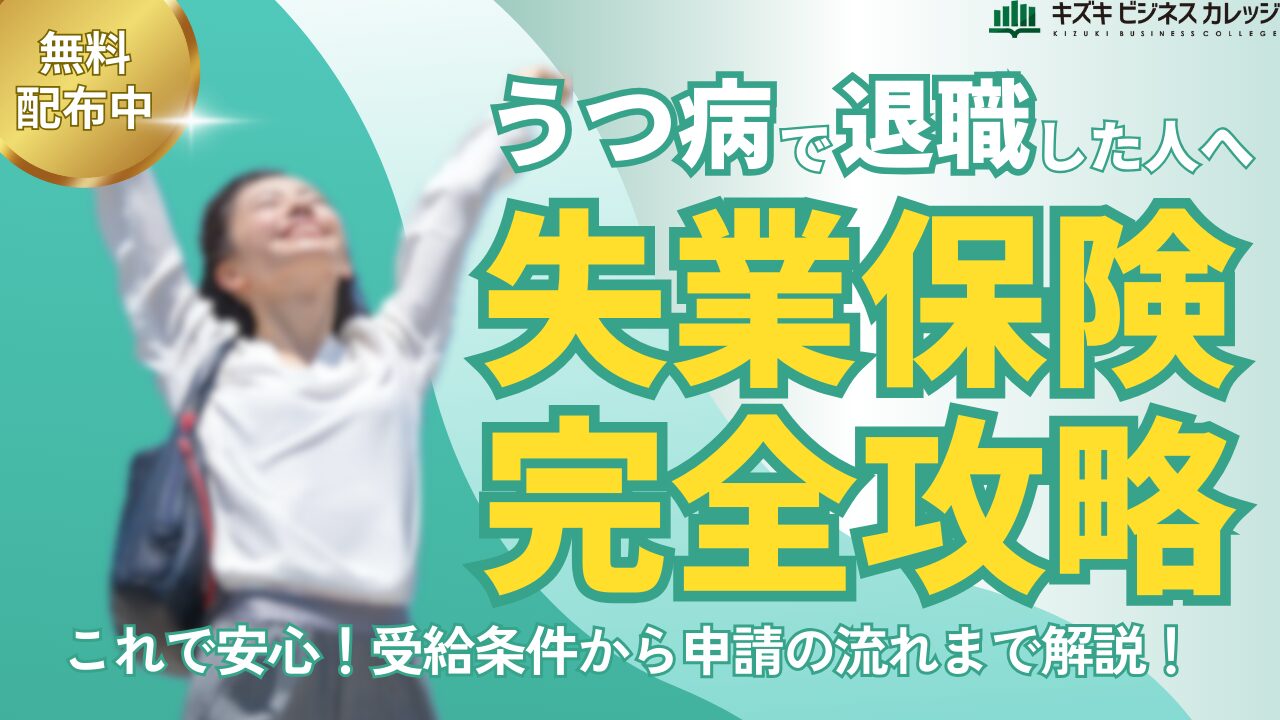
うつ病やメンタル不調により退職した場合、経済的な不安を支える制度として「失業保険(雇用保険の基本手当)」があります。
しかし、体調が万全でないなか、自分が対象かどうかを調べたり、複雑な申請を進めたりするのは容易ではありません。
実際にキズキビジネスカレッジ(KBC)にも以下のような声が数多く寄せられています。
- 申請の方法が分からない
- そもそも失業保険を受けられる状態なのか不安
- 体調に不安があっても、就職意思があれば受け取れるのか?
このような悩みに応えるべく、キズキビジネスカレッジ(KBC)では、「うつ病などで退職した人が失業保険を正しく受け取るためのガイド」を制作。
以下のような情報を、イラストや図解を交えて丁寧に解説しています。こちらからダウンロードください。
- 失業保険の概要・受給条件
- 支給額の目安
- 受給開始日・受給期間
- 申請の流れ・手続き
- よく求められる書類一覧
- 退職後すぐに確認したい3つのポイント〜「就職困難者」として認定されるケースなど〜
- 受給中の4つの注意点
- 失業保険の基本チェックリスト
- うつ病やメンタル不調で退職した人
- うつ病やメンタル不調でこれから退職を考えている人
- 退職後の生活費に不安を感じている人
- 「失業保険の手続きが難しそう」と感じている人
- 医師から「就職活動してもよい」と言われたが、何をすればよいか分からない人
- 「特定理由離職者」に該当する可能性がある人
- ご家族や支援者として、本人をサポートしたいと考えている人
以下ボタンからダウンロードをお願いします。
- コラム内のリンクから簡単なフォームに入力
- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り
- URLからハンドブックを取得
- ※ご提供には簡単なフォーム入力が必要です。
- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。
- ※本ハンドブックのダウンロード後、無断での配布・転載はお控えください。
まとめ:利用できる支援制度はほかにもたくさんあります

うつ病で退職した人や退職を検討している人は、条件に当てはまれば失業保険(失業手当、雇用保険給付)を受給できます。
また、失業保険(失業手当、雇用保険給付)以外にもうつ病のある人も利用できる支援制度はたくさんあります。
改めて、失業保険(失業手当、雇用保険給付)などの支援制度の利用は、決して恥ずかしいことではありません。支援制度を利用して、治療・休養に専念することが何よりも大切です。
実際のあなたが利用できる支援制度については、医師や専門家、支援機関などと話しつつ、具体的に探していくことをオススメします。
このコラムが、うつ病で退職した人、退職を検討している人の参考になったなら幸いです。
失業保険とは、何ですか?
失業保険(失業手当、雇用保険給付)とは、失業・退職した人が就職するまでの一定期間に給付金を支給する支援制度のことです。正式名称は、基本手当です。
詳細については、こちらで解説しています。
失業保険の受給対象者を教えてください。
監修志村哲祥
しむら・あきよし。
医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。
臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。
【著書など(一部)】
『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』
他、学術論文多数
日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧
時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
監修角南百合子
すなみ・ゆりこ。
臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→