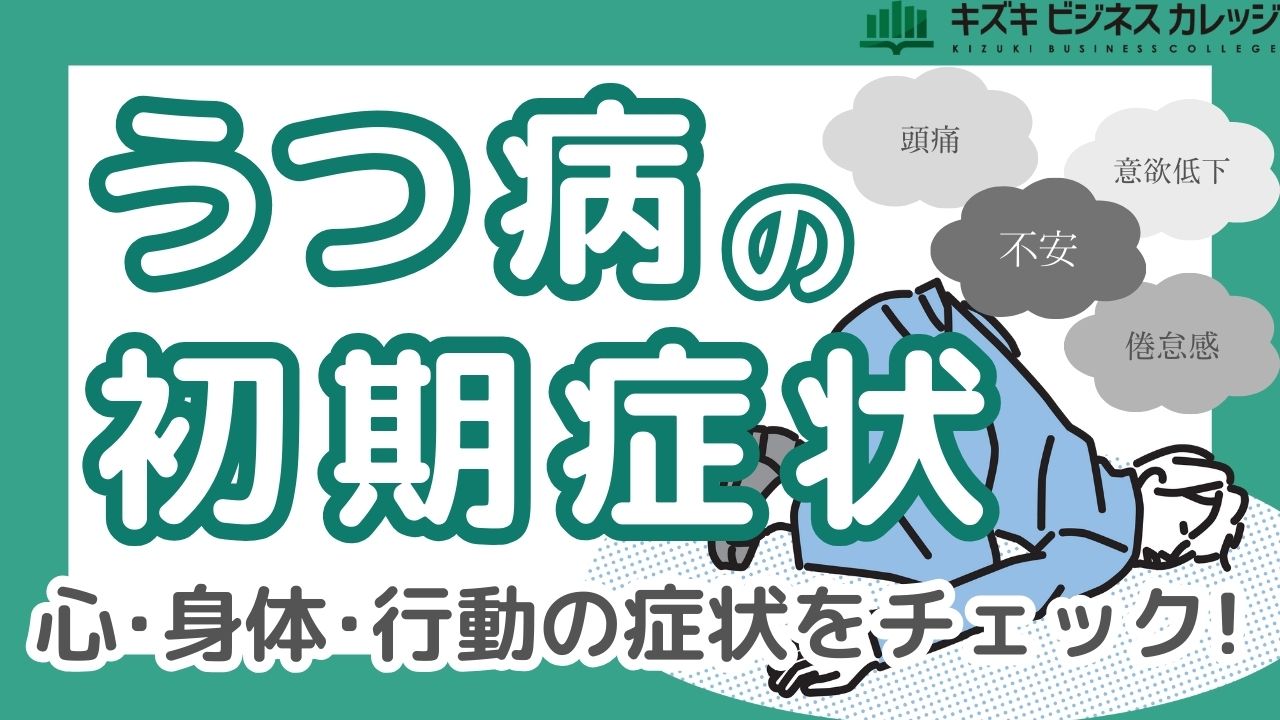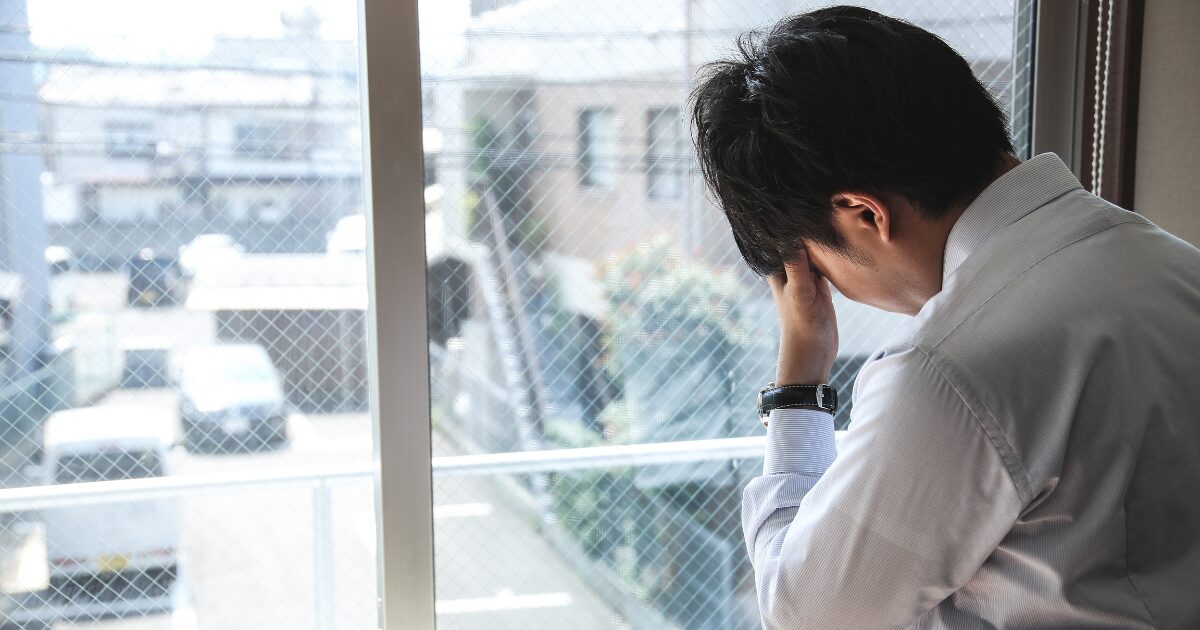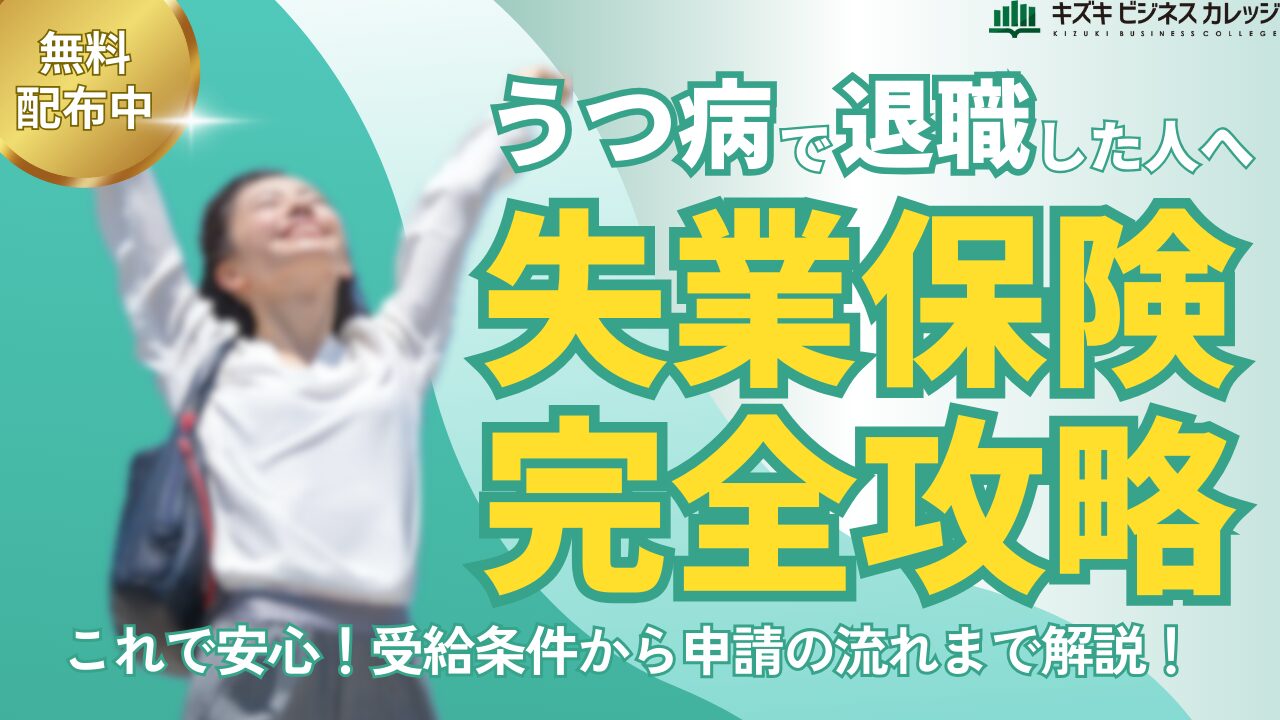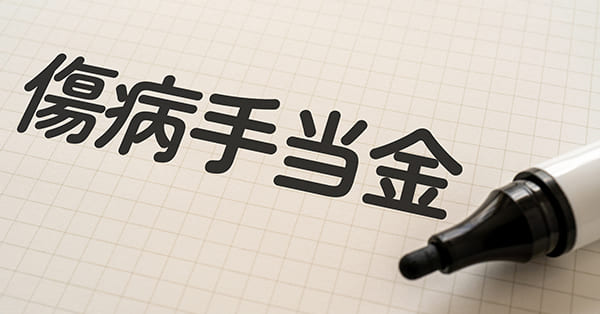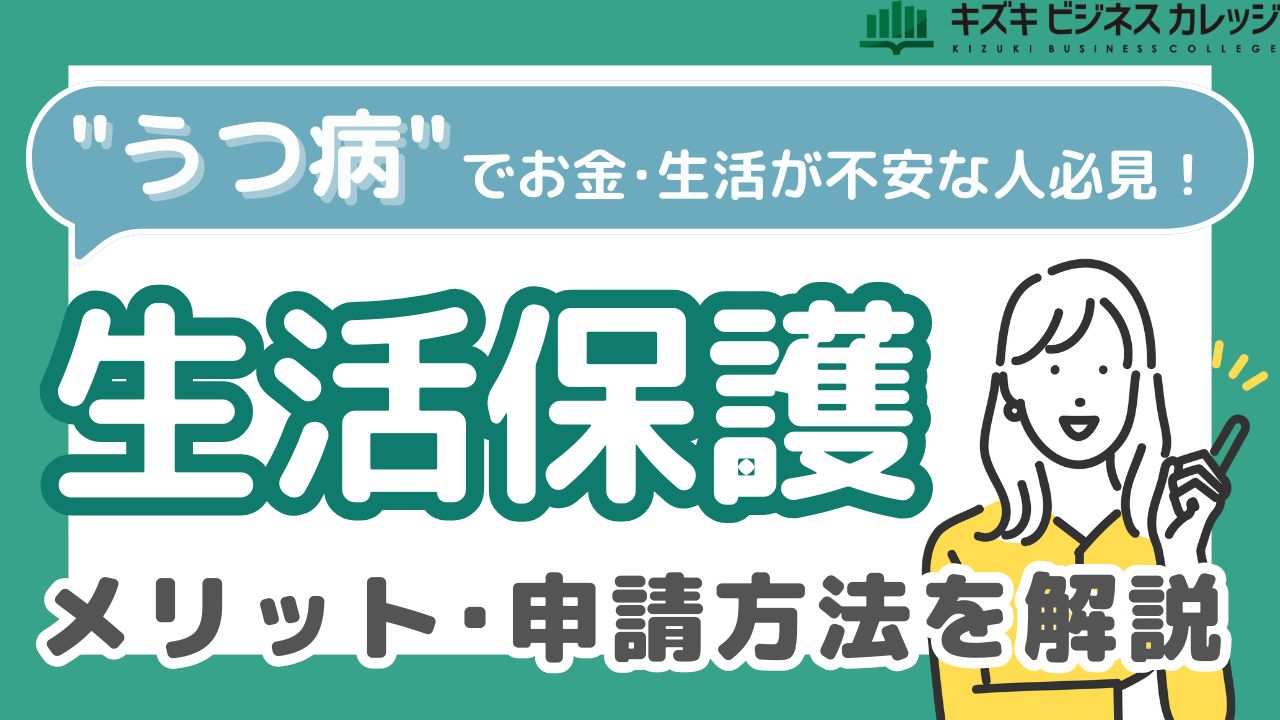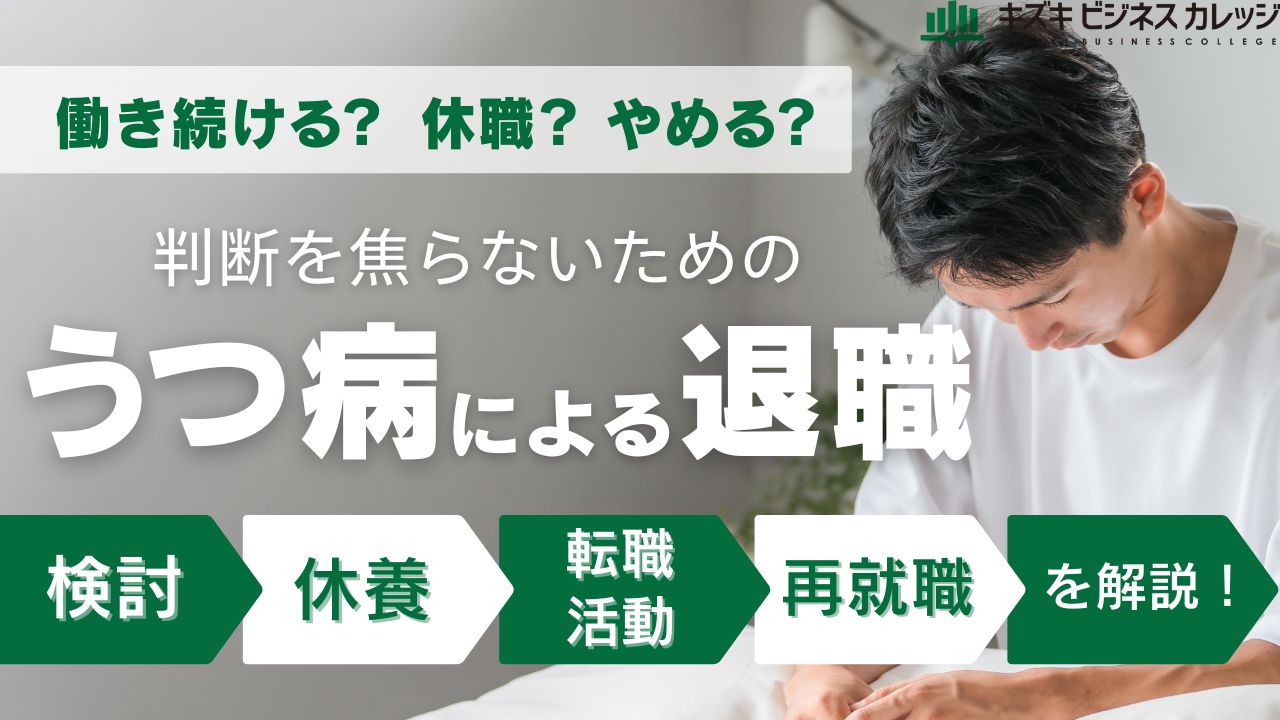お風呂に入りたくないのはうつ病の症状? 入りたくないときの対処法を解説

こんにちは。キズキビジネスカレッジ(KBC)利用者の山本です。
少し前に、風呂キャンセル界隈という言葉が話題になりました。さまざまな理由からお風呂に入りたくても入れない人が世の中には沢山います。
お風呂に入りたくても入れないのは、うつ病のある人によくみられる症状です。
筆者も、「あと数分経ったらお風呂に入ろう」と思っていても、なかなか身体が動かずにその日に入るのを諦めたことが何度もあります。
このコラムを読んでいるあなたも、同じような悩みや経験があるのではないでしょうか?
このコラムでは、お風呂に入りたくない理由やうつ病でお風呂に入りたくないときの対処法、どうしてもお風呂に入れないときの対処法などについて解説します。
このコラムを読んで、少しでもあなたの力になれば幸いです。
さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、支援を利用するかどうか悩んでいるうつ病のある方に向けて、「お金・仕事・自立の不安を解消!"うつ病"のある人のための支援機関・支援制度ガイドブック」の無料配布を開始いたしました。
うつ病のある方が利用できる支援機関・支援制度の概要、利用条件、利用方法までを、わかりやすく丁寧に解説しています。
ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。
お風呂に入るのがつらいうつ病のあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
お風呂に入りたくないのはうつ病の症状?
この章では、お風呂に入りたくないのはうつ病の症状が原因なのかと悩んでいる人に向けて、入浴とうつ病の関係性などについて解説します。
うつ病と入浴の関係性

精神疾患の有無に関わらず、多くの人がお風呂に入ることを面倒だと思っています。
特に、うつ病になると、以前はお風呂に入るのが好きだった人でもお風呂に入りたくなくなることも少なくありません。
なぜなら、うつ病になると、気持ちが落ち込みやすくなるからです。その気持ちの落ち込みによって、お風呂に入る気が起きない、めんどくさいという気持ちが症状として現れます。
また、うつ病になるとお風呂に入ることやシャワーを使うことにハードルを感じ、お風呂場に近づけなくなる制止症状がおきることもあります。(参考:秋田 巌『うつの人の風呂の入り方: 精神科医からの「自分で治すための」46提案』)
うつ病の初期症状・うつ病のある人がとる行動
うつ病のサイン・初期症状は、以下のとおりです。
- 睡眠障害:寝付けない、何度も目が覚める
- 慢性疲労:だるい、身体が重い
- めまいや動悸:目が回る、呼吸が苦しい
- 食欲の減退:ご飯を食べる気が起きない
- 性欲の減退:性的なものへの興味が減る
- 身体の痛み:原因不明の頭痛や腹痛がある
- 気分が沈む:憂鬱で気が晴れない
- 思考力・集中力の減退:判断力が落ちる、思考がまとまらない
- 意欲の低下:何もする気になれない
うつ病のサイン・初期症状については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
また、うつ病のある人がとる行動は、以下のとおりです。
- 物忘れやケアレスミスが多くなる
- 人との会話を避けるようになる
- 遅刻や欠勤が増える
- 離席が増える
- 机上が散らかりはじめる
- 電話の受け答えが緩慢になり沈黙が増える
- 眠気が強く日中でももうろうとしている
- 自分を責めるような発言が増える
- 話し方に抑揚がなくなり声が小さくなる
- 身だしなみを整えなくなり清潔感がなくなる
うつ病のある人がとる行動については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
お風呂に入りたくないと思うなら医療機関を受診すべき?

急にお風呂に入りたくなくなったり、何日も入る気が起きない状態が続いたりするとうつ病の可能性があります。
うつ病は誰しもがなる可能性のある病気です。
「自分はうつ病かもしれない」と心あたりのある人はうつ病についてまとめている以下のコラムを参考にしてみてください。
また、ご自身の状態がこれまでとは違っており、違和感を覚えたら、早めに心療内科や精神科を受診することをオススメします。
お風呂に入りたくない3つ理由
この章では、お風呂に入りたくない理由について解説します。
理由①お風呂の工程が多くてめんどくさい

お風呂に入るということは、簡単そうにみえて複数の工程を辿ります。
- お風呂の掃除
- 湯を沸かす
- 風呂後に着る服・下着を用意する
- 服を脱ぐ
- 身体を洗う
- 髪・顔を洗う
- お湯につかる
- 頭・体を拭く
- 身体・顔などを保湿する
- 服を着る
- 髪を乾かす
- ヘアケア剤をつける
- スキンケア
人によってお風呂の工程の数、順番はさまざまです。工程の途中で休憩をはさむ人もいれば、日によっては特定の工程をとばす人もいます。
身体も心もしんどいと思う時に、頭の中でこれらの工程をすべてしないといけないと思うと、面倒で身体が動かなくなり、お風呂に入りたくなくなるのではないでしょうか?
理由②お風呂からあがったあと、暑かったり寒かったりする
お風呂からあがったあと、夏場は脱衣所が暑く少し汗をかいたり、逆に冬場は身体が冷えたりします。
特に、冬場はお風呂に入る前が寒く、湯舟で温まるまでに時間がかかります。
急な身体温度の変化は、人間の身体にとって不快な感情につながるので、その感情がお風呂に入りたくない思いを助長させます。
理由③毎日入らないといけないという固定観念をもっている

多くの人は毎日ご飯を食べるように、毎日お風呂に入らなくてはいけないと思っているでしょう。
お風呂に入らなくても生死には関係はありませんが、毎日入らないと不潔になるというイメージがあり、入らざるを得ない気持ちになります。
しかし、人はやらなくてはいけないと思うと、やりたくなくなるものです。
また、毎日お風呂に入っていないと、周りからどう思われるか気になり、お風呂に入ることを強制されている気持ちになる人もいるでしょう。
うつ病でお風呂に入りたくないときの対処法6選
この章では、うつ病でお風呂に入りたくないときの対処法について解説します。
対処法①お風呂の時短をはかる

そもそものお風呂にかかる時間を短くする方法は効果的です。
髪を短くすると、髪を洗う時間や乾かす時間が減って時間の削減になります。また、バスローブを使うと、お風呂から上がってすぐ身体を拭く行為を省けるので、ゆっくりお風呂あがりに過ごすことができます。
お風呂にかかる時間を少なくすれば、その分の労力も削減されるので入るのが面倒な気持ちが減ると思います。
対処法②入浴前と入浴後の寒暖差をなくす
脱衣所の温度調整の工夫をすることをオススメします。
こちらで解説したとおり、入浴後の寒暖差を想像してお風呂に入る足が遠のく場合は、脱衣所の温度調整の工夫をすることをオススメします。
夏であれば、冷房や扇風機、サーキュレーターなどを用意して汗をかかないようにしましょう。
冬であれば、風呂場の暖房機能をつかってそこで服に着替えたり、脱衣所に暖房を用意したり、温かい飲み物を用意しておくと対策できると思います。
また、保温機能がある下着やパジャマを用意するのもいいでしょう。
対処法③とりあえず一つずつの工程に集中する
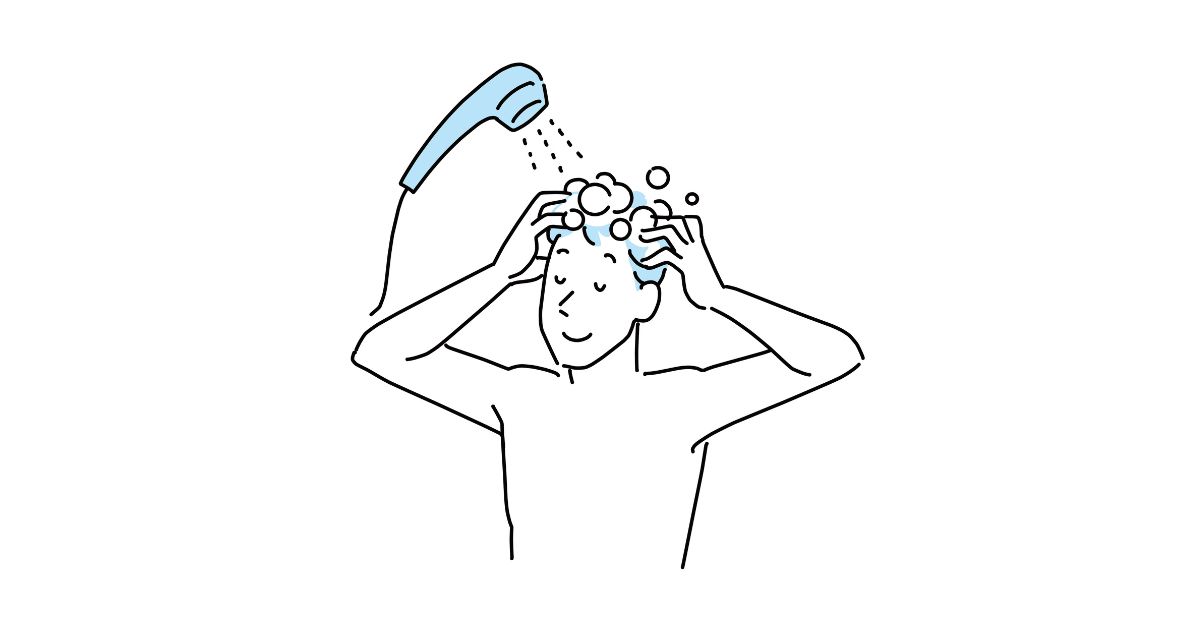
とりあえず目の前のことに一つ一つ集中して、最終的に入浴を目指す方法です。
こちらで解説したとおり、お風呂に入るには工程が多く、全てをきっちりやろうとすると入りたくなくなります。
その対策として、とりあえず目の前のことに一つ一つ集中して、最終的に入浴を目指す方法です。これは、実際にうつ病のある人から効果があったと聞いた方法です。
まず、脱衣所にいってみて、服を脱いでみる、それができたら湯舟につかってみるなど、小さな目標を立ててこなしていきましょう。
目の前のことに集中して、最終的にお風呂に入れば心理的負担が減るはずです。
対処法④お気に入りの入浴剤・シャンプーを見つける
お気に入りのものを見つけることで、お風呂に入る時間を楽しめると思います。
新しい入浴剤やシャンプーを見つけると、試してみたくなりませんか?それらは、お風呂場でしか試せないので、お風呂に入りたくなると思います。
さらに、お気に入りのものを見つけたり、日替わりでいろいろなものを用意したりすれば、お風呂に入る時間を楽しめると思います。
対処法⑤2日に1回入る

お風呂に入る日、入らない日を決めることで悩む労力が減るでしょう。
こちらで解説したとおり、お風呂に毎日入らないといけないという固定観念がある場合は、お風呂に入る日、入らない日を決めることで悩む労力が減るでしょう。
2日以上入らない日が続くと、髪がベタベタしたり匂いが気になってくるため、逆にストレスが増える可能性があります。
また、こちらで解説するとおり、身体を清潔に保つことは病気の予防にもなるため、2日に1回は入るようにしましょう。
対処法⑥ルーティーン化する
毎日の生活の動作の中でお風呂に入るタイミングをルーティン化すると楽に入れるのではないかと思います。
お風呂に入ることを日常のルーティーンに組み込むとよいでしょう。
筆者の場合は帰宅後、家に帰ったらすぐにお風呂に入るようにしています。あらかじめ、前日にお風呂から上がる直前に掃除をしておき、脱衣所に下着の収納棚を置くことで、湯を沸かすボタンを押すだけでお風呂に入れるようにしています。
はじめは、意識して帰宅したらすぐお風呂に入っていましたが、慣れてくると気が付いたらボタンを押してお風呂の用意をしています。そうすると、お風呂に入るかどうか悩む時間もなくお風呂に入ることができます。
入るかどうか、いつ入るかなどを悩むことで精神的に疲れます。
しかし、毎日の生活の動作の中でお風呂に入るタイミングをルーティン化すると楽に入れるのではないかと思います。
実際に、筆者もルーティン化してから、あとで入ろうと思いながら時間だけが過ぎていくことや入るか入らないか悩むことがなくなりました。
どうしてもお風呂に入れないときの対処法5選
どうしてもお風呂に入れない時は、入らないという手もあります。
この章では、どうしてもお風呂に入れないときの対処法について解説します。
対処法①温かいタオルで拭く

1つ目の対処法は、温かいタオルで身体を拭く方法です。
タオルをお湯に濡らすか、水で濡らして絞り、電子レンジで1分ほど温めると、簡単に温かいタオルを用意できます。
温かいタオルで身体を拭くと、血行を促進するメリットがあります。ほかの対処法に関しては、血行促進の効果はないため、身体を温めたい人や血のめぐりをよくしたい人にはこの方法がオススメです。
血行を促進すると体温があがり気分もよくなるので、うつ病の改善につながります。また、必要なものはタオルだけなのですぐに実践ができることがメリットです。(参考:日本経済新聞「血流が良くなると心の悩みまで解消する、は本当か ヒット書籍『血流がすべて解決する』著者・堀江昭佳さんに聞く(後編)」)
対処法②拭き取りクレンジングシートや乳液などの簡単な方法でメイクを落とす
疲れていたり、気持ちが下がっていたりする時は、メイクを落とすこともしんどいですよね。
そんな時は、拭き取りクレンジングシートや乳液で顔の汚れを取りましょう。
特にメイクをしている人は、メイクを落とさずに寝ると毛穴が詰まって角栓になるため、その日のうちにクレンジングをした方が良いでしょう。
メイクをしていない人でも日中の活動でほこりや皮脂などの汚れが沢山ついているので、クレンジングで汚れを落とすことをオススメします。
顔の汚れを落とすには、拭き取りクレンジングシートが一番手軽です。顔にシートをのせて、しばらく待つと汚れがシートにつく仕組みです。
拭き取りクレンジングシートを使うのが面倒な人は乳液をコットンにつけて、顔にくるくると馴染ませると同様にメイクを落とすことができます。
顔が汚れたまま寝ると、翌日顔がベタベタになり不快になります。顔が清潔になると、気分転換にもなるので、どうしても身体を洗う気力がない時はクレンジングだけでもしてみましょう。
対処法③ドライシャンプーを使う

ドライシャンプーとは、水やお湯を使わずに髪や頭皮の汚れ・汗・皮脂・臭いを取り除けるアイテムです。
主にスプレータイプやパウダータイプがあり、頭皮に直接かけて、軽くマッサージすることで皮脂や汚れを吸着させ、ブラシで取り除くだけで簡単に使用できます。
ドライシャンプーは水やお湯を使わないので、どうしてもお風呂に入りたくないときや、シャンプーしたいときに便利です。お風呂場に行かずにどこでも使うことができるので、制止症状を回避できます。
なお、洗い流すシャンプーよりも洗浄力が弱く、完全に汚れや皮脂を落とすのは難しいため、継続使用は控えましょう。ドライシャンプーだけを使い続けると、かゆみやフケ、かぶれの原因になる可能性があります。(参考:秋田 巌『うつの人の風呂の入り方: 精神科医からの「自分で治すための」46提案』)
対処法④ボディシートを使う
ボディシートは、汗を拭き取って肌のベタつきやニオイを抑えるシートです。
デオドラントシートとも呼ばれ、厚手のウエットティッシュのような形状をしています。
こちらも、小さくて持ち運びできるのでお風呂場でなくても使うことができます。さらに、持ち運びできるので出先で使えるのがメリットです。
そして、昨今ではさまざまなタイプのボディシートが発売されています。
その中でも、エタノールやメントールなどの成分が配合されているボディシートは、拭き取った後に清涼感を得られます。また、有効成分として殺菌成分などが配合されている医薬部外品タイプもあり、ニオイの原因となる菌の増殖を抑えることができます。
特にお風呂に入りたくない人は、そのための大判のボディシートが発売されており、一枚で全身を拭き取れるためオススメです。種類が沢山あるので、自分の用途や好みに合ったものがみつかると思います。
ただし、使いすぎると湿疹の原因になるので、使いすぎには注意しましょう。
対処法⑤清拭剤を使う

清拭剤(せいしきざい)とは、お風呂に入れないときに使う、身体を清潔に保つためのアイテムです。
主に負傷者や要介護者を介護するときに使うものですが、ドラッグストアで販売しているので医療・介護従事者でなくても使えます。
清拭剤は泡タイプと液体タイプがあります。どちらのタイプも泡立てる必要がないので、石鹸を使うよりは手間がかかりません。
泡タイプは、蒸しタオルやお湯にひたしたタオルに泡をのせて身体を拭きます。
液体タイプは、洗面器などにお湯をいれて、そのなかに液体をいれて溶かしタオルを絞った後に身体を拭きます。顔から、首、上半身、下半身と上から下に、末端から中心部分に、と順番に拭いていきます。
この方法もこちらで解説した方法と同様に血行が促進され、血の巡りが良くなり、うつ病改善につながります。
お風呂に入ることで得られる5つの効果
この章では、お風呂に入ることで得られる効果・効能について解説します。
これらを知っておくと、お風呂に入るメリットと入る目的が分かります。そして、お風呂に入ろうかなと少しでも思えるのではないのでしょうか?
効果①身体が清潔になる

言わずもがなですが、お風呂に入ることで身体が清潔になります。体の汚れの約7割は汗で、シャワーを浴びるだけでも落ちます。残りの約3割は皮脂や古い角質などの汚れで、洗浄料を使って洗う必要があります。(参考:SBI新生銀行「皮膚科医が伝授!あらためて知りたい正しい体の洗い方」)
湯船につかると、毛穴が開き、お湯が皮脂に詰まった汚れを流し清潔にしてくれます。肌が綺麗になると、気持ちがすっきりしますし、何よりも健康保持・病気予防になります。
効果②疲労が回復する
入浴には、疲労回復の効果があります。疲れて家に帰ってきた後、お風呂に入らずに寝ると、翌朝疲れがとれていないことはありませんか?
湯船につかると、身体が温まり、血管が広がってたくさんの血液が体内を巡ることで、新陳代謝が活発になります。また身体全体に水圧がかかることで、足のむくみの原因となる滞留した血液を水圧で押し戻すことができます。
また、身体が温まると筋肉や関節部の緊張がほぐれます。家でのデスク作業などによる肩や腰の痛みは筋肉が緊張しておこるため、入浴によって改善する可能性が高いです。
しんどい時はシャワーだけでも構いませんが、湯船につかることでより高い効果を得られます。(参考:大阪市水道局「ええことづくめ!お風呂の健康効果とおすすめの入浴法」)
効果③ストレス解消になる

湯船につかると、体が芯まで温まり、神経や筋肉の緊張がほぐれます。これにより、ストレスで活性化された交感神経の働きが抑制され、副交感神経が優位になり、心身がリラックスします。(参考:大阪市水道局「ええことづくめ!お風呂の健康効果とおすすめの入浴法」)
加えて、お風呂は日常から区切りをつけて一人でゆっくりできる空間なので、気持ちをリフレッシュできるでしょう。
さらに、こちらで解説したとおり、自分の好きな香りにつつまれながらお風呂に入ると気分転換やストレス解消になります。
日常から解放される空間ということを利用して、お風呂場をストレスを解消する場所に設定して好きなものを置いたり、インテリアを工夫したりすれば心身ともにリセットができる素敵な場所になるでしょう。
効果④安眠効果がある
眠気は、体温が下がることによって生じやすいということです。私たち人間のように昼行性動物は、深部体温が日中は高く、夜は低い傾向にあります。そして、睡眠は深部体温が低い時間帯におこり、深部体温の高い時間帯には起こりにくいです。(参考:J-Stage「ヒトの体温調節と睡眠」)
したがって、入浴し一時的に体温を上昇させて、お風呂から上がった後、放熱して体温が下がることで眠りやすくなります。
良質な睡眠は心身の健康のためにとても重要です。特にうつ病のある人は、よく眠れなかったり、なかなか寝付けなかったりするなど、睡眠に関する悩みを抱えている人が少なくありません。
実際、うつ病のある人は睡眠時間が6時間以下の人や寝床にいる時間(床上時間)が長い人が多いです。(参考:厚生労働研究科学センターベース「一般成人における睡眠時間の不足とうつ病の関連について」)
そして、適切な入浴をすることで、睡眠の質があがるという研究結果もあります。したがって、睡眠の質があがることは、うつ病の改善にも効果的です。(参考:厚生労働研究化学センターベース「入浴と睡眠の関連に関するシステマティックレビュー)
特に必要なものはないので、うつ病対策の一つとして試してみる価値はあるでしょう。
効果⑤肌が綺麗になる効果がある

入浴すると以下のように、肌が綺麗になる効果が期待できます。
- 毛穴が開くことで、毛穴につまった汚れが落ちる
- 体温があがり血行が促進されるので、代謝があがる
- 副交感神経が優位になり、自律神経が整うことで肌の荒れやくすみが改善される
肌が綺麗になると、鏡で自分を見たときに自信に繋がりますし、気分も良くなりますよね。
ただし、逆に入浴中の行動で美容に関して逆効果になることがあります。それは、長風呂とお風呂の中でスマホを見ることです。
長風呂をすると肌に必要な皮脂や肌の内部にある水分を保つ脂質が流れ出て乾燥肌になる恐れがあります。
また、お風呂でスマホを見ると脳が興奮して交感神経が活発になり、自律神経が乱れやすくなります。肌荒れの原因につながるおそれがあるので極力控えましょう。(参考:日本経済新聞「美容には逆効果! やってはいけない入浴法」)
効果的な入浴方法
効果的な入浴方法は医学的に明らかになっています。
簡単にいうと、入浴の前後に水分をしっかりとって、いきなりつかるのではなく、徐々にお湯の熱さに身体を慣れさせるという方法になります。(参考:名古屋市上下水道局「医学的に正しいお風呂の効果的な入り方」)
この章では、効果的な入浴方法について解説します。
手順①水分を摂る

お風呂に入ると汗をかき、人体の約800mlの水分が失われるといわれています。(参考:大塚製薬「イオン飲料を用いた研究成果 「入浴時の脱水に対する有用性」を臨床研究により日本で初めて確認」)
そのため、お風呂に入る前には脱水症状を避けるために、充分に水分をとりましょう。
冷たい飲み物は身体が温まるのがおそくなるので、常温や温かい飲み物が良いとされています。
入浴15分前にコップ1杯〜2杯の水やミネラルウォーター、麦茶等を補給することをオススメします。
ただし、アルコールは利尿作用があり、体内の水分が失われるので入浴前後は控えましょう。
手順②かけ湯(シャワー)をする
急に寒い場所から暖かい場所に移ると、身体がヒートショックをおこす可能性があります。
ヒートショックとは、温度の急激な変化で血圧が上下に大きく変動することによって、失神したり心筋梗塞や脳卒中といった血管の病気などを引き起こしたりする健康被害のことです。(参考:滋賀県「ヒートショック対策について」)
ヒートショックを防ぐためにも、かけ湯をしましょう。
手や足の末端から、体の中心部や頭へ順番に、桶もしくは手桶でお湯をかけます。かけ湯には、体の汚れを取り、湯船の中を清潔に保つことと、血圧の急上昇を防ぐ役割があります。(参考:名古屋市上下水道局「医学的に正しいお風呂の効果的な入り方」)
手順③半身浴をする

いきなり全身をお湯につける前に、身体を湯の温度に慣らすために、みぞおちあたりまでゆっくりとつかりましょう。1~2分したら全身浴に切り替えます。
肺や心臓が弱い人は半身浴を37〜39度のお湯で30~40分することをオススメします。みぞおちより下までしか湯船につかっていないので、肺や心臓にかかる水圧の負荷が少ないです。(参考:ウェザーニュース「本当に効果のある正しい半身浴とは」)
手順④全身浴をする
全身浴をする場合の温度は40度で、合計10〜15分がいいといわれています。7〜8分×2回もしくは5分×3回など一度あがっても合計10〜15分になれば問題ないでしょう。
なぜ40度かというと、副交感神経が優位になって血流が増えるのに適した温度だからです。(参考:日本経済新聞「半身浴より全身浴が効く 疲れとる入浴法、お湯は40度」)
手順⑤洗い場で髪や体を洗う

一度湯船から出た後は、洗い場で髪や体を洗うようにしましょう。
お風呂には洗浄作用があるので、髪や体を洗う時には、ゴシゴシこすらず、泡立てた石けんでやさしくなでるくらいで充分です。
手順⑥再度、全身浴をする
こちらの手順と同じく、合計10〜15分になるように再び全身浴します。
この時、目の疲れをとるために、ホットタオルを目に当て上から目の周りを指で押すと目の疲れがとれるためオススメです。(参考:日本経済新聞「半身浴より全身浴が効く 疲れとる入浴法、お湯は40度」)
手順⑦お風呂から出る

充分に身体があったまったらゆっくりとお風呂から出ます。
お風呂場と脱衣所の気温差が大きいと、極度の寒暖差が生まれるのでヒートショックが起きる可能性があります。冬場は脱衣場を温めるように工夫しましょう。
お風呂から出たら、身体の水滴をタオルなどで拭くようにしてください。
手順⑧再度、水分を摂る
こちらでもお伝えしたとおり、お風呂に入ると平均800mlの水分が失われるといわれています。
入浴後も脱水症状を防ぐために、入浴後すぐにコップ1~2杯程度の水分をとりましょう。
手順⑨休息する

人間は体温が下がっていくときに眠くなります。
就寝1〜2時間前に入浴すると、寝るころには体温が下がり睡眠が促されます。そのため、入浴後は約1時間ほど休憩してから布団に入りましょう。(参考:日清製粉グループ「体が喜ぶ「正しい入浴法」とは?」)
入浴する際の注意点
入浴する際の注意点は、以下のとおりです。
- お風呂の温度は38〜40度で、ぬるめのお湯にする
- 入浴時間は10分から15分程度
- 入るタイミングは、寝る前の1〜2時間前
42度以上の湯船につかると、交感神経が優位になり血圧や脈拍が上がって筋肉が硬直します。さらに、急激な温度変化でヒートショックを起こす恐れがあります。注意しましょう。
また、長風呂をすると、脱水症状を引き起こす可能性があります。
加えて、体温が下がると眠気がおこるといわれています。就寝時にちょうど体温が下がり、眠りにつきやすいため、入浴する時間も意識するようにしてみてください。
うつ病のある人が使える支援制度・機関
うつ病になると、今までできていたことができなくなったり、気分が落ち込んだりして日常生活に支障がでます。
しかし、うつ病は誰でもなる可能性のある病気です。
国や民間の支援や制度に頼ることは恥ずかしいことではありません。つらい時に相談できる人がいたり、支援を受けられたりすると少し気持ちが穏やかになるかもしれません。
困ったときは、一人で抱えずに自分にあった支援機関・制度を見つけて利用してみましょう。
うつ病のある人が使える支援制度

うつ病のある人が使える支援制度は意外と沢山あります。
例えば、傷病手当金は会社員でお風呂にも入れず会社に行くこともしんどい人が休職を会社に申請すると受け取れる手当です。
また、失業保険は失業中や退職して次の仕事を探すまで時間がある人がハローワークで申請すると受け取れる手当のことです。
そして、自立支援医療制度はうつ病の治療に取り組んでいて、金銭的負担がある人の病院代や薬代が三割から一割負担になる制度です。
どの支援制度が使えるかは人によって異なるので、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口かこの後に記載する支援機関で相談してみてください。
支援制度についてより詳しく知りたい方はこちらのコラムをご覧ください。
うつ病のある人が相談できる支援機関
続いて、うつ病のある人が相談できる支援機関についてご紹介します。
「うつ病で生活がままならなくて誰かに相談したい、どうしたらいいか分からない…」。そんな時に誰かに相談できたら少し気持ちが楽になりますよね。
例えば、障害者就業・生活支援センターや就労移行支援事業所では就労のサポート以外に生活に関する困りごとを相談できます。
また、精神保健福祉センターは精神障害者に特化したサポート支援機関で、主に精神疾患に関連する悩みの相談ができます。
これらの支援機関は手帳の有無は関係なく相談することができます。
相談することで他に適した機関があれば繋げてくれる可能性があるので、まずはどこかに相談してみるのも一つの手だと思います。
詳しい支援機関を知りたい方はこちらのコラムをご覧ください。
【無料配布中!】「”うつ病”のある人のための支援機関・支援制度ガイドブック」
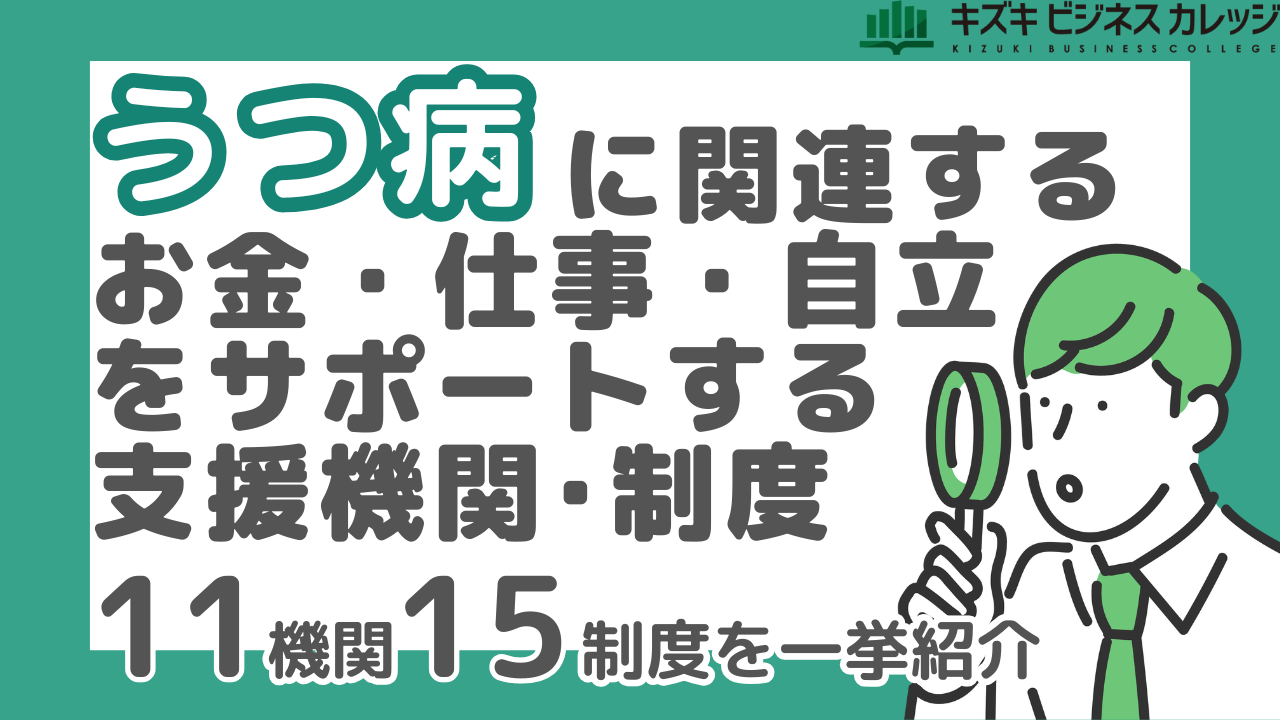
- 「支援を利用したいけど、どこに相談すればいいかわからない…」
- 「手続きが難しそうで、自分でできる気がしない」
このように、うつ病のある人は支援を利用したいと思っても、どこに相談すればいいのかわからなかったり、制度の内容が難しかったりすることで、支援を活用できないことは少なくありません。
本資料では、うつ病のある人が利用できる主な支援機関や支援制度をわかりやすく整理しました。
加えて、各支援機関・支援制度の概要や利用条件、利用方法など、支援を活用するための情報を厳選してまとめています。
少しでも負担が軽くなるよう、支援を受けるためのヒントとしてご活用いただければ幸いです。
- 医療・福祉的な支援機関・制度
- 経済的な支援機関・制度
- 就労に関する支援機関・制度
- つながりをつくるための支援機関・制度
- どこに相談していいかわからない方の相談先
- うつ病になりどうすればいいかわからず悩んでいる方
- うつ病の症状がつらく誰かに相談したい方
- お金や今後の生活など、経済面でお困りの方
- 今後の仕事や働き方について考えたい方
- うつ病など自分と似た経験をした人とのつながりたい方
- ご家族や支援者として正しい知識を持ちたい方
- リンクから申し込みフォームにアクセス
- 簡単なフォームに入力
- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り
- URLから資料を取得!
- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。
- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。
- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。
まとめ:できることからはじめてみよう

このコラムを読んでいる人の中には、お風呂に入ることができなくて困っていたり、悩んでいたりしている人がいると思います。
今までできなかったことや嫌だと思っていたことを、いきなりできるようにするのはなかなか難しいことですよね。
まずは、このコラムで解説した対処法を実践してみて、自信をつけてから、習慣化すると挑戦しやすいかと思います。
もちろん、正しい実践の順序はありません。ご自身にあった対処法が見つかればそれが一番です。
もしほかにつらいことや困りごとがあれば、一人で抱え込まずに支援制度を利用して、支援機関に相談してみてください。
このコラムを読んで、あなたの生活がよりよいものになれば幸いです。
うつ病でお風呂に入りたくないときの対処法を教えてください。
以下が考えられます。
- お風呂の時短をはかる
- 入浴前と入浴後の寒暖差をなくす
- とりあえず一つずつの工程に集中する
- お気に入りの入浴剤・シャンプーを見つける
- 2日に1回入る
- ルーティーン化する
詳細については、こちらで解説しています。
どうしてもお風呂に入れないときの対処法はありますか?
以下が考えられます。
- 温かいタオルで拭く
- 拭き取りクレンジングシートや乳液などの簡単な方法でメイクを落とす
- ドライシャンプーを使う
- ボディシートを使う
- 清拭剤を使う
詳細については、こちらで解説しています。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→