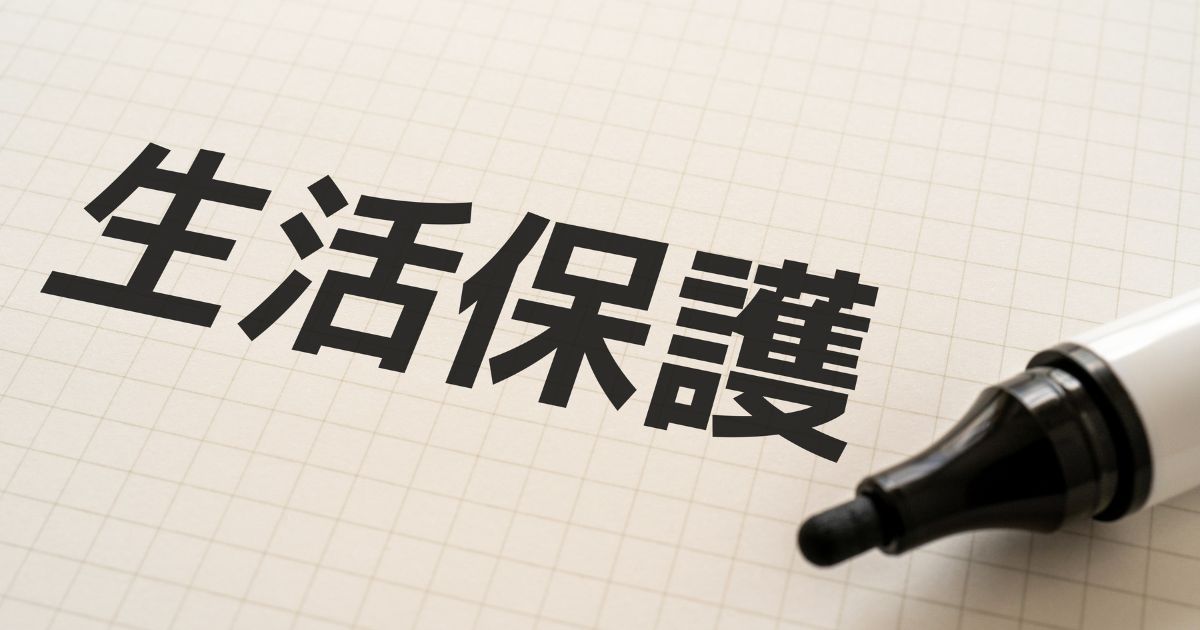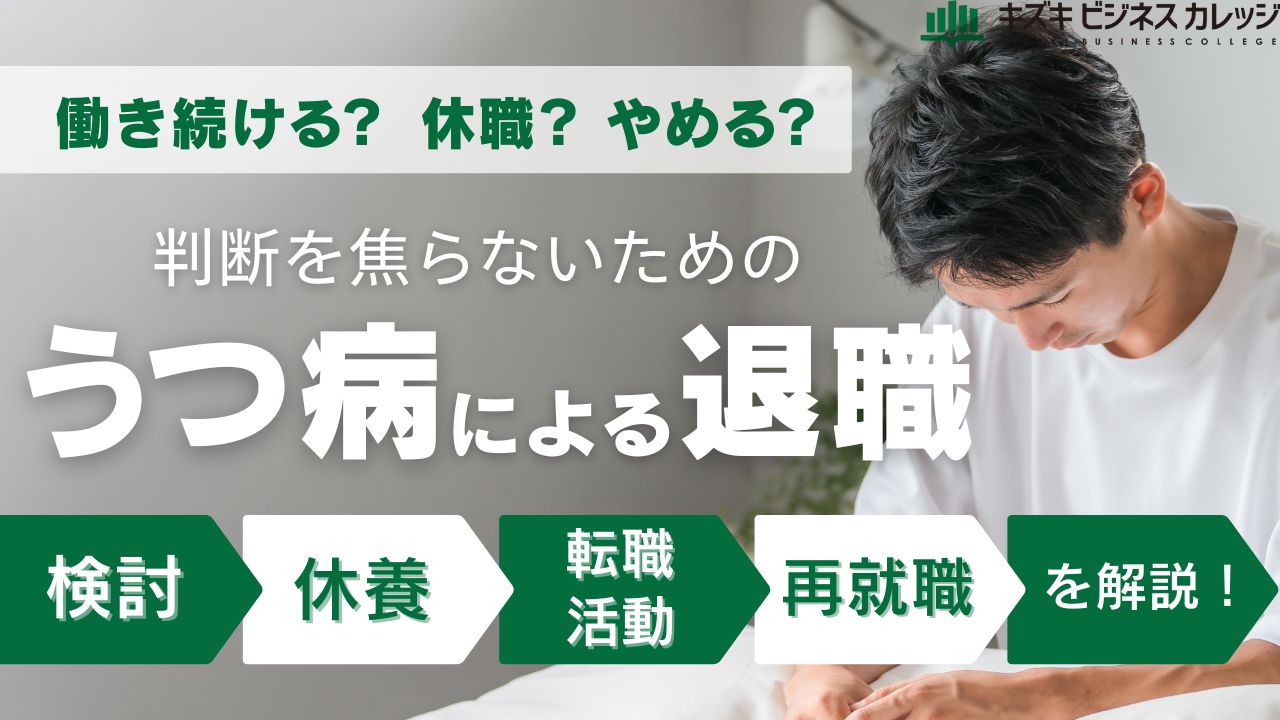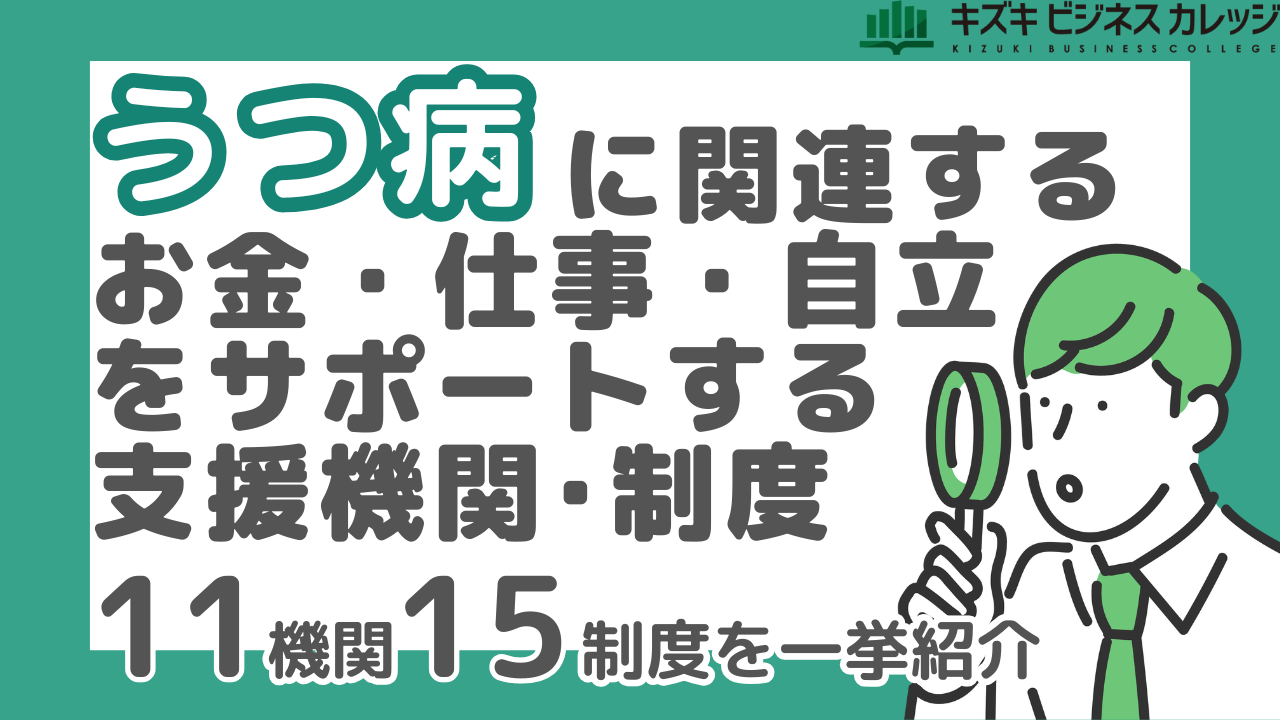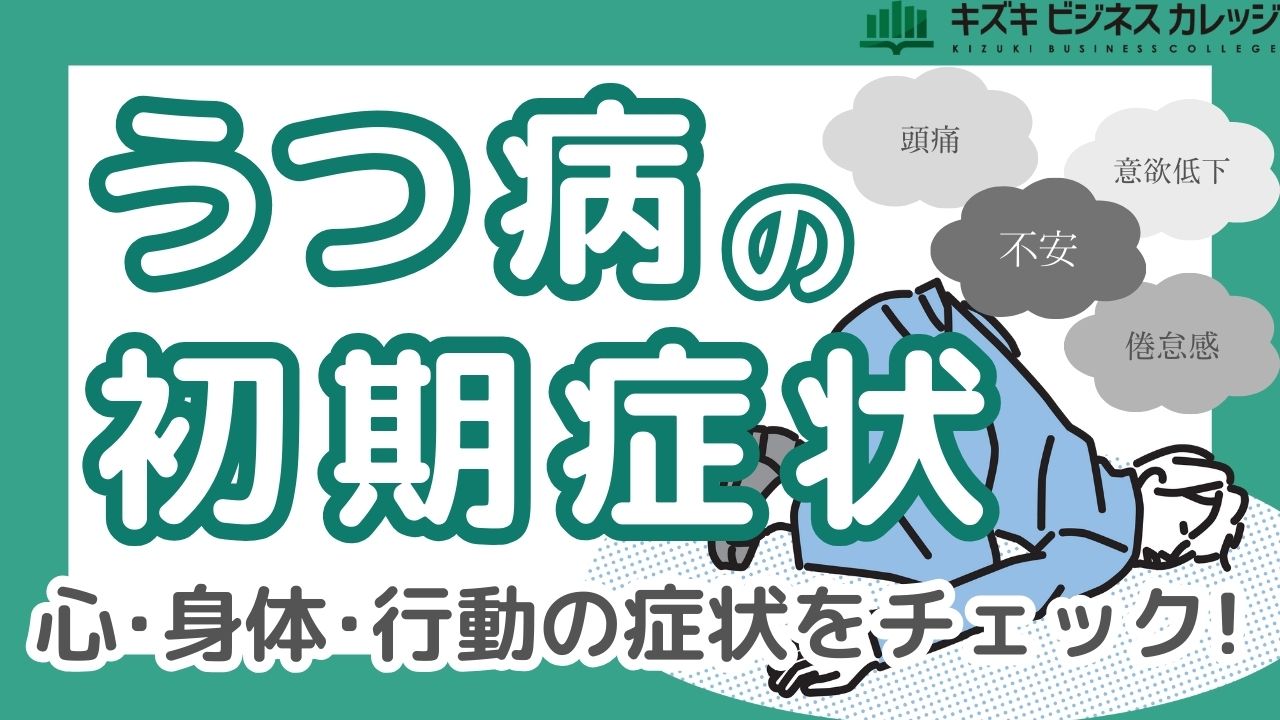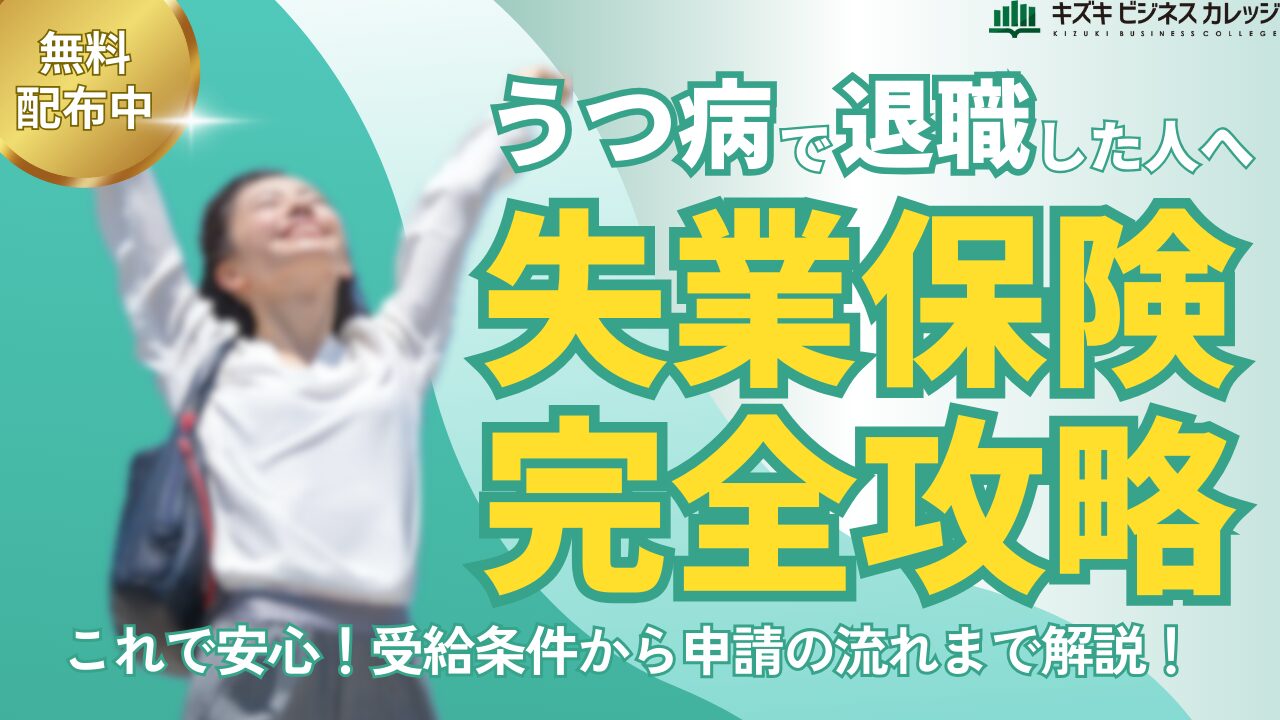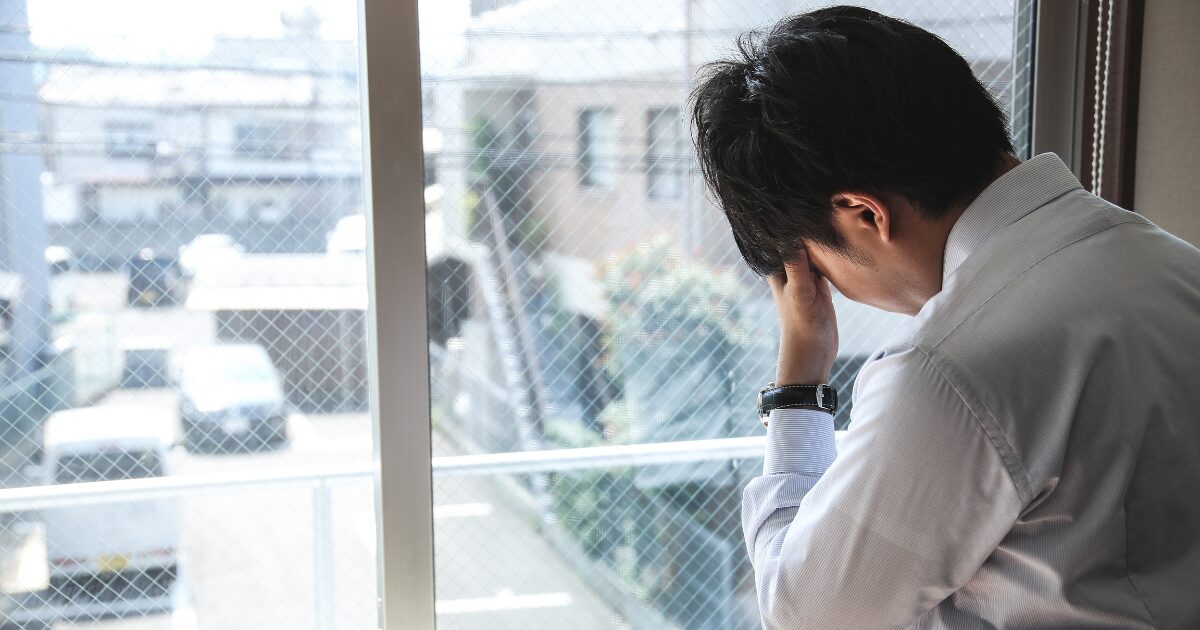うつ病のある人が生活保護を申請する前に確認すべきポイント 利用するメリットを解説【ガイドブック配布中】
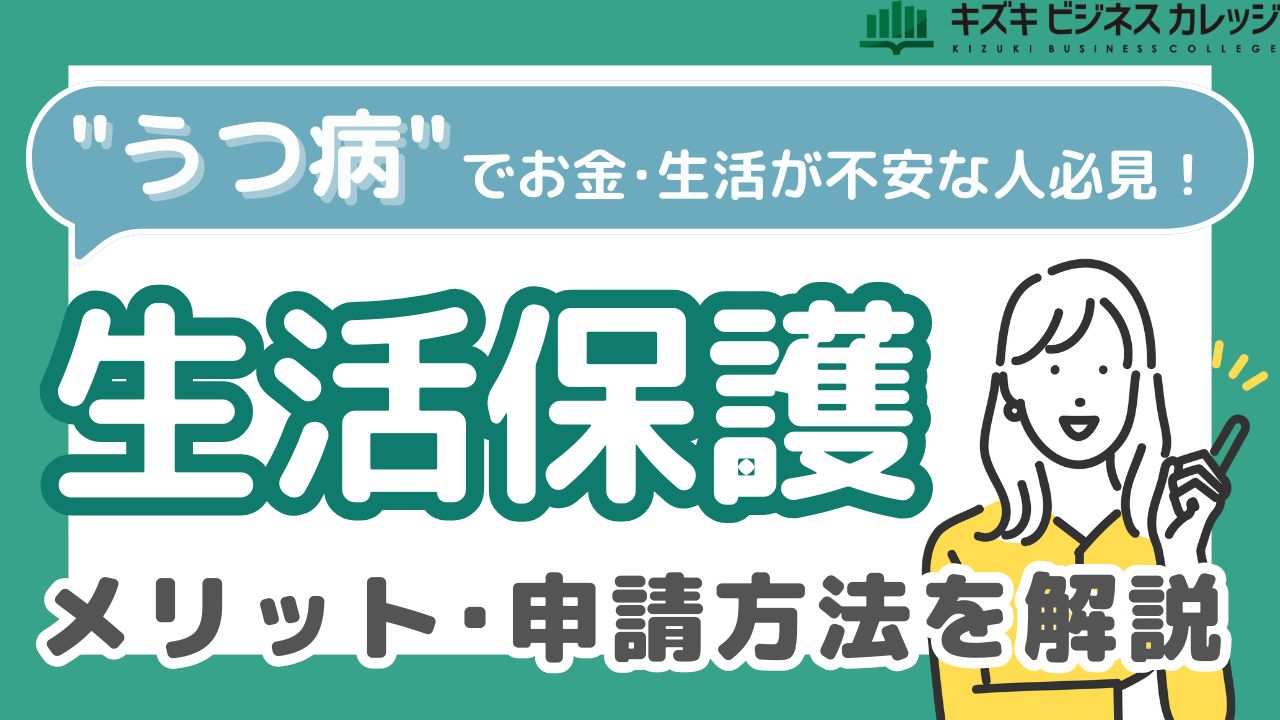
こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC) です。
うつ病によって就労が困難となり、生活に困窮している人が、まず不安になるのが、生活費や治療費などのお金のことでしょう。
このコラムでは、うつ病で就労が困難となり、生活に困窮している人に向けて、うつ病のある人が生活保護を申請をする前に確認すべきポイントや生活保護の概要などについて解説します。
生活保護などの支援制度を利用することは、決して恥ずかしいことではありません。
支援制度を利用しつつ、しっかり休養・治療することが、うつ病からの回復、その後の就労には欠かせません。
このコラムを参考に生活保護などの支援制度について知っていただけると幸いです。
さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病により働くことが難しく、生活やお金の不安を抱えている人に向けて、『【完全保存版】”うつ病”のある人必見!生活保護・完全攻略ガイドブック』の無料配布を開始いたしました。
生活保護の概要や支援内容、利用するメリット、申請方法などをわかりやすく解説しています。
ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。
生活保護の申請を検討しているうつ病のあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
うつ病のある人が生活保護を申請をする前に確認すべき3つのポイント
この章では、うつ病のある人が生活保護を申請をする前に確認すべきポイントについて解説します。
ポイント①医師や支援機関などに相談しましょう

生活保護の仕組みには、複雑な部分があります。
実際のあなたが生活保護を利用できるかどうかは、主治医や専門家、支援機関に相談してみてください。
また、生活保護などの支援制度に関して、うつ病のあるあなた一人で検討・申請するのは、難しい部分もあると思います。
そのような場合でも、お住まいの自治体の担当する部署・窓口や主治医、専門家、支援機関に相談することで、生活保護に限らず、あなたに必要な支援制度を利用できるようになると思います。
ポイント②生活保護を利用することは正当な権利です。恥ずかしいことではありません
生活保護をはじめ、支援制度を利用することは、正当な権利です。
厚生労働省も、以下の様に伝えています。(参考:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」)
生活保護などの支援制度を利用することは、決して恥ずかしいことではありません。当然、遠慮する必要もありません。
適切な支援制度を利用することで、安心してうつ病の治療に取り組めます。また、就職・転職などの次の一歩にも進みやすくなるでしょう。
ポイント③生活保護以外の支援制度の利用も検討しましょう

生活保護は、一般的には、そのほかの支援制度などを利用してなお、生活が困窮している人が受給できる支援制度です。
生活保護以外の支援制度について、各窓口に相談していない人は、まずはそちらに相談するようにしましょう。
生活保護とは?
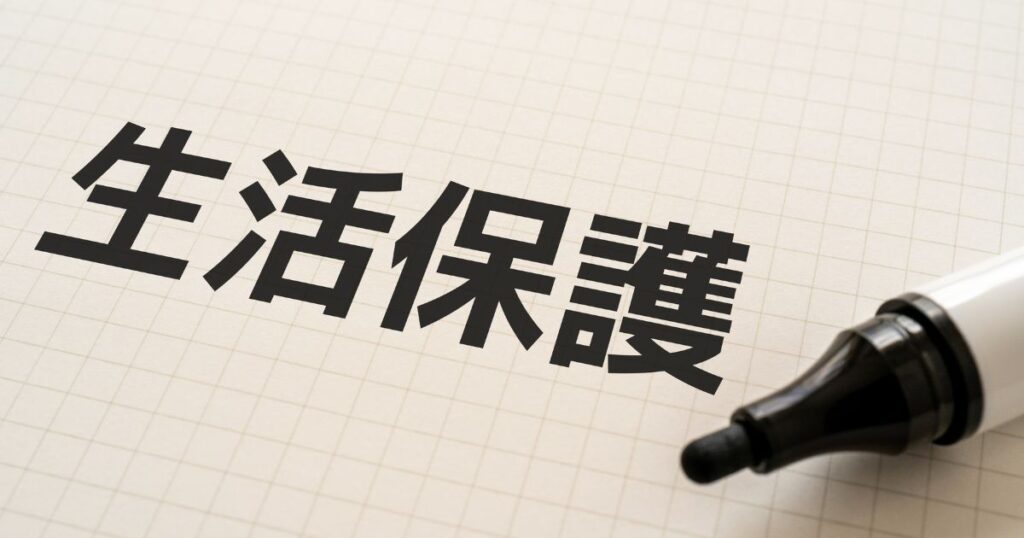
生活保護とは、生活に困窮している人や病気やケガ、障害などで就労できない人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活の保障と自立の助長を目的とした支援制度のことです。(参考:厚生労働省「生活保護制度」、厚生労働省「「生活保護制度」に関するQ&A」)
生活に必要な最低限度のお金を持つことが困難な人が、お金を受給できる制度とも言えます。
お住まいの自治体を所管する福祉事務所、またはお住まいの自治体に福祉事務所がない自治体の場合、お住まいの自治体の生活保護を担当する部署・窓口で行えます。
なお、一定の資産がある場合、申請できないため注意してください。
また、生活保護は最後のセーフティネットとも呼ばれるように、本当にサポートが必要な人だけを対象とする支援制度です。
一般的に審査が厳しく、生活保護以外の支援制度の利用を提案されたり、申請が却下されたりする可能性があることを心に留めておいてください。
生活保護の概要やメリット、申請する流れなどについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
生活保護の種類
生活保護の種類は、以下のとおりです。
- 生活扶助:食費・被服費・光熱費等
- 住宅扶助:アパートなどの家賃
- 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費
- 医療扶助:医療サービスの費用
- 介護扶助:介護サービスの費用
- 出産扶助:出産費用
- 生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用
- 葬祭扶助:葬祭費用
ただし、受給金額は、地域や世帯の状況などによって異なります。
生活保護の減免措置

生活保護の減免措置は、以下のとおりです。(参考:東京都足立区「受給者用 生活保護のしおり」)
- 国民年金保険料
- 住民税
- 固定資産税
- NHK放送受信料
- 上下水道基本料金
- 都営住宅共益費
- 住民票の写し等の発行手数料
- 都営交通の無料乗車券の交付
ただし、減免措置は、世帯の状況などによって異なります。必ず減免されるわけではありません。
生活保護を申請する流れ・手続き
生活保護の申請をする前に、以下のようなことを検討・実行しましょう。
- 預貯金や、生活に利用されていない土地・家屋などを売却したお金を、生活費に充てる
- 働くことが可能な人は、その能力に応じて働く
- ほかの支援制度を利用できる場合は、まずそれらを利用する
- 親族などから援助を受けることができる場合は、援助を受ける
生活保護の申請方法は以下のとおりです。
- 福祉事務所に相談
- 生活保護の申請
お住まいの自治体を所管する福祉事務所の生活保護を担当する部署・窓口に相談します。お住まいの自治体に福祉事務所がない自治体の場合、お住まいの自治体の生活保護を担当する部署・窓口に相談します。
生活保護の決定のために、家庭訪問や預貯金・保険・不動産などの調査などが行われます。うつ病のある人の場合は、申請時に医師の診断書が必要な場合もあります。
申請が認められれば、受給が開始されます。厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から年金や就労収入などの収入を差し引いた金額を毎月受給します。
生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告する必要があります。また、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
また、働ける可能性のある人は、就職や労働についての助言を受けることができます。
補足:専門家や支援機関に相談したり、同席を求めたりしましょう

生活保護の申請への対応は、自治体によって異なります。一概に「こう申請すればよい」とは言えません。
また、うつ病の症状が重い場合は、一人で申請に行くのが難しいこともあるでしょう。書類の記載内容を理解しづらいなどもあるはずです。
その場合、申請に関連して、諸々の手続きなどをスムーズに進めていくために、専門家や支援機関に相談したり、同席を求めたりすることをオススメします。(参考:ヨミドクター「貧困と生活保護(21) 生活保護の申請は支援者と一緒に行こう」)
「同席にもお金がかかるのでは?」と心配かもしれません。しかし、ボランティアで活動している場合や、費用を国が負担する場合などもあります。
同席可能な専門家・支援機関の例は以下のとおりです。
- 民生委員
- ケースワーカー
- ソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)
- 生活困窮者自立支援の相談窓口(自治体の相談窓口)
- 弁護士・司法書士
- 通っている病院の社会福祉士や相談担当者
- 基幹相談支援センターの職員
- 自治体独自の支援者
状況に応じて、申請の手続き自体も、以上の専門家・支援機関が行えます。
家族や特に何らかの資格のない友人などの周囲の人も同席は可能です。
体験談:KBC利用者さんが感じた、申請時同席のメリット
私が生活保護を申請しようと決めたきっかけは、生活について相談をした支援機関の人から勧められたことです。申請時も、その支援機関の人に同行していただきました。
生活保護という制度は知っていたものの、詳しい内容までは知らず、「若い人は受けたらダメなのではないか」という勝手なイメージや、「家族に知られるのではないか」という心配がありました。
一人で申請に行っていたら、とても心細く、不安でいっぱいになっていたと思います。
生活保護の制度と自分の事情の両方を知っている人が一緒に居てくれたことで、心強く思えました。また、制度のよい使い方などアドバイスももらえて、大変助かりました。
(20代女性)
生活保護を利用するメリット

生活保護を利用するメリットとして考えられるのは、経済面の安定です。
特にうつ病のある人の場合、安心して治療に取り組めるようになるでしょう。日常生活や今後の就職・復職・転職に向けた活動などにも前向きになれると思います。
また、家族のサポートを受けている場合は、生活保護を早めに申請・受給することで、家族の経済的負担の軽減にもつながります。
体験談:KBC利用者さんが感じた、生活保護のメリット
生活保護を受給して一番よかった点は、家を借りることができて、安心して病気や生活の改善を始められたことです。
会社に勤めて一人暮らしをしていた私は、うつ病で退職して家賃を払えなくなり、家を失いました。
仕事と家を失うということは、お金も住所もなく、新しく仕事や家を探すことすらできないということです。保険証もなく、体調が悪くても病院へも行けないのです。
退職した頃はうつ病の症状も重く、何も考えられず、ひきこもり状態で、いろいろな支援制度の手続きが行えませんでした。
その後も症状はよくならず生活状況もどんどん悪化していき、気づけば何から手をつけて生活を立て直せばいいのかわからなくなっていました。
生活保護を受給したことで、一つ一つ生活の立て直しを行い、今はうつ病の症状も安定して、就職も決まりました。
(20代女性)
生活保護を利用する際の注意点

生活保護を利用する際は、以下のような点に注意が必要です。
- 利用前に、生活に利用されていない土地・家屋などを売却したお金を、生活費に充てる必要がある
- 利用中は、収入や資産を得た際などには、福祉事務所・役所に申告する必要がある
- 福祉事務所・役所の人の定期的な家庭訪問を受け、生活の維持向上のための指導・指示があった場合は従う必要がある
それぞれうつ病のある人には対応が大変な場合もあるかもしれません。
さまざまな専門家や支援機関と繋がっておくことで、そうしたやりとりも進めやすくなるでしょう。
うつ病とは?

うつ病とは、気分の落ち込みや憂うつ感、さまざまな意欲の低下などの精神的症状と、不眠、食欲の低下、疲労感などの身体的症状が一定期間持続することで、日常生活に大きな支障が生じる精神障害・気分障害のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、厚生労働省「1 うつ病とは:」、厚生労働省「うつ病に関してまとめたページ」、、厚生労働省「うつ病」、国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「うつ病」、株式会社メディカルノート「うつ病について」、MSDマニュアルプロフェッショナル版「抑うつ症候群」)
また、脳の機能が低下している状態、脳のエネルギーが欠乏した状態を指し、脳の中で神経細胞間のさまざまな情報の伝達を担うセロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンなどの神経伝達物質のバランスの乱れや、感情や意欲を司る脳の働きに何らかの不調が生じているものと考えられています。
うつ病の概要や症状、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
【無料配布中!】『生活保護・完全攻略ガイドブック』
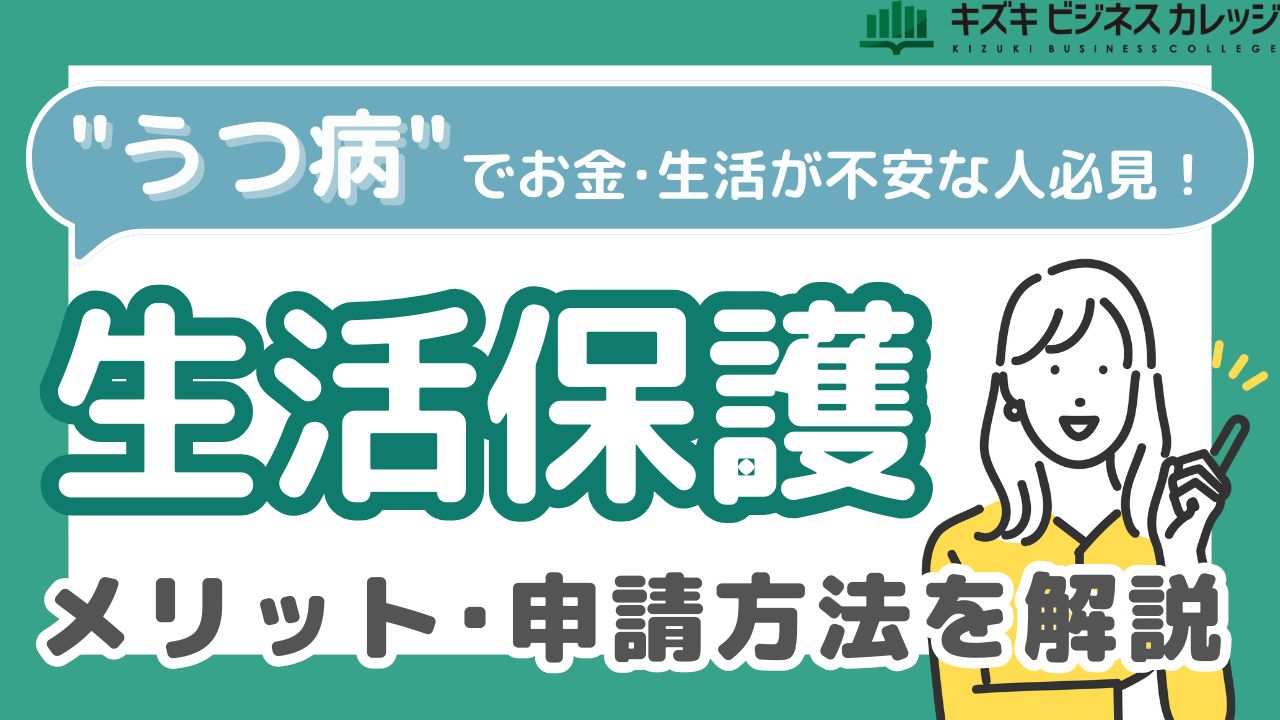
- うつ病で体が動かず働けない…
- 生活費が足りず、この先が不安…
このような悩みを抱えている人は少なくありません。
特に、うつ病による就労困難は、本人の意思や努力だけでは解決できず、生活や将来への不安が心身の回復をさらに妨げることもあります。
また、生活保護=甘えという誤解や制度に関する情報不足によって、生活保護を利用できず苦しんでいる人は少なくありません。
本資料では、うつ病などで働くことが難しい人に向けて、 生活保護の概要やメリット・注意点、申請方法をわかりやすくまとめています。
ぜひ、本資料を活用して、生活保護の申請という選択肢を視野に入れ、ご自身の今後について考えていきましょう!
- 生活保護の基礎知識
- 支援内容(生活費・医療費・住宅費など)
- 利用するメリット・注意点
- 申請の流れと準備事項
- 受給中の過ごし方についてのよくある質問
- うつ病の症状で働けず、生活に不安を感じている人
- 生活保護の申請を検討しているが迷っている人
- 制度の詳細や申請方法がわからず、困っている人
- 生活やお金について困っているものの、誰にも相談できず悩んでいる人
- すでに別の支援制度を利用しているが、それだけでは生活が厳しい人
- 家族や友人にうつ病で生活に困っている人がいる人
- リンクから申し込みフォームにアクセス
- 簡単なフォームに入力
- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り
- URLから資料を取得!
- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。
- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。
- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。
まとめ:あなたに合うサポートを探しましょう

うつ病のある人も、条件に当てはまれば生活保護を受給できます。
また、生活保護以外にもうつ病のある人も利用できる支援制度はたくさんあります。
改めて、生活保護などの支援制度の利用は、決して恥ずかしいことではありません。
医師や専門家、支援機関などと相談しながら、あなたに合う支援制度を探しましょう。
各支援制度を利用しながら治療も続けることで、うつ病の寛解や、就職・転職などの次の一歩も近づいてくるはずです。
生活保護とはどのような制度ですか?
生活保護とは、生活に困窮している人や病気やケガ、障害などで就労できない人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活の保障と自立の助長を目的とした支援制度のことです。
詳細については、こちらで解説しています。
生活保護を申請する前に確認すべきポイントはありますか?
以下が考えられます。
- 医師や支援機関などに相談しましょう
- 生活保護を利用することは正当な権利です。恥ずかしいことではありません
- 生活保護以外の支援制度の利用も検討しましょう
詳細については、こちらで解説しています。
監修志村哲祥
しむら・あきよし。
医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。
臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。
【著書など(一部)】
『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』
他、学術論文多数
日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧
時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
監修角南百合子
すなみ・ゆりこ。
臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→