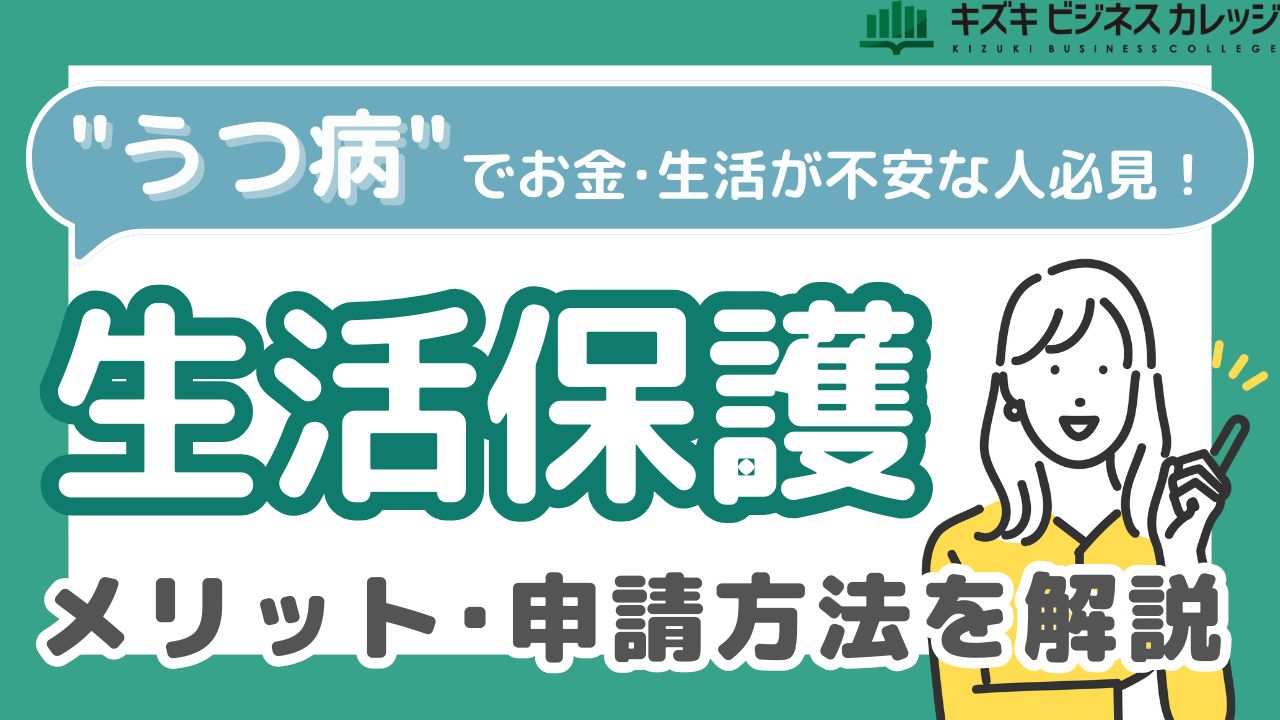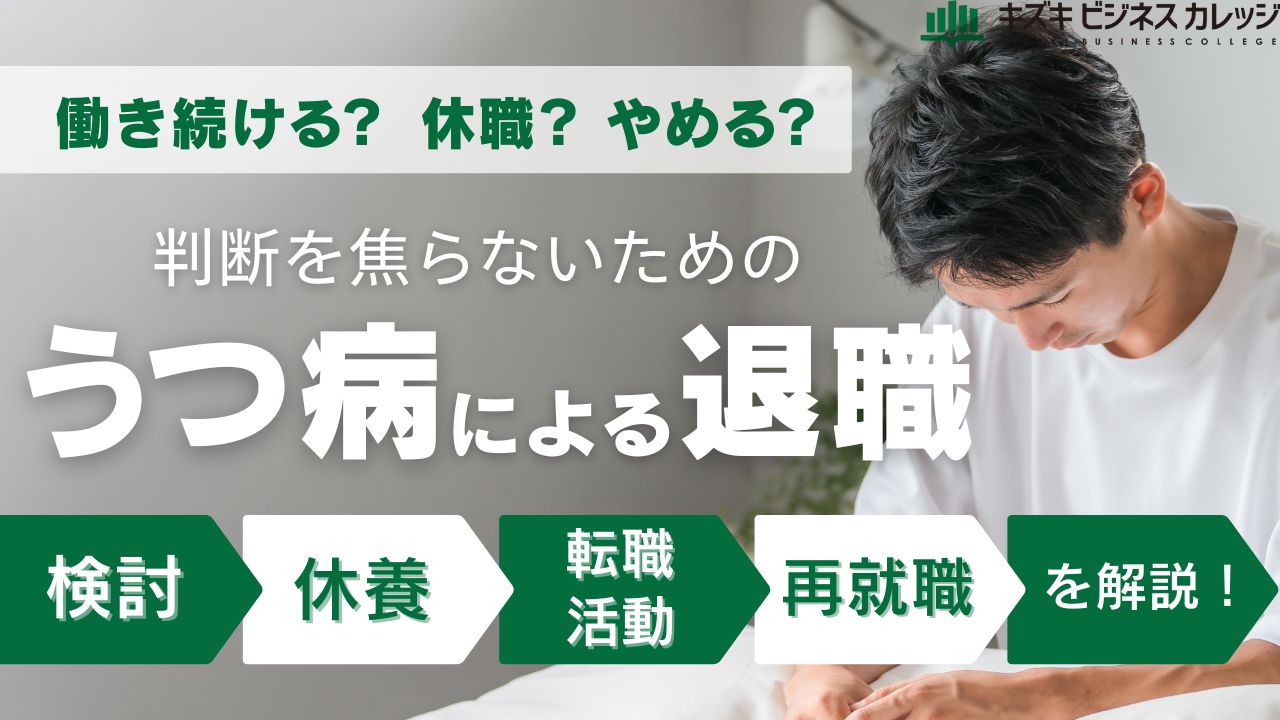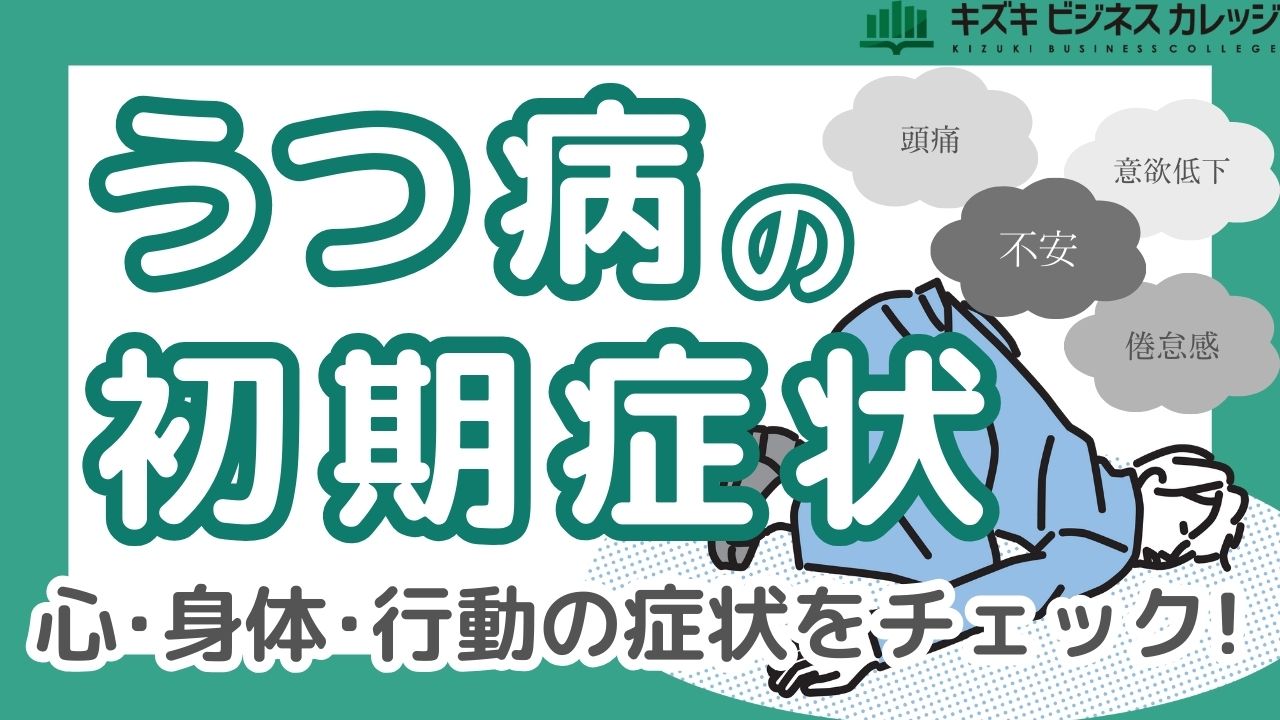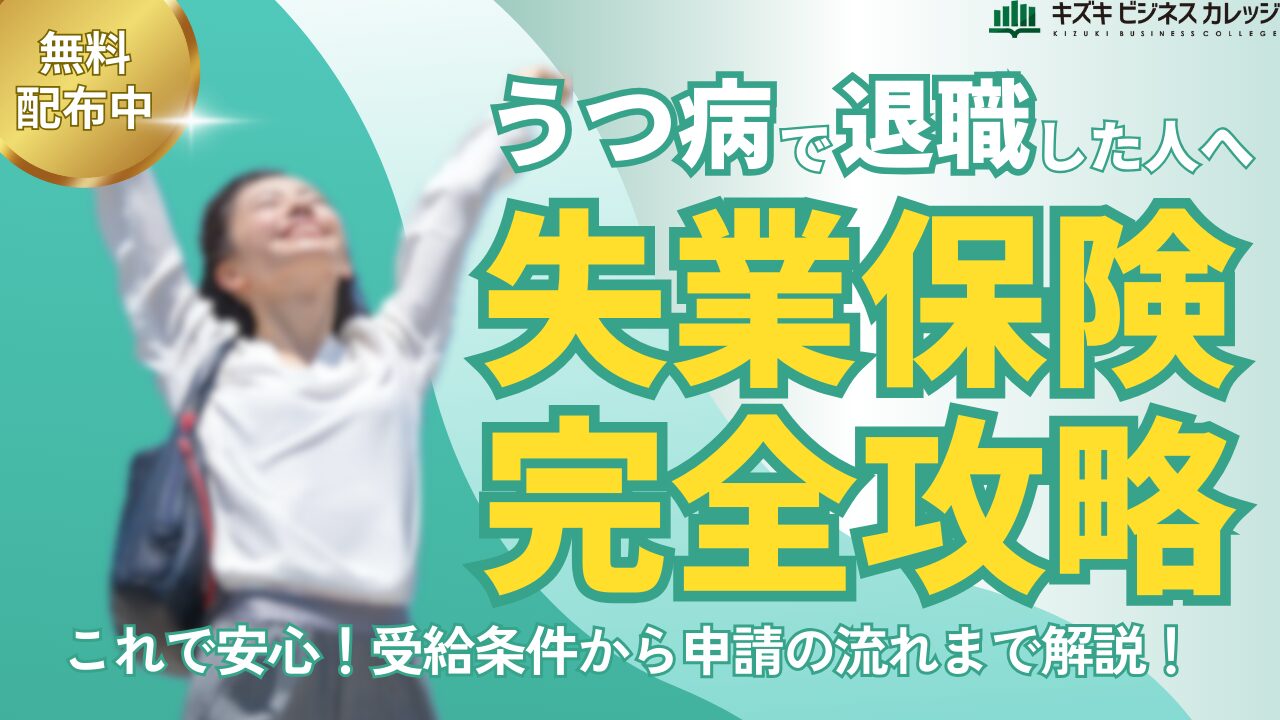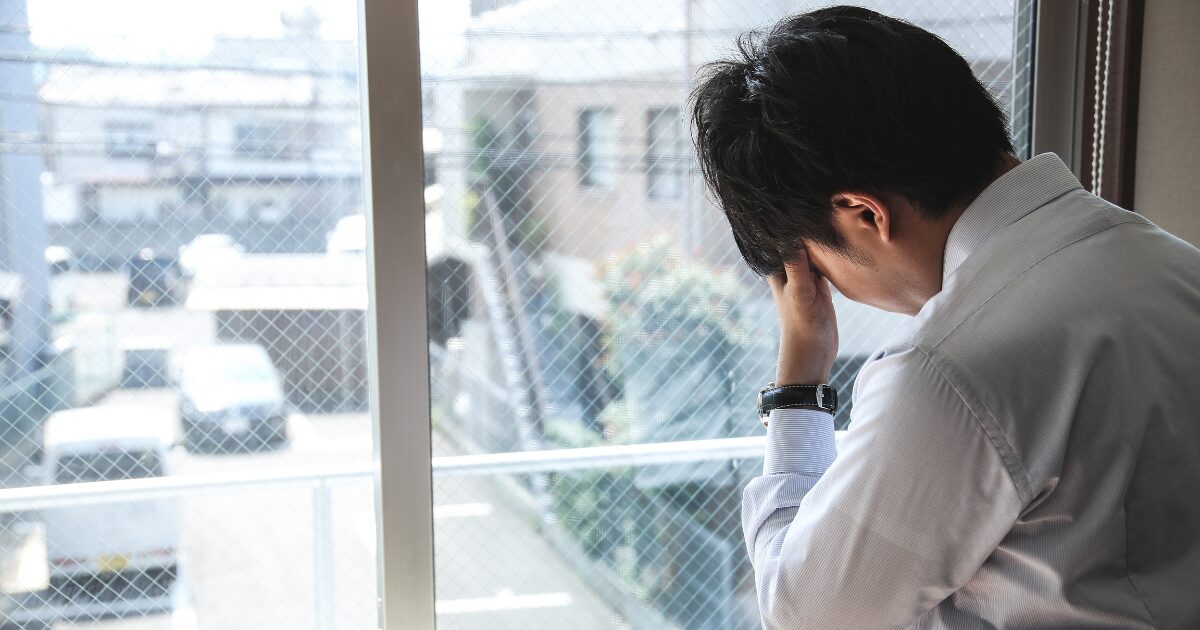うつ病と仕事を両立させるコツ10選 両立させるポイントを解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
うつ病のあるあなたは、仕事と両立させる方法がわからずに、悩んではいませんか?
うつ病は一朝一夕で治る病気ではありません。そのため、うつ病の治療を進めながら、仕事を続けている人が多いと思います。
しかし、うつ病の症状である意欲低下や疲れやすさのせいで、仕事と両立することが難しく感じられる人も少なくありません。
このコラムでは、うつ病を治療しながら仕事を続けた経験のある筆者の経験に基づき、うつ病と仕事を両立させるコツや両立させるためのポイントについて解説します。
お悩みの人はぜひ参考にしてみてください。
さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、支援を利用するかどうか悩んでいるうつ病のある方に向けて、「お金・仕事・自立の不安を解消!"うつ病"のある人のための支援機関・支援制度ガイドブック」の無料配布を開始いたしました。
うつ病のある方が利用できる支援機関・支援制度の概要、利用条件、利用方法までを、わかりやすく丁寧に解説しています。
ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。
仕事との両立を検討しているうつ病のあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
うつ病と仕事の両立は可能

うつ病と仕事の両立は可能です。
前提として、うつ病の診断を受けたら、最優先で寛解(かんかい)、つまり症状がほとんど目立たなくなり、日常生活がおくれるようになる程度まで症状が軽減した段階になるまで休養を取ることが必要です。
しかし、うつ病のある人の中には、様々な事情から治療と仕事の両立を考えなくてはならないという方も多いと思います。
経済面の不安を感じた場合は、職場に休職制度などがあるかを確認した上で、支援制度の利用などを検討してみてください。
その際には、職場の上司や人事担当者、後述する産業医などに相談することが大切です。
また、うつ病を治療しながら仕事を続ける場合、ご自身でうつ病に関する知識や注意点を理解しておくことも大切です。
とりわけ、主治医への相談は、絶対に欠かさないようにしてください。
休職する場合でも、あるいは休職後に復職する場合でも、専門医の診断書が必ず求められます。
診断書は医師のみが記載できます。さまざまなサポートを受ける際にも診断書を求められることがあるため、主治医とはしっかりと相談をしましょう。
適切な支援を受ければ、寛解してからでも仕事に復帰することは十分可能ですので、絶対に焦らないことを心掛けましょう。
うつ病と仕事を両立させるコツ10選
この章では、うつ病と仕事を両立させるコツについて解説します。(参考:佐藤隆『職場のメンタルヘルス実践ガイド』、川上憲人『基礎からはじめる職場のメンタルヘルス』)
前提:無理をせず、主治医の判断に従う

前提として大切なのは、無理をしないこと、そして主治医の判断に従うことです。
もし病状が悪化した際には、医師と相談した上で、十分な休養を取るようにしましょう。
また、自己判断での断薬は絶対にしないでください。
眠気などの副作用が気になる場合であっても、主治医と相談の上、薬の量や種類を徐々に変えていくことが必要になります。
コツ①通院やカウンセリングを続ける
まず、どんなに仕事が忙しくても、通院はきちんと続けるようにしてください。
臨床心理士によるカウンセリングなどを受けている場合も同様です。
通院を怠ることで、あなたの心身のリズムが崩れる可能性があります。
もし、「医師の診断にどうしても納得できない」「処方された薬を服用することに抵抗がある」という場合は、セカンドオピニオンなどを求めて別の病院を受診するのも、ひとつの手段です。
ただし、一般論として、別の医師でも治療の方針があまり変わらないようなら、多少納得できない面があったとしても、元の方針に従うことをオススメします。
また、代替医療や民間療法ではなく、専門の医療機関の治療を受けるようにしましょう。
コツ②定期的に産業医面談を受ける

2つ目のコツは、定期的に産業医面談を受けることです。
産業医とは、労働者の健康管理について助言や指導を行う医師のことです。(参考:厚生労働省「産業医について」)
労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者が在籍する事業所に1人以上、3000人超の事業所では2人以上の産業医が配置されています。
以上の条件を満たしていれば、あなたの職場にも産業医がいるはずですので、一度確認してみてください。
人によっては、面談の結果が人事査定に影響するのではないかと心配されるかもしれませんが、産業医は中立的な立場から面談を行います。ご安心ください。
もし、産業医が職場の上司から説明を求められたとしても、個人情報保護の観点から、共有してよいかを原則ご本人に確認することになります。
料金なども発生しませんし、場合によっては上司も同席の上で、業務に関する具体的な相談をすることも可能です。ぜひ一度、利用してみてください。
コツ③支援機関に通所・相談する
うつ病と仕事を両立したい人は、支援機関に通所・相談するのも一つの手段です。
うつ病の診断を受けた人に対して、障害福祉サービスを提供している支援機関は、公民を問わずたくさんあります。
中には、就労移行支援事業所などのように、単にうつ病の症状に関する相談だけでなく、仕事で活かせる自己管理の方法や、実践的な仕事術、専門的なスキルの講習など、多様な支援を行っている機関もあります。
サービスの内容にもよりますが、基本的には無料でサービスを受けられるところばかりです。そうした支援機関も、相談先の選択肢として持っておくとよいでしょう。
支援機関については、こちらで紹介します。
コツ④できる範囲で職場の同僚の理解を得る

うつ病について職場の同僚の理解を得ることも大切です。
うつ病のある人は、仕事中に気分が悪くなったり、通勤時に調子を崩したりすることが少なくないかと思います。
そうしたときに、職場の同僚に病状のことを伝えてあると、周囲が仕事の穴をカバーしたり、シフトに融通を利かせたりと、サポートを受けやすくなるでしょう。
また、職場の方でも、理由を明かされずに欠勤となるより、理由があらかじめわかっていた方が安心できるという面があります。
できる範囲で構いません。信頼できる人から、病状を話してみてください。
コツ⑤残業は極力控える
調子を大きく崩さずに仕事を続けたいのであれば、残業は極力控えるようにしましょう。
うつ病のような気分障害では、調子のムラが生じやすいため、「今日は具合がいいからもっと進めておこう」「今日は残業しても大丈夫そうだ」と感じることもあると思います。
しかし、そこで無理に残業をしたりすると、週の後半に体調を崩したり、休日に身体を休めても疲れが取れなかったりと、どこかにひずみが生じる可能性があります。
うつ病の症状を考慮に入れて、無理はせず、普段から残業をしないで済むような仕事のスケジュールを立てるようにしましょう。
コツ⑥余裕を持って行動する

6点目は、「余裕を持って行動する」です。
具体的な業務の予定だけでなく、例えば、通勤時に気分が悪くなって駅で休んでも問題なく出社できる時間に家を出たり、満員電車を極力避けたりするなど、できるだけご自身の負担を減らす方向で行動を取ることが大切です。
余裕を持って行動することで、不測の事態が起こったときにも、過度に慌ててストレスを感じることが減ります。日頃から予定を詰めすぎていないかという点に注意しましょう。
コツ⑦生活習慣を整える
7点目は、生活習慣を整えることです。
就寝と起床の時間は、なるべく一定にするよう心掛けましょう。
睡眠リズムの乱れは、生活リズムの乱れに直結するだけでなく、あなたの仕事のパフォーマンスや、日頃感じるストレスにも大きく影響します。
また、特に薬物療法を受けている人などは、アルコールやカフェインの摂取に注意してください。
これらの嗜好品は、薬効に悪影響を及ぼす可能性があるだけでなく、頭痛や不安の原因にもなることもあります。
また、依存性もあるため、ストレス解消につながるように思えても、控えるのが賢明でしょう。
コツ⑧自分なりのリラックス法を身につける

8点目は、自分なりのストレス対処法を身につけることです。
仕事を続ける以上、ストレスは避けて通れません。
そのため、ストレスが溜まったときに、上手に発散する方法を身につけることが大切です。
気心の知れた友人と雑談をしたり、好きなスポーツに興じたりと、あなたなりのストレス対処法を探してみてください。
また、ちょっとした隙間時間に、一人でできるリラックス法を修得するのも有効です。
一例として、私が実践しているリラックス法を挙げておきます。
- 深呼吸をする
- 簡単な屈伸運動やストレッチをする
- 職場の周りを散歩する
- 肩の力を抜き、目を閉じて数秒じっと休む
ストレスを軽減するだけでなく、発散する方法も身につけるようにしましょう。
コツ⑨短時間勤務制度などを利用する
9点目は、短時間勤務制度などを利用することです。
これは特に、調子の波が激しいことで悩んでいる人にオススメしたいコツです。
うつ病のある人の場合、朝はつらいけど午後からなら出勤できる、調子次第で勤務時間に融通を利かせたいと感じることが度々あると思います。
そういった方は、短時間勤務制度を活用するだけで、仕事との両立がずっと楽になります。
まずは、人事を担当する部署に制度があるかを確認し、申請可能か確認してみましょう。
コツ⑩どうしてもつらいときは休職する

仕事との両立にこだわらないで、どうしてもつらいときは休職するという選択も大切です。
仕事をある程度長く休むことになると、通常の有給休暇をつなげるという方法もあります。しかし、休職制度があるのなら利用した方がよい場合もあります。
というのも、休職から復職したときに、仕事への慣れを取り戻すために、最初は休みを挟みながらの出勤になることが多いからです。
ただし、職場によって休職中の給与支給の有無や適用期間など、条件が異なりますので、その点をきちんと精査してから休職に入ることが大切です。
実際に検討する際には、まずは医師に相談の上で、上司や人事担当者と面談をするようにしましょう。
繰り返しにはなりますが、なによりも優先すべきは、あなたの体調なのだということを、忘れないようにしてください。
うつ病と仕事を両立させるためのポイント5点
この章では、うつ病と仕事を両立させるためのポイントについて解説します。
もし、仕事と両立しはじめたものの、調子を崩したというときには、無理をせずに医師に意見を求めることが大切です。
あなた自身は「もう少し頑張れるはず」と思っていても、専門家の目からすると、休養が必要という場合があります。
仕事との両立を考えているうつ病のある人は、その点を念頭に置いて、以下のポイント5点を意識するようにしましょう。(参考:五十嵐良雄『うつ病・躁うつ病で「休職」「復職」した人の気持ちがわかる本』、厚生労働省「いわゆる新型うつの理解と対策は?」)
ポイント①問題を一人で抱え込まない

まずは、問題を一人で抱え込まないことが大切です。
ここで言う問題とは、うつ病の症状に限らず、仕事やプライベートなどで、あなたがいま抱えている悩みのことです。
問題を一人で抱え込むと、ストレスを溜めやすくなるだけでなく、解決の糸口になりえる新情報や適切なアドバイスを得る機会が少なくなります。
そのため、悩みがあるという人は、可能な限り、信頼できる人に相談しましょう。
また、医師やカウンセラーは、うつ病に関することだけでなく、仕事やプライベートなど一見すると関わりのないようなことも含めて、総合的に話を聴いた上でアドバイスをします。
問題を一人で抱え込む前に、まずは、そういった専門家に悩みを打ち明けることをオススメします。
ポイント②すぐに治そうと焦らない
2点目は、すぐに治そうと焦らないことです。
うつ病と仕事の両立を目指す場合、症状の影響で作業効率が下がったり、疲れが取れなかったりなど、思うようにいかないことが少なくありません。
そういったことが重なると、「うつ病は甘えなんじゃないか」と人に言われたり、自分でも「努力が足りてないだけなんじゃないか?」と思い詰めたりする人もいると思います。
そのため、いち早くその状況から抜け出したいと思い、「とにかく早く治したい」「気の持ちようですぐに治せるはず」と焦りを感じることも多いはずです。
しかし、その焦りがプレッシャーになり、「早く治したいのに少しもよくならない」「こんなに長引くようだと、もう治らないんじゃないか」と落ち込んだり、症状を悪化させたりすることがあります。
すぐに治そうと焦るよりも、「時間がかかってもきちんと治そう」「この機会に生活習慣や環境を見直そう」と前向きに捉えた方が、心にゆとりが生まれます。
すぐに治そうと焦らずに、余裕を持って治療を進めることを意識しましょう。
ポイント③症状を受け入れる

症状を受け入れることも、仕事との両立のために大切です。
例えば、うつ病だと、夕方になると疲れて、仕事が手につかないということも比較的多いと思います。
そうしたときに、発症以前の感覚で「夕方以降も頑張れるはず」と考えていると、スケジュール通りに進まず、モチベーションも下がる可能性があります。
そのため、「夕方は疲れが出るから、この仕事は午前に終わらせておこう」「明日に回しても大丈夫なように、納期に余裕を持たせよう」と、自身の症状を受け入れた上で予定を立てることをオススメします。
ポイント④原因を考えすぎない
4点目は、原因を考えすぎないことです。
うつ病には明確な原因がないというケースが多々あります。
仮に原因があったとしても、それが解消されたからといって、すぐに抑うつ症状がなくなるとは限りません。
したがって、原因についてはあまり考えすぎず、まずは症状を受け入れた上で、どう治していくか、どう生活していくかといった具体的な方針・方策を考えて、実践していくことをオススメします。
ポイント⑤公私ともに無理をしない

最後は、公私ともに無理をしないことです。
うつ病だと、身体がだるかったり、疲れやすかったりするため、無理に仕事をすると、翌日まで疲労が残ることが多いです。
そのため、公私ともに無理をしないことが、うつ病と仕事を両立させるための秘訣です。
うつ病とは?

うつ病とは、気分の落ち込みや憂うつ感、さまざまな意欲の低下などの精神的症状と、不眠、食欲の低下、疲労感などの身体的症状が一定期間持続することで、日常生活に大きな支障が生じる精神障害・気分障害のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、厚生労働省「1 うつ病とは:」、厚生労働省「うつ病に関してまとめたページ」、、厚生労働省「うつ病」、国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「うつ病」、株式会社メディカルノート「うつ病について」、MSDマニュアルプロフェッショナル版「抑うつ症候群」)
また、脳の機能が低下している状態、脳のエネルギーが欠乏した状態を指し、脳の中で神経細胞間のさまざまな情報の伝達を担うセロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンなどの神経伝達物質のバランスの乱れや、感情や意欲を司る脳の働きに何らかの不調が生じているものと考えられています。
うつ病の概要や症状、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
【無料配布中!】「”うつ病”のある人のための支援機関・支援制度ガイドブック」
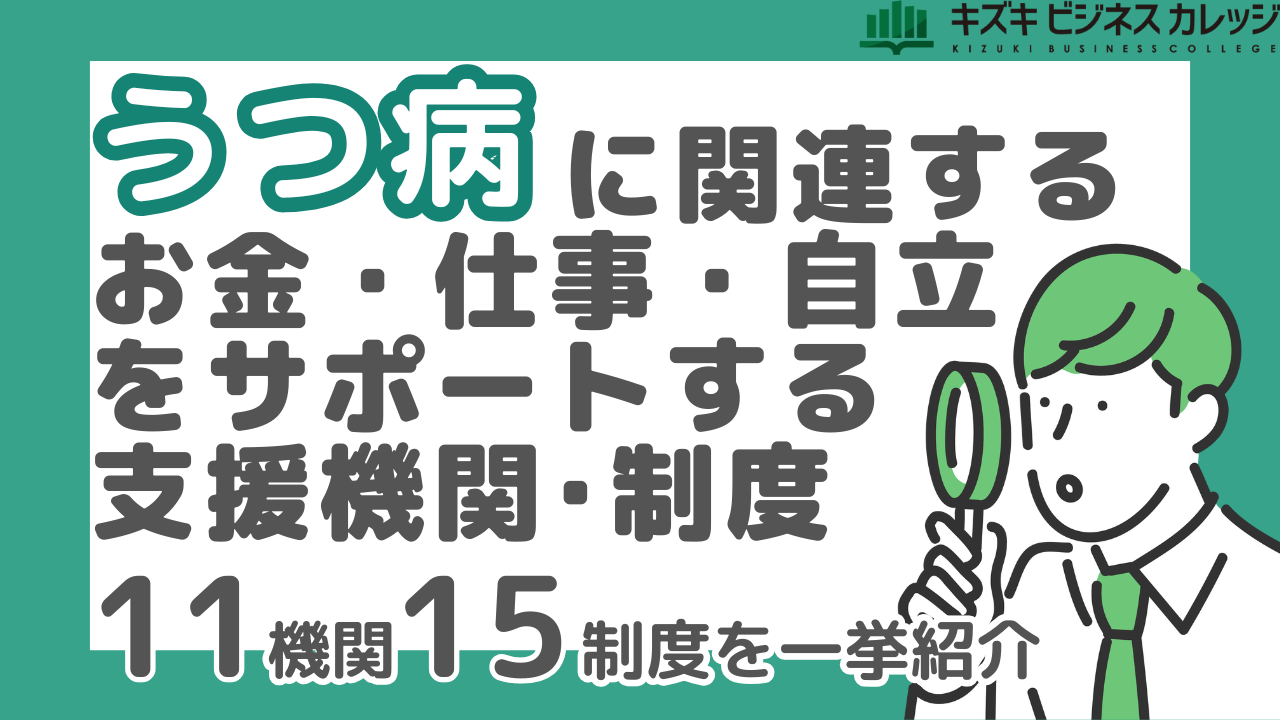
- 「支援を利用したいけど、どこに相談すればいいかわからない…」
- 「手続きが難しそうで、自分でできる気がしない」
このように、うつ病のある人は支援を利用したいと思っても、どこに相談すればいいのかわからなかったり、制度の内容が難しかったりすることで、支援を活用できないことは少なくありません。
本資料では、うつ病のある人が利用できる主な支援機関や支援制度をわかりやすく整理しました。
加えて、各支援機関・支援制度の概要や利用条件、利用方法など、支援を活用するための情報を厳選してまとめています。
少しでも負担が軽くなるよう、支援を受けるためのヒントとしてご活用いただければ幸いです。
- 医療・福祉的な支援機関・制度
- 経済的な支援機関・制度
- 就労に関する支援機関・制度
- つながりをつくるための支援機関・制度
- どこに相談していいかわからない方の相談先
- うつ病になりどうすればいいかわからず悩んでいる方
- うつ病の症状がつらく誰かに相談したい方
- お金や今後の生活など、経済面でお困りの方
- 今後の仕事や働き方について考えたい方
- うつ病など自分と似た経験をした人とのつながりたい方
- ご家族や支援者として正しい知識を持ちたい方
- リンクから申し込みフォームにアクセス
- 簡単なフォームに入力
- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り
- URLから資料を取得!
- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。
- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。
- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。
まとめ:うつ病と仕事を両立させるには周囲の助けが必要です

繰り返しにはなりますが、大切なのは、一人で抱え込まずに周囲の人に相談することです。
無理をすると、症状の悪化につながる可能性があります。かかりつけの医師や産業医、専門家、支援機関などの意見を聴きながら、慎重に仕事を続けていく意識を保ちましょう。
周囲の助けを借りながら、焦らずに治療に励めば、うつ病と仕事を両立させることは充分に可能です。
このコラムが、うつ病と仕事の両立を目指す人の参考になれば幸いです。
うつ病と仕事は両立できるのでしょうか?
うつ病と仕事の両立は可能です。前提として、うつ病の診断を受けたら、最優先で寛解(かんかい)、つまり症状がほとんど目立たなくなり、日常生活がおくれるようになる程度まで症状が軽減した段階になるまで休養を取ることが必要です。
詳細については、こちらで解説しています。
うつ病と仕事を両立できるコツを教えてください。
監修志村哲祥
しむら・あきよし。
医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。
臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。
【著書など(一部)】
『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』
他、学術論文多数
日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧
時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
監修角南百合子
すなみ・ゆりこ。
臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→