ADHDのある大人の特徴 特性への対処法を解説
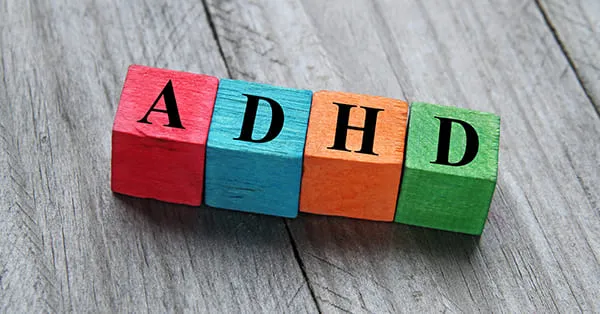
こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)の堺です。
あなたは、自分はADHDではないかと悩んではいませんか?
ADHDや発達障害という言葉を聞くと、子どものものと感じるかもしれません。
しかし、近年、子どものうちは問題なく成長してきても、大人になって生きづらさを感じることで医療機関などを受診し、発達障害と診断されるケースが増えています。
かくいう筆者も、大人になってからADHDと判明した、大人のADHDの当事者です。
以下のような生きづらさを抱える人は、もしかすると大人のADHDかもしれません。筆者も経験しました。
- がんばっても仕事が上手くいかず、続かない
- 自分ではどこが悪いのかわからないけど、人間関係の悩みが尽きない
このコラムでは、ADHDのある大人の特徴や特性への対処法、向いてる仕事などについて解説します。あわせて、ADHDに関する相談先を紹介します。
このコラムを読むことで、大人のADHDへの理解が深まり、次の一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
ADHDの特性のお悩みのあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
ADHDとは?

ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害、Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)とは、不注意性や多動性・衝動性の特性から日常生活などに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、田中康雄・監修『大人のAD/HD』、岩波明『大人のADHD─もっとも身近な発達障害』、司馬理英子『ササッとわかる 「大人のADHD」 基礎知識と対処法』、星野仁彦『それって、大人のADHDかもしれません』、e-ヘルスネット「ADHD(注意欠如・多動症)の診断と治療」)
ADHDの特性は大きく、以下の2つの特性に分けられます。
- 不注意性:忘れ物やケアレスミスが多い、注意散漫、整理整頓・管理が不得意
- 多動性・衝動性:落ち着きがない、気が散りやすい、後先考えず行動する
ADHDのある人だからといってすべての特性が生じるというわけではありません。いずれかの特性、または複数の特性から困難が生じている人もいます。
ADHDのある人は、必ず不注意性や多動性・衝動性が現れるというわけではなく、人によって特性の現れ方、得意なこと・不得意なことが違う点が大きな特徴です。
ADHDの概要や特性、診断基準などについては、以下のコラムで解説しています。
大人のADHDとは?
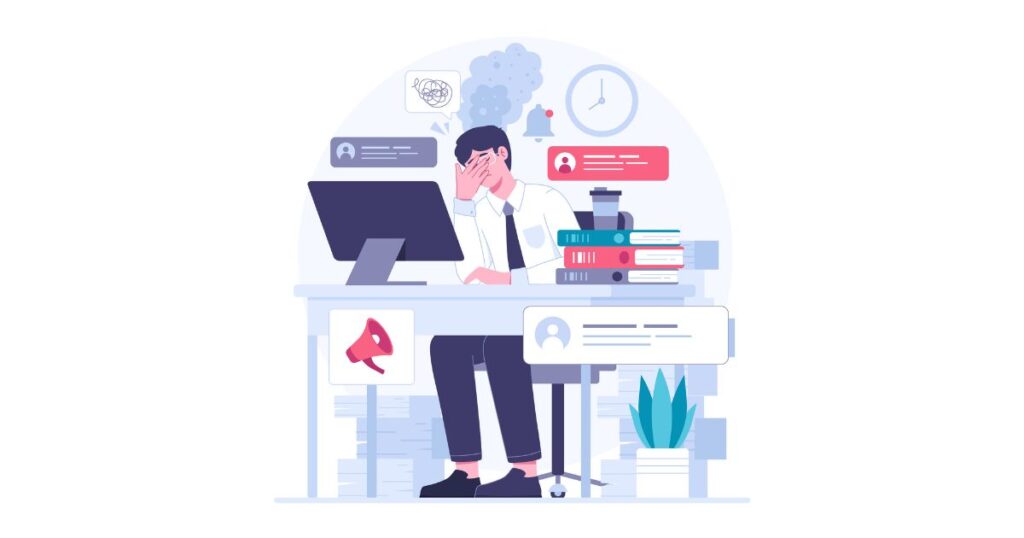
大人の発達ADHDは、医学的に正式な診断名称ではない俗語です。(参考:林寧哲『これでわかる 大人の発達障害』、黒澤礼子『新版 大人の発達障害に気づいて・向き合う完全ガイド』)
明確に定められた定義はありませんが、一般的には、幼少期の時点で診断を受けておらず、大人になってからADHDの確定診断を受けた状態のことを指すようです。また、幼少期の時点でADHDの確定診断を受けていた人が、大人になった状態のことを、大人のADHDと表現することもあるようです。
なお、ADHDなどの発達障害は、脳の構造的な特性によって生じる、生まれつきのものです。本来、ADHDの特徴は一般的に乳幼児から幼児期に現れます。大人と子どもで本質的には異なる部分はなく、現在の医学では、大人になっても継続するものとされています。
そのため、「大人になってからADHDになる」「成長するにつれてADHDになる」ということはありえません。また、「思春期から」「育ち方や親のしつけの影響で」など、成長してから、または成長につれて後天的にADHDになるということもありえません。
大人の発達障害については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
ADHDのある大人の特徴
ADHDのある大人の特徴は、以下のとおりです。(参考:岩波明『大人のADHD─もっとも身近な発達障害』、星野仁彦『それって、大人のADHDかもしれません』)
なお、ADHDのある大人全てに、以下の特徴が必ずあるとは限りません。また、以下の特徴に当てはまる場合でも、必ずADHDであるというわけではありません。
- 忘れ物や失くし物が多い
- 整理整頓が苦手
- 注意散漫でのケアレスミスが多い
- 確認作業が苦手
- 片づけができない
- じっとしていられず落ち着きがない
- 気が散りやすい
- 人の話を聞いていない
- 直接話しかけられても、話を聞いているように見えない
- 思いついたままに発言し、行動する
- 特定のものごとに極端に熱中する
- 他人の会話をさえぎったり、割り込んだりする
- 指示を最後までやり遂げず、仕事を終えられない
- 課題や仕事を計画的に進めることが困難である
- おしゃべりが止まらず、人が口を挟む隙を与えない
- マルチタスクやスケジュール管理が苦手
- 順番を待つのが苦手
- 我慢をすることが苦手
- 時間の経過を正確に把握できない
- 時間の見積もりが甘い
- 未来の予定を具体的にイメージできない
- 時間に対する焦燥感を感じにくい
- 約束を守れない
- 衝動買いをすることがある
- 金銭管理が苦手
- 発想力や独創性に優れている
- アイデアがたくさん浮かぶ
- 好奇心が強く、行動力や決断力がある
- 興味のあることには抜群の集中力を発揮する
自分はADHDかもしれないとな悩む大人ができる対処法2選

自分の特徴や特性が本当にADHDによるものなのか、気になっている人もいると思います。
筆者自身も、自分がADHDではないかと思った際に、どうすればよいのか、本当にADHDなのか、大きく悩んだ時期がありました。
このコラムでは、ADHDのある大人ができる対処法について解説します。
もし、ご自身の特徴が気になる場合は、参考としてみてください。
対処法①ADHDの診断基準を知る

アメリカ精神医学会が定めた精神障害の診察基準『DSM-5』によると、ADHDの診断基準は以下のとおりです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』)
診断基準に当てはまれば、ADHDの可能性があります。
- (a)学業、仕事、または他の活動中に、しばしば綿密に注意することができない、または不注意な間違いをする (例:細部を見過ごしたり、見逃してしまう、作業が不正確である)
- (b)課題または遊びの活動中に、しばしば注意を持続することが困難である (例:講義、会話、または長時間の読書に集中し続けることが難しい)
- (c)直接話しかけられたときに、しばしば聞いていないように見える (例:明らかな注意を逸らすものがない状況でさえ、心がどこか他所にあるように見える)
- (d)しばしば指示に従えず、学業、用事、職場での義務をやり遂げることができない (例:課題を始めるがすぐに集中できなくなる、また容易に脱線する)
- (e)課題や活動を順序立てることがしばしば困難である (例:一連の課題を遂行することが難しい、資料や持ち物を整理しておくことが難しい、作業が乱雑でまとまりない、時間の管理が苦手、締め切りを守れない)
- (f)精神的努力の持続を要する課題(例:学業や宿題、成人では報告書の作成、書類に漏れなく記入すること、長い文書を見直すこと)に従事することをしばしば避ける、嫌う、またはいやいや行う
- (g)課題や活動に使うようなもの(例:学校教材、鉛筆、本、道具、財布、鍵、書類、眼鏡、携帯電話)をしばしばなくしてしまう
- (h)しばしば外的な刺激(成年後期および成人では無関係な考えも含まれる)によってすぐ気が散ってしまう
- (i)しばしば日々の活動(例:用事を足すこと、お使いをすること、青年後期および成人では、電話を折り返しかけること、お金の支払い、会合の約束を守ること)で忘れっぽい
- 上記の項目のうち、6つ以上の項目が少なくとも6か月以上続いている
- 症状のいくつかが2つ以上の環境(職場・家庭・学校など)で見られる
- 12歳以前から複数の症状が見られる
- (a)しばしば手足をそわそわ動かしたりトントン叩いたりする、またはいすの上でもじもじする
- (b)席についていることが求められる場面でしばしば席を離れる (例:教室、職場、その他の作業場所で、またはそこにとどまることを要求される他の場面で、自分の場所を離れる)
- (c)不適切な状況でしばしば走り回ったり高い所へ登ったりする (注:成人では、落ち着かない感じのみに限られるかもしれない)
- (d)静かに遊んだり余暇活動につくことがしばしばできない
- (e)しばしば”じっとしていない”、またはまるで”エンジンで動かされているように”行動する (例:レストランや会議に長時間留まることができないかまたは不快に感じる;他の人には、落ち着かないとか、一緒にいることが困難と感じられるかもしれない)
- (f)しばしばしゃべりすぎる
- (g)しばしば質問が終わる前に出し抜いて答え始めてしまう (例:他の人達の言葉の続きを言ってしまう;会話で自分の番を待つことが困難である)
- (h)しばしば自分の順番を待つことが困難である (例:列に並んでいるとき)
- (i)しばしば他人を妨害し、邪魔する (例:会話、ゲーム、または活動に干渉する;相手に聞かずにまたは許可を得ずに他人の物を使い始めるかもしれない;青年または成人では、他人のしていることに口出ししたり、横取りすることがあるかもしれない)
- 上記の項目のうち、6つ以上の項目が少なくとも6か月以上続いている
- 症状のいくつかが2つ以上の環境(職場・家庭・学校など)で見られる
- 12歳以前から複数の症状が見られる
対処法②医師による検査・診断を受ける
チェック項目に当てはまるからといって、必ずしもADHDと診断されるわけではありません。
ADHDの診断は、心療内科・精神科・神経科などで生育歴の確認、知能検査なども経て、医師が総合的に判断して行われます。
筆者も実際に検査を受け、ADHDと診断されました。
当時の心境としては、ADHDかもしれないと悩んでいたときに比べると診断を受けることで、これまでの苦労の原因がわかり、心のどこかがほっとして落ち着いた気分になったことを覚えています。
補足:ADHDだと診断できるのは医師のみ

ADHDの診断は、医師による問診や心理士が実施する心理検査を中心に行われます。
ADHDの診断は医師だけが可能です。
自分はADHDであると思っている場合でも、必ずしも、ADHDであるとは限りません。
どういった状態が診断基準に当てはまるか、他の病気や障害の可能性がないかどうかを含めて、医師だけが判断できます。
診断基準にあるいずれかの症状に該当していると思う場合でも、自身で「ADHDである」と判断しないようにしましょう。
ADHDであるかどうかを知りたい場合、病院を受診することをオススメします。
診断を受けるのが不安な場合、事前に支援機関やお住まいの自治体の発達障害支援センター、あるいは、障害福祉を担当する部署・窓口などに相談してみてください。
ADHDのある大人ができる特性への3つの対処法

ADHDの特性に働きかける治療や対応は確立されてきています。なお、根本的にADHDではなくなるための治療や対応は現在のところありません。
この章では、ADHDのある大人ができる特性への対処法について解説します。
紹介するもの以外にも対応はたくさんあります。特性や性格によって向き不向きがありますので、あなた自身のADHDの特性への対応は、医師や支援機関に相談しながら探すことをオススメします。
対処法①認知行動療法
対処法の一つは、認知行動療法です。(参考:国立研究開発法人国立精神・神経医療センター認知行動療法センター「認知行動療法とは」)
- 認知行動療法は、認知に働きかけて気持ちを楽にする精神療法(心理療法)の一種です。ストレスを感じた人は悲観的に考えがちになって、問題を解決できないこころの状態に追い込んでいきます。認知行動療法ではそうした考え方のバランスを取って、ストレスに上手に対応できるこころの状態をつくっていきます。
認知行動療法は「自分の思考の癖を知って、多角的な視点で物事を見ること」を目的としています。
不安やストレスを感じた場面で認知行動療法の手法を使用することで、思考の整理ができ、不安やストレスを軽減することができます。
結果、発達障害の二次障害と言われる不安やうつの症状の緩和ができます。
対処法②ソーシャルスキルトレーニング

ソーシャルスキルトレーニング(SST)という方法もあります。(参考:医療社団欣助会吉祥寺病院「SST(ソーシャルスキルトレーニング)について」)
- ソーシャルスキルトレーニング(SST)は、「生活技能訓練」または「社会生活技能訓練」と訳され、認知行動療法に基づいたリハビリテーション技法です。相手の気持ちや状況を尊重しながら、自分の気持ちや状況を上手に伝えられるスキルを学んでいきます。、ストレス対処や問題解決ができるようトレーニングすることで、発達障害の特性で生じる生きづらさを軽減していきます。
ソーシャルスキルトレーニング(SST)では、具体的な「困る場面」での対応方法を学び、学んだ対応方法を実践することで失敗を減らしていけます。
結果、対人場面などでの苦手意識が減り、自信に繋がります。
対処法③投薬治療
ADHDは病気ではありませんが、近年の研究によって脳の神経伝達物質に作用し、特性を緩和する薬が開発されています。
以下、代表的なものを紹介します。
- 脳内の神経細胞の間で情報を伝える神経伝達物質(ドパミン、ノルアドレナリン)を増加させ、神経機能を活性化し注意力を高めたり、衝動的で落ち着きがないなどの症状を改善します。(引用元:一般社団法人くすりの適性使用協議会「コンサータ錠18mg」)
コンサータは不適正な使用による依存や乱用のリスクを避けるために、処方できる病院・薬局が限られています。また、患者情報も「ADHD適正流通管理システム」というものに登録されます。
- 脳内の神経細胞の間で情報を伝える神経伝達物質を調節し、不注意や多動・衝動的で落ち着きがないなどの症状を改善します。(引用元:一般社団法人くすりの適性使用協議会「ストラテラカプセル25mg」)
- アドレナリン受容体に作用して、脳内の神経伝達物質の働きを調節することにより、注意欠陥/多動性障害の症状を改善します。(引用元:一般社団法人くすりの適性使用協議会「インチュニブ錠3mg」)
大人のADHDの人に有効な仕事術、特性を活かせる仕事、活躍できる職業

ADHDの特徴は大人になって仕事をする上で大きな困難となることもあります。
しかし、大人のADHDの特徴とうまく付き合いながら仕事で活躍する人もいます。
中にはその特性を活かし、仕事で大きな成果を上げる人もいるようです。
この章では、ADHDの人に有効な仕事術、強み、向いている仕事などを紹介いたします。
①ADHDに有効な仕事術
大人のADHDの人は、仕事の優先順位がつけられない、忘れ物が多い、片づけられないなど、多くの困りごとが発生します。
しかし、これらは対策を習慣づけることで乗り越えられることもあります。
下記は大人のADHDに生じやすい困りごとを減らす有効な仕事術の例です。
- 整理整頓だけする時間を設定する
- 徹底的にリスト化する
- 持ち物などは前日に準備する
- ゲーム要素を取り入れる
- アプリやツールを利用する
実際に筆者は、仕事をする際、ふせん(ポストイット)に「やることリスト」を書き込み、常にPCに張り付けるという対策をすることで、業務の抜けをなくすようにしています。
ADHDの仕事術をさらに詳しく知りたい人は、下記コラムをご覧ください。
②特性を活かした仕事をする
大人のADHDの特性は大きな困難を伴うこともありますが、逆にとらえれば強みとなる部分も多くあります。
- 発想力に富んでいてアイディアが豊富
- 好奇心旺盛で新しいことにチャレンジできる
- 興味のある分野には没頭することができる
- 決断力があるのでスピーディーに物事を判断できる
- 感覚に優れていて周囲の環境に敏感
上記の特性をうまく活かすことができれば、仕事上で大きく活躍することができるでしょう。(参考:榊原洋一『図解 よくわかる大人のADHD』)
③ADHDの人が活躍できる職業

前述のように強みを活かすことで、大人のADHDでも大きく活躍することが可能です。
特性を活かす仕事の例として、以下の職業が例として挙げられます。
- デザイナー
- アニメーター
- イラストレーター
- 営業職
- ジャーナリスト
- カメラマン
- 起業家
- プログラマー
- エンジニア
- 研究者
それぞれの職業がなぜオススメなのかなど、詳しくは、下記コラムをご覧ください。
なお、ADHDの特性は人それぞれで異なるため、紹介した職業はあくまで例です。
「大人のADHDでも、社会人生活を送れる」という安心材料にしていただいた上で、「実際のあなた」に向いた職業や働き方は、次章のサポート団体などと話をすることで、具体的にわかっていくと思います。
ADHDのある大人が利用できる支援機関8選

自分が大人のADHDと判明したときや大人のADHDかもしれないと思ったときに利用出来る支援機関はたくさんあります。
一人で抱え込まず、相談機関を利用してみてください。
この章では、ADHDのある大人が利用できる支援機関を紹介します。
相談内容によって下記のようなざっくりとした区分が可能です。
支援機関①就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。実際のサービスは、国の基準を満たしたさまざまな民間の就労移行支援事業所が行います。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
就労移行支援事業所は各地にあります。私たち、キズキビジネスカレッジ(KBC)もその一つです。それぞれ特徴が異なるため、気になるところがあれば問い合わせてみてください。
支援機関②発達障害者支援センター

発達障害者支援センターは、発達障害の早期発見と早期支援を目的として、発達障害のある人とその家族などをサポートするための支援機関のことです。(参考:国立障害者リハビリセンター 発達障害情報・支援センター「発達障害支援センターとは」)
保健、医療、福祉、教育、労働など、さまざまな分野の関係機関と連携しながら、地域の支援ネットワークを構築し、多様な相談に応じて、指導や助言を行っています。また、求人に関する情報提供や就業先へのアドバイスなども行っています。
発達障害支援センターは、幼少期に発達障害の診断を受けた人だけでなく、大人になってから発達障害の診断を受けた人も支援の対象です。また、医師から発達障害の診断を受けていない人でも支援を受けることが可能で、発達障害がある可能性がある人からの電話相談なども受け付けています。
運営は都道府県や政令市が主体です。うち約75%は社会福祉法人・特定非営利活動法人などの民間法人が委託を受けて運営しています。(参考:発達障害者支援センター全国連絡協議会「発達障害者支援センターについて」)
各施設には、発達障害者支援センター運営事業実施要綱に基づき、最低3名の専任職員が配置されることになっています。要綱には社会福祉士の配置が規定されていますが、センターによっては臨床心理士、言語聴覚士、精神保健福祉士、医師などの専門家も配置されているところもあります。
2024年8月時点で、全国に約100か所の施設があります。窓口は、各自治体や指定の事業所に設置されています。
支援機関③精神保健福祉センター

精神保健福祉センターとは、精神障害のある人のサポートを目的とした、地域の精神保健福祉の中核を担う支援機関のことです。(参考:東京都福祉保健局「精神保健福祉センターとは」、e-Gov法令検索「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)
精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)に基づき、各都道府県に設置されています。地域によって、こころの健康センターや心と体の相談センターなど、一部名称が異なります。
精神保健福祉センターでは、精神疾患に関連する悩みの相談や社会に適応するための指導と援助を行っています。
精神障害による症状で悩んでいる本人だけでなく、ご家族や周囲の人の相談も受け付けています。また、匿名での相談も受け付けています。医師から正式な診断を受けていなくても相談は可能です。
詳しくは、お住まいの自治体の精神保健福祉センターにお問い合わせください。
支援機関④基幹相談支援センター
「地域の相談支援の拠点」として、障害のある人のための総合的な相談を行ったり、より適切なサポート団体との連携を行ったりします。
お近くのセンターは「お住まいの市区町村名または都道府県名+基幹相談支援センター」などのインターネット検索で見つかると思います。
支援機関⑤地域障害者職業センター

地域障害者職業センターとは、病気や障害のある人に対して、職業評価や職業指導、職業準備訓練、職場適応援助などの専門的な職業リハビリテーションを提供する支援機関のことです。(参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センターによる支援」、厚生労働省「地域障害者職業センターの概要」)
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しており、障害者雇用促進法に基づいて、全国47都道府県に設置されています。(参考:厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律」)
ハローワークや医療・福祉機関と連携しているため、仕事に関する相談や訓練、復職するためのサポートを行っています。
病気や障害に悩む当事者だけでなく、障害のある人を雇用する事業所に対して、雇用管理に関する相談・援助も行っています。
支援機関⑥障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターとは、雇用や保健、福祉、教育に関する関係機関と連携し、障害のある人の雇用の促進・安定を目的とした一体的な支援を行っている支援機関のことです。(参考:厚生労働省「障害者就業・生活支援センター」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」、厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」)
障害のある人の就職活動の支援や求人の紹介、職場定着のためのサポートなどを行います。
就業面だけでなく、金銭管理などの経済面や生活面のことまで、日常および地域生活に関する支援も行っています。
生活習慣や金銭管理、健康管理などについても幅広く相談できるため、生活面のサポートも受けたい人にオススメです。
2024年4月1日時点で、障害者就業・生活支援センターは全国に337箇所設置されています。
支援機関⑦ハローワーク

ハローワーク(公共職業安定所)とは、仕事を探している人や求人を募集したい事業者に対して、就労に関連するさまざまなサービスを無償で提供する、厚生労働省が運営する支援機関のことです。正式名称は公共職業安定所で、職安と呼ぶ人もいます。(参考:厚生労働省「ハローワーク」厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」厚生労働省「公共職業安定所(ハローワーク)の主な取組と実績」、東京労働局「東京ハローワーク」、厚生労働省「こころの健康サポートガイド」、厚生労働省「ハローワークにおける障害者の就労支援」)
主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示などを行っており、具体的な支援内容は事業所によって異なりますが、一般的には以下のような幅広いサポートを行います。
全国に500ヶ所以上あり、主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示、雇用保険や雇用対策など、地域密着型の雇用に関する幅広いサポートを行います。
また、病気や障害のある人に向けたサポートも行っています。障害者手帳を所持していない人でも、医師による診断書があれば、障害の特性や希望職種に応じた職業相談や履歴書や面接での病気・障害の伝え方などのサポートを受けることができます。
支援機関⑧自助会・互助会・ピアサポート
「同じ悩みを抱えている人たち」が互いに支え合い、情報交換などを行う団体の総称です。お悩みを打ち明けたり、対処方法などを共有できたりします。
具体的な実施内容や目的は、会によって様々です。
インターネット検索などで気になるところが見つかったら、問い合わせたり話を聞いてみたりできると思います。
まとめ:より生きやすくなる答えが見つかっていくはず

このコラムを読まれているあなたは、多くの困りごとを抱えているかもしれません。
大人のADHDの特徴は、仕事や生活をする上は大きな困難となることがあります。
実際、私自身も大人のADHDで悩みを抱えた当事者です。
しかし、この記事で紹介したとおり、特性・特徴を理解したり、治療や対策をすることで大人のADHDの人でも楽しく人生を送ったりすることはもちろん可能です。
お一人で悩まずに、ぜひいろいろな人に相談してみてください。
私もADHDと判明した後は自分の道を模索し、一歩一歩前へと進んでいます。
きっとあなた自身にも、より生きやすくなる答えが見つかっていくはずです。
この記事が大人のADHDに悩むあなたの役に立ったなら幸いです。
「大人のADHDかも」と思ったときにできることを知りたいです。
一般論として、次の2つが考えられます。(1)自分のADHD傾向などを確認する、(2)ADHDの検査・診断を受ける。詳細はこちらをご覧ください
大人のADHDの特徴を知りたいです。
一般論として、次のようなものがあります(個人差があります)。(1)集中力が持続せずに気が散りやすくケアレスミスが多い、(2)物を失くす、置き忘れる、(3)段取りが下手で先延ばしにする。他にもありますので、詳細はこちらをご覧ください。
監修志村哲祥
しむら・あきよし。
医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。
臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。
【著書など(一部)】
『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』
他、学術論文多数
日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧
時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
監修角南百合子
すなみ・ゆりこ。
臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→
























