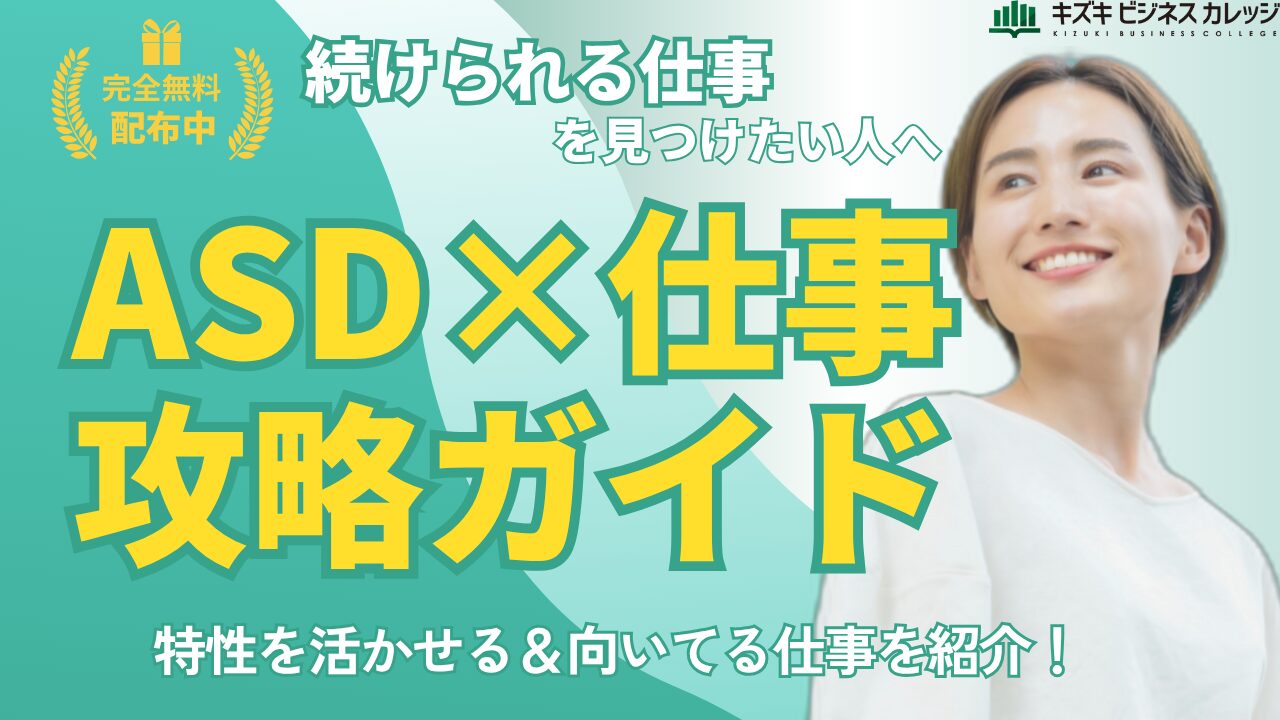発達障害だと仕事が続かない? 理由や長続きする方法を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC) です。
発達障害のあるあなたは、仕事についてさまざまな不安や疑問があり、以下のように悩んでいないでしょうか?
- 仕事が続かないのは発達障害のせい?
- 転職を繰り返しているが、自分に合う仕事が見つからない……
- 発達障害でもできる仕事はある?
このコラムでは、発達障害の概要や障害ごとの特徴に加えて、発達障害のある人が仕事を続かない理由や長続きさせる方法、発達障害の特性を活かせる仕事・適職について解説します。
あわせて、仕事が続かないと悩む人が利用できる支援機関も紹介します。仕事について悩む発達障害のある人の参考になれば幸いです。
さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)は、アルバイト探しに悩む発達障害のある人に向けて、『“働きやすさ”から見つける 発達障害のある人のためのアルバイト探しガイドブック』を公開いたしました。
向いてるアルバイトを見つけるための3つのステップ、ADHD(注意欠如・多動性障害)・ASD(自閉症スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)・LD/SLD(学習障害/限局性学習症)ごとの向いてるアルバイトを具体的に解説しています。
ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。
発達障害のあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
発達障害とは?
この章では、発達障害の3つの種類について解説します。
ASD(自閉スペクトラム症)の特徴

ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害、Autism Spectrum Disorder)とは、人とのコミュニケーションなどに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、e-ヘルスネット「ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について」、CDC「Autism Spectrum Disorder (ASD) 」、厚生労働省「No.1 職域で問題となる大人の自閉症スペクトラム障害」、福西勇夫、福西朱音『マンガでわかるアスペルガー症候群の人とのコミュニケーションガイド』)
かつて使用されていた以下の診断名・分類は、ASDという診断名・分類に統合されています。
- アスペルガー症候群
- 自閉症
- 高機能自閉症
- 広汎性発達障害(PDD)
それぞれ別の発達障害として、診断基準も異なっていましたが、2013年に行われた『DSM-5』の改訂の際に、厳密に区分するのではなく、地続きの=スペクトラムな障害として捉える現在のASDに変更されました。
ただし、変更前の診断名・分類が、法令や病院、日常会話などで現在も使用されることがあります。また、かつてアスペルガー症候群などと診断された人が、現在のASDという名称を認知していないこともあります。
ASDについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
ADHD(注意欠如多動症)の特徴

ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害、Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)とは、不注意性や多動性・衝動性の特性から日常生活などに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、田中康雄・監修『大人のAD/HD』、岩波明『大人のADHD─もっとも身近な発達障害』、司馬理英子『ササッとわかる 「大人のADHD」 基礎知識と対処法』、星野仁彦『それって、大人のADHDかもしれません』、e-ヘルスネット「ADHD(注意欠如・多動症)の診断と治療」)
ADHDの特性は大きく、以下の2つの特性に分けられます。
- 不注意性:忘れ物やケアレスミスが多い、注意散漫、整理整頓・管理が不得意
- 多動性・衝動性:落ち着きがない、気が散りやすい、後先考えず行動する
ADHDのある人だからといってすべての特性が生じるというわけではありません。いずれかの特性、または複数の特性から困難が生じている人もいます。
ADHDのある人は、必ず不注意性や多動性・衝動性が現れるというわけではなく、人によって特性の現れ方、得意なこと・不得意なことが違う点が大きな特徴です。
ADHDについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
LD(学習障害)の特徴

LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害、Learning Disorder/Specific Learning Disorder)とは、読む・書く・計算する・推論するなど、特定の学習行為のみに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』、厚生労働省「学習障害(限局性学習症)」、小池敏英・監修『LDの子の読み書き支援がわかる本』、バーバラ・エシャム・文、マイク&カール・ゴードン・絵、品川裕香・訳『算数の天才なのに計算ができない男の子のはなし 算数障害を知ってますか?』)
LD/SLDは症状別に、以下の3つの種類に分類されます。
- 読字障害(ディスレクシア)
- 書字表出障害(ディスグラフィア)
- 算数障害(ディスカリキュリア)
LD/SLDのある人は、全ての学習行為に困難が生じるというわけではありません。
いずれかの学習行為、または複数の学習行為に困難が生じている人もいます。計算することのみが不得意、読むことと書くことが不得意などのように、人によってさまざまです。
また、いずれの学習行為においても、人によって得意なこと、不得意なことは異なってきます。
例えば、読字障害のある人のなかでも、スムーズな音読が不得意な人もいれば、音読はできてもその内容を理解することが難しいという人もいます。
このように、LD/SLDのある人は、学習する事柄が総合的に不得意というわけではなく、ごく一部の事柄に困難が生じるという点が大きな特徴です。
LD/SLDについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害のある人が仕事が続かない主な理由
この章では、発達障害のある人が仕事が続かない主な理由について解説します。
理由①ASDの特性による理由

ASDのある人は、対人関係やコミュニケーションの難しさや、こだわりの強さなどの特性から、仕事が続かないことがあります。
ASDの特性として、職場での雑談や暗黙の了解、あいまいな指示が苦手です。同じパターンの繰り返し作業には集中できる一方で、突然の変更やイレギュラーな対応には混乱しやすい傾向があります。
また、感覚の過敏さから、職場の音や光などにストレスを感じやすい特性がある人もいます。
そのため、業務の調整や同僚とのやり取りがうまくいかず、仕事を続けるのが難しくなるケースが少なくありません。
理由②ADHDの特性による理由
ADHDのある人は、集中力の維持が難しい・ミスや忘れ物が多い・物事を計画的に進めるのが苦手といった特性から、仕事が続かないことがあります。
また、衝動的な言動が出てしまうときや気が散りやすい環境下では、自分をコントロールできず、仕事のパフォーマンスが安定しにくいという課題もあります。
その結果、職場での評価が下がったり、上司や同僚との信頼関係が築きにくくなったり、「仕事が続かない」と悩む状況につながることが多くあります。
理由③LD/LSDの特性による理由

LD/LSDのある人は、読み書きや計算など、学習面の特定の分野で困難が生じやすい特性があります。
資料作成やメールのやり取り、数字のミスが許されない事務処理などで苦戦しやすく、ストレスや不安を抱えて仕事が続かないことが多くあります。
また、周囲から努力不足と誤解されたり、自分の特性を理解してもらえないことで孤立を感じたりしやすいのも、仕事が続かない理由となります。
仕事が続かないことによる影響
発達障害のある人が仕事が続かない状況が続くと、以下のような影響が出てくる可能性があります。
- 経済的な不安の増大:収入が不安定になり、将来への経済的な見通しが立ちにくくなる
- 社会的信用の低下:職を転々とすることで、社会的な信用を得にくくなる場合がある
- 自信の喪失:仕事がうまくいかない経験が積み重なることで、自己肯定感が低下する
- スキルアップの困難:1つの職場で長く働く機会が少ないため、特定の業務スキルや専門知識を深めることが難しくなる傾向がある
これらの影響は、生活全体の質にも関わります。発達障害のある人は自身の特性を理解し、長く安定して働くための工夫が重要です。
発達障害のある人が仕事を長続きさせる方法
この章では、発達障害のある人が仕事を長続きさせる方法について解説します。
仕事が続かない背景には、周囲とのコミュニケーションの難しさや、業務内容が自分に合っていないことが影響している場合があります。
自分自身の特性を理解し、それに合った対策や工夫を重ねることで、仕事を長く続けられる可能性が高まります。
方法①自己理解を深める

発達障害のある人が仕事を長く続けるためには、自分の特性や得意・不得意を把握することが重要です。
自分がどのような環境や業務が得意なのか、逆にどのような場面でストレスを感じやすいのかを明確にしておくと、適切なサポートを求めやすくなり、仕事が続かないと悩む場面を減らすことにつながります。
自己理解を深める方法としては、自分の得意・不得意を紙に書き出して整理したり、家族や友人など身近な人から意見をもらったりすると良いでしょう。
専門家や支援機関を利用することも効果的です。自己理解を深めることで仕事が続かない原因に気づき、対策を立てやすくなります。
方法②職場でのコミュニケーションを工夫する
発達障害のある人にとって、職場でのコミュニケーションは仕事が続かない一因となることがあります。発達障害の特性ゆえに、相手の意図が読み取りづらかったり、自分の気持ちをうまく伝えられなかったりするためです。
発達障害のある人が自分の考えや困りごとを伝えるのに役立つのが、アサーションです。
アサーションとは、相手を尊重しつつ、自分の意見や感情を率直かつ適切に表現するコミュニケーションスキルのことです。アサーションを意識することで、周囲の期待や要求へ応えようとして、必要以上に努力をする過剰反応を防げます。
また、職場の上司や同僚に自分の特性を共有し、サポートを受けやすくすることも仕事を長続きさせるポイントです。
自分の特性を理解してもらった上で、職場に働きやすい環境を整えてもらうことを合理的配慮と呼びます。
合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と同じように生活し、活動できる均等な機会を確保するために必要な配慮のことを指します。
アサーションや合理的配慮などをとおして、相手に自分の考えや困りごとを理解してもらうことで人間関係のストレスが軽減し、仕事を続けやすくなるでしょう。
発達障害がある人の過剰反応や合理的配慮については、以下のコラムで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
方法③働き方を見直す

自分に合った働き方を選ぶことも、発達障害のある人が仕事を長く続けるために重要です。
例えばフルタイム勤務が負担になりやすい場合は、時短勤務や在宅勤務など柔軟な働き方を検討してみましょう。
また、業務内容や職場環境を自身の特性に合わせて調整することも大切です。現在一般雇用枠で働いている人は、障害者雇用枠で働くことで働きやすくなる可能性があります。
障害者雇用には、以下のようなメリットがあります。
- 業務内容や勤務形態への配慮を受けられる
- 通院や服薬を優先できる
- 支援機関と就職先による支援を受けられる
特に発達障害のある人にとって、職場で必要な配慮や支援を受けられる点は、仕事を続けるための大きなメリットです。
一方で、障害者雇用は一般雇用と比べると就職先の選択肢が少なく、給与水準が低い傾向があるとされています。
職場の担当者や支援機関と相談しながら、自分に合った働き方を模索してみましょう。
障害者雇用については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害の特性を活かせる仕事・適職
この章では、発達障害の特性を活かせる仕事・適職について解説します。
なお、ここで解説する仕事は、あくまで一般的に言われている特性に基づいた内容です。以下の仕事以外にも、同じ傾向や特徴がある仕事であれば、発達障害のある人に向いてる可能性が高いでしょう。
ASDの特性を活かせる仕事

ASDのある人は、パターン化された作業やルールが明確な仕事に集中しやすい傾向があります。そのため、以下のような仕事がASDの特性を活かせるといえるでしょう。
- データ分析
- プログラマー
- 経理職
- 研究職
ASDのある人は、特定の分野において強い集中力を発揮することができるため、自身の得意分野や興味の持てる職場を選ぶことが大切です。
また、対人関係に苦手意識がある場合は、一人黙々と進める作業が主体となる職場で力を発揮しやすいでしょう。
ASDのある人に向いてる仕事については、以下のコラムで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
ADHDの特性を活かせる仕事
ADHDのある人は、不注意優勢タイプか、多動・衝動性優勢タイプかによってその特性が異なります。
不注意優勢タイプの人は、豊かな発想力や独創性が特徴です。そのため、以下のようなクリエイティブな分野の仕事が向いてるといえるでしょう。
- デザイナー
- イラストレーター
一方で、多動・衝動性優勢タイプの人は、じっとしているのが苦手な傾向があります。
また、単調な作業や細かなルールが厳しい場面は苦手な場合もあります。そのため、以下のような仕事が向いてるといえるでしょう。
- 営業職
- 起業家
- フリーランス
不注意性や多動性・衝動性の傾向に限らず、興味のある分野への集中力が高いADHDのある人もいます。
自分の特性を理解し、得意を活かせる仕事を選ぶことが、仕事が続かない悩みを解消する大きな手立てとなります。
ADHDのある人に向いてる仕事については、以下のコラムで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
LD/LSDの特性を活かせる仕事

LD/LSDのある人は、読み書きや計算が苦手といった特性があります。
しかし、その苦手分野はタブレットやスマートフォンなどを活用することで補うことができます。
そのため、音声入力や読み上げ機能、写真や動画など、LD/LSDのある人が困難な部分を補助するツールを活用できる職場であれば、無理なく仕事を続けやすいといえるでしょう。
また、補助ツールが活用できない場合は、自身の特性について理解してもらえる職場環境であるかどうかが重要です。
苦手分野の作業は極力避けてもらう、サポートが受けられる体制を整えてもらうなどの対応ができないか相談してみると良いでしょう。
LD/LSDのある人が仕事でできる対処法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害のある人に向いてない仕事の特徴
発達障害のある人が、一般的に苦手を感じやすいとされている仕事の特徴は、以下のとおりです。
- ルールが曖昧で臨機応変な対応が求められる
- マルチタスクが長時間ある
- 厳しいノルマ管理がある
仕事を長続きさせるために大切なのは、自身の苦手な業務特性を知り、できる限り自分に合った職場環境を選ぶことです。専門家や支援機関などの力を借りながら、自身の適職を確認していきましょう。
仕事が続かないと悩む人が利用できる支援機関
この章では、「仕事が続かない...」と悩む人が利用できる支援機関を紹介します。
それぞれの支援機関の特徴やサポート内容を知ることで、自分に合ったサポートを見つけやすくなります。ぜひ活用してください。
支援機関①発達障害者支援センター

発達障害者支援センターとは、発達障害の早期発見と早期支援を目的として、発達障害のある人とその家族などをサポートするための支援機関のことです。(参考:国立障害者リハビリセンター 発達障害情報・支援センター「発達障害支援センターとは」)
保健や医療、福祉、教育、労働など、さまざまな分野の関係機関と連携しながら、地域の支援ネットワークを構築し、多様な相談に応じて、指導や助言を行っています。また、求人に関する情報提供や就業先へのアドバイスなども行っています。
また、求人に関する情報提供や就業先へのアドバイスなども行っているため、仕事が続かない理由を一緒に整理しながら、あなたに合ったアドバイスや情報提供が受けられます。必要な支援機関につなげる役割も担っているのが発達障害者支援センターです。
発達障害者支援センターについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援機関②地域障害者職業センター

地域障害者職業センターとは、病気や障害のある人に対して、職業評価や職業指導、職業準備訓練、職場適応援助などの専門的な職業リハビリテーションを提供する支援機関のことです。(参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センターによる支援」、厚生労働省「地域障害者職業センターの概要」)
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しており、障害者雇用促進法に基づいて、全国47都道府県に設置されています。(参考:厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律」)
ハローワークや医療・福祉機関と連携しており、仕事が続かない・ミスが多い・人間関係に不安があるといった悩みに対し、適職探しのサポートや訓練を行っています。
また、企業に対しては障害者雇用に関する助言を行い、職場環境の整備や障害のある人が働きやすい環境づくりに協力しています。
地域障害者職業センターについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援機関③障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターとは、雇用や保健、福祉、教育に関する関係機関と連携し、障害のある人の雇用の促進・安定を目的とした一体的な支援を行っている支援機関のことです。(参考:厚生労働省「障害者就業・生活支援センター」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」、厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」)
障害のある人の就職活動の支援や求人の紹介、職場定着のためのサポートなどを行います。
就業面だけでなく、金銭管理などの経済面や生活面のことまで、日常および地域生活に関する支援も行っています。
生活習慣や金銭管理、健康管理などについても幅広く相談できるため、生活面のサポートも受けたい人にオススメです。
また、発達障害のある人の職務適性の見極めも積極的に行っています。
障害者就業・生活支援センターについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援機関④ハローワーク

ハローワーク(公共職業安定所)とは、仕事を探している人や求人を募集したい事業者に対して、就労に関連するさまざまなサービスを無償で提供する、厚生労働省が運営する支援機関のことです。正式名称は公共職業安定所で、職安と呼ぶ人もいます。(参考:厚生労働省「ハローワーク」厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」厚生労働省「公共職業安定所(ハローワーク)の主な取組と実績」、東京労働局「東京ハローワーク」、厚生労働省「こころの健康サポートガイド」、厚生労働省「ハローワークにおける障害者の就労支援」)
主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示などを行っており、具体的な支援内容は事業所によって異なりますが、一般的には以下のような幅広いサポートを行います。
全国に500ヶ所以上あり、主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示、雇用保険や雇用対策など、地域密着型の雇用に関する幅広いサポートを行います。
また、病気や障害のある人に向けたサポートも行っています。障害者手帳を所持していない人でも、医師による診断書があれば、障害の特性や希望職種に応じた職業相談や履歴書や面接での病気・障害の伝え方などのサポートを受けることができます。
求人紹介だけでなく、職業訓練や就労セミナーなども充実しているため、発達障害の特性に合った働き方を探したり、必要なスキルを身につけたりするための第一歩として活用できる機関といえるでしょう。
ハローワークのメリットについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援機関⑤就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。実際のサービスは、国の基準を満たしたさまざまな民間の就労移行支援事業所が行います。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
就労移行支援事業所は各地にあります。私たち、キズキビジネスカレッジ(KBC)もその1つです。それぞれ特徴が異なるため、気になるところがあれば問い合わせてみてください。
就労移行支援事業所については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
【無料配布中!】『“働きやすさ”から見つける アルバイト探しガイドブック』
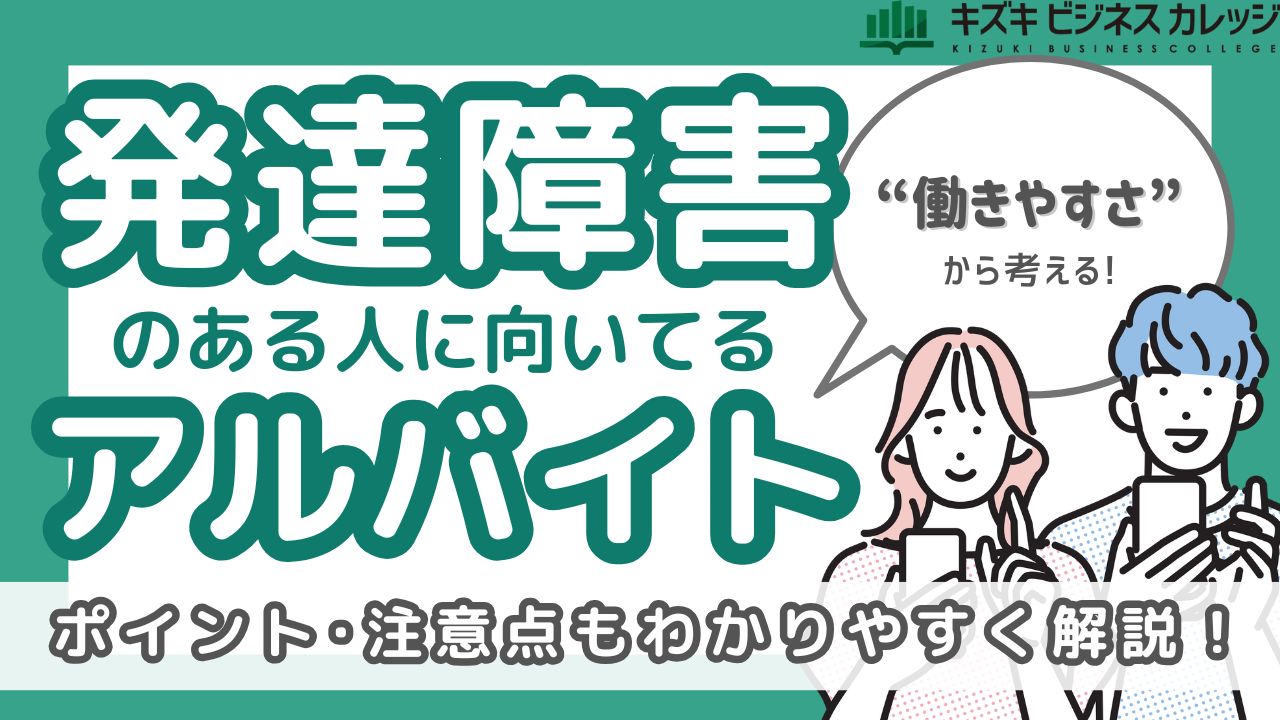
- 自分に合うアルバイトが分からない…
- アルバイトを始めたいけど、自分に合う仕事が見つからない
発達障害のある人の中には、このような悩みを抱える人が少なくありません。
発達障害のある人は、特性によって一般的に簡単とされる仕事でも困難を感じやすい場合があります。
その結果、周囲と比較して自信をなくしたり、アルバイト探し自体が苦痛になったりすることもあります。
本資料では、発達障害のある人が向いてるアルバイトを見つけづらい理由や、向いてるアルバイトを見つけるためのステップ、向いてるアルバイトの具体例などを解説しています。
ぜひ本資料を活用して、あなたに合うアルバイトを見つけませんか?
- 発達障害のある人が向いてるアルバイトを見つけづらい理由
- 自分に合うアルバイトを見つけるための3ステップ
- 【ADHD・ASD・LD/SLD別】向いてるアルバイトの傾向と具体例
- 向いてない可能性のあるアルバイトの特徴
- 発達障害の診断を受けており、自分に合うアルバイトが分からない人
- アルバイトがうまくいかず、自信をなくしている人
- これから働き始めたいが、どのように探せばよいか悩んでいる人
- 無理なく続けられる仕事の条件を整理したい人
資料の入手方法
本資料は、以下のリンクから無料でダウンロードいただけます。
- リンクから申し込みフォームにアクセス
- 簡単なフォームに入力
- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り
- URLから資料を取得!
- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。
- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。
- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。
まとめ:周囲のサポートを得ながら自己理解を深めよう!

発達障害のある人が仕事を続けるためには、自身の特性を理解することが何より大切です。
そして、その自己理解は一人で抱え込むものではありません。職場の上司や同僚、支援機関など、周囲のサポートを積極的に活用しましょう。
自身の得意不得意を理解し周囲に伝えることは、働きやすい職場を築き、仕事を長く続ける自信にもつながります。
このコラムが、発達障害で仕事が続かないと悩んでいるあなたの一助となれれば幸いです。
発達障害のある人が仕事が続かない影響について教えてください。
発達障害のある人が仕事が続かない状況が続くと、以下のような影響が出てくる可能性があります。
- 経済的な不安の増大
- 社会的信用の低下
- 自信の喪失
- スキルアップの困難
詳細については、こちらで解説しています。
発達障害のある人が仕事を長く続けられるようにする方法が知りたいです。
①自己理解を深める②職場でのコミュニケーションを工夫する③働き方を見直す
詳細については、こちらで解説しています。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→