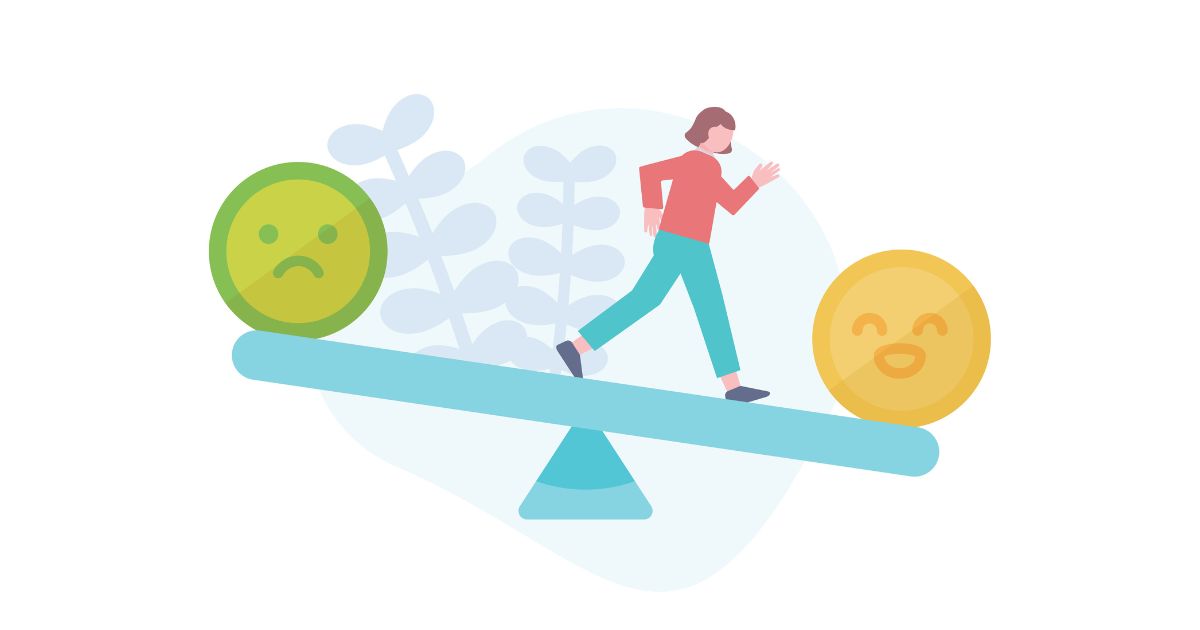双極性障害のある人が就職活動を成功させるコツ 体験談を紹介

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
双極性障害のあるあなたは、以下のようにお悩みではありませんか?
- 双極性障害の支障が仕事で出ている
- 双極性障害とのつき合い方がわからず、就職活動に向けた具体的な行動も取れない
- 就職活動・転職活動を成功させたいけれど、どうしたらよいのかわからない
双極性障害があっても、向いてる仕事や働き方に向けて就職/転職することはもちろん可能です。
このコラムでは、キズキビジネスカレッジ(KBC)の知見に基づき、双極性障害のある人が就職活動を成功させるコツについて解説します。あわせて、就職活動を成功させた体験談や就職活動で利用できる支援機関、経済的支援制度を紹介します。
大前提として、就職活動に関係してもしなくても、双極性障害の人にとって大切な大前提は、医療機関とのつながりを適切に保つことです。自己判断で通院や服薬をやめたりせず、治療を継続しましょう。
双極性障害で就職活動にお悩みでしたら、ぜひご一読ください。
本コラムの主な想定読者は、在職中で、転職としての就職活動を始めようとする人ですが、新卒の人、退職済みの人、すでに就職・転職活動を進めている人の参考にもなると思います。双極性障害と就職活動にお悩みがあるなら、どなたもぜひご覧ください。(参考;野村総一郎『新版 双極性障害のことがよくわかる本』、加藤忠史『これだけは知っておきたい双極性障害 躁・うつに早めに気づき再発を防ぐ! 第2版 ココロの健康シリーズ』、南中さくら『みんなの双極症 日常の悩みから最新知識まで』
さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、「気分の波に振り回されて思うように働けない」と悩む双極性障害のある人に向けて、利用できる可能性がある支援制度の1つである『障害者手帳 活用ガイドブック』を公開いたしました。
障害者手帳の概要やメリット、申請の流れ、障害者手帳以外に利用できる可能性がある支援をわかりやすくまとめています。
ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。
就職を成功させたい双極性障害のあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
就職活動・転職活動の一般的な流れ

最初に、双極性障害かどうかに関わらず、就職活動(転職活動)の一般的な流れを紹介します。各段階でやるべきことなどを検討しましょう。
- 転職活動の準備(転職エージェントへの登録、情報・条件の整理(経歴・スキル・資格・向き不向き・希望条件・やりたいこと・やりたくないことなど))
- 興味のある求人のチェック
- 応募書類の作成
- 応募
- 面接
- 内定
- 内定受託・現職の退職や引き継ぎの手続き
- 新しい職場での勤務開始
就職活動には、数か月を要することもあります。長期にわたる活動であり、現職や治療と同時に一人で進めようとすると、心身ともに疲れる可能性が高いです。
そのため、双極性障害の人の就職・転職をサポートするサービスやエージェントを利用して、効率的に進めるのがオススメです。
そうしたサポート団体では、スキル獲得、社会人としてのマナーの勉強、書類作成や面接対策のサポートなどのためにも利用できますし、病気や自己への理解も深めることができます(サポート団体の例は後で紹介します)。
双極性障害のある人が就職活動を成功させる7つのコツ

この章では、双極性障害のある人が就職活動を成功させるコツについて解説します。
各事項を検討することで、双極性障害との付き合い方がわかったり、自分の適性に合った仕事・働き方に出会いやすくなったりすると思います。
前提:いまが就職活動をするタイミングか、立ち止まって考えてみる

双極性障害の人の就職活動については、まず、「双極性障害があっても、病気を受け止めて、適切な予防や措置を取れば、いまの仕事を続けることもできる」ということをお伝えします。
大前提として大切なことは、病院との繋がりを保ち、治療を続けることです。後で紹介するサポート団体なども、適切に利用しましょう。
その上で、「いま」が就職活動をするタイミングかどうかを、よく検討しましょう。
双極性障害の「躁」「軽躁」の状態で仕事を変える人は多いようです。しかし、この状態のときに仕事を変えるのは大きなリスクとなりえます。
理由として、「自分ならどこでもやっていける!」と、普段とは違うハイテンションで就職活動を成功させても、躁(軽躁)状態からうつ状態になったときに後悔をすることがあるからです。
しっかり通院しながら、病状を落ち着かせることから始めることを推奨します。
そして、心が安定したとき(寛解期)に、「いまの職場で続けていくか」「やはり就職活動を始めて、次の仕事をやってみるか」と考えても遅くはありません。
そうしたことは、あなた一人で考える必要はありません。後で紹介するように、現在は、双極性障害のような精神疾患を本人自身が受け止めるために、多くの相談先があります(無料で利用できるところもあります)。
ぜひ、悩みや希望を、そうした人たちと話してみてください。
コツ①双極性障害に関連する、仕事上での悩みを知る
双極性障害のある人には、仕事を続ける中で起こしやすい悩みがあります。
それを知り、予防できると、就職活動も、就職後の業務や人間関係も、円滑に進めやすくなります。
- 自信満々な精神状態で仕事を意欲的にこなせるが、相手に感情的で強く当たりすぎる
- エネルギーが無限にあふれる感覚を覚えて、じっとすることができない
- 体調が過度に悪くなって、欠勤を続けることが何度もある
以上は例ですので、個人によってトラブルの内容は他にもさまざまあるでしょう。
職場で不安定な状態が慢性化すると、(就職活動が成功した新しい職場でも)休職や退職のきっかけにつながります。
予防策としては、以下のようなものがあります。
- 自分の状態を観察してみる
- 相談できる相手(家族、医師、信頼している人など)と話してみる
医療機関やサポート団体を通じて、自分を客観視できるような取り組みを行ってみましょう。
コツ②障害者枠を知る
障害者枠とは、特定の病気や障害がある人に向けた雇用枠のことです。双極性障害の人も利用できます。厚生労働省が中心となって推進している制度です。
障害者枠の目的は、誰もが能力・適性に応じて雇用される機会を創出して、地域で自立した生活を送れる社会を実現するところにあります。
障害者枠では、病気や障害の特性などと関連して、その人の能力と特性に応じて働けるような配慮が行われます。
次項とも関連して、障害者枠のことを知っておくと、就職活動(応募先・働き方)の選択肢が増えます。障害者枠が多い、「特例子会社」という形態の会社もあります。
障害者枠の詳細な情報は、以下のコラムをご覧ください。
コツ③クローズ就労、オープン就労障害者枠の3つを比べてみる

前項の障害者枠に対して、「障害者枠ではない雇用や求人枠」のことは、俗に「一般枠」と言います。そして、一般枠で就職活動する場合は、以下の選択肢があります。
- (1)オープン就労(病気や障害を開示して応募・勤務すること)
- (2)クローズ就労(病気や障害を開示せずに応募・勤務すること)
前述の障害者枠は、必ずオープン就労になります(一般的に、障害者枠の利用のためには、障害者手帳の取得と開示が必要なためです)。
これら3つの雇用枠を、就職活動の判断基準となりそうな項目ごとにまとめると、以下のように考えられます。もちろん、職場によって異なる部分もありますが、就職活動の参考としてご覧ください。
- 一般枠(クローズ就労):幅広い業界・職種・雇用形態がある
- 一般枠(オープン就労):上に同じ
- 障害者枠(オープン就労):一般枠よりも少ない傾向にある
- 一般枠(クローズ就労):障害者枠と比べると、給料や出世の観点で待遇がよい傾向にある
- 一般枠(オープン就労):上に同じ
- 障害者枠(オープン就労):一般枠と比べると、給料や出世の観点で待遇がよくない傾向にある
- 一般枠(クローズ就労):なし。自分で、通院、休憩、業務の負担軽減をコントロールする
- 一般枠(オープン就労):職場が可能な範囲で対応(合理的配慮)。現実的には配慮されないこともある
- 障害者枠(オープン就労):必要な配慮が得られる可能性が高い
- 一般枠(クローズ就労):一般枠で働く他の同僚と同じ
- 一般枠(オープン就労):上に同じ
- 障害者枠(オープン就労):休日や労働時間を調節しやすい
- 一般枠(クローズ就労):病気・障害を理由とした採用の敬遠がない
- 一般枠(オープン就労):現実的には、病気・障害への偏見や違法な独自ルールによって、採用を敬遠されることがある
- 障害者枠(オープン就労):病気・障害そのものを原因に採用が敬遠されることはない。ただし、「実際の症状・特性」「伝え方」「病気・障害以外の原因」によっては、採用されないことはもちろんある
- 一般枠(クローズ就労):病気を開示できないことで、心に負担が生じる場合もある
- 一般枠(オープン就労):病気を開示することで、心に負担が生じる場合もある
- 障害者枠(オープン就労):上に同じ
※特にこちらは、「実際のあなた」や「実際の職場」によって、双極性障害を開示する・しないのどちらが気が楽なのかは分かれるところです。
オープン就労・クローズ就労については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
コツ④専門機関に相談してみる

双極性障害の人は、病気・障害のある人のための専門機関・サポート団体を利用しながら就職活動をすることをオススメします。そうすることで、ご自身の症状、特性、長所や短所への理解を深めながら、就職活動の相談ができるからです。
具体的には、以下のようなサポートを受けられます。
- ビジネススキルの学習・練習
- ビジネスマナーの学習・練習
- 自己分析・障害理解の相談
- 履歴書・エントリーシート・職務経歴書の添削
- 面接練習など
コツ⑤就職先の障害への配慮を調べておく
自分が希望する就職先の、合理的配慮の実践状況を調べましょう。
- 事業主は、(略)募集・採用に当たり障害者からの申出により障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。また、(略)障害の特性に配慮した、施設整備、援助者の配置などの必要な措置を講じなければなりません。(略)(障害者雇用促進法第36条の2~36条の4)(参考:厚生労働省「事業主の方へ」)
合理的配慮の実践状況を知ることで、就職・転職後のミスマッチを予防できます。ただし、あなた一人で調べるのは難しいと思います。こちらもサポート団体に相談することをオススメします。
コツ⑥障害者枠の面接では、支援スタッフなどの同行を検討する

障害者枠での面接では、サポーターの同行が可能な場合もあります。
ここでいうサポーターとは、専門機関やサポート団体の支援スタッフを指します。
同行時には、ご自身に必要な合理的配慮などを、支援スタッフから客観的に面接担当者に伝えることもできます。これで、ミスマッチの発生を防ぎやすくなります。
ただし、サポーターが面接に同行できるかどうかは、応募先によって異なります。事前に問い合わせるなどして、確認するようにしておきましょう。
コツ⑦職場定着支援を利用する
「職場定着支援」とは、就職後のサポートのことです。就労移行支援の事業所などで実施されています。
職場定着支援では、実際の就職後の状況・困りごとなどを相談できます(オープン就労の場合は、就職先を交えて話し合うことも可能です)。
就職後は、新しい環境での風土や規則、人間関係になれるまでにそれなりの負担がかかります。職場定着支援を利用することで、新しい環境に馴染みやすくなり、負担も軽くなるはずです。
職場定着支援については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
双極性障害のある人に向いている仕事・働き方

双極性障害の人には、一般的には、体調の浮き沈みが起きにくい仕事・働き方が向いています。
例えば、以下のような特徴のある仕事・働き方です。
- 年間を通して、業務量が安定している
- 勤務時間の変動が少ない
- 自分のペースで仕事を進めることができる
- ストレスとなる対人折衝が少ない
具体的な職種や働き方の例には、以下のようなものがあります。
- 事務職
- フリーライター
- 在宅ワーク
その上で、双極性障害であることを受容して、適切に付き合うことができれば、仕事や働き方の選択肢は広がっていく可能性もあります。
双極性障害のある人に向いてない仕事・働き方

一方で、双極性障害の人にはあまり推奨されていない仕事・働き方もあります。
それは、勤務時間が変動しやすい仕事や職種です。理由は、生活リズムが不規則になるからです。
不規則な生活リズムは、症状の再発リスクを高めたり、不安定なメンタルにつながったりと、私生活にも支障がでる恐れがあります。
避けたい働き方は、以下のようなものです。
- 業務内容の大部分が対人関係を占めている
- 勤務時間が不規則になりがちになる仕事
具体的な職種や働き方の例には、以下のようなものがあります。
- 営業職
- 接客業
- 看護師
- シフト制の勤務(深夜勤務がある仕事)
双極性障害のある人が就職活動を成功させた体験談5選
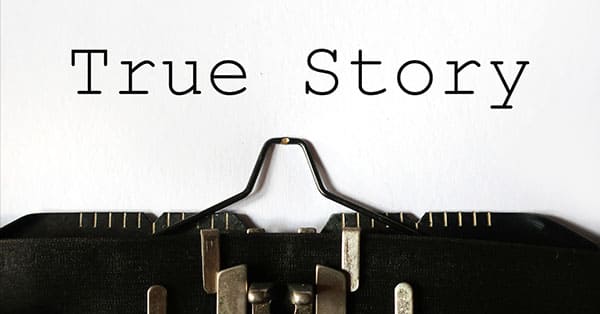
この章では、双極性障害当事者の人の就職活動の成功例を、ご本人が語る形で紹介します。発症当時から現在の仕事に至るまでの経緯をお聞きしました。
※個人の特定に繋がらないよう、一部事実を変更しています。
体験談①仕事のことしか考えられない日々で、双極性障害の診断を受ける
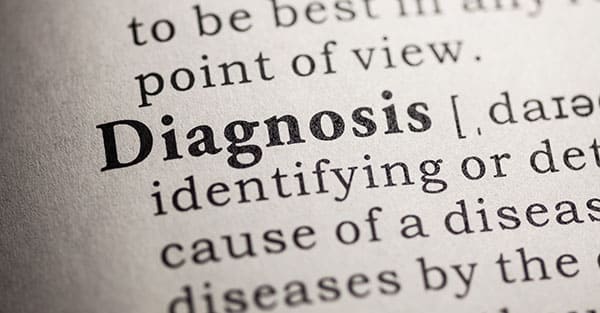
以前の職場で、私は周りから「真面目で仕事熱心ですね」とよく言われていました。
実際にそのとおりで、私は仕事が大好きでした。
一方で、仕事に没頭するあまり、休日も仕事のことで頭がいっぱいでした。
そのうち、仕事のことしか考えられない日々が3~4年続いて体調不良となり、休職を余儀なくされました。
最終的に、「双極性障害」という診断を受け、離職しました。
体験談②信頼できる医師と治療を続け、気力がよみがえる
療養のために実家で母と2人暮らしをしながら、働けない自分にふがいなさを感じる日々でした。
しかし、信頼できる医師とのコミュニケーションを続けて自分に合った薬が見つかったことで、体調がよくなってきました。
そして、定期的に運動も始めて、体力も少しずつ取り戻すことができました。
この頃から、少しずつ仕事をする気力がよみがえってきました。
体験談③就労継続支援で経験を積み、自身も持てるように

そこから私は、地域の相談支援施設に通って、就労継続支援B型(※)で2年間働きました。
就労継続支援B型は、「自分の体調に合わせて、仕事をする日を選べる」のがメリットでした。
ここで、継続して働くという経験を踏めたことに私は自信が持てるようになり、就労継続支援A型(※)の事業所に転職しました。
A型では、「雇用契約を結び、給料を稼ぐ」ことができました。
ここで2年間勤めたことで、「次はこんな働き方をしたい」と、自分が望むキャリアを考えられるようになってきました。
この4年間は、非常に有意義な時間だったと思っています。
- 就労継続支援とは、病気や障害に関連して、就労支援を利用しても雇用につながらなかった人や、一般企業での勤務が困難な人などに、軽作業や生産活動の機会を提供する福祉サービスです。詳細を知りたい場合は、以下のリンクをご覧ください。
体験談④一般企業への就職活動を開始。さまざまなサポート団体を利用して、障害者枠で就職
そして私は一般企業への就職活動を決意し、行動に移しました。
まず、無料で利用できる「ハローワーク」「障害者職業センター」「障害者就業・支援センター」で求人を探しました。
また、「障害者就業・生活支援センター」に行って、相談したりもしました。(※これらの施設は、次章で紹介します。)
就労継続支援A型でお世話になっていたスタッフさんにも相談をしました。
就職活動をする上で、私が一番強く指摘されたのは「病気を再発させないように、仕事とプライベートを切り分けて考える」ということでした。
面接では、そのスタッフさんに同行してもらい、希望する就職先と私の間でミスマッチが生まれないように、客観的に合理的配慮を伝えてもらいました。
結果として私は、小売業の仕事に障害者枠で転職することができました。
転職してから今年で6年目になり、現在も充実して働いています。
体験談⑤一人で悩み込まないで

これが私の発病から現在までの経緯です。
最後に、私と同じ双極性障害で悩んでいる人に伝えたいことがあります。
それは、「一人で悩みこまないで」ということです。
双極性障害に限らず、人には言いにくい症状や特性を持っている人は、とにかく「誰に相談していいのかわからない」という状況は避けるべきだと思います。
あせらずに、適切な医療機関、サポート団体を見つけるところから、就職活動を始めることをお勧めします。
双極性障害のある人が就職活動で利用できる支援機関6選

双極性障害などで仕事に支障がある方に向けて、さまざまな支援先やサポート団体が存在します。
自分の症状の度合いに合わせて、適切な相談先を確保するだけでも安心することができると思います。
この章では、具体的な相談機関や支援先を紹介します。
支援機関①就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。実際のサービスは、国の基準を満たしたさまざまな民間の就労移行支援事業所が行います。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
就労移行支援事業所は各地にあります。私たち、キズキビジネスカレッジ(KBC)もその一つです。それぞれ特徴が異なるため、気になるところがあれば問い合わせてみてください。
就労移行支援事業所については、下記コラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援機関②ハローワーク(公共職業安定所)

ハローワーク(公共職業安定所)とは、仕事を探している人や求人を募集したい事業者に対して、就労に関連するさまざまなサービスを無償で提供する、厚生労働省が運営する支援機関のことです。正式名称は公共職業安定所で、職安と呼ぶ人もいます。(参考:厚生労働省「ハローワーク」厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」厚生労働省「公共職業安定所(ハローワーク)の主な取組と実績」、東京労働局「東京ハローワーク」、厚生労働省「こころの健康サポートガイド」、厚生労働省「ハローワークにおける障害者の就労支援」)
主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示などを行っており、具体的な支援内容は事業所によって異なりますが、一般的には以下のような幅広いサポートを行います。
全国に500ヶ所以上あり、主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示、雇用保険や雇用対策など、地域密着型の雇用に関する幅広いサポートを行います。
また、病気や障害のある人に向けたサポートも行っています。障害者手帳を所持していない人でも、医師による診断書があれば、障害の特性や希望職種に応じた職業相談や履歴書や面接での病気・障害の伝え方などのサポートを受けることができます。
支援機関③地域障害者職業センター

地域障害者職業センターとは、病気や障害のある人に対して、職業評価や職業指導、職業準備訓練、職場適応援助などの専門的な職業リハビリテーションを提供する支援機関のことです。(参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センターによる支援」、厚生労働省「地域障害者職業センターの概要」)
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しており、障害者雇用促進法に基づいて、全国47都道府県に設置されています。(参考:厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律」)
ハローワークや医療・福祉機関と連携しているため、仕事に関する相談や訓練、復職するためのサポートを行っています。
病気や障害に悩む当事者だけでなく、障害のある人を雇用する事業所に対して、雇用管理に関する相談・援助も行っています。
支援機関④障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターとは、雇用や保健、福祉、教育に関する関係機関と連携し、障害のある人の雇用の促進・安定を目的とした一体的な支援を行っている支援機関のことです。(参考:厚生労働省「障害者就業・生活支援センター」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」、厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」)
障害のある人の就職活動の支援や求人の紹介、職場定着のためのサポートなどを行います。
就業面だけでなく、金銭管理などの経済面や生活面のことまで、日常および地域生活に関する支援も行っています。
生活習慣や金銭管理、健康管理などについても幅広く相談できるため、生活面のサポートも受けたい人にオススメです。
2024年4月1日時点で、障害者就業・生活支援センターは全国に337箇所設置されています。
支援機関⑤精神保健福祉センター

精神保健福祉センターとは、精神障害のある人のサポートを目的とした、地域の精神保健福祉の中核を担う支援機関のことです。(参考:東京都福祉保健局「精神保健福祉センターとは」、e-Gov法令検索「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)
精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)に基づき、各都道府県に設置されています。地域によって、こころの健康センターや心と体の相談センターなど、一部名称が異なります。
精神保健福祉センターでは、精神疾患に関連する悩みの相談や社会に適応するための指導と援助を行っています。
精神障害による症状で悩んでいる本人だけでなく、ご家族や周囲の人の相談も受け付けています。また、匿名での相談も受け付けています。医師から正式な診断を受けていなくても相談は可能です。
詳しくは、お住まいの自治体の精神保健福祉センターにお問い合わせください。
支援機関⑥就職・転職エージェント

民間の就職・転職サービスもたくさんあります。
特に、エージェント(担当サポーター)を利用すると、しっかりと相談をしながら就職活動を進めることができます。
いずれも、基本的なサービスとして、「就職準備のサポート」「キャリア相談」「求人紹介」「求人元と就職希望者の条件の調整」などを行っています。
情報収集としても便利なサービスですが、運営会社によって、求人の数や種類、サポート内容などが異なります。
負担にならない範囲で複数に登録したり話を聞いたりして、自分に合いそうなところを利用してみるとよいと思います。
一般のエージェントの代表例には、以下のようなところがあります。
双極性障害の人が利用できる経済的支援制度4選

双極性障害の人は金銭的・経済的サポートを利用できることがあります。
お金があれば、心のゆとりもできていきます。
ご自身の状況に合った経済支援を探すことで、安定した経済状況で療養や就職活動に専念できると思います。
金銭的なサポートは他にも利用できる可能性があります。
お住まいの市区町村役所や、前述のサポート団体に相談しましょう。
支援制度①自立支援医療制度

自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療に関する医療費の自己負担額を軽減する公費負担の支援制度のことです。LD/SLD(学習障害/限局性学習症)もその支援の対象です。(参考:厚生労働省「自立支援医療について」、厚生労働省「自立支援医療制度の概要」、東京都福祉保健局「自立支援医療(更生医療)」)
通常、医療保険による医療費の自己負担額は3割です。自立支援医療制度を利用すれば、原則1割まで軽減することができます。この制度は、指定の医療機関・薬局のみで利用可能です。
さらに、自己負担額には上限が設定されています。1割負担であっても、月額の上限以上となる金額は、原則として負担を免除されます。ただし、世帯の総所得額によっては、自己負担額が変動したり、対象外になったりする場合があります。
また、費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない場合や所得の程度に応じて、さらに軽減措置が行われます。
自立支援医療は、下記の3種類に分けられます。
- 精神通院医療:精神疾患の治療など
- 更生医療:身体障害に関わる治療など
- 育成医療:身体障害がある子どもに関わる治療など
特定の精神疾患がある人以外に、身体障害者手帳を持つ人なども対象です。
具体的な支援内容や条件、名称は、自治体によって異なります。
気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。
支援制度②傷病手当金
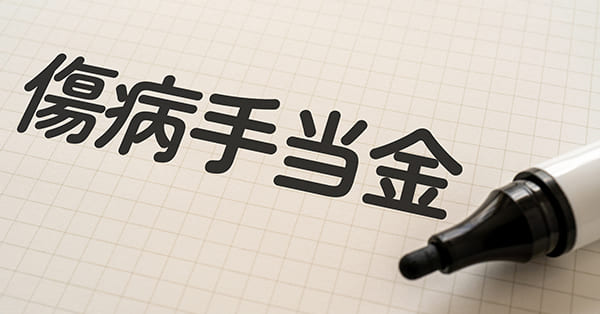
傷病手当金とは、病気やケガ、障害のために仕事を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に、健康保険(社会保険)の加入者・被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた支援制度のことです。(参考:全国健康保険協会「傷病手当金」、全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」、全国健康保険協会「傷病手当金について」)
国民健康保険の加入者・被保険者は対象外です。
対象となる病気やケガ、障害は、業務外の理由で生じた場合に限ります。会社の業務が原因で生じた病気やケガ、障害は、労災保険により補償されます。
傷病手当金の受給対象は、病気やケガ、障害によって就労不能であり、十分な報酬を受けられない人です。そのため、医師の診断書が必要です。
また傷病手当金は、退職前・在職中に就労できない状態の場合に受給できます。ただし、一定の条件を満たせば、退職後も継続して受給できます。具体的な受給金額や受給期間は、その人の休職の状況などによって異なります。
申請は、加入している全国健康保険協会や各健康保険組合、各共済組合で行えます。気になる人は、加入している健康保険の協会・組合にご相談ください。
支援制度③障害年金

障害年金とは、病気やケガ、障害などによって仕事や生活などに支障を生じている場合に、年金加入者が受給できる支援制度のことです。(参考:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」、日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」、日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」、日本年金機構「国民年金」、日本年金機構「障害年金ガイド令和5年度版」、日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」)
事故で足を失った場合や生まれつき四肢が不自由な場合、知的障害がある場合などのケースだけでなく、発達障害・精神疾患、あるいは癌や生活習慣病などで生活に困難を生じている場合も受給の対象になります。
一般的な年金は高齢者にならなければ受け取れませんが、障害年金は現役世代でも受給できることが特徴です。
申請は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口・年金事務所・年金相談センターなどで行えます。
障害年金については、下記コラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援制度④障害者手帳
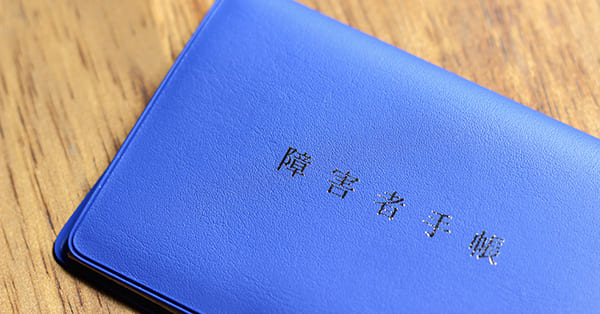
障害者手帳とは、一定以上の障害のある人に交付される手帳のことです。
障害者手帳を所持することで、障害があることの証明が可能です。障害者手帳を所持する人は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の対象として、さまざまな支援を受けられます。(参考:厚生労働省「障害者手帳について」、e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
種類は、以下のとおりです。
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
気になる人は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。
障害者手帳については、下記コラムで解説しています。ぜひご覧ください。
双極性障害とは?
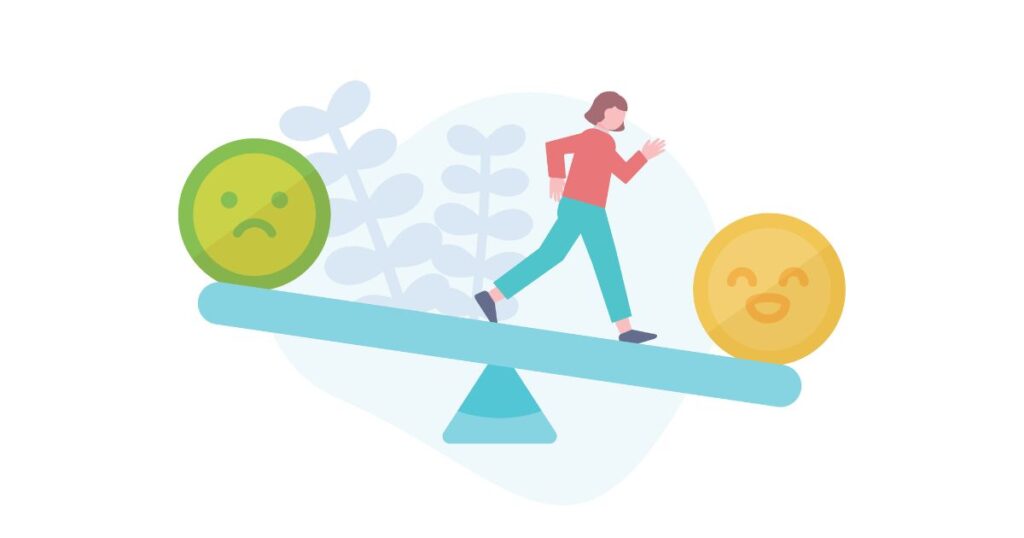
双極性障害とは、気分が高揚する躁状態と、気分が落ち込むうつ状態を繰り返す精神障害の一種のことです。かつては、躁うつ病という名前で知られていました。(参考:こころの情報サイト「双極性障害(躁うつ病)」、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の精神疾患の診断・統計マニュアル』、加藤忠史『これだけは知っておきたい双極性障害 躁・うつに早めに気づき再発を防ぐ! ココロの健康シリーズ』、MedlinePlus「Bipolar Disorder」、MSDマニュアル家庭版「双極性障害」、国立国際医療研究センター病院「双極性障害とは?」、大塚製薬「双極性障害とは」)
双極性障害の躁状態は、過度の身体活動やその状況にふさわしくない程度の高揚感を特徴としています。
双極性障害の発生率に性差の影響はありません。また、通常、10代から30代までに発症するとされており、小児が双極性障害を発症することは少ないそうです。
双極性障害には、大きく分けて以下の種類にわかれます。
- 双極性障害Ⅰ型(双極Ⅰ型障害)
- 双極性障害Ⅱ型(双極Ⅱ型障害)
主な違いは、躁状態の激しさと社会生活への影響です。
双極性障害については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
【無料配布中!】双極性障害×障害者手帳『活用ガイドブック』
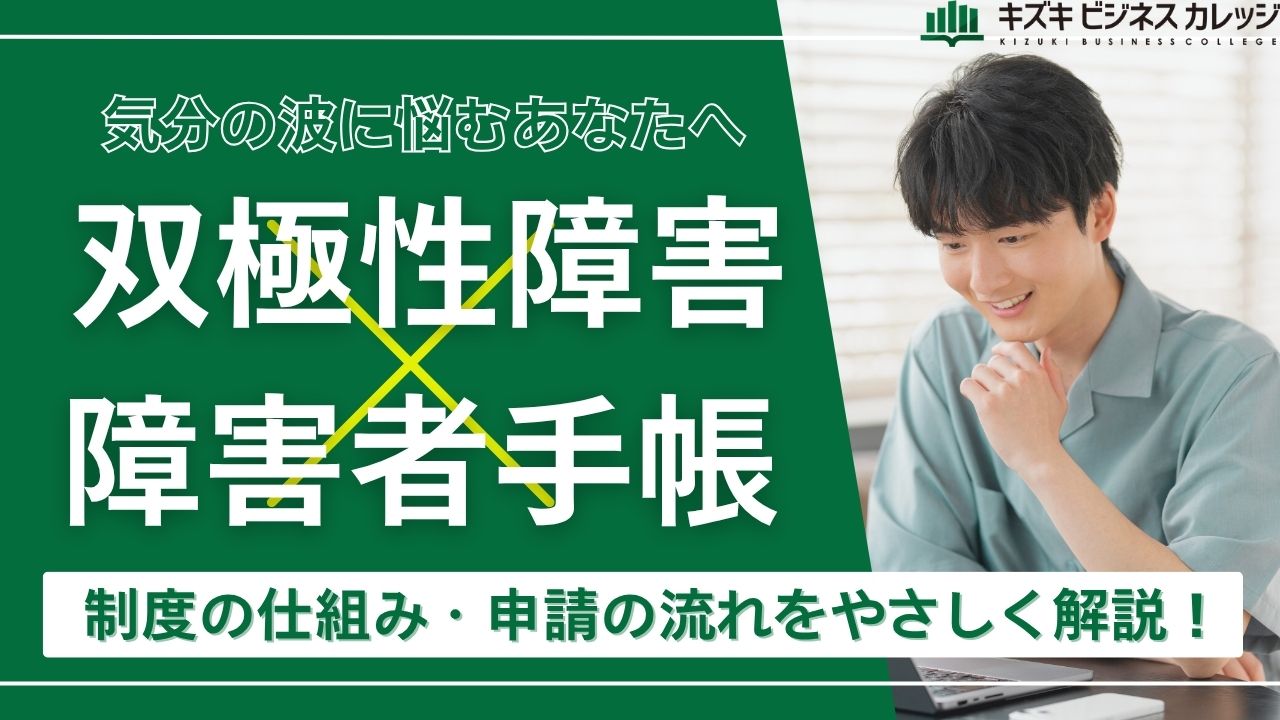
双極性障害のある人は、以下のような悩みや不安を抱えていることが少なくありません。
- 気分の波に振り回されて思うように働けない
- 将来が不安だけど、何から始めれば良いか分からない
双極性障害は本人の意思だけではコントロールしづらいため、まずは安心して次の一歩を考えられる環境が大切です。そして、活用できる支援制度の1つが障害者手帳です。
本資料では、双極性障害のある人に向けて、障害者手帳の概要から取得するメリット、具体的な申請方法までを、わかりやすく解説しています。
本資料を活用して、生活や働くことへの不安を解消しませんか?
- 双極性障害とは?
- 障害者手帳とは?
- 双極性障害のある人が障害者手帳を取得するメリット
- 障害者手帳を申請する流れ・準備
- 障害者手帳以外に利用できる支援制度・支援機関
- 双極性障害と障害者手帳に関するよくある質問
- 障害者手帳がどのような制度なのか全体像を整理したい人
- 自分が障害者手帳の対象か分からず、困っている人
- 医療費・税制優遇・割引などのメリットを把握したい人
- 障害者手帳の申請に必要な書類やステップを知りたい人
- 就労支援や障害者雇用など活用を検討したい人
- 障害者手帳以外の制度についても知りたい人
資料の入手方法
本資料は、以下のリンクから無料でダウンロードいただけます。
- リンクから申し込みフォームにアクセス
- 簡単なフォームに入力
- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り
- URLから資料を取得!
- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。
- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。
- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。
まとめ:積極的に支援機関を利用しましょう

双極性障害があっても、就職・転職を成功させることはもちろん可能です。
そのためにも、医師とのつながりを保ち、積極的に支援機関を利用しましょう。
このコラムがお役に立ったなら幸いです。
双極性障害のある自分が就職活動(転職活動)を成功させる方法を知りたいです。
一般論として、以下のようなことを検討すると、就職活動は成功に近づきます。
- 前提:「いま」が就職活動をするタイミングか、立ち止まって考えてみる
- 双極性障害に関連する、仕事上での悩みを知る
- 「障害者枠」を知る
- 「一般枠(クローズ就労)」「一般枠(オープン就労)」「障害者枠」の3つを比べてみる
- 専門機関に相談してみる
- 就職先の障害への配慮を調べておく
- 障害者枠の面接では、支援スタッフなどの同行も可能だと知る
- 「職場定着支援」を利用する(就労移行支援などを利用して就職した場合)
詳細はこちらをご覧ください。
双極性障害のある自分に向いてる働き方を知りたいです。
一般論として、以下のような働き方が向いています。
- 年間を通して、業務量が安定している
- 勤務時間の変動が少ない
- 自分のペースで仕事を進めることができる
- ストレスとなる対人折衝が少ない
詳細はこちらをご覧ください。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→