発達障害が劣等感に悩まされやすい理由 対処法を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
発達障害は脳の特性によるものですが、特性に対する無理解や環境とのミスマッチから、本人が劣等感を抱くケースも見られます。
発達障害のある人が抱きやすい劣等感には、いくつかの背景があります。適切な理解と工夫によって、その苦しさは和らげられるかもしれません。
このコラムでは、発達障害の概要や発達障害のある人が劣等感に悩まされる理由、発達障害のある人が劣等感を克服するための具体的な方法について解説します。
発達障害のある人や関わりの深い方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)は、アルバイト探しに悩む発達障害のある人に向けて、『“働きやすさ”から見つける 発達障害のある人のためのアルバイト探しガイドブック』を公開いたしました。
向いてるアルバイトを見つけるための3つのステップ、ADHD(注意欠如・多動性障害)・ASD(自閉症スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)・LD/SLD(学習障害/限局性学習症)ごとの向いてるアルバイトを具体的に解説しています。
ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。
発達障害による劣等感を抱えているあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
発達障害とは?
この章では、発達障害の種類について解説します。
ASD(自閉スペクトラム症)の特徴

ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害、Autism Spectrum Disorder)とは、人とのコミュニケーションなどに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、e-ヘルスネット「ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について」、CDC「Autism Spectrum Disorder (ASD) 」、厚生労働省「No.1 職域で問題となる大人の自閉症スペクトラム障害」、福西勇夫、福西朱音『マンガでわかるアスペルガー症候群の人とのコミュニケーションガイド』)
かつて使用されていた以下の診断名・分類は、ASDという診断名・分類に統合されています。
- アスペルガー症候群
- 自閉症
- 高機能自閉症
- 広汎性発達障害(PDD)
それぞれ別の発達障害として、診断基準も異なっていましたが、2013年に行われた『DSM-5』の改訂の際に、厳密に区分するのではなく、地続きの=スペクトラムな障害として捉える現在のASDに変更されました。
ただし、変更前の診断名・分類が、法令や病院、日常会話などで現在も使用されることがあります。また、かつてアスペルガー症候群などと診断された人が、現在のASDという名称を認知していないこともあります。
ASDについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
ADHD(注意欠如多動症)の特徴

ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害、Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)とは、不注意性や多動性・衝動性の特性から日常生活などに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、田中康雄・監修『大人のAD/HD』、岩波明『大人のADHD─もっとも身近な発達障害』、司馬理英子『ササッとわかる 「大人のADHD」 基礎知識と対処法』、星野仁彦『それって、大人のADHDかもしれません』、e-ヘルスネット「ADHD(注意欠如・多動症)の診断と治療」)
ADHDの特性は大きく、以下の2つの特性に分けられます。
- 不注意性:忘れ物やケアレスミスが多い、注意散漫、整理整頓・管理が不得意
- 多動性・衝動性:落ち着きがない、気が散りやすい、後先考えず行動する
ADHDのある人だからといってすべての特性が生じるというわけではありません。いずれかの特性、または複数の特性から困難が生じている人もいます。
ADHDのある人は、必ず不注意性や多動性・衝動性が現れるというわけではなく、人によって特性の現れ方、得意なこと・不得意なことが違う点が大きな特徴です。
ADHDについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
LD(学習障害)の特徴

LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害、Learning Disorder/Specific Learning Disorder)とは、読む・書く・計算する・推論するなど、特定の学習行為のみに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』、厚生労働省「学習障害(限局性学習症)」、小池敏英・監修『LDの子の読み書き支援がわかる本』、バーバラ・エシャム・文、マイク&カール・ゴードン・絵、品川裕香・訳『算数の天才なのに計算ができない男の子のはなし 算数障害を知ってますか?』)
LD/SLDは症状別に、以下の3つの種類に分類されます。
- 読字障害(ディスレクシア)
- 書字表出障害(ディスグラフィア)
- 算数障害(ディスカリキュリア)
LD/SLDのある人は、全ての学習行為に困難が生じるというわけではありません。
いずれかの学習行為、または複数の学習行為に困難が生じている人もいます。計算することのみが不得意、読むことと書くことが不得意などのように、人によってさまざまです。
また、いずれの学習行為においても、人によって得意なこと、不得意なことは異なってきます。
例えば、読字障害のある人のなかでも、スムーズな音読が不得意な人もいれば、音読はできてもその内容を理解することが難しいという人もいます。
このように、LD/SLDのある人は、学習する事柄が総合的に不得意というわけではなく、ごく一部の事柄に困難が生じるという点が大きな特徴です。
LD/SLDについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害のある人が劣等感に悩まされる理由
発達障害の特性は人それぞれです。劣等感に悩まされる理由もさまざまで、実際には多様な要因が絡まっているケースが多くあります。
この章では、劣等感に悩まされる理由として考えられる要因について解説します。
理由①失敗経験を引きずりやすいから

発達障害がある人の中には、幼少期から学習や対人関係、日常生活で繰り返し小さな失敗や挫折を経験してきた方もいるでしょう。
例えば忘れ物が多い、指示がうまく理解できない、場の雰囲気を読めないなどの特性から、周囲に叱責されたり誤解されたりするケースもあります。
こうした経験は否定的な記憶として残り、現在の自分の行動にも影響を及ぼす可能性があります。
「また失敗するかもしれない」「どうせ自分にはできない」といった否定的な自己評価につながり、劣等感が強まる可能性があります。
理由②自身と他者と比較するから
発達障害のある人もない人も、周囲の人と自分を比較するものです。
しかし、発達障害のある人は、比較の対象が定型発達の人であることが多いため「自分だけができていない」「みんなは簡単にできるのに」と感じやすい可能性があります。
他者との違いを痛感することで自己評価が下がり、それが劣等感の要因になっているのかもしれません。(参考:外山美樹「社会的比較が学業成績に影響を及ぼす因果プロセスの検討」)
理由③周囲から誤解を受けやすいから

発達障害の特性のため、周囲から怠けている、空気が読めない、わがままなどの誤った印象を持たれることがあります。
本人は努力しているにもかかわらず、その努力が認められない状況が続くと、「どうせ何をしても評価されない」「自分には価値がない」と感じても無理はないでしょう。
こうした誤解や否定的な扱いは、自己否定の気持ちや劣等感を深める原因になりかねません。(参考:太田晴久・監修『大人の発達障害 仕事・生活の困ったによりそう本』、湯汲英史・監修『心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話』)
理由④正しい自己認識の形成に困難があるから
発達障害のある人の中には、自分の特性を客観的に理解しづらい人もいるかもしれません。
その結果、自分の価値や能力を過小評価したり、過剰に自己批判的になったりすることがあります。
さらには、周囲の評価と自己評価がかけ離れていたり、自分の得意・不得意をうまく言語化できなかったりすることもあり得るでしょう。
正しい自己認識が育たないまま周囲とのギャップを感じ続けることで、劣等感が強まる恐れがあります。(参考:太田晴久・監修『大人の発達障害 仕事・生活の困ったによりそう本』、 湯汲英史・監修『心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話』)
発達障害のある人が劣等感を克服するための具体的な方法
発達障害の特性によって生じる劣等感は、ときに傷つきや苦しみにつながることがあります。しかし、特性を理解し適切な対策を取ることで、劣等感を乗り越えられるかもしれません。
この章では、発達障害のある人が劣等感を克服するための方法について解説します。
方法①セルフケア方法を身につける

劣等感を克服するには、まず心と体の安定を保つことが基本です。発達障害のある人は、感覚過敏や疲れやすさ、不安の高まりなどから、ストレスをため込みやすい傾向があります。
そのため、日常的にリラックスできる時間を持つ、十分な休息を取るなどのセルフケアが大切です。深呼吸やマインドフルネス、趣味の時間の確保など、自分に合ったリラックス方法を見つけておくことで、自己否定の悪循環から少しずつ抜け出すきっかけになるかもしれません。(参考:伊藤絵美『セルフケアの道具箱 ――ストレスと上手につきあう100のワーク』)
方法②周囲の人と関係を構築する
発達障害の特性によって、周囲とのコミュニケーションがうまくいかず、孤立感を抱きやすい場合があります。安心して気持ちを話せる相手とのコミュニケーションは、自己理解が深まったり、劣等感を軽減させたりなど、よい影響をもたらす可能性があります。
信頼できる友人や理解のある同僚、家族との関係を築くことは有効な方法の一つです。ただし、無理な付き合いがストレスとなることもあります。自分にとって心地よい間関係を選び、大切にするのがポイントです。(参考:太田晴久・監修『大人の発達障害 仕事・生活の困ったによりそう本』、 湯汲英史・監修『心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話』)
方法③職場や家庭での環境を整える

発達障害のある人にとって、環境は能力の発揮に大きく影響します。例えば、音や光に敏感な人が騒がしい職場で働くとパフォーマンスが低下する場合があります。
自分の能力が発揮できない状況は、劣等感にもつながります。そのため、自分の特性に合った環境を整えることが大切です。
家庭ではルールや役割分担を明確にする、職場では業務を見える化し、静かな作業スペースを設けるなどの工夫が効果的です。周りの人と相談しながら、環境を整えていきましょう。
方法④専門的な支援を受ける
劣等感が強く、日常生活に支障をきたしている場合は、専門家に相談することが有効です。
発達障害に詳しいカウンセラーや医師、就労支援機関、福祉サービスなどを利用すれば、自分では気づきにくい思考の偏りや環境の問題点が明らかになるかもしれません。
診断や支援を受けることで、原因は自分の能力ではなく特性によるものと気づき、過度な自己責任感が和らぐことも考えられます。
各支援機関に関しては以下のコラムで解説しているため、利用を検討したい人はあわせて確認しておきましょう。
方法⑤小さな成功体験を積み重ねる

自分はできるという感覚を持つことは、劣等感を和らげるきっかけになります。心理学の分野では、小さな目標を設定して成功体験を重ねるシェイピングという方法が用いられることがあります。
例えば5分だけ集中する、忘れ物を1つ減らすといった、小さなチャレンジから始めてみるとよいでしょう。成功体験が積み重なることで自信が育ち、劣等感も少しずつ軽くなっていきます。(参考:実森正子、中島定彦『学習の心理 第2版 行動のメカニズムを探る』)
方法⑥劣等感の原因を知り対策する
劣等感の原因は人それぞれ違います。どんなときに劣等感を強く感じるのかを振り返り、自分の思考の傾向を知ることが、対策の第一歩です。
要因を特定することで、漠然とした悩みを具体的な課題に変えられます。例えば人との比較が原因なら、SNSを見る時間を減らす、自分の成長に集中するといった対策が役立ちます。
発達特性が影響している場合は、特性を理解した上で環境を調整したり、支援機関に相談したりすることが効果的です。自分だけで悩まず、周囲の人や専門家に相談しながら対策を考えていきましょう。
【無料配布中!】『“働きやすさ”から見つける アルバイト探しガイドブック』
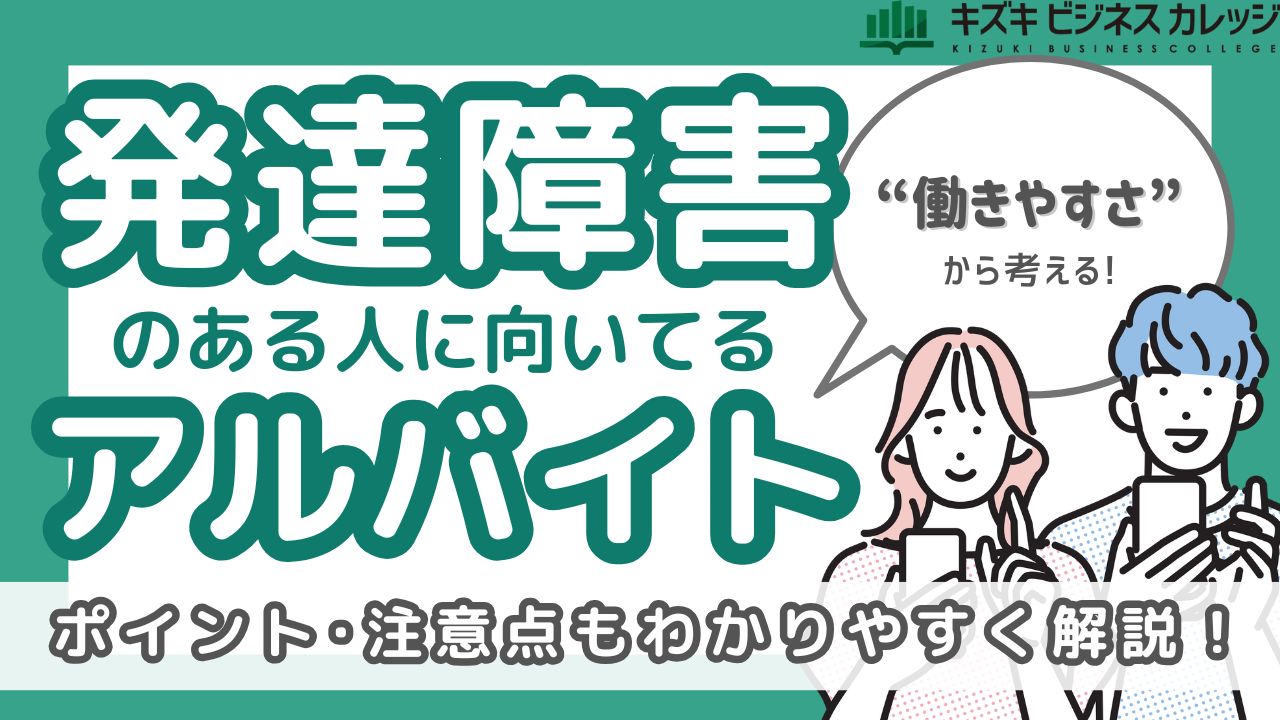
- 自分に合うアルバイトが分からない…
- アルバイトを始めたいけど、自分に合う仕事が見つからない
発達障害のある人の中には、このような悩みを抱える人が少なくありません。
発達障害のある人は、特性によって一般的に簡単とされる仕事でも困難を感じやすい場合があります。
その結果、周囲と比較して自信をなくしたり、アルバイト探し自体が苦痛になったりすることもあります。
本資料では、発達障害のある人が向いてるアルバイトを見つけづらい理由や、向いてるアルバイトを見つけるためのステップ、向いてるアルバイトの具体例などを解説しています。
ぜひ本資料を活用して、あなたに合うアルバイトを見つけませんか?
- 発達障害のある人が向いてるアルバイトを見つけづらい理由
- 自分に合うアルバイトを見つけるための3ステップ
- 【ADHD・ASD・LD/SLD別】向いてるアルバイトの傾向と具体例
- 向いてない可能性のあるアルバイトの特徴
- 発達障害の診断を受けており、自分に合うアルバイトが分からない人
- アルバイトがうまくいかず、自信をなくしている人
- これから働き始めたいが、どのように探せばよいか悩んでいる人
- 無理なく続けられる仕事の条件を整理したい人
資料の入手方法
本資料は、以下のリンクから無料でダウンロードいただけます。
- リンクから申し込みフォームにアクセス
- 簡単なフォームに入力
- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り
- URLから資料を取得!
- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。
- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。
- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。
まとめ:発達障害のある人が劣等感に対処するには

発達障害のある人が抱える劣等感は、さまざまな要因が重なっている場合があります。克服するには、一人ひとりの特性や状況に合わせた方法を選ぶことが大切です。
まずは自分の劣等感の原因を知り、無理のない範囲で取り組めることから少しずつ実践してみましょう。
発達障害とは何ですか?
発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。
詳細については、こちらで解説しています。
ASDのある人に向いている働き方を教えてください。
ASDのある人は、専門性やこだわり、視覚処理能力を活かせる働き方であれば向いてるでしょう。
ADHDのある人に向いている働き方を教えてください。
ADHDのある人は、仕事中一か所に留まることが少ない、自由な発想を活かせる仕事やスピード感が必要な働き方が向いてると言われています。
LD/SLDのある人に向いている働き方を教えてください。
LD/SLDのある人の場合、ご自身の工夫や職場の配慮によって取り除くことができれば、あなたの望む働き方ができる可能性は高まるでしょう。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→









