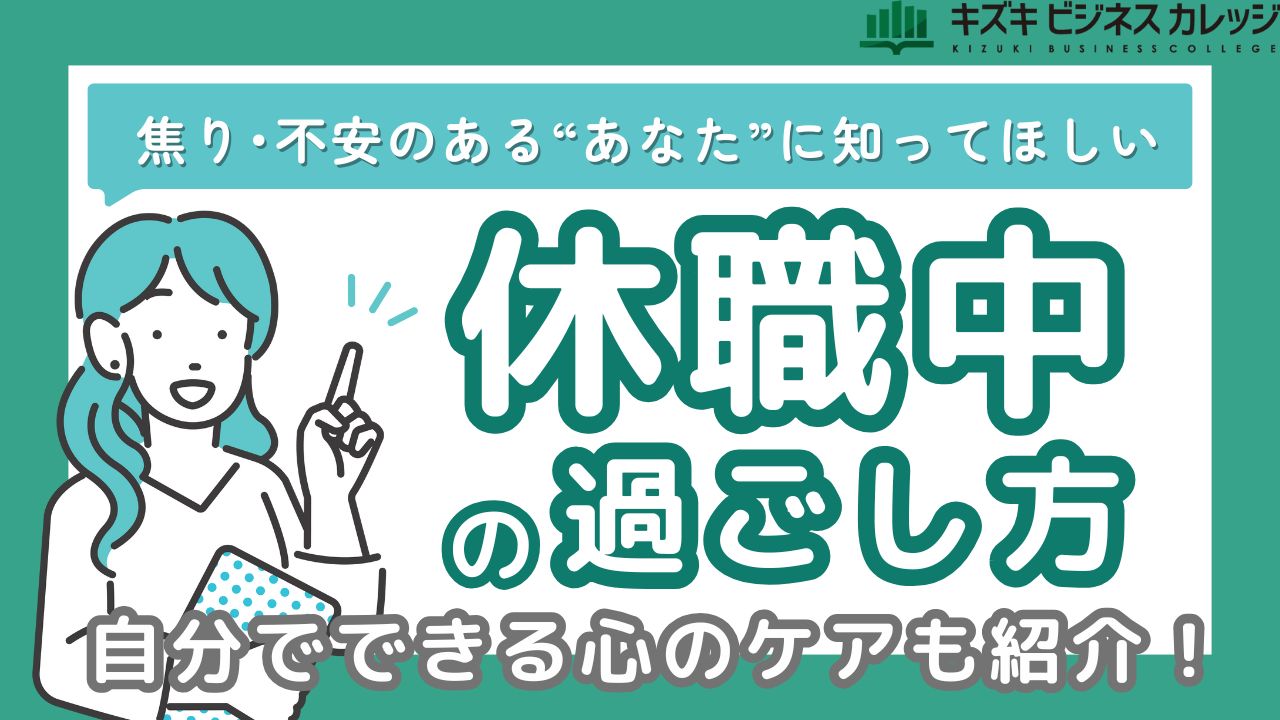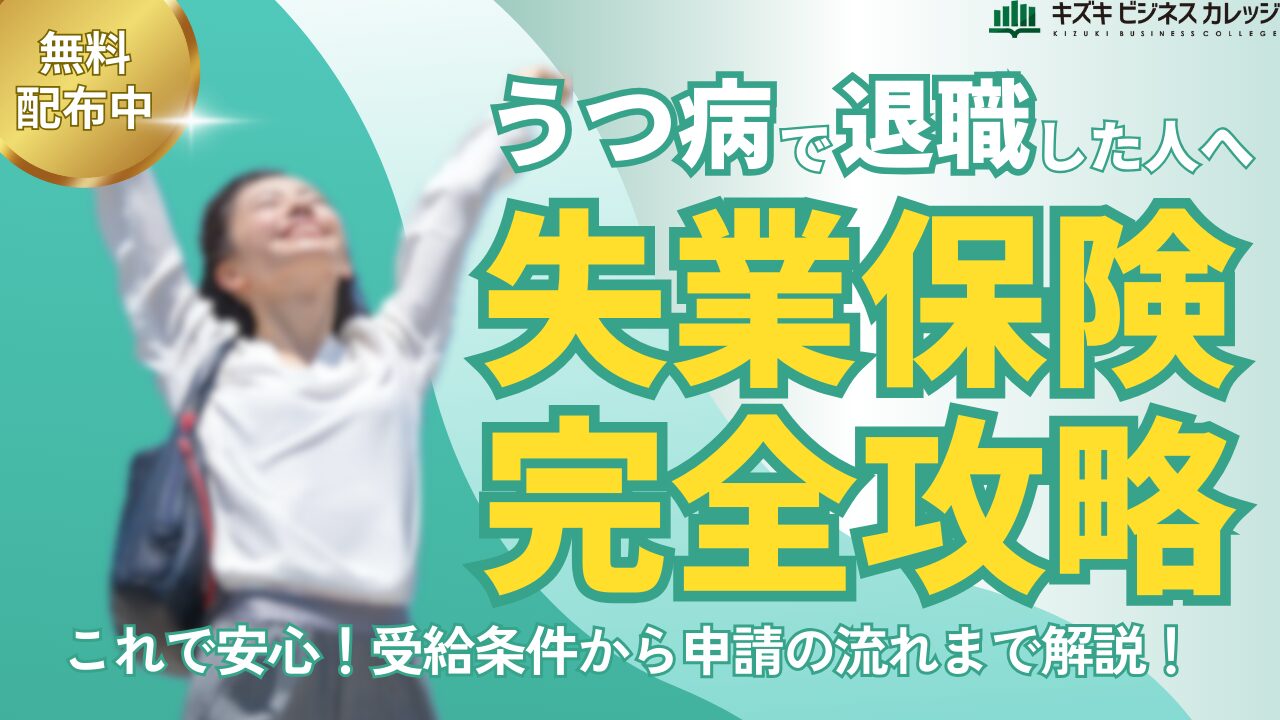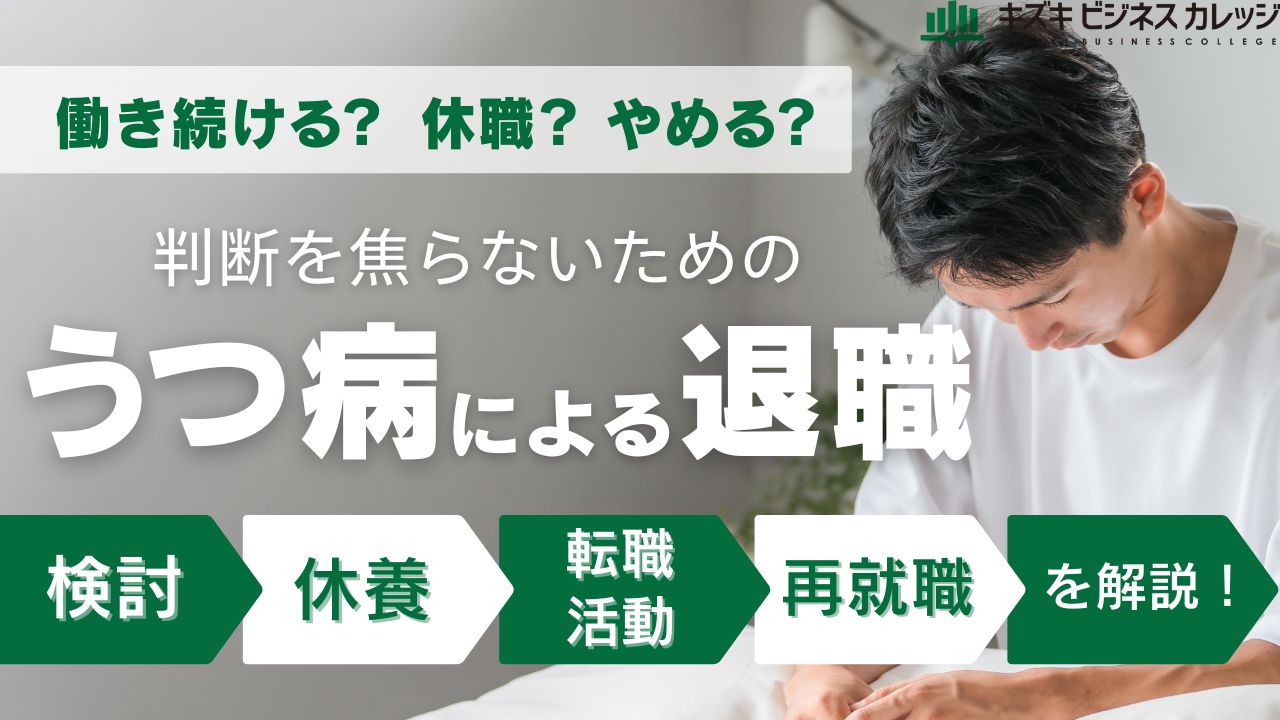メニエール病のある人に向いてる仕事 仕事を続けるコツを解説
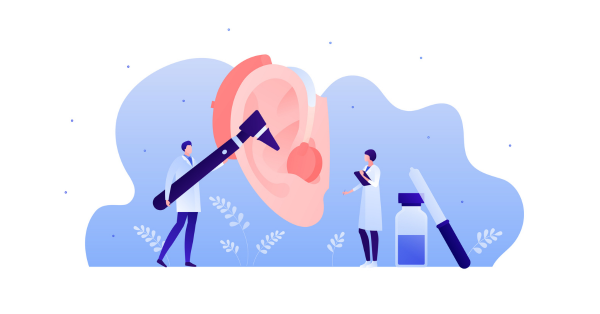
こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
あなたは以下のような症状に悩まされてはいないでしょうか?
- 急にひどいめまいや吐き気に襲われて、これまでどおりに仕事ができない
- めまいや耳鳴りは昔からあったが、最近悪化して、仕事に支障をきたしている
メニエール病の主な症状は、これらのめまいや耳鳴り、吐き気だと言われています。めまいといっても、症状の重い人では立っていることができなくなり、日常生活に大きな影響が出るケースも少なくありません。
このコラムでは、メニエール病のある人、またはメニエール病と思われる症状に悩む人に向けて、メニエール病の概要やメニエール病のある人に向いてる仕事、メニエール病のある人ができる対策について解説します。あわせて、メニエール病のある人が利用できる支援制度や支援機関を紹介します。
メニエール病の治療のためには、メニエール病に詳しい医師のいる耳鼻科やめまいの専門医に行くことが何よりもまず大切です。あなたの症状を見てもらい、適切な治療を進めていきましょう。
メニエル病にお悩みのあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
メニエール病とは?
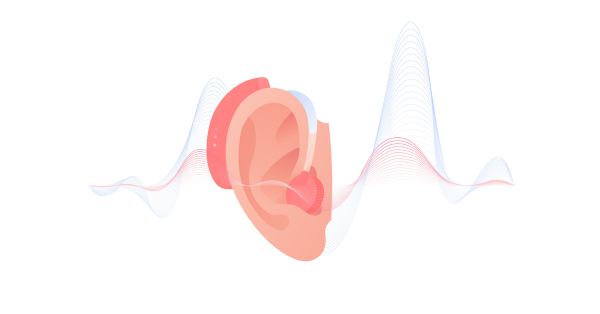
この章では、メニエール病の概要や代表的な症状、原因について解説します。
メニエール病の概要
メニエール病とは、回転性のめまいや吐き気を主な症状とする病気のことです。人によっては、耳鳴りやふらつき、難聴などの症状が現れることもあります。(参考:日本医師会「ストレスが引き金になるメニエル病とは…」、NHK「そのめまい危険かも?メニエール病の症状チェック、原因や治療法は」)
その症状の現れ方も大きな個人差があり、数分ほどの発作を一度起こしたことがあるという人もいれば、数時間にわたる発作を何度も繰り返すという人もいます。
発症する年齢層は30〜50代と言われており、高齢の方はあまり発症しないのが特徴です。
個人差が大きく、メニエール病の発作が起きても自然に回復する場合もある一方で、耳鳴りが慢性化したり、難聴が進行したりするといった後遺症が残るケースもあります。
「メニエール病なのかな...」と不安に思ったら、まずは病院で診察を受けることが大切です。耳鼻科やめまいの専門医の診察を受け、あなたの症状の原因を見極めましょう。
メニエール病の症状
メニエール病の代表的な症状は、以下のとおりです。(参考:日本医師会「ストレスが引き金になるメニエル病とは…」)
- 耳鳴り:一般的に、めまいの発作が起こる前に発生する症状。発作を繰り返すうち、慢性的に発生する場合もある
- ふらつき:直立していても身体がふわふわとふらつき、実際によろけたり、転倒する症状。静止しているものが動いているように見えるという症状もある
- 難聴:一般的には、低音が聞き取りにくくなる症状。発作を起こすと同時に難聴になるケースと、発作を繰り返す中で難聴になっていくケースがある
- めまい・吐き気:めまいが中心的な症状。めまいに伴い吐き気を感じる場合、嘔吐する場合がある
メニエール病の原因
メニエール病の原因は、耳の中の内耳にある器官、三半規管と蝸牛を満たしている内リンパ液が増えすぎることです。(参考:NHK「そのめまい危険かも?メニエール病の症状チェック、原因や治療法は」)
内リンパ液の量が適切であれば、体のバランスを取る三半規管と、音を感じ取る蝸牛が正常に機能してくれます。この内リンパ液が過剰になると、三半規管や蝸牛の働きが阻害され、めまいやふらつき、耳鳴りや難聴が起こります。
メニエール病のある人に向いてる仕事

一般的には、メニエール病のある人に向いてる仕事は、身体的、精神的負荷がかかりにくく、自分のペースで仕事を進めることができるような仕事だといわれます。
こちらで解説しますが、メニエール病の治療のためには、ストレスを減らすことが大切です。
ストレスがかかりやすい仕事だと、メニエール病の症状が悪化する可能性があります。
そのため、一般的に向いていないとされる仕事は、クレームなどを受けることが多い接客業やコールセンター、結果を求められる営業職などです。
このストレスがかかりにくいという条件について、より具体的に考えると、以下のような要素が出てきます。
- 人間関係に関するトラブルが少ない
- ノルマなどが求められない
- 労働時間が長くない
- 自分がやりたい仕事ができる
最後の自分がやりたい仕事ができる点については、一人ひとり違うと思います。そのため、以上の観点から、メニエール病のある人に向いている仕事は以下のとおりです。
- 事務職
- 経理
- ライター
- webデザイナー
- プログラマー
- システムエンジニア
- 工場勤務
- データ入力
以上のような仕事は一般的に、人付き合いが少なく、自分のペースで業務を進めることができるものです。メニエール病の治療において大切なストレス原因に近づかないという対策が取りやすいといえます。
ただし、もちろん自分は接客が好きで、苦にならない、体を動かす仕事が好きだという人にとっては、むしろストレスでしょう。
以上の仕事はあくまで一例です。主治医や、病気のある人の就職・転職・働き方をサポートする支援機関などとも相談しつつ、あなたにとってストレスのかかりにくい仕事は何か考えてみましょう。
メニエール病のある人が仕事を続けるコツ4選

この章では、メニエール病のある人が仕事を続けるコツについて解説します。
メニエール病の基本的な対策は、生活習慣の改善になります。
これらの対策を行うことで、メニエール病の症状が軽くなり、めまいなどの症状を予防していくことができます。
ただしこちらは一般論です。実際のあなたのための治療法・対策は、医師の指示に従うようにしましょう。(参考:NHK「そのめまい危険かも?メニエール病の症状チェック、原因や治療法は」)
コツ①ストレスを減らす
ストレス原因をはっきりさせ、それから距離を取るか、取り除きましょう。また、疲労を溜めないために十分な睡眠を取ることや、自分にあったストレス解消法、気分転換の方法を見つけることも大切です。
コツ②塩分摂取量を減らす
塩分を過剰に摂取すると、体内の塩分濃度を調節するために体内に水が溜まりやすくなります。減塩をして、症状を軽くしていきましょう。
コツ③適度な水分補給をする
カフェインや塩分を含まない、水や麦茶を適度に摂取することで、体内の水分量が正常に保ちやすくなります。
コツ④適度な運動をする
適度に運動をすることで、耳の血液の巡りがよくなり症状の改善につながります。特に、ウォーキングやジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動が効果的と言われています。
メニエール病のある人が利用できる支援制度

この章では、メニエール病のある人が利用できる支援制度について解説します。
メニエール病のある人が転職したい場合:就労移行支援、就労継続支援
仕事を辞めて転職したい場合や症状と付き合いながら自分のペースで働きたい場合、就労移行支援や就労継続支援のサポートを利用できる可能性があります。
就労移行支援とは、「障害者総合支援法(一般企業などへの就職を目指す、病気や障害のある人」向けに、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」に基づいて行われる福祉サービスのことです。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
実際のサービスは、国の基準を満たしたさまざまな民間の就労移行支援事業所が行います。
就労移行支援事業所では、体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができます。
さらには、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
一方、就労継続支援は、就職することが難しい障害者のある人などを対象に、配慮が受けられる環境での就労を提供しているものです。
就労移行支援、就労継続支援、いずれのサポートを受ける場合でも大切なのは、自分の症状を把握していることと、症状への対処法をきちんと説明できることです。
面接などで自分の症状を適切に説明できれば、転職・就職できる可能性はぐっと高まります。
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)でも、症状の説明を含んだ面接対策を行っています。
就労移行支援と就労継続支援については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
メニエール病のある人が休職したい場合:傷病手当金
メニエール病を発症すると、その症状といつまた症状が出るかわからないという不安感から仕事を続けることが難しくなることがあります。
そういった場合には、休職することもひとつの選択肢です。
休職することでメニエール病の治療に専念でき、結果として、無理して働き続けるよりも早く仕事にしっかり取り組めるようになる可能性が高まります。
休職について検討している場合、お勤め先の上司や人事に相談しましょう。休職期間や休職中の給与の有無などは、職場によって条件が異なります。確認しておく必要があります。
その後、実際に休職申請をするときには診断書が必要になります。そのため、かかりつけの医師にも会社を休職したいということを伝え、診断書を出してもらいましょう。
休職からの復帰や休職中の過ごし方については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
休職中の給与が支払われない場合、会社で加入している健康保険の制度を利用して傷病手当金を受け取ることができます。
この傷病手当金を受け取るには、いくつかの条件はありますが、最長で1年6ヶ月の間受け取ることができます。(参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」)
傷病手当金については、以下のコラムで解説しています。うつ病のある人に向けた内容になりますが、参考になるかと思います。ぜひご覧ください。
メニエール病のある人が退職する場合:失業手当(雇用保険の基本給付)
退職する場合、退職する日までに雇用保険に1年以上加入していれば、失業手当(雇用保険の基本給付)が原則受け取れます。
こちらは、支給期間や支給額が個々人の状況によって変わってきますので、各自治体窓口やハローワークに相談して詳細を確認してみてください。(参考:厚生労働省「雇用保険制度> 基本手当について」)
失業手当については、以下のコラムで解説しています。うつ病のある人や発達障害のある人、適応障害のある人に向けた内容になりますが、参考になるかと思います。ぜひご覧ください。
補足:メニエール病の症状がひどい場合:障害者手帳、障害年金
メニエール病の症状が続き、めまいや耳鳴りなどで日常生活に支障をきたす場合、身体障害者手帳の取得や障害年金の申請ができる可能性があります。
これらについては、症状の詳しい確認や審査が必要になってきます。まずはかかりつけの医師に自分の症状は交付基準に該当するかを確認しましょう。その後、各自治体の障害福祉課などに相談し、申請を行っていきましょう。(参考:東京都福祉局「身体障害者手帳について」 、日本年金機構「障害年金」)
障害者手帳と障害年金については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
メニエール病のある人が利用できる支援機関
まずは、耳鼻科やめまいの専門医がいる病院に相談しましょう。
メニエール病は、専門的な知識を持つ医師の指示に従って治療していくのがもっとも確実な治療法です。
病院の診察を受け、治療を進めていく中で、身体的な悩みや生活の悩み、精神的な悩みが出てきた場合は、以下のような支援機関に相談するのがオススメです。
- 基幹相談支援センター
- 福祉事務所
- 保健所
- お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口
まとめ:あなたにあった対処法や仕事が見つかることを願っています

メニエール病は個人差が大きい病気です。人によっては仕事や日常生活に支障をきたすほどの症状が現れることがあります。
このコラムでは、症状がひどい方には一度しっかり治療する道を、症状が軽くなってきた方には復職や転職する道を示しました。
このコラムを読むことで、あなたの現在の症状に応じた適切な対処法と、向いてる仕事や働き方が見つかることを願っています。
メニエール病にある私に向いてる仕事を知りたいです。
メニエール病のある人に向いてる仕事として、以下が考えられます
- 事務職
- 経理
- ライター
- webデザイナー
- プログラマー
- システムエンジニア
- 工場勤務
- データ入力
詳細については、こちらで解説しています。
メニエール病について相談できる場所を知りたいです。
メニエール病について相談できる支援機関として、以下が考えられます
- 基幹相談支援センター
- 福祉事務所
- 保健所
- お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口
- 精神保健福祉センター
詳細については、こちらで解説しています。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→