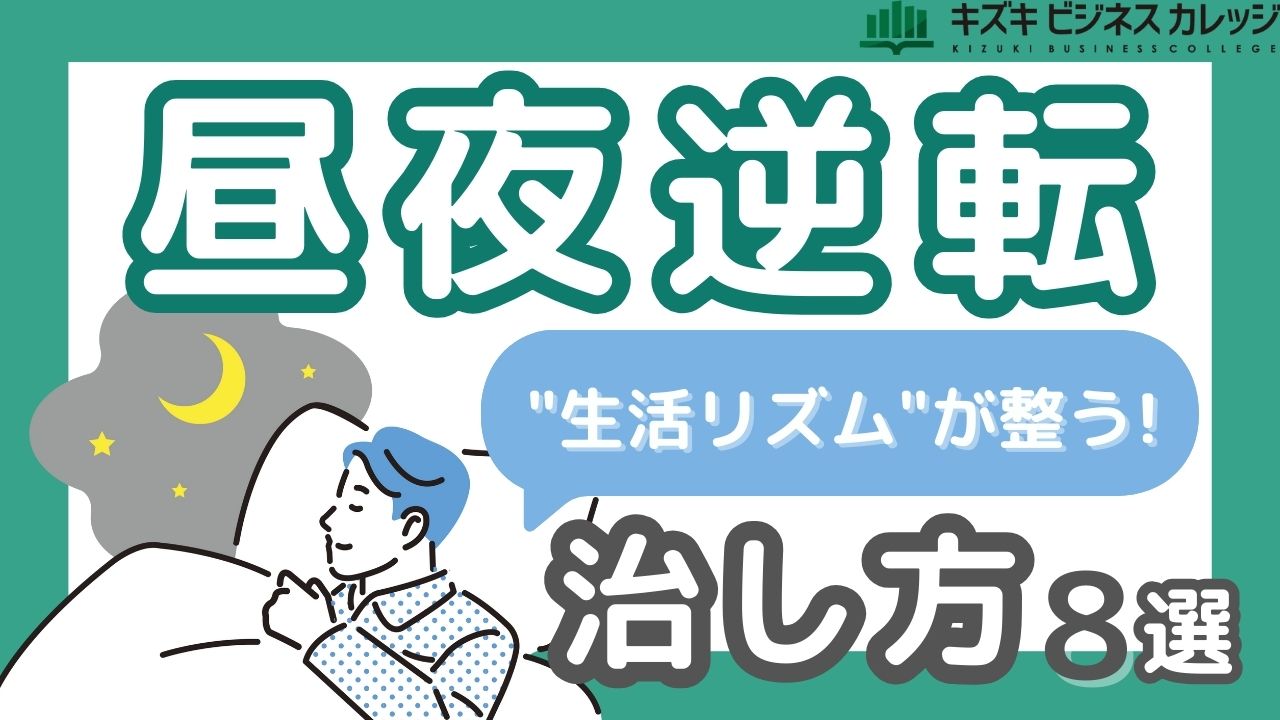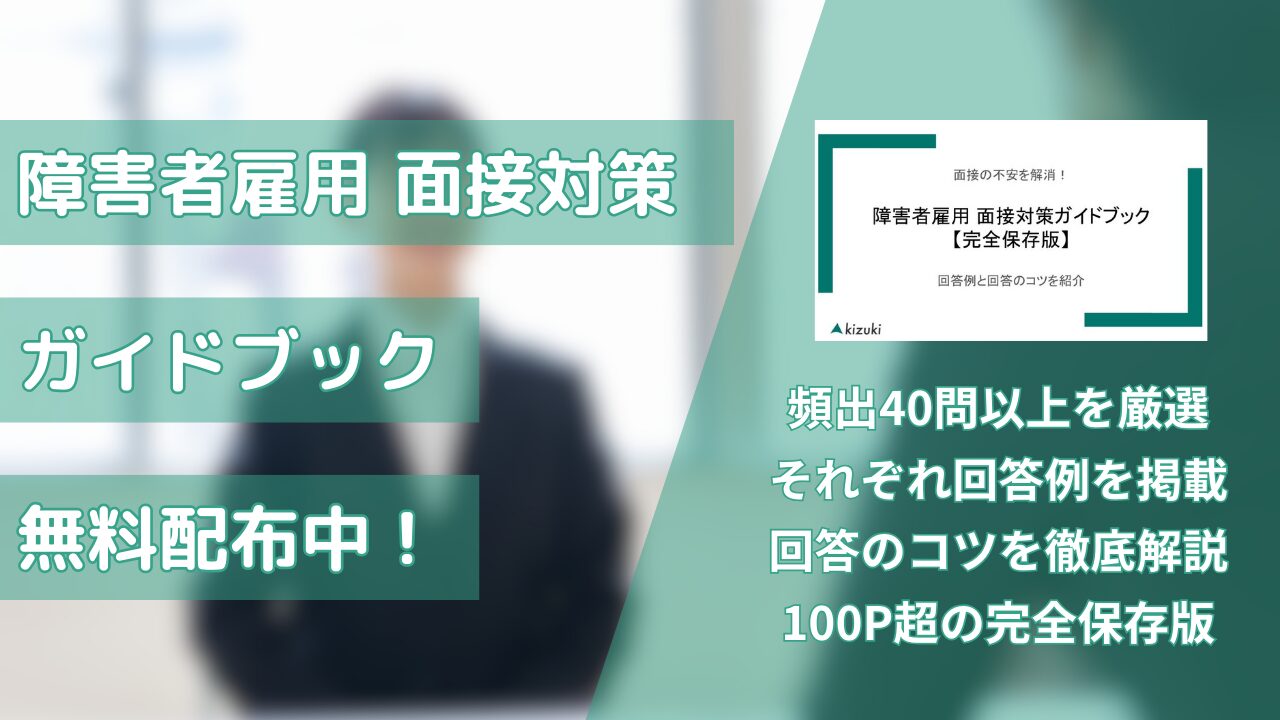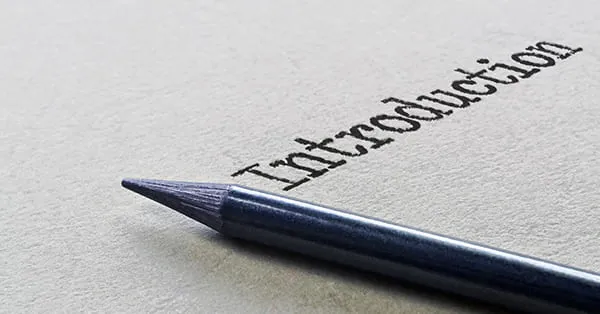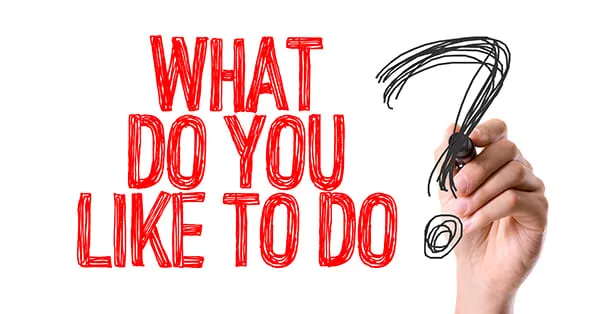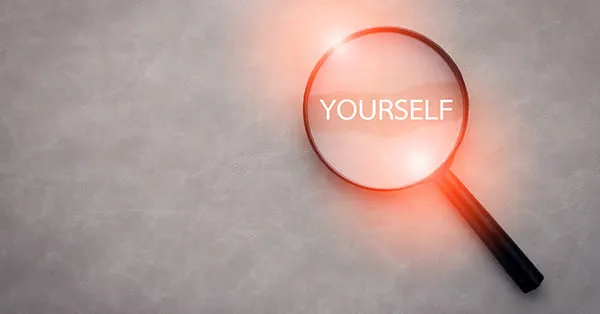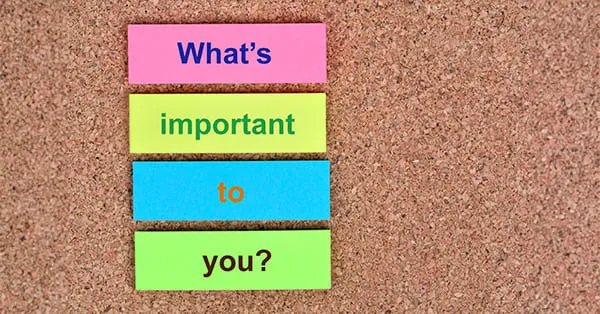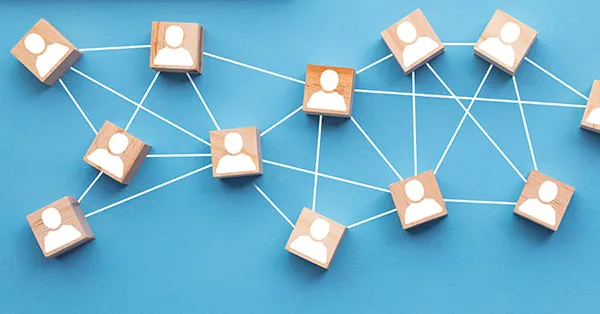ひきこもり状態にある人に向いてる仕事 社会復帰をする方法を解説【マニュアル配布中】
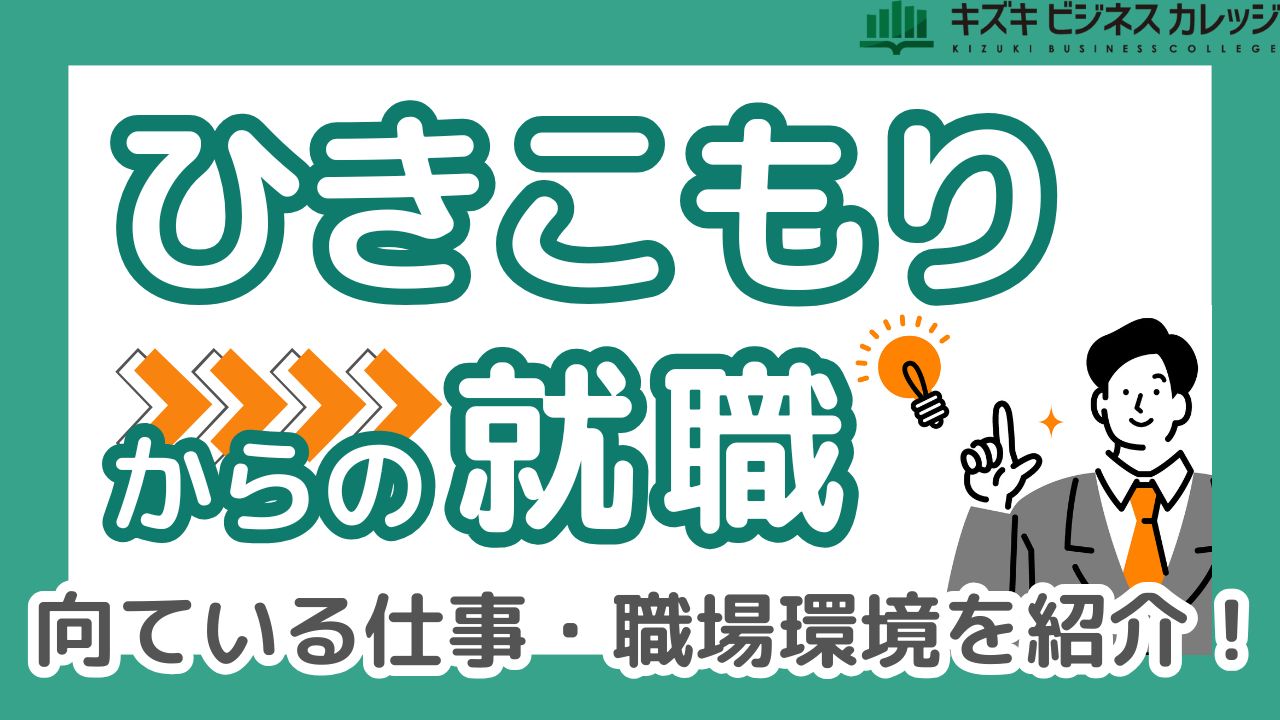
こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC) です。
ひきこもりから仕事を見つけるのは無理だと思っている人もいるかもしれません。
- 社会に出ることが不安…
- 仕事を見つけても、継続的に働けるだろうか…?
- 無職の期間が長いため、就職に希望を持てない...
さまざまな不安が浮かぶこともあるでしょう。
このコラムでは、ひきこもり状態にある人にオススメの仕事と、仕事探しを成功させる方法などについて解説します。
ひきこもり状態からの社会復帰を目指すきっかけに、少しでもなれば幸いです。
さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、ひきこもり状態からの就職に不安を抱えている人に向けて、『ひきこもりからの就職 完全マニュアル』を公開いたしました。
ひきこもり状態にある人が働くための4つの準備やひきこもり状態にある人が向いてる仕事・職場環境について解説しています。
ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。
ひきこもりから働き始めたいあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
ひきこもり状態でも、仕事を見つけることは可能です

今あなたがひきこもり状態にあっても、「仕事を見つけられない」と諦める必要はありません。
世間には、たくさんの仕事や働き方があります。ひきこもり経験がある人を求めている会社もあれば、リモートワークやシフト制など自分に合った働き方ができる職場もあります。
また、正社員として働くことだけが社会復帰ではありません。契約社員やアルバイトなど非正規雇用で働いている人も、さまざまなかたちで社会に貢献しています。
そのため、フルタイム労働に不安がある人は、アルバイトなど短時間の勤務を通じて、少しずつ仕事や人との関わりに慣れていくという選択肢もあります。
ひきこもり状態から仕事を見つけるときに大切なことは、まず自分に合った環境や働き方を見つけることです。
ひきこもりとは?
ひきこもりとは、さまざまな原因から自宅以外での就学・就労などの社会的な活動の機会を避けて、長期にわたって自宅に留まり続けている状態のことです。(参考:ひきこもりVOICE STATION「まず知ろう!「ひきこもりNOW」!」、厚生労働省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」)
ひきこもりは、厚生労働省によって以下のように定義されています。
ひきこもりとは、「様々な要因の結果として社会的参加 (義務教育を含む就学, 非常勤職を含む就労, 家庭外での交遊など) を回避し、原則的には6ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない形での外出をしていてもよい) を指す現象概念である。」(参考:厚生労働省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」)
ここでいう社会的参加には、学校や仕事に行くことのほか、家族や同居人以外の人との交流なども含まれます。
外出していたとしても、それが他者と関わらない形の外出の場合は、ひきこもりに該当します。例えば、近所のコンビニへの買い物のために外出をしていても、ほかの人との交流がない場合は、ひきこもりと見なされることがあります。
反対に、外出をほとんどせずに通信制高校に在籍している人やリモートワークをしている人などは、就学・就労をしているため、ひきこもりに該当しません。
ひきこもり状態にある人が自分に合う仕事を見つける5つの方法
この章では、ひきこもり状態にある人が自分に合う仕事を見つける方法について解説します。
方法①さまざまな働き方を知る

仕事といえば、正社員として決まった時間に出社するというイメージがあるかもしれません。
しかし、働き方は多種多様になってきています。そのため、自分のライフスタイルや働きやすい環境を選びやすくなってきています。
働き方に大きく影響する勤務形態には、以下のようなものがあります。
定時制
- 多くの職場で採用されている働き方
- 始業時間と就業時間が決まっている
- 出勤する曜日も決まっていることが多い
- 生活習慣を整えやすい
- 全社員が常にそろっているため周囲と連携を取りやすい
- 休日となる曜日が固定されており、事前に休みの予定を入れやすい
- 通勤・帰宅ラッシュにあいやすい
- 休みの日が定められているため、個人的な事情に対応しづらい
- 週5日連続での出勤などが、疲労の原因となる場合がある
シフト制
- 決められた時間帯で交代勤務をする
- サービス業・製造業・運送業・医療現場・介護職などに多い
- 早朝もしくは夜間に勤務できる場合がある
- 予定や生活習慣にあわせて働ける 好きな時間帯の勤務を希望できる場合がある
- 希望休を出しやすい
- 夜間や週末に出勤すると割増賃金が支払われる場合がある
- 勤務時間が不規則だと、体調を崩す可能性がある
- 希望する時間帯で出勤できない場合がある
- 5日以上の連続勤務になる場合がある
フレックスタイム制
- 定められた時間内で勤務時間を調整する
- コアタイムでは出勤が必要な時間帯以外は自由な時間に働ける
- フレキシブルで好きな時間帯に働ける
- 仕事量や体調により柔軟に対応できる
- 予定や生活習慣にあわせて勤務時間を選べる
- 業務量にあわせた柔軟な働き方ができる
- 毎月定められた時間は働く必要がある
- 勤務時間スケジュールや予定を自己管理する必要がある
- 制度を取り入れている企業の数が限られている
現在は出社だけではなく、リモートワークとして家からできる仕事も増えています。
それぞれのメリットとデメリットは、以下のとおりです。
職場勤務
- オフィスや店舗など、家の外で働く勤務形態出勤が必要
- 上司や同僚などの職場の人と直接コミュニケーションが取れる
- 仕事とプライベートのメリハリがつけやすい
- 仕事に集中しやすい
- 上司や同僚などの職場の人と連携が取りやすく、相談もしやすい
- 人間関係の構築にストレスを感じる可能性がある
- 通勤・帰宅時間が負担となる場合がある
- 仕事場の状況によっては気が散りやすい
リモート勤務
- 自宅から、オンラインで仕事をする勤務形態
- 完全在宅でできることが多い
- 週の定められた日数もしくは会議のときのみ出社が必要な場合がある
- 家から出る必要がなく、ひとりで落ち着いて仕事ができる
- 対面でのコミュニケーションを避けられる
- 好きな時間帯で勤務できることが多い
- 職場の人との連携が取りづらいときがある
- 職場勤務と比較すると電気代の負担が増す可能性がある
- 生活環境の状況によって仕事に集中できない可能性がある
方法②自分の得意を知る
自分の得意なことを把握しておくと、継続的に働ける仕事を見つけやすくなります。(参考:八木仁平『世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 人生のモヤモヤから解放される自己理解メソッド』)
なぜなら、苦手なことより得意なことを活かせる仕事のほうが、ストレスを感じにくいからです。
得意なことといっても、ほかの人より秀でているものでなくても大丈夫。普段はなんなくこなしていることが、仕事で役立つときもあります。
得意なことを見つけるために検討すべきポイントについては、こちらで解説しています。
方法③自分の苦手な職場環境を整理する

自分に合う働き方や得意なことがなかなか思い浮かばない人もいるかもしれません。
その場合、避けたい労働環境を整理しておき、その特徴に当てはまらない仕事を探すようにしましょう。
避けたい労働環境を整理しておくことで、応募する求人を絞りやすくなります。
また、ストレスを感じる原因を減らし、継続しやすい仕事を見つけられる確率が高くなるでしょう。
方法④理想の生活習慣を具体的にする
理想の生活習慣にあった勤務ができる職場であれば、無理なく勤務を続けやすいはずです。
例えば、勤務時間は、9時から18時、もしくは10時から19時などが一般的です。しかし、朝早くから夕方まで、もしくは昼頃から夜にかけて勤務できる職場もあります。
できるだけ早く帰ってゆっくりとする時間や家族とコミュニケーションを取る時間を大切にしたい人は、早朝から働ける仕事を探してみるといいかもしれません。
一方で朝はゆっくりしたい人や、昼夜逆転の生活が改善できるか不安な人は、昼頃から出社できる仕事を探してみましょう。
方法⑤支援機関を利用する

自分に合う仕事を見つけるときは、支援機関を利用することも大切です。
どのような仕事や職場がいいか、プロが一緒に考えてくれるだけではなく、履歴書や面接の対策についても教えてくれる場合があります。
利用できる支援機関については、こちらで紹介します。
ひきこもり状態の人にオススメの5つの仕事環境
この章では、ひきこもり状態にある人にオススメの仕事環境について解説します。
環境①人との関わりが少ない

しばらくひきこもりの状態にあると、うまく会話を続けなければと頑張りすぎることもあるかもしれません。また、人との関わりが多いと疲労を感じる人もいるでしょう。
人とのコミュニケーションが不安な人の場合、事務や工場での作業など、パソコンや機械と向き合いながら進める作業であれば、人との関わりを最小限に抑えられます。
- コミュニケーションはリハビリから始めていきたい人
- 一人で静かに作業できる環境のほうが好きな人
- 人との関りが苦手な人
人との関わりが少ない仕事については、こちらで解説しています。
環境②在宅でできる
仕事はしたいけど、毎日の外出は負担に感じる人もいるでしょう。なかには満員のバスや電車での移動を避けたい人もいるはず。
最近では、家でできる仕事が増えています。職場の人たちとのコミュニケーションや相談はオンラインのチャットツールを通じて行い、会議はWEBミーティングから参加します。
出社が一切不要な職場と、定められた日数だけ出社が必要な場合があります。
すべてリモートで完結したいのか、ときには出社をして外出や対面でのコミュニケーションの機会を得たいのか、自分に合わせた働き方ができる求人を探してみましょう。
- 家にいながら社会復帰を目指したい人
- 外出に不安がある人
- ひとりで仕事を進めることが苦ではない人
在宅でできる仕事については、こちらで解説しています。
環境③覚えることが少ない

はじめて仕事をする場合や離職期間が長い場合、仕事を覚えるまでに時間がかかる場合があるかもしれません。
そのなかで「やっぱり仕事は無理だ」「周囲の人に迷惑をかけている」と感じることもあるでしょう。
慣れないうちは誰だってうまくいかないものです。自分がダメだと思わなくても大丈夫です。
ゆっくりと仕事に慣れていきたい場合は、新しく覚えることが少ない単純作業を中心とした仕事などから初めていきましょう。
- プレッシャーを感じると頑張りすぎる人
- 少しの困難でも挫けそうだと不安を感じている人
- 自分のペースで社会復帰を目指したい人
覚えることが少ない仕事については、こちらで解説しています。
環境④シフト制で働ける
定められた時間内で交代勤務で働くシフト制の仕事であれば、自分にあった時間帯で働ける場合があります。
シフト制の職場のなかには、時間だけではなく休みの曜日を選べる場合もあります。通院をしながら働く場合、週末は混んでいて予約が取れないときもあるでしょう。
平日に休みを取得できる仕事であれば、通院と勤務を両立させやすくなります。
- 朝が苦手なため、昼以降に出勤したい人
- 勤務開始までに昼夜逆転生活を改善できるか不安がある人
- 通院などの予定と仕事を両立させたい人
シフト制で働ける仕事については、こちらで解説しています。
環境⑤ひきこもりの経験を生かせる

ひきこもり状態にあると、仕事探しにおいて不利になると思う人は多いかもしれません。
しかし、ひきこもりを経験したあなただからこそできる仕事があります。
例えば、悩みを抱える人の相談支援をするNPO法人や、不登校状態にある人に対応している学習塾などです。
過去の経験があるからこそ、ほかの人には分かってもらえない気持ちを共有しあえます。
そのスキルが、ほかの誰かの心に居場所を作ったり安心感を与えるときもあるでしょう。
ひきこもりの経験は必ずしも不利になるわけではなく、むしろ強みになる場合もあると知っておいてください。
- 過去の経験を活かして、同じ経験にいる人の支えになりたい人
- 社会活動に興味がある人
- やりがいを実感しやすい仕事がしたい人
ひきこもりの経験を活かせる仕事については、こちらで解説しています。
人との関わりが少ない4つの仕事
この章では、人との関わりが少ない仕事について解説します。
仕事①事務職

事務職と一言でいっても、書類作成・データ入力・経理会計など、さまざまな種類があります。
ほかの部署の人から業務をお願いされるなど、コミュニケーションが求められる場面もあるかもしれませんが、基本的にはパソコンと向き合っている時間が多いです。
職場によっては、自宅でオンラインのチャットツールを使って社内の人と連絡を取りながら進めることも可能です。
電話での顧客対応が業務に入っている場合もあります。人との関わりを極力控えたい場合は、具体的な業務内容を確認しておくようにしましょう。
資格や経験がなくても応募可能な求人がたくさんあり、仕事未経験者や離職期間が長い人からも人気です。
- 同じ作業を黙々とすることが好きな人
- スキルがなくても始められる仕事を探したい人
- 社内のコミュニケーションを最低限に控えたい人
仕事②システムエンジニア
システムエンジニアとは、システムの設計や開発を行う仕事のことです。
クライアントの要望に沿って業務を進めていく必要があるため、打ち合わせへの参加が必要な場合があります。しかし、ほとんどの業務はひとりで進めていきます。
また、スキルを磨いていけば高い報酬が支払われる可能性もあります。
資格や経験なしで応募できる求人もありますが、IT関連の資格を持っていると就職活動で有利になるでしょう。
未経験から合格を目指すなら、AWS 認定ソリューションアーキテクト – アソシエイトなどに挑戦してみてください。
- 論理的に物事を考えることが得意な人
- スキルアップを目指していきたい人
- モノづくりが好きな人
仕事③配達員

商品や荷物を運ぶ仕事です。新聞や手紙など軽量なものであれば、バイクや自転車を使い、段ボールなど大きさや重量があるものはトラックを使って運びます。
配達先では玄関などでのやり取りが発生しますが、移動中の時間が多いため、ひとりで過ごす時間がほとんどです。
一方で時間とおりに荷物を届けたり、重たい荷物を運ぶなど、責任感や体力が必要となります。
バイクやトラックを運転する場合は運転免許が必要ですが、それ以外のスキルは必要ありません。初心者でもはじめやすく、求人が比較的多い点も特徴です。
- 道を覚えることが得意な人
- 外に出る時間を作りながら働きたい人
- 時間管理ができる人
仕事④警備員
商業施設やオフィスビルなどで、安全管理・異常のチェック・利用者の案内などをします。
建物の管理人とのコミュニケーションや利用者からの質問など、人と関わる場面もあります。
しかし、基本的にはひとりで巡回をするか特定の場所に立ったまま、周囲で異常がないかを確認している時間がほとんどです。
夜間警備の求人もあるため、夜に働きたい人は夕方以降にシフトに入れる求人を探しましょう。
スキルや資格は不要なため、未経験の人でも始められます。立ち仕事なので、体力をアピールできるといいでしょう。
- 長時間立っていることが苦ではない人
- 集中力がある人
- 責任感がある人
在宅でできる5つの仕事
この章では、在宅でできる仕事について解説します。
仕事①WEBライター

クライアントの要望に沿って、WEB上に掲載される記事や文章を執筆する仕事です。
リサーチや執筆のみで完結する場合が多く、在宅でできる求人が豊富です。
未経験であっても、正社員としてライティング会社に務めたりライタースクールに通って徐々にスキルを身につけていけば、フリーランスとして活躍することもできます。
クライアントとの打ち合わせやインタビューのために外出が必要なこともあるため、外出や対面でのコミュニケーションを避けたい人は、インタビューライターなどは避けるようにしましょう。
- 文章を書くことが好きな人
- 情報収集が好きな人
- 修正を学びとして捉えられる人
仕事②WEBデザイナー
WEBサイトなど、インターネット上のページのデザインを作成する人のことです。
パソコン1台あれば仕事ができるため、在宅ワークが可能な求人が豊富です。
初心者であっても、仕事やスクールを通じてスキルアップしていけば、フリーランスとして活躍することもできます。
基本的には、クライアントの要望に沿ってデザインを企画・作成していきます。
そのため、業務開始時の打ち合わせやフィードバックなどでクライアントとコミュニケーションを取る必要はありますが、基本的にはひとりで作業を進められます。
- 絵やデザインなど創作することが好きな人
- 自ら進んで学んでいく人
- 相手の想いを汲むことが得意な人
仕事③動画・画像編集

クライアントの使用目的に合わせて、動画の切り抜き・つなぎ・テロップ入れや、画像の加工をする仕事です。
最近は、SNSを通じて収益を得たり広告を載せる個人・企業が増えたことから、需要が高まりつつあります。
未経験で始められ、仕事やスクールでの学びを通じてスキルを身につけていけば、フリーランスとして活躍することもできます。
- 黙々と作業を続けられる人
- SNSや映画をよく見る人
- スキルアップしながら働きたい人
仕事④データ入力
顧客情報や売上データを、指定のファイルなどに記入していく仕事です。
特別なスキルは不要で、決まった業務内容を繰り返すことが多いです。そのため、未経験やはじめて仕事をする人でも始められます。
派遣会社やアルバイトの募集が多く、正社員やフリーランスとして働くことに不安がある人にもオススメです。
ワードやエクセルを使える人が就職に有利になることが多く、業務開始後もスムーズに仕事を進められます。
そのため、パソコンを触る機会があまりなかった人は、基礎的な使い方だけでも学んでおくといいでしょう。
- 単純作業が好きな人
- 正確性を大切にできる人
- パソコンを使い慣れている人
仕事⑤カスタマーサポート

カスタマーサポートとは、顧客の問い合わせに応じる仕事です。商品・サービスに関する相談や質問に、電話やメールなどを使って答えます。
さまざまな質問や相談が寄せられますが、受け答えのマニュアルが用意されていることが多いため、安心して働けるでしょう。
パソコンやスマートフォンがあれば働けるため、在宅での求人も豊富で、ひきこもり状態にあった人や子育て・介護中で家から離れられない人からも人気です。
顧客とコミュニケーションを取ることが業務の大部分を占めるため、会話をしていると疲れやすい人は注意しましょう。
また、クレームに遭うこともあるため、顧客の感情に流されず冷静に対応することも大切です。
- 人と話す機会を設けたい人
- 冷静な人
- 同じ業務を繰り返すことが好きな人
覚えることが少ない4つの仕事
この章では、覚えることが少ない仕事について解説します。
仕事①受付

来客などの対応・電話対応・簡単な事務作業を行う仕事です。
具体的な勤務場所としては、オフィスビルや病院などがあります。
幅広い業務を担当しますが、決まった流れで決まった内容をすることが多いです。
また、内容も簡単な業務がほとんど。そのため、1日の流れを覚えさえすれば、あとはスムーズに仕事を進めやすいでしょう。
常に人前に立っているため、愛想の良さや笑顔を心掛ける必要があります。少しずつコミュニケーション能力を高める練習になるかもしれません。
- 人と接する環境に身を置きたい人
- 細かいことに気を配れる人
- 長時間座っていることが苦にならない人
仕事②工場の作業員
包装や仕分けなどのライン作業と言われる簡単な業務から、設備管理や品質管理といった責任のある業務まで、さまざまな作業があります。
ライン作業であれば求人も多く、マニュアルどおりに決まった作業を繰り返すことがほとんど。そのため、仕事を見つけやすく、業務内容も比較的覚えやすいでしょう。
業務に慣れていけば、新しい作業にも挑戦できるかもしれません。しかし、段階的に覚えていけるため無理に頑張りすぎる必要はありません。
工場によっては早朝出勤や夜出勤を選べるため、自分の生活習慣に合わせて働けます。
- 少しずつスキルアップしたい人
- 黙々と作業をしたい人
- 自分の生活リズムに合った仕事をしたい人
仕事③清掃員
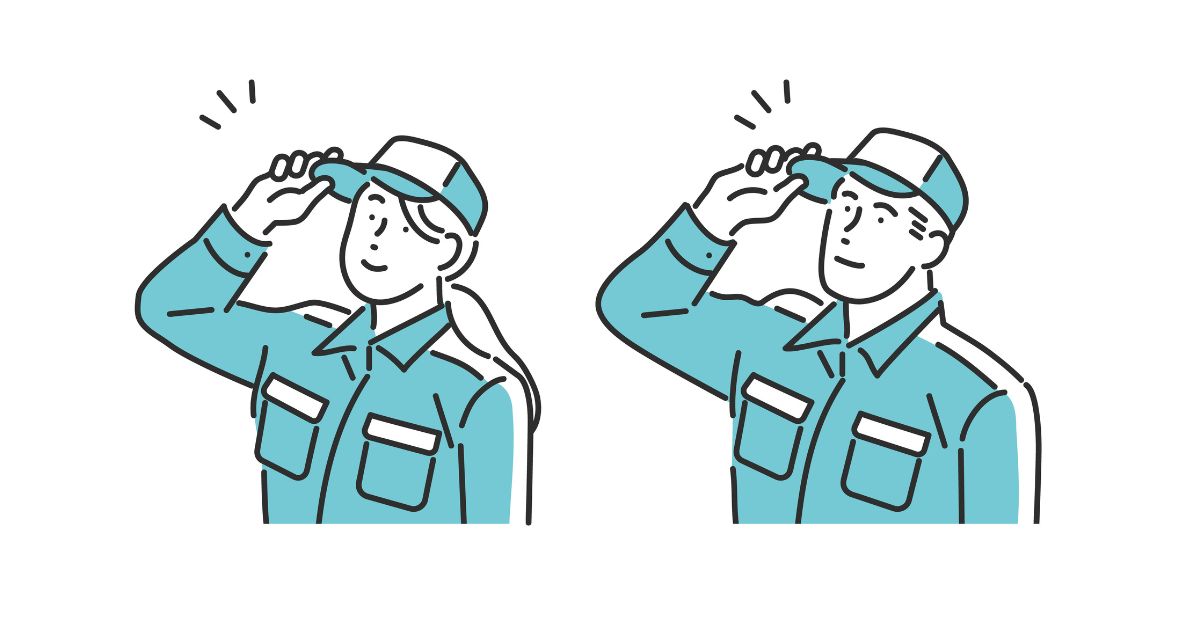
商業施設・オフィスビル・宿泊施設などで清掃をする仕事です。
覚えることが限られているうえ、簡単な作業が多いため、仕事に慣れるまで時間はかからないでしょう。
決まった時間内に特定の場所の清掃を終える必要があるため、時間管理をしながらテキパキと動く必要があります。
最初は先輩が効率的に仕事を進めるコツを教えてくれるので、少しずつ慣れていきましょう。
勤務時間は早朝や夜中など、さまざま。そのため、自分の生活習慣に合わせて働けます。
仕事を覚えたあとはひとりで作業を進めることが多いです。人との関わりが苦手な人にとっても働きやすいでしょう。
- テキパキと動きたい人
- 細かい汚れなどに気付ける人
- ひとりで黙々と作業をしたい人
仕事④倉庫管理
工場などの倉庫で、商品の仕分け・整理・在庫の管理などを行います。
簡単な業務が多く、日々同じような作業を繰り返すため、慣れるまで時間がかかりにくいです。
少しずつ在庫の置き場を覚え、効率的な動きを身につけていけるでしょう。
立ち仕事が多く体力を使いますが、重たい荷物を運ぶといった身体的な負担はかかりにくい職場が多いです。
大人数で働く場合もありますが、基本的に作業そのものはひとりで行うことがほとんどです。そのため、コミュニケーションが必要な仕事は避けたい人も、働きやすいでしょう。
- 体力に自信がある人
- 注意深くミスが少ない人
- 整理整頓が得意な人
シフト制で働ける4つの仕事
この章では、シフト制で働ける仕事について解説します。
仕事①飲食店

カフェや居酒屋などで、接客対応・調理・調理補助のいずれか、もしくは複数を担当する仕事です。
宿泊施設併設の飲食店のように早朝からの出勤が必要なお店もあれば、居酒屋やバーのように夕方以降に出勤できるお店もあります。
ご自身の生活習慣に遭った仕事場を探すようにしましょう。
業務内容は比較的簡単な場合がほとんどですが、スピード感を求められることがあります。
また、居酒屋などはにぎやかな雰囲気がほとんど。急かされることや雑音の多い環境が苦手な人は注意しましょう。
基本的には、応募時に接客か調理のいずれかを選べます。少しずつコミュニケーションに慣れていきたい人は接客、黙々と作業をしたい人は調理がオススメです。
- 自分の生活習慣に合った働き方をしたい人
- テキパキと作業することが得意な人
- 気遣いができる人
仕事②販売職
実店舗で商品説明やレジ係を行います。
昼間の時間帯を中心に、希望のシフトで働ける職場が多いです。そのため、柔軟なシフトで働きたい人にオススメです。
商品説明やお客さんの質問への対応など、コミュニケーションを取る機会は比較的多くあります。しかし、受け答えで伝える内容は、ある程度決まっています。
そのため、簡単な会話から始めることができるでしょう。
余裕が出てきたら、日常会話やお客さん一人ひとりに合った応答を心掛けてみてください。
商品について覚えることは多いかもしれません。先輩に聞きながら、少しずつ覚えていきましょう。
- 少しずつコミュニケーションに慣れていきたい人
- 身だしなみに気を遣える人
- 覚えることが得意な人
仕事③インストラクター

集団もしくは個別のクラスでヨガを教えたり、ジムの利用者にマシンの使い方や健康アドバイスをする仕事です。
インストラクター経験があるに越したことはないですが、採用後に研修を用意している職場では、未経験でも応募可能な場合もあります。
インストラクターとして知識や経験を積むなかで、自分自身の体調を整えていくことができるでしょう。
そのため、利用者の健康に貢献するだけではなく、自分自身の生活習慣改善やメンタル向上にもつなげられます。
利用者と話す機会が多いですが、個人レッスンや少人数のクラスをメインで行っている職場であれば、比較的プレッシャーを感じずに仕事がしやすいです。
- 心身の健康に興味がある人
- 体力がある人
- 人との接点を増やしたい人
仕事④介護職
介護施設利用者の食事や入浴など、日常生活をサポートする仕事です。
24時間スタッフが勤務している必要があるため、シフト制ではたらけます。
夜勤が発生する場合もあるため、希望の時間帯に固定で入るか相談してみることも可能でしょう。
一部の業務を除いて無資格・未経験でも働くことができ、正社員だけでなくアルバイト・パートの求人も豊富です。
いきなりフルタイムでの労働が心配な人は、アルバイトで短時間から勤務してみるといいでしょう。
- 体力がある人
- お世話をすることが好きな人
- 気配りができる人
ひきこもりの経験を活かせる2つの仕事
この章では、ひきこもりの経験を活かせる仕事について解説します。
仕事①NPO法人

ひきこもりや不登校状態にある人・孤立状態にある人への支援を行っているNPO法人では、ひきこもりの経験を活かして仕事に携わることができます。
例えば、相談員として相手の気持ちに寄り添ったり、広報担当として社会への啓蒙活動を行うなどです。
職員のなかには、自分と同じ経験を持つ人が比較的多いため、過去の経験について打ち明けやすく、気を遣われすぎる心配も少ないでしょう。
また、NPO法人は一般企業と比べ少人数体制の職場がほとんどです。
そのため、落ち着いた環境で働きながら、徐々に幅広い業務に携わっていくことも可能です。
- 気持ちに寄り添いたい人
- 人との繋がりを築きたい人
- 社会貢献をしたい人
仕事②塾講師
塾講師は、資格取得や受験に向けて勉強する生徒さんを対象に授業を行う仕事です。
学習塾のなかには、ひきこもりや不登校状態にある人に対応している場所もあります。
そうした環境では、勉強を教えるスキルだけではなく、メンタルサポートをするために生徒さんの心に寄り添おうとする姿勢も求められます。
ひきこもりを経験したあなただからこそ、分かり合える気持ちもあるはず。「分かってくれる人がいる」と思ってもらえるということは、生徒さんに安心できる居場所を作ることにもつながります。
塾講師は、教員免許がなくても働けますが、受験経験や資格合格経験が求められることがあります。
過去、学習を頑張った経験がある人は、チャレンジしてみてもいいかもしれません。
働きやすい時間帯で授業を設定できるので、自分の生活習慣に合わせて働けます。
ひきこもりや不登校状態にある人などを専門としている学習塾では、少人数制もしくは個別指導がほとんど。
そのため、大人数の前では緊張する人でも働きやすいです。
- 気持ちに寄り添いたい人
- 人の成長を見ることが好きな人
- 自分自身も成長していきたい人
ひきこもりから就職を成功させる4つのコツ
この章では、ひきこもりから就活を成功させるコツについて解説します。
コツ①規則正しい生活を送る

自分の生活習慣に合わせて働ける求人は豊富にありますが、定時制で午前中から夕方にかけての勤務を求める職場のほうが多いでしょう。
そのため、規則正しい生活習慣を身につけておくと、応募できる求人の幅も広がります。
さらに、生活習慣が整うことで疲れを感じにくくなり、健康的に仕事を続けやすいメリットもあります。
そのためには、まず睡眠時間を改善することを心がけてみてください。
生活習慣を改善できるか心配な人は、以下の方法を試してみてください。
すべて一気にやると体が順応せず疲れるかもしれないので、コツコツとできることからやっていきましょう。
- 食事は寝る前の2〜3時間前に終わらせる
- 寝る1〜3時間前に、38〜40℃の湯船に浸かる
- 就寝時刻の1時間前には、スマホやPCの使用を中止して照明を落とす
- 寝室は眠るためだけに使う
- 寝るときの服を決めておく
- 15分で入眠できないときはあえて一度起きる
- 寝不足のときは15〜20分間の昼寝をする
- 睡眠外来がある病院を受診してみる
コツ②身だしなみを整える
面接を受ける際、受け答えだけではなく身だしなみも非常に重要です。
身だしなみが整っていないと、実際の人柄に関係なく、「社会人としての最低限の常識がないのでは?」「信用できる人なのか?」など、ネガティブなイメージを持たれる恐れがあります。
化粧品メーカーである株式会社マンダムが行った調査によると、上場企業新卒採用担当者のうち93%が、「身だしなみから受ける印象は選考に大いに影響する」「やや影響する」と答えています。(参考:PR TIMES「「身だしなみは選考に影響」9割以上!面接で重要となるのは「礼儀」と「清潔感」 清潔感を感じ取るポイント1位は「髪型」」)
以下のポイントをチェックして、清潔感のある身だしなみに整えましょう。
- 髪を整える
- 爪を切る
- ヒゲを剃る
- 歯を磨く
- 口臭をケアする
- シワ・シミのない服を着る
- メイクはナチュラルにする
- 肌の調子を保つ
また、面接時の服装にも気を配りましょう。特に指定がない場合は、スーツを着用することが一般的です。また、対面面接、Web面接に関わらず、しっかりと身だしなみを整えることが大切です。
コツ③対人関係のリハビリをする

面接では、受け答えの明確さや質問の意図を読み取る力といったコミュニケーション能力を見られることがあります。
職場によっては、業務開始後は周囲との協力や協調性が重要となるでしょう。
そのため、就職活動を始める前に対人関係のリハビリを行っておくことがオススメです。
いきなり社会に出て人間関係を築こうとしても難しいかもしれません。同じ経験を持つ人とであれば落ち着いて話せるようであれば、自助グループやピアサポートを通じて、自分のことを相手に伝える練習をしてもいいでしょう。
以下のような場所でコミュニケーション研修やロールプレイを用いた対人関係の練習をすることができます。利用を検討してみてください。
- 精神科デイケア
- 地域若者サポートステーション
- 就労移行支援事業所
コツ④社会人としてのマナーを学ぶ
社会人としてのマナーが実践できるということは、周囲の人々と気持ちのよいコミュニケーションを取れるということ。社内で円滑な人間関係を築いたり、顧客の信頼を得るために非常に重要です。
社会人としてのマナーは、書籍を通じて学ぶことができます。図書館や本屋でマナー本を探してみるといいでしょう。
実際に練習を積み重ねたい人や分からない点を聞きたい人は、講座やセミナーを受けることをオススメします。以下の場所を利用すれば、社会人向けのマナー講座やセミナーを受講できます。
- 自治体の就業サポートセンター
- 求職者支援訓練
- 転職エージェント主催のイベント
- 地域若者サポートステーション
- 就労移行支援事業所
ひきこもり状態にある人が得意なことを見つけるために検討すべき3つのポイント
この章では、得意なことを見つけるために検討すべきポイントについて解説します。(参考:八木仁平『世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 人生のモヤモヤから解放される自己理解メソッド』)
ポイント①これまでの人生で充実していた体験は?

まずは、これまでの人生で充実していた体験を思い出してみましょう。充実といっても、誰もが憧れるような体験ではなく、心地がよいと思えた体験で十分です。
充実していると感じられる理由は、あなたが得意なことを無意識にやっていて、物事がスムーズに進みストレスが少ないからです。不得意なことをやっているときは、物事がうまく運ばないときのほうが多いでしょう。
どうして充実していると感じたのかを深掘りしてみると、自分の得意なことが見えてくるはずです。
ポイント②ほかの人がやっていると、イラッとする瞬間は?
ほかの人がうまくできていないとき、「どうしてこんなこともできないの?」「もう少し早くできると思う」と感じることはありませんか?
そう感じる理由は、ほかの人にとっては難しいけれど、あなたにとっては簡単にできることだからです。
そのようなことを仕事にすると、スムーズに働けるかもしません。
ポイント③周囲の人に自分の長所を聞くと、どんな答えが返ってくる?

得意なことは、普段自分が何気なくこなしていることかもしれません。そのため、自分では気づいていないけど、周囲の人が気づいている場合があります。
友人、家族や通院先の医師など、周囲の人にあなた自身の長所を聞いてみましょう。
ひきこもり状態にある人の履歴書の書き方
履歴書を書くときは、具体的かつ簡潔に伝えるようにしましょう。
採用側は、多くの就職希望者の書類を見ています。ほかの業務の合間に時間をつくって見ることも少なくありません。
具体的に書くことで納得感のある文章になり、簡潔に伝えることで「こちらの忙しい事情を汲んでくれている。他者視点で考えられる人かもしれない」という印象を与えられます。
以下のポイントを意識して、履歴書を書きましょう。
- 文字数の目安は、400字以内
- 決めたテーマに沿って、文章構造に当てはめながら作成する
- 「自分が採用側にアピールしたいこと」を、話の着地点にする
- アピールしたいことを証明できるような角度で、過去の経験を切り取る
- 「過去から学んだこと」、「今後どうしていきたいか」など、前向きな表現にして書く
- 一般的に伝わりやすい言葉で書く
- 専門用語は、できるだけ避ける。どうしても必要な場合は、補足説明を加える。ただし、短文で分かりやすく説明することが重要
- 数字で表せる実績があると、なおいい
自己PRや学生時代に頑張ったことなど、各項目の具体的な書き方は以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
ひきこもり状態にある人の面接対策

話すのが苦手でも、面接を上手くやることは可能です。
面接を受ける際も履歴書同様、具体的かつ簡潔に伝えることがオススメです。相手に好印象を与えるには、たくさん話すよりも、端的に話すほうが重要です。
1分間以上の話は、興味を強く引くような話し方でない限り、面接担当者を飽きやすくします。
そのため、就職希望者は、前もって、伝える内容を整理しておくとよいでしょう。
- 面接での一つの回答の目安は、20〜30秒。
- 「私」という主語で普段話さない人は、いつもの主語が出ないように気をつける。
- 会話のキャッチボールをして、面接相手とのやりとりの回数を増やせるようにする。
- 会話に余白を残しておく。余白を残して、相手が聞きたいことを聞いてもらうようにすると、採用側の質問の意図をあまり考えずにすむ。
- 聞かれたことだけに答える。そのため、結論を話すことが、もっとも重要になる。
- 結論以外の発言は、聞いてほしい端的な情報を、いくつかひそませておく。
- 面接相手に、自分が話したいことを聞いてもらえるようにする。
- 人間には元々、初対面の人を、見た目や声色で判断する傾向があるため、明るくハキハキ話したり、服装を整えることを意識する。
- 話す内容などに関しては、好印象の判断基準は、企業や面接相手の価値観によると意識する。
- いつもの話し方より、声の高さを上げる。
- 自分が伝えたいワードのときだけ、強調して言う。
- 言葉尻は、曖昧だったり早口になりやすいので、最後までゆっくりと言い切る。
- 声量を上げるのが難しい人は、話し方に工夫をする。
- 一般的に好印象なやり方がどうしても難しい場合は、第一印象に左右されにくい仕事を探す(スタートアップ企業、外資系企業など)。
- 障害者雇用での就職を目指すのであれば、話し方や表情などが障害由来の場合は、企業へ希望する配慮事項として伝える。
具体的な質問の答え方は、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
ひきこもり状態にある人が利用できる支援機関5選
この章では、ひきこもり状態にある人が利用できる支援機関を紹介します。
支援機関①就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。実際のサービスは、国の基準を満たしたさまざまな民間の就労移行支援事業所が行います。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
就労移行支援事業所は各地にあります。私たち、キズキビジネスカレッジ(KBC)もその一つです。それぞれ特徴が異なるため、気になるところがあれば問い合わせてみてください。
支援機関②ひきこもり地域支援センター
ひきこもり地域支援センターとは、ひきこもり状態にある人やその家族を支援するための公的な支援機関のことです。
家庭内で孤立している人や社会参加への不安を抱える人が再び自分の生活を取り戻せるように、本人だけでなくその家族もサポートできる体制が整えられています。(参考:厚生労働省「ひきこもりVOICE STATION」)
ひきこもり地域支援センターでは、社会福祉士や精神保健福祉士などのさまざまな専門家が支援コーディネーターとして相談支援などを行います。相談者が一歩ずつ社会復帰や生活改善を目指せるよう、個々の状況に応じた支援を受けることが可能です。
ひきこもり地域支援センターは、すべての都道府県・指定都市に設置されています。
支援機関③ハローワーク

ハローワーク(公共職業安定所)とは、仕事を探している人や求人を募集したい事業者に対して、就労に関連するさまざまなサービスを無償で提供する、厚生労働省が運営する支援機関のことです。正式名称は公共職業安定所で、職安と呼ぶ人もいます。(参考:厚生労働省「ハローワーク」厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」厚生労働省「公共職業安定所(ハローワーク)の主な取組と実績」、東京労働局「東京ハローワーク」、厚生労働省「こころの健康サポートガイド」、厚生労働省「ハローワークにおける障害者の就労支援」)
主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示などを行っており、具体的な支援内容は事業所によって異なりますが、一般的には以下のような幅広いサポートを行います。
全国に500ヶ所以上あり、主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示、雇用保険や雇用対策など、地域密着型の雇用に関する幅広いサポートを行います。
また、病気や障害のある人に向けたサポートも行っています。障害者手帳を所持していない人でも、医師による診断書があれば、障害の特性や希望職種に応じた職業相談や履歴書や面接での病気・障害の伝え方などのサポートを受けることができます。
支援機関④地域若者サポートステーション

地域若者サポートステーション(サポステ)とは、働くことに悩みを抱える15歳から49歳までの若者を対象とした厚生労働省委託の就労支援機関です。若者支援の実績やノウハウがある民間団体が運営しています。(参考:厚生労働省「地域若者サポートステーション」、「サポステ」)
2025年2月1日現在、全国177か所に設置されています。
支援機関⑤就職・転職エージェント
求職者に担当のスタッフがつき、条件や希望に合う求人を紹介してもらえたり、選考対策のサポートを受けられたりするサービスです。
企業がお金を払って利用するサービスなので、人を採用することにお金をかけられる企業やより積極的に人を採用したい企業の求人を紹介してもらえる可能性が高いです。
豊富な求人数から仕事を探したい人にオススメです。
受けられる支援はエージェントによって異なりますが、以下の支援を受けられることが多いです。
- 就職先に関する相談
- 非公開求人の紹介
- 履歴書の添削・面接の添削
- 面接後の企業からのフィードバックの共有
ひきこもりから就職をしたあとの相談先3選
仕事を見つけても、実際に継続的に勤務できるか不安な人もいるでしょう。
業務や対人関係で困ったことがあれば、ひとりで悩みを抱えなくても大丈夫。周囲のサポートを活用しながら、解決策を考えてみましょう。
この章では、就職をしたあとの相談先について解説します。
相談先①上司や同僚などの職場の人

職場で起きている悩みは、まずは同じ職場にいる上司や同僚などの職場の人に相談することをオススメします。
職場についてよく理解があり、あなたの悩みを知ることで必要に応じて気配りや手助けをしてくれることもあります。
以下のポイントを意識して、相談するようにしましょう。
- まずは時間があるかを確認する
- 何を聞きたいのか具体的に伝える
- 詳細は要所をまとめて簡潔に伝える
- 自分の考えも伝える
なお、解決策を相手に委ねることは避けましょう。人に聞くだけではなく、自分で考えることも大切だからです。
「私は〇〇だと考えていますが、どう思いますか?」と、自分の考えを伝えたうえで客観的な意見を求めることがオススメです。
相談先②労働条件相談ほっとライン
無理な残業を強いられている場合や賃金が未払いの場合など、労働基準関係法令に関する問題が発生している場合は、厚生労働省委託事業の「労働条件相談ほっとライン」を利用してください。
専門知識を持つ相談員が対応してくれます。電話で相談に応じてくれ、費用はかかりません。(参考:厚生労働省「労働条件相談「ほっとライン」(Working Hotline)」)
相談先③精神科・心療内科

勤務を続けるなかで、体調やこころに不調が現れた場合は、精神科もしくは心療内科を受診してみてください。
必要に応じて治療薬を処方してくれたり、求職・退職の診断書を作成してくれます。
仕事を始めてから通院をすることに抵抗がある人もいるかもしれません。
しかし、通院は恥ずかしいことやダメなことではなく、日常生活をスムーズかつ健康的に送る手助けを受けるためのものです。
医師の診断や手助けが必要な場合は、まずは一度現状を相談してみましょう。
【無料配布中!】『ひきこもりからの就職 完全マニュアル』
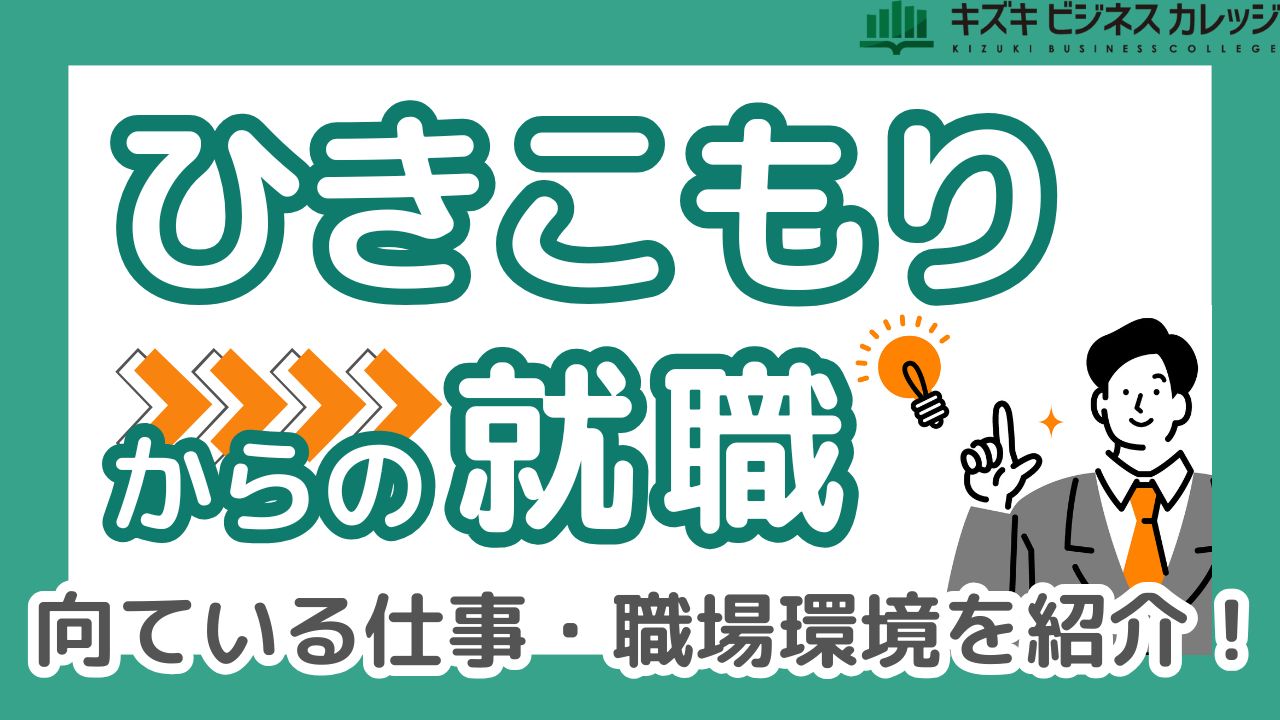
- 働きたいけど、外に出るのが怖い…
- 就職を考えているけど、何から始めればいいか分からない…
ひきこもり状態は決して珍しいことではなく、若者から中高年まで幅広い層に見られます。
精神的な不調や人間関係のトラブル、不登校経験など、さまざまな要因が絡み合い、一人での解決が難しいケースもあります。
本資料では、ひきこもり状態にある人が働くための4つの準備やひきこもり状態にある人に向いてる仕事・職場環境について詳しく解説しています。
ぜひ本資料を活用して、ひきこもり状態から一歩踏み出しませんか?
- ひきこもりとは?
- ひきこもり状態にある人が働くための4つの準備
- ひきこもり状態にある人に向いてる仕事・職場環境
- さまざまな働き方の選択肢
- ひきこもり状態にある人が再出発するための心構え
- ひきこもり状態から働くための1歩を踏み出したい人
- ひきこもり状態からの就職を考えているが、何から始めればよいか分からない人
- 外に出ることや人と接することに不安がある人
- 在宅でできる仕事や、自分に合った職場環境を探したい人
- ご家族がひきこもり状態にあり、支援方法を知りたい人
資料の入手方法
本資料は、以下のリンクから無料でダウンロードいただけます。
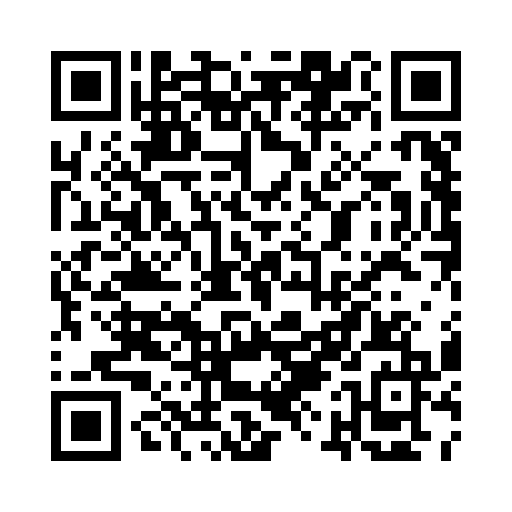
- リンクから申し込みフォームにアクセス
- 簡単なフォームに入力
- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り
- URLから資料を取得!
- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。
- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。
- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。
まとめ:ひきこもりから仕事を見つけることはできます

ひきこもりから仕事を見つけ、継続的に働くことは可能です。
しかし、自分にあわない職場を選ぶと、すぐに辞めたくなったり自信をなくすかもしれません。
また、ひとりで悩みを抱えていると、体調を崩すこともあります。
まずは、自分にあった働き方や職種を整理することからはじめてみましょう。就職活動に不安がある人やアドバイスが欲しい人は、支援機関を活用してみてください。
就業開始後もひとりで悩まず、上司や同僚などの職場の人、もしくは支援機関を頼ることが大切です。
そうすることで、少しずつ仕事に慣れていけるはずです。
ひきこもり状態から仕事を見つけられますか?
今あなたがひきこもり状態にあっても、「仕事を見つけられない」と諦める必要はありません。世間には、たくさんの仕事や働き方があります。ひきこもり経験がある人を求めている会社もあれば、リモートワークやシフト制など自分に合った働き方ができる職場もあります。
詳細については、こちらで解説しています。
ひきこもり状態にある人が自分に合う仕事を見つける方法を教えてください。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→