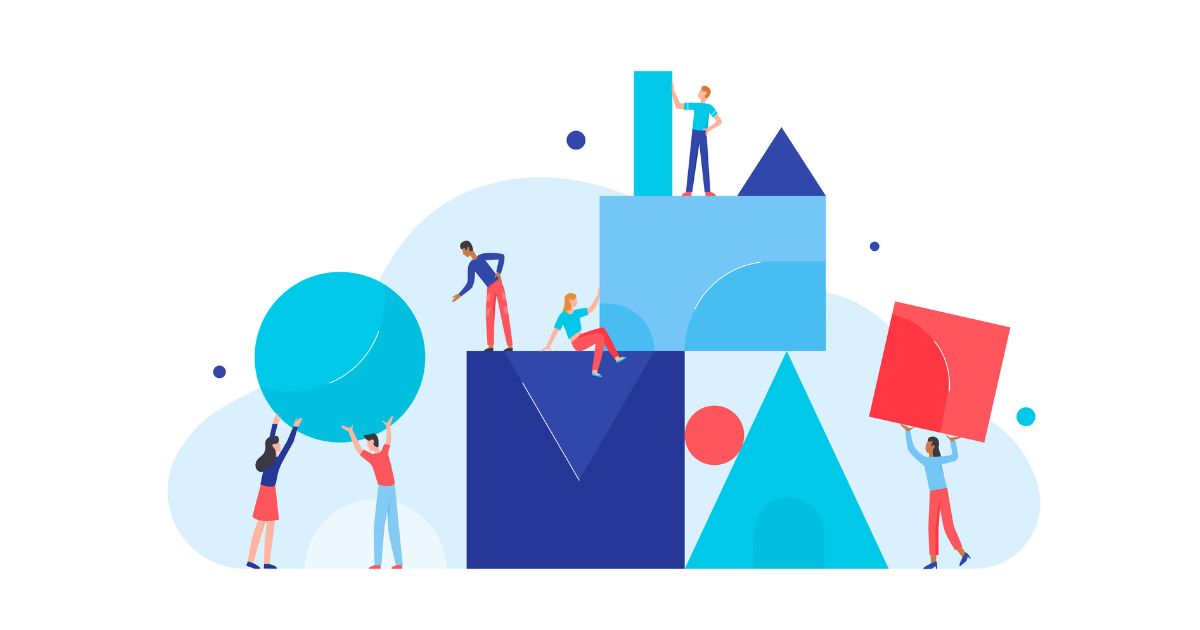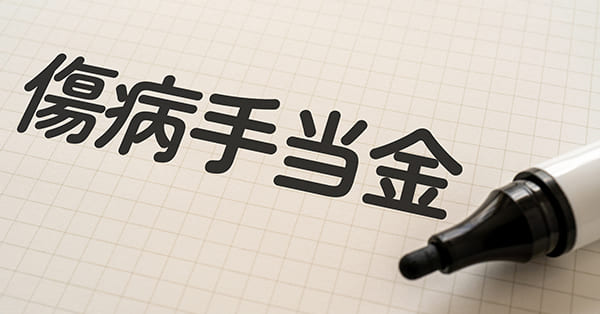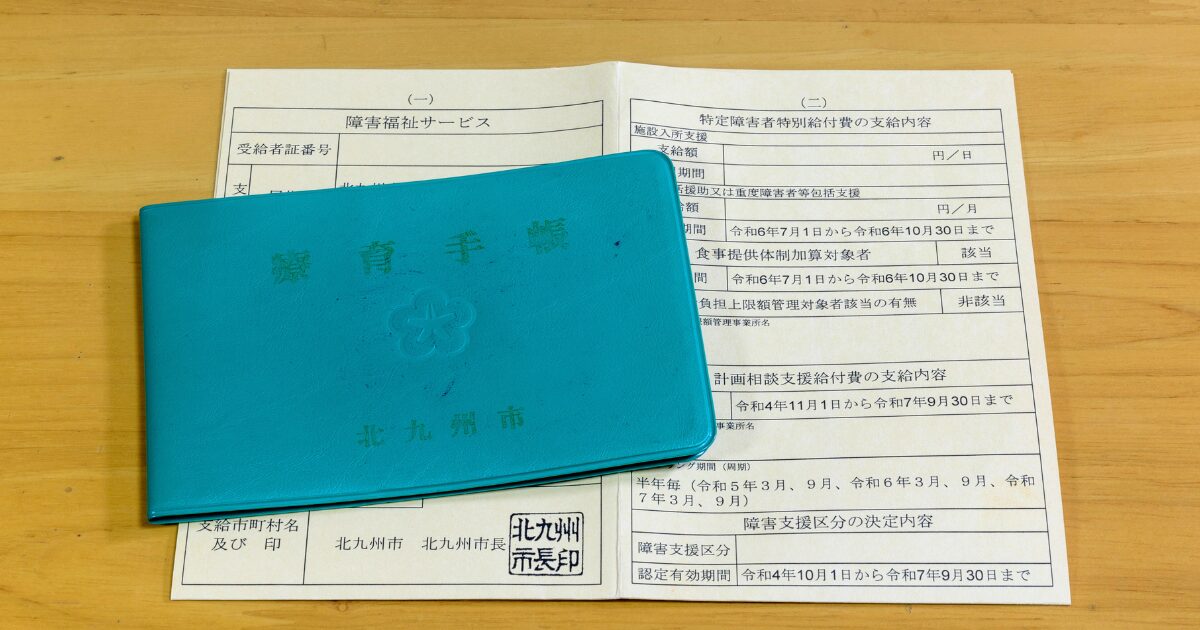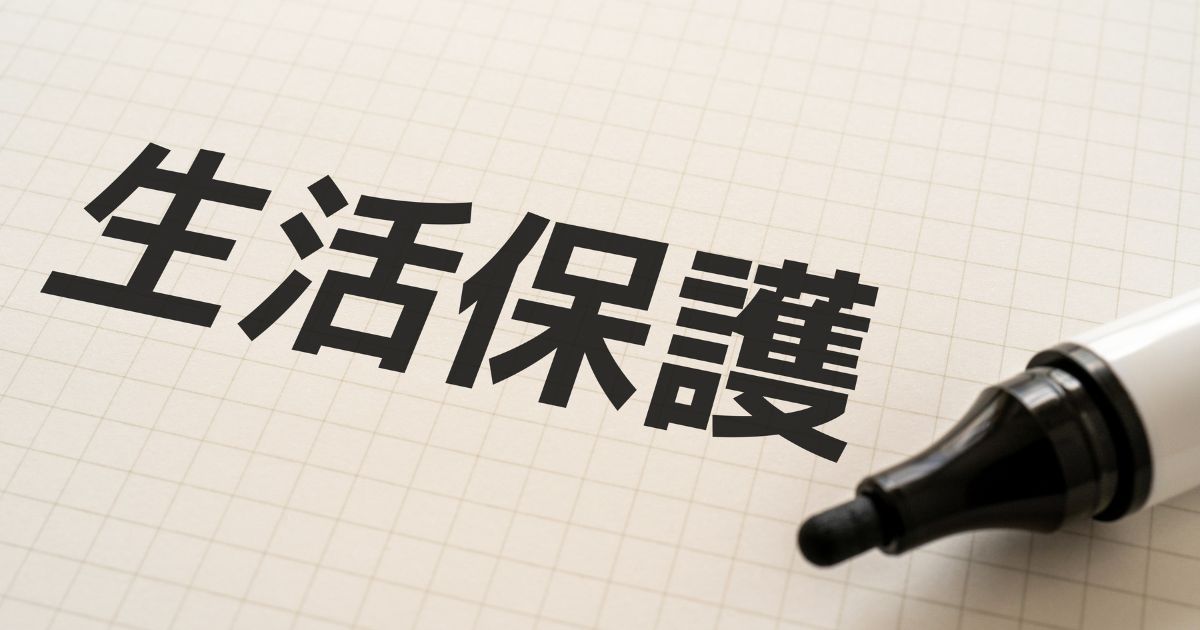障害者雇用で働くメリット デメリット・注意点について解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
障害者雇用で働くことを考えているあなたは、以下のような疑問や不安を感じているのではないでしょうか?
- 障害者雇用で働くとどんなメリットがある?
- デメリットがないか心配…
- 実際に障害者雇用で働くためにはどうすればいい?
このコラムでは障害者雇用で働くか悩んでいる人に向けて、障害者雇用のメリットやデメリット・注意点、障害者雇用で働くための流れについて解説します。
あわせて、企業が障害者雇用を行うメリットや利用できる助成金を紹介します。
あなたの障害特性に合った働き方を探す参考になれれば幸いです。
さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、障害者雇用での就職を考えている人に向けて、「障害者雇用 面接対策ガイドブック【完全保存版】」の無料配布を開始いたしました。
障害者雇用の面接で頻出する40以上の質問、それぞれの質問への解答例、好印象を与えるポイントなどを、わかりやすく丁寧に解説しています。
ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。
また、障害者雇用の面接対策については、については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。
障害者雇用で働くことを検討しているあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
障害者雇用とは?

障害者雇用とは、身体障害、精神障害を問わず、障害のある人を対象とした雇用枠を設けて雇い入れる制度のことです。障害の特徴や内容、個々の能力などに合わせて、安心して働けるようにすることを目的としています。
障害のある人でも、個々の能力や特性に応じて会社側の配慮を受けながら、安定的に働けるようにすることを目的としています。会社側としては、規模に応じて雇う必要があり、会社の成長に沿って障害者雇用による採用も増加しています
障害者雇用で働く4つのメリット
この章では、障害者雇用で働くメリットについて解説します。
メリット①労働時間を調節しやすい

1つ目のメリットは、労働時間を調節しやすいことです。
障害者雇用の場合、一般雇用においてフルタイムと呼ばれる、1日8時間労働・週40時間労働と比べると、短い労働時間に設定されている場合が多いです。
厚生労働省が行った調査によると、1週間あたりの労働時間は以下のとおりです。(参考:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」)
- 週30時間以上:約56.2%
- 週20時間以上、週30時間未満:約29.3%
- 週20時間未満:約11.1%
また、週5日働くことが難しい場合には、週3日など調整がしやすい傾向にあります。
加えて、その日の体調に合わせて、短時間勤務にしたり早退したりするなど、融通を利かせることができるというメリットもあります。
メリット②配慮を受けられる
2つ目のメリットは、配慮を受けられることです。
こちらで解説した労働時間の調整も含めて、障害の特性に配慮した業務や職場環境に配慮した配属がされることがあります。
例えば、聴覚過敏の症状で騒がしい職場や聞き取りが苦手という人であれば、その旨を申告することで静かなオフィスに配属されたり、電話応対を業務から除外できたりします。
ほかにも、ASDやADHDなどの発達障害のある人であれば、過集中によって疲れすぎないように休憩の時間を設けることができたり、残務がなくなるような配慮を受けたりできます。
こうした業務内容や配属先への配慮は職場定着に関わるため、大きなメリットと言えるでしょう。
メリット③支援機関と就職先が連携したサポートを受けられる

3つ目のメリットは、支援機関と就職先が連携したサポートを受けられることです。
例えば、障害者の就労に関する福祉サービスに、就労移行支援というものがあります。
就労移行支援では、就職までのサポートを行うとともに、就職後の定期面談を含む職場定着支援を行っています。
こうしたサポートの有無によって、職場定着率が大きく変わってきます。
実際に、支援機関によるサポートによって、職場定着率が約20%もあがるという調査結果も出ています。(参考:障害者職業総合センター「障害者の就業状況等に関する調査研究」)
メリット④障害年金を受給しながら働ける
条件付きではありますが、障害年金を受給しながら働ける点も、1つのメリットとして挙げられるでしょう。
障害年金とは、病気やケガ、障害などによって仕事や生活などに支障を生じている場合に、年金加入者が受給できる支援制度のことです。(参考:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」、日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」、日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」、日本年金機構「国民年金」、日本年金機構「障害年金ガイド令和5年度版」、日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」)
厚生労働省の発表によると、障害年金を受給している人のうち約34.0%が就業しています。(参考:厚生労働省「年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)令和元年」)
つまり、3人に1人程度は、働きながら障害年金を受給しているということです。
通常の給料にくわえて障害年金も受給できれば、生活や精神の安定につながるでしょう。
ただし、障害年金の申請時には就労状況も確認されます。就労して十分な給料を稼いでいると、日常生活を送れる能力があるため支給は不適切と判断される場合がある点は覚えておきましょう。
障害年金については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
障害者雇用で働く3つのデメリット・注意点
この章では、障害者雇用における以下のデメリット・注意点について解説します。
注意点①賃金が少ない可能性がある
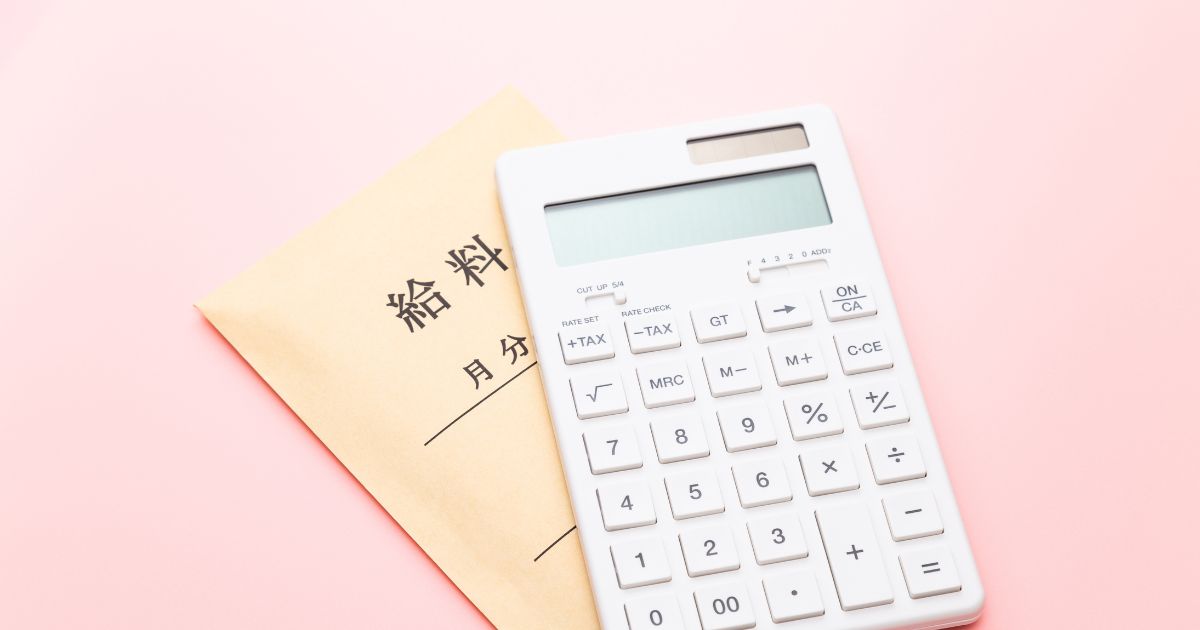
1つ目の注意点は、賃金が少ない可能性があることです。
障害者雇用で働く場合、労働能力によっては、最低賃金額の減額特例措置によって受け取れる賃金が少なくなる可能性があります。(参考:厚生労働省「最低賃金法第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可制度について」)
しかし、厚生労働省の発表によると、以下のように2018年と2023年の平均賃金を比較すると、増加していることがわかります。(参考:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」)
- 身体障害者:約21万5000円
- 知的障害者:約11万7000円
- 精神障害者:約12万5000円
- 発達障害者:約12万7000円
- 身体障害者:約23万5000円
- 知的障害者:約13万7000円
- 精神障害者:約14万9000円
- 発達障害者:約13万円
このことから、将来的にはさらに賃金が改善されていくかもしれません。
また、賃金は職種や企業によって大きく異なるため、就職活動中に雇用条件などをしっかりと確認しておくことが大切です。
注意点②正社員募集が少ない
2つ目の注意点は、正社員募集が少ないことです。
障害者雇用の求人は、正社員以外の雇用形態が多い傾向にあります。例えば、パートタイムやアルバイト、契約社員などが挙げられます。
また、そもそも障害者雇用の求人数が少ないということもあります。
例えば、求人サイト「求人ボックス」で「正社員/東京都」という条件で検索すると、2023年11月2日時点で、159万6584件の求人情報がヒットします。
それに対し、先ほどの条件に障害者採用の求人という条件を追加した場合には、同時点で、求人情報の数は2599件となります。
一般雇用に比べて、障害者雇用の数はまだまだ少ないというのが現状です。
しかし、障害者雇用での求人数自体は年々増えてきています。
また、パートタイムやアルバイト、契約社員などで働き始めた場合でも、正社員登用制度を導入している企業もあるため、正社員になれる可能性はあります。
注意点③職種の選択肢が比較的少ない

最後の注意点は、職種の選択肢が比較的少ないという点です。
障害者雇用での職種は、定型的な一般事務が多い傾向にあります。
反対に営業職や総合職など、機動力や柔軟性を求められる職種の求人は、一般事務と比較すると少ないということは、覚えておいた方がよいでしょう。
例えば、障害者向けの転職サービス「dodaチャレンジ」には1429件の公開求人が掲載されていますが、その大半が事務系職種であり、2023年11月2日時点で、その割合は約71%です。
また、求人数や職種が限られるということは、仕事のキャリアを積み上げていく際のデメリット・注意点にもつながります。
障害者雇用で働く流れ
この章では、筆者の経験談を交えながら、障害者雇用で働く流れについて解説します。
流れ①心療内科などで診断書を受けとる

まずは、心療内科などを受診して、診断書を受け取りましょう。
ある人に障害者雇用を適用できるかどうかは、実態として、障害者手帳を所持しているかどうかで判断します。(参考:厚生労働省「障害者手帳について」)
そして、障害者手帳の取得には、医師の診断書が必要になるため必ず受診してください。
障害者手帳とは、一定以上の障害のある人に交付される手帳のことです。
障害者手帳を所持することで、障害があることの証明が可能です。障害者手帳を所持する人は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の対象として、さまざまな支援を受けられます。(参考:厚生労働省「障害者手帳について」、e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
障害者手帳の概要や取得する流れなどについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
流れ②自治体の役所や支援機関に相談する
次に、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に相談しましょう。
役所に相談することで、障害者雇用で働くために受けられる支援や、支援を行っている機関の情報を得られます。また、障害者手帳の取得についても話を聞けるでしょう。
また、役所以外にも障害者雇用について相談できる支援機関があります。例えば、以下のような支援機関です。
- ハローワーク
- 障害者職業センター
- 就労移行支援事業所
ハローワークでは、傷病手当金や失業保険や障害年金などの説明や障害者雇用の求人票を確認できます。
また、今後利用する支援機関をどう選んだらいいかなどの相談もできます。
地域障害者職業センターでは、訓練や座学を受けて、現時点での職業能力の評価を受けることができます。評価次第では、すぐにでも就職活動に移っても良い場合もあります。
就労移行支援事業所は、障害や病気の症状にともなう体調のコントロールや働くための新たなスキルの習得などを目的に利用できます。
就労移行支援事業所は雰囲気などさまざまです。ネットでの情報収集や見学などを重ねて自分に合った事業所を探しましょう。
それぞれの支援機関については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
流れ③障害者雇用に関する情報を収集する

支援機関に相談することも大切ですが、自分自身で障害者雇用に関する情報を集めることも大切です。
基本的には、インターンシップや説明会などに参加して情報収集を行います。
最近ではオンラインで実施されるインターンシップや説明会もあるため、障害の特性として外出が苦手な人でも気軽に参加できるでしょう。
実際にインターンシップや説明会に参加することで、障害者雇用への理解が深まることはもちろん、企業ごとの雰囲気や業務内容、雇用条件などの情報も得られます。
なお、就労移行支援事業所でも情報収集が可能です。キャリア面談を通して相談をしたり、過去の経験から自分に合った職種や企業についてもアドバイスを得られるはずです。
そのほかにも、利用しているハローワークや就職エージェントなどで求人情報を閲覧するのもよいでしょう。気になった会社で障害者雇用を募集していないかを確認してみてください。
流れ④自己分析する
ある程度、障害者雇用に関する情報収集ができたら、自己分析を行いましょう。
まず、障害者雇用で働くにあたって、何が課題になるのか、職場側に配慮してほしいことは何かを整理しましょう。
例えば、こちらで解説した労働時間の調節を1つ取っても、1週間に勤務できる日数や1日当たりの希望の勤務時間、通院のための半休や休暇はどの程度必要か、などを整理しておく必要があります。
反対に、得意なことや配慮が必要ない部分についても、しっかりとまとめておくと、履歴書の作成や面接の際に役立ちます。
ほかにも、障害者雇用かどうかにかかわらず、自分に向いている職種は何か、どんな社風の企業であれば働きやすいかなどについても、自分の性格や価値観などと照らし合わせて考えておきましょう。
流れ⑤スキルを獲得する

就職活動を行うにあたって、自分のスキルが足りないと感じるのであれば、スキルを獲得する必要があるでしょう。
スキル獲得を目指す場合は、地域障害者職業センターや就労移行支援事業所などの支援機関の利用がオススメです。
地域障害者職業センターと就労移行支援事業所は、どちらも自己分析やスキル獲得が可能です。
特に、就労移行支援事業所では、スタッフへの相談、スキルチェックの依頼が可能なため、1人で勉強する事が苦手という人にオススメです。
また、体調のコントロールや自己理解などについても学べます。
ただし、就労移行支援事業所の利用期間は、原則2年間なので、計画的に利用しましょう。各支援制度については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
流れ⑥就職活動を行う
情報収集や自己分析、スキルの獲得などがひと段落したら、実際に就職活動を行っていきます。
就職活動を行う場合も支援機関の利用がオススメです。
例えば、就労移行支援事業所を利用すれば、履歴書の添削や面接練習、インターン・職場体験先の紹介、職場探しの手伝いなど、幅広いサポートを受けられるためです。
また、障害者雇用で働くかどうかを迷っている場合も、相談できます。障害者雇用か一般雇用か、正規雇用か非正規雇用か、オープン就労かクローズ就労かなど、幅広く相談ができます。
ただし、就労移行支援事業所を利用しない場合でも、就職活動を進められます。
ハローワークを利用して障害者雇用の求人を紹介してもらい面接を受けたり、障害者雇用に特化した転職エージェントを利用したりするなど、方法はたくさんあります。
就職活動は、精神的にも身体的にも大きな負担がかかります。ぜひ、自分自身が安心して前向きに取り組める方法を見つけた上で、就職活動に取り組みましょう。
流れ⑦採用後は職場定着支援を利用する

採用後は職場定着支援を利用することをオススメします。
職場定着支援とは、病気や障害のある人が、就労先の労働環境や業務内容に順応し、長く働き続けられるようにサポートする制度のことです。
障害者雇用で働く人に就職後の不安に対するアドバイスを行ったり、場合によっては企業側に働きかけて働きやすい職場作りのサポートを行ったりします。
また、似た制度として、ジョブコーチ制度があります。
こちらは障害者職業センターや就労移行支援事業所などから依頼する場合もあれば、企業に在籍している場合もあります。
職場定着支援と似ていますが、サポート内容は職場適応に特化しています。各支援制度については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
企業が障害者雇用を行うメリット

企業が障害者雇用を行うメリットは、以下のとおりです。
- 施設や設備を改善するための経済的サポートを受けられる
- 会社のCSRやダイバーシティ実現
- これまで顕在化していなかったニーズに気づく
- 職場のコミュニケーションやモチベーションが高まる
企業が障害者雇用を行うメリットについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
障害者雇用を行う企業が利用できる助成金10選
障害者雇用を行う企業が利用できる助成金は、以下のとおりです。
- トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- 障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)
- 障害者作業施設設置等助成金
- 障害者福祉施設設置等助成金
- 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
- 障害者介助等助成金
- 職場適応援助者助成金(障害者職場適応援助コース)
- 重度障害者等通勤対策助成金
- 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
加えて、障害者雇用をサポートする支援機関もたくさんあるため、障害者雇用を始めようと考えている場合は、支援機関に相談することをオススメします。
企業が障害者雇用を行うメリットや支援機関については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
【無料配布中!】障害者雇用 面接対策ガイドブック
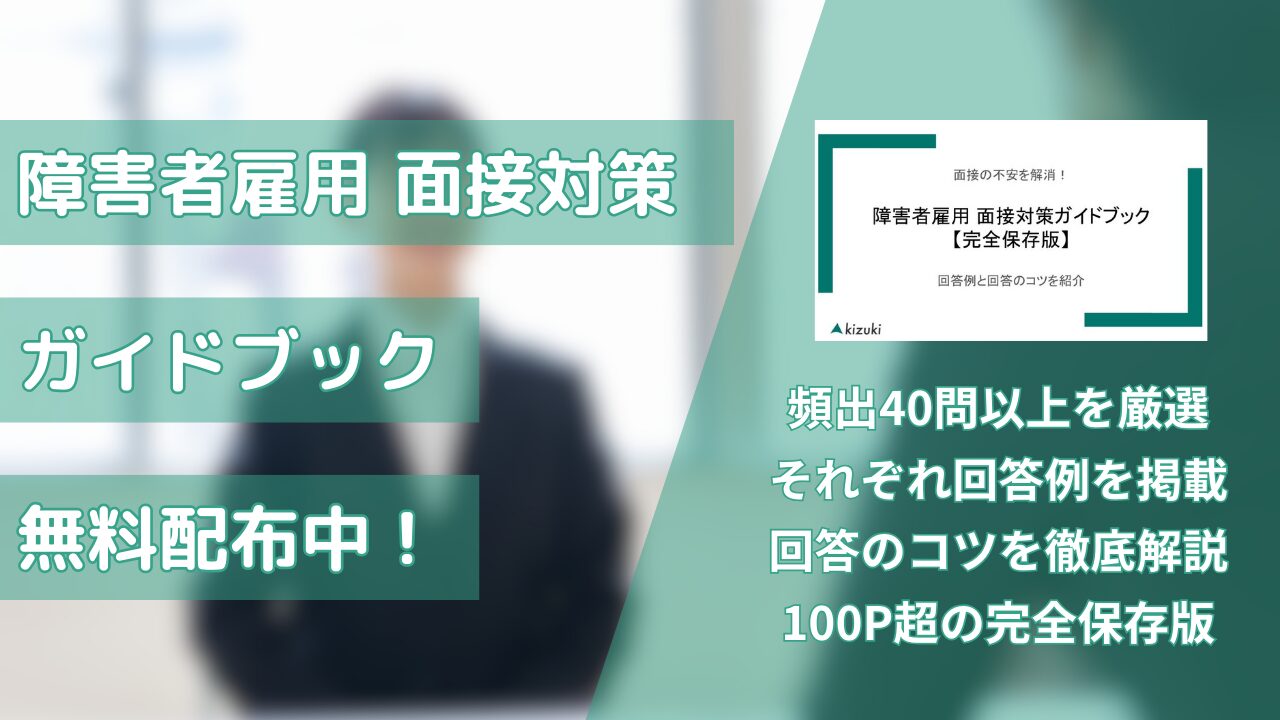
- 障害者雇用での就職を検討しているけど面接が不安…
- 面接で特性や症状についてうまく説明できる自信がない…
このように、障害者雇用を検討している人の中には、面接に対する不安を抱えている人が少なくありません。
また、事前に回答を用意しようと思っていても、どんなことを聞かれるかわからなかったり、どのように答えればよいか迷ったりすることもあるでしょう。
さらに、面接の際に特性や症状について詳しく伝えられていないと、入社後に必要なサポートを受けづらくなる可能性も考えられます。
本ガイドブックでは、障害者雇用の面接でよく聞かれる質問40問以上を厳選し、キズキビジネスカレッジ(KBC) の知見をもとに、それぞれの回答例と回答のコツを詳しく解説しています。
「障害者雇用 面接対策ガイドブック」を活用し、自信を持って面接に臨みましょう。
- 障害者雇用の面接で頻出する40問以上を厳選
- 8つのカテゴリーから紹介
- 回答例を掲載し、どのように答えればよいかが明確
- 回答のコツ付きで、面接官に好印象を与えるポイント、採用につながる伝え方を解説
- 障害者雇用の面接が初めてで、どのように答えればよいか分からない方
- 面接で緊張しやすく、自信を持って話せるようになりたい方
- 過去の面接で苦戦した経験があり、改善したいと考えている方
- 採用を目指し、より効果的な面接対策を行いたい方
- 障害があることをどう伝えればよいか迷っている方
- リンクから申し込みフォームにアクセス
- 簡単なフォームに入力
- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り
- URLから資料を取得!
- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。
- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。
- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。
また、障害者雇用の面接対策については、については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ:障害者雇用は働き方の1つです

障害者雇用は働き方の1つであり、働くことへの不安や悩みを軽減できるなどのメリットがある働き方です。
一方で、障害者雇用で働く場合の注意点は、事前にしっかりと理解しておく必要があります。
実際に障害者雇用で働くかどうかは、自分1人で決める必要はありません。ぜひ主治医やカウンセラー、支援機関に相談しながらを考えていきましょう。
読者の皆様がより良い人生を歩めるよう願っております。
障害者雇用とは、何ですか?
障害者雇用とは、身体障害、精神障害を問わず、障害のある人を対象とした雇用枠を設けて雇い入れる制度のことです。障害の特徴や内容、個々の能力などに合わせて、安心して働けるようにすることを目的としています。
詳細については、こちらで解説しています。
障害者雇用で働くメリットを教えてください。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→