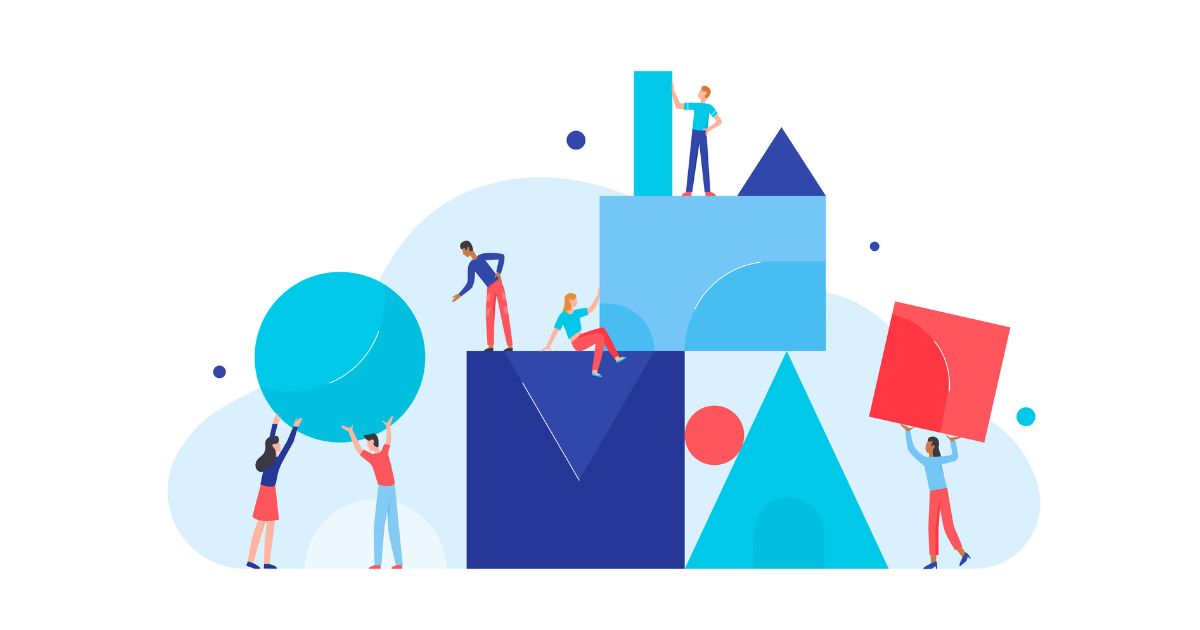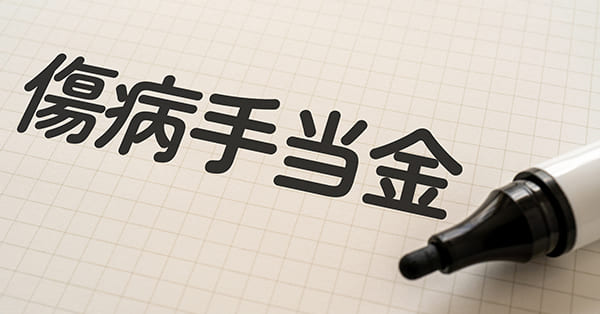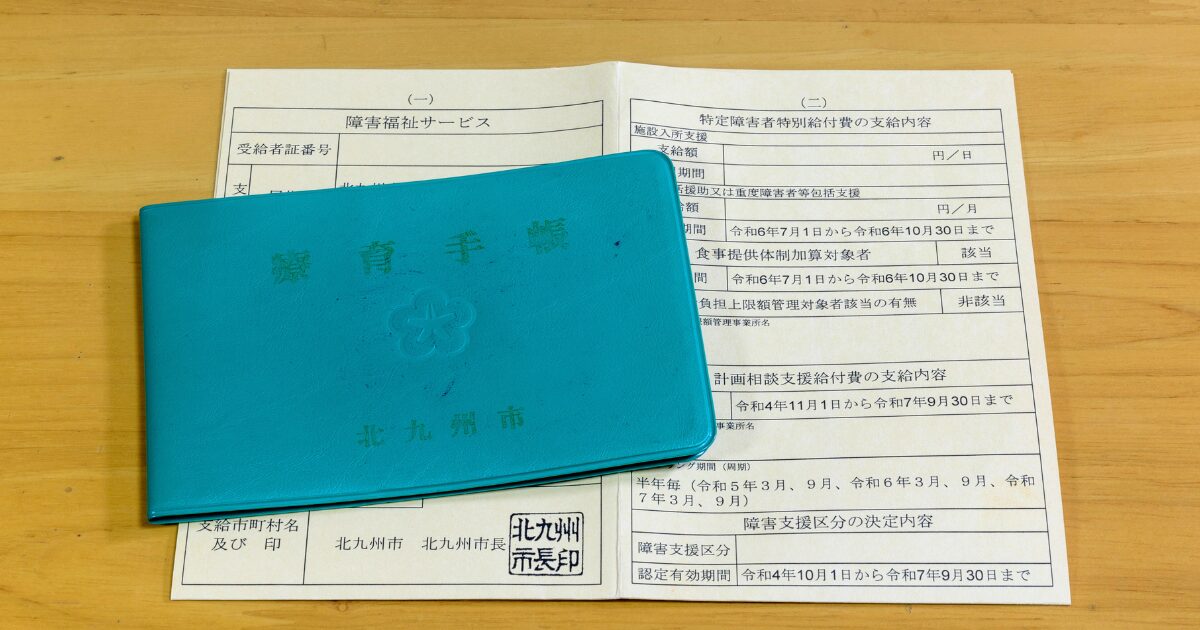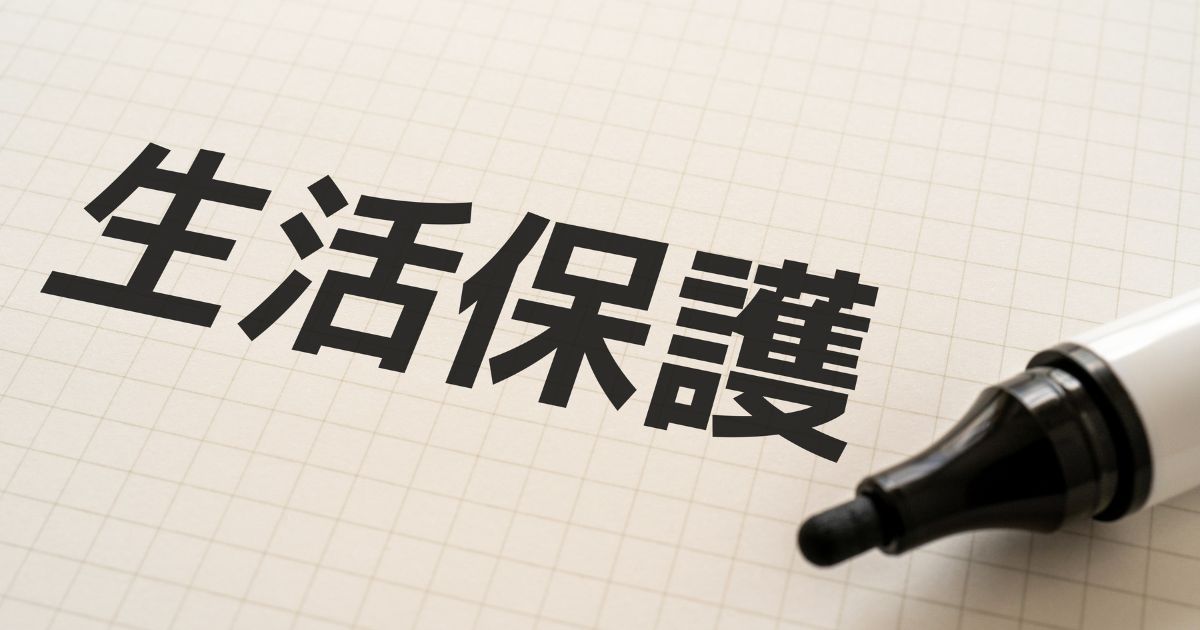労災保険のメリットとは? 補償内容や注意点を解説

こんにちは。キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
労働災害のリスクが比較的高い職種の人にとって、労災保険の内容や対象範囲は気になるのではないでしょうか?
労災保険は雇用されて働く人であれば、雇用形態を問わず利用できます。ただし、事業者の手続き状況によっては利用できないケースもあるため、事前に確認が必要です。
このコラムでは、労災保険の概要やメリット、受給対象者、種類、受給金額、期間などについて解説します。
労災保険について知って万が一に備えたい人は、ぜひ参考にしてください。
労災保険の利用を検討しているあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
労災保険とは?
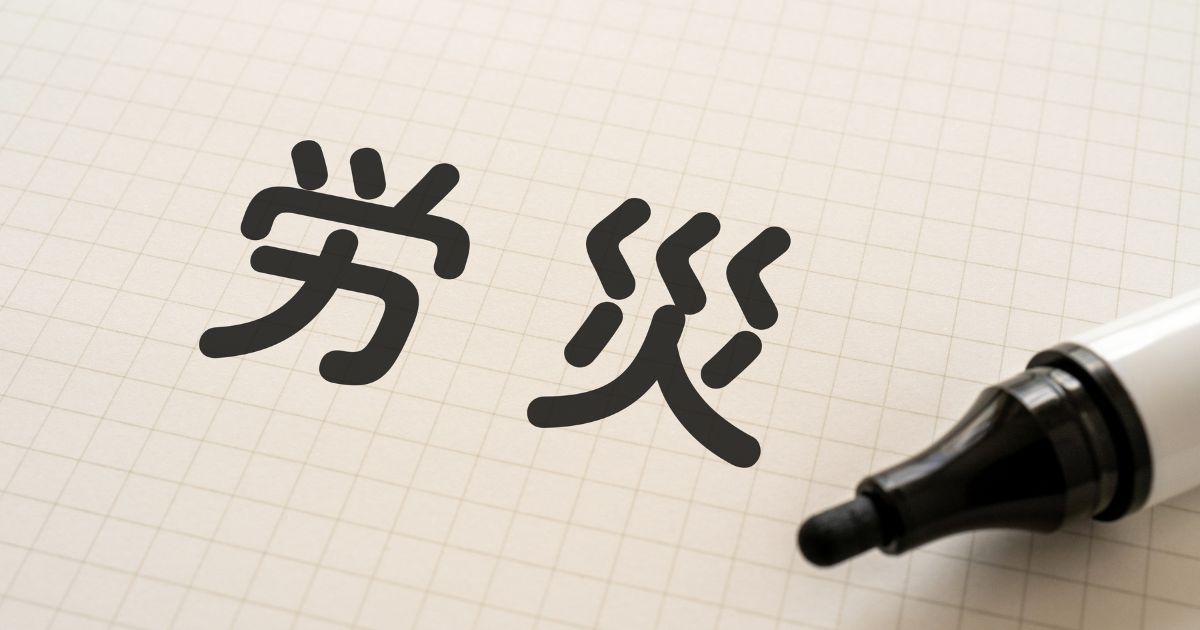
労災保険(労働者災害補償保険)は、業務中または通勤中に発生した病気やケガ、障害などの労働災害に対して保険給付を行い、対象者の社会復帰を促すための支援制度のことです。
一人でも労働者を雇用している事業では、業種や会社の規模を問わず加入義務があります。ただし、労災保険の加入義務が生じるのは、主に従業員や被雇用者です。事業主や役員などは、任意で加入します。(参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労災保険給付の概要」、厚生労働省「労働保険とはこのような制度です」、厚生労働省「労災補償」)
労災保険の受給対象者
万が一のときに労災保険の給付を受けられるのは、従業員を一人でも雇用している事業所に勤める労働者です。つまり、雇用されて働いている人で、通勤中・業務中に負傷した人や、病気や障害を発症した人などは受給対象となります。(参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労災保険給付の概要」、厚生労働省「労災補償」)
労働災害が発生したときは、労働者の雇用形態や就業形態を問わず労災保険を利用できます。
労災保険が適用される労働災害の種類
この章では、労働保険が適用される労働災害の種類について解説します。
種類①業務災害

業務災害とは、業務を原因として被った病気やケガ、障害または死亡などの労働災害のことです。
業務災害と判断されるには、以下の条件を満たしている必要があります。 (参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労災保険給付の概要」)
- 労災保険が適用される事業場に雇われている
- 事業主の支配下にあるとき
- 業務が原因
ただし、業務上の負傷において以下のケースは対象外となります。あらかじめ、よくチェックしておきましょう。
- 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、または業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それが原因となって災害を被った場合
- 労働者が故意に災害を発生させた場合
- 労働者が個人的な恨みなどによって、第三者から暴行を受けて被災した場合
- 地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などによって、天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められる)
種類②複数業務要因災害
複数業務要因災害とは、事業主が異なる複数の事業場で働く労働者に適用される病気やケガ、障害または死亡などの労働災害のことです。 (参考:福井労働局「【労災補償課】労災認定の考え方(業務災害・複数業務要因災害・通勤災害)」)
複数業務要因災害と判断する際は、業務上の負荷を総合的に評価します。2つ以上の事業場の業務が要因と判断されれば、複数業務要因災害です。一方、1つの事業場の負荷が要因と判断される場合は、こちらで解説した業務災害に該当します。
なお、労働者として就業しつつ、同時にフリーランスや業務委託などの働き方で就業している人の場合、複数事業労働者には該当しません。また、転職などで複数の事業場に同時に使用されていない人についても複数事業労働者には該当しません。
種類③通勤災害

通勤災害とは、通勤時に被った病気やケガ、障害または死亡などの労働災害のことです。
ただし通勤は、就業に関して以下の移動を、合理的な経路および方法で行うことと定められています。 (参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労災保険給付の概要」)
- 住居と就業の場所との間の往復
- 就業の場所からほかの就業の場所への移動
- 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
ただし、通勤時に逸脱や中断をした場合、その時間とその後の移動は通勤とはみなされないため注意しましょう。例えば以下などのケースは、補償対象外です。
- 退勤後の就業の場所から居酒屋への移動
- 通勤前に映画鑑賞をした映画館から就業の場所への移動
補足:第三者行為災害
第三者行為災害とは、労災保険給付の原因となった災害の原因が第三者の行為にあるときに認められる労働災害のことです。(参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労災保険給付の概要」)
- 通勤途中に交通事故に巻き込まれる
- 建設現場からの落下物に当たって怪我をする
第三者行為災害が生じた際には、通常の労災保険給付書類にくわえて、第三者行為災害届などの関係書類も提出する必要があります。
労災保険を受給する4つのメリット
この章では、労災保険を受給するメリットについて解説します。
メリット①保険給付を受け取れて金銭的な負担を軽減できる

労災保険は、万が一のときに受け取れる支援制度です。傷病の治療費に充てられるほか、休業中や、障害が残った際の収入を補填するためにも役立つでしょう。
とくに治療費に関しては、全額が補償されるのが大きな特徴です。治療が長期化したり後遺症が生じたりした場合でも、金銭的な負担・不安が軽減され、回復に専念できるでしょう。
メリット②過失割合に影響されず保険給付を受け取れる
労災保険は、業務中だけでなく通勤中にも適用されます。通勤中に交通事故が発生しても、労災保険で治療費を全額補償してもらえるでしょう。
例えば、自賠責保険や任意保険で対応すると、過失の割合に応じて補償額が減る可能性があります。また上限金額までしか補償されず、自己負担分が生じる可能性もあるでしょう。しかし、労災保険を利用すれば過失割合や上限金額を考慮せずに済みます。
メリット③社会復帰促進等事業を利用してスムーズな復帰を目指せる

労働災害後には、必要に応じて、労災保険の社会復帰促進等事業を利用できます。
社会復帰促進等事業には以下のような事業があり、再手術費用、補装具購入費用の支給や賃金補填など、さまざまなサポートが行われています。(参考:厚生労働省「社会復帰促進等事業」、厚生労働省「社会復帰促進等事業の一覧」)
- 外科後処置等経費
- 義肢等補装具支給経費
- 特殊疾病アフターケア実施費
- 社会復帰特別対策援護経費 など
メリット④被災労働者等援護事業を利用して家族へのサポートも受けられる
労働災害に遭ったあとは、労働者の家族は被災労働者等援護事業を利用できます。介護料や就学経費など、さまざまな支援を受けられます。(参考:厚生労働省「社会復帰促進等事業の一覧」)
- 労災就学等援護経費
- 労災ケアサポート事業経費
- 休業補償特別援護経費
- 長期家族介護者に対する援護経費 など
労災保険の種類・受給金額・期間
この章では、労災保険の種類とそれぞれの受給金額・期間について解説します。
(参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労災保険給付の概要」 厚生労働省「7-5 労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか。」)
種類① 療養(補償)等給付

療養(補償)等給付とは、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害で負った傷病で療養するときに受けられる給付金のことです。
労災病院や労災保険指定医療機関などで療養する場合は、必要な療養の給付が受けられます。そのほかの機関で療養する場合も、療養費用の受給が可能です。また療養するために通院したときには、通院費用も支給される場合があります。
受給期間に上限は設けられていないため、療養が長期化しても、安心して治療に専念できるでしょう。
ただし、療養費用が生じた翌日から2年後に請求の時効が設けられています。その間に手続きしなければならない点に注意しましょう。
種類② 休業(補償)等給付
休業(補償)等給付とは、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害で負った傷病が原因で労働できず、賃金を得られないときに受けられる給付金のことです。
給付金を受け取れるのは休業4日目以降で、1日ごとに労働基準法の平均賃金に相当する額である給付基礎日額の約60%相当の給付を受け取れます。
休業等給付が打ち切られることはありませんが、受給して1年6か月目以降は、こちらで解説する傷病等年金へ移行することに留意しましょう。
また、請求権が発生した翌日から2年時点に請求時効が設定されているため、それまでに手続きが必要です。
種類③ 障害(補償)等給付

障害(補償)等給付とは、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害で負った傷病が治癒・症状固定したのちに、障害が残ったときに受けられる給付金のことです。
障害等給付には、障害(補償)等年金と、障害(補償)等一時金の2種類があります。
障害等年金とは、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害で負った傷病が治癒・症状固定したのちに、障害等級第1〜7級に該当する障害が残ったときに受けられる年金のことです。障害等級に応じて、給付基礎日額の131〜313日分の年金を受給できます。
- 第1級:313日分
- 第2級:277日分
- 第3級:245日分
- 第4級:213日分
- 第5級:184日分
- 第6級:156日分
- 第7級:131日分
障害等一時金は、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害で負った傷病が治癒・症状固定したのちに、障害等級第8〜14級に該当する障害が残ったときに受けられる一時金のことです。こちらも等級に応じ、56〜503日分の一時金を受給できます。
- 第8級:503日分
- 第9級:391日分
- 第10級:302日分
- 第11級:223日分
- 第12級:156日分
- 第13級:101日分
- 第14級:56日分
障害等給付の請求時効は、傷病・症状固定が治癒した翌日から5年です。受給条件に該当する場合は、時効を迎える前に手続きをしましょう。
種類④遺族(補償)等給付
遺族(補償)等給付とは、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害によって死亡したときに受けられる給付金のことです。
遺族等給付には、遺族(補償)等年金と、遺族(補償)等一時金の2種類があります。
遺族等年金とは、被災者が業務災害・複数業務要因災害・通勤災害によって死亡したときに受けられる年金のことです。 遺族の人数などに応じて、給付基礎日額を153〜245日分の年金を受給できます。
- 1人:153日分
- 2人:201日分
- 3人:223日分
- 4人以上:245日分
一方、遺族等一時金とは、以下の場合に受けられる一時金のことです。
- 遺族等年金を受け取る遺族がいないとき
- 遺族等年金を受けている人が失権し、かつ、ほかに遺族等年金を受け取る人がおらず、支給済みの年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき
①のケースでは1000日分の一時金が、②の場合は1000日分から支給済みの年金合計額を差し引いた額を受給できます。
遺族等給付の請求時効は、労働者が亡くなった翌日から5年です。
種類⑤葬祭料等(葬祭給付)

葬祭料等(葬祭給付)とは、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害によって死亡した人の葬祭をするときに受けられる給付金のことです。 以下のうち、いずれか多いほうを受給できます。
- 31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額
- ①の額が給付基礎日額の60日分に満たない場合、給付基礎日額の60日分
葬祭料等の請求時効は、労働者が亡くなった翌日から2年です。
種類⑥傷病(補償)等年金
傷病(補償)等年金は、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害で負った傷病の療養を開始してから1年6か月を経過し、かつ以下の両方に該当しているときに受けられる年金のことです。
- 傷病が治癒・症状固定していない
- 傷病による障害の程度が、傷病等級に該当する
条件を満たしている場合、障害の程度に応じて、給付基礎日額の245〜313日分の年金を受け取れます。
- 第1級:313日分
- 第2級:277日分
- 第3級:245日分
また、この年金には請求の時効が定められていません。
種類⑦介護(補償)等給付

介護(補償)等給付とは、障害等年金または傷病等年金を受給している人のうち、障害等級が第1級の人、または第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害があり、介護を受けているときに受けられる給付金のことです。
給付金額は、以下のとおりです。
- 常時介護の場合:介護費用として支出した額(上限17万7,950円)
- 親族などに介護されており介護費用が発生しない場合、または支出額が8万1290円を下回る場合:8万1290円
- 親族などに介護されており介護費用が発生しない場合、または支出額が4万600円を下回る場合:4万600円
介護等給付の請求時効は、介護を受けた翌月1日から2年です。
種類⑧二次健康診断等給付
二次健康診断等給付とは、直近の定期健康診断などで、以下の両方に該当するときに受けられる給付のことです。
- 血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、腹囲またはBMI(肥満度)のすべてで異常の所見があると診断された
- 脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していない
該当する人は、二次健康診断や特定保健指導の給付を受けられます。診断や指導の時効は、一次健康診断の受診日から3か月以内のため、早めに手続きをしましょう。
労災保険を受給する際の5つの注意点
この章では、労災保険を受給する際の注意点について解説します。
前提:基本的にデメリットはない

労災保険を利用するデメリットは、基本的にはありません。
労災保険を利用する際に、「事業主側に迷惑に思われるかもしれない」などと不安を抱くかもしれませんが、労働保険を利用することは、保険に加入している労働者に認められた権利です。労働災害の規模にかかわらず、申請して問題ありません。
また、労働災害が発生した際に手続きをしなかった場合、事業主側は刑事責任を問われることもあります。労働災害が発生した場合には、事業主へ報告し、正しく手続きをする必要があります。(参考:厚生労働省「労働災害が発生したとき」、横浜労災事故相談室「労災保険を使うことのメリットとデメリットはなんでしょうか?」)
注意点①労災保険の未手続事業者もいる
労災保険に加入する義務があるにもかかかわらず、未手続の事業者もいます。
厚生労働省が未手続事業一掃対策を行っていますが、未手続事業者がいなくなっているわけではありません。労災保険を利用する可能性が高い人は、念のため加入状況を確認しておくとよいでしょう。(参考:厚生労働省「労働保険とはこのような制度です」)
注意点②労務担当者と連携して手続きをする

労災保険の手続きは、労務担当者と連携しながら進めることが大切です。
例えば、労災保険の給付を受けながら治療に臨む場合は、労災保険指定医療機関で、労災の旨を伝えて受診する必要があります。指定機関以外で治療を受けたり健康保険を利用したりすると、自己負担分が生じ、のちの手続きが煩雑になります。
労働災害発生時における手続きの不安・負担を軽減するためにも、社内で連携を取るようにしましょう。
注意点③精神障害は労災保険で認定されにくい傾向にある
一般論として、うつ病や適応障害などの精神障害による労災認定は難しいと言われています。なぜなら、精神障害は原因の特定が難しく、私生活を含む様々な要因が複合的に絡みあって発症するケースが多いからです。
精神障害を発症した際に労働災害として認定されるためには、以下の要件を満たす必要があります。(参考:厚生労働省「精神障害の労災認定」)
- 認定基準の対象となる精神障害があること
- 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
- 業務以外の心理的負荷や個体側要因によって発病したとは認められないこと
業務による強い心理的負荷があったと認められるためには、特別な出来事が確認できるか、具体的出来事の総合的評価で「強」と判断される必要があります。特別な出来事と具体的出来事の例は、以下のとおりです。
- 特別な出来事:発病直前の極めて長い労働時間など(例:発病直前の1か月におおむね160時間以上の時間外労働を行った)
- 具体的出来事:仕事量の著しく増加し、労働も大幅に増える状況になり、業務に多大な労力を費やしたなど労働時間がおおむね倍以上に増加し、1か月あたりおおむね100時間以上の時間外労働をした)
注意点④公的年金給付にあわせて支給額が調整される場合がある

公的年金と労災保険は、同時に受給できます。
しかし、労災保険のうち傷病等年金・障害等年金・遺族等年金は調整が行われ、全額受け取れなくなる点に注意しましょう。例えば、障害厚生年金や障害基礎年金と労災保険を受け取る場合は、以下のような調整が行われます。(参考:厚生労働省「7-1 労災保険給付と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。」)
- 障害厚生年金+障害基礎年金+傷病等年金/障害等年金(労災保険):調整率0.73を適用
- 障害厚生年金+傷病等年金(労災保険):調整率0.88を適用
- 障害厚生年金+障害等年金(労災保険):調整率0.83を適用
- 障害基礎年金+傷病等年金/障害等年金(労災保険):調整率0.88を適用
注意点⑤療養給付以外は、全損害額が補償されるわけではない
労災保険のうち療養給付は全額補償されますが、そのほかは、全額が補償されるわけではありません。
補償の種類によっては、給付金額や受給できる期限の上限が設けられていることもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
労災保険を申請する流れ
この章では、労災保険の申請と給付の流れについて解説します。(参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労災保険給付の概要」)
申請の流れ①療養給付の場合

療養給付を申請する場合、手続きの流れは以下の3つです。
- 1.労働災害が発生した後、労災病院・労災保険指定医療機関などで診療を受ける
- 2.事業主が請求書に証明必要事項を記入する
- 3.療養の給付請求書を指定病院などへ提出する
療養費用は、労働基準監督署・都道府県労働局などを通じて医療機関へ支払われます。
指定医療機関で診療を受ける場合は、立て替えや自己負担はありません。ただしすでに取り上げたとおり、指定医療機関以外で診察を受けたときには、立て替えや自己負担が生じるため注意しましょう。
申請の流れ②二次健康診断等給付の場合
二次健康診断等給付を受ける場合の申請・受給の流れは以下のとおりです。
- 1.事業主が請求書に証明必要事項を記入する
- 2.労働者が二次健康診断等給付請求書を持って二次健康診断を受ける
- 3.病院などから二次健康診断結果が送付される
- 4.二次健康診断などの結果を事業主へ提出する
二次健康診断等給付も、費用は都道府県労働局・厚生労働省から医療機関へ支払われます。
申請の流れ③そのほかの場合

療養給付・二次健康診断等給付以外の補償を受けるときには、以下の流れで手続きを行います。
- 1.労災病院・労災保険指定医療機関などで診断書・請求書などを発行する
- 2.事業主が請求書に証明必要事項を記入する
- 3.請求書を労働基準監督署へ提出する
給付は、被災労働者または遺族へ行われます。
労災で障害が残ったときの転職相談先
労働災害によって障害が残った場合、仕事を変えたいと思う人や、仕事を変えざるを得ない人もいるでしょう。その場合は、ハローワークや、就労移行支援事業所などを利用できます。
とくに就労移行支援事業所では、個別面談によるサポートを受けられるため、不安や悩みを軽減しながらの就職・転職活動が可能です。サポートを得ながら、無理なく、合った就職先を見つけることが大切です。
まとめ:労災保険を利用して負担と不安を軽減しましょう

労働災害が発生したときには、労災保険の補償を受けることで、負担や不安を軽減しながら療養できます。労災保険は、雇用形態や就業時間を問わず利用が可能です。
ただし、補償を受ける条件や注意事項もあります。あらかじめ労災保険の概要や利用の流れを把握しておくことが大切です。
このコラムが、労働災害に不安を抱くあなたの助けになることを願います。
労災保険とは何ですか?
労災保険(労働者災害補償保険)は、業務中または通勤中に発生した病気やケガ、障害などの労働災害に対して保険給付を行い、対象者の社会復帰を促すための支援制度のことです。
詳細については、こちらで解説しています。
労災保険を受給するメリットを教えてください。
以下が考えられます。
- 保険給付を受け取れて金銭的な負担を軽減できる
- 過失割合に影響されず保険給付を受け取れる
- 社会復帰促進等事業を利用してスムーズな復帰を目指せる
- 被災労働者等援護事業を利用して家族へのサポートも受けられる
詳細については、こちらで解説しています。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→