ADHDと感覚過敏の関係 対策を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)利用者でADHD当事者の大久保です。
あなたは以下のような経験でお悩みではありませんか?
- 職場で周囲の音が気になって、仕事に集中できない
- ベッドのシーツなど、苦手な手触りのものと触れていると、気持ちが悪くなる
それらはADHDに見られる特性の一つである、感覚過敏によるものかもしれません。
ADHDと感覚過敏に関する正しい知識と対処法を知ることで、感覚過敏による生活への影響を減らし、今よりも快適に暮らす事ができます。
このコラムでは、ADHDと感覚過敏のそれぞれの概要や関係性、五感それぞれに見られる感覚過敏の症状とのその対処法などについて解説します。
あわせて、筆者を含め、感覚過敏のある人の体験談や感覚過敏にお悩みのADHDのある人の就職・転職に関する支援機関を紹介します。
ぜひこのコラムを読み、前向きに日々を過ごせるようになっていただけたら嬉しいです。
ADHDによる感覚過敏に悩んでいるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
ADHDとは?
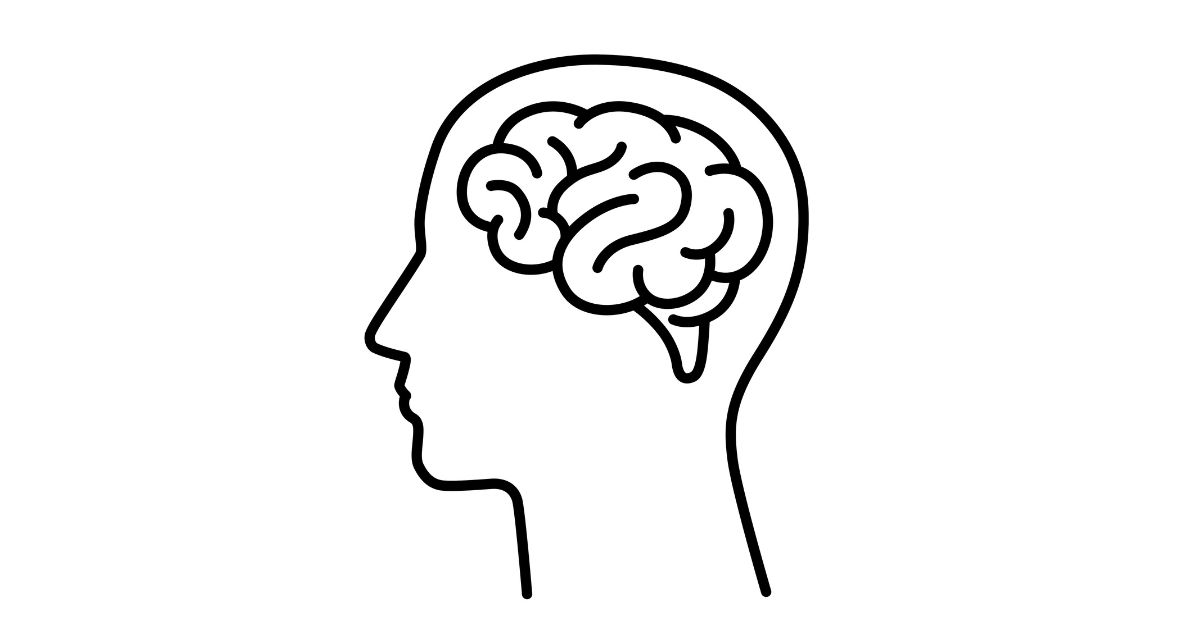
ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害、Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)とは、不注意性や多動性・衝動性の特性から日常生活などに困難が生じる発達障害の一種のことです。 (参考:American Psychiatric Association・著、 日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、 田中康雄・監修『大人のAD/HD』、 岩波明『大人のADHD─もっとも身近な発達障害』、 司馬理英子『ササッとわかる 「大人のADHD」 基礎知識と対処法』、 星野仁彦『それって、大人のADHDかもしれません』、 e-ヘルスネット「ADHD(注意欠如・多動症)の診断と治療」)
ADHDの特性は大きく、以下の2つの特性に分けられます。
- 不注意…忘れ物やミスが多く、確認作業が苦手。段取りが下手で先延ばしにしやすい
- 多動・衝動性…気が散りやすく、些細なことで口論になるなど、トラブルを起こしやすい
ADHDのある人だからといってすべての特性が生じるというわけではありません。いずれかの特性、または複数の特性から困難が生じている人もいます。
ADHDのある人は、必ず不注意性や多動性・衝動性が現れるというわけではなく、人によって特性の現れ方、得意なこと・不得意なことが違う点が大きな特徴です。
ADHDについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
感覚過敏とは?
感覚過敏とは、聴覚・視覚・触覚・嗅覚・味覚の五感の一部、または複数からの刺激を過度に感じることで、苦痛や不快感が生じている状態のことです。(参考:イルセ・サン・著、 枇谷玲子・訳『鈍感な世界に生きる敏感な人たち』、 岡田尊司『過敏で傷つきやすい人たち HSPの真実と克服への道』)
症状や程度は人によってさまざまですが、感覚過敏の人の多くが日常生活や仕事の場面においてストレスを感じていると言われています。その強弱は人によって異なります。
目や耳や鼻などの感覚器に先天的な異常がある場合など、幼少期から感覚過敏を自覚している人もいます。また、不安やストレスが原因で、大人になってから感覚過敏の症状に悩む人もいます。
感覚過敏については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
ADHDと感覚過敏の関係性

発達障害がある人の多くは、感覚過敏を持っていると言われています。
特に、感覚過敏が多く現れる発達障害は、ASD(自閉症スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)ですが、ADHDのある人でも感覚過敏は現れるという報告があります。(参考:国立障害者リハビリテーションセンター「発達障害のある人の感覚の問題」、 発達障害ナビポータル「発達障害者の感覚の問題(国立障害者リハビリテーションセンター研究所)」、 BRAIN CLINIC 「感覚過敏の症状や原因、対処法、発達障害との関連性についてマンガで解説」)
では、なぜADHDがある人の多くは、感覚過敏があるのでしょうか。
その理由は、ADHDの原因である脳機能異常にあります。なんらかの脳機能異常が刺激に対して過度に反応しているのです。
ここで間違いやすい考え方についても触れておきます。「感覚過敏があるからADHDである」「感覚過敏がないからADHDではない」ということはありません。
あくまで、多くみられるという程度で、感覚過敏=ADHDということはないのです。また、その程度もさまざまです。
そのため、「感覚過敏があるからADHDだと思います」という考えを医師に伝えても、ADHDだと診断がつくとは限りません。ADHDかどうかは、医療機関で受けられる検査によって診断される点に注意しておきましょう。
ADHDの感覚過敏の症状例と対策
この章では、五感に見られる感覚過敏の症状と対策法について解説をします。 (参考:発達障害ナビポータル「発達障害者の感覚の問題(国立障害者リハビリテーションセンター研究所)」、 厚生労働省「マスク等の着用が困難な状態にある方への理解について」、 BRAIN CLINIC 「感覚過敏の症状や原因、対処法、発達障害との関連性についてマンガで解説」)
聴覚にみられる症状

感覚過敏のある人の多くは、大きな音に苦手意識を持ちます。例えば、以下のような音です。
- 運動会のピストルなど突発的な爆発音
- 甲高い叫び声
ひどい時は気分が悪くなったり、イライラしたり、頭痛やめまいにおそわれたりすることもあります。また、騒がしい場所での会話が困難な人も多いようです。具体的な症状例は、以下のとおりです。
- 駅などの騒がしい場所での聞き取りが困難である
- 会話中に相手の声と周囲の雑音が同じくらいの大きさに聞こえて、会話に集中できない
- 換気扇などの一定のリズムを刻む小さな音にイライラする
聴覚過敏に対する対策
聴覚過敏に対する対策は、苦手な音から物理的に離れたり、その音を遮断したりするのが有効な手段といえます。例えば、以下のような対策が考えられます。
- 苦手な音や大きい音から離れる
- 耳栓・ヘッドホンを着用する
- 好きな音楽を聴いて気を紛らわせる
視覚にみられる症状

ADHDのある人の中には、眩しい光や目に入る大量の情報に苦手意識を持つ人が多いようです。具体的には、以下のような症状例があります。
- 強い光をまぶしく感じる
- 点滅する光が苦手
- たくさんの看板やネオンで注意が妨げられる
- 白い紙が極端にまぶしく感じる
- 目に入る情報量が多いとパニックになる
視覚過敏に対する対策
視覚過敏の対策は、聴覚過敏と同じように、苦手な視覚情報から物理的に離れるのが効果的です。例えば、以下のような対策が考えられます。
- サングラスを着用する
- 人混みの場所に行く場合は、目的地まで寄り道をせずに行く
嗅覚に見られる症状

ADHDのある人の多くは、特定の匂いに苦手意識を持ちます。例えば、以下のような匂いです。
- マスクの匂いが苦手で、予防のためのマスクが着用できない
- 洗剤や香水、化粧品などの強い匂いが苦手
- バスや電車などの匂いに反応し、乗車することができない
嗅覚過敏に対する対策
嗅覚過敏に対する対策としては、聴覚や視覚と同じように、物理的な方法で苦手な匂いから離れる必要があります。具体的には、以下のとおりです。
- 苦手な匂いがする場所は避ける
- マスクを着けて匂いをできる限り遮断する
- 物を購入する際、家に置いたり、身に着けたりする物は苦手な匂いがしないかを確認する
また、心地よいと感じる匂いを持ち歩き、鼻をリセットするという方法もあります。
触覚にみられる症状

ADHDのある人の中には、特定の素材のシーツやシャツのシワなどが気になり、肌がかゆくなったり、眠れなくなったりする人もいます。具体的な症状例として、以下のようなものがあります。
- チクチクした肌触りが苦手
- シーツの布ずれが気になって眠れない
- 他人と肌が触れ合うとぞわっとする
- マスクのカサカサした質感が苦手で、予防のためのマスクが着用できない
触覚過敏に対する対策
触覚過敏への対策としては、洋服やシーツなど肌に触れる素材を事前に確認することで、触覚に関する不快感は減らすことができます。具体的な対策としては、以下のことが考えられます。
- 苦手だと思う素材の服は無理に着ない
- 着心地を確認してから購入する
- 周囲の人に、「急に自分に触れないで」と前もって伝えておく
味覚にみられる症状

味覚過敏は食べ物の好き嫌いとは異なるものです。舌触りや食感、味付けの濃度などに過敏に反応することが多いようです。例えば、以下のような症状例があります。
- 独特な食感や舌触りの食べ物が苦手
- 濃い味付けの食べ物が苦手
- 食べ物の好き嫌いとは違う
味覚過敏に対する対策
味覚過敏は、単なる好き嫌いによるワガママだと勘違いされることがあるため、周囲に「苦手な食感がある」ということを知らせ理解を得るようにしましょう。
- 苦手な食べ物は無理に食べない
- 人と食事に行く場合は、「苦手な触感がある」と前もって周囲に伝えておく
ここでご紹介した症状と対策は、数ある中のほんの一部です。
前述したとおり、症状の程度は人によります。また、「聴覚だけは過敏で、触覚は鈍感である」といった場合もあります。感覚過敏はまさに十人十色なのです。
ここにご紹介した対策だけでなく、ご自身にあった方法を見つけて、快適な生活を送れるようにしましょう。
ADHDに伴う感覚過敏に関する筆者の体験談
この章では、ADHDによる感覚過敏の当事者である筆者の体験談を紹介します。
感覚過敏の経験~幼少期から現在まで~

著者は、強い聴覚過敏と嗅覚過敏があります。聴覚過敏には幼少期のころから悩まされています。
例えば、静かな真夜中に突然走ってくる爆音のバイクや、工事現場の騒音、機械音、雷の音がとても苦手です。これらの大きな音を聞くと、心臓がえぐられるような感覚に襲われ、心臓がバクバク鳴ります。
他にも、人混みで会話をすると相手が口パクに見えることも子どものころからありました。また、以前は金融機関で働いていたのですが、職場は苦手な機械音であふれていました。
例えば、通帳を記帳する際に出る音や、両替機の小銭の音など。職場にいると常に頭痛がしました。
嗅覚過敏は、生臭い匂いや強い香水の匂いが苦手です。また、匂いに敏感すぎるせいで、独特の匂いを持つ公共交通機関の乗り物に乗ると、すぐに酔ってしまいます。
ここまで読んでいただくと、「感覚過敏って大変だ」と改めて実感し、日常生活に不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、現在の筆者はこうした症状にうまく対処しながら生活しています。
ここからは、その対処法についてお伝えしようと思います。
著者が実践している感覚過敏への対策
まずは聴覚過敏についてです。ヘッドホンやイヤホンを使用し好きな音楽を聴きリラックスしつつ苦手な音を遮断するか、耳栓をすることで対処しています。
耳栓やイヤーマフの着用によって音を遮断する方法は、手軽な手段として医師によっても推奨されています。
しかし、耳栓やイヤーマフを長時間装着すると、音の認知機能を悪くし、聴覚過敏が悪化する可能性があるそうです。 そのため、短時間の装着に留めましょう。(参考:おおかみこころのクリニック「大きい音が怖い【聴覚過敏】はうつ病の前兆?対策を解説」 )
次に、嗅覚過敏についてです。これは乗り物酔いにも起因していると書きました。そこで筆者は苦手な匂いのしない電車に乗るようにしています。
幸い東京には多くの電車が走っているため、目的地までの移動手段が数多く存在します。
筆者の場合は、地下鉄特有の匂いが苦手なので、地下鉄を避け、できる限り地上を走っている電車を使うようにしています。また、歩ける距離であれば、歩くようにしています。
「感覚過敏のせいで歩く羽目になるなんて」と悲観的になる人もいると思います。しかし歩くことにはさまざまな良い効果があります。
例えば、電車賃がかかりません。これは物価高の昨今には嬉しい効果です。もちろん健康にも良い効果があります。
感覚過敏によって生活が制限されていると感じるかもしれませんが、先程ご紹介した対処を実践することで、日常生活は比較的快適に過ごすことができます。
また、積極的に社会に出ていくことで、楽しいことを新しく発見できるかもしれません。感覚過敏のある人は、他人が気にならない刺激で体調を崩したり、生活や行動を制限されたりするなど、歯がゆい思いをすることもあるでしょう。
また、苦手な音を遮断するための耳栓を買ったり、同じ素材の洋服ばかりを買ったりするなど、対処法を実践するために煩わしいこともあるでしょう。しかし、感覚過敏は決して悲観的な面しか持っていないわけではありません。
感覚に対して過敏であることは、感覚に対して人よりも精度の高いアンテナを持っていると言い換えることができるのです。
例えば、味覚過敏の人は、それを生かして料理の才能を発揮するかもしれません。視覚過敏な人は芸術面で花開くかもしれませんし、聴覚過敏な人は音楽方面で才能が見られるかもしれません。
実際に、筆者は子どものころから、一度聞いただけのCMソングを歌ったり、音楽の音程をすぐに取れたりするなどと、音楽への才能がありました。(自分で才能と言うのはおこがましいですが)
それによって家族から褒められたり、学校で合唱コンクールのリーダーを任されたりしたことは筆者の大切な財産です。
悲観的になりすぎず、自分に合った対処しながら、自分の特性とうまく付き合えると良いのではないかと思います。
職場における感覚過敏への対処法~働き方の提案~

職場は多くの人が長時間を共に過ごす場所です。そのため、苦手な音はもちろん、苦手な匂いなどもあるでしょう。
たった一日我慢するのであれば、可能かもしれません。しかし心身がつらいのは確かです。また、その職場に長く勤め、ストレスがかかり続けた結果、心身に何らかの症状が現れる可能性があります。
そこで選択肢の1つとなるのが、障害者雇用という働き方です。
障害者雇用とは、身体障害、精神障害を問わず、障害のある人を対象とした雇用枠を設けて雇い入れる制度のことです。障害の特徴や内容、個々の能力などに合わせて、安心して働けるようにすることを目的としています。
障害のある人でも、個々の能力や特性に応じて会社側の配慮を受けながら、安定的に働けるようにすることを目的としています。会社側としては、規模に応じて雇う必要があり、会社の成長に沿って障害者雇用の採用も増加します。
筆者も現在、キズキビジネスカレッジ(KBC)に通いながら、障害者雇用での就職を目指しています。
筆者の場合は、ADHDによる感覚過敏で苦手な音があることを説明し、必要な配慮として耳栓・ヘッドフォンの着用や、できる限り静かな席に配置してもらうなどを記載します。
障害者雇用であれば、職場においても感覚過敏における苦手なものから可能な限り離れることができるのです。
ここで障害者雇用について、一点注意点があります。それは、障害者雇用で就職する際には障害者手帳を取得していることが求められるという点です。
障害者雇用を検討する場合は、心療内科などの主治医に、障害者手帳の取得を申請しましょう。
障害者雇用や障害者手帳については、については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
感覚過敏に悩むADHDのある人が相談できる支援機関
この章では、ADHDのある人が日常生活の悩みを相談できる機関や、障害者雇用など就職の支援を利用できる機関をご紹介します。
自分自身で感覚過敏を緩和することもできます。しかし、一人では不安なこともあるでしょう。
そういった時に頼りになる場所があると安心するものです。ぜひ気になったものを利用してみたり、様子をのぞきに行ったりしてください。
発達障害のある人が利用できる支援機関については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
- 通院先の病院
- 精神科デイケア:通所(病院が持っているデイケアサービス)
- リワーク
- 地域活動支援センター(日程を決めずに通えるところ)
- 発達支援センター(発達相談)
- ハローワーク(障害者専用窓口、障害者雇用求人)
- 人材紹介サービス
- 地域のしごと支援センター
- しごとサポートセンター
- 東京しごとセンター
- 若者サポートステーション
- 就労移行支援(2年間限定)
- 就労継続A、B型(福祉的就労、2年以上かけて就職を目指す)
- 職業リハビリセンター(職業センター・能力開発校)
- 就労移行支援:就職後~6か月目
- 就労定着支援:7か月目~就職後から最大3年半
まとめ:感覚過敏がある自分とうまく付き合うために

筆者の愛読書の一つである『赤毛のアン』にとても好きなフレーズがあります。「持っていて良い面しか無いものはない」つまり何事にも良い面と悪い面があるということです。
ADHDも感覚過敏も持って生まれたものであるため、手放すことは難しいです。長い人生で付き合っていくものです。だからこそ自分の特性を理解し、苦手な刺激を避ける必要があります。その対処は時には億劫で面倒でしょう。
しかし先にも述べた通り、物事には必ず良い面と悪い面があります。自分の特性に、良い面を見つけ、良い面を伸ばす。これこそが感覚過敏がある自分とうまく付き合うコツであると筆者は考えます。
一人で自分の特性の良い面を探すのは難しいと感じている人は、支援機関を頼ってみるのも良いでしょう。きっと一緒にあなたの感覚過敏について相談できます。
ADHDや感覚過敏に限らず、誰もが良い面と悪い面を持つ自分とともに生きています。それを忘れずに、自分の特性を理解して、正しく対処して、明るい日々を送れたらと思います。
本コラムがその一助となっていたら嬉しいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
ADHDと感覚過敏の関係性について教えてください。
発達障害がある人の多くは、感覚過敏を持っていると言われています。特に、感覚過敏が多く現れる発達障害は、ASD(自閉症スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)ですが、ADHDのある人でも感覚過敏は現れるという報告があります。
詳細については、こちらで解説しています。
ADHDによる感覚過敏には、どのような症状がありますか?
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。 サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC) うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)








