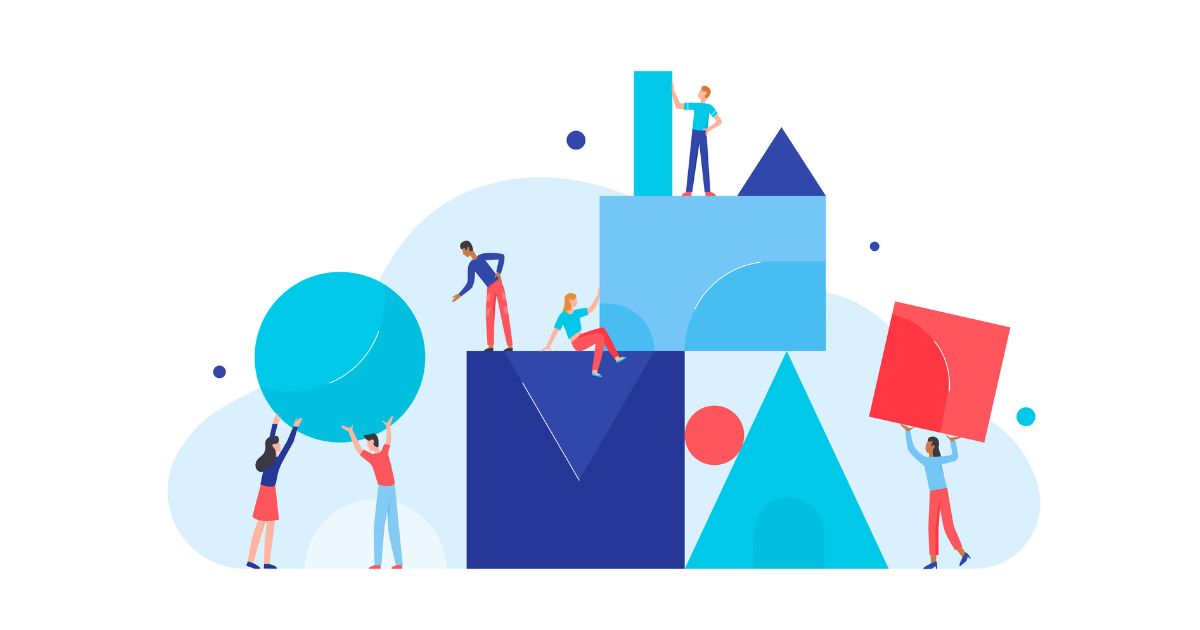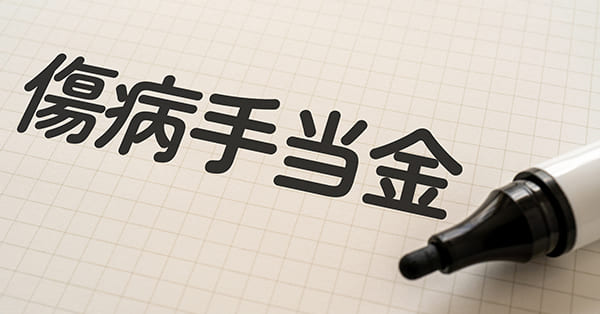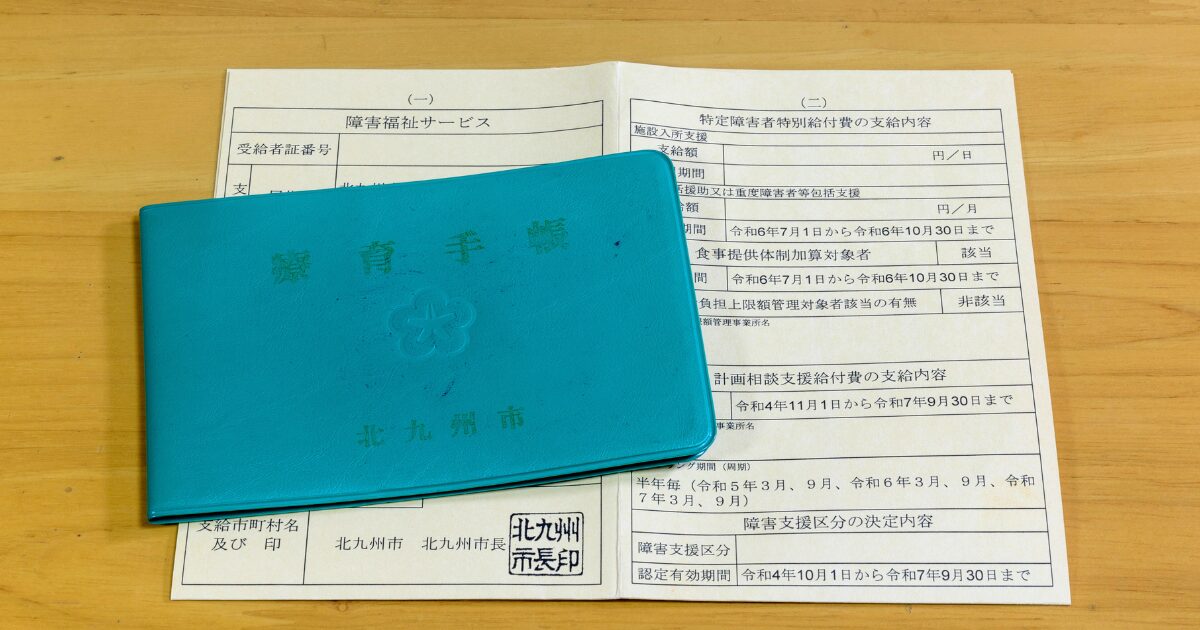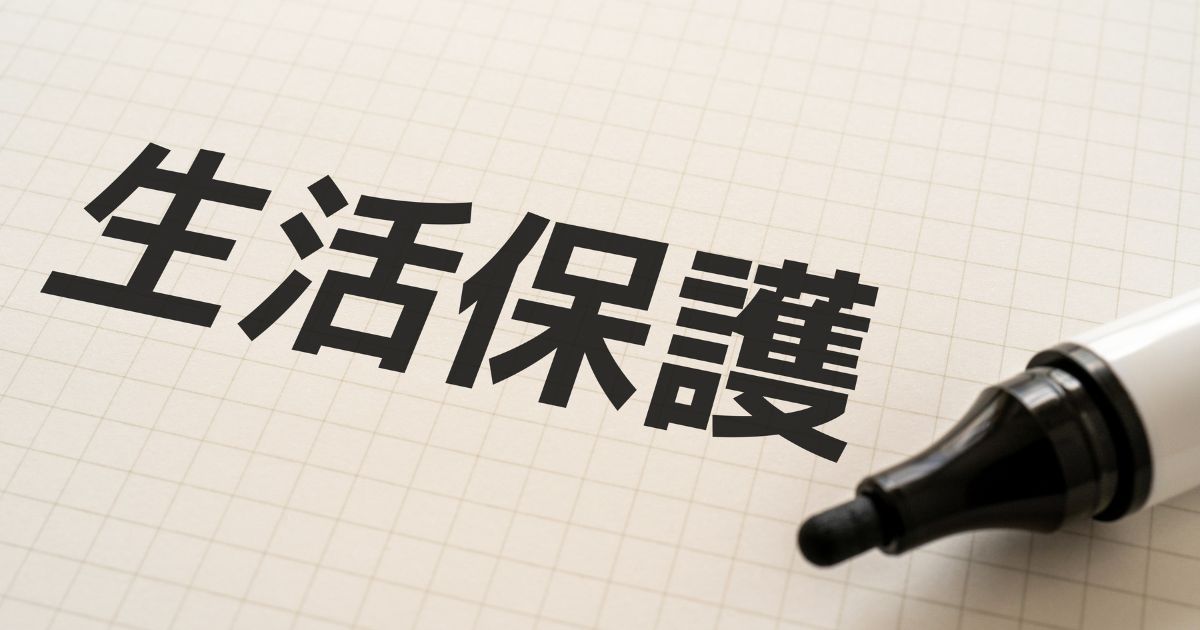生活困窮者自立支援制度と生活福祉資金貸付制度は何が違う? 支援内容を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
- 生活に困窮し、誰に相談すればいいか分からない
- 住む場所や仕事に困っている
- 将来の見通しが立たなくて、不安を感じている
あなたは、このようなお悩みを抱えていませんか?
生活困窮者自立支援制度と生活福祉資金貸付制度は、どちらも経済的にちらも経済的に困難な状況にある方を支援するための国の制度です。
しかし、支援内容や目的には違いがあります。この記事では、それぞれの制度の違い、概要、利用条件、手続きの流れなどについて解説します。
それぞれの違いについて理解し、あなたにとって必要な支援を見つけましょう。
さまざまな支援の利用を検討しているあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
生活困窮者自立支援制度と生活福祉資金貸付制度の違い

生活困窮者自立支援制度と生活福祉資金貸付制度の大きな違いは、その支援の目的とアプローチにあります。それぞれの違いは以下のとおりです。
- 生活困窮者自立支援制度:生活に困窮している人が自立した生活を送れるよう、包括的な相談支援や、住居・就労の支援など、多角的なサポートを提供する制度
- 生活福祉資金貸付制度:一時的に生活が困窮している人や、特定の目的のために資金が必要な人に対し、必要な資金を貸し付けることで生活の安定を図る制度
つまり、生活困窮者自立支援制度は自立支援そのものを目指すのに対し、生活福祉資金貸付制度は、資金の貸付を通じて生活の安定を支えるという点で異なっています。
生活困窮者自立支援制度とは?
この章では、生活困窮者自立支援制度の概要や対象者、メリットなどについて解説します。
概要

生活困窮者自立支援制度とは、経済的な不安だけでなく、仕事や住居、健康など複合的な問題を抱える方に向けた支援制度のことです。(参考:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」)
生活困窮者自立支援制度では、さまざまな取り組みを行い、生活困窮者に対して包括的な支援を実施します。支援内容は、以下のとおりです。
- 自立支援相談事業:困りごとの相談に応じ、解決に向けた支援プランを作成
- 住居確保給付金の支給:離職等により住居を失った方に対し、家賃相当額を一定期間支給
- 就労準備支援事業:社会参加や就労に向けた基礎能力を養うためのプログラムを提供
- 家計改善支援事業:家計状況の分析や改善に向けたアドバイスや支援
- 就労訓練事業:知識や技能習得の機会を提供
- 生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業:学習支援や居場所づくりなどを通して、子どもの成長をサポート
- 一時生活支援事業:緊急的な生活困窮者に対し、一時的な宿泊場所や食事などを提供
これらの支援を組み合わせることで、経済的な困窮だけでなく、孤立や将来への不安といった複合的な問題の解決を目指します。
制度の目的と背景
生活困窮者自立支援制度の目的は、従来の制度ではカバーしきれなかった人たちに対して、早い段階で支援を届け、生活の立て直しと社会参加を促すことです。
日本では、生活が立ち行かなくなった人に対して生活保護という制度が用意されています。
生活保護とは、生活に困窮している人や病気やケガ、障害などで就労できない人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活の保障と自立の助長を目的とした支援制度のことです。(参考:厚生労働省「生活保護制度」、厚生労働省「「生活保護制度」に関するQ&A」)
しかし実際には、生活保護を選べない人や、社会保障の枠組みで救済できない人など、すき間にある人々も多く存在しているのです。
そこで、生活保護に至る前の生活困窮者に対して貧困対策を継続的に行うことが求められ、2013年に生活困窮者自立支援制度が制定、2015年に施行される運びとなりました。(参考:厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度について」、厚生労働省「生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携のあり方について」、社会保障審議会「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会報告書」)
制度の対象者・利用条件

制度の対象者は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人とされています。(参考:e-GOV「生活困窮者自立支援法」、厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」)
つまり、経済的な困窮で生活保護に至るおそれがあり、なおかつ自立が見込まれる人が対象です。経済的な事情で困難な状況にある人を包括的に支援するため、資産や収入に関する具体的な要件は定められていません。(参考:厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集」)
ただし、状況に応じて適切な支援が提供されるため、相談内容によっては対象外になる場合もあります。制度全体としては幅広い対象者を想定していますが、たとえば、住居確保給付金など、一部の支援には収入や離職の状況に関する要件が設けられています。
支援が必要かどうか迷う段階でも、ひとりで抱え込まず、まずはお住まいの自治体窓口に相談してみてください。
利用するメリット
生活困窮者自立支援制度のメリットは、相談から就労・住居・家計改善まで、個別のニーズに応じた包括的な支援を受けられることです。自分が支援の対象か分からないと悩む人でも、相談窓口に行けば、自分に合った支援プランを一緒に考えてもらえます。
ひとつの窓口で幅広いサポートを受けられるため、問題の根本的な解決にもつながりやすいでしょう。
利用する際の注意点

生活困窮者自立支援制度では、利用者一人ひとりの状況に応じて支援内容が決まります。そのため、誰もがすべての支援を受けられるわけではありません。
支援内容に対して特定の希望があっても、実際の支援内容は面談や状況確認のうえで決定されます。
また、相談後すぐに支援が始まるとは限りません。必要な手続きや審査を経て、具体的な支援計画が立てられる流れとなります。そのため、スムーズに支援を受けるためにも、早めに相談することが大切です。(参考:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携のあり方について」)
生活困窮者自立支援制度の支援内容
生活困窮者自立支援制度では、経済的な困難だけでなく、住まいや就労、家計、子育てなど、さまざまな生活課題に対して複数の支援が用意されています。
この章では、制度の主な支援内容について具体的に解説します。
支援内容①自立相談支援

自立相談支援は、生活困窮者自立支援制度の入り口となる支援です。この支援では、相談支援員が利用者と伴走するかたちで、生活の再建に向けた計画を一緒に立ててくれます。
また、相談は一度きりのものではありません。継続的に支援を受けながら、少しずつ自立に向かって進んでいけるのが特徴です。この支援を通じて、住居支援や就労支援など、他のサポートへの橋渡しも行われます。
支援内容②住居確保給付金の支給
住居確保給付金とは、離職や収入の減少などにより家賃の支払いが困難になった人に対して、一定期間、家賃相当額を支給する制度のことです。
支給は原則3か月ですが、状況に応じて最大9か月まで延長できます。給付金は大家さんなどの住宅の貸主に直接支払われ、住まいの喪失を防ぐ仕組みとなっています。支給には、求職活動への参加などの条件がありますが、生活の安定と再スタートに向けた強力な支援となります。(参考:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度における居住支援について」)
支援内容③就労支援

生活困窮者自立支援制度における就労支援は、就職先のあっせんにとどまらず、就労に向けた準備段階から手厚くサポートされます。
面接対策や履歴書の書き方の指導、職業訓練の紹介、さらには働く自信がないといった気持ちの整理まで、多角的に支援してくれるのが特徴です。一人ひとりの状況に応じた支援計画が立てられるため、自分のペースで就労を目指せます。
就労準備支援や就労訓練を通じて、社会に出る前のリハビリ的な期間を設けながら、少しずつ就職へのステップを踏めるでしょう。(参考:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度について」)
支援内容④居住支援
居住支援では、住まいを失うおそれがある人や、すでに住居を失った人に対して、住まいの確保に向けた支援を行います。
物件探しのサポートや、家主との調整、必要に応じて関係機関との連携などを行い、安心して暮らせる住まいを確保するのが目的です。
住居喪失を喪失した人に対しては、一定期間の間、衣食住を提供する緊急的な支援も実施されます。生活全体の安定につながる重要な支援です。(参考:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度における居住支援について」)
支援内容⑤家計改善・相談支援

家計改善・相談支援では、収入と支出のバランスを見直し、安定した家計管理ができるようサポートします。
専門の支援員が家計簿の作成や支出の整理を手伝いながら、生活設計や借金がある方には無理のない返済計画を一緒に考えていきます。生活の再建に向けた第一歩となる支援です。(参考:一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク「家計改善支援事業」)
支援内容⑥子どもの学習・生活支援
子どもの学習・生活支援は、経済的に困難な状況にある家庭の子どもたちを対象に、学習の機会や居場所を提供する取り組みです。
学習教室や、安心して過ごせる場を通じて、子どもの成長を支えます。
また、基礎的な学力向上を目指すだけでなく、進路相談や社会とのつながりもサポート。将来の進学や就労に向けた土台づくりから、子どもの将来の可能性を育てる支援です。(参考:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度について」、東京都庁「生活困窮者自立支援制度について」)
生活福祉資金貸付制度とは?
この章では、生活福祉資金貸付制度の概要や対象者、メリットなどについて解説します。
概要

生活福祉資金貸付制度とは、一時的に生活に困窮している人や、特定の目的のためにまとまった資金が必要な人に対し、無利子または低利子で資金を貸し付ける公的制度のことです。
各種資金にはそれぞれ利用目的が定められており、状況に応じた柔軟な支援が可能です。
この制度では、以下のような資金が用意されています。
- 総合支援資金:失業や収入減少により生活に困っている方への生活費支援
- 福祉資金:福祉用具の購入や介護サービス費用など、日常生活に必要な費用の支援
- 教育支援資金:高校・大学等への進学や在学中の学費支援
- 不動産担保型生活資金:持ち家を担保にして、長期的な生活資金を確保する支援
いずれの貸付も、原則として無利子(または低利子)であり、返済の負担を抑えながら生活再建を目指せる仕組みになっています。貸付の相談・申請は、お住まいの地域の社会福祉協議会で行います。(参考:厚生労働省社会・援護局 地域福祉課「【生活福祉資金貸付制度について」、厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」
制度の目的と背景
生活福祉資金貸付制度の目的は、低所得世帯や高齢者・障害者世帯、ひとり親家庭などが抱える経済的な困難を一時的に緩和し、生活の安定と自立の支援を行うことです。
具体的には、生活再建に必要な資金を貸し付けることで、生活の安定を図り、再就職や住居の確保など、社会復帰に向けた支援を行っています。
生活福祉資金貸付制度の歴史は、1955年に前身となる世帯更生資金貸付制度が設立されたのが始まりです。戦後の生活困難な状況にある人々を支援することを目的としてスタートしました。
その後、非正規雇用の増加、ひとり親家庭や障害のある方の孤立、高齢者の無年金・低年金問題などの社会情勢や経済状況の変化に伴い、支援対象や支援内容が見直され、現在の形となっています。(参考:厚生労働省社会・援護局 地域福祉課「生活福祉資金貸付制度について」、社会福祉法人全国社会福祉協議会「福祉の貸付制度」
制度の対象者・利用条件

生活福祉資金貸付制度の対象となるのは、おもに低所得世帯や高齢者世帯、障害者世帯です。これらの世帯で、一時的に資金が必要となり、自立に向けた具体的な目的がある場合に利用できます。
住民票がある市区町村に居住しており、他の制度による支援が受けられない場合が対象です。
申請にあたっては、貸付の用途や返済計画などを明確にし、必要に応じて保証人の有無も確認されます。(参考:東京都社会福祉協議会「生活福祉資金貸付制度 福祉資金のご案内」、社会福祉法人 京都府社会福祉協議会「生活福祉資金 貸付制度ご案内」)
利用するメリット
制度には総合支援資金や教育支援資金、福祉資金など、生活状況に応じた複数の種類があります。これにより、失業中の生活費や子どもの学費、介護・障害にかかわる出費など、具体的なニーズに合った支援を受けることが可能です。
また、生活福祉資金貸付制度は、貸付という形式をとりながらも、無利子・据置期間あり・返済相談可など、利用者の生活再建を第一に考えた柔軟な仕組みが整えられています。
申請から貸付後のフォローまで一貫して支援してくれるため、初めて制度を利用する人でも安心して手続きできます。制度に詳しい専門職が相談に乗ってくれるため、不安を感じやすい場面でも心強い支えになるでしょう。
利用する際の注意点

生活福祉資金貸付制度で受けられる支援は、あくまで貸付であり、給付金ではありません。そのため、原則として返済が必要です。
無利子または低利子とはいえ、返済計画を立てた上で、責任を持って利用することが求められます。
申請時には、現在の収入や家計状況、将来の返済見通しも確認されます。返済能力が著しく低い場合や、目的が不明確な場合は貸付が難しいこともあるため、まずは窓口で相談することが大切です。(参考:東京都社会福祉協議会「生活福祉資金貸付制度 福祉資金のご案内」、社会福祉法人 京都府社会福祉協議会「生活福祉資金 貸付制度ご案内」)
生活福祉資金の種類
生活福祉資金貸付制度には、支援の目的や対象に応じていくつかの種類があります。
この章では、それぞれの種類について解説します。
種類①総合支援資金

総合支援資金とは、離職や収入減少などにより生活に困窮している世帯に対して、生活を立て直すまでの期間、生活費を無利子または低利で貸し付ける制度のことです。総合支援資金は、おもに以下3つで構成されます。
- 生活支援費:失業や収入の減少により、日常生活の維持が困難になった人に対して、食費や光熱費などの基本的な生活費を一定期間貸し付ける支援
- 住宅入居費:住居を失った方や、転居が必要な人に対して、敷金・礼金・仲介手数料・家具の購入費などを貸し付ける支援
- 一時生活再建費:就職活動や就労に必要な技能習得、生活の再建にあたって必要な一時的な費用を支援する資金
収入の途絶えた人や住居を失った人が対象で、支援の幅が広いのが特徴です。貸付限度額は以下のとおりです。
- 生活支援費:単身世帯で月15万円以内、2人以上世帯で月20万円以内
- 住宅入居費:40万円以内
- 一時生活再建費:60万円以内
(参考:厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧」)
種類②福祉資金
福祉資金とは、高齢者や障害のある人、その介護を担う家族など、日常生活に何らかの困難を抱える人々を対象に、必要な費用を無利子または低利子で貸し付ける制度のことです。
福祉用具の購入や住宅改修、技能習得、さらには介護サービスの導入時に発生する初期費用など、暮らしの質を保つためのさまざまな目的に対応しています。
貸付上限額は最大で580万円とされていますが、用途に応じて異なります。(参考:厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧」)
種類③教育支援資金

教育支援資金とは、低所得世帯の子どもが高校や大学などに進学・在学する際に必要となる学費や生活費を支援する制度のことです。授業料や教材費のほか、通学にかかる交通費なども対象となるため、進学をあきらめかけている家庭にとって大きな後押しとなるでしょう。
入学に際して必要な経費である就学支度金の貸付限度額は、50万円以内とされています。教育支援費の貸付限度額は高校で月3.5万円以内、高専で月6万円以内、短大で月6万円以内、大学で月6.5万円です。ただし、特に必要と認める場合は各上限額の1.5倍まで貸付が認められる場合もあります。(参考:厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧」)
種類④不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金とは、主に自宅やその他の不動産を担保に、生活支援資金を貸し付ける制度のことです。住宅ローンや生活資金に困窮する世帯が、所有する不動産を担保として提供することで、安定した生活を維持するための資金を調達できます。
上限限度額は土地の評価額の70%程度で、月30万円以内とされています。(参考:厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧」)
生活困窮者自立支援制度を申請する流れ

制度の利用には、最寄りの自治体の福祉課や支援センターで相談を行い、必要な手続きや書類について確認することが重要です。
申請には、生活困窮の状況を証明するための書類や、支援を受けるための条件に関連する資料が必要となります。申請の流れは以下のとおりです。
- 福祉課や支援センターに相談
- 必要書類の提出
- 自立支援プランの作成
- 支援内容の提供
- 自立支援に向けたフォローアップ
支援が始まると定期的なフォローアップが行われ、進捗に応じた支援が提供されます。(参考:内閣府大臣官房政府広報室「様々な事情で暮らしにお困りのかたのための相談窓口があります!」)
生活福祉資金貸付制度を申請する流れ
生活福祉資金貸付制度は、各都道府県または市区町村の福祉事務所が窓口となります。まず、最寄りの福祉事務所や社会福祉協議会に相談し、申請に必要な書類や手続きについて確認しましょう。
申請には、本人確認書類や収入証明書、住民票などに加えて、収入状況や生活状況などを証明する資料も提出します。申請する流れは、以下のとおりです。
- 福祉事務所に相談
- 必要書類の提出
- 審査の実施
- 貸付の決定と契約
- 貸付交付
- 返済開始
生活困窮者自立支援制度を利用することで、必要な支援を受けながら自立に向けた第一歩を踏み出せます。まずは福祉課や支援センターに相談し、適切な支援を受けるための手続きを進めましょう。(参考:社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会「福祉資金 生活福祉資金貸付制度」)
まとめ:生活困窮者自立支援制度と生活福祉資金貸付制度の違いを理解しましょう
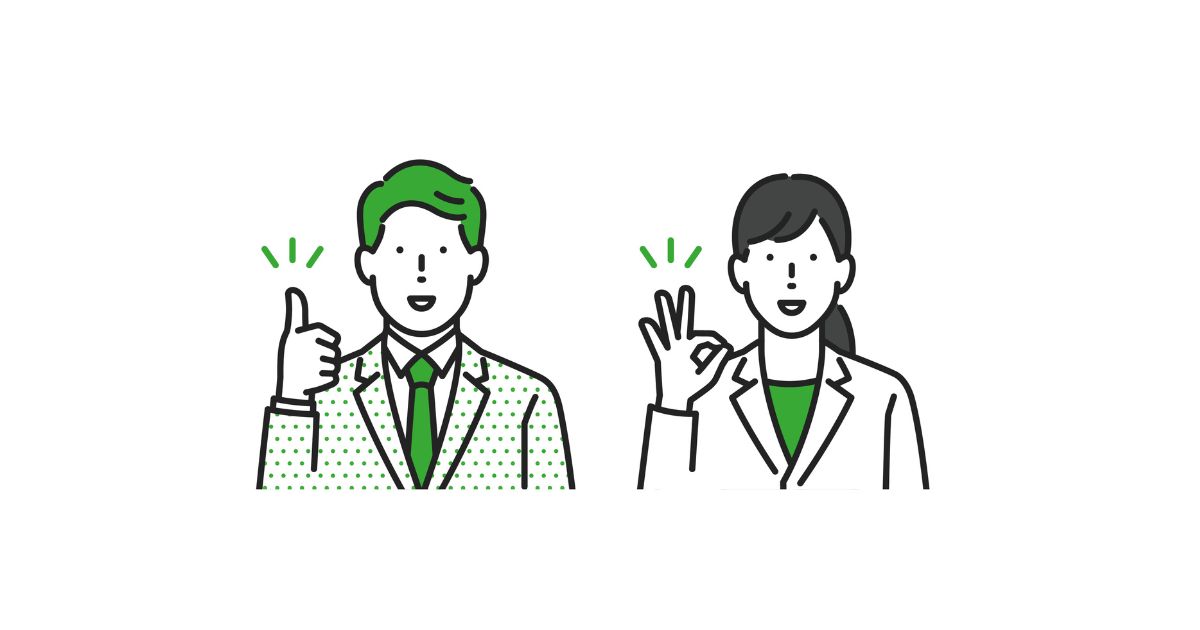
生活困窮者自立支援制度と生活福祉資金貸付制度には、それぞれ対象者に対する条件が設けられています。
生活困窮者自立支援制度は、経済的困窮が続く人々に向けた支援を行う一方、生活福祉資金貸付制度は、低所得者や障害者、高齢者世帯に対し一時的な資金支援を行う制度です。
このように、両制度にはそれぞれ異なる支援の形があります。自分の状況に合った支援を受けることで、生活の安定や自立を目指す手助けになります。
まずは、各制度の内容をしっかり理解し、必要な場合には早めに申請するのがオススメです。自分一人で悩まず、制度を活用して新たな一歩を踏み出してみてください。
生活困窮者自立支援制度と生活福祉資金貸付制度の違いを教えてください。
生活困窮者自立支援制度は自立支援そのものを目指すのに対し、生活福祉資金貸付制度は、資金の貸付を通じて生活の安定を支えるという点で異なっています。
詳細については、こちらで解説しています。
生活困窮者自立支援制度の支援内容を教えてください。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→