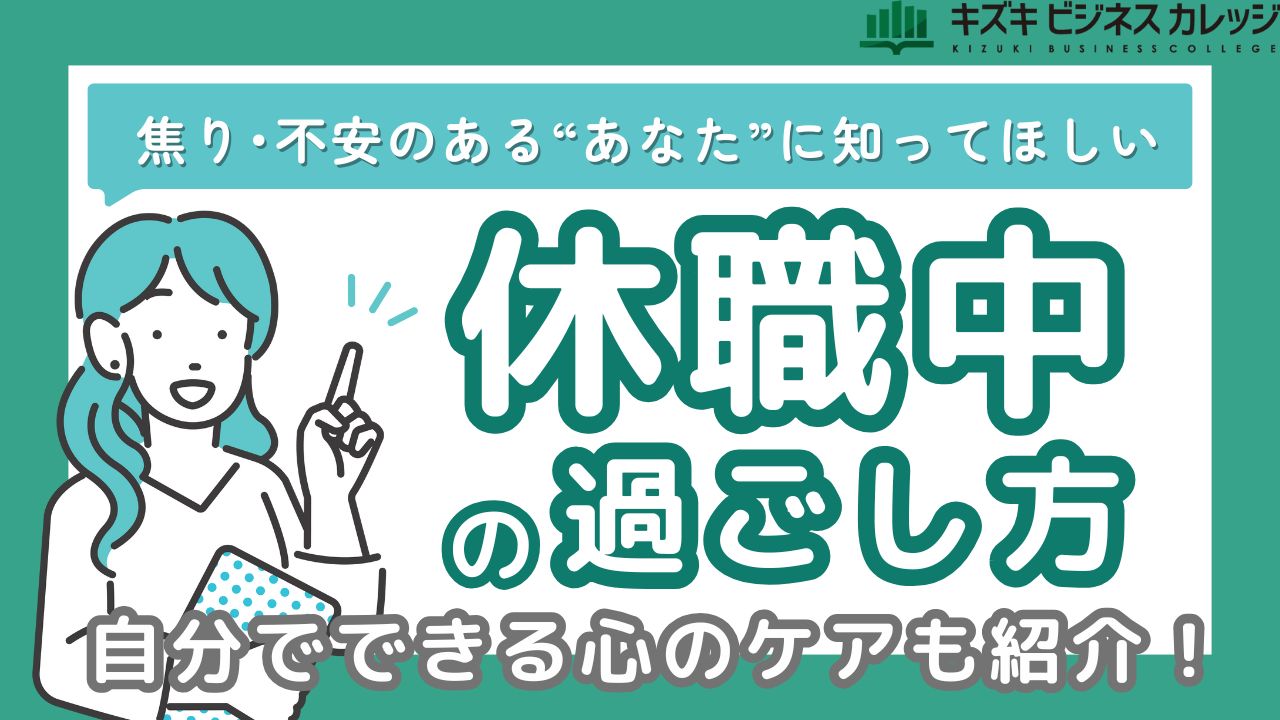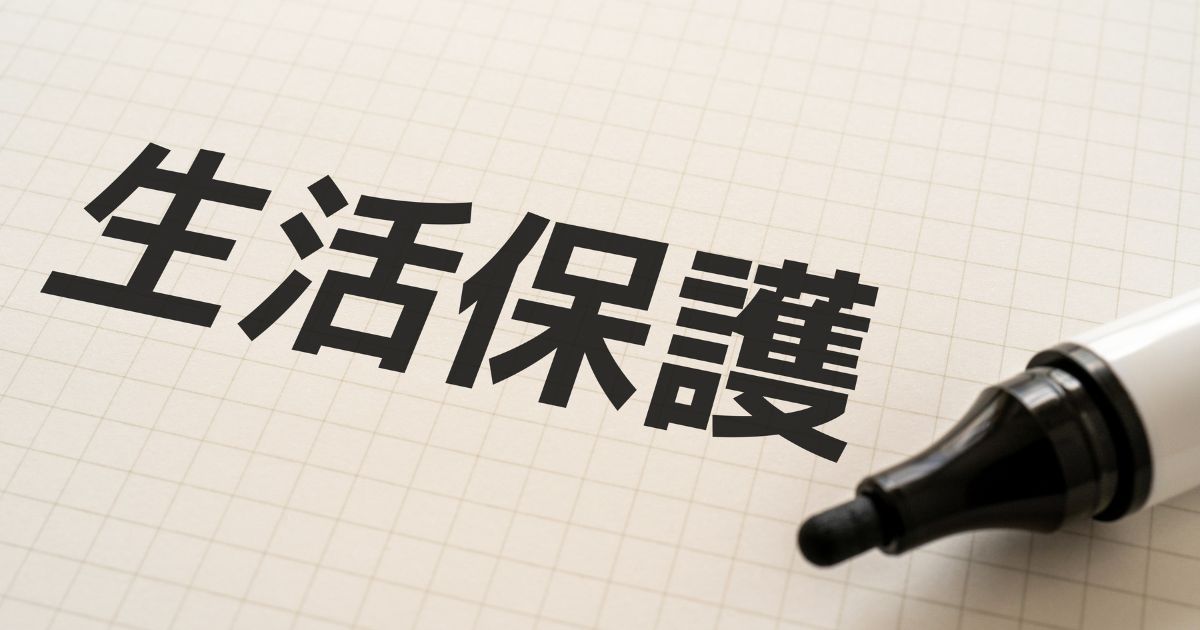PTSDのある人が仕事を続けるコツ 向いてる仕事を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC) です。
PTSDのあるあなたは、仕事をすることについて、さまざまな不安や疑問があり、以下のように悩んでいるのではないでしょうか?
- PTSDで休職中だが、復職できるか心配...
- PTSDと思われる症状があるが、仕事は続けられるのだろうか?
- PTSDでもできる仕事はある?
このコラムでは、PTSDの概要や症状、原因、診断基準、治療方法に加えて、PTSDのある人が仕事を続けるコツや向いている仕事・職場環境について解説します。
あわせて復職する際のポイントや支援制度、支援機関も紹介します。参考になれば幸いです。
PTSDのあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
PTSD(心的外傷後ストレス障害)とは?
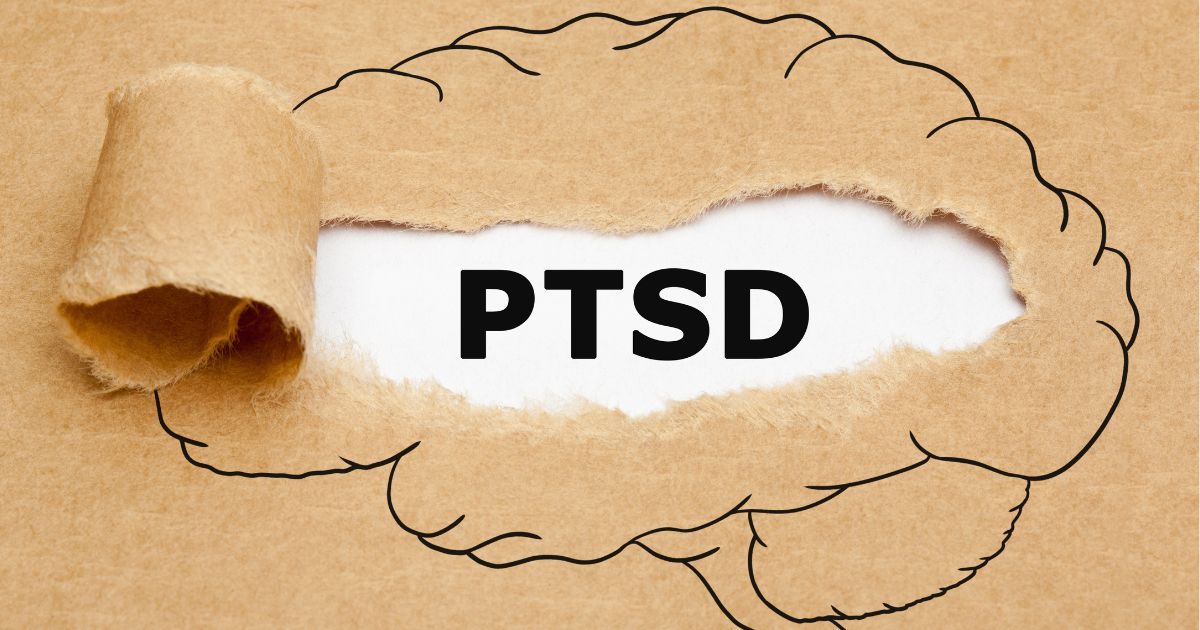
PTSD(心的外傷後ストレス障害、Post Traumatic Stress Disorder)とは、死の危険や極度の恐怖を感じる出来事に直面したことで、そのショックが心身に影響を及ぼす精神障害のことです。(参考:国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 「こころの情報サイト こころの病気を知る - PTSD」)
また、生死に関わる体験だけでなく、その出来事を目撃した場合や、身近な人に起きたことを知ることもPTSDの発症のきっかけになり得ます。
PTSDの場合、一度体験した恐怖や不安が、本人の意思とは無関係に繰り返しよみがえる、悪夢が続く、現実感が薄れるなどの症状が現れることがあります。
これらの症状は、生死に関わる体験をした人に多くみられますが、多くは一過性であり、数ヶ月で落ち着く場合も少なくありません。
しかし、PTSDの場合は時間が経っても症状が消えなかったり、ますます辛くなったりすることが特徴です。
PTSDの症状
PTSDは、その特有の症状によって、日常生活や仕事においてさまざまな困難を引き起こすことがあります。
この章では、PTSDの症状について解説します。(参考:国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 「こころの情報サイト こころの病気を知る - PTSD」、文部科学省「CLARINETへようこそ 外傷体験とは」、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 行動医学研究部「PTSDとは」)
症状①侵入症状
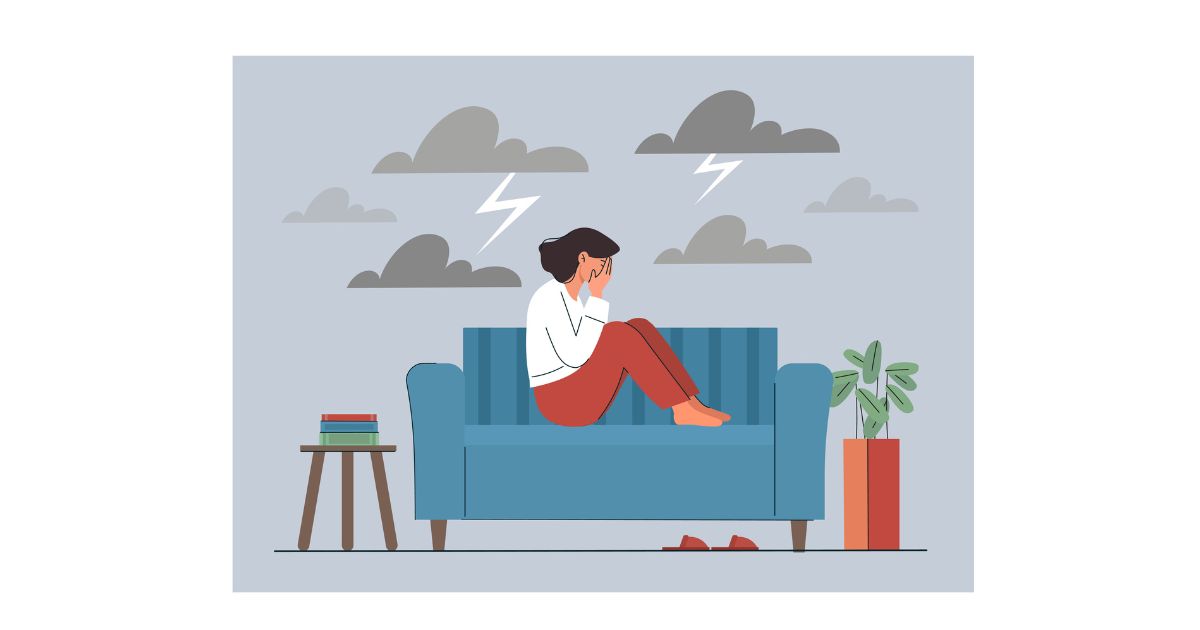
侵入症状とは、本人の意識とは無関係に、過去のトラウマ体験が突然よみがえる現象のことです。
当時の出来事を再び体験しているような感覚に陥るフラッシュバックと呼ばれる現象や悪夢など、日常生活において予期せぬタイミングで症状が出ることがあります。
症状②回避症状
回避症状とは、トラウマ体験を思い出させる状況や場所、人、話題を避ける行動のことです。
トラウマに関連する記憶を無意識に避けるため、自分でも気づかないうちに生活範囲が狭まり、孤立してしまうことも少なくありません。
また、記憶が一部消えて、当時の出来事が思い出せなくなることもあります。
症状③過覚醒症状

過覚醒症状とは、常に神経が張り詰めた状態が続くことを指します。
周囲の状況に過敏になり、常に不安感やイライラを感じるようになります。
また、過去のトラウマ体験を思い出すような音や動作を敏感に察知するため、リラックスするのが難しくなります。そのため眠りが浅くなったり、悪夢を見たりすることもあります。
過度の警戒心から人との交流を避けたくなり、孤立感を深める要因となることもあります。
症状④認知と気分の陰性化
認知と気分の陰性化とは、感情が麻痺したように感じ、自分や周囲に対する否定的な見方が強くなる症状のことです。
これまで周囲に抱いていた愛情や優しさが感じられなくなったり、自己評価が極端に低くなったりすることが多く見られます。
活動の意欲も低下するため、仕事でのチャレンジ精神を失い、周囲からの誤解を招くことも少なくありません。
PTSDの原因

PTSDは、以下のような特定の出来事に遭遇した場合、もしくは脅威にさらされた場合に発症しやすくなるとされています。(参考:国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 行動医学研究部「PTSDとは」)
- 生死に関わる事故
- 犯罪被害
- 災害
- 性的暴行
- 戦争や紛争などの戦闘体験
- テロ攻撃
- など
共通しているのは死の危険に直面した体験であり、深刻な恐怖を伴っていることです。
また、被害の後に社会的サポートが不足していたり、ストレスの多い環境に置かれていたりすると、PTSDのリスクが高まることがわかっています。
さらに、恐怖反応の引き金となりやすいアドレナリンが分泌されやすい人なども、PTSDのリスクが高いとされています。
PTSDの診断基準
PTSDの診断は、一般的に「DSM-5 TR(精神疾患の診断・統計マニュアル)」に基づいて行われます。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 TR精神疾患の診断・統計マニュアル』)
侵入症状、回避症状、過覚醒症状、認知と気分の陰性化、それぞれの項目で該当するものが1つ、または2つ以上あり、症状が1ヶ月以上持続していること、さらに、その症状により日常生活や社会生活に支障をきたしている場合、PTSDと診断されます。
PTSDの治療方法
この章では、PTSDの治療方法について解説します。
治療方法①精神療法

PTSDの治療において、精神療法は重要な役割を担っています。中でも、認知行動療法の1つである持続エクスポージャー療法やEMDR療法(眼球運動による脱感作と再処理法)はPTSDに効果がある治療方法として知られています。
持続エクスポージャー療法は、恐怖の元となった場面を安全な環境で再現し、段階的に恐怖を克服していく治療方法です。
専門家のもとであえてトラウマ体験を思い出したり、体験について語ったりすることで、「その出来事はもう危険ではない」と体感的に学んでいきます。(参考:厚生労働省「PTSD(心的外傷後ストレス障害)の認知行動療法マニュアル(治療者用)」)
EMDR療法とは、眼を左右に動かしたり、タッピングや音で左右を刺激することで、過去の記憶を再処理する治療法です。
脳の適応的情報処理モデルに基づく治療法で、健全な情報処理を助ける効果があるとされています。(参考:日本EMDR学会「EMDRとは」)
治療方法②薬物療法
薬物療法は、PTSDの症状を和らげるために有効な治療方法とされています。
特に、PTSDによる不安、うつ状態、睡眠障害には、SSRIなどの抗うつ薬や抗不安薬が用いられることが多くあります。(参考:国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター ストレス・災害時 こころの情報支援センター「IPAP Post-Traumatic Stress Disorder アルゴリズムの解説」、北海道「PTSDについて」)
ただし、薬の副作用には注意が必要です。特に服薬の初期には、頭痛や焦燥感が現れる場合があります。主治医と相談しながら、自分に合った治療方法を見つけることが大切です。
PTSDと複雑性PTSD、急性ストレス障害(ASD)との違い
この章では、PTSDと複雑性PTSD、急性ストレス障害(ASD)との違いについて解説します。
PTSDと複雑性PTSD(複雑性心的外傷後ストレス障害)との違い

複雑性PTSD(複雑性心的外傷後ストレス障害、Complex Post Traumatic Stress Disorder、CPTSD)とは、通常のPTSDの症状に加えて、感情や対人関係に影響を及ぼす精神障害のことです。(参考:公益財団法人日本心理学会「機関誌 心理学ワールド97号 複雑性PTSD」)
PTSDと複雑性PTSDの違いは、発症のきっかけとなったトラウマ体験の機関と反復性です。短期的なトラウマ体験によってPTSDが引き起こされるのに対し、長期的なトラウマ体験によって複雑性PTSDが引き起こされます。
複雑性PTSDは、児童期からの虐待やいじめ、DVなど、長期間にわたり何度もトラウマを経験した人に多く見られるとされています。
複雑性PTSDは、フラッシュバックなどのPTSDの症状に加えて、感情のコントロールが難しくなる、自己を否定的に捉える、対人関係がうまく築けなくなるなどの症状が現れます。
これにより、日常生活や仕事に支障をきたす場合があるため、PTSDと同様に早期の対応が重要です。
PTSDと急性ストレス障害(ASD)との違い
急性ストレス障害(ASD、Acute Stress Disorder)とは、災害や事故など強いストレスを受けた後に、フラッシュバック、回避行動、情緒不安定などの症状が現れる精神障害のことです。(参考:文部科学省「CLARINETへようこそ 外傷体験とは」、文部科学省「災害や事件・事故発生時における子どもの心のケア」)
PTSDと急性ストレス障害(ASD)は、どちらもトラウマ体験に対する反応として現れる病気です。症状も似ていますが、症状が持続する期間には違いがあります。
多くの場合、急性ストレス障害(ASD)は、トラウマ体験から1ヶ月未満で症状が現れ、1ヶ月以内に改善します。(参考:文部科学省「CLARINETへようこそ 外傷体験とは」)
一方でPTSDは、1ヶ月以上経過しても症状が続きます。また、PTSDの場合、トラウマ体験から数ヶ月、数年経ってから症状が現れることもあります。(参考:国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 「こころの情報サイト こころの病気を知る - PTSD」)
1ヶ月以上続く場合はPTSDの可能性があり、日常生活や仕事により大きな影響を与えることがあります。専門的な診断や長期間にわたる治療が必要です。
PTSDでも働ける?:PTSDのある人が仕事を続ける2つのコツ
PTSDのある人でも、適切なサポートと環境があれば仕事を続けることは可能です。
この章では、PTSDのある人が仕事を続けるための具体的なコツについて解説します。(参考:独立行政法人労働者健康安全機構「職場における災害時のこころのケアマニュアル」)
コツ①職場環境を調整する

PTSDの症状を最小限に抑えるためには、職場環境を整えることが重要です。
PTSDのある人は、フラッシュバックを引き起こすような状況を避けることが、仕事を続ける鍵となります。
まずは職場の上司や同僚とコミュニケーションを取り、業務内容やスケジュールで配慮してほしい点を共有しましょう。上司や同僚からの理解を得ることで、例えば、静かな作業環境や体調に合わせた勤務時間など、柔軟な対応をとってもらえる場合があります。
また、恐怖心や不安が続く場合は、職場の産業医やカウンセラー、外部の支援機関に相談することも重要です。専門家に協力を仰ぎ、できる限り不安要因を取り除いてもらいましょう。
コツ②休職を検討し治療に専念する
PTSDの症状が深刻な場合は、無理せず休職を検討することも大切です。一旦職場を離れて自身の治療と回復に専念することで、症状の改善を図ることができるでしょう。
休職中は医師やカウンセラーなどの専門機関や職場との連携を図りながら、自分のペースで治療を進めることが重要です。
PTSDのある人に向いている仕事・職場環境
この章では、PTSDのある人に向いている仕事や職場環境について解説します。
適切な仕事や職場環境を選ぶことで、フラッシュバックなどのPTSDの症状悪化を防ぐことができるはずです。(参考:日本赤十字社「PFA(Psychological First Aid:心理的応急処置)リーフレット」)
仕事①業務スケジュールに融通が利く仕事

PTSDのある人には、業務スケジュールに柔軟性がある仕事が向いています。
自分の体調に合わせて勤務時間を調整できることは、大きな安心材料になります。
特にパートタイムやフレックスタイム制、さらには在宅勤務などの選択肢がある職場は、症状に応じて働くペースを調整できるので、心身への負担が少なく働くことができるかもしれません。
また、在宅勤務は通勤によるストレスを回避できるメリットもあるでしょう。
仕事②外部との接触が少ない仕事
業務内容が比較的静かで、外部との接触が少ない仕事も、PTSDのある人にはオススメです。
例えば、データ入力やプログラミングなど、一人で集中して取り組める作業は、外部からの刺激が少なく、フラッシュバックなどPTSDのリスクを減らすことができます。
また、対人関係のストレスが少なく、自分のペースで進められる点も症状の悪化を防ぐポイントです。
仕事③コミュニケーションが取りやすい仕事

PTSDのある人にとって、コミュニケーションがスムーズに取れる職場環境も重要です。特に、職場での相談がしやすく、上司や同僚がPTSDへの理解を示してくれる環境は、不安やストレスの軽減に繋がります。
また、万が一職場でPTSDの症状が現れた場合でも、安全確認や傾聴など、適切な処置ができ、必要であれば支援機関につなげる体制が整っていることもポイントです。
PTSDのある人が安心して仕事を続けるためには、周囲の協力が不可欠であると言えるでしょう。
PTSDのある人が復職する際の3つのポイント
PTSDのある人が復職する際には、適切な準備とサポートが欠かせません。
この章では、PTSDのある人が復職する際のポイントについて解説します。
ポイント①無理のないタイミングを見極める

休職して初期の段階は、まずはしっかりと休むことに集中しましょう。「休むことが仕事」と考えて、生活リズムには過度にこだわらず、心身をリラックスさせることが大切です。
しっかり休んで症状が落ち着いてきたら、徐々に生活リズムを整えていきましょう。早寝早起きや軽い散歩など、少しずつ規則正しい生活を心掛け、社会復帰に向けた準備を進めていきます。
復職のタイミングは自己判断せず、必ず医師に相談しましょう。職場によっては診断書の提出が求められる場合もあります。
復職に焦りは禁物です。休職期間は心身を休ませることを最優先にして、少しずつ復職後を想定した過ごし方に移行していきましょう。
ポイント②リワークプログラムを利用する
リワークプログラムを活用することも、復職をスムーズに進めるためには有効です。
リワークとは、「return to work」の略で、病気や障害が原因で休職中の人を対象に行う、復職や転職、再就職に向けたリハビリテーションのことです。リワークプログラムと同じ意味で、復職支援プログラムや職場復帰支援プログラムという名称が使われることもあります。
リワークは、医療機関、地域障害者職業センター、企業内、就労移行支援事業所、自立訓練で実施されています。
それぞれの機関によってプログラムの内容は異なりますが、復職後の安定した勤務を目的としている点は共通しています。
医師と相談しながら、自分に合ったリワークを活用することで、職場復帰を円滑に進めることができます。
なお、リワークは参加前に見学できる場合がほとんどです。実際のプログラムを見て、参加できそうかを判断することも大事なプロセスです。
ポイント③負担の少ない仕事から始める

復職後は、負担の少ない仕事から徐々に慣らしていきましょう。すぐにフルタイムで働き始めるのは避け、短時間勤務から始めるのがオススメです。
また、職場に試し出勤制度があれば、ぜひ利用を検討してみてください。試し出勤制度とは、正式な職場復帰の前に少量の仕事から徐々に慣れていくための制度のことです。通勤訓練や模擬出勤などを取り入れ、心身の負担を減らしながら本格的な復職に備えましょう。
復職後は周囲のサポートを受けながら、一人で問題を抱え込まないことが重要です。必要に応じて医師や支援機関に頼ることも、長期的に仕事を続けるために大切なポイントです。
PTSDのある人が利用できる支援制度8選
PTSDは、日常生活や仕事に長期にわたって影響を及ぼすことがある精神障害です。そのため生活や仕事を続けていくには、適切な支援が不可欠です。
この章では、PTSDのある人が利用できる支援制度についてご紹介します。
支援制度①自立支援医療制度

自立支援医療制度とは、心身の障害を緩和・除去するために継続的な治療が必要な人に対して、医療費の自己負担額を軽減する公的な支援制度のことです。(参考:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」)
通常、公的な医療保険による医療費の自己負担額は3割ですが、自立支援医療制度を利用すれば、収入によって異なりますが、基本的に自己負担額を1割に軽減できます。
この制度は、指定の医療機関・薬局のみで利用可能です。
支援制度②障害者手帳
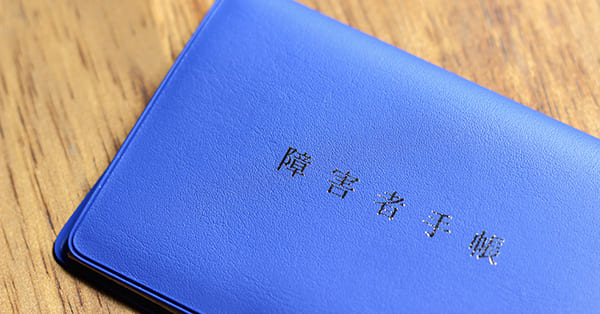
障害者手帳とは、一定以上の障害のある人に交付される手帳のことです。
障害者手帳を所持することで、障害があることの証明が可能です。障害者手帳を所持する人は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の対象として、さまざまな支援を受けられます。(参考:厚生労働省「障害者手帳について」、e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
種類は、以下のとおりです。
気になる人は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。
支援制度③傷病手当金
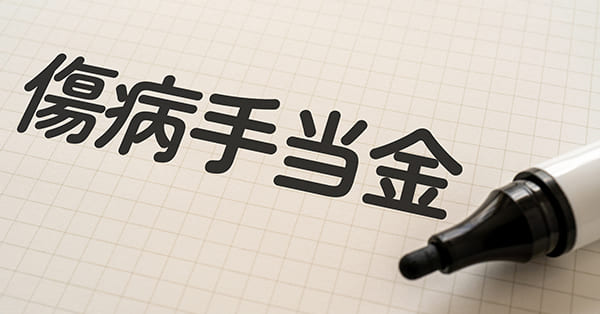
傷病手当金とは、病気やケガ、障害のために仕事を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に、健康保険(社会保険)の加入者・被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた支援制度のことです。(参考:全国健康保険協会「傷病手当金」、全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」、全国健康保険協会「傷病手当金について」)
国民健康保険の加入者・被保険者は対象外です。
対象となる病気やケガ、障害は、業務外の理由で生じた場合に限ります。会社の業務が原因で生じた病気やケガ、障害は、労災保険により補償されます。
傷病手当金の受給対象は、病気やケガ、障害によって就労不能であり、十分な報酬を受けられない人です。そのため、医師の診断書が必要です。
また傷病手当金は、退職前・在職中に就労できない状態の場合に受給できます。ただし、一定の条件を満たせば、退職後も継続して受給できます。具体的な受給金額や受給期間は、その人の休職の状況などによって異なります。
申請は、加入している全国健康保険協会や各健康保険組合、各共済組合で行えます。気になる人は、加入している健康保険の協会・組合にご相談ください。
支援制度④失業保険

失業保険(失業手当、雇用保険給付)とは、失業・退職した人が就職するまでの一定期間に給付金を支給する支援制度のことです。正式名称は、基本手当です。(参考:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」、ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」、ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」)
また、失業保険は失業した人の金銭面の不安を軽減し、求職活動に専念できるようにすることを目的としています。(参考:厚生労働省「基本手当について」)
そのため、失業保険は、退職後に就労できる状態の場合に利用できます。具体的な受給金額や受給期間は、その人の退職の状況などによって異なります。
申請は、お住まいの自治体に設置されているハローワークで行なえます。
支援制度⑤犯罪被害給付制度
犯罪被害給付制度とは、犯罪行為によって不慮の被害を受けた人を対象に、国から給付金を支給する支援制度のことです。(参考:警察庁「犯罪被害給付制度のご案内」)
PTSDなどの精神障害のある人にも障害給付金が適用される場合があり、金額は等級に応じて異なります。通常、PTSDは9級、12級、14級に該当することが多く、生活の再建に向けた経済的支援を受けることが可能です。
犯罪被害給付制度は、被害を受けた人が安心して生活を立て直すための支援制度です。利用には申請が必要ですので、条件や手続きは都道府県の警察本部、または警察署で確認してみてください。
支援制度⑥特別障害者手当
特別障害者手当とは、精神または身体に著しく重度な障害があり、日常生活において常に特別な介護を必要とする在宅生活をしている人に対して、必要となる精神的、物質的な負担の軽減を目的に、手当を支給する支援制度のことです。(参考:厚生労働省「特別障害者手当について」)
支援制度⑦特別障害給付金
特別障害給付金制度とは、国民年金に任意加入していなかったことで、障害基礎年金など受給要件を満たせず、障害年金を受給できない障害のある人に対して、福祉的措置として創設された支援制度のことです。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく給付であり、障害基礎年金や障害厚生年金とは異なる制度です。 (参考:e-Gov法令検索「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」)
支援制度⑧生活保護
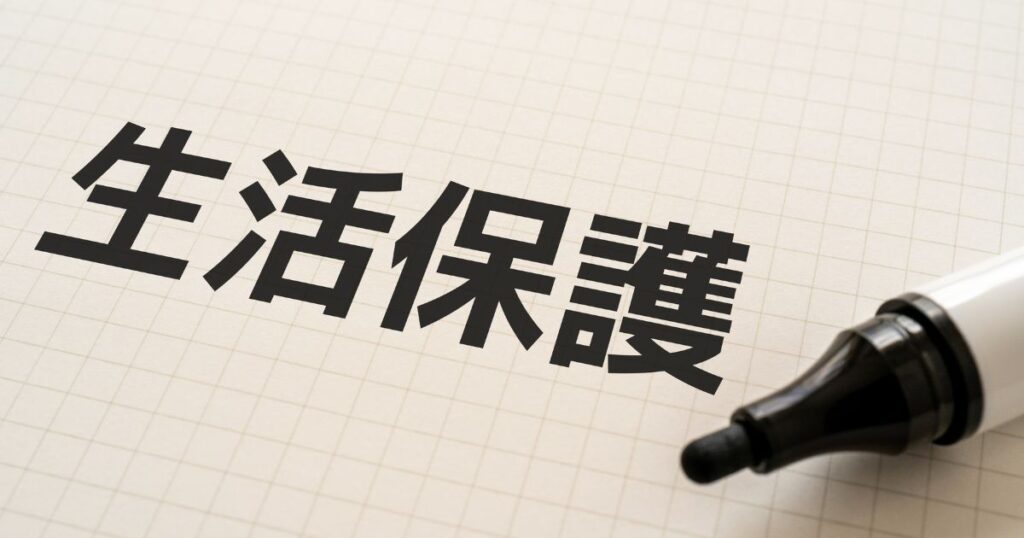
生活保護とは、生活に困窮している人や病気やケガ、障害などで就労できない人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活の保障と自立の助長を目的とした支援制度のことです。(参考:厚生労働省「生活保護制度」、厚生労働省「「生活保護制度」に関するQ&A」)
生活に必要な最低限度のお金を持つことが困難な人が、お金を受給できる制度とも言えます。
お住まいの自治体を所管する福祉事務所、またはお住まいの自治体に福祉事務所がない自治体の場合、お住まいの自治体の生活保護を担当する部署・窓口で行えます。
なお、一定の資産がある場合、申請できないため注意してください。
また、生活保護は最後のセーフティネットとも呼ばれるように、本当にサポートが必要な人だけを対象とする支援制度です。
一般的に審査が厳しく、生活保護以外の支援制度の利用を提案されたり、申請が却下されたりする可能性があることを心に留めておいてください。
PTSDのある人が利用できる支援機関6選
この章では、PTSDのある人が利用できる支援機関についてご紹介します。
PTSDについて相談できる窓口は全国に設置されています。今悩まされている症状が「PTSDかもしれない」と思った人でも活用できます。ぜひ参考にしてみてください。
支援機関①就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。実際のサービスは、国の基準を満たしたさまざまな民間の就労移行支援事業所が行います。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
就労移行支援事業所は各地にあります。私たち、キズキビジネスカレッジ(KBC)もその一つです。それぞれ特徴が異なるため、気になるところがあれば問い合わせてみてください。
支援機関②精神保健福祉センター

精神保健福祉センターとは、精神障害のある人のサポートを目的とした、地域の精神保健福祉の中核を担う支援機関のことです。(参考:東京都福祉保健局「精神保健福祉センターとは」、e-Gov法令検索「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)
精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)に基づき、各都道府県に設置されています。地域によって、こころの健康センターや心と体の相談センターなど、一部名称が異なります。
精神保健福祉センターでは、精神疾患に関連する悩みの相談や社会に適応するための指導と援助を行っています。
精神障害による症状で悩んでいる本人だけでなく、ご家族や周囲の人の相談も受け付けています。また、匿名での相談も受け付けています。医師から正式な診断を受けていなくても相談は可能です。
詳しくは、お住まいの自治体の精神保健福祉センターにお問い合わせください。
支援機関③地域障害者職業センター

地域障害者職業センターとは、病気や障害のある人に対して、職業評価や職業指導、職業準備訓練、職場適応援助などの専門的な職業リハビリテーションを提供する支援機関のことです。(参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センターによる支援」、厚生労働省「地域障害者職業センターの概要」)
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しており、障害者雇用促進法に基づいて、全国47都道府県に設置されています。(参考:厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律」)
ハローワークや医療・福祉機関と連携しているため、仕事に関する相談や訓練、復職するためのサポートを行っています。
病気や障害に悩む当事者だけでなく、障害のある人を雇用する事業所に対して、雇用管理に関する相談・援助も行っています。
支援機関④障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターとは、雇用や保健、福祉、教育に関する関係機関と連携し、障害のある人の雇用の促進・安定を目的とした一体的な支援を行っている支援機関のことです。(参考:厚生労働省「障害者就業・生活支援センター」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」、厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」)
障害のある人の就職活動の支援や求人の紹介、職場定着のためのサポートなどを行います。
就業面だけでなく、金銭管理などの経済面や生活面のことまで、日常および地域生活に関する支援も行っています。
生活習慣や金銭管理、健康管理などについても幅広く相談できるため、生活面のサポートも受けたい人にオススメです。
2024年4月1日時点で、障害者就業・生活支援センターは全国に337箇所設置されています。
支援機関⑤DV等に対する相談窓口
DV被害に対する相談窓口として、自治体ごとに配偶者暴力相談支援センターが設置されています。このセンターでは、DV被害を受けた人の相談支援や一時保護、自立支援などを行なっています。(参考:内閣府男女共同参画局「配偶者暴力相談支援センター」)
DV相談ナビ「#8008」に電話をかけると、全国どこからでも最寄りの配偶者暴力相談センターにつながります。
また、内閣府が設置しているDV相談プラスでは、電話のほか、メールやチャットでも24時間相談を受け付けています。(参考:内閣府「DV相談プラス」)
専門の相談員によるカウンセリングや援助を受けることができます。ぜひ活用してみてください。
支援機関⑥犯罪被害に対する相談窓口

犯罪被害の中でも、特に性犯罪の被害を受けた人のために、「#8103(ハートさん)」と「#8891(はやくワンストップ)」という全国共通の短縮ダイヤルがあります。(参考:警視庁「犯罪被害等に遭われた方へ 性犯罪被害<性被害の相談>」、内閣府男女共同参画局「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」)
電話をかけることで、最寄りの性暴力被害者支援センターに直接つながり、産婦人科医療やカウンセリング、法律相談などの専門的なサポートを受けることができます。相談者のプライバシーを尊重した相談窓口で、通話料も無料で利用できます。
性犯罪被害のほかにも、身体的な被害や交通事故などに関する相談窓口について、警察庁のポータルサイトで公開しています。(参考:警察庁「犯罪被害者等施策」)
ぜひ確認してみてください。
PTSDのある人への接し方の2つのポイント
PTSDのある家族や友人、同僚などと接する際、どのようにサポートしたらよいのか悩む人も多いのではないでしょうか。
この章では、PTSDのある人と接する際のポイントについて解説します。(参考:厚生労働省「家族や友達がPTSDになったとき」)
ポイント①話を聞くときは傾聴する

PTSDのある人と接する際に大切なのは、まずその人の話をじっくりと聞くことです。
話を聞く際には、相手の話を中断せずに受け止める傾聴の姿勢が求められます。
よかれと思って伝えた一般的な励ましの言葉が、かえってその人を傷つけることもあります。相手の言葉を否定せず、寄り添う姿勢で話を聞くことで、安心感を生むことができるでしょう。
ポイント②一人で抱え込まない
PTSDのある人と接することで「この人を理解できるのは私だけ」と、重い責任を感じる場面もあるかもしれません。
しかし、そのような思い込みはとても危険です。すべてを一人で抱え込み、解決しようとするのは大きな負担となります。
4複数の人と協力し合いながら支援の輪を広げることで、PTSDへの理解も深まり、長期的で無理のないサポートが可能となります。
まとめ:PTSDがあっても仕事は続けられます

PTSDは長期的な治療とサポートが必要な精神障害ですが、適切な職場環境や周囲の理解やサポートがあれば、仕事を続けることは可能です。
今悩まされている症状の原因が、過去の辛い経験だと気づかない場合もあります。少しでも症状に気づいたときは専門家に相談するなど、一人で抱え込まないことが大切です。
このコラムが、PTSDで悩んでいるあなたの不安や疑問を解消する一助となれば幸いです。
PTSDとは、何ですか?
PTSD(心的外傷後ストレス障害、Post Traumatic Stress Disorder)とは、死の危険や極度の恐怖を感じる出来事に直面したことで、そのショックが心身に影響を及ぼす精神障害のことです。
詳細については、こちらで解説しています。
PTSDの症状を教えてください。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→