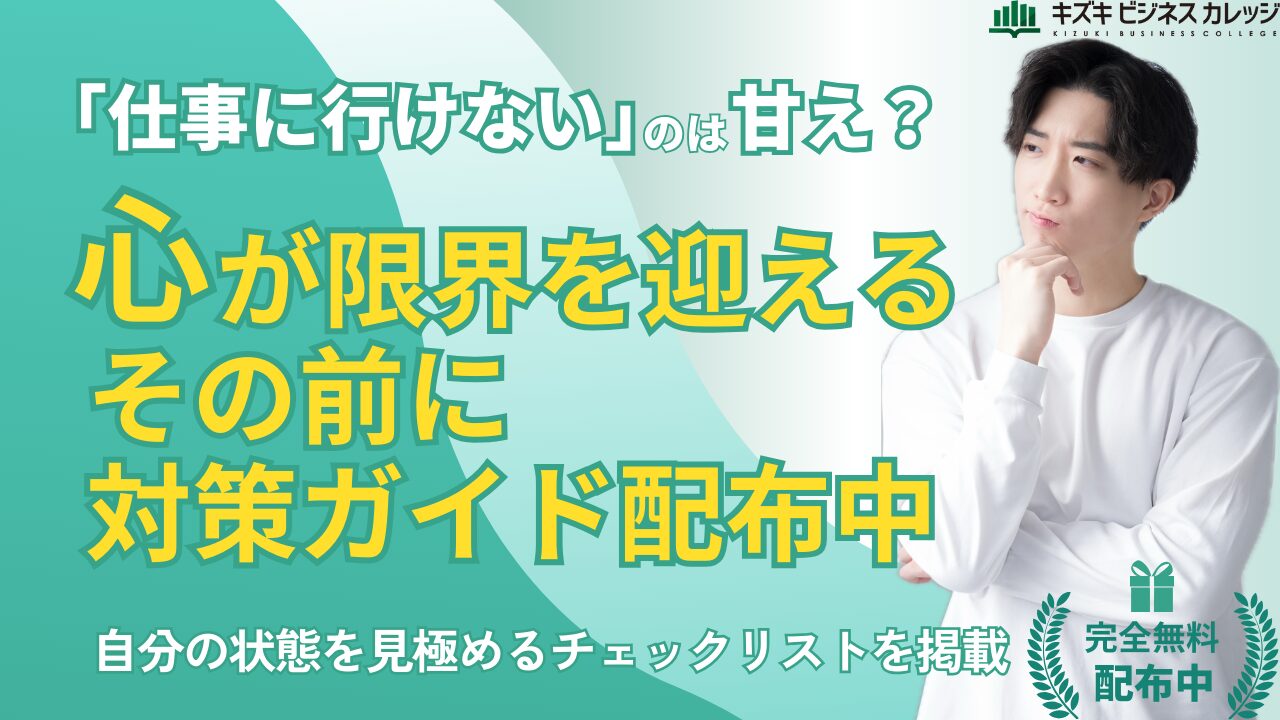復職の不安を減らしたいあなたへ 不安への対処法を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)利用者の山田です。
- 復職してもまた失敗するんじゃないか?
- みんな頑張って働いているのに、自分だけ取り残されているようだ
あなたも、このような不安を感じているのではないでしょうか?
メンタルヘルスの不調から休職する人は少なくありませんが、多くの場合、医療機関を経て少しずつ回復し、仕事のことを考えられるようになります。休職を選択したことで、良い結果に繋がることもあるでしょう。
しかし、休職後は休職前までの苦しい経験などから、不安が湧いてくるのも当然のことです。
このコラムでは、不安になった時の対処法や、復職準備のポイントなどについて解説します。あわせて、実際に復職した人の事例も紹介します。
ひとりで不安に襲われた時などに、よければ読んでみてください。
復職に不安を感じているあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
休職後に陥りがちな復職に関する不安
休職後は、自分の理想の姿と現在の姿のギャップに落ち込み、不安にさいなまれることもあるでしょう。
不安とは、誰もが生活の中で感じる当たり前の感情の一つです。しかし、不安の強さや続く時間、不安によってあらわれる身体症状は、人それぞれ異なります。
仕事を辞めた後は、以下のような思考に陥ることで不安を感じる人も多いでしょう。
不安①自分に対して厳しい評価をしてしまう

休職する前、多くの人は、調子が悪くても何とか仕事をこなそうと頑張っていたのではないでしょうか?
しかし、うつ病などの精神疾患の症状により、以前は出来ていた仕事や日常生活が、思うように出来なくなることがあります。そのため、自分自身に対して「仕事ができない」「だらしない」といった厳しい評価をして、自信を失いがちです。
「私に出来る仕事はあるのか?」と不安にもなるでしょう。「友達は皆、今頃働いているのか」と想像し、休んでいる自分と比較して落ち込むかもしれません。
しかし、自分への厳しい評価は、回復途中の心を自ら攻撃するようなもの。症状の悪化につながることもあるため、そんな不安への対処法を身に着けましょう。
復職に関する不安への対処法については、こちらで解説しています。
不安②自分の存在価値がわからなくなる
休職中は、社会との繋がりが希薄になりがちです。人間関係のストレスから解放される一方で、心配してくれる人、一緒にいてくれる人、感謝してくれる人との関わりが減ることもあるかもしれません。
何かしらの役割を担い、社会に必要とされているという感覚は心の健康にとって重要です。しかし休職後は、その感覚を保つことが難しくなるでしょう。
気分がふさぎ、自分自身をありのままに見ることが難しくなると、不安にもなりやすくなります。「今の私は、自分の存在価値がわからなくなっているんだな」と、一旦その気持ちを受け入れましょう。
体調が安定してきたら、これまでの経験やスキルを整理し、自身の役割や今後のプランについて考えてみてもよいでしょう。
復職に関する不安への対処法6選
不安な気持ちでいっぱいになると、「働きたくない」「働くのが怖い」と感じますよね。感情的に自分を責めるなど、辛い時間が続くこともあるでしょう。
この章では、すぐに取り組めるものを中心に、復職に関する不安への対処法について解説します。あなたに合う方法を見つけてみてください。
対処法①不安を書き出す

1つ目は、不安な気持ちを書き出す方法です。ひとりで気軽に取り組むことができます。原因や感情が整理されることで、不安の軽減につながるでしょう。代表的な方法として、ジャーナリングという手法があります。
ジャーナリングとは、頭に浮かんでくる考えや感情を紙などに書いていくことで、他者の反応を気にせずに心を整理する方法のことです。書く瞑想とも言われ、メンタルヘルスや仕事の効率向上に広く活用されています。
不安についてパッと頭に浮かんだ事実や気持ちを、自由に紙に書き出しましょう。書いているうちに不安というテーマから離れていっても、問題ありません。5分、15分と、あらかじめ時間を決めておき、その間ひたすら手を動かします。
誤字脱字や、内容の良し悪しは気にしません。頭に浮かんだことを、そのまま書くことが大切です。
書き終えたら、内容を振り返りましょう。何度も書いている内容やキーワードに気がつく、忘れていた対処法を思い出す、といったことがあるかもしれません。ペンの色を変えて、コメントを書き込んでも良いでしょう。
ネガティブな内容を読み返すのが辛いと感じたら、振り返らずに終えても大丈夫です。
最近では、ジャーナリング用のスマートフォンアプリ等も登場しています。はじめやすい方法で、まずは不安を書き出してみましょう。
対処法②誰かに聞いてもらう
2つ目は、書く代わりに、話す方法です。信頼できる相手がいれば、その人に不安な気持ちを聞いてもらいましょう。
愚痴を聞いてもらってスッキリしたという経験はありませんか?不安について誰かに話すという行為も、感情が発散され、同様の感覚を得ることが期待できます。
加えて、聞いてくれる相手がいるという実感が、安心感につながります。「わかってもらえた」「大切にしてもらえた」と思い、孤独感が軽減するかもしれません。
また、相手から質問や確認などの反応があれば、気持ちの整理が進むこともあるでしょう。
ただし、話す相手が適切でないと、悲しい思いをしてしまう可能性もあります。できれば、離職の経緯や、メンタル不調の状況を理解してくれそうな誰かに、聞いてもらいましょう。
信頼のおける医師やカウンセラーに聞いてもらうのもよいでしょう。相談先についてはこちらで紹介します。
対処法③必要以上に考えないため、注意を逸らす

「上司に嫌われるかもしれない」などとネガティブな想像が頭をよぎり、不安になることもあるでしょう。
将来起こりそうな問題を想像することは、必要な時もあります。しかし、ネガティブな側面ばかりに注目し、同じことを延々と思い悩むと、不安や後悔が増すばかりで悪循環におちいりかねません。
まずは、「必要以上に考えすぎているな」と気がつくことが大切です。これ以上考えても分からないことは、考えないようにしましょう。
考えすぎることを止めるためには、不安と関係のない行動をして、注意を逸らしましょう。動画を見る、絵を描く、カラオケに行くなど、好きなことをしてみてください。他のことを考えるよりも、行動に意識を向ける方が、簡単に注意を逸らせるはずです。
筆者の場合は、ラジオを聞きながらスーパーへ買い物に行くことが多いです。黙々と掃除をしたり、何かを磨いたりして、達成感を味わうという手もあります。また、運動をするのも効果的です。スポーツや筋トレなどに打ち込み、汗を流してもいいでしょう。
必要以上に考え続けることは、時間やエネルギーを浪費するだけでなく、心身に悪影響を与えかねません。好きな行動に切り替えることで、上手く注意を逸らしていきましょう。
対処法④ネガティブな感情も、価値観を知る手がかりと捉える
ネガティブな感情に触れ続けるのは、良くありません。しかし、そういった感情も常に否定するのではなく、時には掘り下げることで、自分を知る手がかりになるでしょう。
例えば「〇〇が怖い」という感情について「なぜ?」と問い続けていきます。すると、自分が失いたくないもの、大切にしていることに紐づいていることがあります。
他にも、生きづらいという感覚がある場合は、本来自分が望んでいる環境が別にあると考えられます。
日々の生活の中で「嫌だ」「生きづらい」と感じることを書きとめ、それらをひっくり返していきましょう。自分が本当はどうありたいのか、望む環境や社会が見えてくるかもしれません。
このように、ネガティブな感情も自己理解に繋げることができれば、今後の仕事の選択にも活きてくるでしょう。
対処法⑤休職したことのメリットを考える
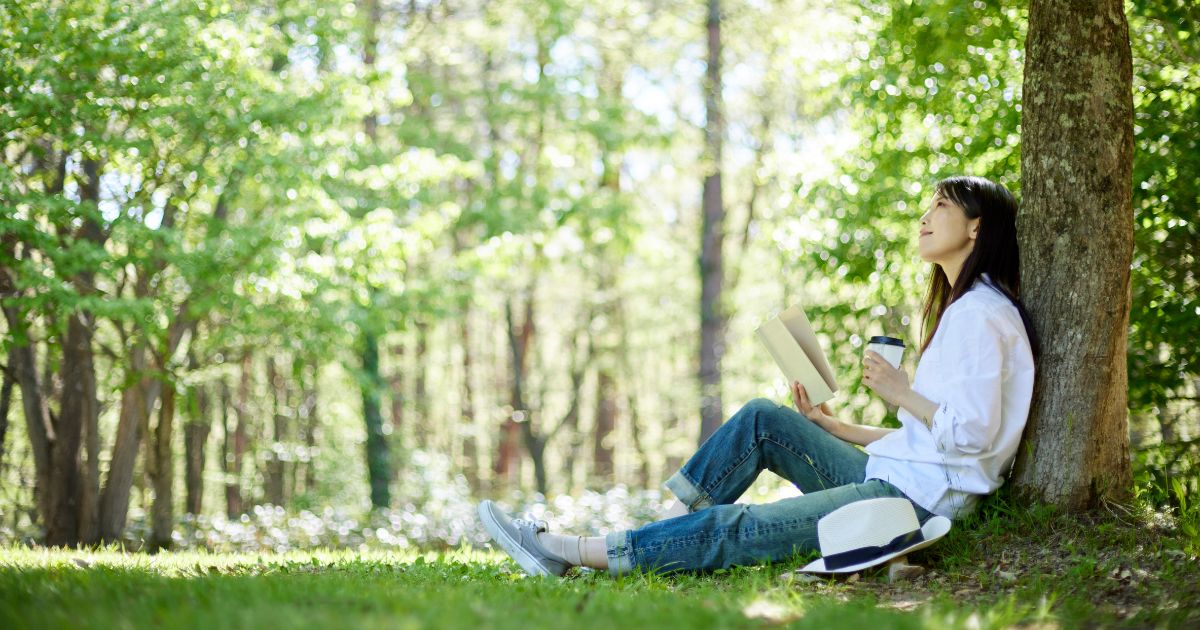
休職したことを後悔しそうな時は、メリットの方に目を向けてみましょう。主なメリットは2つ考えられます。
1つ目は、休職期間を自由に過ごせる点です。
会社に対して責任を負うことなく、自由に休み、学ぶことができます。自分の感覚や気分に従って、予定を変えることも可能です。体調が回復すれば、短期の仕事やボランティア、旅行などもできるかもしれません。「自分のために行動した」「好きなだけ考えた」といった感覚は、復職後の納得感にもつながるでしょう。
2つ目は、環境を大きく変えられる点です。
メンタル不調の再発防止を考える時、外部要因である職場環境は、重要な問題です。
予想もしていなかった出来事がターニングポイントとなり、人生が好転したという話は多くあります。一度仕事から離れた今、これまでと違ったことに興味を持ち、学び、挑戦してみるのもいいかもしれません。
対処法⑥自分ができることを意識する
休職から復職までの道のりには、いくつかの段階があります。十分に療養し、徐々に活動量を増やした後、復職に向けて動き始めるというのが大まかな流れです。焦って進めようとせず、それぞれの段階をしっかり過ごすことで、回復はより確実なものになります。
療養の段階ではしっかり休むことに集中しましょう。体力を回復させる段階では、無理に多くのことに手を出しません。
変化や成果が目に見えないと、不安になることもあるでしょう。そのような時は、チェックリストを作る、手帳に記録するなど、できたことの可視化をオススメします。「7時間以上寝た」「外に出て歩いた」など、小さなことだと思わずに、自分の今日にたくさん丸を付けましょう。
昨日は前向きに頑張っていたのに、今日は不安でやる気も出ないという人は、このような波を経験しながら徐々に回復し、復職に向かっています。段階ごとにできることをしていると、ふと気が付けば、復職に向かって進んでいるはずです。
不安な時こそ知っておきたい復職準備の3つのポイント
不安な気持ちが続くと、何もやる気が起きない時もありますよね。復職の目処が立たず、ひとりで落ち込むこともあるかもしれません。
この章では、不安な時こそ知っておきたい復職準備のポイントについて解説します。
なお、このコラムは、メンタルヘルスの不調から休職した人に向けたものです。休職中の人は、以下のコラムをご覧ください。
ポイント①しっかり休む

まずは、ここまで頑張ってきた自分を労い、しっかり休みましょう。社会的な要求から離れてダラダラと過ごし、療養する期間とわりきってください。眠くなったら寝て、目が覚めたら起き、食べたい時に食べましょう。
身近な人の優しさに触れて心が安らぐ時もあれば、ひとりが落ち着く時もあると思います。欲求に従い、好きなように過ごせるとよいでしょう。
不調が続く時、心身が普段と違う状態になり、自分らしい考え方ができないこともあります。そのような時に将来に関わる意思決定をするよりも、まずは休んで回復し、本来の自分を取り戻しましょう。
回復したと感じても、自己判断で通院や服薬を中断すると、症状の再発や悪化につながる可能性があります。主治医に相談しながら次の段階に進むことが大切です。
この時期にしっかり休むことで、心身の緊張が解け、回復に繋がっていきます。
経済的に不安がある場合、「休んでる場合ではない」と感じるかもしれません。傷病手当金や失業保険など、利用できる支援制度は活用し、療養に専念できる環境を整えましょう。
どのような制度があるか分からないという人は、以下のコラムも参考にしてみてください。
ポイント②相談できる相手や仲間を見つける
不安な気持ちは、できるだけひとりで抱え込まず、誰かに相談してみましょう。
もし身近に信頼できる人がいれば、まずは話してみるとよいでしょう。解決の糸口が見えない、誰に話したらよいか分からない場合は、公的な相談機関やカウンセラーなどを探してみてください。
具体的な相談先については、こちらで紹介しています。
また、自身と似た不安を持つ人とつながることで、気軽に相談できる仲間を見つけられることもあるでしょう。就労移行支援事業所やハロートレーニング、当事者会などを通じて、話が合いそうな人とコミュニケーションを取るのもおすすめです。
ハロートレーニングについては、こちらで解説しています。
ポイント③無理をしない働き方を考える

一度メンタル不調を経験すると、ストレスがかかる状況で「また調子が悪くなるんじゃないか」という不安が生じやすくなります。一方で復職後は、責任感や焦りから、つい頑張り過ぎる人も多くいます。
復職直後は特に、心身に負担がかからないよう、できるだけ無理をしないことが大切です。
離職中はこれまで以上に、自身の体調や気分の変化、そのきっかけに注意を向けてみましょう。1日の体調を数値化し、気分を言語化して記録しておくと、後で分析しやすくなります。
体調が回復してきたら、前職の経験を振り返ることも大切です。どのような状況がストレスにつながっていたかが分かれば、今後の働き方を決めやすくなります。
夜勤のシフトなど時間が不規則な働き方も、ストレス要因となり得ます。「昔できていたから大丈夫だろう」と簡単に判断せず、主治医やカウンセラー、友人などに相談してみましょう。
復職直後は仕事の量を少し抑え、段階的に増やしていくのが理想的です。業務量の調整が難しい場合は、期限に余裕をもって仕事を振ってもらう、質問しやすい環境を整えてもらうなど、他の方法も検討しましょう。
自身の病気や障害が、大きな不安やストレスに繋がっている場合、そのことを会社に開示して働くオープン就労で障害者雇用で働くという選択肢もあります。
会社の負担が重すぎない範囲で合理的配慮を受けられる、周りの人から理解を得やすいなどのメリットがあります。
合理的配慮は、手帳の有無に関わらず誰でも意思表明する権利があります。配慮の希望と併せて、自身でカバーできる点や、環境が整えばどのような働きができるかも伝えられるとよいでしょう。
合理的配慮、障害者手帳について知りたい人は、以下のコラムもご覧ください。
復職に関する不安の相談先
この章では、復職に関する不安の相談先を紹介します。
相談先①就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。実際のサービスは、国の基準を満たしたさまざまな民間の就労移行支援事業所が行います。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
通所型のサービスであるため、生活リズムを整えやすいなどのメリットがあります。相談会や体験利用を活用し、「通いたい」と思える場所を探してみましょう。
また、メンタル不調で休職・退職した人も多く通っているため、利用者同士で分かり合えることもあるでしょう。
利用者間の交流については、事業所により方針や環境が異なります。筆者の場合は、普段から励まし合える友人ができました。
キズキビジネスカレッジ(KBC)もその一つです。それぞれ特徴が異なるため、気になるところがあれば問い合わせてみてください。
相談先②臨床心理士
臨床心理士のいるクリニックでは、心理学の知識や技法を生かしたカウンセリングが受けられます。(参考:一般社団法人日本臨床心理士会「臨床心理士に出会うには」)
一定の費用はかかりますが、専門家にゆっくり話を聴いてもらえます。心理士との相性などもありますので、話してみて抵抗や違和感を感じた場合は、他の人にも相談してみましょう。
相談先③こころの健康相談統一ダイヤル

全国共通の番号で、電話をすると、その地域の公的な相談機関に接続されます。多くの自治体が平日のみの対応です。
時間帯により、自治体の相談窓口、もしくは公益社団法人日本精神保健福祉士協会、公益社団法人日本公認心理師協会が対応してくれます。(参考:厚生労働省「こころの健康相談統一ダイヤル」、公益社団法人日本精神保健福祉士協会「精神保健福祉士について」、公益社団法人日本公認心理師協会「公認心理師とは」)
相談先④よりそいホットライン(一般社団法人 社会的包摂サポートセンター)
よりそいホットライン(一般社団法人 社会的包摂サポートセンター)は、24時間、フリーダイヤルで相談できます。(参考:一般社団法人 社会的包摂サポートセンター「よりそいホットライン」)
生活や仕事など、あらゆる内容に対応しています。
なお筆者の経験では、多くの人が相談しているのか、回線が混み合っていて繋がらないことがありました。一度かけて繋がらなくても、何度もかける、時間帯を変えてかけ直すなどしてみることで、相談できることがあります。
相談先⑤自治体の障害福祉を担当する部署・窓口
さまざまな理由で生活が困窮している人が相談できます。
内容に応じて利用可能な支援制度の案内や、情報提供を受けられます。
相談先⑥障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターとは、雇用や保健、福祉、教育に関する関係機関と連携し、障害のある人の雇用の促進・安定を目的とした一体的な支援を行っている支援機関のことです。(参考:厚生労働省「障害者就業・生活支援センター」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」、厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」)
障害のある人の就職活動の支援や求人の紹介、職場定着のためのサポートなどを行います。
就業面だけでなく、金銭管理などの経済面や生活面のことまで、日常および地域生活に関する支援も行っています。
生活習慣や金銭管理、健康管理などについても幅広く相談できるため、生活面のサポートも受けたい人にオススメです。
2024年4月1日時点で、障害者就業・生活支援センターは全国に337箇所設置されています。
相談先⑦ハローワーク

ハローワーク(公共職業安定所)とは、仕事を探している人や求人を募集したい事業者に対して、就労に関連するさまざまなサービスを無償で提供する、厚生労働省が運営する支援機関のことです。正式名称は公共職業安定所で、職安と呼ぶ人もいます。(参考:厚生労働省「ハローワーク」厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」厚生労働省「公共職業安定所(ハローワーク)の主な取組と実績」、東京労働局「東京ハローワーク」、厚生労働省「こころの健康サポートガイド」、厚生労働省「ハローワークにおける障害者の就労支援」)
主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示などを行っており、具体的な支援内容は事業所によって異なりますが、一般的には以下のような幅広いサポートを行います。
全国に500ヶ所以上あり、主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示、雇用保険や雇用対策など、地域密着型の雇用に関する幅広いサポートを行います。
また、病気や障害のある人に向けたサポートも行っています。障害者手帳を所持していない人でも、医師による診断書があれば、障害の特性や希望職種に応じた職業相談や履歴書や面接での病気・障害の伝え方などのサポートを受けることができます。
また、ハローワークでは、就職可能性を広げるという観点で職業相談を行った上で、ハロートレーニング(公的職業訓練)への受講あっせんを行っています。
ハロートレーニングとは、雇用保険(失業保険)を受給している求職者を主な対象とする「公共職業訓練」と、雇用保険を受給できない求職者を主な対象とする「求職者支援訓練」の総称です。離職者向けの訓練期間は、基本的には2〜6ヶ月となります。公的な制度のため、受講料は基本的に無料です。
相談先⑧当事者会
同じ病気や障害、トラウマなどを経験をした人たちの集まりです。
休職した理由となった病気や障害に関する当事者会を検索してみると、さまざまな場所で開催されています。友人や家族には共感してもらえなかったことも、同じ境遇の人と話すことで「あるある」と盛り上がるかもしれません。
復職に関する不安を乗り越えた体験談
実際に不安を乗り越えて、復職した人はたくさんいます。どのような不安を抱え、どのように離職期間を過ごしていたのでしょうか。
この章では、復職に関する不安を乗り越えた体験談を紹介します。
体験談①自分と相手の考えを、切り分けて考えるようにしました

もともと趣味で関心のあった業界で、就職されたAさん(男性・26歳)。
職場でパワハラに遭ったことをきっかけに休職に至りました。休職期間は1年2ヶ月続くことになります。
迷いもあったそうですが、普段から仲良くしているご近所の人の助言もあり、休職を決めることができたそうです。
──休職直後はどのように過ごしていましたか?
家で、ずっと布団に潜っていました。ずっと家にいると、食べるものがなくなっていくので、夜、人の少ない時間を狙ってコンビニだけ行ってました。店内で人とすれ違うだけで、恐怖を感じるような状態だったんです。
「みんな働いてるのに、なんで自分は休んでるんだろう」みたいに、自分を責めることもありました。気を紛らわせようとして趣味のプラモデルを触っても、5分くらいで調子悪くなってましたね。
──復職しようと思ったのはいつ頃ですか?
自分では結構回復したと思ったので、半年くらいで復職しようとしました。でも産業医にそれを伝えたら、まだ早いと言われて。自分の表情や発言から、怒りが強く出てたみたいです。それで人事と話して、怒りの感情と上手く付き合っていくために、アンガーマネジメントを学ぶことにしました。その流れで就労移行支援事業所のことを知りました。
──怒りや不安にはどう対処しましたか?
怒りに対しては、深呼吸、運動をするのと、自分はべき思考が強いと分かったので、自分と相手の考えを切り分けて考えるようにしました。
不安に対しては、就労移行支援事業所の講座で、コミュニケーションのパターンを覚えることで、職場での失敗を回避するというものがありました。色々な状況をシュミレーションして、会社に行ってもこうすれば大丈夫だなと思えました。
──復職準備でやって良かったことは?
講座で、ゲームをしながら楽しくコミュニケーションをとったり、自分がやりがちな失敗について知ったことです。例えば、会社で休みの申請をする時に、余計なことまで長々と話していたと、グループワークで指摘されて気付いたりしました。ライティング講座も、相手を意識して言葉を選ぶようになったので、話す時にも役立っています。
あとは、キズキビジネスカレッジ(KBC)の交流会です。利用者スタッフとして交流会の運営にも参加して、学んだことを実践する機会ができました。朝みんなで15分ほど話す朝活にも毎日出るようにして、生活リズムを改善しました。
──復職直前ですが、不安を感じる時はありますか?
あまりないですが、気分にまだ少し波があるので、たまには不安になる時もあります。例えば、会社では電話も鳴るし、マルチタスクになる時もあると思うので、実際に働いてみないと分からないことも多いです。
不安を感じる時は、好きなことを考えたり、体を動かしたり、顔を手でパチッと叩いて気分を変えています。あとは、小さい目標を細かく立てるとか、少し先の楽しい予定を作るようにしています。
体験談②「働けてたんだから大丈夫だろう」「いや無理だろう」を繰り返していました
前職では、福祉の児童指導員をされていたTさん(女性・33歳)。退職時は失業手当金などの知識もなく、生活のために早く働かなければと、焦って仕事を探していたそうです。
体調が悪い中、何社か面接も受けましたが、良い結果は得られず。「この体調でできる仕事って何なんだろう?」と考えるようになり、離職していた10ヶ月の間、働き方について調べる中で就労移行支援事業所の存在を知りました。
──退職後、不安な気持ちが続くことはありましたか?
結構ありました。夜、家族が寝た後とか、1人でシーンとした部屋にいると考えちゃいます。いつこのしんどいのは終わるんだろうって。こんなんじゃ働けないんじゃないかって。退職してすぐの頃は、毎日考えてました。やっぱり体調が悪いと、悪いふうに考えることが増えますね。
──回復してきたと感じたのはいつ頃ですか?
就労移行支援事業所で社会との繋がりみたいなのを持てて、回復したところはあります。話しかけてくれる人もいましたし、交流会や講座のグループワークだと、自動的にみんなと話す時間が持てました。同じような悩みをみんな持っているんだなって感じて、自分だけじゃないと思えました。
回復してきたと思ったら足を骨折して(笑)、1ヵ月在宅での通所になりました。ほとんど家から出られなかったので休むしかなくて、多分その時に1番ゆっくりしたんですよね。そのおかげか、めちゃくちゃ体調が良くなりました。
──復職準備で、取り組んで良かったと思うことは?
どんなに良い職場に行っても、人間関係で悩むことはあるだろうと思ったので、それをどうにかしようと思いました。
就労移行支援事業所で自己理解講座で学んだ後、何かストレスがかかるような事があったら、ワークシートに書き込んで心の整理をしました。毎週個人面談もあったので、その時に書いたものを見てもらったんですが、とても褒めてもらって、自己肯定感が爆上がりしました。自分ひとりで考え方や捉え方を変えるのは難しかったと思うので、面談で何度もフィードバックをもらえたのが良かったと思います。
諦めたり、しょうがないと思えるようになったのも良かったです。身体が動かなくて何もできなかった時に罪悪感で1番しんどかったんですけど、「いまはそういう時期なんだな」って思えたり、「休んで大丈夫」って自分に言い聞かせるようになりました。
──就職活動で不安だったことは?
喋るのが苦手なこともあって、面接が苦手で、それが1番不安でした。
就職活動しながらキズキビジネスカレッジ(KBC)で面接練習をしたり、自分で調べてネガティブな退職理由をポジティブな表現に変える方法を学んだのが、結構役に立ちました。
──復職が近づいてきた頃はどうでしたか?
働いてた時とは生活のリズムが変わっていたので、それを戻せるかが不安でした。10時〜15時に通所するだけでしんどいことがあって、これはフルタイムで働けないぞと。「これまで働けてたんだから大丈夫だろう」と思ったり、「いや無理だろう」と思ったり、それを繰り返してましたかね。でも実際に働いてみたら大丈夫でした。
──調子が悪くなりそうな時はどうしていましたか?
私の場合は、仲の良い人と喋ったりすることで気持ちが楽になっていました。
友達に言えないようなことは、面談で吐き出していました。あとは、気持ちが落ちている時は開き直ってゆっくりしてました。好きなお笑いの動画を見たりして、笑って過ごしました。やっぱり笑うと元気になることが多いなって。まぁ、ならない時もありますけど。人と話して笑うことがあれば、それでも元気になります。
まとめ:その不安を誰かに相談しましょう

メンタルヘルスの不調を経験した人の話を、身近な人から聞く機会はあまり多くありません。
しかし、あなたと同じように不安を抱える人はたくさんいます。話を聞いてくれる支援者や、生活や復職をサポートしてくれる支援機関もあります。まずはその不安を誰かに相談しましょう。
このコラムが、少しでもあなたの不安の軽減につながれば幸いです。
休職後に陥りがちな復職に関する不安を教えてください。
復職に関する不安への対処法はありますか?
以下が考えられます。
- 不安を書き出す
- 誰かに聞いてもらう
- 必要以上に考えないため、注意を逸らす
- ネガティブな感情も、価値観を知る手がかりと捉える
- 休職したことのメリットを考える
- 自分ができることを意識する
詳細については、こちらで解説しています。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→