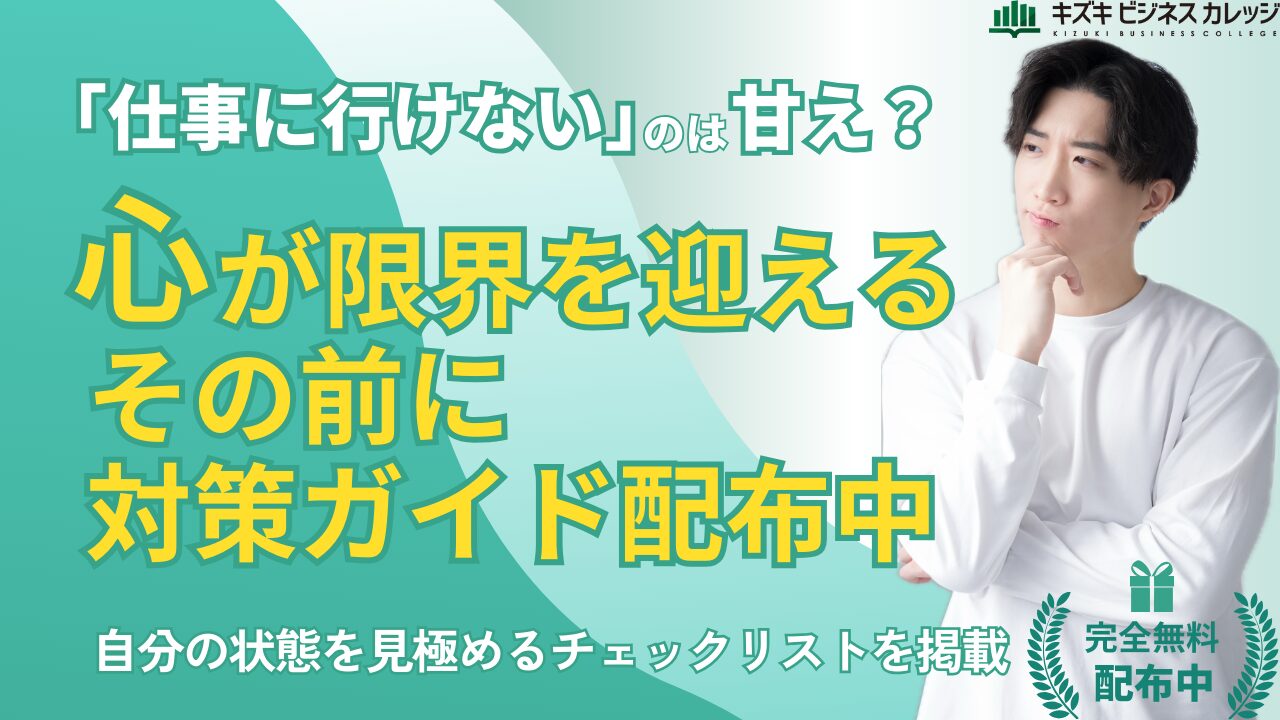仕事に行きたくないのは甘え?うつ病の可能性も? 理由や対処法を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
朝になると気分が重く、「仕事に行きたくない」「このまま家にいたい」と、暗い気持ちになることはありませんか?
仕事に行きたくないという気持ちは、多くの人が抱くごく一般的な感情です。「甘えではないか」と自分を奮い立たせ、無理を重ねる人もいますが、これは身体や心が発する重要な警告である場合もあります。
このコラムでは、「仕事に行きたくない」という感情が起こる理由と対処法について、詳しく解説します。
今まさに、「明日の朝が怖い」「仕事に行くのがつらい!」と感じている人は、ぜひご一読ください。
さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、仕事でストレスを感じている人に向けて、ストレス対策ハンドブック【自己評価チェックリスト付き】」の無料配布を開始いたしました。
職場のストレスの原因や自分でできるストレスマネジメントなどを、わかりやすく丁寧に解説しています。
また、今すぐ活用できるストレス対策チェックリストも掲載しています。
ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。
また、仕事のストレスへの対処法については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。
仕事に行きたくないあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 平均4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
仕事に行きたくないのは甘え?実は心や体からのSOSかも
「働くうえでつらいのは当たり前、それに耐えてこそ立派な社会人」という日本の風潮も手伝い、「仕事に行きたくない自分は甘えている」と、思い詰める人は少なくありません。
実際に「行きたくない」と口にして、家族や友人からたしなめられた経験がある人もいるでしょう。「仕事に行きたくない」という感情が本当に甘えにあたるのか、以下で詳しく説明します。
仕事に行きたくないのは甘えではない

結論として、「仕事に行きたくない」という気持ちは、決して甘えではありません。多くの人が一度は抱く、ごく自然な感情です。まずは「自分だけではない」と安心してください。
さらにこの感情は、身体や心が「限界が近い」と警告している可能性があります。世間には「我慢して働くのが当たり前」という風潮がありますが、こうしたサインを看過してはなりません。無理を続けると、心身の不調が深刻化し、回復にも時間がかかります。
「仕事に行きたくないのは甘えだ」と短絡的に片付けず、「身体や心が限界を知らせてくれている」と受け止めましょう。
仕事に行きたくないと感じる人は多い
先述のとおり、「仕事に行きたくない」と感じる人は少なくありません。
厚生労働省が実施した「令和5年労働安全衛生調査」によると、現在の仕事や職業生活に関して「強い不安、悩み、ストレスとなっていると感じる事柄がある」と答えた労働者は約82.7%に達しています。
すなわち、労働者のおよそ8割が仕事に強いストレスを抱えている計算です。なお、年代別の内訳は、以下のとおりです。
- 20歳未満:約21.1%
- 20~29歳: 約72.0%
- 30~39歳:約86.0%
- 40~49歳:約87.9%
- 50~59歳:約86.2%
- 60歳以上:約64.8%
さらに、同調査によれば、過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休業、または退職した労働者がいる事業所の割合は、約13.5%に上ることも判明しています。このような状況下で、「仕事に行きたくない」という感情が起こるのは、ごく自然なことでしょう。(参考:厚生労働省「令和5年安全衛生調査(実態調査)の概況」)
仕事に行きたくないと感じる理由は?
そもそも、なぜ「仕事に行きたくない」という感情が生じるのでしょうか?
ひと言でストレスといっても、その要因は多岐にわたります。以下で主な原因について解説します。
理由①仕事量や業務時間の負担が大きい

仕事に行きたくないと感じる要因の1つに、過重な業務量が挙げられます。
業務が多く、連日の残業や休憩をほとんど取れない状況が続けば、疲労とストレスは次第に蓄積します。その結果、「また今日も仕事か…行きたくない」といった憂うつな思いに至ります。
業務量や就業時間が過度の負担となっている場合は、抱え込まずに周囲へ相談し、業務の整理・見直しを図ることが重要です。
理由②仕事の質が合わない
「仕事に行きたくない」という感情の背景には、「仕事内容が自分に合っていない」という問題が潜んでいる場合もあります。
人にはそれぞれ得手・不得手があり、同じ業務内容でも感じ方や適性は大きく異なります。
たとえば、人と関わる業務が苦手な方が接客に従事していたり、細かい作業が不得意にもかかわらず事務処理を担当していたりすると、それだけで日々のストレスが増大します。やりがいや達成感も得にくくなり、やがて出社への意欲が低下します。
厚生労働省の「令和5年雇用動向調査」によれば、転職者に前職の離職理由を尋ねたところ、「仕事内容に興味を持てなかった」と回答した労働者が多数を占めました。この結果からも、仕事内容のミスマッチが大きなストレス要因となり得ることがうかがえます。(参考:厚生労働省「令和5年安全衛生調査(実態調査)の概況」)
理由③給料や労働条件に不満がある

仕事に行きたくないと感じる背景には、賃金や労働条件への不満も大きく影響しています。
- いくら努力しても給与が見合わない
- サービス残業が常態化している
- 有給休暇を取得しにくい
上記のような環境では、容易にモチベーションが低下します。やる気がそがれ、出勤への意欲も次第に薄れていくでしょう。
こうした労働条件への不満は、ストレスや疲労を蓄積させるだけでなく、職場への信頼感を損なう要因にもなります。自らの労働が正当に評価されていないと感じる場合には、冷静に現状を見直し、職場と対話を図ることを検討してください。
理由④人間関係がつらい
職場の人間関係を理由に「仕事に行きたくない」と感じる人は、決して少なくありません。
職場は1日の大部分を過ごす場であり、上司や同僚との関係が円滑でない場合、長時間にわたり強いストレスにさらされます。理不尽な指示や陰口、無視といった状況が続けば、心身が疲弊するのも当然です。
人間関係の問題は、自身の努力だけでは解決が難しい場合が多く、我慢を重ねるうちに出社そのものが苦痛になるおそれがあります。
厚生労働省の「令和5年雇用動向調査」によると、離職理由のうち「職場の人間関係が好ましくなかった」は男性で2位、女性では1位を占めました。職場の人間関係に悩む人がいかに多いかがうかがえます。こうした悩みを抱えた際は、信頼できる第三者に相談し、自分だけで抱え込まない姿勢が重要です。(参考:厚生労働省「令和5年安全衛生調査(実態調査)の概況」)
理由⑤仕事にプレッシャーを抱えている

過度のプレッシャーを受けて「仕事に行きたくない」と感じる人も少なくありません。
常に高い成果を求められ、ミスが許されない緊張感の下で働き続ければ、心が休まる瞬間はほとんどなくなります。
「失敗してはならない」「周囲の期待に応えなければ」と自らを追い込み過ぎることで、仕事に対する恐怖や不安が増幅し、出勤が一層つらくなるのは当然です。
真面目で責任感の強い人ほど、このような状況に陥りやすい傾向があります。過度のプレッシャーを感じたときは、いったん立ち止まり、置かれている状況を冷静に見つめ直すことが肝要です。
仕事に行きたくない原因はうつ病の可能性も

「仕事に行きたくない」と感じる日が続き、これまで楽しめていた事柄にも興味を示せなくなっている場合、うつ病の初期症状が疑われます。
うつ病とは、気分の落ち込みや憂うつ感、さまざまな意欲の低下などの精神的症状と、不眠、食欲の低下、疲労感などの身体的症状が一定期間持続することで、日常生活に大きな支障が生じる精神障害・気分障害のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、厚生労働省「1 うつ病とは:」、厚生労働省「うつ病に関してまとめたページ」、、厚生労働省「うつ病」、国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「うつ病」、MSDマニュアルプロフェッショナル版「抑うつ症候群」)
以下のような状態が2週間以上続くようであれば、心の不調を念頭に置いて対処する必要があります。
- 朝、起き上がれない
- 食欲がない
- 理由もなく涙が出る
- 集中力が続かない
うつ病は誰にでも発症し得る病気であり、特に真面目で責任感の強い人ほど症状を見過ごしやすい傾向があります。
「気持ちの問題」や「弱さ」と自己判断して我慢せず、少しでも異変を覚えたら、精神科または心療内科を受診するといいかもしれません。
うつ病の症状や原因、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。
仕事に行きたくないときの対処法
ここでは、仕事に行きたくないと感じた際の対処法について解説します。自身に合うと感じる方法があれば、実践してみてください。
対処法①専門家に相談する

仕事に行きたくないと感じた場合は、専門家への相談を検討しましょう。
心身に不調を覚えたとき、最も重要なのは一人で抱え込まないことです。
多くの人は仕事上のストレスやプレッシャーを自己解決しようとする傾向にありますが、専門家の支援を受けることで解決の糸口が見つかることがあります。
カウンセリングでは、話をするだけでも気持ちが整理され、心が軽くなる場合があります。また、医師に相談することも有効です。心のケアを専門とする医療機関や産業医を積極的に利用してください。
専門家から適切な助言を受けることで、安心して前に進むための力を得られます。
対処法②休職を検討する
仕事に行きたくない状態が長く続く場合は、限界に達する前に休職を検討することも一案です。
休職期間を設ければ心身を十分に休める時間が確保され、長期的な健康維持の観点からも有効な対策となります。
休職は、病気休暇や労働基準法に基づく休業制度を利用して取得可能です。たとえば、うつ病や過度のストレスが要因であれば、医師の診断書を添えて病気休暇を申請する方法が一般的です。
現在、多くの企業は従業員の健康管理を重視しており、適切な休職制度を整備しています。十分な休養によって回復を図れれば、復職時には新たな気持ちで業務に臨めるでしょう。
休職中は焦らず、自身のペースで回復を目指すことが肝要です。また、休職を決断する前に上司や人事部門と相談し、手続きや復職後のサポート体制を確認しておくと安心です。
休職は決して後ろ向きの選択ではありません。心身の回復に専念することが、結果として長期にわたり仕事を続けるための最良の手段になります。
対処法③転職を視野に入れる

転職という選択肢を視野に入れることも有効です。現職でのストレスや不満、労働環境が原因であれば、職場を変えることで心身のリフレッシュが期待できます。
転職を検討する際は、今後のキャリアをどのように築くかを明確にします。たとえば、現職の人間関係に問題がある場合は、オープンで協力的な職場文化を重視するなど、自己分析と企業研究が転職を成功させる鍵となります。
転職の決断は容易ではありませんが、健康は何よりも重要です。限界を感じるようであれば、心身を守る手段として転職を前向きに検討することも一案です。
うつ病の場合は障害者雇用という選択肢も
うつ病や心の不調が原因で「仕事に行きたくない」と感じ、日常生活に支障をきたすほどの状態に達すると、通常の勤務形態を継続するのは難しくなる場合があります。そのようなケースで検討したい選択肢の1つが「障害者雇用」です。
障害者雇用は、精神障害などのある人が特性に応じて就労できるよう、企業が別枠を設けて雇用する制度を指します。
障害者基本法第1条に基づき、障害のある人の社会参加を促進し、共生社会を実現することを目的として整備されました。企業は全従業員数に対し一定割合以上の障害のある人を雇用する義務があり、この割合を「法定雇用率」と呼びます。
障害者雇用では、柔軟な勤務時間設定、テレワークなど勤務場所の多様化、業務量の調整、職場内サポート体制の整備など、心身の状態に配慮した環境が提供されるのが一般的です。
精神的な病気のある人も、こうした配慮のもとで就労を継続しやすくなります。
一般的な職場環境で働くことが困難な場合でも、障害者雇用を選択すれば、体調に合わせた働き方を実現しやすくなるでしょう。
障害者雇用の条件などについては、以下のコラムで解説しています。
障害者雇用で働くには
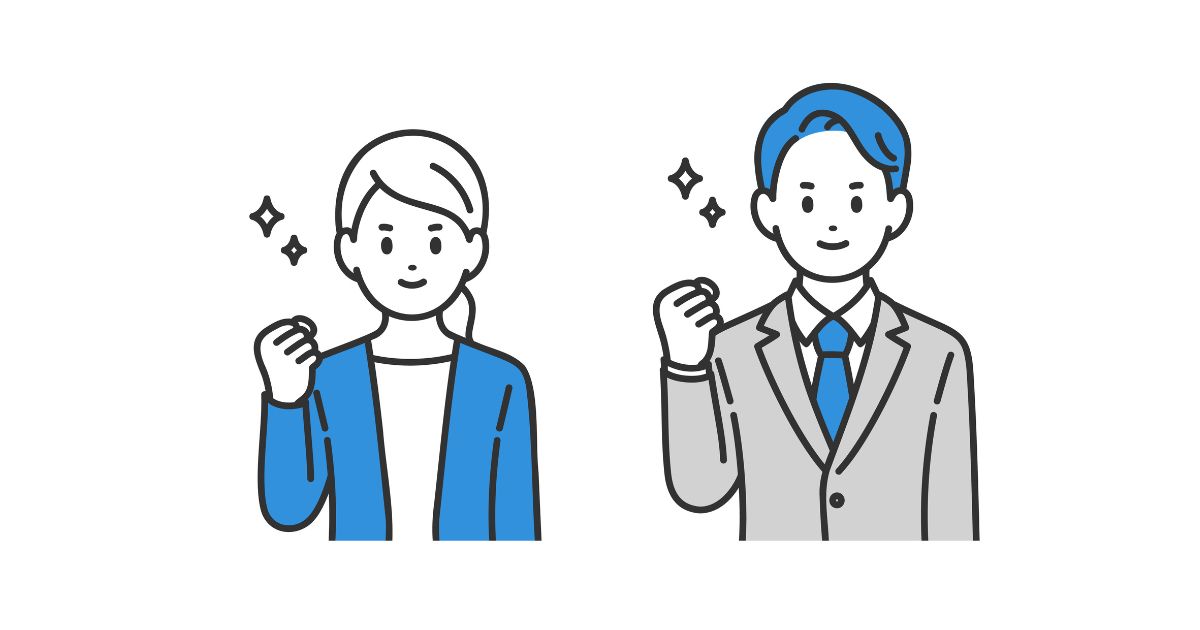
障害者雇用での就労を希望する場合、具体的にどのような手続きを踏むべきか説明します。
障害者雇用で働く場合、実質「障害者手帳」の取得が必要です。障害者手帳とは、一定以上の障害のある人に交付される手帳のことです。
障害者手帳を所持することで、障害があることの証明が可能です。障害者手帳を所持する人は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の対象として、さまざまな支援を受けられます。(参考:厚生労働省「障害者手帳について」、e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
障害者手帳は、障害により日常生活に支援が求められる方に対し、自治体が交付します。初めに医療機関で診断を受け、その診断書をもとに自治体へ交付申請を行います。
本来、障害者手帳を取得していない障害のある人でも、障害者雇用促進法上、障害者雇用の対象になります。
しかし、同法では障害者手帳を取得していないと、障害のある人を雇用しても前述した法定雇用率に算定できない定めです。
そのため民間企業は手帳を取得していない障害のある人を積極的に障害者雇用で採用しない傾向にあります。障害者雇用で働くには、実質、障害者手帳が必要になるわけです。
なお、障害者雇用には必要な配慮を受けられる反面、「賃金水準が低い傾向にある」「キャリアアップの機会が限定される」といった注意点も存在します。メリットと注意点を把握し、自身にとって最適な働き方を選びましょう。
障害者手帳を取得する方法や取得するメリットなどについては、以下のコラムで解説しています。
就労移行支援事業所も検討
うつ病などの精神疾患により出勤が難しい場合には、障害者雇用を検討する前段階として、「就労移行支援事業所」の利用を視野に入れる方法があります。
就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。
体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
- 職業訓練:就労に必要な知識・技能の習得を支援します。自己管理能力、コミュニケーションスキル、業務効率化の手法など、現場で即戦力となる内容を学べます。
- 就職活動のサポート:履歴書の作成、面接対策、求人情報の提供など就職活動全般を支援します。障害者雇用を実施する企業とのマッチングも行い、適切な職場探しを後押しします。
- 職場定着支援:就職後も長期的に安定して働けるよう、フォローアップ面談や職場での課題に関する相談に対応します。
就労移行支援事業所を利用すれば、精神的負担を軽減しつつ職場復帰に向けた準備が可能です。
全国各地に多様な事業所が存在し、提供プログラムや支援内容、雰囲気は事業者ごとに異なります。パソコン訓練に強みを持つ所、就職実績に定評のある所、メンタルケアを充実させている所など、特色はさまざまです。
自身の体調や特性、希望する働き方に適した事業所を選択することが、安定した就労への近道となります。見学や体験利用を通じて、無理なく継続できる環境かを確認してください。
キズキビジネスカレッジ(KBC)は、就労移行支援事業所の一つとして、うつ病や発達障害などを理由に離職した方の「もう一度働きたい」という思いに応えるべく設立されました。多彩なプログラムと講座を通じて高度なビジネススキルの習得を支援しています。新たな職場で生き生きと働く未来を、私たちとともに目指してみませんか?
【無料配布】ストレス対策ハンドブック・自己評価チェックリスト付き

- 「事のストレスに負けそう…
- もう限界かもしれない…
そんな気持ちを抱えながら、仕事を続けていませんか?
適度なストレスはモチベーションを高めることもありますが、過度なストレスは心身に悪影響を与えます。
大切なのは、ストレスを根本からなくすのではなく、適切に対処することです。
本ハンドブックでは、ストレスのセルフケア方法やストレスマネジメントの実践方法を紹介し、自己評価ができるチェックリストも掲載。日々の生活習慣を見直すきっかけとしてご活用いただけます。
「仕事のストレスを減らしたい」「毎日をもっと心地よく過ごしたい」と考えている人は、ぜひこのハンドブックを活用してみてください。
- ストレスの原因を理解し、適切な対処法を学べる
- ストレスマネジメントの実践方法をわかりやすく解説
- 自己評価チェックリスト付きで、自分のストレス対策を確認できる
- 仕事のストレスが大きく、適切な対処法を知りたい人
- 職場での人間関係や業務負荷に悩んでいる人
- 生活習慣を見直し、健康的な働き方を目指したい人
- 自分に合ったストレスマネジメント方法を探している人
- リンクから申し込みフォームにアクセス
- 簡単なフォームに入力
- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り
- URLから資料を取得!
- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。
- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。
- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。
また、仕事のストレスについては、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ:「仕事に行きたくない」のサインをとらえて最適な働き方を見つけよう

「仕事に行きたくない」という気持ちは、誰にでも起こる自然な反応です。自分を責めず、まずはその感情を認め、必要に応じて専門家の力を借りてください。
状況によっては、休職や転職、障害者雇用といった選択肢も前向きな一歩になります。大切なのは、あなた自身の心身の健康です。無理をせず、自分らしい働き方を目指していきましょう。
就労移行支援事業所であるキズキビジネスカレッジ(KBC)では、「もう一度働きたい」という思いをかなえるための多彩なプログラムを用意しています。専門的スキルを身に付け、ご自身の特性に即した環境で活躍したいとお考えの人は、ぜひお問い合わせください。
仕事に行きたくないと感じる理由を教えてください。
仕事に行きたくないときの対処法はありますか?
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年6月現在8校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年6月現在、首都圏・関西に8校舎を展開しています。トップページはこちら→