適応障害で休職した際の給料は? お金の心配を解決する支援・申請方法を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
- 適応障害で休職したが、給料はどうなる?
- 適応障害で休職した際に受けられる支援は?
以上のような疑問や不安を抱いたことはありませんか?
このコラムでは、適応障害を経験した筆者の知見に基づき、適応障害で休職した人に向けて、適応障害で休職した際の給料をはじめ、お金の心配を解決できる経済的支援制度や申請方法、社会保険料支払いの有無、利用できる支援機関について解説します。
お金や復職への心配を解決し、安心して療養するための手助けになれば幸いです。
適応障害で休職しているあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
適応障害で休職した際の給料は?

適応障害で休職した場合、基本的に給料は支払われません。これは、民法第624条に由来します。(参考:デジタル庁 e-Gov 法令検索「労働基準法 第二十四条(賃金の支払)」、デジタル庁 e-Gov 法令検索「民法 第六百二十四条(報酬の支払時期)」)
ただし、会社によって就業規則が異なることにより、休職中でも一部または全額が支給される場合もあるようです。
「給料が支払われないのであれば、どのように生活費などをまかなえば良いのか」といったお金の心配を解決する方法の一つとして、経済的支援制度の利用があります。
適応障害で休職中の人が利用できる経済的支援制度
この章では、給与の約3分の2を受給できる傷病手当金と医療費の自己負担額を3割から1割へ減額できる自立支援医療制度を紹介します。
支援制度①傷病手当金
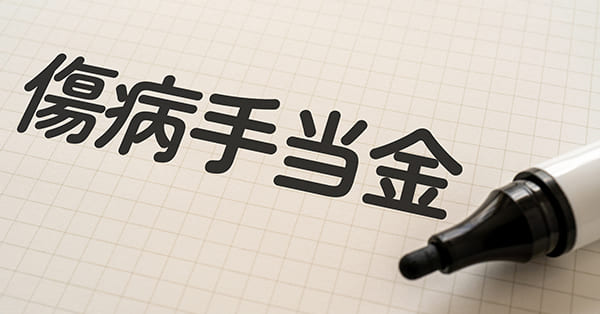
傷病手当金とは、病気やケガ、障害のために仕事を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に、健康保険(社会保険)の加入者・被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた支援制度のことです。(参考:全国健康保険協会「傷病手当金」、全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」、全国健康保険協会「傷病手当金について」)
国民健康保険の加入者・被保険者は対象外です。
対象となる病気やケガ、障害は、業務外の理由で生じた場合に限ります。会社の業務が原因で生じた病気やケガ、障害は、労災保険により補償されます。
傷病手当金の受給対象は、病気やケガ、障害によって就労不能であり、十分な報酬を受けられない人です。そのため、医師の診断書が必要です。
また傷病手当金は、退職前・在職中に就労できない状態の場合に受給できます。ただし、一定の条件を満たせば、退職後も継続して受給できます。具体的な受給金額や受給期間は、その人の休職の状況などによって異なります。
申請は、加入している全国健康保険協会や各健康保険組合、各共済組合で行えます。気になる人は、加入している健康保険の協会・組合にご相談ください。
傷病手当金については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援制度②自立支援医療(精神通院医療)制度

自立支援医療制度とは、心身の障害を緩和・除去するために継続的な治療が必要な人に対して、医療費の自己負担額を軽減する公的な支援制度のことです。(参考:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」)
通常、公的な医療保険による医療費の自己負担額は3割ですが、自立支援医療制度を利用すれば、収入によって異なりますが、基本的に自己負担額を1割に軽減できます。
この制度は、指定の医療機関・薬局のみで利用可能です。
具体的には、以下を利用した際に医療機関に支払う金額が対象となります。
- 外来受診
- 外来受診時の投薬
- デイケア・ナイトケア
- 訪問介護
以下で発生した費用は適用対象外のため、注意してください。
- 入院
- 公的医療保険適応外の治療(病院や診療所以外で受けたカウンセリングなど)
- 自立支援医療制度の対象外の疾患への治療
自立支援医療制度については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
また、適応障害のある人が利用できる支援機関については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
補足:その他の支援制度
傷病手当金や自立支援医療制度のほかにも、労災保険や障害者手帳、障害年金など、利用できる支援制度があります。
ほかにも、各自治体独自の支援金や貸付制度があります。また、民間の就業不能保険や所得補償保険に加入していればそちらの給付も受けられる場合があります。(参考:全国健康保険協会「被保険者の資格」、全国健康保険協会「費用の負担」、日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」、厚生労働省「障害者手帳」、国立研究開発法人 国立精神・神経医療センター「障害者手帳・障害年金」、日本年金機構「障害年金」)
適応障害で休職中の社会保険料の免除・減免
この章では、休職中の社会保険料の支払いについて解説します。
なお、社会保険料とは、一般的に以下の5つからなるものです。
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 労災保険
休職中は、支払う必要がなくなったり、状況によっては免除や減免されることがありますので、確認しておきましょう。
社会保険①健康保険・厚生年金保険の保険料

健康保険・厚生年金保険の保険料は、休職中も支払う必要があります。
理由として、休職中とはいえ雇用契約は続いており、被保険者資格が継続しているためです。(参考:厚生労働省「休職と被保険者資格について」)
徴収方法については、会社によって異なるため、必要に応じて人事を担当する部署や労務担当に確認すると良いでしょう。
ただし、産前産後休業または育児休業期間中であれば、健康保険・厚生年金保険の保険料が条件付きで免除される場合があります。(参考:日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」)
また退職した場合は、被保険者資格を喪失するため、任意継続健康保険や国民健康保険、ご家族の健康保険(被扶養者)のいずれかに加入する必要があります。(参考:全国健康保険協会 協会けんぽ「会社を退職するとき」)
社会保険②労災保険・雇用保険の保険料(労働保険料)
労働保険料は、休職中に給料が支払われていなければ、支払い不要です。
理由として、労働保険料の計算式の基本形は、以下のとおりとなっており、賃金を得ていなければ支払いが不要になります。(参考:厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引き「第7章 労働保険料のしくみ」)
- 賃金総額×保険料率=一般保険料
ただし、休職中でも賃金が発生した場合は支払いが発生するため、注意が必要です。
社会保険③介護保険の保険料

介護保険料の支払いについては、個人の状況によって大きく異なります。
理由として、加入している健康保険や都道府県、所得状況、該当者数によって異なる介護保険料率が適用されるため、その人の状態次第で支払いの有無や額も異なるからです。(参考:全国健康保険協会「協会けんぽの介護保険料率について」、全国健康保険協会「都道府県毎の保険料率」)
ただし、一般的に支払いの有無については、年齢によって判断することができます。(参考:生命保険文化センター「公的介護保険への加入はいつから? 保険料はどのように負担する?」)
- 40歳未満:介護保険料は40歳以上の人が加入するため、40歳未満の人は支払いが発生しない
- 40歳~64歳(第2号被保険者):介護保険料は標準報酬月額(給料など)を計算に用いるため、休職中に給与を受け取っていない場合は支払いは発生しない
- 65歳以上(第1号被保険者):自治体などが定める基準額と所得に応じて支払いが発生する
休職から復職に向けて利用できる支援機関
この章では、適応障害を含む精神障害のある人が、休職から復職に向けての準備として利用できる支援機関を紹介します。
地域障害者職業センターや障害者就業・生活支援センターなど、そのほか支援機関についても、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援機関①就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。
体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。実際のサービスは、国の基準を満たしたさまざまな民間の就労移行支援事業所が行います。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
就労移行支援事業所は各地にあります。私たち、キズキビジネスカレッジ(KBC)もその一つです。それぞれ特徴が異なるため、気になるところがあれば問い合わせてみてください。
就労移行支援事業については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援機関②精神保健福祉センター

精神保健福祉センターとは、精神障害のある人のサポートを目的とした、地域の精神保健福祉の中核を担う支援機関のことです。(参考:東京都福祉保健局「精神保健福祉センターとは」、e-Gov法令検索「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第二章 精神保健福祉センター(第六条―第八条)」、厚生労働省「精神保健福祉センター運営要領について」)
精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)に基づき、各都道府県に設置されています。地域によって、こころの健康センターや心と体の相談センターなど、一部名称が異なります。
精神保健福祉センターでは、精神疾患に関連する悩みの相談や社会に適応するための指導と援助を行っています。また規模にもよりますが、医師、精神保健福祉士、臨床心理技術者などの専門職が居ます。
精神障害による症状で悩んでいる本人だけでなく、ご家族や周囲の人の相談も受け付けています。また、匿名での相談も受け付けています。医師から正式な診断を受けていなくても相談は可能です。
詳しくは、お住まいの自治体の精神保健福祉センターにお問い合わせください。(参考:精神保健福祉センターの全国一覧 厚生労働省「精神保健福祉センター」)
精神保健福祉センターについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
適応障害による休職から復職するまでの流れ
筆者の経験に基づき、適応障害による休職から復職するまでの流れを紹介します。
具体的な流れは、以下のとおりです。
- 医療機関で適応障害と診断される
- 適応障害を理由に休職する
- 給与の約2/3を受給できる「傷病手当金」と、医療費の自己負担額を3割から1割へ軽減できる「自立支援医療制度」の申請をする
- 傷病手当金を受給しつつ、自立支援医療制度で医療費を軽減しながら通院する
- 必要に応じて支援機関(就労移行支援事業所、精神保健福祉センターなど)を利用し、復職に向けた準備をする
- 復職する
まとめ:お金の心配を解決して、治療を優先しましょう。

休職期間中における最も大切なことは、無理をせず、治療することだと筆者は考えています。
ただ、治療が最優先とはいえ、適応障害と診断され休職したことで、金銭面と精神面での心配事が多くなり、療養に集中できない人も少なくないと思います。
そんな心配を解決できる制度や施設を利用して、治療に専念することをオススメします。
医師や家族、職場の人に相談できるのが理想ですが、そういった人々に相談しにくい人も、支援機関の利用をご検討してみてはいかがでしょうか。
本コラムがお金や復職への心配を解決し、安心して療養する為の助けになれば幸いです。
適応障害で休職した際の給料はどうなりますか?
適応障害で休職した場合、基本的に給料は支払われません。これは、民法第624条に由来します。ただし、会社によって就業規則が異なることにより、休職中でも一部または全額が支給される場合もあるようです。
詳細については、こちらで解説しています。
適応障害で休職中の人が利用できる経済的支援制度を教えてください。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→






