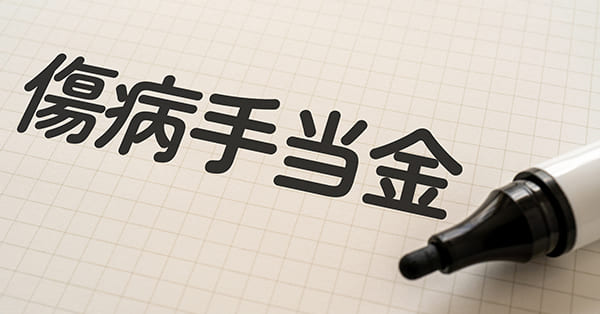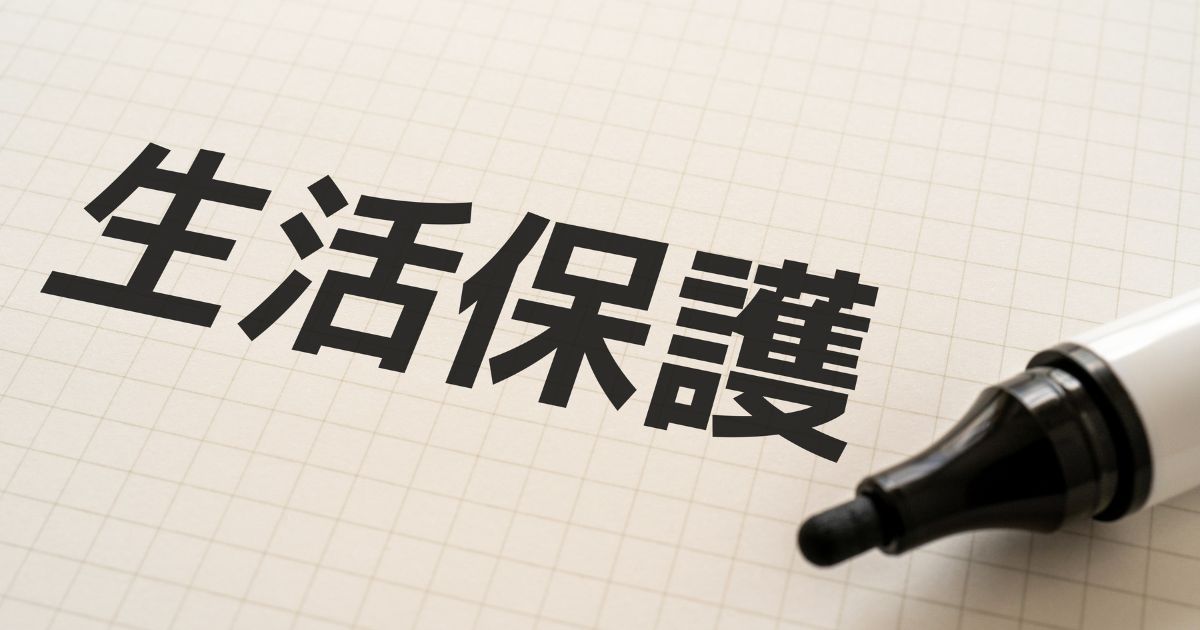就労移行支援は働きながら利用できる? 生活費の不安を解消する方法も解説
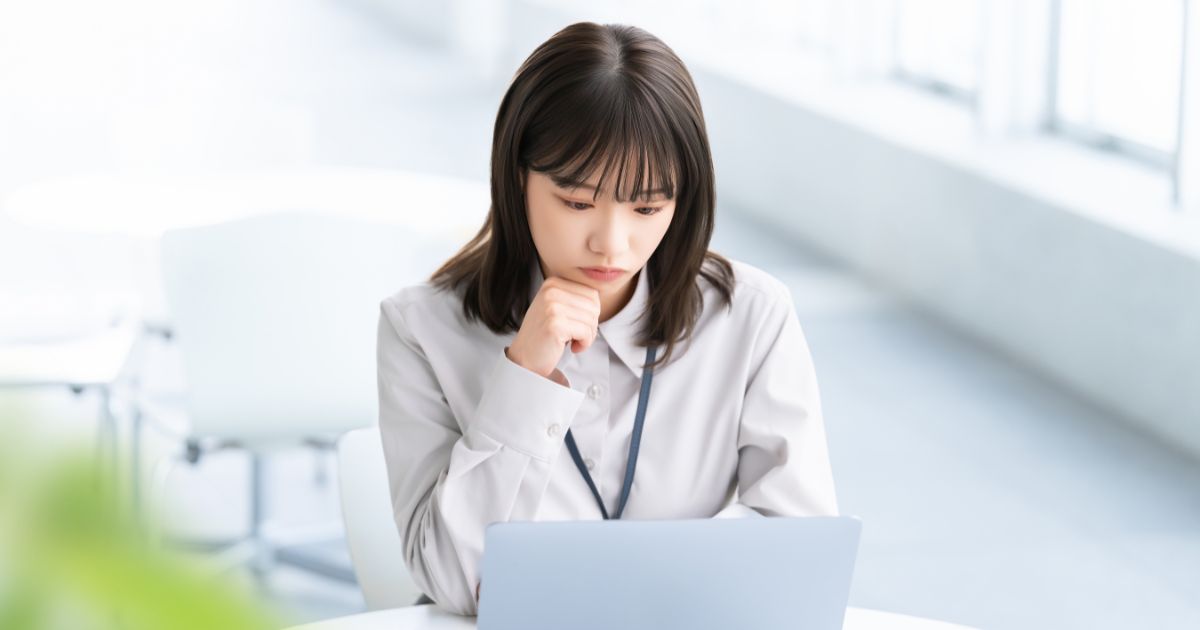
こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
- 働きながら就労移行支援を利用できるのかわからない
- 仕事を辞めたあと、生活費はどうしたらいいの?
このようなお悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、就労移行支援の利用条件や休職中の利用の可否、就労移行支援以外の働きながら受けられる支援についてわかりやすく解説します。
就労移行支援の利用を考えている人や生活費の不安の解消方法を知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
就労移行支援の利用を考えているあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
就労移行支援は原則働きながら利用できない

就労移行支援とは、障害のある人が就職に向けて集中的に訓練を行うための福祉サービスです。就労移行支援だけでは生活費を工面することが難しく、働きながら通所したいと思われる人もいるでしょう。
しかし、就労移行支援は、原則として仕事をしながら利用することはできません。就労移行支援は、障害のある人で一般企業で働くことを希望している人が対象であるためです。
すでに雇用されている人は就労中と見なされるため、原則として支援の対象外となります。ただし、条件つきで利用できる場合もあります。(参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」)
休職中に就労移行支援は利用できる?
就労移行支援は原則として就職を目指す人を対象とした制度ですが、休職中に心身のコンディションを整え、復職に向けたステップアップとして利用が認められるケースがあります。
ただし、休職中の利用には主治医の診断書や自治体の判断が不可欠です。まずは、お住まいの自治体の障害福祉窓口や就労移行支援事業所に相談してみましょう。(参考:厚生労働省「障害者の就労支援について」)、(池田市「休職中の障害福祉サービス(就労移行支援事業、就労継続支援事業等)の利用について」)
就労移行支援以外の復職・就労支援
この章では、就労移行支援以外の復職・就労支援について解説します。
就労移行支援以外にも、働きながら利用できたり、就労移行支援とは異なる目的で利用できたりする支援が存在しますので、参考にしてください。
支援①リワークプログラム

リワークプログラムとは、主に精神疾患で休職している人がスムーズに職場復帰できるようにサポートする専門的なプログラムです。医療機関や企業、一部の就労移行支援事業所などが提供しています。
リワークプログラムの主な目的は、職場への円滑な復帰と再発防止です。生活リズムの再構築やストレス対処法の習得、作業能力の回復を目指すための訓練などを実施します。
就労移行支援と異なり、元の職場への復職と定着を図るのが特徴です。
支援②就労継続支援A型・B型
就労継続支援とは、病気やケガ、障害などが原因で就労が困難な人に向けて、知識や能力を向上させるために必要な就労の機会や生産活動の機会を提供する福祉サービスのことです。
個々の状況やニーズに合わせて、仕事の技能向上や職場への適応支援などの幅広いサポートを提供します。
就労継続支援は、以下の2種類です。
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
A型は雇用契約を結んで働き、B型は雇用契約を結ばずに自分のペースで働くという違いがあります。
支援③デイケアなどの福祉サービス

デイケアなどの福祉サービスも、就労に向けたリハビリとして有効な手段です。
精神科の医療機関などが提供するデイケアでは、生活リズムの安定や対人関係スキルの向上を目指すプログラムが受けられます。精神疾患などがあり、社会参加の第一歩を踏み出したい人にオススメです。
また、地域活動支援センターなどで障害福祉サービスが提供されていることもあります。就労移行支援やリワークプログラムとはまた異なるアプローチで、働くための土台作りを始めるのも選択肢の1つでしょう。(参考:厚生労働省「地域活動支援センターの概要」)
仕事を辞めたときに生活費の不安を解消できる制度
この章では、仕事を辞めたときに生活費の不安を解消できる制度について解説します。
仕事を辞めたあと、生活費をどうするかについて不安を感じる人も多いでしょう。特に、収入がなくなることへの心配は切実です。
そのような場合に生活費をサポートしてくれる制度がありますので、就労移行支援の利用とあわせて検討してみてください。
制度①失業保険

失業保険は、雇用保険の被保険者であった人が、離職後に再就職の意思がありながら仕事が見つからない場合に、生活の安定を図るために支給される給付金です。
受給するには、離職理由や雇用保険の加入期間などの条件を満たす必要があります。(参考:厚生労働省「離職されたみなさまへ」)
制度②傷病手当金
傷病手当金は、病気やケガで仕事を休んだ際、健康保険の加入者を対象に生活を保障する制度です。医師の診断書が必要で、退職前・在職中に就労できない場合に支給されます。
在職中のほか、一定の条件を満たせば退職後も受け取ることが可能です。受給金額や受給期間は対象者の状況によって異なるため、加入している健康保険組合に確認しましょう。
制度③障害年金
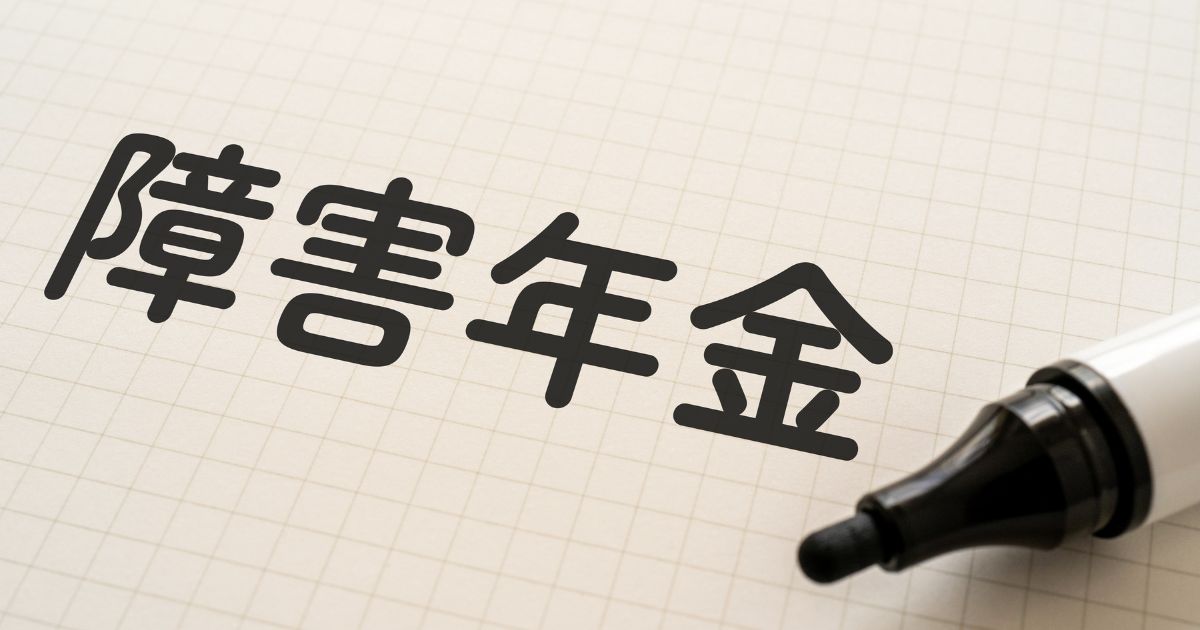
病気やケガが原因で生活や仕事に大きな支障が出ている場合、障害年金が利用できる可能性があります。現役世代も対象となる年金制度で、病気やケガで障害の状態になったときに、国から年金が支給される仕組みです。
障害の程度や年金の加入状況によって、受け取れる年金の種類や金額が変わります。主治医や年金事務所に相談してみましょう。
制度④生活保護
生活保護は、国が定めた最低限度の生活を保障する公的扶助制度です。あらゆる手段を尽くしても生活に困窮する場合、生活保護制度の利用が選択肢に挙がります。
病気やケガで働けない、障害があるなど、やむを得ない事情で生活に困窮している人が対象です。住居や医療、教育など、生活を営むうえで必要な扶助が受けられます。
なお、生活保護の申請は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所でおこないます。生活保護の利用を検討する場合は、福祉事務所で現在の状況について相談してみましょう。
制度⑤生活困窮者自立支援制度
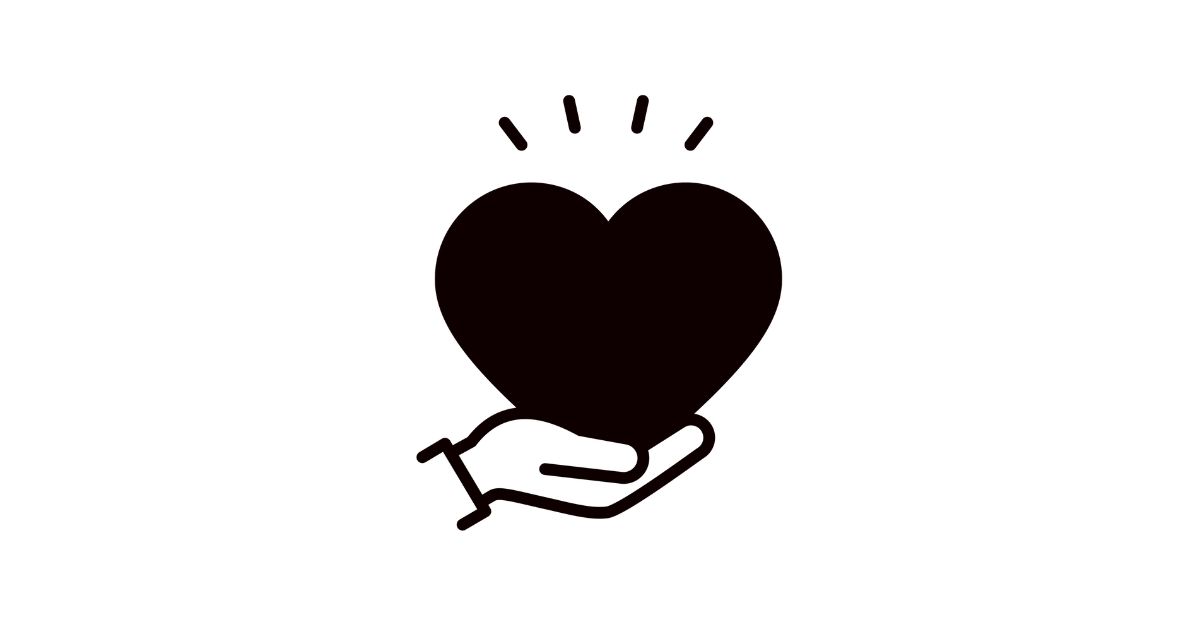
生活困窮者自立支援制度とは、経済的な不安だけでなく、仕事や住居、健康といった複合的な問題を抱える人に向けた支援制度のことです。
生活困窮者自立支援制度では、さまざまな取り組みを行い、生活困窮者に対して包括的な支援を実施します。支援内容は、以下のとおりです。
- 自立支援相談事業:困りごとの相談に応じ、解決に向けた支援プランを作成
- 住居確保給付金の支給:離職などにより住居を失った人に対し、家賃相当額を一定期間支給
- 就労準備支援事業:社会参加や就労に向けた基礎能力を養うためのプログラムを提供
- 家計改善支援事業:家計状況の分析や改善に向けたアドバイスや支援
- 就労訓練事業:知識や技能習得の機会を提供
- 生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業:学習支援や居場所づくりなどを通して、子どもの成長をサポート
- 一時生活支援事業:緊急的な生活困窮者に対し、一時的な宿泊場所や食事などを提供
これらの支援を組み合わせることで、経済的な困窮だけでなく、孤立や将来への不安といった複合的な問題の解決を目指します。
制度⑥生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度とは、一時的に生活に困窮している人や特定の目的のためにまとまった資金が必要な人に対し、無利子または低利子で資金を貸し付ける公的制度のことです。
各種資金にはそれぞれ利用目的が定められており、状況に応じて必要な支援を受けられます。
この制度で用意されている資金は、以下のとおりです。
- 総合支援資金:失業や収入減少により生活に困っている人への生活費支援
- 福祉資金:福祉用具の購入や介護サービス費用など、日常生活に必要な費用の支援
- 教育支援資金:高校・大学などへの進学や在学中の学費支援
- 不動産担保型生活資金:持ち家を担保にして、長期的な生活資金を確保する支援
いずれの貸付も、原則として無利子(または低利子)であり、返済の負担を抑えながら生活再建を目指せるのが、大きな魅力です。貸付の相談・申請は、お住まいの地域の社会福祉協議会でおこないます。
まとめ:働きながら就労移行支援は原則として利用できない

就労移行支援は、働きながらの利用は原則として認められていませんが、例外的に利用できる場合があります。
まずは、お住まいの自治体や利用を検討している就労移行支援事業所に相談し、ご自身の状況に合わせて適切な方法を見つけましょう。
また、退職後の生活費の不安を解消するには、失業保険や傷病手当金、障害年金などの公的制度の活用が選択肢として有効です。
これらの制度をうまく活用し、経済的な不安を和らげながら、安心して就職や復職に向けた準備を進めてみてください。
休職中に就労移行支援は利用できますか?
就労移行支援は原則として就職を目指す人を対象とした制度ですが、休職中に心身のコンディションを整え、復職に向けたステップアップとして利用が認められるケースがあります。
詳細については、こちらで解説しています。
仕事を辞めたときに生活費の不安を解消できる制度はありますか?
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→