社会不安障害・対人恐怖症のある人に向いてるアルバイト11選 探す際のポイントを解説
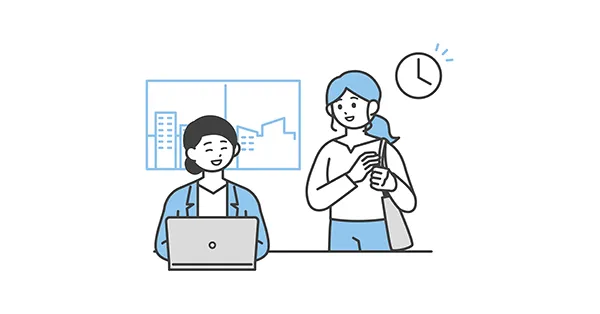
こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)の西村です。
このコラムをお読みのあなたは、社会不安障害(対人恐怖症)のために、「人と目を合わせるのがこわい」「人とうまく話せない」といった症状でお悩みではないでしょうか?
このコラムでは、社会不安障害の症状があるけれどアルバイトに挑戦したい人に向けて、社会不安障害の人に向いてるアルバイトやアルバイトを探す際のポイント、電話や面接で気をつけておきたいコツ、よくある困りごとと対処法について解説します。あわせて、社会不安障害のある人が利用できる支援機関を紹介します。
社会不安障害(対人恐怖症)の症状は、治療で軽減していくことができます。ですので、「現時点では難しいアルバイト」があっても、将来的には、様々な業種にチャレンジできるようになる可能性は大きいです。
このコラムで紹介する「おすすめのアルバイト」はあくまで例です。「実際のあなた」によって、おすすめできるアルバイトは、もっと多様にあり得ます。このコラムは、「社会不安障害(対人恐怖症)があっても、おすすめのアルバイトはある」という安心材料にしてください。その上で、「実際のあなた」に向いてるアルバイトは、後で紹介する支援団体などを利用することで、より具体的に見つかっていくはずです。
さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、周囲の目が気になり疲れを感じている方に向けて、「気疲れをやわらげる実践ガイドブック」の無料配布を開始いたしました。
「周囲の目が気になる…」という悩みに寄り添い、少しでも気持ちが楽になるよう、考え方のヒントや行動の見直し方をやさしく解説しています。
ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。
社会不安障害・対人恐怖症でお悩みのあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
社会不安障害の人に向いてるアルバイト11選

早速ではありますが、一般論として、社会不安障害の人におすすめできるアルバイトを11個、理由などとともにお伝えします。
アルバイト①短期で、ひとりで作業できる派遣アルバイト
1つ目は、派遣会社に登録してアルバイトする、という働き方です。派遣会社で働くことのメリットは2つあります。
1つ目のメリットは「仕事内容をある程度選べる」ということです。派遣会社では、派遣の会社が、実際に働く会社とあなたの間に立ってアルバイトを仲介してくれます。
そこで派遣会社の担当の人に「できるだけ人との関わりが少ない仕事を紹介してほしい」と伝えておくことで、社会不安障害の人が苦手とする「人との関わりが多い仕事」を紹介される可能性は下がります。
2つ目のメリットは「短期間でやめることもできる」という点です。派遣では、数か月、半年、1年などの短期契約を交わす場合が多いです。仕事が合わなければ、契約満了で辞職して、また別の仕事を探すということができます。
特に「自分に向いている仕事がわからない」という人にとっては、いくつかの仕事を経験する中で「自分にとって得意な業務・苦手な業務」を見極め、長く続けられる仕事内容を探していくことに役立ちます。
アルバイト②デリバリー配達・新聞配達
デリバリー配達は、最近ではウーバーイーツや出前館などが有名です。この仕事では、人との関わりは商品の受け渡しのみで、その他の時間はひとりでの移動となります。社会不安障害の人にとってハードルの低い仕事のひとつと言えるでしょう。
新聞配達は、人との関わりがいっそう少ないです。「業務で人と関わる場面を少しでも減らしたい」という人には向いている可能性があります(ただし朝が早い、休みづらい、体力が必要などの注意点もありますので、「人と関わりたくない人には絶対におすすめ!」というものではない旨、正直にお伝えします)。
アルバイト③在宅ワーク
在宅ワークも、人との接触が少ない点で社会不安障害の人におすすめのアルバイトのひとつです。
在宅ワークとひとくちにいっても、たとえば次のように、多様な仕事があります。
- ライター
- プログラマー
- イラストレーター
- アンケート回答
- 箱詰めなどの内職
最近では、クラウドワーキングといって、企業が業務の一部を在宅ワークとして外部発注している事例も増えてきています。
初心者向けの案件などもありますので、在宅ワークに興味があれば検討してみることをおすすめします。
アルバイト④工場のライン作業
4つ目は工場のライン作業です。この仕事は「人との関わりが少ない仕事」の代表的なものと言えるでしょう。黙々と作業を行い、ほとんど人と話すことなく仕事を終えることができます。
アルバイト⑤倉庫の仕分け
倉庫の仕分けアルバイトでは、注文された商品を取りに行くピッキングと、商品を箱に詰める箱詰め作業が主な業務です。
これらの仕事はマニュアルがあり、決まった動作を繰り返すことが多いです。臨機応変な対応を求められることは少なく、社会不安障害の人におすすめのアルバイトのひとつといえます。
アルバイト⑥清掃業務
社会不安障害の人には、ビルの清掃やホテルのベッドメイキングなどの清掃スタッフのアルバイトもおすすめです。
特に、ビルの清掃は夜の間に作業することが多く、ひとりで自分のペースを崩さず作業することができます。
ただ、ホテルの清掃となると2人1組や3人1組で作業する場所もあるので、応募する際には注意しておきましょう。
アルバイト⑦警備員
警備員は、業務中ほとんど人と話す必要がないですし、基本ひとり仕事なので、社会不安障害のある人におすすめのアルバイトのひとつです。
交通整理、イベント警備、ビルなどの警備、セキュリティ系の警備といった分類はありますが、いずれも上でお伝えしたのと同じメリットがあるといえるでしょう。
ただ、ビルの警備などは夜に行われる場合が多いので、暗い場所が苦手な人は避けておいたほうがいいかもしれません。
その上で、警備員は、「何かの事件・事故」が発生しないようにするとともに、発生したときには対応を求められる仕事です。警察や正社員の警備員ほどではありませんが、「アルバイト」の中では責任が比較的重いものであるということは、認識しておきましょう。
アルバイト⑧深夜のコンビニ
「深夜の人通りが少ない地域」であれば、コンビニのバイトもおすすめです。もちろん、お客さんが全く来ないわけではありません(だからこそ出店・営業しているのです)。「あまり人と関わりたくないけど、少しずつ人に接する経験を積んでいきたい」という人に特に向いているでしょう。
また、コンビニの業務は、工場のライン作業や倉庫のバイトに比べてやることが多く、複雑なので「同じ単純作業を続けるのはあまり好きではない」という人にもおすすめできます。
アルバイト⑨看板持ち
モデルルームやマンションギャラリーなどの、案内の看板を持つバイトです。指定の日に指定の場所に出勤し、看板やプラカードを持って立ちます。お客さまから尋ねられればチラシを渡したり道順を案内したりします。
仕事中のコミュニケーションが、「尋ねられたとき、質問に答える」のみであることが多いためにおすすめです。コミュニケーションが苦手な人もトライしやすいバイトです。
また、覚えることが少ないこと、単発の求人が多く、空いた時間にシフトを入れやすいこともメリットです。
アルバイト⑩交通量調査
交通量調査は、交差点の端や施設の入り口などに座って、車や人の数をカウントする仕事です。
行き交う車や人の数をひたすらカウントする作業なので、人とコミュニケーションを取る機会はほとんどないのでおすすめです。その代わり、集中して取り組む必要があります。
交通量調査は、道路工事の前や新しい商業施設の建設前などに行われることが多いです。そのため、求人の大半は長期ではなく、短期・単発です。
アルバイト⑪ポスティング
ポスティングとは、一戸建て住宅やアパート・マンションなどのポストに、チラシや広告を投函するアルバイトです。
時給制のところと、配布したチラシの枚数に応じた出来高制を採用しているところがあります。慣れてコツをつかめば、出来高制の方が効率よく稼げる可能性があります。
こちらも、「指定されたルートを一人で回る」ことが多いため、ほとんど人と関わらない仕事です。
社会不安障害の人がアルバイトを探す際の2つのポイント

前章のアルバイトは、あくまで一般論です。「実際のあなた」にはもっとおすすめのアルバイトがあったり、逆に前章のアルバイトは向いてなかったりもするでしょう。
そこで、社会不安障害の人がアルバイトを探すときに、押さえておきたい2つのポイントを紹介します。
ポイント①まずは自己分析をする
1つは「自己分析」です。特に、自分の症状、得意・苦手を把握した上で「できること」「できないこと」を見極め、アルバイトを選んでいく必要があります。
自分を見つめ直す作業である自己分析は、社会不安障害のない人であっても1人でするのは難しいものです。また、社会不安障害がある人の場合、自己分析という作業中にも不安な気持ちが表れることもあるかもしれません。
ですので、就労移行支援事業所や、障害者就業・生活支援センターの支援者などに相談してみてください。そうした支援者と、一緒に自己分析を行っていくことをおすすめします。
社会不安障害の症状から、「相談することが苦手」な人もいらっしゃるでしょう。ですが、そういった支援機関にいるスタッフや職員は、日頃から社会不安障害を含む様々な病気・障害のある人たちと向き合っています。
きっと、これまでの経験や知識を活かしてあなたの助けとなってくれます。(支援機関の詳細について、詳しくは後の章「社会不安障害の人がアルバイトや仕事を探すときに利用できるサポート団体5つ」で紹介します)
ポイント②苦手な要素の少ないバイトを探す
もう1つのポイントは「苦手な要素の少ないバイトを探す」ことです。
あなたには、社会不安障害の症状として「人前でプレゼンする」「電話対応する」など、なにかしら苦手な業務があるのではないかと思います。
前項の自己分析をもとに、あなたにとって苦手な要素を洗い出し、それらができるだけ少ないアルバイトを探していきましょう。例えば、以下のような「苦手」が考えられます。
- 人と頻繁に関わる環境
- 業務内容が定型的ではなく、臨機応変な対応が求められる環境
- 騒音や大きな音がする環境
- しばしば話しかけられるなど、自分のペースが乱されやすい環境
なお、支援者と話すことで、「社会不安障害が関係しない部分の苦手」や、逆に「得意な分野」「興味のある分野」なども(あなたが自分で気づいていた以上に)わかっていきます。
支援者への相談が役立つのは、「社会不安障害の特性が関わる『苦手』なアルバイトを避けることができる」ためだけではなく、「『苦手』を避けた上で、『得意』や『興味のある』アルバイトを探す」ためでもあるということです。
電話や面接で気をつけておきたい2つのコツ

「アルバイトをしたい」と考えたときに避けて通れないのが、電話や面接です(ウェブを通じて応募できるアルバイトは増えていますが、「まずは電話で連絡する必要がある」「応募前の調整は電話でのやりとりとなる」といったところも、もちろんあります)。
社会不安障害のある人は、電話・面接を苦手としている人が多いと思います。
ここでは、電話や面接といった場面でどういったことが求められているか、電話・面接で気をつけておきたいコツ2つについてお伝えします。
コツ①緊張しても大丈夫
電話や面接となると緊張してしまう、という人の中には「緊張しないように工夫しよう」「何度も練習して緊張せず話せるようにしよう」という方向で考える人が多くいらっしゃいます。
ですが「緊張しないようにしよう」と考えれば考えるほど、緊張に意識がいき、結果として緊張が強化されることも珍しくありません。
筆者は、受験や就職についての面接対策を行うことがよくあります。そこでお伝えするのは、「『緊張してもいい』『緊張するのは仕方ない』と考えてみてください」ということです。
電話にしろ面接にしろ、伝える必要のある内容をしっかりと相手に伝えられれば問題ありません。そこでどもったり噛んだり、といったことは、相手方は気にしていない場合が多いのです。
「自分が緊張している」という事実を否定するのではなく、「あぁ緊張しているな」「今自分は緊張しているんだな」と受け止めることで、緊張が強化されにくくなります。慣れも必要かもしれませんが、ぜひ試してみてください。
コツ②自己分析した内容を話せるように
「緊張していることを受け止める」「伝える必要のある内容を伝えられれば大丈夫」とお伝えしましたが、もちろん「何を伝えるか」は考えておく必要があります。
自己分析の内容を相手に適切に伝えられるように、言う内容を決めておきましょう。
その上で「何度か伝える練習をする」といったことは必要です。メモを見ながら話すなどの工夫をして、相手に伝える必要がある内容をしっかり伝える、ということを目標に取り組んでみましょう。
サポート団体・支援施設を利用すれば、そういった面接のロールプレイも手伝ってくれます。
また、面接の際にもメモを見る必要がある場合には、あらかじめ「すみません、緊張しているので、メモを見ながらお話ししてもよいですか」と伝えるようにしましょう。ほとんどの場合、OKをもらえるでしょう。
就労移行支援では支援者が面接に同行してくれるケースもあります。就労移行支援の利用を検討している場合、ぜひ相談してみてください。(利用できる支援施設・サポート団体について詳しくは、後の「社会不安障害の人がアルバイトや仕事を探すときに利用できるサポート団体5つ」をご覧ください)
社会不安障害によくある困りごとと対処法2選

続いて、社会不安障害の症状によって発生する、アルバイトに関係するよくある困りごととその対処法を2つお伝えします。
ただし、あくまで参考です。あなたひとりだけで対処しようとせず、社会不安障害の知識がある医師や支援者に協力を求めるようにしてください。
困りごと①電車やバスに乗ると症状が出る
電車やバスは、特にラッシュ時は人が多いため、社会不安障害の症状が表れやすくなります。
「ここで症状が強まると周りの人に迷惑をかけるのではないか」といったことも症状のきっかけとなりえます。
症状が出ることを避けるためには、乗る時間帯を変える、経路を変えるなど、できるだけ混雑していない電車やバスに乗れるように工夫をしてみるとよいでしょう。
どうしても時間帯や経路を変えることが難しい場合は、時間はかかりますが、心療内科や精神科での治療で考え方のクセを少しずつ切り替えていくことで対処できるようにしていくことが可能です。
困りごと②プレゼンなど、人前で話すことができない
社会不安障害の人の中には、人前で話すことに対する不安が強いことがよくあります。「以前、人前でうまく話せなかった」という経験が予期不安(次もそうなるんじゃないかという不安)になって、そういった場面を避けるようになった人も多いのではないでしょうか。
「人前で話すことができない」という症状についても、心療内科や精神科での薬物療法やカウンセリングの中で慣らしていくことで、症状を軽減させることが可能です。
カウンセリングでは、発作や不安の引き金になる認知(思考やイメージ)の癖を修正する「認知行動療法」や、不安や恐怖を覚えやすい状況に少しずつ身を置いて徐々に慣らしていく「曝露療法」などがあります。
こういった治療を適切に受けることによって、人前で話すことに対する苦手意識も少しずつ軽減していくことができます。
社会不安障害のある人が利用できる支援機関5選

社会不安障害の人がアルバイトを探す際に利用できる、代表的なサポート団体・支援機関を5つご紹介します。気になるところがあれば、問い合わせたり見学に行ったりして、利用するかどうかを検討してみてください。
支援機関①就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。実際のサービスは、国の基準を満たしたさまざまな民間の就労移行支援事業所が行います。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
就労移行支援事業所は各地にあります。私たち、キズキビジネスカレッジ(KBC)もその一つです。それぞれ特徴が異なるため、気になるところがあれば問い合わせてみてください。
支援機関②ハローワーク

ハローワーク(公共職業安定所)とは、仕事を探している人や求人を募集したい事業者に対して、就労に関連するさまざまなサービスを無償で提供する、厚生労働省が運営する支援機関のことです。正式名称は公共職業安定所で、職安と呼ぶ人もいます。(参考:厚生労働省「ハローワーク」厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」厚生労働省「公共職業安定所(ハローワーク)の主な取組と実績」、東京労働局「東京ハローワーク」、厚生労働省「こころの健康サポートガイド」、厚生労働省「ハローワークにおける障害者の就労支援」)
主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示などを行っており、具体的な支援内容は事業所によって異なりますが、一般的には以下のような幅広いサポートを行います。
全国に500ヶ所以上あり、主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示、雇用保険や雇用対策など、地域密着型の雇用に関する幅広いサポートを行います。
また、病気や障害のある人に向けたサポートも行っています。障害者手帳を所持していない人でも、医師による診断書があれば、障害の特性や希望職種に応じた職業相談や履歴書や面接での病気・障害の伝え方などのサポートを受けることができます。
支援機関③障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターとは、雇用や保健、福祉、教育に関する関係機関と連携し、障害のある人の雇用の促進・安定を目的とした一体的な支援を行っている支援機関のことです。(参考:厚生労働省「障害者就業・生活支援センター」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」、厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」)
障害のある人の就職活動の支援や求人の紹介、職場定着のためのサポートなどを行います。
就業面だけでなく、金銭管理などの経済面や生活面のことまで、日常および地域生活に関する支援も行っています。
生活習慣や金銭管理、健康管理などについても幅広く相談できるため、生活面のサポートも受けたい人にオススメです。
2024年4月1日時点で、障害者就業・生活支援センターは全国に337箇所設置されています。
支援機関④精神保健福祉センター

精神保健福祉センターとは、精神障害のある人のサポートを目的とした、地域の精神保健福祉の中核を担う支援機関のことです。(参考:東京都福祉保健局「精神保健福祉センターとは」、e-Gov法令検索「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)
精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)に基づき、各都道府県に設置されています。地域によって、こころの健康センターや心と体の相談センターなど、一部名称が異なります。
精神保健福祉センターでは、精神疾患に関連する悩みの相談や社会に適応するための指導と援助を行っています。
精神障害による症状で悩んでいる本人だけでなく、ご家族や周囲の人の相談も受け付けています。また、匿名での相談も受け付けています。医師から正式な診断を受けていなくても相談は可能です。
詳しくは、お住まいの自治体の精神保健福祉センターにお問い合わせください。
支援機関⑤地域障害者職業センター

地域障害者職業センターとは、病気や障害のある人に対して、職業評価や職業指導、職業準備訓練、職場適応援助などの専門的な職業リハビリテーションを提供する支援機関のことです。(参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センターによる支援」、厚生労働省「地域障害者職業センターの概要」)
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しており、障害者雇用促進法に基づいて、全国47都道府県に設置されています。(参考:厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律」)
ハローワークや医療・福祉機関と連携しているため、仕事に関する相談や訓練、復職するためのサポートを行っています。
病気や障害に悩む当事者だけでなく、障害のある人を雇用する事業所に対して、雇用管理に関する相談・援助も行っています。
社会不安障害、対人恐怖症とは?
この章では、社会不安障害について、概要や症状をお伝えします。既にご存知かもしれませんが、これまでに紹介した内容の理解も深まると思いますので、ぜひご覧ください(参考:『精神診療プラチナマニュアル第2版』、厚生労働省 こころもメンテしよう〜若者を支えるメンタルヘルスサイト〜「不安障害」)
社会不安障害の概要
社会不安障害とは、不安障害の一種で、対人恐怖症とも呼ばれているものです。社会不安障害の人は、多くの人の注目が集まるような場面で「人の目が過剰に気になる」「人と話すととても緊張し、息苦しさや腹痛を感じる」といった症状が表れます。
社会不安障害の症状
社会不安障害の一般的な症状には、以下のようなものがあります。
- 大勢の人の前で話す
- 多くの人の注目を浴びる
- 他者との雑談
- 電話対応
- 人前での食事
- 誰かに見られている状況で字を書く
- 話すことが必要とされる場所(美容院など)
- デートや出会いの場(合コンなど)
- 電車の中や、人の多い空間など
- 不安
- 恐怖
- 顔が赤くなる
- うまく喋れない(声がふるえるなど)
- 心拍数の上昇
- めまい
- 吐き気
- 手足のふるえ
- 口渇(口の乾き)
- 多量の汗
社会不安障害の症状は軽減できる
社会不安障害では、上記のような症状に長く苦しめられている人も少なくありません。ですが、こういった社会不安障害の症状は軽減していくことができます。
症状を軽減させていくためには、医療機関やサポート機関につながることがもっとも確実な方法です。社会不安障害の治療では、主に薬物療法とカウンセリングが使用されます。
カウンセリングでは、認知行動療法や曝露療法といった方法が用いられ、あなたのお話をお聞きしながら「自分自身の考え方のクセを見直していく」「苦手な場所や状況に、段階的に少しずつ慣らしていく」といった治療が行われます。
決して無理な治療は行われませんし、医師・治療者があなたの苦手なタイプであれば、場所を変え、セカンドオピニオンを求めてもまったく問題ありません。むしろ、精神疾患の治療には、患者と治療者の信頼関係が大切なので「この人ならある程度信頼できそう」と思える医師や医療者を見つけ、治療していくことをおすすめします。
心療内科や精神科で上記のような治療法を用いることで、社会不安障害の症状は少しずつ軽減していくことが可能です。
【無料配布中!】『気疲れをやわらげる実践ガイドブック』
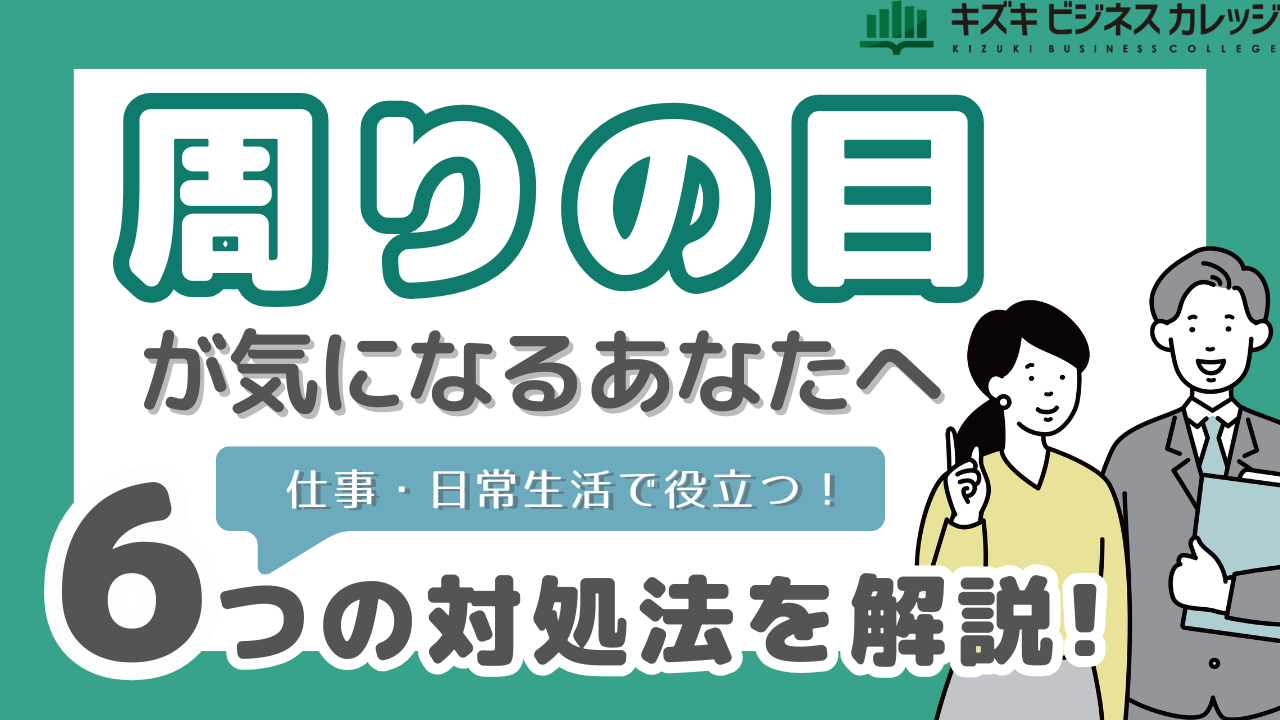
- 「職場で浮いていないか不安」
- 「変に思われないか心配で行動できない」
このように周囲の目を気にし、日常生活でつらさや疲れを感じる人が増えています。
他人の視線に敏感になること自体は悪いことではありません。しかし、過剰になると、自分らしくいられなくなり、心身の不調を招くこともあります。
本資料では、周囲の目が気になる方の悩みに寄り添い、少しでも気持ちが楽になるよう、考え方のヒントや行動の見直し方をやさしく解説しています。
ぜひ、この機会にあなたの悩みやつらさを一緒に取り除きませんか?
- 周囲の目が気になる理由と背景
- 周りの目を気にしすぎることで起こりうる問題
- 自分をラクにするための6つの対処法
- 思考の偏りや完璧主義との向き合い方
- 「気にしすぎ」から自由になる考え方のヒント
- 他人の目が気になって行動に自信がもてない方
- 職場や日常生活で過度に気を遣っている方
- 自分の本音を抑え込みがちな方
- 完璧でいようとして疲れている方
- 悩みやつらさを一人で抱え込んでいる方
- リンクから申し込みフォームにアクセス
- 簡単なフォームに入力
- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り
- URLから資料を取得!
- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。
- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。
- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。
まとめ:症状の対処をしながら自分に合うバイトを見つけよう!

ここまで、社会不安障害の人におすすめのアルバイトや電話・面接での注意点などをお伝えしました。
社会不安障害の症状があるために「アルバイトが長続きしない」「自分に向いてるバイトが見つけられない」と感じている人も多いと思います。
症状を軽減しながら、自分に合ったアルバイトを見つけ、続けていくためにも、ぜひ一度医師や支援者に相談していただくことをおすすめします。
社会不安障害の知識がある医師や支援者とともに「あなたに合ったアルバイト」を探していくことで、これまでとは違った視点からあなたに向いているアルバイトを見つけていくことができるでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。このコラムの情報があなたのアルバイト探しのお役に立てば幸いです。
社交不安障害・対人恐怖症の自分に向いてるアルバイトを知りたいです。
一般論として、次のようなアルバイトは向いてる可能性があります。
- 短期で、ひとりで作業できる派遣アルバイト
- デリバリー配達・新聞配達
- 在宅ワーク
- 工場のライン作業
- 倉庫の仕分け
- 清掃業務
- 警備員
- 深夜のコンビニ
- 看板持ち
- 交通量調査
- ポスティング
詳細はこちらをご覧ください。
社交不安障害・対人恐怖症の自分がアルバイトを探すためのポイントを知りたいです。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→







