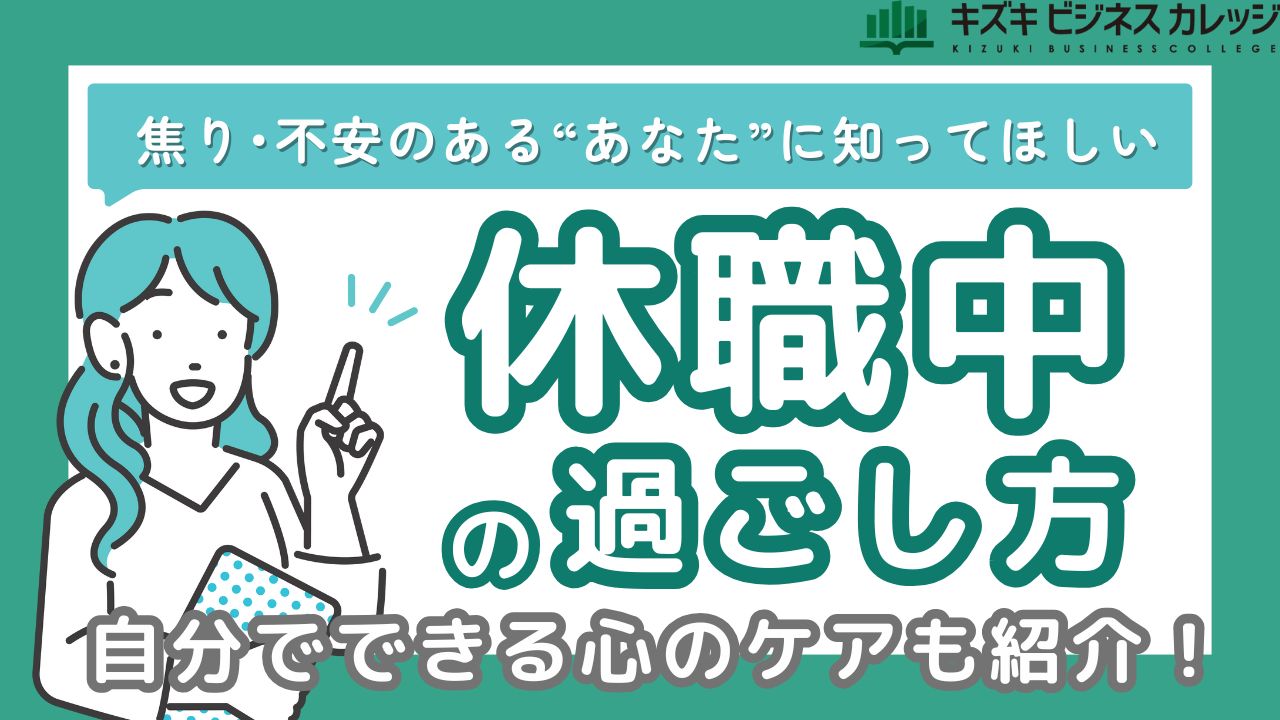仕事で急にミスが増えた原因とは? 対処法や病気の可能性について解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
「最近、いつもなら絶対にしないようなミスばかりしている...」。そんな悩みを抱えていませんか?
これまで問題なく仕事ができていたのに、突然ミスが増えると不安になりますよね。
仕事で急にミスが増える背景には、一時的な要因から心身の健康問題まで、さまざまな原因が存在しています。
このコラムでは、仕事で急にミスが増えたときの原因と対処法、病気の可能性について解説します。
あわせて、相談できる支援機関も紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
仕事のミスが増えて悩んでいるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
仕事で急にミスが増えたときの6つの原因
この章では、仕事で急にミスが増える原因について解説します。
仕事のミスへの対処法は、こちらで解説します。
原因①心身の疲労・ストレスの蓄積

慢性的な疲労やストレスは、ミスを引き起こす大きな原因の一つです。
長期間にわたって蓄積された疲労は、脳の判断力や記憶力を大幅に低下させます。「いつもなら気づくのに…」というミスは、まさに疲労が原因かもしれません。
また、人間関係や仕事のプレッシャーによるストレスも、注意力散漫の原因になります。ストレスを受けると、思考や記憶をコントロールする脳の前頭前野という領域の機能が低下します。(参考:東邦大学「ストレスと脳」)
その結果、普段なら簡単にできる情報の整理や優先順位の判断ができなくなり、小さなミスを見逃しやすくなります。
特に責任感の強い人ほど、「完璧にやらなければ」というプレッシャーが逆にストレスとなり、悪循環になりやすいため注意が必要です。
原因②職場環境の変化
転職や異動、新しいシステムの導入など、職場環境の変化はミスが急増する大きな要因です。
慣れない環境では確認漏れが発生しやすく、新しい業務やシステムに適応するまでの間は特にミスが起こりやすくなります。
また、新しい職場での人間関係の構築に気を遣ったり、以前とは異なるコミュニケーション方法に戸惑ったりすることで、本来の業務への集中力が分散することもあります。
「前の職場では問題なかったのに」と感じているなら、環境変化による一時的な適応障害による症状かもしれません。
適応障害については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
原因③睡眠不足・休息不足

睡眠不足や休息不足は、脳の情報処理能力を大きく低下させます。
十分な睡眠を取れていないと、簡単なケアレスミスを見逃しやすくなります。特に夜更かしが続いたり、質の悪い睡眠が続いたりすると、翌日の集中力や判断力に大きな影響を与えます。
「最近、よく眠れていない」「朝起きても疲れが取れない」という状況が続いているなら、睡眠の質を見直す必要があるでしょう。また、休息不足も同様で、適度なリフレッシュタイムがないと、集中力の持続時間が短くなります。
原因④仕事量の増加によるオーバーワーク
新規プロジェクトの立ち上げや人員不足で業務量が増加すると、自分の処理能力を超えることがあります。
締切に追われる状況では、一つひとつの作業に十分な確認時間が取れず、どうしてもミスが発生しやすくなります。
さらに、過度な業務量が精神的負担を増やし、集中力を低下させる要因となります。長時間労働や残業が常態化すると、慢性的なストレスが蓄積され、頑張っているのにミスが多くなるという悪循環になりやすいです。
原因⑤整理整頓や確認作業の不足

デスク周りの整理整頓ができていないと、必要な資料を探すだけで時間を取られます。
「あの資料はどこに置いたっけ?」「このファイルの最新版はどれだろう?」といった状況が続くと、作業そのものに集中できなくなり、ミスが起こりやすくなります。
また、メモやチェックリストを使わずに記憶だけで作業を進めると、うっかりミスが起こりやすくなります。さらに、時間がないからといって確認作業を省略すると、かえって大きな時間のロスにつながります。
いつも探し物をしている、確認作業を飛ばしがち、という心当たりがある場合は、作業プロセスを見直してみましょう。
原因⑥組織体制の問題
個人の努力だけでは解決できない、会社や組織の仕組みによるミスも存在します。
作業の手順書やマニュアルが適切に整備されていない場合、業務を覚える際に、正確な手順を把握できないままに作業を進めることで、ミスが発生しやすくなります。
また、業務分担や責任範囲が曖昧だと、「誰がやるべき作業なのか分からない」「ほかの人がやってくれると思っていた」といった認識のずれから、重要なタスクの抜け漏れが発生するリスクが高まります。
さらに、定期的な研修や指導の仕組みが整っていないと、個人の経験や勘に頼った作業が増え、ミスが多くなる原因になります。
自分でできるミスを減らすための対処法6選
この章では、ミスを減らすために自分でできる対処法について解説します。
対処法①メモの活用

メモを活用することで、記憶に頼らない確実な情報管理ができるようになります。
会議や電話の内容は、聞いた瞬間に書き留める習慣をつけましょう。「これくらいは覚えているだろう」という思い込みを捨てて、自分の記憶力を過信しないことが大切です。
スマートフォンの音声メモ機能やToDoアプリなどのデジタルツールも併用すると、より確実に情報を保存できます。
また、メモした内容は定期的に見直し、必要に応じてタスクリストやスケジュールに反映させると良いでしょう。
対処法②優先順位を決める
優先順位を明確にすることで、締め切りに追われることなく効率的に作業ができるようになります。
緊急度と重要度でタスクを以下の4つに分類します。
- 緊急かつ重要
- 重要だが緊急ではない
- 緊急だが重要ではない
- 緊急でも重要でもない
タスクを分類することで、今すぐやるべきことと後回しできることを明確に区別します。
ただし、優先順位は状況の変化に応じて変わるため、定期的な見直しが必要です。始業時や昼休み後など、決まったタイミングで優先順位を確認し、必要に応じて調整しましょう。
一度に全てをやろうとせず、優先順位に従って一つずつ確実に進めることが重要です。
対処法③チェックリスト作成
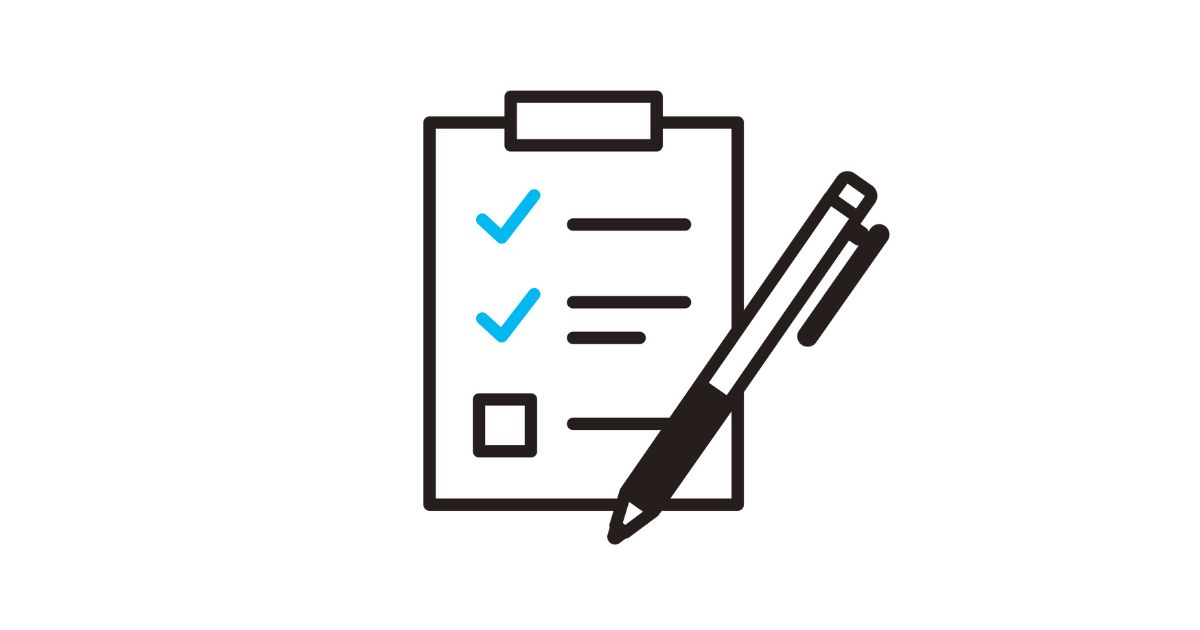
決まった作業をするときは、作業の手順を箇条書きにしたチェックリストを作成することで抜け漏れを効果的に防げます。
手順や注意点を時系列で整理し、完了時にチェックを入れる習慣をつけましょう。チェックを入れることで、どこまで進んだかが一目でわかります。
最初は面倒に感じるかもしれませんが、一度作ってしまえば同じ作業を繰り返すときに大きな安心感が得られます。「確認したかどうか分からない」という不安からも解放されますよ。
対処法④作業環境の見直し
作業環境を整えることで、集中力を高めることができます。
まずは、デスクの整理整頓から始めましょう。
頻繁に使用するものは手の届く範囲に配置し、使わないものは視界に入らないように片付けます。必要な物を適切に配置することで、作業効率が大幅に向上します。
適切な照明と室温の調整も重要なポイントです。
暗すぎる環境は目が疲れやすくなり、明るすぎる環境は集中力を低下させます。照明は適度な明るさに調整し、室温は空調の設定や調節しやすい服装などで快適な温度を保ちましょう。
「なんだか集中できない」と感じたら、まずは身の回りの環境をチェックしてみてください。小さな変化でも、集中力に大きな影響を与えることがあります。
対処法⑤適度な休息を取る

定期的に短い休憩を挟むことで、長時間の集中力を維持できます。
1時間に5〜10分程度の小休憩を取ることを心がけましょう。
昼休みは席を離れ、軽い散歩やストレッチを行うのがオススメです。外の空気を吸ったり、軽く体を動かしたりすることで、午後の業務に向けてリフレッシュできます。
また、疲労が蓄積している場合は、必要に応じて有給休暇を取得することも大切です。
疲れた状態で無理に働き続けるよりも、しっかり休んでから取り組むほうが、最終的には効率が上がり、ミスの発生も抑えられるはずです。
ただし、有給休暇だけでは回復できないほどの疲労を感じている場合は、休職という選択肢も検討する必要があるでしょう。
休職については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
対処法⑥睡眠・生活習慣の見直し
注意力を維持し、ミスを防ぐためには、生活習慣を見直すことが重要です。
毎日7〜8時間の睡眠を取ることで、脳内の記憶の整理が行われ、翌日の注意力と判断力が回復します。
質の良い睡眠を取るには、就寝前のスマートフォンやテレビの使用を控え、部屋を暗くして静かな環境を整えることが効果的です。
また、バランスの取れた食事と栄養管理も重要な要素です。特に朝食を抜いたり、糖質ばかりの食事を続けたりすると、血糖値の急激な変動で集中力が続かなくなります。
規則正しい生活リズムを心がけて、身体のコンディションを整えることで、仕事のパフォーマンスも自然と向上していきます。
職場でできるミスを減らすための対処法4選
この章では、ミスを減らすために職場でできる対処法について解説します。
対処法①ダブルチェック体制づくり

チームでダブルチェック体制を構築し、お互いにミスを防ぎ合う仕組みを作りましょう。
一人で作業した内容を別の人が確認することで、個人では見落としがちなミスをチーム全体でカバーできます。
ほかの人の視点が入ることで、作成者が気づかなかった問題点や改善点を発見できるというメリットもあります。
また、ミスが発生した際は、ミスの発生パターンを分析し、対策を立てることが重要です。過去のミス事例を蓄積し、チーム内で共有することで再発防止につながります。
お互いにチェックし合うことで、チーム全体のスキルアップにもつながります。
対処法②上司や同僚への相談
困ったことがあるときは、一人で悩まずに上司や同僚に積極的に相談することが大切です。
上司に定期的な面談や進捗確認の時間を設けてもらい、現在困っていることや不安に感じていることを率直に話してみましょう。
分からないことがあれば遠慮せずに質問し、不明点は早めに解消することも重要です。
特に、業務量の調整については、上司としっかり話し合い、現在の作業量が適切かどうか検討してもらいましょう。
無理な業務量を一人で抱え続けていると、ミスが増えるだけでなく、ストレスや疲労が蓄積して心身の健康を損なう恐れもあります。
また、同僚との情報共有も効果的です。似たような経験を持つ先輩からアドバイスをもらったり、チーム全体で業務の進め方を見直したりすることで、働きやすい環境を作ることができます。
対処法③合理的配慮を受ける

発達障害や精神障害などのある人は、職場で合理的配慮を申請できます。
合理的配慮とは、障害のある人の社会的なバリアを取り除くため、事業者側が過重な負担にならない範囲で必要な対応をすることです。(参加:政府広報オンライン「対話が重要 障害のある人への合理的配慮」)
合理的配慮を受けると、業務量の調整や作業手順の変更、職場環境の改善など、個人の特性に応じた支援を受けられます。
合理的配慮を申請する際は、直属の上司や人事を担当する部署、産業医などに相談してみてください。
申請時には、自分が抱えている困りごとを具体的に説明し、自分にとってどのような配慮が必要なのかを明確に伝えることが重要です。
適切な配慮を受けることで、ミスを減らしながら、持っている能力を最大限に活かせる環境を作っていくことができます。
ただし、合理的配慮を受けられるかどうかについては、職場の状況やあなたの症状などによって異なりますので、まずは職場や主治医、専門機関と相談してみましょう。
対処法④産業医やカウンセラーへの相談
職場に産業医や企業内カウンセラーがいる場合は、健康面やメンタル面のサポートを受けられます。
産業医との面談を通して、定期的な健康チェックや相談をすることで、身体的・精神的な不調がミスの原因になっていないかを確認できます。
産業医は、身体の不調だけでなく、業務に関連するストレスや心の健康についても幅広く対応し、医学的な観点から適切なアドバイスを提供します。
また、企業内カウンセラーは心理的なサポートに特化しており、ストレスや不安、職場の人間関係の悩みなど、精神的な負担がミスにつながっている場合に力になってくれます。
なお、これらの専門家は守秘義務があるため、安心して相談ができます。
早めに専門家に相談することで、問題が深刻化する前に対処でき、職場復帰や業務改善につながります。一人で悩まず、専門家の力を借りることも大切な選択肢です。
急にミスが増えるのは病気の可能性も
この章では、急にミスが増える可能性がある病気について解説します。
①うつ病

うつ病とは、気分の落ち込みや憂うつ感、さまざまな意欲の低下などの精神的症状と、不眠、食欲の低下、疲労感などの身体的症状が一定期間持続することで、日常生活に大きな支障が生じる精神障害・気分障害のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、厚生労働省「1 うつ病とは:」、厚生労働省「うつ病に関してまとめたページ」、、厚生労働省「うつ病」、国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「うつ病」、MSDマニュアルプロフェッショナル版「抑うつ症候群」)
また、脳の機能が低下している状態、脳のエネルギーが欠乏した状態を指し、脳の中で神経細胞間のさまざまな情報の伝達を担うセロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンなどの神経伝達物質のバランスの乱れや、感情や意欲を司る脳の働きに何らかの不調が生じているものと考えられています。
うつ病の症状として、集中力・判断力・記憶力の低下などが現れ、仕事でのミスが増加することがあります。
以前は楽にこなせていた業務でも集中が困難になり、簡単な作業でも時間がかかったり、重要な点を見落としたりするようになります。
気分の落ち込み、やる気の著しい低下、睡眠障害なども併発することが多く、日常生活全般に支障をきたします。
しかし、うつ病は適切な治療により改善が期待できる疾患です。治療には抗うつ薬の服用や心理療法が効果的とされています。
一人で抱え込まず、医療機関や周囲のサポートを積極的に活用することが重要です。
②適応障害

適応障害とは、仕事や職場の人間関係などから生じる特定可能な明確な心理的・社会的ストレスを原因に、心身がうまく対応できず、情緒面の症状や行動面の症状、身体的症状が現れることで、社会生活が著しく困難になっている状態のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、松﨑博光『新版 マジメすぎて、苦しい人たち:私も、適応障害かもしれない…』e-ヘルスネット「適応障害」)
症状は通常、ストレスの原因となった出来事から3ヶ月以内に始まり、その原因がなくなれば6ヶ月以内に回復することが多いのが特徴です。
具体的な症状として、憂うつな気分や不安感に加え、思考力や集中力の低下が現れ、仕事でのミスの増加につながることがあります。
また、頭痛や胃痛、倦怠感などの身体症状を伴う場合もあります。
適応障害は、ストレス要因の除去や軽減、カウンセリングなどの治療により改善が期待できます。
環境変化に伴ってミスが増えた場合は、適応障害の可能性を考慮し、早めに対処することが重要です。
③発達障害

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)
これまで問題なく働けていても、業務の複雑化や環境の変化により、発達障害による困難が顕在化することがあります。
ADHD(注意欠如・多動性障害)の場合、注意散漫や衝動的な行動により、確認不足や優先順位の判断ミスが目立つようになります。
ASD(自閉症スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)では、暗黙の了解や曖昧な指示の理解が難しく、対人コミュニケーションのずれから作業指示を誤解しやすくなることがあります。
LD/SLD(学習障害/限局性学習症)がある場合は、読み書きや計算処理に通常より時間がかかるため、業務効率の低下やミスの増加につながることもあります。
しかし、発達障害があっても、適切な診断を受けて特性を理解し、必要に応じて治療や支援を受けることで状況は改善できます。
また、職場での合理的配慮により、個人の強みを活かしながら働き続けることも可能です。
急にミスが増えたとき相談できる支援機関
この章では、ミスが増えたときに相談できる支援機関を紹介します。
支援機関①総合労働相談コーナー
総合労働相談コーナーは、職場でのトラブルや労働条件などあらゆる分野の労働問題に関する相談に対応しています。
専門相談員による適切なアドバイスを受けることができ、必要に応じてほかの機関への紹介も行っています。
予約不要で無料で利用でき、面談もしくは電話での相談が可能です。
全国の労働局や労働基準監督署内など379か所に設置されています。各地域の所在地や電話番号は厚生労働省のサイトで確認できます。(参考:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」)
厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
支援機関②こころの耳

こころの耳は、働く人のメンタルヘルス専門の相談窓口です。
- 電話番号:0120-565-455
- 受付時間:
平日(月曜日~金曜日) 17:00~22:00
土曜日・日曜日 10:00~16:00
(祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
電話やメール、SNSでの相談が可能で、産業カウンセラーなどの専門知識を持つ相談員が対応してくれます。(参考:こころの耳「働く人の「こころの耳電話相談」)
仕事でのミスが増えた背景にストレスやメンタルヘルスの問題がある場合、専門的な視点からアドバイスを受けられます。
支援機関③自立相談支援機関
自立相談支援機関は、就職や住まい、家計管理などの困りごとを抱えている人を支援する機関です。
就労に関する相談とサポートを行っており、家計管理や住居確保の支援も受けることができます。(参考:困窮者支援情報共有サイト「自立相談支援事業」)
関係機関との連携による総合的な支援が特徴で、個々人の状態に合わせたプランに基づく継続的な支援を受けられます。
各地域の自立相談支援機関の相談窓口は、以下のサイトから確認できます。
一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク 困窮者支援情報共有サイト ~みんなつながるネットワーク~「自立相談支援機関 相談窓口一覧」
支援機関④就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。実際のサービスは、国の基準を満たしたさまざまな民間の就労移行支援事業所が行います。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)も就労移行支援事業所のひとつです。
キズキビジネスカレッジ(KBC)では、ビジネススキルの講座や自分に合った職業を見つけるための適職診断などのプログラムを行っています。
さらに、個別面談を通じて、ミスが生じる原因の分析や対処法についても相談することが可能です。
障害者手帳がなくても、医師の診断や定期的な通院があれば、支援を受けられる可能性があります。
相談・見学は無料なので、気になる事業所があれば、問い合わせてみてください。
まとめ:自分に合った対処法を見つけましょう

仕事でミスが急に増えた場合、その原因は疲労やストレス、環境の変化、病気の可能性など多岐にわたります。
まずは原因を正しく把握し、自分に合った対処法を見つけることが大切です。
自分でできる対策に加えて、職場環境の改善や専門的な支援の活用も重要な選択肢になります。
つらいときは一人で抱え込まず、上司や同僚、専門機関への相談を検討してみてください。
仕事で急にミスが増えたときの原因は何ですか?
以下が考えられます。
- 心身の疲労・ストレスの蓄積
- 職場環境の変化
- 睡眠不足・休息不足
- 仕事量の増加によるオーバーワーク
- 整理整頓や確認作業の不足
- 組織体制の問題
詳細については、こちらで解説しています。
自分でできるミスを減らすための対処法を教えてください。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→