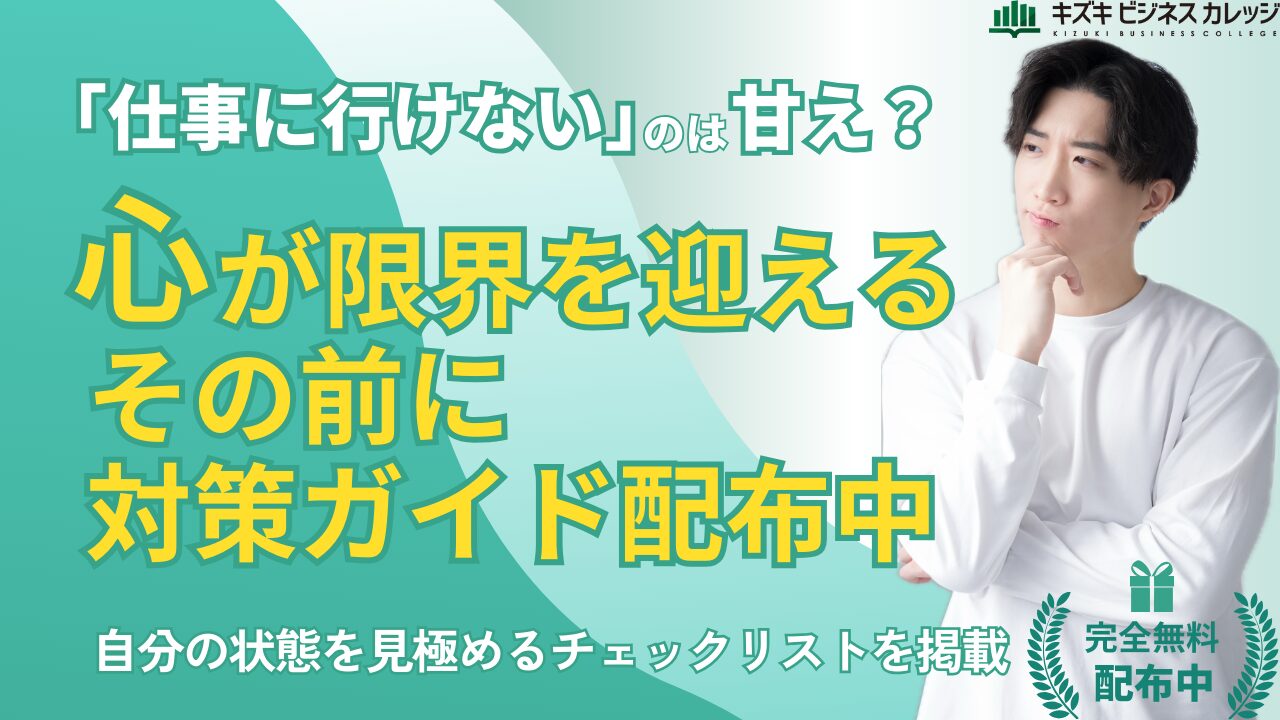やりたい仕事の見つけ方7選 困ったときに頼れる支援機関を紹介

こんにちは、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
このコラムを読んでいるあなたは、以下のような悩みを持っているのではないでしょうか?
- 仕事をしてはいるものの、今一つ没頭できない
- 本当にやりたい仕事を見つけたい
- もっと自分が貢献できる仕事を見つけたい
このコラムでは、向いてる仕事がわからない人の多さややりたい仕事が見つからない人の傾向、やりたい仕事の見つけ方などについて解説します。また、やりたい仕事を見つけられる就職支援機関を紹介します。
仕事についてお悩みの人は、ぜひご覧ください。
やりたい仕事を見つからず悩んでいるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
向いてる仕事がわからない人は多い

向いてる仕事がわからないと悩んでいる人は、実は少なくありません。
2021年、労働政策研究・研修機構は、大都市の若者を対象に就業行動と意識に関する調査を行いました。(参考:労働政策研究・研修機構『労働政策研究報告書No.213大都市の若者の就業行動と意識の変容-「第5回 若者のワークスタイル調査」から』)
この調査によると、大学または大学院を卒業後に就職、転職した人のうち「自分に向いてる仕事がわからない」という問いに「そう思う」と答えた人の割合は、以下のようになりました。
- 男性:25~29歳約19.1%、30~34歳約15.2%
- 女性:25~29歳約16.4%、30~34歳約16.5%
ここから、向いてる仕事ややりたい仕事を見つけられずにいる人は少なくないことが推測できます。
やりたい仕事が見つからない人の傾向
この章では、やりたい仕事が見つからない人の傾向について解説します。
傾向①自信がない

社会人としての理想像と現状のギャップ、実績・経験の少なさなどから、社会人として自信を持てずにいるケースがあります。
それによって仕事に対する抵抗感が生じれば、仕事をやりたくない、やりたい仕事がないと感じることもあるでしょう。
このような場合には、目の前の仕事に没頭する、新しくスキルを獲得するなどを通じて、成功体験を重ねましょう。
できることが増えて自信を持てるようになれば、仕事のやりがいや面白さを見つけられる可能性があります。
また、過去の失敗を思い出しやすい人は、対処方法を学ぶよい経験を得られたと捉え、今後に活かそうとする気持ちを持つことが大切です。
傾向②慎重すぎる
転職や就職を確実に成功させたい、転職するなら失敗してはいけないなど、慎重になりすぎているケースもあります。
転職や就職の際は、まずは情報収集や応募などのアクションを起こすことが大切です。さまざまな仕事の情報に触れるうちに、やりたい仕事が見つかる可能性が高まります。
1度の転職で必ず成功させようと思わず、「まずは詳細を見てみよう」「もし合わなかったらまた転職してもいい」くらいの気持ちで着手してみましょう。
また、仕事探しに慎重になるあまり、内容・職場の悪い面ばかりに目が向いてるケースもあります。悪い面ばかり注目する傾向のある人は、良い面と悪い面の双方を見て、総合的な判断ができるよう、気持ちに余裕を持って取り組むことも大切です。
傾向③自分自身への理解が深くない

自己分析が足りず、仕事選びの軸がはっきりしていないために、やりたい仕事が見つからないケースもあります。
例えば、以下の要素についておおまかな方向性を見出しておくと、やりたい仕事を見つけるのに役立つでしょう。
- 仕事を通じてやりたいこと、得たいもの
- 自分が好きなこと、嫌いなこと、興味があること
- 得意なこと、苦手なこと
自己分析は、1人で取り組んでも問題ありません。しかし、第三者との対話を通じて理解を深めると、自分自身では思いつかなかったような、思わぬ長所が見つかることもあります。身近な人の手も借りながら、自己分析に取り組んでみましょう。
傾向④希望する条件が多い
仕事や職場に対する希望条件が多い場合も、やりたい仕事が見つからない状況になる可能性があります。
適職を見つけるためにいくつかの条件を設けることは必要ですが、以下のように条件が多すぎると、合致する職場をなかなか見つけられなくなるでしょう。
- 家から徒歩圏内
- 給料は30万円以上必須
- 福利厚生が手厚い
- フレックスタイム制を導入している
- リモートワークができる
- 興味を持てる仕事内容がメイン
条件に照らし合わせながらさまざまな求人を比較していると、そもそもなにをやりたかったのか、本当にやりたいと思っていたことなのか、などがわからなくなることもあるでしょう。
理想と完全に一致する職場はないことを前提として、譲れない条件のみに絞って求人を探すことが大切です。
傾向⑤仕事そのものをしたくない、興味がない

疲れやストレスによって、そもそも仕事をしたくない、仕事に興味を持てない状況に陥るケースもあります。
仕事のマイナス面にばかり目が向きやすい人や、仕事以外のことへの興味が強すぎる人も、こうした状況に陥る可能性があるでしょう。
この場合は、仕事の取り組み方や考え方を変えたり、仕事と趣味のバランスを調整することで、やりたい仕事ができる可能性があります。
傾向⑥周囲の目を気にしすぎている
周囲の意見や世間体、企業イメージなどを意識しすぎるあまり、自分自身がやりたいと思える仕事を見つけられていないケースもあります。
「親が正解とみなすキャリアを歩まなければ」「他人に自慢できる企業に就職しなければ」などと意識すると、自分の意思や希望がわからなくなることもあるでしょう。
今一度自分の気持ちに向き直り、興味を持てること、楽しいと感じることなどを明確にしたうえで、やりたい仕事を探してみる必要があります。
やりたい仕事の見つけ方7選
この章では、やりたい仕事の見つけ方について解説します。
見つけ方①自己分析をする

自己分析を通じて、自分が楽しい、うれしいと思うこと、興味を持てることがなにかを知ると、やりたい仕事を見つけやすくなります。
感情がプラスに動く瞬間がいつか、なぜそう感じるのかを掘り下げることで、没頭できる仕事を絞り込めるでしょう。例えば、自分がオススメしたアイテムが、友人に「すごく良い!教えてくれてありがとう!」と共感されたときにとくに喜びを感じる人は、接客業に向いてるかもしれません。
あるいは、得意なことや強みから向いてる仕事を探すのも有効です。周囲から評価されたのはどのようなことだったか、褒められた経験を思い出してみましょう。なかでも、転職して中途採用される場合は、とくに経験やスキルを重視される傾向にあります。自身の強みがわかっていれば、活躍できる仕事を選びやすくなるでしょう。
もし以上のことで思い当たるものが見つからなかった場合は、逆に、仕事で嫌だと感じたこと、向いてないと感じた仕事内容、転職に踏み切ろうと思ったきっかけを考えてみるのも有効です。向いてないと感じる要素をはっきりとさせ、その業務をせずに済む職種や職場を探しましょう。
見つけ方②職種・業種を知る
仕事といっても、業務内容は多岐にわたります。あらためて職種や業種について学ぶと、やりたい仕事を見つけるために役立つでしょう。
例えば、職業情報提供サイトjobtagでは、さまざまな切り口から仕事内容を検索できます。
仕事内容や特徴、収入、求められる能力など、さまざまなデータが統計をもとに紹介されています。また同サイトには自己診断ツールやキャリア分析ツールも公開されているため、仕事との適性を確認するのに役立つでしょう。
あるいは、周囲の人の仕事について聞いてみることも、選択肢を増やすのに有効です。具体的な仕事内容やたいへんなことがわかるため、家族や友人などの周囲の人、キャリアカウンセラーなどに話を聞いてみたり、就職イベントに参加して話を聞いてみたりしましょう。
見つけ方③関連する職種にも目を向ける

気になる仕事はあるものの、国家資格が必要だったり専門的なスキルが求められたりするために、就業できないこともあるでしょう。
その場合、その場合、ほかの仕事に心を動かされず、やりたい仕事がないと思うかもしれません。
そのときは、ほかにやりたい仕事がないと諦めるのではなく、関連する職種に目を向けてみましょう。
例えば看護師として働くためには、専門教育を受けたうえで国家資格を取得する必要があります。
そのため、社会人になってから目指すのはたいへんです。しかし看護助手なら、学歴や資格による制限は設けられていません。大学へ進学しなかった人、四年制大学を卒業した人でも就職できます。
このように、関連する職種も含めて広く検討することで、やりたい仕事を見つけられる可能性が上がります。
見つけ方④周囲に相談してみる
考えてもやりたい仕事がわからなかったら、家族や友人などの周囲の人に相談してみるのもよいでしょう。
対話を通じて、自分では認識していなかった強みや好みの傾向がわかる可能性があります。
- 〇〇の仕事をしているときは生き生きとしている
- △△するときのクオリティが高い
以上のような評価をもらい、そのスキルを活かせる仕事を探してみましょう。
見つけ方⑤現職の取り組み方を見直してみる

やりたい仕事がどうしても見つからないときは、今の仕事をがんばってみることも選択肢となるでしょう。
新しい仕事を無理に探すのではなく、以下のような工夫を通じて、今の仕事に面白さを見出すことも大切です。
- さらに効率的に仕事を終わらせるためになにができるかを考えて、ゲーム感覚で楽しんでみる
- 今の仕事で獲得できるスキルを見つけてチャレンジしてみる
- 少しでも興味を持てている仕事を見つけて、積極的に取り組んでみる
- 仕事の意味や意義を見つめなおしてみる
このような取り組みをしたあとに、このまま仕事を続けるか、ほかに適職を探すかをあらためて検討してみましょう。
見つけ方⑥副業やインターンシップも経験してみる
副業や社会人インターンシップ、アルバイト、ボランティアなどを通じて、ほかの仕事を試してみるのも有力な選択肢となります。
短い期間でも実際に仕事をすることで、やりがい、面白さ、たいへんさなどを体験できます。経験を通じて、適性を見極めたり、職種について学んだりできるでしょう。
また、副業などを通じて自己分析を深めれば、やりたい仕事を探すことに役立てられます。
副業をしてみて、うれしいこと、やりがいを感じられたこと、嫌だと感じたことを整理すれば、価値観を明確にしやすくなります。さまざまな仕事を経験しながら、ゆっくりと選択肢を絞ってみましょう。
見つけ方⑦将来像から考える
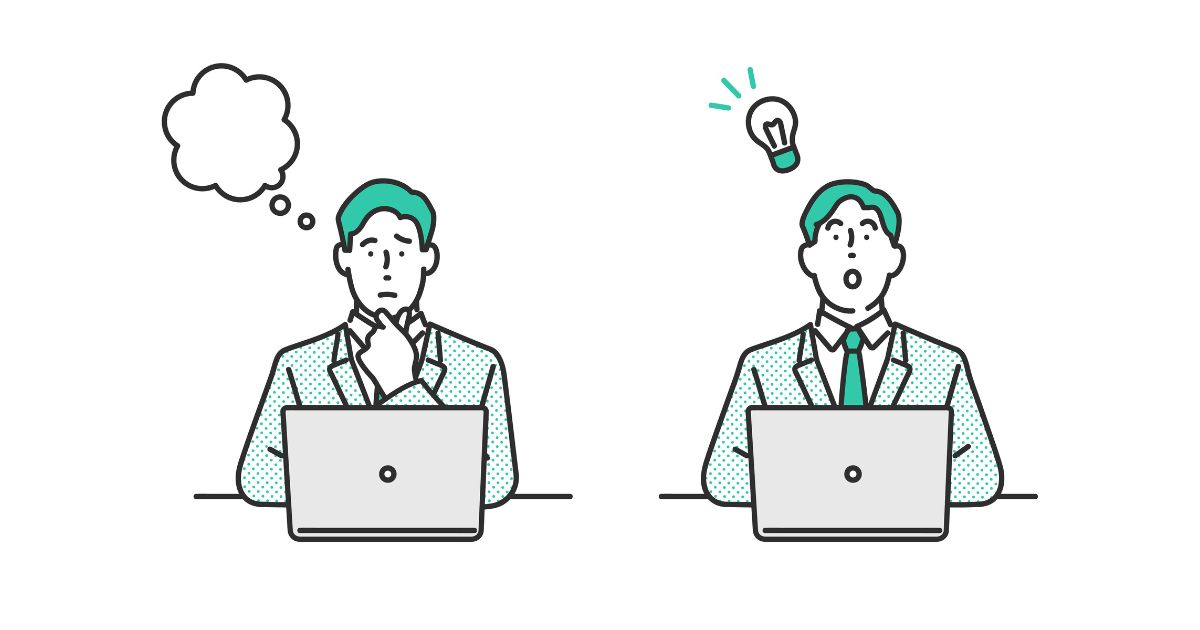
やりたい仕事がないものの、「10年後や20年後にこういう自分になっていたい」というおおまかなイメージを抱いている人もいるのではないでしょうか?
例えば、以下のように理想のイメージを想像してみましょう。
- 10年後にはこれくらいの貯金をしていたい
- 管理職に就いて後進の指導に励んでいたい
- 開業して無理のない働き方をしていたい
そのイメージを具体的にしていくなかで、どの仕事ならそれが実現できるのか、なにを重視したいと思っているのかを見つけられる可能性があります。
理想の将来像を、おおまかに描いてみましょう。
やりたい仕事を探すときの2つの注意点
この章では、やりたい仕事を探すときの注意点について解説します。
注意点①イメージや印象で決めない

やりたい仕事に対して抱いているイメージや印象は、実際の仕事内容とは異なるかもしれません。
職種や企業へのイメージ、憧れだけで応募先を決めないようにしましょう。思っていたのと違ったと後悔しないためには、自分自身や業界、職種、企業について理解を深めておくことが大切です。
注意点②優先したい条件を見つけておく
どうしても譲れない条件と妥協してもいい条件に振り分け、順位付けしておくことも大切です。
例えば仕事内容や福利厚生など、希望条件のすべてを満たす仕事を見つけるのは難しいといえるでしょう。とくに条件が多くなるほど、理想の職場を見つける難易度が上がります。
希望条件を整理し、必要に応じて妥協するなど、柔軟に検討する必要があります。
やりたい仕事を見つけられる就職支援機関8選
この章では、やりたい仕事を見つけるときに頼れる転職支援機関について解説します。
支援機関①転職サイト

転職サイトは、求人情報が掲載されたサイトです。
自分自身のペースで、隙間時間も活用しながら幅広く仕事を探せます。ゆっくりと検討しながら、慎重に仕事を探したい人に向いてるといえるでしょう。
その一方で、やりたい仕事が絞れていない場合、膨大な求人のなかから適した応募先を見つけ出すのはたいへんです。くわえてほかの支援サービスと異なり、書類作成や面接対策なども自身で対応する傾向にあることも把握しておきましょう。
支援機関②転職エージェント
転職エージェントは、担当のコンサルタントのサポートを受けながら、適した応募先を探せる支援サービスです。
コンサルタントによって厳選された、適職となる可能性が高い求人のなかから応募先を探せます。自身の強みがなにか相談しながら求人を探したい人、スキルを活かせる仕事を探したい人など、サポートを得ながら効率的に仕事を探したいときに適したサービスです。
一方で、サービスを利用するときにはコンサルタントと面談するほか、面接後などに適宜コミュニケーションを取る必要があります。細かな連絡のやり取りが苦手な人、自分のペースでゆっくりと検討したい人には不向きといえるでしょう。
支援機関③ハローワーク

ハローワーク(公共職業安定所)とは、仕事を探している人や求人を募集したい事業者に対して、就労に関連するさまざまなサービスを無償で提供する、厚生労働省が運営する支援機関のことです。正式名称は公共職業安定所で、職安と呼ぶ人もいます。(参考:厚生労働省「ハローワーク」厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」厚生労働省「公共職業安定所(ハローワーク)の主な取組と実績」、東京労働局「東京ハローワーク」、厚生労働省「こころの健康サポートガイド」、厚生労働省「ハローワークにおける障害者の就労支援」)
主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示などを行っており、具体的な支援内容は事業所によって異なりますが、一般的には以下のような幅広いサポートを行います。
全国に500ヶ所以上あり、主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示、雇用保険や雇用対策など、地域密着型の雇用に関する幅広いサポートを行います。
また、病気や障害のある人に向けたサポートも行っています。障害者手帳を所持していない人でも、医師による診断書があれば、障害の特性や希望職種に応じた職業相談や履歴書や面接での病気・障害の伝え方などのサポートを受けることができます。
支援機関④就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。実際のサービスは、国の基準を満たしたさまざまな民間の就労移行支援事業所が行います。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
就労移行支援事業所は各地にあります。私たち、キズキビジネスカレッジ(KBC)もその一つです。それぞれ特徴が異なるため、気になるところがあれば問い合わせてみてください。
キズキビジネスカレッジ(KBC)は、関東地方と関西地方に合計8校を開校している就労移行支援事業所です。ビジネス英語やプログラミングなど、専門的なスキルを習得することもできます。くわしくは以下からご確認ください。
支援機関⑤障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターとは、雇用や保健、福祉、教育に関する関係機関と連携し、障害のある人の雇用の促進・安定を目的とした一体的な支援を行っている支援機関のことです。(参考:厚生労働省「障害者就業・生活支援センター」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」、厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」)
障害のある人の就職活動の支援や求人の紹介、職場定着のためのサポートなどを行います。
就業面だけでなく、金銭管理などの経済面や生活面のことまで、日常および地域生活に関する支援も行っています。
生活習慣や金銭管理、健康管理などについても幅広く相談できるため、生活面のサポートも受けたい人にオススメです。
2024年4月1日時点で、障害者就業・生活支援センターは全国に337箇所設置されています。

地域障害者職業センターとは、病気や障害のある人に対して、職業評価や職業指導、職業準備訓練、職場適応援助などの専門的な職業リハビリテーションを提供する支援機関のことです。(参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センターによる支援」、厚生労働省「地域障害者職業センターの概要」)
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しており、障害者雇用促進法に基づいて、全国47都道府県に設置されています。(参考:厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律」)
ハローワークや医療・福祉機関と連携しているため、仕事に関する相談や訓練、復職するためのサポートを行っています。
病気や障害に悩む人だけでなく、障害のある人を雇用する事業所に対して、雇用管理に関する相談・援助も行っています。
障害のある人それぞれに合わせた指導をするとともに、事業主への助言と支援も実施しています。また、障害のある人の就労支援に関する専門家が在籍しており、総合的な支援を受けられるのも特徴です。
支援機関⑦精神保健福祉センター

精神保健福祉センターとは、精神障害のある人のサポートを目的とした、地域の精神保健福祉の中核を担う支援機関のことです。(参考:東京都福祉保健局「精神保健福祉センターとは」、e-Gov法令検索「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)
精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)に基づき、各都道府県に設置されています。地域によって、こころの健康センターや心と体の相談センターなど、一部名称が異なります。
精神保健福祉センターでは、精神疾患に関連する悩みの相談や社会に適応するための指導と援助を行っています。
精神障害による症状で悩んでいる本人だけでなく、ご家族や周囲の人の相談も受け付けています。また、匿名での相談も受け付けています。医師から正式な診断を受けていなくても相談は可能です。
詳しくは、お住まいの自治体の精神保健福祉センターにお問い合わせください。
支援機関⑧地域若者サポートステーション

地域若者サポートステーション(サポステ)とは、働くことに悩みを抱える15歳から49歳までの若者を対象とした厚生労働省委託の就労支援機関です。若者支援の実績やノウハウがある民間団体が運営しています。(参考:厚生労働省「地域若者サポートステーション」、「サポステ」)
2025年2月1日現在、全国177か所に設置されています。
まとめ:人に相談しながらやりたい仕事を見つけましょう

やりたい仕事を見つけられずにいる人は、決して少なくありません。しかし、自分自身への理解を深めたり仕事に関する知見を深めたりすることで、やりたいと思える仕事を見つけられます。
もし自分だけで見つけられなくても、周囲の人に協力してもらう、支援サービスを利用するといったアクションを通じて、やりたい仕事を見つけられるでしょう。
周囲と相談しながら、やりたい仕事がなにか、ゆっくりと絞り込んでいきましょう。このコラムでご紹介した内容が、仕事に悩むあなたの助けになることを祈っています。
やりたい仕事が見つからない人の傾向を教えてください。
以下が考えられます。
- 自信がない
- 慎重すぎる
- 自分自身への理解が深くない
- 希望する条件が多い
- 仕事そのものをしたくない、興味がない
- 周囲の目を気にしすぎている
詳細については、こちらで解説しています。
やりたい仕事の見つけ方はありますか?
以下が考えられます。
- 自己分析をする
- 職種・業種を知る
- 関連する職種にも目を向ける
- 周囲に相談してみる
- 現職の取り組み方を見直してみる
- 副業やインターンシップも経験してみる
- 将来像から考える
詳細については、こちらで解説しています。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→