早起きが辛いあなたへ 自分に合った対処法とオススメの働き方を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)利用者の村上です。
「早起きが辛い…」と感じることはありませんか?
朝が苦手な人にとって、早起きは辛いものですよね。遅くまで寝ていたいけど、仕事のために無理やり起きる方も多いと思います。
実は、早起きが辛い原因はクロノタイプにあるかもしれません。
このコラムでは、クロノタイプの概要や、辛い早起きを楽にする対処法、早起きが辛い人にオススメな働き方などについて解説します。
今より快適な目覚めに挑戦してみませんか?
毎日の早起きが辛いと悩んでいる人は、ぜひ読んでみてください。
早起きが辛いあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
クロノタイプとは?
この章では、クロノタイプとは何かについて解説します。
クロノタイプの概要
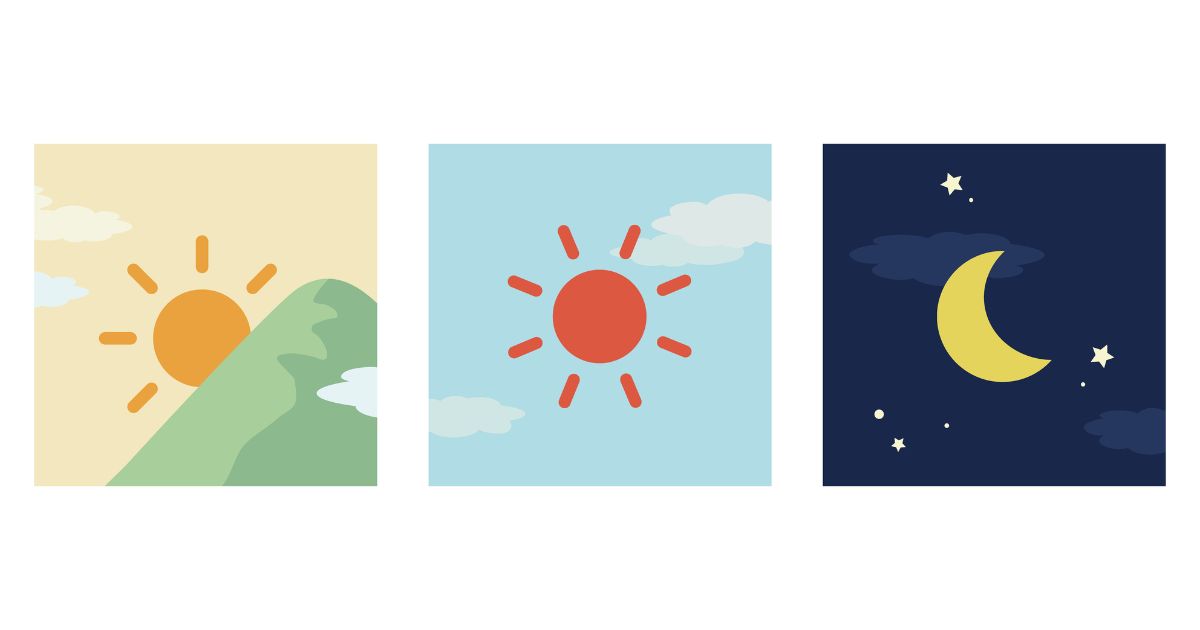
クロノタイプとは、生まれつき持っている睡眠や活動の時間帯の傾向で、朝型、夜型、中間型があります。(参考:日本睡眠学会「睡眠の性差」、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所睡眠・覚醒障害研究部「クロノタイプとは」)
- 朝型:朝〜昼に活動しやすく、朝早くに目が覚めるタイプ
例えば、朝6時に目が覚めて散歩や朝活を楽しめる人。午前中に集中力が高まりやすいのも特徴。 - 夜型:夕方〜夜に活動しやすく、早起きが苦手なタイプ
例えば、夜になるとようやく頭が冴え始め、深夜以降に趣味や作業がはかどることも。 - 中間型:朝型と夜型の中間で、どちらかの特徴を持つか、生活習慣で変化しやすいタイプ
過度な夜更かしや朝寝坊は、体調を崩す原因になることもあるので注意が必要。
早起きが辛いのはどのクロノタイプ?
クロノタイプが夜型の人は、早起きが辛いと感じることが多いです。
遅い時間に就寝して、無理に早起きすることで、睡眠の問題や不調につながりやすいためです。(参考:東京医科大学 精神医学分野 産業精神医学支援プロジェクト「早起きは三文の損: 朝型人間の夜ふかしと、夜型人間の早起きが生産性低下と関連」)
夜型の人が深夜まで眠くならない理由として、メラトニンの分泌タイミングが関係しています。
メラトニンとは脳で作られるホルモンで、眠くなるスイッチを入れる役割があり、夜になると分泌が増え、体に「そろそろ寝る時間だよ」と知らせることで、自然な眠気を促し、体内のリズムを整えます。(参考:厚生労働省e-ヘルスネット「メラトニン」)
しかし、クロノタイプが夜型の人は、メラトニンの分泌が遅く、24時以降になることが多いので、「寝ようと思ってもなかなか眠くならず、気づけば深夜になっている…」と感じやすいのです。
夜型の人は案外多い?

実際、夜型の人はどれくらいいるのでしょうか。
夜型の特徴を持つ人は朝型と同じか、それ以上に存在しているとも考えられます。
2010年に日本人1170人を対象に実施された調査では、朝型の割合が約28%、約41%が中間型、夜型の割合は約31%となり、夜型のほうが朝型よりも多いことがわかっています。
この調査では夜型の人はむしろ一定数いて、朝型よりも多いことがわかります。そう思うと、似た悩みを抱える日本人は意外と多いのかもしれません。データを踏まえると、自分の睡眠の悩みも少し受け止めやすく感じられるかもしれませんね。(参考:三島和夫 「社会的ジェットラグがもたらす健康リスク」日本内科学会雑誌、KADOKAWA「朝型 夜型 中間型は遺伝で決まっている! クロノタイプ別 睡眠レッスン」)
早起きを無理に続けると「社会的時差ボケ」に
この章では、無理に早起きを続けることで起こる社会的時差ボケについて解説します。
社会的時差ボケとは?夜型の人が抱えやすい理由

社会的時差ボケとは、平日の多忙やストレスから睡眠不足になり、休日に寝だめをして生活リズムが乱れることで、頭や体がなんとなくだるく感じている状態を指します。
睡眠のタイミングや時間が安定しないので、ちょうど海外旅行で時差ボケになるのと似たような感覚です。
特に、夜型の人にとって、朝型の社会に合わせて毎朝決まった時間に起きる生活は、負担になりやすい傾向にあります。夜型の人は入眠時刻が遅いので、平日に睡眠不足が続き、週末に寝だめをする習慣が積み重なって、「朝がつらい」「日中ぼんやりする」といった状態になりやすいのです。
このように、夜型の人の社会的時差ボケは、本人の努力不足というより、クロノタイプや生活環境が原因となっていることが多いのです。
だからこそ、無理に合わせようとがんばりすぎるよりも、自分のリズムを少しずつ整えていくことが大切です。気になる人は、このコラムで紹介する対策や働き方を、できそうなところから取り入れてみてください。(参考:厚生労働省「良い目覚めは良い眠りから 知っているようで知らない睡眠のこと(睡眠不足が引き起こす悪影響)」)
無理な早起きは集中力やパフォーマンス低下の原因に
無理な早起きを続けると、日中の集中力やパフォーマンスが発揮しにくくなることがあります。
ある研究では「夜型の人は、朝型社会のスケジュールに無理に合わせると、本来の力を十分に発揮できない可能性がある」という結果も出ています。
こうした傾向は、日常生活の中でもよく見られます。夜型の人がいきなり目覚ましを何時間も早めて生活を変えようとすると、かえって疲れがたまり、日中のパフォーマンスが落ちる可能性があります。その結果、社会的時差ボケの状態に陥るリスクもあるのです。
だからこそ、まずは無理のない範囲で、自分に合った対策を少しずつ試してみることが大切です。(参考:東京医科大学 精神医学分野 産業精神医学支援プロジェクト「早起きは三文の損: 朝型人間の夜ふかしと、夜型人間の早起きが生産性低下と関連」)
クロノタイプを確認する方法

ご自身のタイプが気になったら、まずは簡単なチェックから試してみるのも良いでしょう。
科学的にご自身のクロノタイプを確認するには、国立精神・神経医療研究センターの質問紙を利用することができます。
20問程度の質問に答えると、自分のクロノタイプがわかります。(参考:国立精神・神経医療研究センター「朝型夜型質問紙」)
一方で、昼夜逆転が続いていたり、不眠が続いていたり、気分の落ち込みが強いと感じていたりするときは、こちらの内容を確認の上、専門の医療機関に相談してください。専門家の力を借りることも前向きな選択として考えてみてください。
早起きするために夜型の人ができる6つの対処法
この章では、クロノタイプが夜型の人に向けて、早起きするための6つの対処法について解説します。
また、今回解説する対処法は、夜型以外のタイプの人にも取り入れやすい工夫となっています。無理のない範囲で、できそうなところから試してみてください。
対処法①日中の運動・身体活動を増やす

日中に体を動かし、適度な疲労を感じることで寝付きが促され、睡眠の質が高まります。
実際、運動習慣がある人は寝つきが良く、中途覚醒などの不眠症状が少ない一方で、運動習慣がない人は睡眠で休養がとれている感覚が低いことがわかっています。特に、足早のウォーキングや軽いジョギングといった、続けやすい有酸素運動は効果的とされています。
運動の種類や強度、時間帯によって睡眠への効果は異なりますが、週に数回、息が弾む程度のウォーキングや筋トレなどを続けると、深い睡眠や睡眠時間の増加につながります。1日60分以上が理想ですが、最初は短時間・軽めから始め、無理のない範囲で継続することが大切です。強すぎる運動は睡眠を妨げることもあるため注意しましょう。(参考:健康づくりサポートネット「快眠と生活習慣」)
対処法②太陽光や照明などの明かりを利用する
朝起きたらカーテンを開けて、部屋に太陽の光を入れてみましょう。
日光は体内時計をリセットし、夜の眠りやすさにつながります。もしお部屋に日差しが入りにくい場合は、朝に少しベランダに出てみたり、光で起こしてくれる目覚まし時計や明るめの照明を使ってみるのもオススメです。
また、夜は照明を落としてできるだけ暗く静かな空間に調整しましょう。明るさにメリハリをつけることで、体が自然と朝と夜を感じ取りやすくなります。(参考:健康づくりサポートネット「快眠と生活習慣」)
対処法③起きる時間をなるべく変えない

夜型の人は、起きる時間を大幅に変えないよう意識してみましょう。
例えば、休日でも起きる時間は、平日より最大でも1時間程度のズレに抑えると、体のリズムが整いやすくなります。
また、寝る時間が遅くなった場合は、睡眠時間が短くなったとしても朝はできる限りいつも通りの時間に起きるようにしましょう。万が一、日中に眠くなった場合は、20分以内の短い昼寝を挟んでみてください。
朝起きづらい場合の対処法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
対処法④寝る前はスマートフォン・ゲームをなるべく控える
寝る前のスマホやゲームは、眠気を遠ざける原因になります。
画面から出るブルーライトには、体内時計を遅らせてしまう作用があるからです。特に、寝ながらスマホを使うと画面が目に近く、より強い光を浴びやすくなります。できる限りスマホは寝室に持ち込まず、別の部屋に置いておくのがオススメです。
難しい場合は、寝る直前だけでもスマートフォンやタブレットの操作を控えて、脳と体を休ませる時間にしてみましょう。(参考:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」)
対処法⑤就寝2~4時間前の夕方以降に運動する

夕方から寝る2〜4時間前くらいに軽く体を動かすと、その後、一旦上がった体温が下がるタイミングで自然と眠気が訪れやすくなります。
こうした体温リズムの変化を活かすことで、スムーズに眠りに入れるようになります。仕事帰りのウォーキングやストレッチでもOK。
例えば、駅から少しだけ遠回りして歩く、帰宅後に簡単なストレッチで体を伸ばすだけでも効果があります。無理のない範囲で、少しずつ取り入れてみましょう。(参考:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」)
対処法⑥就寝1~2時間前にぬるめのお湯で入浴する
ぬるめのお風呂にゆっくりつかると、体があたたまり、心もほっとして、眠りにつきやすくなります。
入浴によって体をリラックスさせる働きがある副交感神経が優位になり、心身の緊張がゆるみやすくなるからです。
理想の入浴のタイミングは、就寝の1〜2時間前。手足が温まり、放熱が進むことで体の奥の温度が下がり、自然な眠気が訪れます。熱すぎるお湯はかえって目が冴えることもあるため、38〜40度くらいのぬるめがオススメです。(参考:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」)
どうしても早起きが辛いときは病気・障害が関連している可能性があります

日中の眠気や集中力の低下、気分の落ち込みなどの症状が、睡眠環境や生活習慣を改善しても変わらず、日常生活に支障を伴う場合は不眠症などの睡眠障害の可能性があります。
不眠の背後には、うつ病や不安症といった精神疾患だけでなく、閉塞性睡眠時無呼吸や身体疾患が隠れている場合もあります。自己判断せず、早めに医師に相談をしてください。
受診すべき医療機関については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
早起きが辛い人にオススメな働き方
この章では、早起きが辛い人にオススメの働き方について解説します。
夜型の人や夜型寄りの中間型の人は、朝の早起きを負担に感じることが多いですよね。人にはそれぞれ「活動しやすい時間帯」があり、朝は苦手だけど、夜に集中力や思考力が高まる夜型タイプの人も少なくありません。
そんな人は、朝に少しゆとりを持つために、働き方を見直してみるのもひとつの方法かもしれません。
早起きが辛い人にオススメの働き方として、リモートワーク、フリーランスが考えられます。
早起きが辛い人が苦手な朝にゆとりを持つには?

早起きができると、生活リズムが整いやすく、職場の勤務時間中に集中して仕事に取り組めるなど、うまくハマれば、とても良いスタートが切れるでしょう。
とはいえ、こちらで解説したとおり、クロノタイプが夜型、夜型寄りの中間の人にとって、毎朝決まった時間に起きる生活は、なかなかハードルが高いものです。
だからこそ、「朝型にならなきゃ」と無理に頑張るのではなく、自分に合ったスタイルを選ぶという考え方もあります。
たとえば、始業時間に縛られないリモートワークや、自分のリズムで働けるフリーランスのような無理のない働き方なら、今よりも自然体で一日を始められるかもしれません。
前提:クロノタイプに寄り添う、無理をしない働き方
今の働き方に違和感がある、早起きがいつも辛いと感じているなら、「早起きは苦手」と割り切ることで気持ちが楽になるかもしれません。
クロノタイプに合った働き方を少しずつ試していくことで、精神的な安定や日中のパフォーマンス向上につながります。無理のない日が増えていくと、「朝がつらいな…」と感じる場面もだんだん減っていくはずです。(参考:Narcisse, M.-R., Togher, K., & McElfish, P. A.『Job Flexibility, Job Security, and Mental Health Among US Working Adults』2024)
オススメの働き方①リモートワーク

リモートワークは通勤時間がなく、自分のペースで始業まで家で過ごせるのが魅力です。
特に夜型の方にとっては、朝の満員電車や、出勤前の慌ただしい準備が減るだけでも、心や体の負担が軽く感じられることがあるでしょう。
その朝の時間を軽い運動や朝活、ゆっくり朝食をとる時間にあてることで気持ちが少しずつ整い、自然と集中しやすくなる効果もあります。
こうした小さな余裕が仕事に向かう気持ちを後押ししてくれたり、自分でも今日はうまくやれそうと感じられたりするなど、前向きなリズムにつながっていくかもしれません。(参考:Rodrigues, E. F., & Lemos, M. F.『Repercussions of home office on the mental health of teleworkers: integrative review』Concilium, 24(12), 2024)
オススメの働き方②:フリーランスという選択肢
フリーランスは、特に夜型の人にとって、自分の特性を活かせる働き方です。
時間の制約が少ないため、夜型の人が最も集中力が高まる夕方から夜の時間帯に仕事ができ、高いパフォーマンスを発揮しやすくなります。
また、朝に無理せず、ゆっくり仕事をスタートできることで精神的な余裕が生まれ、一日のエネルギーを効率的に使えるメリットがあります。例えば、夕方までに打ち合わせを終えたら、一旦休憩し、夜22時から集中して作業に取り組む、といったスタイルも選べます。(参考:Gilmer『Workplace Chronotype Bias, Flexible Scheduling, and Performance Beliefs』2018 )
ただし、現在会社勤めをしていて、すぐにフリーランスへと踏み出すのはハードルが高く感じますよね。早起き以外にも、気持ちの整理や生活スタイルの変化、スキルの準備など、ひとつひとつ向き合う必要があると感じている人も多いと思います。
だからこそ、まずは今の生活の中で無理なく集中できる時間を探してみたり、自分にとって心地よい働き方を試してみたりするところから始めてみるのもいいかもしれません。「こういうスタイルなら自分に合うかも」とイメージをふくらませていくことで、自然と自分に合った形が見えてくるはずです。
リモートワークのメリット・注意点
この章では、リモートワークのメリットと注意点について解説します。
リモートワークという働き方に興味があるけれど、具体的にどんなメリットがあり、何に注意すべきかを理解することが重要です。
メリット①通勤に早起きしなくてよい

リモートワークで働くと、通勤に必要だった時間を健康管理や家族と過ごす時間にあてることができます。
例えば、以前は早起きして慌ただしく身支度や通勤準備に追われていた人も、リモートワークなら朝はゆっくりコーヒーを飲んだり、軽くストレッチをしたりしてから仕事を始めることができます。バタバタした朝が減ると、それだけでも心に余裕が生まれてきます。
まずはリモートワークが可能か、職場ごとのルールを確認してみましょう。
メリット②生産性の向上
リモートワークは業務に集中しやすく、生産性向上に繋がる大きなメリットがあります。
厚生労働省によると、リモートワークは業務に集中しやすく、生産性を向上させる大きなメリットが挙げられています。(参考:テレワーク総合ポータル「日本型テレワークとは|基本情報」)
職場では同僚との会話や来客、電話対応などで作業が中断されることが多く、集中力を削ぐ要因になりがちです。しかし、リモートワークではこれらをほとんど気にする必要がないため、集中して業務に取り組めます。
実際、リモートワークを導入している職場への調査では、約9割の社員が「生産性が向上した」または「変わらない」と回答しています。
特に、集中力が求められる資料作成やデータ分析などのデスクワークでは、自宅での静かな環境が大きな効果を発揮します。業務の効率が上がれば、そのぶん仕事のペースにゆとりが生まれ、気持ちも整いやすくなると感じる人もいます。
注意点①運動不足になりやすい

通勤が減ると、外に出る機会が減るので、運動不足になりがちです。
運動不足が続くと夜に眠くなりづらく、寝つきが悪いと感じる可能性があります。
そんなときは、昼休みに周辺を10分だけ散歩したり、デスク横で簡単なストレッチをするだけでも、リズムが整いやすくなります。
注意点②職種・業種が限定される
最新の調査によれば、日本でリモートワーク実施率の高いのは、以下の職種です。
- 事務系管理職
- 事務職・技術系事務職
- 営業職
一方で販売・サービス職やドライバーなど、職種によってはリモートワーク実施が難しい場合もあります。また、業種別にはIT・インターネット業界での実施率が約55.8%と高く、次点とは約30ポイントもの開きがあります。
さらに、リモートワークを導入している職場は減少傾向にあり、リモートワークと出社の併用は約17%と、前回の調査から約1.7%低下していることもわかります。(参考:カオナビHRテクノロジー総研『リモートワーク実施率は17.0%で定着か ~2024年3月 リモートワーク実態調査~』)
リモートワーク実施率が伸び悩む背景には、社内コミュニケーションの減少や、評価・労務管理の難しさ、不公平感などの課題があります。
特に「部下の状況が見えにくい」「連帯感が薄れる」などの不安から、リモートワークの導入を見直す企業もあります。(参考:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「実施率は10%〜20%台。現状での課題はコミュニケーション面などが主」)
ただし、たとえ離れていても安心して働けるように、さまざまな工夫を取り入れている職場も増えています。
たとえば、週1回の1on1ミーティングを行ったり、カメラをONにして顔を見ながら話すようにしたり、気軽に話せる雑談スペースをつくるなど。こうしたルールやちょっとした取り組みで、リモートでもしっかりコミュニケーションが取れるようになってきています。
リモートワーク実施率の高い業種・職種に絞って就職先や転職先を探すことで、リモートワークができる仕事に就くことは可能です。
フリーランスで働くメリットと注意点
この章では、フリーランスで働くメリットと注意点について解説します。フリーランスに興味がある方に、まず参考にしていただければと思います。
メリット①時間・場所の融通が利きやすい

フリーランスは働き方を自分で設定できるケースが多く、時間や場所の融通が利きやすいことが大きなメリットです。
フリーランスの場合、クライアントとのルールを遵守すれば、働き方を自分で設定できるケースが多いです。
例えば、朝が苦手であれば、午後から作業を始めたり、逆に朝型を活かして早朝に集中して午後には仕事を終えたりするなどと、自分のペースに合わせた働き方も選べます。また、カフェや自宅、時にはコワーキングスペースなど、気分に合わせて働く場所を変えることもできます。
このように、フリーランスは勤務時間が固定されている会社員などに比べ、融通が利きやすいといえます。なお、クライアントによっては指定の時間・場所で対応を求められることもあります。
メリット②自分のペースで仕事を進められる
仕事のペース配分を自分で調整できる点もフリーランスのメリットです。
仕事のペース配分も会社員と比較して自由度が高い傾向にあります。具体的には、以下のとおりです。
- 3日働いたらオフを1日入れる
- 睡眠時間を多めに確保する
- 夜間に集中して作業に充てる
もちろん、クライアントと交わしたルール・納期を守り、責任感を持って業務ができることが前提になります。
注意点①自己管理が必要になる

フリーランスは全てセルフマネジメントであり、自己管理能力が重要です。
会社員などの場合、組織にマネジメント体制がありますが、フリーランスは全てセルフマネジメント、つまり自己管理をする必要があります。
仕事のスケジュール以外にも、睡眠や食生活など心身の健康を含めて自己管理することが求められるため、自己管理が苦手な人は注意が必要です。
例えば「今日は少し疲れているから後ろに回そう」と柔軟に決められる反面、計画通りに進めないと納期に響く場面も出てきます。
したがって、フリーランスとして働く場合は、日々のタスクを小分けにしたり、締切までのスケジュールを余裕を持ってんだりするなど、普段の業務から少しずつ整えていくことがポイントになります。
注意点②最初から好条件な仕事とは限らない
フリーランスは経験やスキルが不十分な段階では、低単価や単発案件から始まることが多いです。
業務の経験が浅く、スキルが習熟していない段階では、多くの場合は低単価・単発的な案件が中心になります。例えば、最初は短納期のタスクや、単発のデータ入力・ライティング案件などからスタートするケースも多いです。
継続して案件を受けるためには、自身のスキルアップの継続、結果を積み重ねてクライアントの信頼を得る必要があります。焦らず少しずつ実績を積み上げていくことが、将来的な安定にもつながりやすくなります。
就労支援を利用して働きやすい職場へ就職する
この章では、就労移行支援の利用について紹介します。
「会社の勤務時間が合わなくて毎日つらい…」「仕事のことを考えると眠れない…」など、勤務時間や人間関係などのストレスが原因で、睡眠の改善が難しい場合、支援制度や支援機関を利用して、別の職場に転職するという方法もあります。
睡眠障害を含む病気などが原因で休職した人、退職した人は、就労移行支援を利用できる可能性があります。
就労移行支援事業所とは?

就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。実際のサービスは、国の基準を満たしたさまざまな民間の就労移行支援事業所が行います。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
就労移行支援事業所は各地にあります。私たち、キズキビジネスカレッジ(KBC)もその一つです。
キズキビジネスカレッジ(KBC)では、睡眠と健康の知識を深めたい方に日々の生活や仕事のパフォーマンスにも深く関わる「眠りの授業」、自分自身を深く知るための「自己理解(心理)」、ストレスに流されにくい心を育てる「ストレスレジリエンス」など、心と体の健康を支える講座を用意しています。
また、リモートワークやフリーランスといった柔軟な働き方を目指す方に向けて、「プログラミング講座」「Webデザイン講座」「動画編集講座」など、実践的なスキルを身につけられる講座も実施しています。
就労移行支援事業所は、それぞれ事業所ごとに特徴が異なります。障害者雇用に向けた資格取得に強みを持つ事業所もあれば、プログラミング等の実践的なスキルアップが中心の事業所など様々です。ご自身に合った就労支援を受けるためにも、気になる事業所があれば問い合わせてみてください。
就労移行支援事業所については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ :早起きが辛い人はクロノタイプを知ることから始めてみましょう

早起きが辛い人にとってまず大切なのは、ご自身のクロノタイプを知ることです。クロノタイプを把握することで、無理なく前向きに睡眠リズムを整えやすくなります。
さらに、リモートワークやフリーランスなど、自分に合った柔軟な働き方を視野に入れることで、心身の負担を軽減しながら毎日を過ごせる選択肢も高まります。ぜひ一度、検討してみてください。
また、睡眠障害などが原因で休職した人、退職した人は、転職に向けて就労移行支援を利用できる可能性がありますので、調べてみることをオススメします。
なお、睡眠や心身の悩みはなるべく一人で抱えこまず、お早めに家族や友人などの周囲の人、上司や同僚などの職場の人、医師やカウンセラー、支援機関などに相談しましょう。このコラムが、早起きを辛いと感じているあなたの一助になれば幸いです。
クロノタイプとは何ですか?
クロノタイプとは、生まれつき持っている睡眠や活動の時間帯の傾向で、朝型、夜型、中間型があります。
詳細については、こちらで解説しています。
早起きするために夜型の人ができる対処法を教えてください。
以下が考えられます。
- 日中の運動・身体活動を増やす
- 太陽光や照明などの明かりを利用する
- 起きる時間をなるべく変えない
- 寝る前はスマートフォン・ゲームをなるべく控える
- 就寝2~4時間前の夕方以降に運動する
- 就寝1~2時間前にぬるめのお湯で入浴する
詳細については、こちらで解説しています。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→




