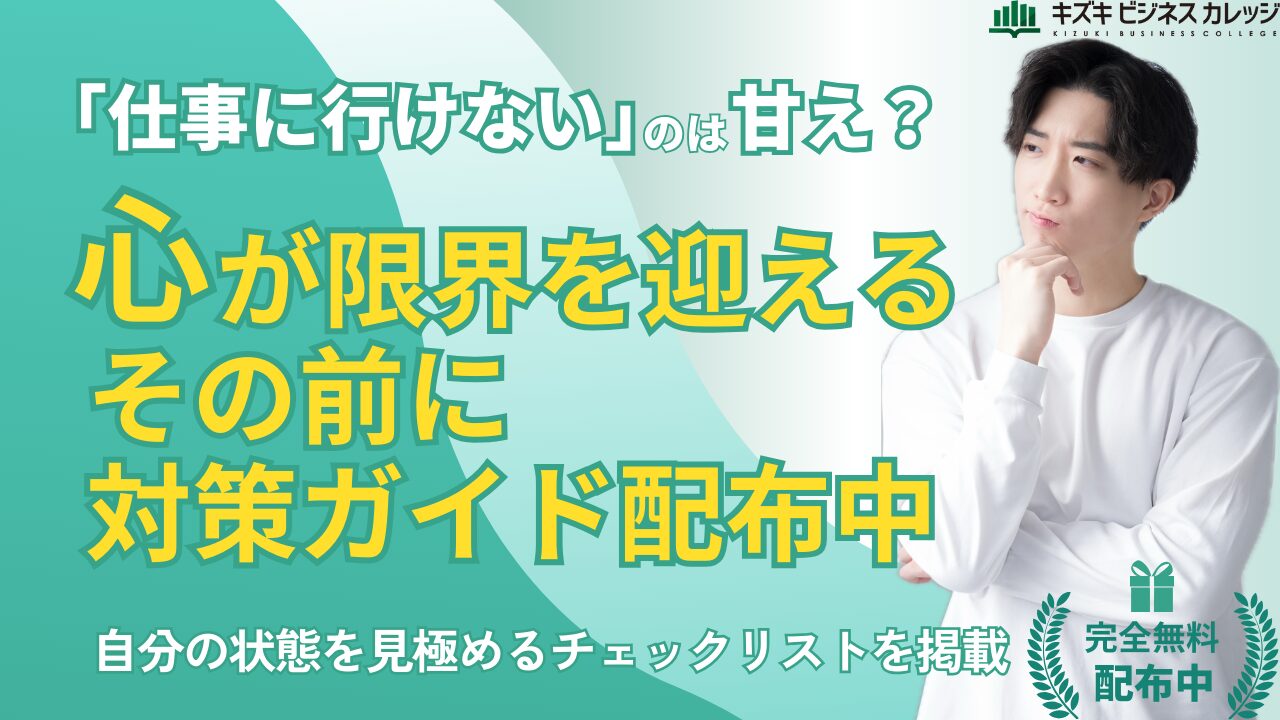いまの仕事に不満を感じているあなたへ 原因と対処法を解説

こんにちは。キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
現代社会において、仕事に対する不満を抱えるのは珍しいことではありません。あなたも、毎日の仕事に不満を感じたことがあるのではないでしょうか?
このコラムでは、仕事に不満を感じる原因について掘り下げ、対処法について解説します。
仕事への不満を抱えている人は、ぜひ参考にしてください。
仕事への不満を抱えているあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
仕事に不満を感じる主な原因12選
この章では、仕事に不満を感じる主な原因について解説します。
それぞれ当てはまる内容がないか、確認してみましょう。
原因①仕事内容にやりがいが感じられない

仕事に不満を抱く原因として、仕事内容にやりがいを感じられないケースが挙げられます。
やりがいは、仕事に対する情熱やモチベーションを維持するために必要不可欠な要素です。
- 単調な作業の繰り返しになっている
- 自分の能力が活かされていないと感じる
- 仕事の達成感や充実感が少ない
このような状況が続くと、業務への意欲が失われ、キャリアの停滞を招くことにもつながります。
やる気が出ないことにお悩みの人は、以下のコラムも参考にしてください。
原因②仕事の成果が評価されない
仕事の成果が適切に評価されないと、不満を抱えやすくなります。たとえ一生懸命に取り組んでも、その努力が上司や同僚などの職場の人に認識されない場合、モチベーションが低下し、仕事への意欲が失われるでしょう。
評価が不十分であると感じる場合、職場の評価基準が不明確であったり、公平性に欠けていたりすることもあるのかもしれません。
このような状況では、自己肯定感が低下したり、不公平感を募らせたりする可能性があります。
原因③仕事への裁量権が少ない

仕事に不満を感じる原因として、裁量権が少ないことも挙げられます。裁量権とは、業務の進め方や方法を自ら選択し、決定する権限のことです。この権限が少ないと、指示を受けるばかりで自分の意見やアイデアを反映させる機会が限られ、やりがいを感じにくくなります。
上司や経営陣からの指示に従うだけでは、仕事に対する責任感や達成感が薄れ、仕事そのものに対して興味が失われる可能性もあるでしょう。
原因④職場の人間関係が悪い
職場の人間関係が悪化すると、仕事に対する不満は急速に増幅します。人間関係のトラブルは、職場の雰囲気を悪化させ、ストレスが蓄積する原因となるでしょう。
さらに、チーム内に不和が生じると業務の効率を低下させ、成果を出すのが難しくなることもあります。
このような状況に直面すると、職場に行くこと自体が苦痛に感じられ、離職を考えるきっかけになるかもしれません。
原因⑤同僚との協力体制ができていない

仕事をする上で、同僚との協力は不可欠です。協力体制ができていないと、業務がスムーズに進まず、不満が募る原因になります。
情報共有の不足は、誤解や認識のズレが起こる原因です。仕事の効率が低下するだけでなく、業務上の問題が生じやすくなるでしょう。連携が難しくなることで、人間関係の悪化にもつながりかねません。
同僚との協力体制ができていない場合、上司のマネジメント方法に問題がある可能性もあります。チーム全体での環境調整が求められるでしょう。
原因⑥職場にハラスメントがある
職場におけるハラスメントは、心身に深刻なダメージを与えます。パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなどさまざまな種類がありますが、共通するのは、個人の尊厳を深く傷つける行為であることです。
ハラスメントを受けると、その後の社会生活にも大きな影響をきたし、キャリアの中断や離職を余儀なくされることもあります。もしハラスメントの被害に遭った場合は、一人で抱え込まず、信頼できる人や機関に相談することが大切です。(参考:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」)
原因⑦職場の立地が悪い

職場の立地が悪いと、通勤自体がストレスになります。とくに公共交通機関の便が悪い、職場が交通渋滞の多いエリアにある場合などは、通勤時間が長引きやすいです。
通勤時間が伸びることで、早朝から出社しなければならなかったり、帰宅が遅くなったりすることもあるでしょう。睡眠時間やプライベートの時間が圧迫されることにより、心身の疲労が蓄積しやすくなります。
原因⑧労働条件に不満がある
労働条件への不満は、従業員の仕事への意欲を低下させ、生産性の低下にもつながる要因です。また勤務時間や休暇制度、福利厚生などが不十分である場合、不満を増大させるおそれがあるでしょう。
とくに労働時間や拘束時間が長かったり、変則的なスケジュールであったりすると、精神的な負担が感じられやすいかもしれません。また、有給休暇や産休・育休制度などが利用しづらいことも、不満の原因に挙げられます。
原因⑨給与が良くない

給与は、従業員が生活を送る上で最も重要な要素の一つです。自分の労働に見合った報酬が得られていないと感じると、モチベーションが低下し、仕事への意欲が失われやすいでしょう。
- 業界の相場に比べて低い
- 同僚よりも給与が低い
- 昇給が期待できない
- 成果が正当に評価されていないと感じる
もし給与への不満を抱えているのであれば、自分の市場価値を把握し、会社との対話を通じて改善を求めることも、視野に入れるべきかもしれません。
原因⑩キャリアアップの機会がない
キャリアアップの機会がないことは、仕事に対して不満を抱く大きな原因の一つです。特にスキルを向上させたい、責任あるポジションに就きたいという意欲が強い人にとって、キャリアの停滞は深刻な問題でしょう。
昇進や新しいプロジェクトを担当する機会がなければ、日常業務がルーティン化しやすくなり、やりがいが失われるかもしれません。キャリアアップの道が閉ざされた職場では、将来への希望を見出しにくくなります。
原因⑪ワークライフバランスが悪い

あなたは、仕事と私生活のバランスが取れているでしょうか?もし、以下のような状況に心当たりがあれば、ワークライフバランスが悪い状態と言えるかもしれません。
- 仕事の連絡が時間外にも頻繁にくる
- 持ち帰り残業が常態化している
- イベントや飲み会への誘いが断りづらい
- 柔軟な働き方が認められない
これらの要因が重なると、長時間労働や過度のストレスによりプライベートの時間を十分に確保できず、家庭や個人の生活に悪影響を及ぼします。
また昨今では、メールやチャットでの連絡が24時間いつでも可能であるため、仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちです。仕事時間外にも業務に関与せざるを得ない状況が続くと、ストレスや不満を増大させる恐れがあるでしょう。(参考:厚生労働省「仕事と生活の調和」)
原因⑫職場自体に不満がある
職場への不満は、物理的環境や組織文化、または経営方針に起因することもあります。具体的には、騒音がひどく集中できない、空調が悪く体調を崩しやすいといった物理的な問題のほか、保守的な組織文化、短期的な利益ばかりを追求する経営方針などが挙げられます。
これらの不満が積み重なると、職場に対する愛着心が失われ、結果として仕事そのものに対する不満へとつながりやすいでしょう。職場環境に対する不満は、個人の努力だけで解決することが難しく、組織全体での改善が求められます。
仕事に不満があるときの7つの対処法
仕事への不満を抱えたままでは、モチベーションの低下や成果に影響を及ぼす可能性があります。
では、どのようにしてこれらの不満を解消し、より良い働き方を実現することができるのでしょうか?
この章では、仕事に不満があるときの具体的な対処法について解説します。より良い働き方を実現するヒントにしてください。
対処法①不満を感じている原因を自分で正しく理解する

仕事への不満を感じながらも、その理由が漠然としていませんか?
しかし、原因が曖昧なままでは、具体的な対策を講じることは難しくなります。まずは、自分がどのような状況で不満を感じているのか、具体的な場面や状況を思い返してみましょう。
例えば、特定の業務がストレスの原因なのか、職場の人間関係が影響しているのか、あるいは会社の方針に納得がいかないのかなど、振り返ってみることから始めます。
また、その不満が一時的なものであるのか、それとも長期的なストレス源であるのかを見極めることも重要です。
一時的なものであれば、時間の経過とともに自然に解決する可能性もあります。しかし長期的なものであれば、根本的な解決に向けて対策を講じる必要があるでしょう。
原因を特定する方法としては、具体的な不満の内容を紙に書き出すのがオススメです。また、信頼できる同僚や友人に話すことでも、頭の中を整理しやすくなるでしょう。原因を明らかにすることで、次に取るべき行動を考えられるようになります。
対処法②自分の行動によって現状を変えられないか考えてみる
自分が抱える不満の原因が明確になったら、その原因に対して、自分自身でコントロールできる範囲がないかを探ってみましょう。
例えば、仕事の進め方に不満があるなら、より効率的な方法を自分で試してみる、労働時間への不満であれば、業務の優先順位を見直すといった対処法が考えられます。
また、人間関係のトラブルに関しても、自分自身の捉え方を見つめなおすことで、心穏やかに過ごせる可能性があります。例えば、上司の指示の仕方がきついと感じる場合、「嫌われている」と捉えるのではなく「忙しく相手に余裕がないのかもしれない」といった解釈をしてみることで、冷静に対応できるかもしれません。
このように仕事に対する姿勢や行動、考え方を見直すことにより、大きな変化をもたらす可能性があります。仕事の進め方を工夫し、職場のルールやプロセスの改善を図ることで、自分自身の働きやすさを向上させられるでしょう。
対処法③仕事へのポジティブな面がないか振り返る

仕事に不満を感じると、その感情は日常生活にも影響がおよびます。しかし、仕事には必ずしも悪い面ばかりではなく、ポジティブな側面も存在するはずです。
自分が日々の業務において喜びや達成感を得ている部分がないか、振り返ってみましょう。
例えば、同僚との協力でプロジェクトを成功させた経験や、お客様から感謝の言葉をもらった出来事などについて思い出すことで、仕事に対する前向きな視点を取り戻せるかもしれません。
今の職場でどのように貢献できるかを考えることも、ポジティブな動機づけにつながります。自分の役割や与えられた責任が、社会全体にどんな影響を与えているのかを理解することで、日々の業務に対する意義を見出せるでしょう。
対処法④気分転換や休息の時間を増やす
仕事に対する不満を感じたとき、気分転換や休息の時間を意識的に増やすことは、心身のリフレッシュに効果的です。
日々の業務で溜まったストレスや疲労を解消するため、短時間でも休息を取り入れてみましょう。
例えば、昼休みや仕事の合間に軽いストレッチや深呼吸を行うことで、身体の緊張をほぐし、リラックスした状態を取り戻せるかもしれません。また、週末や休暇を利用して趣味に没頭したり、自然の中で過ごす時間を設けたりすることも、良い気分転換になるはずです。
日常的にスマートフォンやパソコンと向き合っている場合は、少し距離を置くこともオススメです。こうした小さな工夫や習慣を積み重ねることで、心身のリフレッシュにつながり、仕事にも前向きな気持ちで取り組める可能性があります。
対処法⑤部署異動などの希望を出す

現在の業務内容や人間関係に不満を抱えている場合は、部署移動を希望することで、仕事への不満やストレスが解消される可能性があります。
また、職場の立地が悪いと感じる場合、上司や人事を担当する部署に相談し、リモートワークの導入や通勤時間の調整など、可能な改善策を模索するのも一つの方法です。
ただし、異動したからといって現在の問題がすべて解決するとは限りません。異動を希望する際には、まず自己分析を行い、どのような業務や環境が自分に合っているか明確にしましょう。
異動の希望を出す際は、単に不満を述べるのではなく、職場全体の状況や他部署のニーズを理解し、どのような貢献ができるか、どのようにキャリアを積んでいきたいかなど、ポジティブな視点で伝えることが大切です。快適な職場環境で働くためにも、自分のスキルがどこで最も活かされるかを見極め、周囲から信頼を得ることを意識しましょう。
対処法⑥不満について上司や信頼できる人に相談する
上司や同僚などの職場の人に相談すると、不満を解決する糸口につながるかもしれません。職場での不満は、個人的な視点だけではなく、周囲の状況や組織全体の問題が絡んでいる場合もあります。
第三者からの意見を聞くことにより、自分では気づかなかった問題の本質が見えてきたり、客観的なアドバイスによって具体的な解決策が見つかったりする可能性もあるでしょう。
まずは、自分が抱えている不満がどのようなものかを具体的に整理し、なるべく感情的にならずに伝えてみましょう。相談を通じて、職場全体の問題として認識してもらえれば、組織としての改善が進む可能性もあります。
根本的な解決につながらない場合でも、不満やストレスについて他者と共有することで、気持ちの整理につながるかもしれません。
対処法⑦専門家・支援機関に相談する

不満を抱え続けることは、心身に大きな負担をかけます。職場環境や業務内容が長期にわたって解消されない場合や、自分で解決するのが難しいときは、専門家や支援機関への相談を検討してみましょう。
労働組合や労働相談窓口などは、職場の不満を効果的に解決するためのリソースを提供しています。職場における権利や法律についての知識を持つため、適切な行動を取るための指針を示してもらえるでしょう。
例えば、各都道府県労働局が設置している総合労働相談コーナーでは、職場のトラブルや不当な労働条件での勤務など、さまざまな相談に応じています。(参考:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」)
また、仕事のストレスにより心身への影響が見られる場合、メンタルクリニックや心理カウンセラーの利用を検討するのもオススメです。専門家に相談することで、客観的な視点から自分の状況を捉えることにつながり、治療への道筋を示してもらえるでしょう。
仕事のストレスに対処する方法については、以下のコラムでも解説しています。
補足:不満が解消されないときは転職も視野に
無理に不満を抱え続けることは、キャリアの可能性を狭めるばかりか、心身の健康にも影響を及ぼしかねません。
転職を考えるときに、以下のようなサービスやサポートを利用することで、効率的な情報収集やスキル向上に役立てられます。(参考:厚生労働省「雇用」)
- 転職求人サイト:企業の求人情報が掲載されており、自分で検索・応募できるサイト
- 転職エージェント:キャリアアドバイザーが求職者の希望やスキルに合った求人を紹介し、転職活動を支援するサービス
- ハローワーク:地域に根ざした求人情報の提供や就職相談、スキルアップトレーニングを提供する職業紹介所
- 地域若者サポートステーション:働くことに悩みを抱える若者に対し、相談やキャリア支援などを行う地域の支援機関
- ジョブカフェ:都道府県が設置する若者向けの就職支援施設
- 就労移行支援事業所:障害のある方が一般就労に必要な知識やスキルを習得し、就職活動から定着までをサポートする福祉サービス
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、関東地方に5校、関西地方に3校を展開する就労移行支援事業所です。講座はオンラインでも受講できるため、全国の人に利用してもらえます。
休職中にスキルを獲得して転職やキャリアチェンジに役立てたい人は、以下からご確認ください。
仕事や会社への不満を伝える方法
この章では、仕事や会社への不満を伝える方法について解説します。(参考:働く女性の心とからだの応援サイト「自分ばかりが我慢していると思ったら ~職場でストレスをためない気持ちの伝え方~」)
前提:不満を伝えるのは悪いことではありません

仕事や会社に対する不満を自分自身で解決しようとする姿勢は、とても素晴らしいことです。
しかし、不満の種類によっては、自分だけではどうにもできない場合もあります。
とはいえ、仕事や会社の不満を上司や同僚などの職場の人などに直接伝えるとなると、以下のような不安を感じる人も多いでしょう。
- わがままだと思われたらどうしよう…
- 職場の空気や雰囲気を壊したらどうしよう…
しかし、仕事や会社への不満を伝えることは、悪いことではありません。
あなたの気持ちや考えを伝えることが、相手や職場がより良い方向に向かわせるきっかけとなるかもしれません。
また、世の中の多くの人は、日々の自分の生活や仕事に必死で、周りの人の不満に気付くことが難しい場合も珍しくありません。
そのため、あなたが不満を感じていて、その不満を誰かの協力を得て解決したい場合は、勇気を出して伝えることが大切なのです。
ただし、伝え方によっては職場の人間関係に影響する可能性があることは否めません。
そのため、仕事や会社への不満を伝える際は、伝え方を意識しましょう。
伝え方①冷静に事実を伝える
まずは、冷静に事実を伝えることを心がけましょう。
仕事や会社への不満を伝えるとなると、これまで抱えてきたつらい気持ちから、つい感情的に話しそうになるかもしれません。
しかし、感情的になると、相手は「怒られた」「不満をぶつけられた」などと感じ、あなたが本当に伝えたいことが伝わらなくなる可能性があります。
また、事実を伝えることも大切です。「~と思います」「~かもしれません」とあいまいな表現をすると、何に不満を感じているのかが伝わりづらくなります。
加えて、「言わなくてもわかるでしょ」「それくらい察して」などの言葉は使わないようにしましょう。
伝え方②相手への理解を示す

会社の不満を伝える場合、自分のことばかりを話しそうになるかもしれません。
しかし、相手の立場や状況に理解を示すことも大切です。
「あなたが大変なのは知っている」「今の状況ならこうなるのはわかる」などと伝えることで、相手も自分が尊重されていると感じ、話がスムーズに進みやすくなるでしょう。
伝え方③要望をしっかりと伝える
不満を伝える際は、自分の要望をしっかりと伝えることが大切です。
例えば、「締め切りは2日程度ゆとりをもって設定してほしい」「残業は1日1時間にしたい」などです。
逆に、「締め切りに追われてつらい」と不満だけを伝えたり、「業務量を減らしてほしい」と要望が曖昧だったりすると、相手もどう改善すればいいかがわかりません。
また、自分の要望が難しいと言われる可能性も念頭に置いて、代替案も考えておくことが大切です。
まとめ:原因を明らかにして適切に対処しましょう
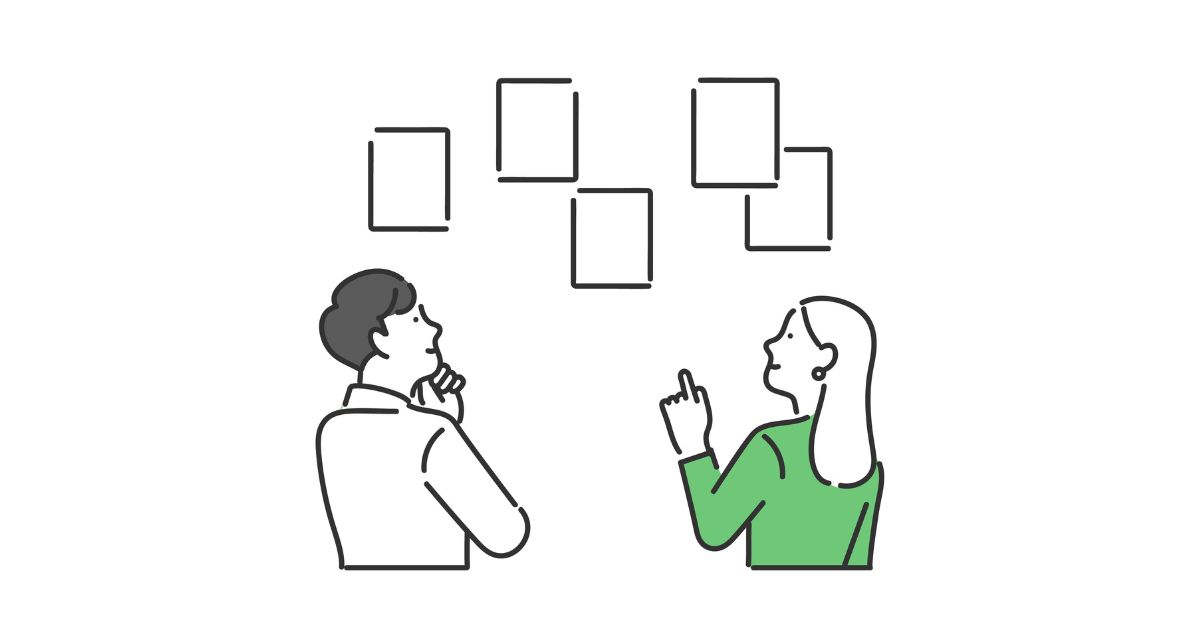
仕事への不満は、誰もが一度は経験するものです。しかし、その不満が蓄積し続けると、心身の健康に悪影響を及ぼすだけでなく、仕事のパフォーマンスにも影響を与える可能性があります。
不満を感じた場合、自分の中で何が原因となっているのかを明確に理解し、適切な対処法を講じることが重要です。業務の進め方を見直してみたり、上司や同僚などの職場の人に相談してみるなど、小さな一歩を踏み出すことで、状況を改善できるかもしれません。
あなた自身のキャリアを大切にし、前向きに働き続けるためにも、このコラムで紹介した内容を参考にしてみてください。
仕事に不満を感じる主な原因を教えてください。
以下が考えられます。
- 仕事内容にやりがいが感じられない
- 仕事の成果が評価されない
- 仕事への裁量権が少ない
- 職場の人間関係が悪い
- 同僚との協力体制ができていない
- 職場にハラスメントがある
- 職場の立地が悪い
- 労働条件に不満がある
- 給与が良くない
- キャリアアップの機会がない
- ワークライフバランスが悪い
- 職場自体に不満がある
詳細については、こちらで解説しています。
仕事に不満があるときの対処法はありますか?
以下が考えられます。
- 不満を感じている原因を自分で正しく理解する
- 自分の行動によって現状を変えられないか考えてみる
- 仕事へのポジティブな面がないか振り返る
- 気分転換や休息の時間を増やす
- 部署異動などの希望を出す
- 不満について上司や信頼できる人に相談する
- 専門家・支援機関に相談する
詳細については、こちらで解説しています。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→