高次脳機能障害のある人に向いてるアルバイト 支援機関を紹介

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
あなたは、高次脳機能障害があって、自分に向いているアルバイトを探しているのではありませんか?
高次脳機能障害のある人も、支援サービスを利用して症状に対する理解と対策をすれば、アルバイトなどの仕事に就ける可能性は充分にあります。
このコラムでは、高次脳機能障害の人に向いてる可能性のあるアルバイトなどについて解説します。
この記事を読むことで、あなたに向いたアルバイトが見つかりやすくなるはずです。
また、働くまでの準備の仕方だけでなく、いざ働き出してから職場に定着する方法についても理解が深まるでしょう。
この記事は章ごとに話題が分かれていますので、興味のある目次のタイトルから読んでもらってかまいません。
また、長い文章を読むことが難しい場合は、他の人と一緒に読むことをオススメします。
高次脳機能障害の特徴の一つは、自分で症状を自覚しにくいことです。障害を受容していくにあたっての心理的ストレスも強いです。アルバイトを探す・アルバイトで働く際にも、ストレスをため込まないように、支援者と繋がりつつ自分に合ったペースで行動していきましょう。
アルバイトしたい高次脳機能障害のあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
高次脳機能障害の人に向いてるアルバイト・難しいアルバイトの特徴と具体例

早速、高次脳機能障害のある人に向いてる可能性のあるアルバイト、難しいと思われるアルバイトを紹介します
※高次脳機能障害は人によって症状が異なります。そのため、自分に向いたアルバイトを探すためには、まず自分の特性を知る必要があります。本章を参考にした上で、改めて自分の症状に合う働き方を考えましょう
①高次脳機能障害の人に共通する「苦手な作業」と「相性のよい作業」
様々な症状がある高次脳機能障害ですが、この障害のある人が仕事において苦手とする作業はある程度同じ特徴が見られます。
その苦手とは、「どう行動するかをその場で考えて、複数の仕事をこなしていく」というものです。
なぜなら、注意障害や遂行機能障害などの低下によって、「新しいことに注意をすぐに切り替えて、計画を修正して取り組むこと」が難しくなっているからです。
逆に、自分で仕事内容を新しく考える必要のない定型作業の方が、高次脳機能障害の人との相性はよいでしょう。
さらに、「疲れやすくなる」という症状も、高次脳機能障害の人の間で共通してよく見られます。
この症状に関しては、全ての職種において課題となる特性であるため、求人を探す際には常に念頭に置いておきましょう。
②高次脳機能障害の人に向いてる可能性があるアルバイト

以上を踏まえると、高次脳機能障害の人には以下のアルバイトが向いてる可能性があります。
- 荷物の仕分け
- 工場のライン作業
- 清掃
- データ入力などの単純な事務作業
ただし、上記の仕事はあくまでも例です。「実際のあなた」や「実際の職場」によっては、向いてるバイトは他にも多様に考えられます。「実際に向いてるバイト」を探すためには、後述するサポート団体を利用しましょう。
③高次脳機能障害の人に向いてない可能性が高いアルバイト

一方で、以下のアルバイトは不向きな可能性が高いです。
- コンビニなど複数の仕事を同時にこなす必要があるバイト
- 接客や営業などコミュニケーションを主とするバイト
- 複雑な処理を必要とする事務作業のバイト
こちらも例ですので、実際のあなた、職場のサポート、実際の仕事内容によっては、向いてる場合もありえます。
④アルバイト以外の働き方の例:就労継続支援
アルバイトではありませんが、障害のある人の働き方の一つに「就労継続支援」という制度があります。
就労継続支援とは、障害によって(のために、が原因で)、一般企業での就業が困難な方などへ、就労の機会や生産活動の機会を提供するサービスです。
就労継続支援にはA型・B型と二つのサービスがあり、それぞれ異なる内容となっております。
B型につきましては、コラム「就労継続支援B型とは?概要・作業内容・事業所選びのコツなどを、10年間の通所経験者が紹介!」で詳細を書いていますので、そちらを参考にしていただければと思います。
A型・B型ともに、ご興味がありましたら、ご利用されている福祉サービスの担当者や、市区町村の福祉課の窓口で相談することをオススメします。
高次脳機能障害の人が、アルバイト探しと並行して利用できるサポート制度

高次脳機能障害のある人は、アルバイト探しと並行して(アルバイト探しの前に)、福祉サービスを利用することをオススメします。
各種の制度を利用することで、生活面や金銭面のサポートを得られ、アルバイト探しにも余裕が出てくるはずです。
この章では、そうした制度の例を紹介します。(参考:大阪府障がい者自立支援協議会作成「高次脳機能障がい支援ハンドブック※PDF」(pp.60-66))
サポート制度①生活訓練プログラム
日常生活の中での障害への対処の訓練を受けていない場合は、生活訓練プログラムを受けてみましょう。
生活訓練プログラムでは、生活管理能力や障害の自己認識など、日常生活において障害と向き合っていく方法を学ぶことができます。
このプログラムは、自立訓練施設や病院のリハビリ施設、障害者施設のデイユースなどで受けることができます。
自分の地域で生活訓練をする自立訓練施設がわからない場合は、担当医や近くの高次脳機能障害相談窓口(※)に聞いてみましょう。
※お近くの相談窓口は、高次脳機能障害情報・支援センターの「高次脳機能障害相談窓口」で探すことができます。
サポート制度②経済的支援制度

経済面において高次脳機能障害の人が利用できる様々な支援サービスがあります。
- 介護保険
- 医療費の自己負担率が下がる自立支援制度
- 障害者年金など
自治体によって違いがあるので、自分がどの制度を受けられるのかは市区町村の福祉課の窓口で聞いてみましょう。
「高次脳機能障害と経済的サポート」の詳細は、高次脳機能障害情報・支援センターの「福祉サービスについて知りたい」をご覧ください。
サポート制度③障害者手帳
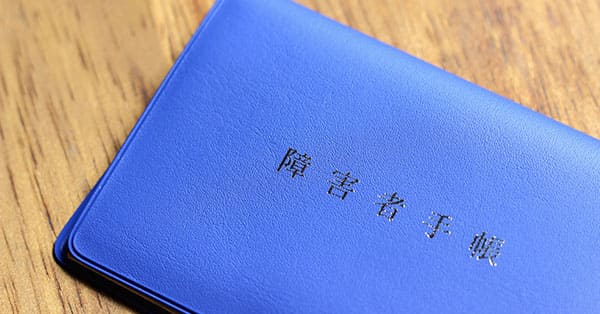
障害者手帳は、障害者枠で仕事をする際には必要ですので、求人に応募する前に取得しておきましょう。
高次脳機能障害の場合、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳のどちらでも申請が可能です。
障害者手帳を持つことで、公共交通機関や文化施設の割引などを受けることができます。
「高次脳機能障害と障害者手帳」の詳細は、高次脳機能障害情報・支援センターの「福祉サービスについて知りたい」をご覧ください。
高次脳機能障害のある人が相談できる支援機関7選

前章で紹介したサービスや制度などを利用した上で、更に利用をオススメするサービスがあります。
それが、これから紹介する障害者に対応した就労サービスです。
アルバイトへの応募にあたっては、自分の障害をうまく説明できると、採用の確率は上がります。
また、採用後にも、自分の障害への対処法を理解していると、何かの「問題」が生じた際への対応もしやすく、トラブルの防止・解決がしやすくなるでしょう。
これから説明するサービスは、そうした助けになります。気になるところがあれば、ぜひ連絡をとってみてください。
それぞれ、「向いてるアルバイト」について相談できるだけでなく、障害の特性を考え、仕事を長続きさせて社会復帰をするための大きな支えとなってくれるはずです。しっかりと福祉サービスと連携を取り、スムースなアルバイト探しをしましょう。(参考:高次脳機能障害情報・支援センター「就労支援について知りたい」、大阪府障がい者自立支援協議会作成「高次脳機能障がい支援ハンドブック※PDF」(pp.60-66))
支援機関①就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。実際のサービスは、国の基準を満たしたさまざまな民間の就労移行支援事業所が行います。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
就労移行支援事業所は各地にあります。私たち、キズキビジネスカレッジ(KBC)もその一つです。それぞれ特徴が異なるため、気になるところがあれば問い合わせてみてください。
就労移行支援事業所については、下記コラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援機関②ハローワーク

ハローワーク(公共職業安定所)とは、仕事を探している人や求人を募集したい事業者に対して、就労に関連するさまざまなサービスを無償で提供する、厚生労働省が運営する支援機関のことです。正式名称は公共職業安定所で、職安と呼ぶ人もいます。(参考:厚生労働省「ハローワーク」厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」厚生労働省「公共職業安定所(ハローワーク)の主な取組と実績」、東京労働局「東京ハローワーク」、厚生労働省「こころの健康サポートガイド」、厚生労働省「ハローワークにおける障害者の就労支援」)
主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示などを行っており、具体的な支援内容は事業所によって異なりますが、一般的には以下のような幅広いサポートを行います。
全国に500ヶ所以上あり、主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示、雇用保険や雇用対策など、地域密着型の雇用に関する幅広いサポートを行います。
また、病気や障害のある人に向けたサポートも行っています。障害者手帳を所持していない人でも、医師による診断書があれば、障害の特性や希望職種に応じた職業相談や履歴書や面接での病気・障害の伝え方などのサポートを受けることができます。
支援機関③精神保健福祉センター

精神保健福祉センターとは、精神障害のある人のサポートを目的とした、地域の精神保健福祉の中核を担う支援機関のことです。(参考:東京都福祉保健局「精神保健福祉センターとは」、e-Gov法令検索「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)
精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)に基づき、各都道府県に設置されています。地域によって、こころの健康センターや心と体の相談センターなど、一部名称が異なります。
精神保健福祉センターでは、精神疾患に関連する悩みの相談や社会に適応するための指導と援助を行っています。
精神障害による症状で悩んでいる本人だけでなく、ご家族や周囲の人の相談も受け付けています。また、匿名での相談も受け付けています。医師から正式な診断を受けていなくても相談は可能です。
詳しくは、お住まいの自治体の精神保健福祉センターにお問い合わせください。
支援機関④地域障害者職業センター

地域障害者職業センターとは、病気や障害のある人に対して、職業評価や職業指導、職業準備訓練、職場適応援助などの専門的な職業リハビリテーションを提供する支援機関のことです。(参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センターによる支援」、厚生労働省「地域障害者職業センターの概要」)
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しており、障害者雇用促進法に基づいて、全国47都道府県に設置されています。(参考:厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律」)
ハローワークや医療・福祉機関と連携しているため、仕事に関する相談や訓練、復職するためのサポートを行っています。
病気や障害に悩む当事者だけでなく、障害のある人を雇用する事業所に対して、雇用管理に関する相談・援助も行っています。
支援機関⑤障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターとは、雇用や保健、福祉、教育に関する関係機関と連携し、障害のある人の雇用の促進・安定を目的とした一体的な支援を行っている支援機関のことです。(参考:厚生労働省「障害者就業・生活支援センター」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」、厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」)
障害のある人の就職活動の支援や求人の紹介、職場定着のためのサポートなどを行います。
就業面だけでなく、金銭管理などの経済面や生活面のことまで、日常および地域生活に関する支援も行っています。
生活習慣や金銭管理、健康管理などについても幅広く相談できるため、生活面のサポートも受けたい人にオススメです。
2024年4月1日時点で、障害者就業・生活支援センターは全国に337箇所設置されています。
支援機関⑥障害者職業能力開発校
障害のある人が働く上で必要な基礎知識や技術を身につけるための職業訓練を行います。
詳細は厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
支援機関⑦障害のある人に特化した求人サイト
求人サイトの中には、障害のある人に特化したところがあります。
そこで掲載されている求人・職場は、一般的に、障害への理解が深いです。
また、意外というか当然というか、Googleなどの検索エンジンで「障害者 アルバイト 求人」などと検索すると、他にも同様の求人(サイト)が見つかります。
高次脳機能障害の人がアルバイトをする際の3つのポイント

ここまで、アルバイトを始めるまでのポイントを紹介してきましたが、働き出してからも注意すべきことがあります。
それは、「障害によって自分ができなくなったことを認識し、対処法を考える」ということです。
高次脳機能障害の様々な症状の中で、アルバイトをする際に対処しなければならない主なものとしては、①記憶力の低下、②社会的行動障害、③疲労感が主に考えられます。
それぞれ、概要と対策の例を紹介します。
ポイント①記憶力の低下
いざ働き出して仕事内容を教えてもらっても、たった今教えてもらったことでも思い出せなくなったり、翌日になると全て忘れていたり、ということがあります。
この症状への有効な対処法は、「メモをこまめに取る」です。
以前はメモに書かずに覚えられていたようなことでも、障害によって忘れるということがあります。
そのため、メモを書く際には、「手順をすっかり忘れた状態で読んでも何をすればいいのか分かる」ように書くようにしましょう。
また、高次脳機能障害では長文を読むことが難しくなることもあり、イラストなどを入れて読みやすくすることを意識しましょう。
デスクワークでPC等を使用する業務の場合は、ドキュメントファイルを職場の人と共有することをオススメします。
自分の抱えている状況を周りの人が即座に確認することができるため、迅速な連携を取ることができます。
他に、記憶障害の人のための「メモリーノート」というノートもあります(参考として、茨城県の「高次脳機能障害支援ツールをご覧ください)。
気になる場合は、利用している支援サービスなどで相談してみましょう。
ポイント②社会的行動障害
社会的行動障害によって、すぐに周りに怒ったり攻撃的な態度を取ったりすることがあります。
一度興奮状態になった際には、他に人のいない場所で休憩をすることが有効的です。
控室や休憩室など、刺激の少ない場所で気持ちが落ち着くのを待つようにしましょう。
ポイント③疲労感

脳の機能が低下している状態で作業をすることによって、障害がなかったときよりも早く疲れるようになります。
前項とも似ていますが、疲れた場合は無理をせずに休憩室などでこまめに休むようにしましょう。
補足
繰り返しとなりますが、いまのあなたにできることや、障害に関連してできなくなったことなどを知るためには、支援サービスを利用することをオススメします。
支援サービスでは、自分の障害がどのようなものなのかについて客観的に説明してもらえるだけでなく、障害と付き合いながら仕事をするにはどう対処すればいいのかということも相談ができます。
障害がある人がアルバイトをする(働く)際の、「合理的配慮」とは何か

自分の障害への対処法を考えていく上では、周りの人との協力が大事です。
特にアルバイト先の人にとって、障害の内容は仕事に大きく関わってくるため、周りがどのような配慮をすればいいのかが伝わる具体的な説明をすることが必要です。
このような説明を「合理的配慮」と言います。
そのためには、以下の3つを説明することが重要です。
- ①自分が障害でこんなことができなくなっている
- ②自分でもできる範囲では対処法を見つけているが、どうしてもできないことがある
- ③どうしてもできないことを周りにはこう対応をしてほしい
この3点がちゃんと考えられていない場合の例を挙げます。
- 自分はよく忘れたり、感情的になってしまうのですが、障害のせいなので怒らないでほしいです
症状についても、自分や周りがどう対応していくのかについても曖昧な説明であり、職場の人たちはどうすればいいのか具体的な方針を決められず、協力体制をしっかりと築けなくなる可能性があります。
次に、この3点をしっかり伝えている例を挙げます。
- 私は記憶力が低下しており、口頭だけで伝えられると忘れてしまうことがよくあるので、こちらがメモが取れるようにゆっくり教えていただけるか、文面で伝えていただけると助かります
具体的かつ相手に何をしてほしいかが明確であり、お互いにどうやって対処をしていくかを考えやすくなるため、職場側の協力も行いやすくなります。
また、自分が客観的に障害を認識しており、働くために自分の中で努力を行っていたことをアピールすることで、採用されやすくなるというメリットもあります。
合理的配慮の説明の仕方についても、前章までにで紹介したサポート団体が相談に乗ってくれます。
働き出してからうまくいかないことがあった際にも、遠慮なく相談しましょう。
高次脳機能障害とは?

高次脳機能障害について、改めて簡単な説明をします。
すでにご存知かもしれませんが、これまでに紹介した内容の理解も深まると思いますので、ぜひご覧ください。
高次脳機能障害とは、脳損傷による認知に関する障害全般を指しており、原因としては事故や脳卒中などの病気によるものが多いです。
症状は人によって様々ですが、身体麻痺の他に、次のようなものがあります。
- ぼんやりしてミスをする
- 複数のことを並行して行えない
- ずっと一つのことを行えない
- 新しいことを覚えられない
- 同じことを何回も聞く
- 行ったことがある場所でも迷子になってしまう
- 自分で計画を立てて実行することができない
- 優先順位がつけられない
- 約束の時間に間に合わない
- 攻撃的な態度をとる
- 自己中心的になる
- 抑うつ状態になる
- 疲れやすくなる
- 視界の半分にあるものを認識できなくなる(半側空間無視)
- 読み書きや聞いたり話す能力の低下(失語)
これらの症状については、時間の経過やリハビリによって改善するものと、そのまま残るものがあります。
詳細については、下記のコラムや国立障害者リハビリテーションセンターの説明をお読みください。
まとめ:支援機関としっかりと連携しましょう

紹介したポイントはどれも大切ですが、一人ですべてをこなすとなると大変です。
そのためにも支援機関としっかりと連携しましょう。
働くということは、「社会と共に生きる」ということでもあります。
アルバイトを始めてからも、「問題」を一人で抱えず、支援サービスに相談することを忘れずに、自分なりの働き方を見つけていきましょう。
高次脳機能障害のある自分に向いてるアルバイトを知りたいです。
高次脳機能障害のある自分がアルバイトをする(働く)上で注意するべきポイントを知りたいです。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→








