ヘルプマークは精神障害のある人も使える? 取得方法や活用法を解説
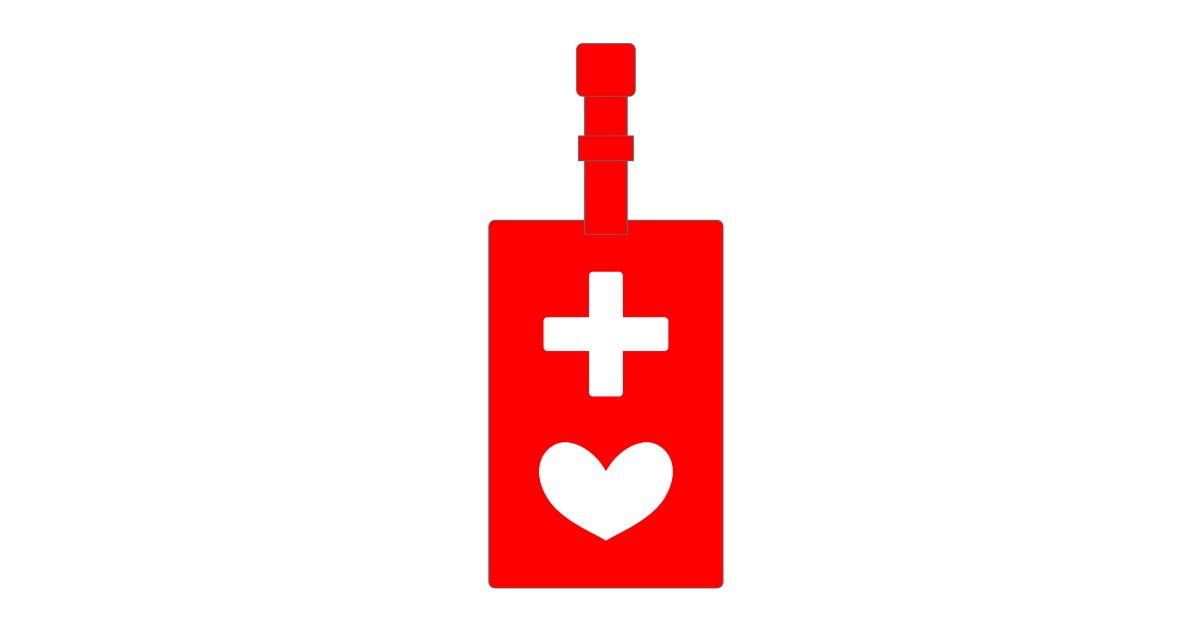
こんにちは。 就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
あなたは、外出時に精神障害の症状によって以下のような悩みを感じることはありませんか?
- 電車が苦手で優先席に座りたいけれど、周囲の視線が気になる…
- 急に具合が悪くなったとき、どうしてほしいかうまく伝えられない…
- 見た目では障害がわからないから、周りの人に配慮を求めづらい…
このような悩みに対する解決手段の一つが、ヘルプマークの活用です。
ヘルプマークは、見た目ではわからない障害や症状のある人が、周囲の人に配慮や支援を求めやすくするためのツールです。
このコラムでは、精神障害のある人に向けて、ヘルプマークの概要やメリット、取得方法、使い方について解説します。
ヘルプマークの利用を検討している人はぜひ参考にしてみてください。
精神障害のあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
ヘルプマークとは?

ヘルプマークは、外見からは分かりにくい障害や疾患のある人が、周囲に配慮や支援が必要であることを知らせるためのマークです。(参考:東京都福祉局「ヘルプマーク」)
赤地に白い十字とハートのシンプルなデザインで、バッグなどに取り付けて使用します。
このマークを利用できる対象者は以下のとおりです。(参考:大津市「ヘルプマークの配布について」、 参考:津山市「ヘルプマーク・ヘルプカード・ヘルプシール」)
- 義足・人工関節を使用している人
- 内部障害のある人
- 難病のある人
- 妊娠初期の人
- 発達障害のある人
- 精神障害のある人
- その他援助および配慮が必要とされる人
外見では判断しにくい援助が必要な全ての人がヘルプマークの対象となっています。
ストラップや紐がついた本体には、裏面にシールがあり、そこに緊急連絡先や配慮してほしい内容を自由に記入できます。
ヘルプマークを使うことで、言葉を使わなくても周囲の人に必要な支援を伝えられるため、外出時の安心につながります。
ヘルプマークの役割・効果
精神障害の症状は、パニック発作や感覚過敏、疲れやすさなど、外見に現れにくい場合が多いです。
そのため、周囲の人からは「怠けている」「わがまま」などと誤解され、必要な配慮を受けられないこともあります。
ヘルプマークは、そのような見た目ではわからない精神障害などへの理解を得やすくし、周囲の人に配慮や援助が必要であることを伝える役割があります。
混雑した電車やバス、長時間の移動など、精神的なストレスを感じやすい場面でも、ヘルプマークを活用することで、自分の状況に合わせた無理のない過ごし方ができるようになります。
見た目では伝わらない「助けがほしい」という思いを、このマークを通して伝えることで、周囲の人から理解してもらいやすくなります。
また、周囲の人も、ヘルプマークがあることで「この人は助けが必要な状態なんだ」と認識でき、声をかけやすくなったり、必要な支援をしやすくなったりするでしょう。
精神障害のある人がヘルプマークを取得するメリット
この章では、精神障害のある人がヘルプマークを取得するメリットについて解説します。
メリット①優先席利用時の周囲の理解を得やすくなる

「健康そうなのに優先席に座るなんて...」という視線を感じたことはありませんか?
精神障害のある人は、めまいやふらつき、疲労感などで長時間立っていることが困難な場合があります。(参考:厚生労働省「不安障害」、 参考:厚生労働省「精神障害(精神疾患)の特性(代表例)」)
ヘルプマークを付けていれば、周囲の理解を得られやすくなるため、周りからの視線を気にする必要がなくなります。
また、電車やバスなどで立っている際に、席を譲ってもらえる可能性が高まります。
メリット②パニック発作などの際に適切な支援が受けられる
パニック発作などの緊急事態が発生したときは、症状のために言葉がうまく出なかったり、自分の状況を説明するのが難しくなったりすることがあります。
そんなとき、ヘルプマークの裏面に症状や対処法を記載しておくことで、言葉が出なくても適切な支援を受けられる可能性が高くなります。
例えば「パニック発作が起きたら静かな場所に連れて行ってください」「深呼吸を促してください」といった具体的な対応方法を書いておけば、周囲の人も的確に行動できるでしょう。
また、緊急連絡先を記入しておけば、必要に応じて家族や主治医に連絡を取ってもらえます。
メリット③職場や学校での理解と配慮につながる可能性がある

ヘルプマークを職場や学校で活用することで、上司や同僚などの職場の人や教職員からの理解を得るきっかけを作ることも可能です。
精神障害は外見からわかりにくいため、「今日は調子が悪いです」と伝えても理解されにくいことがあります。
ヘルプマークを身につけることで、本人は必要な配慮を求めやすくなり、周囲も障害を理解しやすくなります。
例えば、体調が優れないときに「少し休憩させてください」と言いやすくなることはもちろん、周りから誤解されることなく安心して休憩をとることができるでしょう。
また、職場や学校で調子が悪くなったときに、ヘルプマークがあることでほかの人からの声かけやサポートを受けやすくなります。
さらに、静かな場所での休憩や柔軟な勤務時間など、合理的配慮を受けるための話し合いのきっかけになる可能性もあるでしょう。
メリット④災害時や緊急時の支援を受けやすくなる
地震や火災などの災害時に、周囲に自分の障害について説明することは、簡単なことではありません。(一般社団法人ユニバーサルヘルプカード協会「【緊急時・災害時のために今、出来ること。。。】」)
しかし、ヘルプマークを身につけていれば、周囲の人はあなたに配慮や支援が必要だと理解し、適切な対応が受けられます。
また、緊急時に医療従事者や救急隊員がヘルプマークに気づけば、症状や対処法を考慮した支援につながるでしょう。
避難所での生活においても、ヘルプマークがあることで「静かな場所が必要」「薬の服用が欠かせない」といったサポートが必要な部分が明確になり、配慮を受けやすくなります。
ヘルプマークは 、災害時の安全確保にも役立つでしょう。
ヘルプマークの取得方法と申請手続き
この章では、ヘルプマークの取得方法と申請手続きについて解説します。
ヘルプマークの配布場所と入手方法

ヘルプマークは基本的に無料で配布されていて、さまざまな場所で入手できます。主な配布場所は、以下のとおりです。(参考:千葉市「ストラップ型ヘルプマーク・ヘルプカードの配布場所を拡大します」、参考:東京都福祉局「ヘルプマーク」)
- お住まいの都道府県や自治体の役場(福祉課などの担当窓口)
- 保健所や保健福祉センター
- 障害者相談センターなどの福祉関連施設
- 自治体によっては駅や病院など(例:東京都では都営地下鉄の各駅や都立病院)
「どこが最寄りの配布場所なのかわからない...」という人は、お住まいの自治体のホームページで簡単に確認できますので、ぜひチェックしてみてください。
また、体調不良などで外出が困難な場合には、一部の自治体では郵送対応も実施しています。(参考:東京都福祉局「ヘルプマーク」、参考:三鷹市「ヘルプカード・ヘルプマークを配布しています」)
ただし、郵送料は自己負担の自治体もあるので、事前に確認しておくといいでしょう。
補足:ヘルプマークの取得に障害者手帳は必要?
「障害者手帳を持っていないけど、ヘルプマークは取得できる?」と心配している人も多いのではないでしょうか?
実は、ヘルプマークの取得に障害者手帳や診断書は一切必要ありません。(参考:神奈川県「ヘルプマークを知っていますか」)
利用する本人からの申し出のみで、誰でも取得できます。自治体によっては家族を含む代理人による申請も可能です。
多くの自治体では、窓口での簡単な申し出だけで手続きが完了し、その場でヘルプマークを受け取れます。
一部の自治体では申請書の記入が必要な場合もありますが、氏名や住所といった最低限の個人情報を書く程度の簡易的なものがほとんどです。(参考:金沢市「HELPカード・ヘルプマークについて」、参考:石川県「ヘルプマークについて」)
受け取ったヘルプマークにはストラップが付属していることが多いので、すぐにバッグなどに取り付けて使用できます。
ただし、基本的には1人1つまでの配布となっている自治体が多いので、紛失した場合は再交付が可能な自治体が多いため再度窓口に相談してみましょう。(参考:東京都福祉局「ヘルプマーク」、参考:島根県「ヘルプマーク・ヘルプカードについて」)
ヘルプマークの書き方と記入例

ヘルプマークの裏面には、緊急連絡先や支援を必要とする状況、配慮してほしいポイントを記入できるシートがあります。
シートには、以下のように具体的な症状や対応方法を記入するのがオススメです。
- パニック発作がある
- 体に触れられると不安を感じる
- 大きな音が苦手
- 「安全な場所に連れて行ってください」
- 「体に触らずにゆっくり、はっきりと指示してください」
- 「ゆっくり話しかけてください」
また、服用している治療薬や注意事項なども記載しておくと、緊急時に医療関係者が対応しやすくなります。
ただし、プライバシーの観点から、必要以上の個人情報は記入せず、支援に必要な情報に絞ることをオススメします。
また、状況が変わったり、連絡先が変更になったりした場合は、随時シールを貼り替えて最新の情報に更新することも忘れないでください。
補足:ヘルプマークと併用できるヘルプカード
ヘルプカードは、ヘルプマークよりもさらに詳細な情報を記載できるカード式の支援ツールです。(参考:滋賀県「ヘルプマークとヘルプカードについて」)
ヘルプマークの裏面シールでは書ききれない情報を、より詳しく記載できます。
具体的な活用方法として、カバンの中にヘルプカードを入れておき、ヘルプマークの裏面に「カバンの中のヘルプカードを見てください」と書く方法があります。
また、緊急時の連絡先や医療情報など、プライバシーに関わる情報はヘルプカードに記入し、必要なときだけ確認してもらうという方法であれば安心感を得られるでしょう。
ヘルプカードは、自治体の福祉窓口などでヘルプマークと一緒に無料で入手できることが多いです。
自分の状況や必要な配慮をより詳細に伝えたい人は、ぜひヘルプカードとの併用を検討してみてください。
周囲の人ができるヘルプマークを付けている人への適切な対応

ヘルプマークを付けている人は、外見では健康そうに見えても、何らかの配慮や支援を必要としています。
そのため、ヘルプマークを付けている人を見かけたら、主に以下の3つの対応を行いましょう。
- 電車やバスの座席を譲る
- 交通機関などの突発的な出来事が起きた際、声をかける
- 災害時は安全に避難するための支援を行う
また、困っているようであれば、「大丈夫ですか?」「何かお手伝いできることはありますか?」など、相手に伝わっているか確認しながら、ゆっくり話しかけることが効果的です。
ヘルプマークやヘルプカードの提示があれば、記載内容を確認して、相手が求める支援を行いましょう。(参考:宇都宮市「ヘルプマークをご存じですか」)
もし応答がない場合や言葉が出ない様子であれば、ヘルプマークの裏面シールを確認して、記載されている対応方法に従って支援するのが良いでしょう。
例えば、席の提供や静かな場所への誘導、記載されている緊急連絡先への連絡など、状況に合わせた支援を行います。
ただし、最も大切なのは本人の意思を尊重することです。
できる限り本人と対話し、「どうしてほしいですか?」と直接確認することで、本当に必要なサポートを提供できます。
「助けたい」という気持ちが先走りすぎると、かえって本人を困らせることもあるので、まずは本人の意思を大切にしましょう。
まとめ:ヘルプマークの利用を検討してみましょう

ヘルプマークは、見た目だけでは気づかれづらい精神障害のある人が、周囲からの理解と必要な支援を受けられるように手助けしてくれるツールです。
障害者手帳がなくても無料で取得でき、日常から緊急時まで幅広いシーンで生活をサポートしてくれます。
精神障害と向き合いながら日常生活を送るあなたが、少しでも生活しやすくなるよう、ぜひヘルプマークの利用を検討してみてくださいね。
障害のある人を対象にした支援機関を利用して、ストレスを軽減するトレーニングに取り組むこともできます。利用を検討したい人はあわせて確認しておきましょう。ぜひご覧ください。
精神障害のある人がヘルプマークを取得するメリットはありますか?
ヘルプマークを付けていれば、周囲の理解を得られやすくなるため、周りからの視線を気にする必要がなくなります。
詳細については、こちらで解説しています。
ヘルプマークの配布場所はどこですか?
以下が考えられます。
- お住まいの都道府県や自治体の役場(福祉課などの担当窓口)
- 保健所や保健福祉センター
- 障害者相談センターなどの福祉関連施設
- 自治体によっては駅や病院など
詳細については、こちらで解説しています。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→






