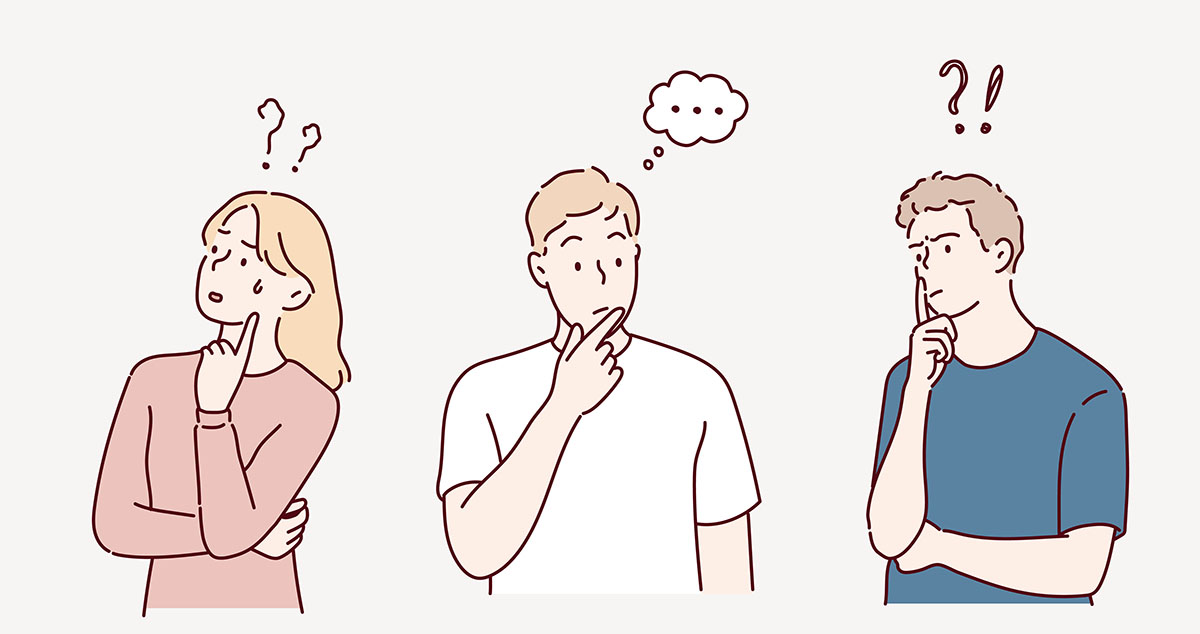就労移行支援の受給者証とは? 発行手続きを解説

こんにちは。就労移行支援事業所、キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
就労移行支援を利用したいものの、受給者証が必要と知って戸惑う人もいるのではないでしょうか。障害者手帳との違いや発行元、手続きの流れがわからず戸惑うこともあるかもしれません。
このコラムでは、就労移行支援で必要となる受給者証の概要や発行手続き、注意点について解説します。
あわせて、就労移行支援を受けるときの相談先も紹介します。就労移行支援を利用して就職を目指す人は、参考にしてください。
就労継続支援の利用を検討しているあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
就労移行支援で役立つ受給者証とは?

受給者証は、正式には「障害福祉サービス受給者証」といいます。自治体が発行する給付の証明書のことで、以下のような障害福祉サービスを利用する際に必要です。(参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」)
- 訓練等給付…就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援など
- 介護給付…居宅介護、重度訪問介護、療養介護、施設入所支援など
就労移行支援を利用するには、障害者手帳ではなく障害福祉サービス受給者証が必要です。障害者手帳がなくても発行でき、申請・発行に費用はかかりません。
障害福祉サービス受給者証には、以下の項目が記載されています。(参考:堺市「障害福祉サービス受給者証(水色)の見方」)
- 受給者番号
- 支給決定障害者等(氏名)
- 障害種別
- 交付年月日
- 支給する自治体名
- 障害支援区分
- 認定有効期間
- 支給決定期間
- サービス種別
- 利用者負担に関する事項 など
これらの項目が利用条件を示す役割を担い、サービスの手続きで重要になります。
受給者証の発行手続き
この章では、障害福祉サービス受給者証の発行手続きについて解説します。
手続き①窓口に相談する

まずは、お住まいの自治体の障害福祉担当窓口に相談しましょう。
ここが障害福祉サービス受給者証の発行を担当する部署です。あるいは、相談支援事業者を通じて手続きを進める方法もあります。
相談支援事業者は自治体の公式ホームページで案内されていることがあるため、必要に応じて確認しておきましょう。
窓口では、申請に必要な書類や手順を教えてもらえます。案内をよく聞き、準備に抜かりがないよう整えてください。
障害福祉サービス受給者証で利用したいサービス事業者(就労移行支援事業所など)が決まっていない場合は、利用先の相談もできます。
手続き②必要書類を用意・提出する
窓口で案内された必要書類を用意し、所定の項目に記入をして提出・申請します。主な書類は、以下の3種類です。
- 障害福祉サービス等支給申請書
- 世帯状況・収入等申告書
- 医師の意見書
医師の意見書は、発行に時間と費用がかかる点に留意してください。
なお、必要書類の種類や意見書の発行費用は自治体によって異なります。あらかじめ公式ホームページを確認するか、電話で問い合わせておくとスムーズです。
さらに、以上のような記入書類のほかに、住所・氏名が確認できる書類や印鑑を求められることが多いため、忘れずに用意しておきましょう。
手続き③サービス等利用計画案を作成する

自治体の相談支援事業者が、本人の意向を聞き取り、「サービス等利用計画案」を作成して提出します。
多くの場合は相談支援事業者を利用しますが、別の事業者を選ぶことも可能です。その場合の対応は以下のとおりです。
- 障害児相談支援事業者が対応:障害児支援利用計画案を作成・提出
- ケアマネジャーが対応:ケアプランを作成・提出
- 自身で対応:セルフプランを作成・提出
なお、提出のタイミングは自治体によって異なることがあります。提出方法は、自治体の案内を確認してください。
手続き④自治体による審査が実施される
必要書類を提出すると、自治体による審査(アセスメント)が実施されます。審査は主に3段階に分かれ、以下のように進みます。
- 障害支援区分認定調査:概況調査、心身の状況に関するアセスメント、特記事項調査
- 1次判定(コンピュータ判定):認定調査の結果と医師の意見書をもとにした判定
- 2次判定(審査会):1次判定の結果、特記事項、医師の意見書をもとにした判定
認定調査の実施にあたっては、調査員との日程調節が必要になるため、開始までに時間を要する場合があります。あらかじめ見込み期間を把握しておくと安心です。
手続き⑤受給者証が発行される
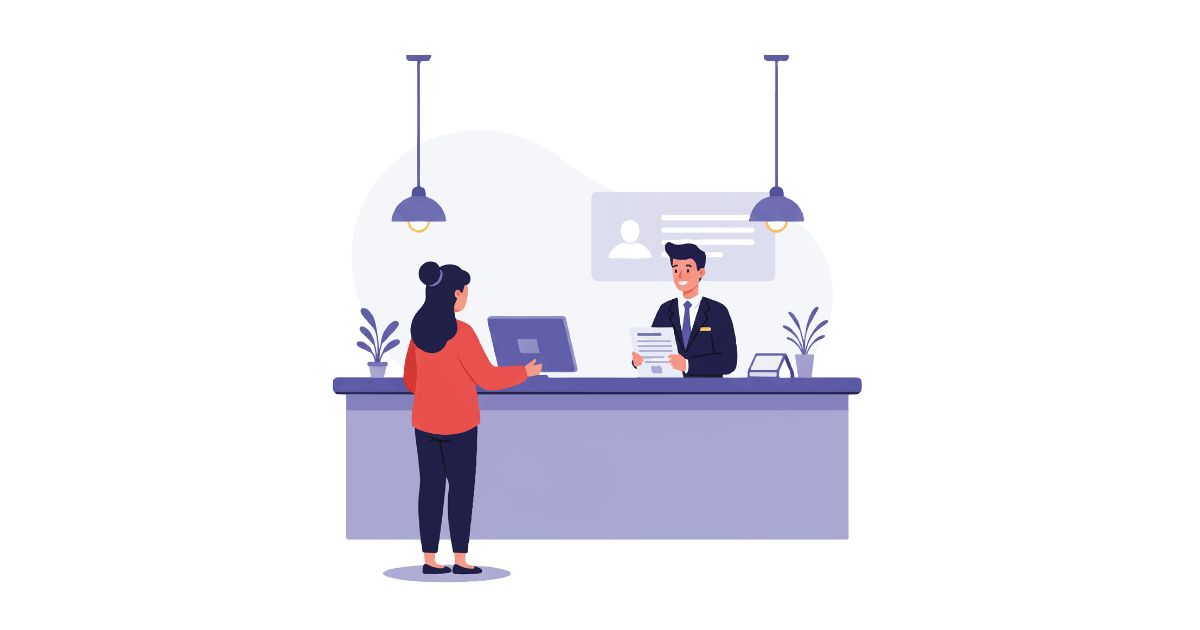
提出されたサービス等利用計画案や特記事項を踏まえ、自治体がサービス支給の可否を決定します。サービス支給が決定したあとの流れは、以下のとおりです。
- 自治体で障害福祉サービス受給者証の交付が決定、通知する
- 通知を受けた相談支援事業者がサービス等利用計画を作成し、自治体へ提出する
- 自治体は計画書を受けて、障害福祉サービス受給者証を作成・発行する
- 利用者は発行された障害福祉サービス受給者証を提示し、障害福祉サービス提供事業者(就労移行支援事業所など)と契約・利用する
なお、自治体によっては障害福祉サービスを暫定支給したのち、正式な発行となる場合もあります。手続きの流れは窓口で案内されるため、説明をよく確認してください。
受給者証で就労移行支援を受けるときの注意点
この章では、障害福祉サービス受給者証を利用して就労移行支援を受けるときの注意点について解説します。
注意点①有効期限がある

障害福祉サービス受給者証を利用して就労移行支援を受ける場合、いずれにも有効期限が設けられている点に注意が必要です。
通常、障害福祉サービス受給者証の有効期限は1年です。就労移行支援の利用期間は2年程度が目安とされています。受給者証の期限後も継続的な支援が必要なときは、更新手続きを行いましょう。(参考:厚生労働省「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」、小田原市「障害福祉サービス等の申請に必要な書類様式(事業者様式含む)」)
有効期限が切れたままだと就労移行支援を利用できない場合があります。送付される案内を確認し、必要書類を早めにそろえておくと安心です。
注意点②発行までに数か月かかる場合がある
障害福祉サービス受給者証は、申請してから発行まで時間を要します。
複数の事業者が関わり審査も行われるため、申請からサービス利用開始までには2か月程度がかかります。
早めの利用開始を希望する人は、事前に準備を進めましょう。手続きに詳しい相談支援事業者や障害福祉サービス事業者のサポートを受けるとスムーズです。
注意点③就労移行支援サービスの対象者を把握しておく

就労移行支援は、誰でも利用できるわけではありません。基本的に、利用できるのは以下の条件を満たす人です。(参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」)
- 就労を希望している障害のある人で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込める人
- 65歳未満の人(※65歳以上の人でも、65歳に達する前の5年間に引き続き障害福祉サービスの支給決定を受けており、かつ65歳になる前日までに就労移行支援の支給決定を受けていた場合は対象)
通常の事業所での雇用が困難だと判断された場合は、就労継続支援A型や就労継続支援B型など、別の障害福祉サービスの活用を検討しましょう。
注意点④変更が生じたら届け出が必要になる
「引っ越しをした」「利用したい障害福祉サービスが変わった」など、申請内容に変更が生じた場合は、必ず届け出が必要です。
手続きの際は、専用の書類に変更後の情報を記入して提出します。出し忘れを防ぐため、申請内容を把握し、必要書類を事前に確認しておきましょう。
注意点⑤自分に合った就労移行支援サービスを見つける

自分に合った就労移行支援事業所を見つけることも重要です。例えば、以下のような項目を確認・比較して検討しましょう。
- 事業所で対応しているスキルと獲得したいスキルが合っているか
- スタッフとコミュニケーションが取りやすいか
- 事業所の雰囲気が合うか
- 支援実績がどれくらいあるか
これらの項目は、見学や体験期間を活用して確認しておくと安心です。
一方で、本格的な支援期間をできるだけ長く確保したい場合は工夫が必要です。就労移行支援事業所を比較している段階で障害福祉サービス受給者証の手続きにも着手し、時間を有効に使ってください。
就労移行支援の探し方としては、インターネット検索に加え、自治体の担当窓口に相談して候補を絞る方法があります。
ハローワークや障害者就業・生活支援センター、相談支援事業者に相談するのも有効です。周囲のサポートを得ながら、相性のよい事業所を見つけましょう。
受給者証の更新手続き方法
就労移行支援を1年以上利用する場合は、途中で障害福祉サービス受給者証の更新手続きが必要です。更新時期は原則として年1回で、誕生月に設定されることが多いです。
更新月の1~3か月前に自治体から案内が送付されるため、内容を確認のうえ手続きを進めてください。
障害福祉サービス受給者証の更新に必要な書類の例は、以下のとおりです。
- 介護給付費・訓練等給付費支給申請書
- 世帯状況・収入等申告書
- セルフプラン
- 本人確認書類(個人情報確認書類)
- 障害福祉サービス受給者証 など
なお、必要書類は自治体によって異なります。加えて、手続き方法も「窓口のみ」「窓口と郵送」などさまざまです。案内を細かく確認し、漏れのない準備を心がけましょう。
受給者証で就労移行支援を受ける流れ
この章では、障害福祉サービス受給者証を利用して就労移行支援を受ける流れについて解説します。
支援を受ける流れ①就労移行支援事業所へ問い合わせする

関心のある就労移行支援事業所に連絡し、資料の取り寄せや詳細の確認を行って判断材料を集めましょう。
問い合わせはWebサイトやチャット、LINE、電話などで受け付けていることが多いため、公式サイトを確認してください。
候補が見つからない場合は、自治体の窓口や相談支援事業者に相談し、紹介された事業所から検討するのもオススメです。
支援を受ける流れ②面談や見学をする
問い合わせの結果、利用を検討したい就労移行支援事業所が見つかったら、面談・見学に進みましょう。
面談・見学は予約が必要な場合があるため、問い合わせのときに確認しておくと安心です。
面談・見学時の確認ポイントは以下のとおりです。
- スタッフとの相性(コミュニケーションがスムーズに取れるかなど)
- 支援内容が希望するものと合っているか
- 就労移行支援事業所の雰囲気が自身に合うか
支援を受ける流れ③体験する

正式な契約の前に、体験利用で相性を確かめてください。「スキルを学びやすい、わかりやすい」「安心して通えそうだ」と感じたら、利用する就労移行支援事業所を決めましょう。
通いやすい場所に事業所がない場合は、オンライン受講の可否や、通信環境で問題なく受講できるかを事前に確認しておくと、無理のない通所計画を立てられます。
障害福祉サービス受給者証の申請手続きは、この段階で着手しておくとスムーズです。
支援を受ける流れ④仮通所する
障害福祉サービス受給者証の発行が完了するまでの間は、仮通所でスタッフと一緒に目標を設定をしましょう。
あわせて、仮通所期間中に無理のない通所ペースを把握しておくことも大切です。実際の利用を想定した準備の例は以下のとおりです。
- スタッフと悩みや課題を共有する
- 就労移行支援事業所での一日の流れを把握する
- 通所経路や所要時間を確認する
支援を受ける流れ⑤利用契約を結ぶ

障害福祉サービス受給者証が手元に届いたら、就労移行支援事業所に持参して正式な利用契約を結びます。
以後は定期的に通所し、2年程度を目安にスキルを身につけて就職を目指しましょう。
就労移行支援を受けるなかで困ったときの相談先
就労移行支援の手続きや利用で困ったことがあれば、以下の窓口へ相談できます。
- 自治体の障害福祉窓口
- 相談支援事業者
ただし、相談支援事業者では、対象とする障害区分や一般相談支援の有無などを設けている場合があります。利用対象者が限られることもあるため、事前に条件を確認してください。
また、就労移行支援事業所でサポートできるケースもあります。手続きや説明のサポートを希望する場合は、利用を検討している事業所へ相談するとスムーズです。
スキルを習得できるキズキビジネスカレッジ(KBC)

キズキビジネスカレッジ(KBC)は、ビジネスに役立つスキルを基礎から学べる就労移行支援事業所です。個別面談で一人ひとりに寄り添い、多様な進路への就職を支援しています。
これまでの支援では、1,000人以上が企業へ就職しており、上場企業グループへの就職実績もあります。学べるスキルは以下のとおりで、希望に合わせて学習内容を選ぶことが可能です。
- 会計・ファイナンス
- 英語
- Webマーケティング
- Webライティング
- Excel/PowerPoint基礎
- 動画制作
- Webデザイン(illustrator・Photoshop)/プログラミング
収入状況によっては、自己負担0円で通所できる場合もあります。実際に通所した人の体験談も参考にしながら検討してみてください。
まとめ:障害福祉サービス受給者証で適切な支援を受けよう
障害福祉サービス受給者証は、就労移行支援の利用に必要な証明書です。この書類には、サービスの種類や支給量、利用期間などの情報が記載されています。
発行手続きは、自治体の窓口や相談支援事業者に相談しながら進めます。自分で利用計画書を作成しても問題ありませんが、相談支援事業者に依頼すると手続きがスムーズです。
交付後は、有効期限に留意し、適切に管理してください。
このコラムが、就労移行支援を検討するあなたの支えになれば幸いです。
受給者証とは、何ですか?
受給者証は、正式には「障害福祉サービス受給者証」といいます。自治体が発行する給付の証明書のことで、訓練等給付や介護給付のような障害福祉サービスを利用する際に必要です。
詳細については、こちらで解説しています。
受給者証の発行手続き
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→