難聴で障害者手帳は発行できる? 取得するメリットや手順を詳しく解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
日常生活で耳が聞こえづらいと感じている人は、障害者手帳が発行されるかもしれません。
難聴で障害者手帳を取得するためには、聴力レベルや生活への影響など、いくつかの条件があります。
このコラムでは、障害者手帳の概要や難聴で障害者手帳を取得するための条件、障害者手帳を取得するメリット、難聴のある人が障害者手帳を発行する手順について解説します。
難聴で障害者手帳を取得したいとお考えの人は、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
障害者手帳の取得を検討している難聴のあるあなたへ
キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?
- 就職率
- 約83%
など
- 就職まで
- 最短4ヶ月
など
- 初任給
- 38万円
など
相談・見学・資料請求は無料です!
入力約1分。お気軽にお問い合わせください。
目次
障害者手帳とは?
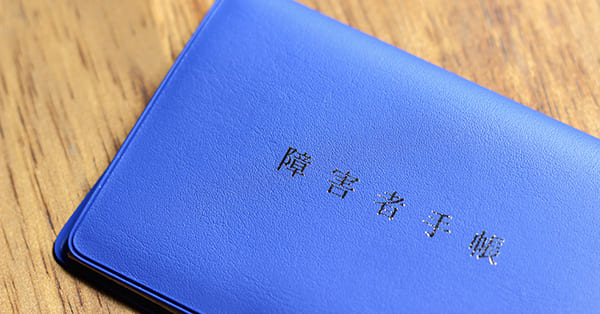
障害者手帳とは、一定以上の障害のある人に交付される手帳のことです。
障害者手帳を所持することで、障害があることの証明が可能です。障害者手帳を所持する人は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の対象として、さまざまな支援を受けられます。(参考:厚生労働省「障害者手帳について」、e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
難聴で障害者手帳を発行する際の条件
難聴で障害者手帳を取得するには、一定の基準を満たす必要があります。
具体的には、聴力レベルが一定以上であることと、それによって日常生活や社会生活に著しい制約があることです。
この章では、それぞれの条件について解説します。
発行条件①聴力検査での結果

厚生労働省の定める基準では、聴力の程度に応じて等級が細かく定められています。聴覚障害の等級分類は、以下のとおりです。
なお、聴覚障害に1級・5級相当はありません。
- 2級相当:両耳の聴力レベルが100dB以上
- 3級相当:両耳の聴力レベルが90dB以上
- 4級相当:両耳の聴力レベルが80dB以上、もしくは両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下
- 6級相当:両耳の聴力レベルが70dB以上、もしくは一側耳の聴力レベルが90dB以上で他側耳の聴力レベルが50dB以上
なお、一方の耳だけ聞こえが悪くなる片耳難聴の場合、6級相当の基準を満たさなければなりません。聴覚障害の等級については、原則として両耳の聴力レベルから判断されます。
以上の点から、片耳難聴のある人に対して手帳の発行が認められるケースは少ないのが現状です。(参考:厚生労働省「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」)
発行条件②難聴による生活への影響
聴力数値が基準を超えているだけでなく、日常生活や社会生活に支障があるかどうかも重要な判断基準です。
手帳交付の可否を判断するにあたっては、専門の医師による聴力検査の結果と、日常生活における支障の度合いが総合的に考慮されます。
例えば、会話が困難であったり、警報音や環境音が認識できなかったりするなど、生活に支障がある場合に障害者手帳の発行が認められやすくなります。(参考:厚生労働省「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)、岡山市「身体障害者手帳の診断書・意見書を書くためのポイント」)
難聴のある人が障害者手帳を取得することで得られるメリット
この章では、難聴のある人が障害者手帳を取得することで得られるメリットについて解説します。
メリット①補聴器購入の補助が受けられる

難聴のある人が障害者手帳を取得すると、補装具費支給制度が利用できます。
これは、障害者総合支援法に基づき、補聴器の購入・修理費用の一部が公的に助成される制度です。
補聴器は高額な医療機器ですが、補助を受けることで利用者の自己負担額が原則1割に抑えられます。
さらに、世帯の所得に応じて月々の負担上限額が設定されているため、経済的な負担の軽減に役立ちます。(参考:厚生労働省「聴覚障害者の認定基準やどんな支援が受けられるのかについてご紹介します!」)
メリット②障害者雇用枠での就職ができる
一般企業の採用枠では、難聴が不利に働くケースも少なくありません。
難聴により障害者手帳を取得すると、障害者雇用促進法に基づき、企業に設けられている障害者雇用枠での就職活動が可能になります。
障害者雇用枠で就職すると、個々の障害特性に配慮した業務内容や労働環境が提供されます。難聴のある人も安心して働きやすいのが利点です。(参考:e-Gov「障害者の雇用の促進等に関する法律」)
メリット③医療費や公共料金の割引が受けられる

障害者手帳は、社会的な支援を受けるための証明となります。
難聴のある人が障害者手帳を取得すると、医療費の助成制度のほか、所得税や住民税の障害者控除、公共交通機関の利用料金などに割引が適用されるケースがあります。
ただし、手帳の等級や自治体、各事業者によって内容が異なるため、各種制度を利用する前には確認が必要です。(参考:厚生労働省「障害者手帳」、東京都心身障害者福祉センター「身体障害者手帳について」)
難聴のある人が障害者手帳を発行する手順
難聴のある人が障害者手帳を発行するには、いくつかの手順を踏む必要があります。この章では、申請から手帳交付までの具体的な手順を解説します。
手順①自治体の窓口で相談する

お住まいの自治体の窓口で、ご自身の状況について相談することが、障害者手帳を発行する第一歩です。
難聴の程度や生活の状況に応じて、担当者から手帳の交付対象となる可能性や、必要な診断書の書式などについて説明が受けられます。
相談時には、現在の聞こえの状況や、困っていることなどを具体的に伝えるのがポイントです。窓口での相談は、今後の手続きを円滑に進めるための重要なステップになります。
手順②指定医療機関で診察・検査を受ける
自治体の窓口で相談後、自治体が指定する身体障害者福祉法第15条に規定される指定医のいる医療機関を受診します。
この指定医は、聴覚障害に関する専門知識と経験を持ち、障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できる医師です。
診察では、純音聴力検査や語音聴力検査などの詳細な聴力検査が行われ、難聴の程度が客観的に評価されます。(参考:e-Gov「身体障害者福祉法」、 大阪市「身体障がい者手帳」)
手順③必要書類を準備する

手続きの際は申請書のほか、医師による診断書や顔写真など、必要書類の準備が求められます。申請に必要な書類は、自治体の窓口で確認しておくとスムーズです。
診断書は指定様式のため、事前に自治体の窓口で受け取ってから医療機関で記入を依頼する流れになります。(参考:厚生労働省「障害者手帳」)
証明写真のサイズや申請書類の記入方法など、不明な点は窓口で確認しておきましょう。
手順④自治体に申請する
準備が整ったすべての書類を、お住まいの地域の自治体の窓口に提出します。この際、申請書類に不備がないか、最終確認を行いましょう。
窓口の担当者から今後の審査の流れや、手帳が交付されるまでの期間について確認しておくと安心です。
手順⑤審査結果をもとに手帳が交付される

提出された申請書類は、自治体の担当者によって内容が確認された後、都道府県の身体障害者更生相談所に送付され、専門家による審査が行われます。
この審査において、難聴の程度が身体障害者福祉法に定められた基準を満たしているかどうかが判定されます。
書類を提出してから手帳が交付されるまでの期間は、通常1〜2ヶ月程度が目安です。審査の結果、基準に該当すると判断された場合に手帳が交付されます。(参考:埼玉県「身体障害者手帳」、 千葉市「身体障碍者手帳交付の方法・手順」、 東京都心身障害者福祉センター「身体障害者手帳について」)
まとめ:難聴でお困りの方は障害者手帳の取得を検討してみましょう

難聴によって日常生活に支障を感じている人は、障害者手帳の取得を検討してみましょう。
難聴で障害者手帳を取得するためには、厚生労働省が定める一定の聴力基準を満たし、日常生活に支障があると認められる必要があります。
手帳を取得すると、補聴器の購入補助や医療費の助成、障害者雇用枠での就職など、多くのメリットが受けられます。
まずは自治体の窓口で相談し、指定医を受診して診断書を作成してもらうことが、重要な最初の手続きです。
障害者手帳とは、何ですか?
障害者手帳とは、一定以上の障害のある人に交付される手帳のことです。障害者手帳を所持することで、障害があることの証明が可能です。
詳細については、こちらで解説しています。
難聴のある人が障害者手帳を取得することで得られるメリットを教えてください。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→




