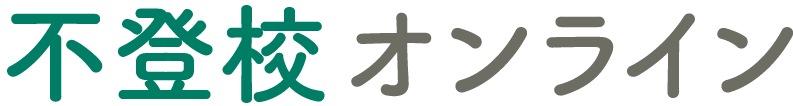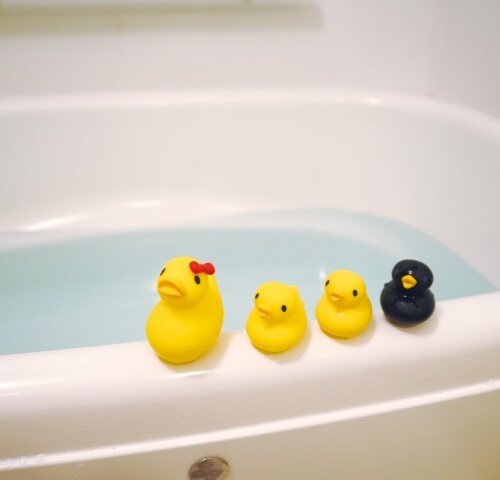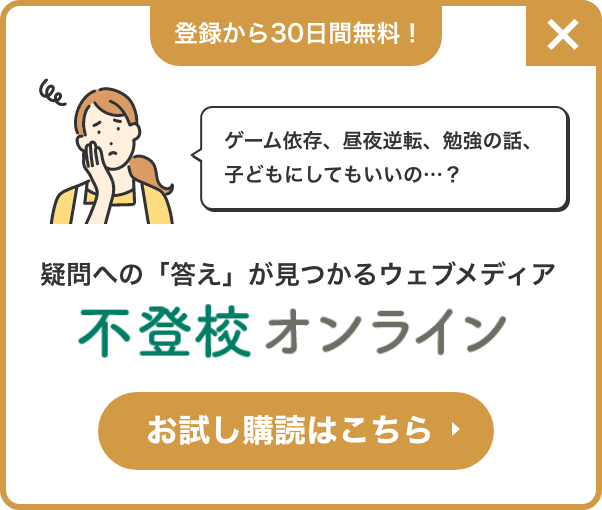特攻「回天」の基地跡で思う現代教育との共通項【8月15日号企画】
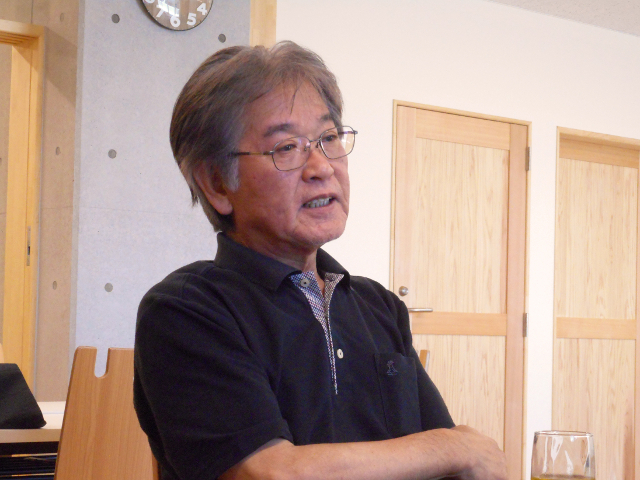
山口県の周南市には徳山湾に浮かぶ大津島という小さな島がある。そこには「回天」の基地跡がひっそりと海辺にたたずんでいる。
「回天」とは太平洋戦争の末期、戦局の悪化に伴い考案された人間魚雷と呼ばれる兵器である。
潜水艇の機首には巨大艦も一撃で沈める威力のある爆薬がしっかりボルトで固定されていて、脱出装置はない。
人間ごと敵艦に体当たりして爆死するか、失敗すれば自爆あるいは自沈という選択肢しかない究極の特攻兵器であった。終戦までの9カ月間で145人の命が海のなかに散っていった。
出撃せず終戦を迎えた「回天」部隊に志願した方の証言――「この戦争は必ず負けると思っていた」が、「戦争批判は口にできなかった」。
それは「不遜な考え」であり、「世間で一番厳しいタブーを犯すことになる」という信念であったという。
教育は、死をもって国に尽くすのが民の義務と教えた。彼らは特攻について、「洗脳されたのではない」、「国や家族を守るための選択」であったと述懐している。
【連載】西村秀明のコラム
記事一覧