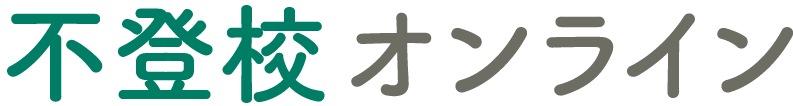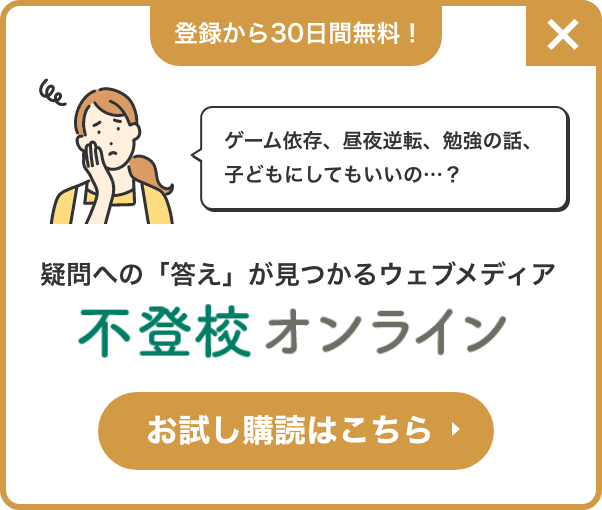子どもの「社会的自立」のために大切にしたい2つのこと

今回が連載最終回となります。貴重な機会をいただきましたこと、読んでくださった多くの方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。
さて、今回のテーマは「社会的自立」です。文科省の「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(2019年)において、不登校児童生徒への支援は、社会的に自立することを目指す必要がある、と記されています。
では、「社会的自立」とはなんでしょうか。これについては、2005年に内閣府から出された『若者の包括的な自立支援方策に関する検討会報告』に概念が示されています。それによると「社会的自立」とは、職業的・精神的・経済的自立とあわせて、日々の生活や社会に関心を持って公共に参画しているかどうかなど、多様な側面を含むものだとしています。そのうえで「人々の生活様式や価値観が多様化した現代の我が国においては、自立の在り方は一様ではない。すなわち、自立しているかどうかは、個人個人について、その置かれた家庭環境、経済状況等の社会的状況などに応じて判断されるべき問題であり、また、自立に向けた支援の必要性やその程度についても、個々に判断されるべきことがらである」。「若者の自立についてみる際には、常に若者一人ひとりにとってふさわしい在り方を考える必要がある」としています。
【連載】すまいる式 子どものわかり方
記事一覧