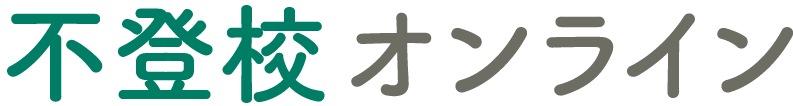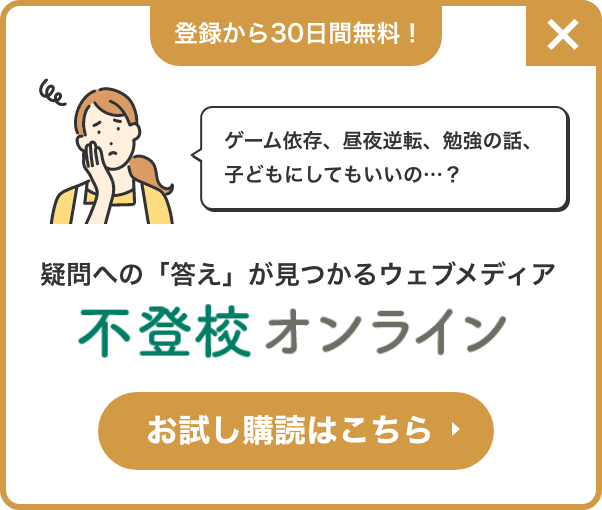子どもの人権を守るために、子どもの居場所で取り組むべき4つのこと【全文公開】

メイン画像:重松和枝さん
子どもに対する暴力や人権侵害は、いつ、どこでも起こり得ます。それは「学校外の居場所」も例外ではありません。フリースクールなどの「学校外の居場所」において、大人はいかにして子どもの安心と安全を守るべきか。子どもへの暴力防止に取り組むNPO法人「CAPセンター・JAPAN」の重松和枝さんにうかがいました。
* * *
――「学校外の居場所」にとって、子どもの安全を守るために、どのような取り組みが必要なのでしょうか。
大きく4点を挙げたいと思います。1つめは「子どもの安全を守るための共通の定義・認識を持つこと」。2つめは「子どもの安全を守るための正しい知識とスキルを持つこと」。3つめは「『もしも』に備えること」。4つめは「安心・安全な関係性のモデルをつくること」です。

以上の4点をひとつずつ、細かく見ていきたいと思います。まずは「子どもの安全を守るための共通の定義・認識を持つこと」。
とくにNPOなどの団体においては子どもの権利や安全について「組織としてどう認識するか」という点があやふやで、各スタッフがバラバラに認識していることもあるかと思います。子どもへの安全配慮が「個人の良識」に任されているわけです。そうではなく、団体としてしっかりと共通認識を持つことが必要です。
そのために、まずは「子どもの権利」という概念について団体全体でしっかりと考えることです。みなさん「子どもの権利」のために活動されていると思います。しかし、「権利」という言葉は非常に抽象的で、多くの大人が実体験を伴うかたちで学んできていないので、認識が各人でバラバラになってしまいがちなのですね。
また、大人だけが考えればいいのではありません。大人とともに、子ども自身が学んで考える機会をつくる必要があると思います。子どもは子どもだけのコミュニティをつくっていますから、そのコミュニティが安全な場であるためにどうすればいいか、ということを、子どもといっしょに考えていく。そうすれば、大人と子どもたちとで共通の定義や認識を持つことができ、何か問題が起きたときに、大人も子どもも「これは、おかしいよね」と気づくことができるのです。
小さな芽から気づけるように
加えて、「子どもの権利侵害」ということを広く捉える必要があります。「いじめ」「虐待」など、名前のついているものだけが権利侵害だと狭く捉えていると、「この件は深刻な状態ではなさそうだ」と、問題が見逃されてしまいます。権利侵害という認識の範囲を広げて、小さな芽の段階でセンシティブになってください。そのために、団体としての定義や共通認識を持たなければいけないのです。
共通の認識のひとつとして、「起きないことを前提にしない」ということは大原則です。権利侵害はどんな場所でも、どんなによい人でも起こしてしまう可能性があります。ただし、その点を念頭に置いたうえで、さらに考えてほしいのは、問題が起きてしまったときに、加害者だけの問題にしても根本的な解決にはならない、ということです。そのような問題を許してしまった場・組織の構造自体を変えていかないといけません。
そもそも、大人と子どものあいだには圧倒的な力の不均衡があります。しかしその不均衡自体が悪いのではありません。大人がその力を乱用したときに、子どもへの権利侵害が発生するのです。そして、どんな人でも、力の乱用は起こり得ます。こうした構造そのものを見る必要があります。
「あの人が力を乱用した」と個人の問題にしてしまうことはかんたんです。しかし、ある1件の権利侵害が発覚するまでに、おそらくいくつも芽があったはずです。そしてそれをほかのスタッフは、気づいてはいても、そのままにしてきた。「あの先生はああいうやり方の人だから」と、見すごしてきた、そういう土壌が団体にありはしないでしょうか。権利侵害を起こした人を排除すれば、今後何も起きないかというと、そうではありません。やはり団体内の土壌そのものを変えていかないと、また新たな加害者が出てきて、いつまで経っても権利侵害はなくなりません。
正しい知識を
さて、子どもの安全のために大切なことの2つめは、「子どもの安全を守るための正しい知識とスキルを持つこと」です。暴力とは何か、人権侵害とは何か、なぜ人権侵害が起きるのか。大人の側にこうした知識・スキルが圧倒的に不足していると思います。大人に知識・スキルがないことで、子どももそれを学ぶ機会を持ちえないのが現状です。
それから、子どもの話を聴くスキルも必要です。「あの子とは信頼関係があるから話してくれるはずだ」と思っていても、実際はなかなか話せないこともあります。また、打ち明けられたときにどうするか。とくに性暴力の場合は、打ち明けられた側がどういう心理状態になるのかも含めて、知っておかなければいけません。
性暴力の場合、事案発生後、初期段階での聞き取りは、「聞きすぎないこと」が第一です。そして、できるだけ早く専門家につないで、団体としていっしょに取り組んでいく姿勢が求められます。正しい知識やスキルを、予防のために持つことが必要だと思います。
そして起きた事案については、当たり前のことですが、当事者の視点から考えること。先ほど力の不均衡の話をしましたが、いずれの暴力も、「イヤ」と言えない関係性があったり、被害者が「恥」の意識を持たされたり、罪悪感や無力感のなかで孤立していくことがあります。当事者の視点から見ることを心掛けていかないと、そうした内面は見えにくいです。むしろ加害者の視点に巻き込まれ、「その程度のことなら」「その人なりに理由があったんだ」というような判断をされてしまうことが往々にしてあり、被害を受けた子どもたちが、どんどん孤立し、あきらめていくという構図が、いろいろなところで起きています。
「もしも」に備え 相談窓口設置を
子どもの安全を守るために大切なことの3つめは「『もしも』に備えること」です。「私たちの活動は『よいこと』で、私たちの団体のスタッフは『よい人』だから、人権侵害など起こらないだろう」、というような空気感が団体内部にないでしょうか。しかし先ほども言ったように「もしも」はどこでも起こります。故意のものだけではなく、無意識のうちに人権侵害をしてしまうこともあり得ます。ですから「もしも」に備えるリスクマネジメント(未然防止・発生防止)やクライシスマネジメント(事後の悪化防止・再発防止)を団体全体として整備することが重要です。
そのためにまず必要なのは、相談窓口の設置です。日ごろから子どもに「困ったことがあったら相談してね」と声をかけていたとしても、仮に「相談してね」と言っているその人から、なんらかの人権侵害を受けていたら、その人には言えないわけです。だから、きちんと子どもの安全を守るための相談窓口を設置することが必要です。
また大人による人権侵害を別の大人が発見したときに、発見者が忖度なく相談できるような窓口も必要です。活動のなかで、子どもへの暴力を目撃するということも当然ありえます。その際に、なかったことにしない。「今のは大丈夫かな」とか「これっておかしいかも」という感覚を放置しないで、しっかりと定められた相談窓口に報告することが重要です。
それから、どうしても後まわしになりがちなことは、当事者以外の子どもたちへのケアやサポート、説明です。事案発生後も何が起きたのか、どうしていくのかという説明も受けないままでは、結果として、周囲の子どもたちもなんらかのかたちでダメージを受けます。「もうこの件は終わったからね」と結論だけが伝えられても、子どもたちが腑に落ちていなければ、ずっと不安なまま、居場所で生活を続けていくことになります。そうしたことが結果として、大人への信頼感を奪っていきます。最悪の場合、事案によって居場所が閉鎖してしまったら、経緯を何も知らされなかった子どもたちは非常に大きな無力感を抱くことになります。
ですから、やはりリスクマネジメントやクライシスマネジメントに予防の観点から具体的に取り組み、ルールや方針をつくっていくことがすごく重要です。子どもたちにしっかりと説明し、できることなら意見も聞き、子どもたちとともに再発防止に取り組んでください。大人には見えてない小さな事案を子どもたちは経験しているかもしれません。子どもとともに取り組むことで、子どもたちは、自分たちを守ろうとしてくれている大人がいること、そして自分たちの力をきちんと認識して、尊重してくれている大人がいることを学べます。それは彼らがダメージから回復するうえで、とても重要なことです。
大人どうしの関係性から
子どもの安全を守るために大切なことの4つめは「安心・安全な関係性のモデルをつくること」。これは、大人どうしの関係性を安心・安全にしていく、ということです。大人どうしが対等にコミュニケーションできているか、気軽に相談し合える関係性をつくれているかどうかは非常に重要です。そうした関係性を見て子どもたちは学んでいきますから。大人たちがまず、子どもたちのよいモデルにならないといけないのです。
とくに家庭の不安定さや、学校教員とのあいだでなんらかのうまくいかない体験があった子たちは、これまでに大人どうしの対等な関係というものを見ることができていないです。大人たちが安心・安全に関わり合う対等な関係性を子どもに見せてあげてください。
先ほども言ったように、「あれ、おかしいな」と思ったときに、それを忖度せずに団体にフィードバックできるか。難しいことだとも思いますが、それをやり続けることが必要です。そうすると、子どもたちもそんな大人を見ながら「コミュニケーションをあきらめなくていいんだな」「思ったことは伝えていいんだな」と学んでいくことができるのです。

――子どもの権利を守るためのガイドラインやルールは、どういうプロセスを経て策定するのがよいと思いますか。
私たちも現在、自団体のガイドラインを策定中です。「私たちの活動でどういうリスクがあるのか」、それをとにかく洗い出すことから始めています。どんなに可能性が低いと思われることでも、絶対に起きないということはありません。また、リスクを出し合い、意識するだけでも予防につながります。
そうしてリスクを出し合った後、「このようなリスクがあるから、私たちはこうします」というかたちで、自団体が取り組むことを明文化されるのが良いのではないでしょうか。明文化する際は、できれば子どもたちにも、読んでわかるようにしたほうがいいと思います。「私たちはこういう考えを軸に、みなさんとこの場所での生活をつくっていきます」と子どもに説明するためです。
子どもたちはガイドラインを読んで「ねえ、やっていることと、ここに書いてあることがちがうよ」と言えるようになれることが理想です。たくさんある必要はありません。10個くらいの約束事でじゅうぶんですので、それをスタッフと子どもたちとの共通認識にしていく。そして半年ごと、1年ごとに点検していく。そのプロセスを子どもたちが見て学んでいく、そうしたサイクルが、結果として子どもの権利保障につながっていくと思います。
――ありがとうございました。(聞き手・茂手木涼岳、協力・本多寿行)
重松和枝(しげまつ・かずえ)
NPO法人CAPセンター・JAPAN事務局次長。1997年にCAPスペシャリストの資格を取得し、幼稚園・保育所・小学校・中学校などでのプログラム実践に携わる。2004年からCAPセンター・JAPANの団体運営に携わり、2011年から現職。保育士研修や大学・NPO団体の人権研修の企画・講師として活動しながら、主としてCAP実践者のトレーニング部門(養成・育成)を担当。
(初出:不登校新聞550号(2021年3月15日発行)。掲載内容は初出当時のものであり、法律・制度・データなどは最新ではない場合があります)