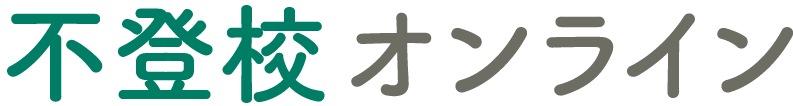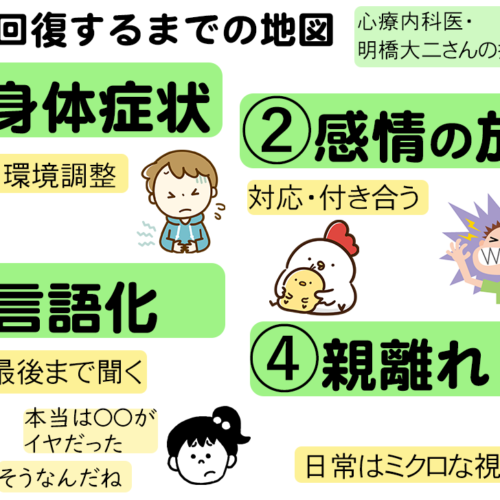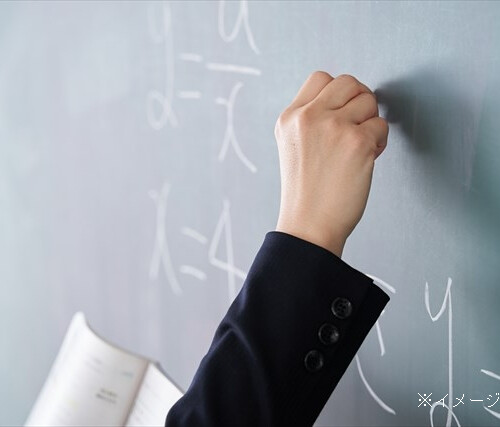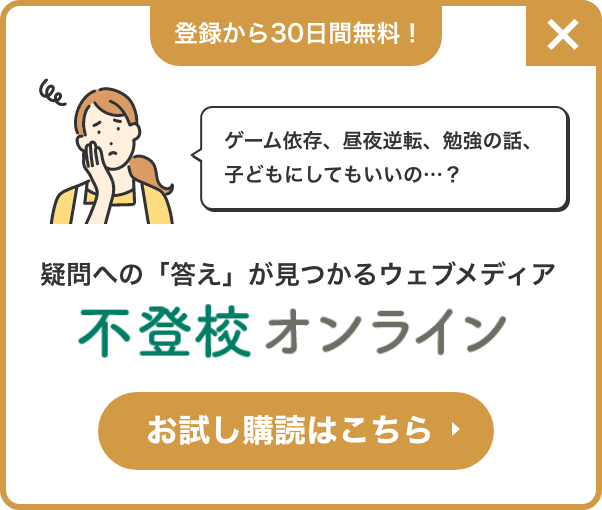直近5年で倍増した小学生不登校背景にある生きづらさの低年齢化

不登校の増加を現場はどのように感じているのでしょうか。不登校の子どもたちが集まるフリースクールを運営し、フリースクールのネットワーク団体の代表を務める江川和弥さんに見解を伺いました。江川さんは大人に突き付けられた課題として「居場所の貧困」と「理解力不足」を挙げています。
* * *
私たちが運営するフリースクールでは不登校の子が増えてきたことを実感していました。時期としては昨年の夏休み明けごろからでしょうか。要因の1つに挙げられるのはコロナ禍です。コロナの影響で昨春、多くの学校が休校しました。子どもたちにとって春というのは「学校に慣れる期間」です。学校での集団生活、同級生や先生との人間関係、勉強などに慣れる期間です。その期間もなく、いきなり学校生活の本番が始まりました。多くの子が苦しんだと思います。その結果が不登校増にもつながったのではないでしょうか。
また、今回の調査で特徴的なのが小学生の不登校増でした。小学生の不登校が前年度から1万人増と大幅に増加しました。これが意味するのは「生きづらさの低年齢化」です。これまで生きづらさを抱える子どもは、思春期に入った中高生だと思われていました。ところが、小学生も、同級生や教師らとの人間関係、学校生活での生きづらさを感じる子が増えています。